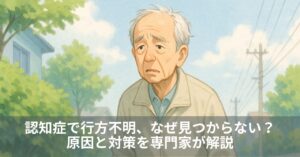「お葬式の集合写真、笑顔で写っていいのかしら…?」なんて、ふと疑問に思ったことはありませんか?大切な故人を見送る最後の時間、失礼があってはならないと考えると、表情ひとつにも気を使いますよね。
結論から言うと、葬式の集合写真で笑顔が許されるかどうかは、故人との関係性や地域ごとの慣習、そしてその場の雰囲気によって大きく変わるんです。ただし、「葬儀で写真撮影は不謹慎ですか?」という基本的な考え方や、「お葬式で笑っちゃだめですか?」といった一般的なマナーを知らないと、思わぬところで配慮に欠けてしまうケースも。
特に、棺の写真はダメだとされることが多く、ご遺族によっては「葬式の集合写真は撮らなくてもいいですか」と考える場合もありますから、一概には言えないのが難しいところなんですよね。
この記事では、葬式の集合写真と笑顔をテーマに、北海道など地域による文化の違い、撮り終えた写真の処分方法、さらには「お葬式にすっぴんはNGですか?」といった身だしなみの疑問まで、あなたの「どうしよう?」をスッキリ解決できるよう、心を込めて解説していきますね!
この記事のポイント
- 葬式の集合写真で笑顔が許されるケースとマナー
- 写真撮影に関する地域ごとの文化や慣習の違い
- 撮影後の写真の適切な処分方法と注意点
- お葬式にふさわしい髪型やメイクなどの身だしなみ

こんにちは!終活や相続の専門家、やえです。
お葬式のマナーって、学校で習うわけじゃないから、いざという時に戸惑いますよね。特に写真撮影は、思い出として残したい気持ちと、厳粛な場にふさわしくないのでは…という気持ちの間で揺れ動くもの。
でも大丈夫!この記事を読めば、あなたが安心して故人をお見送りできるよう、しっかりサポートしますからね。一緒に確認していきましょう!
葬式集合写真で笑顔はあり?基本マナー
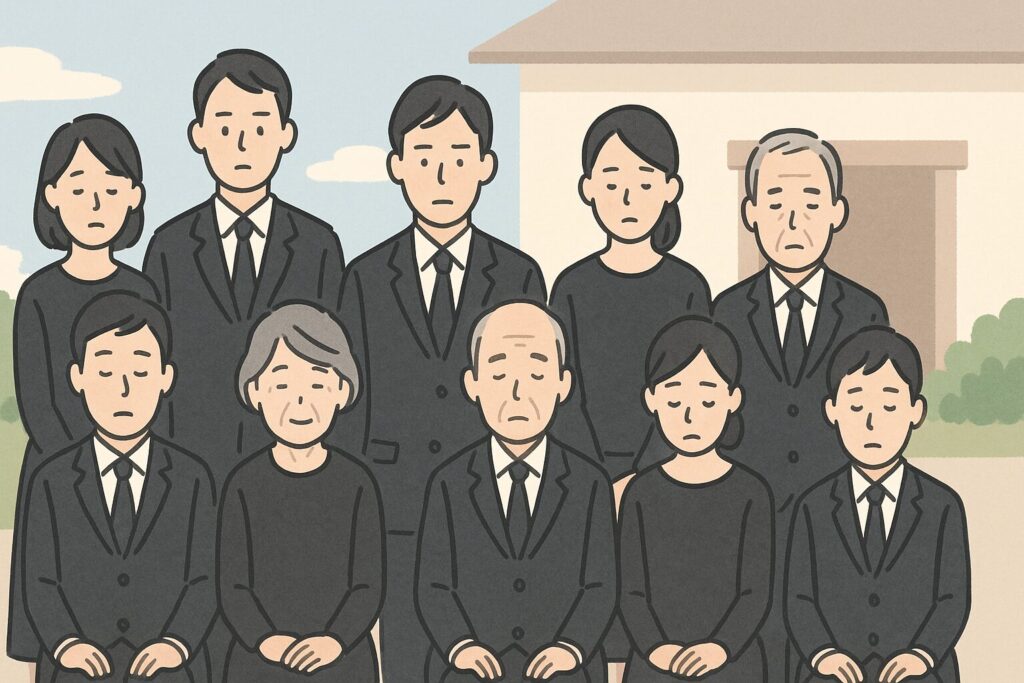
葬儀で写真撮影は不謹慎ですか
まず、多くの方が疑問に思う「そもそも葬儀で写真を撮ること自体、不謹慎なの?」という点について、もう少し掘り下げてお話ししますね。これについては、一概に「はい、不謹慎です」とも「いいえ、問題ありません」とも言い切れないのが実際のところです。
葬儀は故人を偲び、遺族が悲しみを分かち合う、非常にプライベートで厳粛な時間です。その中で、無遠慮にカメラを向ける行為は、故人やご遺族の心情を深く傷つける可能性があり、不謹慎だと捉えられることが少なくありません。
特に、式の進行中にフラッシュをたいたり、シャッター音を響かせたりする行為は、儀式の妨げとなり、厳に慎むべきです。他の参列者から見ても、決して気持ちの良いものではありません。
一方で、「故人との最後の思い出を形に残したい」「遠方で参列できなかった親族に、式の様子を伝えてあげたい」といった切実な思いから、ご遺族自身が写真撮影を希望されるケースも増えています。
また、最近では多くの葬儀社が、式の流れを妨げない形で記録写真を撮影し、後日アルバムにしてお渡しするサービスをプランに含んでいます。これは、慌ただしい中で葬儀を終えたご遺族が、後から「誰が参列してくださったのか」「どんなお花をいただいたのか」を落ち着いて確認できるようにという配慮から生まれたものです。
このように、写真撮影が不謹慎にあたるかどうかは、「誰が、何のために、どのように撮るか」という文脈によって大きく変わります。ご遺族の許可なく個人的な興味で撮影するのはマナー違反ですが、故人を偲び、記録に残すという目的で、ご遺族の合意のもと、式の進行に配慮して行われるのであれば、一概に不謹慎とは言えないのです。
もし撮影を考える場面があれば、まずは喪主やご遺族の意向を確認することが何よりも大切ですよ。
葬式での写真は不謹慎という考え方
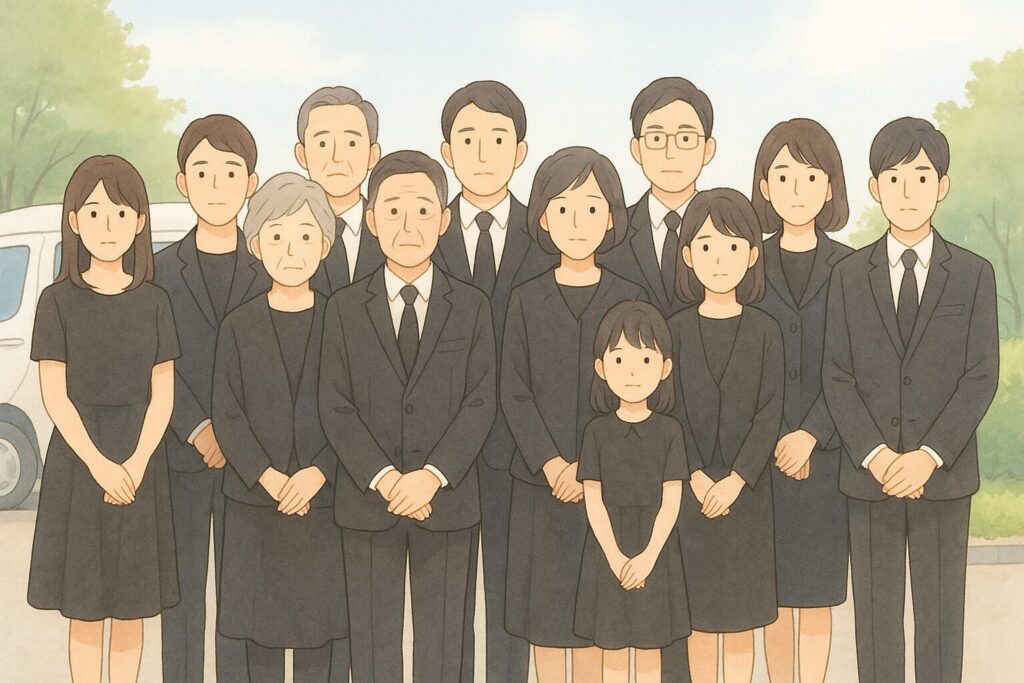
では、なぜこれほどまでに、お葬式の写真が「不謹慎」だという考え方が根強いのでしょうか。その背景には、日本の文化や死生観に根差した、いくつかの深い理由が存在します。
故人と遺族の心情への最大限の配慮
最も大きな理由は、やはり故人の尊厳と、悲しみの渦中にいるご遺族への配慮です。大切な家族を亡くした直後のご遺族は、心に深い傷を負い、精神的に非常にデリケートな状態にあります。そのような状況でカメラを向けられることは、悲しみを覗き見されているような感覚を与え、大きな精神的苦痛になりかねません。
また、安らかに眠る故人の姿を無断で撮影することは、故人のプライベートな最後の瞬間を侵害する行為であり、尊厳を損なうと考えるのが自然な感情です。
儀式の神聖さと「ケガレ」の意識
お葬式は、単なるお別れの会ではなく、故人の魂を安らかに送り出すための神聖な儀式です。その静かで厳かな雰囲気の中で、カシャカシャとシャッター音を響かせたり、撮影のために動き回ったりする行為は、式の空気を乱し、他の参列者の祈りの時間を妨げてしまいます。
古くからの考え方では、死を「ケガレ(穢れ)」と捉え、非日常的なものとして扱う意識もありました。写真に撮るという行為は、その非日常的な出来事を日常に持ち込むこととされ、どこか禁忌的なニュアンスを持っていたのかもしれません。
このように、「不謹慎」という言葉の裏には、故人とご遺族の気持ちを最優先し、儀式の神聖さを守ろうとする、日本の文化に深く根差した「思いやりの心」と「敬意」が込められているのです。
棺の中の写真はダメなのでしょうか
これは非常にデリケートな問題ですが、結論から言うと、棺の中、つまり故人のご遺体の写真を撮影することは、原則として絶対に避けるべきとされています。たとえごく親しい間柄であっても、無断で撮影することは重大なマナー違反です。
闘病で苦しんだ末に安らかな表情を取り戻された故人を見て、「この穏やかな最後の顔を写真に残しておきたい」という気持ちが湧くことは、人間として自然な感情かもしれません。
しかし、多くの場合、ご遺族や他の親族は、故人が亡くなった姿を写真という形で残されることに強い抵抗感を抱きます。なぜなら、「故人の思い出は、生きている時の元気な姿であってほしい」と願うからです。写真を見るたびに、死という辛い現実を突きつけられるのは、遺された家族にとってあまりにも酷なことです。
撮影を希望する場合の絶対的なルール
万が一、遠方でどうしても駆けつけられない家族に見せるためなど、やむを得ない特別な事情がある場合は、必ず事前に喪主やご遺族に丁寧に相談し、明確な許可を得る必要があります。
その際も、他の参列者の目に触れないよう、ごく限られた身内だけで、式の流れを妨げないタイミングで、静かに行うのが最低限のマナーです。無断での撮影は、後々親族間で取り返しのつかないトラブルに発展する可能性もあるため、絶対にやめましょう。
故人との最後の時間は、カメラのレンズ越しではなく、ご自身の目と心に深く、そして温かく刻み込むことを優先するのが、故人への何よりの供養となると言えるでしょう。
葬式の集合写真は撮らなくてもいいですか
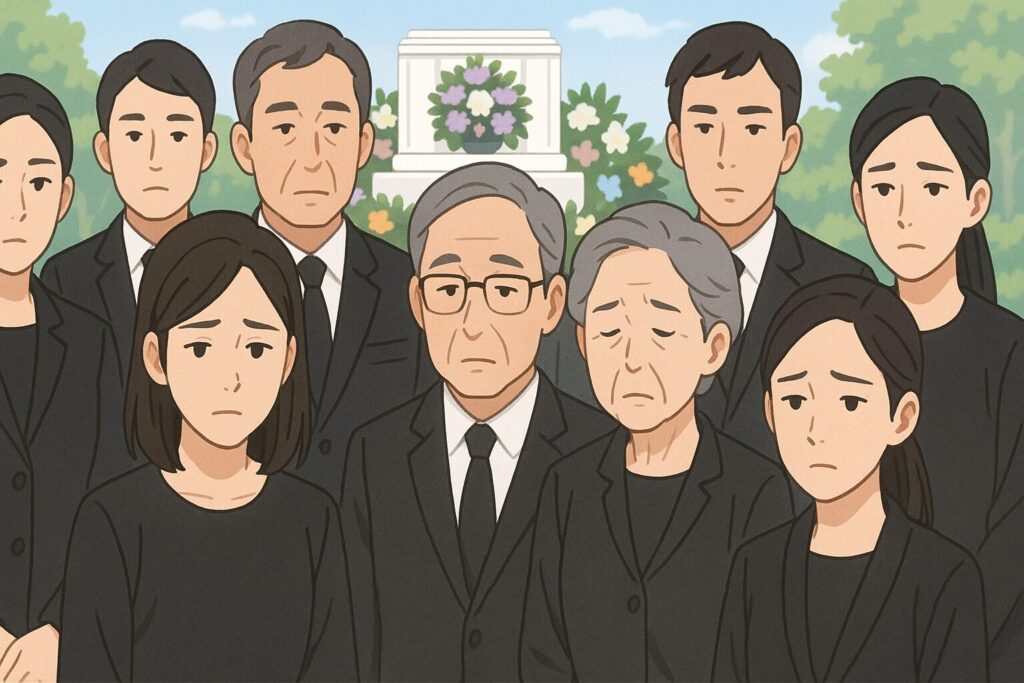
もちろんです!葬式の集合写真は、絶対に撮らなければならないものではありません。むしろ、撮らないという選択も、故人やご遺族の気持ちを尊重した立派な選択肢の一つです。撮影するかどうかは、ひとえに喪主やご遺族の意向によって決まります。
近年、葬儀の形式は大きく変化しています。大規模な一般葬だけでなく、家族だけで静かに見送る「家族葬」や、儀式を簡略化した「一日葬」「直葬」などが増加傾向にあります。
経済産業省の調査でも、こうした葬儀形式の多様化が見られます(出典:経済産業省 特定サービス産業動態統計調査)。このような小規模でプライベートな葬儀では、儀式ばった集合写真を撮らないケースも全く珍しくありません。
ここで、集合写真を撮る意味と、撮らない理由を改めて整理してみましょう。
| 集合写真を撮る意味・メリット | 集合写真を撮らない理由・メリット | |
|---|---|---|
| 記録として | 故人を偲んで誰が参列してくれたのかを後から確認できる公式な記録となる。 | 悲しみの表情が記録として残ることを避けたい。 |
| 親族の繋がり | 普段なかなか会えない親族が一堂に会する貴重な機会。故人が繋いでくれた縁を再確認できる。 | 参列者に写真撮影という気遣いや負担をかけさせたくない。 |
| 故人への想い | 「こんなにたくさんの人があなたのために集まってくれましたよ」という故人への最後の報告になる。 | 儀式的なことよりも、一人ひとりが故人と静かにお別れする時間を大切にしたい。 |
| 感情面 | 後日、写真を見返すことで故人を偲び、葬儀の日を思い出すきっかけになる。 | 悲しみが深く、写真撮影をする精神的な余裕がない。 |
どちらの選択にも、故人を想うそれぞれの形があります。もしあなたが遺族の立場であれば、周りの慣習や「普通はこうだから」という考えに縛られる必要はありません。ご家族でじっくりと話し合い、「私たち家族は、どうやって故人を見送りたいか」を決めるのが一番大切ですよ。
お葬式で笑っちゃだめと言われる理由
「お葬式では笑ってはいけない」と、子どもの頃に大人から教わった方も多いのではないでしょうか。この教えは、単なる形式的なマナーではなく、お葬式という儀式が持つ社会的な意味合いに基づいています。
お葬式は、第一に、故人の死を悼み、その冥福を祈る厳粛な儀式の場です。そして第二に、遺されたご家族の深い悲しみに寄り添い、その気持ちを社会として共有する場でもあります。参列者は、故人との最後のお別れをすると同時に、「あなたの悲しみは、私たちも共に感じています」という無言のメッセージをご遺族に伝える役割も担っているのです。
そのような場で笑顔を見せることは、「悲しんでいない」「故人や遺族の気持ちを軽んじている」と受け取られてしまう可能性があります。これが、「お葬式で笑っちゃだめ」と言われる最大の理由です。
もちろん、人間ですから、故人との楽しい思い出がふとよみがえり、自然と笑みがこぼれてしまうこともあるでしょう。それは決して責められるべきことではありません。故人を偲ぶ形は、涙だけではないからです。
しかし、仲間内で思い出話に花が咲き、大声で笑ったり、はしゃいだりするような行為は、明らかに場の雰囲気を壊し、他の参列者や静かに悲しみに浸るご遺族に深い不快感を与えてしまいます。
TPO(時・場所・場合)をわきまえ、儀式の間は静かに故人を偲び、節度ある態度を心がける。この社会的な共通認識が、お葬式の秩序と尊厳を保っているのです。
葬式で笑顔はマナー違反なのでしょうか
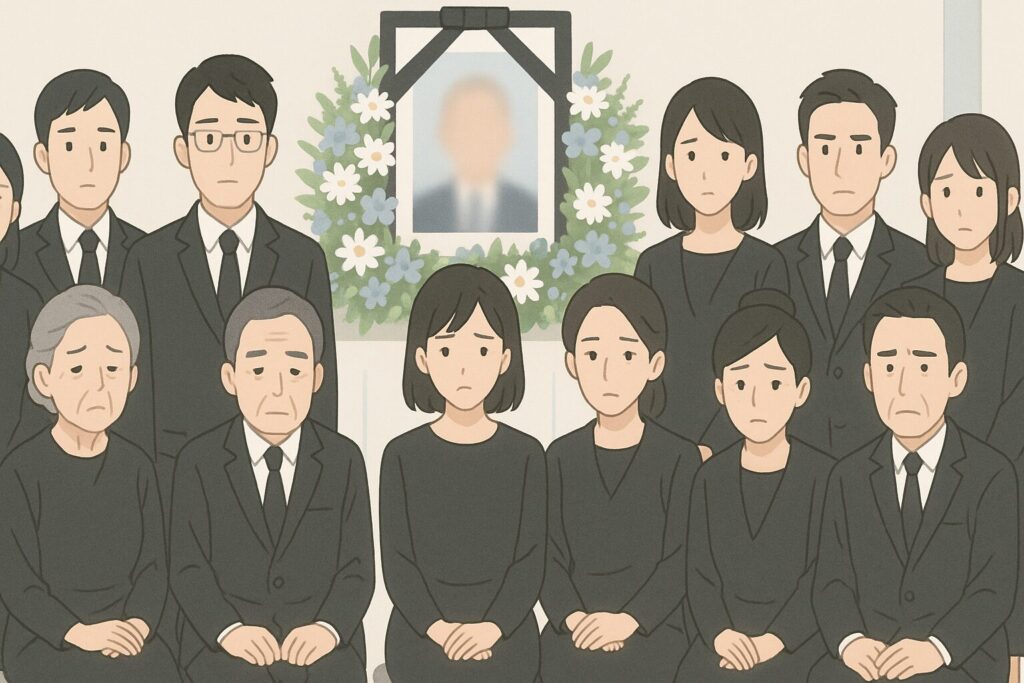
さて、ここが一番気になるポイントかもしれませんね。「お葬式で笑うのはダメ」という基本を踏まえた上で、集合写真の「笑顔」はどうなのでしょうか。これもまた、「はい、マナー違反です」と断定することはできません。故人との関係性やその場の雰囲気によって、判断が分かれる非常に繊細な問題です。
笑顔が許容、あるいは推奨されるケース
- 故人が生前、明るいお別れを望んでいた場合:「俺の葬式で泣くなよ!笑って送ってくれ!」といった遺言があったり、エンディングノートに記されていたりするケースです。この場合、笑顔で送ることが故人の遺志を尊重することになります。
- 大往生で、親族が安堵と感謝の気持ちで見送る場合:90歳、100歳と長寿を全うし、大きな苦しみもなく穏やかに旅立たれた故人に対し、「おじいちゃん、長い間お疲れ様。ありがとう」という温かい感謝の気持ちで見送る雰囲気の時などです。悲しみよりも、故人の人生を称える気持ちが強くなります。
- 故人を囲んで思い出話が盛り上がった後など:撮影の直前に、故人のユニークな人柄を偲ぶエピソードで場が和み、参列者の間に自然な笑顔が生まれることもあります。これは故人がもたらしてくれた温かい時間と言えるでしょう。
とはいえ、最も大切なのは場の空気を読むことです。周りの親族が皆、悲しみに沈み、神妙な面持ちでいる中で、一人だけ満面の笑みで写るのはやはり適切ではありません。
基本的には、歯を見せて笑うような大きな笑顔ではなく、故人への感謝を込めた、口角を少し上げる程度の穏やかな表情を心がけるのが無難です。
| 表情の目安 | 印象 | 適した場面 |
|---|---|---|
| 真顔・伏し目がち | 厳粛・悲しみの表現 | 突然のお別れ、ご遺族の悲しみが深い場合など、最も基本的な表情。 |
| 穏やかな表情(口角を少し上げる程度) | 故人への感謝・優しい眼差し | 場が少し和んでいる時や、故人の人柄を偲ぶ温かい雰囲気の場合。 |
| 歯が見えない程度の微笑み | 明るいお見送り | 故人の遺志である場合や、親族全体が非常に明るい雰囲気の場合。 |
| 歯を見せる笑顔・大笑い | 不謹慎・場にそぐわない | いかなる場合でも、お葬式の集合写真では避けるべきです。 |

そうなんです。一番大事なのは、故人を想う気持ち。故人がユーモアのある方で、みんなが笑顔でいることを望んでいるだろうな…と感じるなら、穏やかな笑顔はきっと供養になりますよ。
逆に、突然のお別れでご遺族が深く悲しんでいる場合は、その気持ちに寄り添い、静かに写真に納まるのが思いやりですよね。
葬式の集合写真には地域差があります
実は、お葬式の集合写真を撮るという慣習自体、地域によってかなり温度差があることをご存知でしょうか。私がこれまで全国の葬儀に立ち会ってきた中でも、関東と関西、都市部と地方では、考え方や慣習が驚くほど異なるケースが多くありました。
例えば、首都圏などの都市部では、葬儀が小規模化・簡素化される傾向にあり、そもそも集合写真を撮らないという選択をするご家庭も珍しくありません。プライバシー意識の高まりも関係しているかもしれませんね。
一方で、地方や昔ながらのコミュニティが根強く残る地域では、親族一同が顔を合わせる重要な機会として、集合写真を撮ることが儀式の一部としてしっかりと定着している場合があります。その写真が、親族間の繋がりを再確認する大切なツールになっているのです。
面白い例で言うと、一部の地域では「次の遺影写真の準備」という少しドキッとするような、しかし実用的な意味合いで撮影されることもあるようです。
これは、高齢になると改まった写真を撮る機会が減るため、「万が一の時に備えて、喪服姿のきちんとした写真を残しておく」という、古くからの知恵なのかもしれません。
もし、あなたが配偶者の実家など、慣れない地域の葬儀に参列する機会があれば、「恥ずかしいことではないので、こちらでは集合写真などは撮りますか?」とパートナーや親しい親族に事前に確認しておくことを強くお勧めします。
「郷に入っては郷に従え」ということわざもありますし、その地域の慣習を尊重し、柔軟に対応する姿勢が、円滑な親族付き合いのためにも大切になりますよ。
葬式の集合写真、北海道では一般的

地域差の非常に分かりやすい例として、北海道が挙げられます。本州の多くの地域、特に都市部にお住まいの方には驚かれるかもしれませんが、北海道の葬儀では、親族の集合写真を撮影することが、ごく一般的で当たり前の慣習として根付いているんです。
これには、やはり広大な土地柄が深く関係していると言われています。ご存知の通り北海道は非常に広く、親戚が道内の各地、場合によっては数百キロ離れた場所に点在していることも珍しくありません。
そのため、冠婚葬祭でもない限り、親族が一堂に会することは物理的に非常に困難です。だからこそ、お葬式という場が、故人を偲ぶと同時に、「久しぶり!元気だったかい?」と親族の絆を確認し、その姿を記録に残すための、またとない貴重な機会となっているのです。
また、葬儀の香典返しに領収書が出るなど、合理的な文化を持つ北海道ならではの考え方かもしれません。北海道出身の方にとっては「撮って当たり前」の光景でも、他の地域から来た方にとっては「え、お葬式で写真を?」とカルチャーショックを受けることも。
このように、自分が常識だと思っていることが、他の地域では非常識、あるいはその逆というケースはたくさんあるんですね。こうした文化の多様性を知っておくことも、現代社会における大切なマナーの一つと言えるかもしれません。(参考:一般社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会)
葬式の集合写真の処分方法
撮影した後の写真、特に故人が写っている可能性のある集合写真の処分は、多くの方が悩む問題です。普通の写真と同じように一般ゴミとして捨てるのは、心情的にどうしても気が引けますよね。かといって、ずっと保管しておくのも…という場合、どのように対処すれば良いのでしょうか。
もし、手放したいと考えるのであれば、故人への敬意を払い、ご自身の気持ちもすっきりするような、以下のような方法が考えられます。
お焚き上げを依頼する
最も丁寧な方法の一つが、神社やお寺での「お焚き上げ」です。これは、古いお札やお守り、人形など、魂が宿るとされるものに感謝の気持ちを伝えてから、浄火によって天に還すという日本の伝統的な儀式です。写真も同様に、故人やご先祖様の想いが込められたものとして、お焚き上げの対象としている寺社が多くあります。
事前に、近隣の寺社に電話などで「写真のお焚き上げは受け付けていますか?」と問い合わせてみましょう。費用(初穂料・玉串料など)や持ち込み方法を確認してから依頼するとスムーズです。
専門の業者に依頼する
最近では、遺品整理サービスの一環として、写真の供養や処分を専門に代行してくれる業者も増えています。「遺品整理 写真 供養」などのキーワードで検索すると、様々なサービスが見つかります。
業者に依頼するメリットは、プライバシーに配慮し、他の遺品と合わせて適切に処理してくれる点です。合同供養を行った後に、供養証明書を発行してくれるところもあり、安心して任せることができます。
自分で処分する場合の配慮
やむを得ず自分で処分する場合は、写真を白い紙に包み、塩をひとつまみ振ってお清めをしてから、他のゴミとは別の袋に入れて出す、という方法があります。
これはあくまで気持ちの問題ですが、何もしないよりは心が安らぐかもしれません。写真をシュレッダーにかけるなどして、個人が特定できないようにする配慮も大切です。
いずれの方法を選ぶにせよ、故人や一緒に写っている方々への「ありがとう」という感謝の気持ちを忘れずに、丁寧に扱うことが何よりも大切です。

写真って、思い出そのものだから処分に悩みますよね。私も、祖母の遺品整理の時にたくさんの写真が出てきて、一枚一枚見返しながら涙した経験があります。
無理にすぐに処分する必要はありません。ご自身の気持ちの整理がつくまで、大切に保管しておくというのも一つの選択肢。時間が経ってから、どうするかをゆっくり考えても良いんですよ。
葬式の写真撮影についてよくあるご質問FAQ
ここでは、お葬式の写真撮影に関して、皆さんからよく寄せられる質問にお答えしますね。
-
葬儀の様子を撮影した写真をSNSに投稿してもいいですか?
-
故人や遺族のプライバシーを守るため、無断でSNSに投稿することは絶対に避けるべきです。必ず事前に喪主やご遺族全員の許可を得るようにしてください。
-
集合写真はいつ、どのタイミングで撮影することが多いですか?
-
告別式の終了後や出棺前など、儀式が一段落したタイミングで撮影されるのが一般的です。ただし、これも葬儀社や地域の慣習によって異なる場合があります。
-
集合写真の費用は誰が支払うのが普通ですか?
-
葬儀社に撮影を依頼した場合、その費用は葬儀費用一式に含まれることがほとんどです。そのため、基本的には喪主(葬儀の主催者)が負担することになります。
葬式集合写真で笑顔以外の身だしなみ
お葬式にすっぴんで参列はNGですか
写真撮影の有無にかかわらず、お葬式でのメイクは女性にとって気になるポイントですよね。「悲しみを表現するために、ノーメイク(すっぴん)で行くべきなのでは?」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、実はフォーマルな場であるお葬式でのすっぴんは、かえって「準備を怠った」「配慮に欠ける」と見なされ、失礼にあたる場合があるんです。
お葬式でのメイクは「片化粧(かたげしょう)」と呼ばれる、色味を抑えた控えめで清潔感のあるナチュラルメイクが基本マナーとされています。これは、派手な化粧をしないことで哀悼の意を示すと同時に、故人への敬意と、儀式に臨むための最低限の身だしなみとして行われるものです。社会人としてのエチケット、と考えても良いかもしれません。
お葬式にふさわしい「片化粧」のポイント
- ベースメイク:肌のトーンを均一に整えることを目指します。ツヤ感の強いリキッドファンデーションやクッションファンデは避け、マットな質感のパウダーファンデーションなどが適しています。コンシーラーでクマやシミを軽く隠す程度にしましょう。
- アイメイク:ラメやパール、鮮やかなカラーアイシャドウは絶対にNGです。アイラインはまつ毛の隙間を埋める程度に細く引き、マスカラもビューラーは使わず、一度塗りで控えめに。つけまつげやカラーコンタactも外します。
- チーク・リップ:健康的に見せるためではなく、あくまで血色を悪く見せない程度に。チークは肌なじみの良いベージュ系をごく薄く。リップも同様に、ベージュや薄いピンク系のマットな口紅を選び、グロスのようなツヤの出るものは避けましょう。
もちろん、普段から全くメイクをしない方や、肌が弱くてメイクができないなど、特別な事情がある場合はその限りではありません。大切なのは、「故人を敬い、きちんと身だしなみを整えて参列しました」という姿勢を示すこと。
すっぴんで参列する場合も、眉を整え、髪をきちんとまとめ、清潔感のある服装を心がけることが何よりも重要です。服装やメイクだけでなく、持ち物にも細やかな配慮が求められます。例えば、葬儀用のバッグや、身につけるアクセサリーにもマナーがありますので、合わせて確認しておくと安心ですね。
お葬式でハーフアップはNGですか
髪型も、身だしなみの重要な要素です。特に女性の髪型でよくご質問をいただくのが「ハーフアップ」ですが、結論から言うと、お葬式の場では避けた方が無難とされています。
ハーフアップは、結婚式やパーティーなど、お祝いの席や華やかな場面で好まれる髪型です。髪の上半分を飾りゴムやバレッタで留めるスタイルは、どうしても「おしゃれをしている」「飾っている」という印象を与えがちです。そのため、故人を偲ぶお悔やみの場にはふさわしくないとされています。
また、実用的な面でも、お焼香や読経の際にお辞儀をする場面が多いお葬式では、ハーフアップだとサイドの髪が顔にかかってしまい、だらしなく見えてしまう可能性があります。何度も髪をかき上げる仕草は、見苦しいだけでなく、他の参列者の集中を妨げることにもなりかねません。
お葬式でのヘアアレンジの基本原則は、「清潔感」「控えめ」「邪魔にならない」の3つです。長い髪は、耳より下の低い位置で一つにまとめるのが最も適切で、誰から見ても失礼のない髪型です。
この際、派手なヘアアクセサリーは絶対NG。黒や紺、茶色などの地味な色のヘアゴムや、飾りのないシンプルなシュシュ、バレッタを使用しましょう。
お葬式でロングヘアーをポニーテールにするのはNGですか
「ポニーテール」と聞くと、元気でカジュアルな印象を受けるかもしれませんが、これも結ぶ位置によって、お葬式の場にふさわしいかどうかが大きく変わってきます。
前述の通り、お葬式の髪型の基本は「控えめ」であること。耳より高い位置で髪を結ぶ、いわゆる一般的なポニーテールは、華美でアクティブな印象を与えるため、お葬式の場にはふさわしくありません。これは「祝い事」を連想させるスタイルと見なされるためです。
| OKなまとめ方(弔事用) | NGなまとめ方(慶事・日常用) | |
|---|---|---|
| 結ぶ位置 | うなじのあたり、耳より下の低い位置 | 耳と同じか、それより高い位置 |
| 全体の印象 | 落ち着いている、清潔感がある、控えめ | 華やか、元気、アクティブ、おしゃれ |
| 名称の例 | ひとつ結び、ローポニー | ポニーテール、サイドテール、お団子ヘア |
| アクセサリー | 黒・紺・茶のシンプルなゴムやバレッタ | 飾り付きのゴム、シュシュ、リボン、カチューシャなど |
また、まとめた後れ毛やサイドの髪が顔にかからないよう、黒いヘアピンなどで見えないようにきちんと留めておくと、よりすっきりと清潔な印象になります。あくまで「おしゃれ」をする場ではなく、故人に敬意を表すための「身だしなみ」として髪を整える、という意識が大切ですね。
葬式集合写真で笑顔でいるための配慮
最後に、これまでの内容を踏まえて、もしあなたが「笑顔」で集合写真に臨む場合に心がけたい具体的な配慮についてまとめます。これは、あなたの優しい気持ちを、誤解なく周囲に伝えるための大切なステップです。
まず大前提として、何度もお伝えしますがご遺族の気持ちに寄り添うことが最優先です。突然のお別れなどでご遺族が深い悲しみに暮れているのであれば、無理に笑顔を作る必要は全くありません。静かに故人を偲び、少し伏し目がちに solemn な表情でいることが、何よりの弔意の表明になります。
その上で、故人が明るいお別れを望んでいたなど、穏やかな雰囲気の中で笑顔で撮影することになった場合は、以下のステップでご自身の表情を考えてみると良いでしょう。
- 【ステップ1】場の雰囲気とご遺族の表情を観察する
カメラの前に立つ前に、まず周りを見渡しましょう。特に喪主や故人の配偶者、お子さんといった中心的なご遺族がどのような表情をしているかを確認します。皆さんが穏やかな表情であれば、それに合わせることができます。 - 【ステップ2】穏やかな表情を意識する
たとえ笑顔が許される雰囲気であっても、歯を見せてニッと笑うような大笑いは避けましょう。故人への感謝の気持ちを込めて、目を少し細め、口角をほんの少しだけ上げるような、優しい微笑みを意識するのがポイントです。「悲しいけれど、あなたの人生は素晴らしかったですよ」という気持ちを表情に乗せるイメージです。 - 【ステップ3】故人との楽しい思い出を心に浮かべる
無理に笑顔を作ろうとすると、表情がこわばって不自然になりがちです。そんな時は、目を閉じて、故人と過ごした一番楽しかった時間や、一番笑った瞬間を思い出してみてください。そうすると、心の中から自然で温かい表情が生まれてくるはずです。
写真撮影は、葬儀という長い時間の中の、ほんの一瞬です。その一瞬のために、故人を偲ぶ大切な気持ちや、ご遺族、そして周りの参列者への配慮を忘れることがないようにしたいものですね。あなたのその細やかな心遣いが、場の調和を保ち、温かいお見送りの時間を作り出すのです。

いかがでしたか?お葬式のマナーは、決まり事だから守るというよりも、「故人やご遺族を大切に想う気持ち」の表れなんですよね。
笑顔も涙も、故人を想うからこそ生まれる自然な感情。その気持ちを大切にしながら、周りの方への配慮を忘れなければ、きっと故人も喜んでくれるはず。あなたの優しい気持ちが、ご遺族の心を少しでも温かくすることを願っています。
葬式集合写真で笑顔 まとめ
- 葬式の集合写真で笑顔が許されるかは状況による
- 基本は故人を偲ぶ厳粛な場のため控えめな表情が望ましい
- 故人が明るいお別れを望んでいた場合は笑顔も供養の一つになる
- 大往生など穏やかな雰囲気の葬儀では笑顔が見られることもある
- 写真撮影自体、不謹慎と考える人もいるため配慮が必要
- 撮影の可否やタイミングは喪主や遺族の意向を最優先する
- 棺の中の故人を撮影することは原則として避けるべきマナー
- 集合写真を撮る慣習には地域差があり北海道などでは一般的
- 撮影後の写真の処分に困る場合はお焚き上げなどの方法がある
- お葬式でのメイクは控えめな片化粧が基本で、すっぴんは避けた方が無難
▼あわせて読みたい関連記事▼
終活とは?意味と始め方をわかりやすく解説|初心者が損しない準備法

お気軽にご相談ください
相続は100人いれば、100通り
唯一無二の最適な相続をご提案いたします
CONTACT
専門家やえさん

- 専門家やえさん
-
堀川 八重(ほりかわ やえ)
大阪不動産・FPサービス株式会社 代表
15年以上にわたり1,500組を超えるご家族の相続や不動産のお悩みに、専門家として寄り添ってまいりました。私の信条は、法律や数字の話をする前に、まずお客様ご家族の歴史や言葉にならない想いを丁寧に「聞く」こと。信頼できる各分野の専門家チームと共に、皆様が心から安心できる最善の道筋をオーダーメイドでご提案します。一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。
最新の投稿
 お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説
お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説 相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説
相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説 お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例
お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例 お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説
お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説