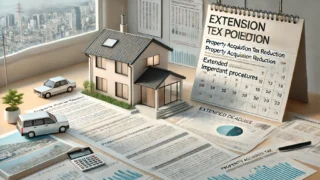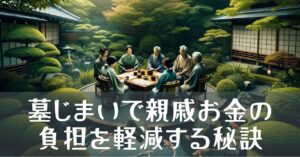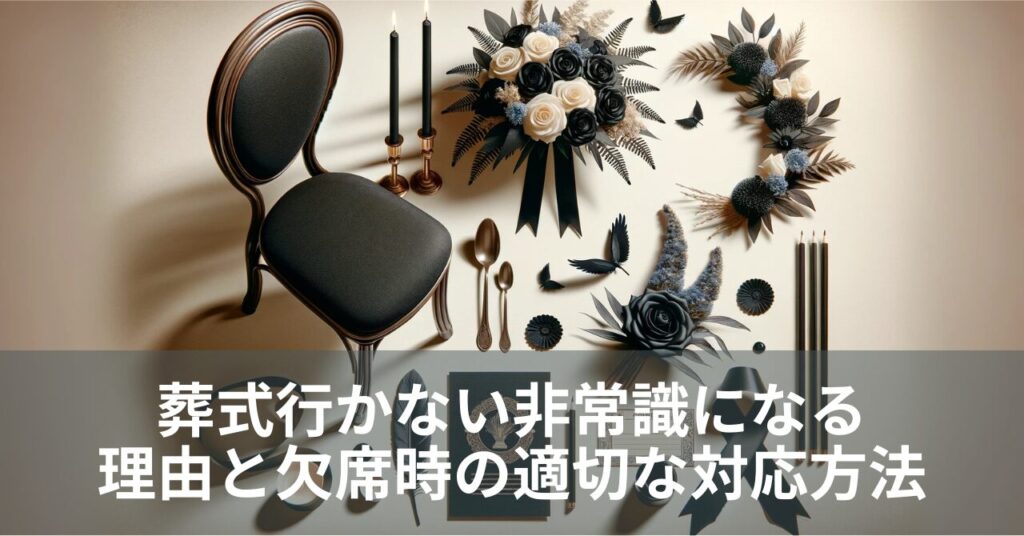
葬式に行かないことが非常識だと感じられることは少なくありません。しかし、さまざまな事情や主義を持つ人々にとっては、葬式に行かない選択が必要な場合もあります。
例えば、葬式に行かないことがめんどくさいと感じる人や、葬式に行きたくないニート、葬式行かない主義を貫く人など、それぞれの理由があります。さらに、葬式に行かない孫や祖母の葬式に行かない孫、親族との関係に悩む場合なども考えられます。
本記事では、葬式に行かないことが非常識と見なされる理由や、それに対する適切な対処法について詳しく解説します。葬儀に行かない方がいいと判断する場合や、葬式に行かない際のマナーについても触れていますので、ぜひ参考にしてください。
この記事のポイント
- 葬式に行かないことが非常識と見なされる理由
- 葬式に行かない場合の適切な対処法とマナー
- 葬儀に行かない方がいい場合の判断基準
- 親族や故人への敬意を示すための代替手段
一般社団法人終活協議会認定資格 終活ガイド・心託コンシェルジュのお役立ちブログです。終活についてのご相談やサポートサービスをご提供しています。生涯笑顔で過ごせる環境づくりをお手伝いさせていただいております。
・生活のサポートを含むサービス
『入院、介護施設入居に伴う身元保証(身元引受け)連帯保証』のご相談
・おひとりさまや、もしもの時に家族に負担をかけたくないあなたに
『葬儀、連絡、お墓、手続き、遺品整理、遺言、相談、公正証書の作成』のご相談
・今は元気だが歳を重ねても不安にならないために
老後資金や年金、貯金の不安のご相談、万一認知症やお体や生活環境に不自由が発生し、デイサービスや老人施設が必要となった際の選び方や準備金、入所の問題
上記のように簡単に気になる事を並べただけでもたくさんあり、終活は多岐にわたりますのでその方のご事情によって様々です。
私たちは、医療、介護、法律、金融をはじめお客様の様々なご事情に対応できる専門家チームが一丸となりお客様に寄り添いながら様々なご事情に合わせた適正なサービスをご提供し、生涯笑顔で過ごせる環境づくりをお手伝いをしています。お気軽にご相談ください。
終活・相続 お悩みご相談事例
- 相続人に長い間連絡が取れない人がいる
- 相続人の仲が悪い
- 今依頼している弁護士・税理士等が親身に対応してくれない
- 財産が何があるのかよくわからない
- 再婚している
- 誰も使っていない不動産がある
- 子供がいない
- 相続する人に『障害』『未成年』『認知』等の人がいる
- 誰にも相談せずに作った遺言がある
- 相続税がかかるのか全く分からない
他にもたくさんお気軽に相談いただいて解決しております。
『もっと早く相談すればよかった』とのありがたいお声をたくさんいただいております。

終活・相続
お気軽にご相談ください
- 何をしたら良いのかわからない
- エンディングノート・終活
- 老後資金・自宅売却の時期
- 資産活用対策・医療・介護
- 施設選び・生命保険・相続対策
- 遺言・葬儀・お墓・相続登記
- 相続発生後の対応や処理方法
- 信用できる士業への安全な橋渡し
その他なんでもお気軽にご相談ください!
営業時間 10:00-18:00(日・祝日除く)
葬式行かない非常識

葬式に行かないと非常識になる理由
葬式に行かないと非常識だと感じられる理由はいくつかあります。ここでは、具体的な理由を説明します。
社会的な礼儀を欠くとみなされるため
葬式は故人に対する最後の別れの場です。社会的な儀礼として、多くの人が故人に敬意を表し、遺族を慰めるために参列します。この場に参加しないことは、社会的な礼儀を欠くとみなされることがあります。
遺族の心情を傷つける可能性があるため
葬式に行かないことで、遺族は「故人や遺族を軽視している」と感じるかもしれません。特に親しい関係であった場合、不在は遺族に対して心の痛みを与えることがあります。
故人への敬意を欠いていると見なされるため
葬式は故人への敬意を示す場です。出席しないことで敬意を欠いていると見なされることがあります。これは特に、故人が生前に多くの人々に影響を与えた人物である場合に顕著です。
社会的な評価に影響するため
葬式への出席は、社会的な評価にも影響を与えることがあります。他の参列者や地域社会からの評価が下がる可能性があるため、出席することが一般的なマナーとされています。
後々の人間関係に影響を及ぼすため
葬式に行かないことは、今後の人間関係に悪影響を及ぼすことがあります。特に、同じ地域や職場の人々との関係において、非常識だと思われることで距離を置かれる可能性があります。
家族や親族との関係悪化を招くため
家族や親族間での関係も重要です。葬式に行かないことで、親族との関係が悪化し、将来的なコミュニケーションに支障をきたすことが考えられます。
会社や職場での印象が悪くなるため
職場の同僚や上司が葬式に出席するのに対し、自分が行かないことで、職場での印象が悪くなることがあります。これは特に、職場の関係者が故人である場合に当てはまります。
文化的・宗教的な背景も影響するため
文化や宗教によっては、葬式への出席が特に重要視されることがあります。これらの背景を理解し、適切な行動をとることが求められます。
このように、葬式に行かないことで非常識とみなされる理由は多岐にわたります。社会的な礼儀、遺族の心情、故人への敬意、そして今後の人間関係を考慮して、できる限り出席することが望ましいです。
葬式に行かない場合の対処法
葬式に行かない場合、適切な対処法が求められます。以下に、その対処法を紹介します。
故人や遺族に直接連絡をとる
まずは、故人や遺族に直接連絡をとり、欠席の理由を丁寧に説明します。適切な形で敬意を示し、心情を伝えることが大切です。
手紙やメールでお悔やみを伝える
葬式に出席できない場合、手紙やメールを通じてお悔やみの意を伝えることができます。丁寧な言葉で故人や遺族に哀悼の意を表しましょう。
花や供物を贈る
遠方にいる場合や、葬式に出席できない状況でも、花や供物を贈ることで哀悼の気持ちを示すことができます。心のこもった贈り物を選びましょう。
後日、遺族を訪ねる
葬式後に、遺族を訪ねてお悔やみを述べることも良い方法です。適切なタイミングで訪問し、遺族の心情を尊重しましょう。
思い出や感謝の言葉を伝える
葬式に出席できない場合でも、故人や遺族に対する思い出や感謝の言葉を伝えることが重要です。直接会うことが難しい場合でも、手紙や電話で伝えることができます。
葬儀後に連絡をとる
葬儀後、適切なタイミングで遺族に連絡をとり、お悔やみの意を再度伝えることが大切です。適切なフォローアップを行い、遺族を支えることができます。
葬式 行かない 孫の対応方法
葬式に孫が行かない場合、適切な対応方法が求められます。以下に、その具体的な方法を紹介します。
欠席理由を丁寧に説明する
まず、孫が葬式に行けない理由を丁寧に説明することが重要です。例えば、学業や仕事の都合、遠方での生活など、具体的な理由を明確に伝えることで理解を得やすくなります。
お悔やみの言葉を伝える
欠席する場合でも、故人への敬意を示すためにお悔やみの言葉を伝えることが大切です。手紙や電話でお悔やみの気持ちを伝えると良いでしょう。
弔電や供花を送る
孫が葬式に行けない場合、弔電や供花を送ることで、故人への敬意と遺族への配慮を示すことができます。弔電はインターネットや電話で手配でき、供花も同様に手配可能です。
後日訪問してお悔やみを述べる
葬式に出席できない場合、後日遺族を訪問してお悔やみを述べるのも一つの方法です。遺族の都合を確認した上で、適切なタイミングで訪問しましょう。
故人との思い出を共有する
孫が故人との思い出を共有することも、敬意を示す方法の一つです。手紙や電話で故人との思い出や感謝の気持ちを伝えることで、遺族も慰められるでしょう。
香典を送る
葬式に行けない場合、香典を送ることも重要です。香典は郵便局の現金書留を使って送ることができます。香典に添えて、お悔やみの手紙も一緒に送ると良いでしょう。
家族と相談して対応を決める
葬式に行けない場合は、家族と相談して対応を決めることが大切です。家族の意見を聞きながら、最適な対応方法を見つけるようにしましょう。
これらの方法を活用して、孫としての敬意と配慮を示すことができます。葬式に行けない場合でも、故人や遺族への敬意を忘れずに、適切な対応を心がけましょう。
葬式 行かない 親族への配慮
葬式に行けない場合、親族への配慮が非常に重要です。以下のポイントを参考にして、適切な対応を心がけましょう。
事前に欠席の連絡をする
葬式に行かないことが決まったら、できるだけ早く親族に連絡を入れることが大切です。早めの連絡で、親族も葬式の準備に影響を受けずに済みます。
丁寧な言葉で欠席理由を説明
欠席する理由は丁寧に説明しましょう。例えば、仕事の都合、体調不良、遠方に住んでいるなど、具体的な理由を伝えることで理解を得やすくなります。
お悔やみの言葉を伝える
欠席の連絡と一緒に、お悔やみの言葉を伝えることを忘れないようにしましょう。「このたびはご愁傷さまです」「心からお悔やみ申し上げます」などの言葉で気持ちを伝えます。
弔電や供花を送る
葬式に行かない場合でも、弔電や供花を送ることで故人への敬意を示すことができます。これにより、親族にも配慮していることが伝わります。
香典を郵送する
香典を郵送する際は、現金書留を使用しましょう。香典に加えて、お悔やみの手紙を添えると、より一層の配慮を示すことができます。
後日訪問してお悔やみを述べる
葬式に行けなかった場合、後日親族を訪問してお悔やみを述べることも大切です。事前に訪問の日時を確認し、無理のない範囲で直接気持ちを伝えましょう。
電話や手紙でフォローアップ
直接会えない場合は、電話や手紙でフォローアップすることも有効です。親族への感謝の気持ちやお悔やみの言葉を伝えることで、誠意が伝わります。
親族との関係を大切にする
葬式に行かない場合でも、親族との関係を大切にする姿勢を示すことが重要です。日常的に連絡を取るなど、親しい関係を維持する努力をしましょう。
適切なタイミングでお詫びを伝える
欠席したことに対して、適切なタイミングでお詫びの気持ちを伝えることも忘れないようにしましょう。誠意を持って対応することで、親族も理解してくれるはずです。
感謝の気持ちを忘れない
親族に対しては、常に感謝の気持ちを持って接することが大切です。葬式に行けなかったとしても、日頃からの配慮が信頼関係を築く鍵となります。
以上の方法を活用して、葬式に行けない場合でも親族への配慮をしっかりと行いましょう。誠意を持った対応が大切です。
葬式 行かない めんどくさいと感じる時
葬式に行かないことを「めんどくさい」と感じる瞬間があるかもしれません。ここでは、そうした状況に対処する方法と、それでも参列することの重要性について説明します。
時間が取れない場合
忙しいスケジュールの中で葬式に参列する時間を作るのは大変です。仕事や家庭の用事が重なると、時間を割くのが難しくなります。しかし、亡くなった方との最後のお別れの場であることを考えると、時間を作る価値があります。
精神的に疲れている時
日々のストレスや疲労が溜まっていると、葬式に行くのが負担に感じることもあります。特に、葬式は感情的にも辛い場面です。自分の心身の健康を優先することも大切ですが、後悔しない選択をするためにも、可能な限り参列を検討しましょう。
人間関係のストレス
葬式では親戚や知人と顔を合わせることが避けられません。これがストレスに感じる人も少なくありません。距離を置いた関係であっても、葬式に参列することで礼儀を尽くし、後々のトラブルを避けることができます。
移動が不便な場合
葬式の会場が遠方であったり、交通の便が悪かったりする場合、移動が面倒に感じることがあります。この場合でも、タクシーやレンタカーを利用するなどの手段を考えてみると、移動の負担を軽減できます。
準備が煩わしいと感じる時
葬式に参列するためには、喪服の準備や香典の用意などが必要です。これらの準備が煩わしく感じることもあるでしょう。しかし、一度準備を整えておくことで、次回からはスムーズに対応できるようになります。
個人的な事情がある場合
例えば、葬式の直前に予定していた旅行やイベントがあると、葬式に行くのが面倒に感じることがあります。このような場合、自分の優先順位を見直し、最も重要なことを選択するようにしましょう。
経済的な負担が大きい時
葬式に行くための交通費や香典など、経済的な負担も無視できません。費用がかかることが理由で行くのが面倒に感じる場合もあるでしょう。無理のない範囲で参列し、どうしても難しい場合は他の方法でお悔やみを伝えることも検討してください。
対策とまとめ
葬式に行かない理由が「めんどくさい」と感じることから来る場合でも、その理由を見直し、可能な限り参列することが後悔しない選択に繋がります。時間や準備の負担を軽減する方法を探し、自分なりの対策を立てることが大切です。どのような状況であっても、礼儀を尽くすことで周囲との関係を良好に保つことができます。
葬式行かないことが問題にならない場合
葬式に行かないことが必ずしも問題になるわけではありません。以下のような状況では、葬式に行かないことが問題にならない場合があります。
遠方に住んでいる場合
遠方に住んでいるため葬式に行くのが難しい場合、無理に出席する必要はありません。交通費や宿泊費の負担が大きくなることもあり、遠距離での移動が困難な場合は、その旨を伝えるだけで理解してもらえることが多いです。
体調不良や療養中の場合
体調が悪い場合や療養中の場合は、無理をして参列する必要はありません。自分の健康を優先することが重要であり、入院中や病気療養中であることを伝えれば、遺族も理解してくれるでしょう。
関係が薄い場合
故人との関係が非常に薄い場合、例えば数回しか会ったことがない知人や仕事関係者であれば、参列しないことが非常識とは見なされないことが多いです。この場合も、お悔やみの言葉や弔電を送ることで誠意を示すことができます。
家族葬である場合
家族葬が行われる場合、近親者のみが参列することが一般的です。家族葬の意向を尊重し、外部の人が無理に参列しないほうが、かえって配慮に繋がります。この場合、後日弔問するか、香典を送ることで対応しましょう。
仕事の都合がつかない場合
仕事の都合でどうしても休めない場合もあります。重要な会議やプロジェクトがある場合、仕事を優先せざるを得ないことがあります。この場合も、事前に遺族に連絡し、お悔やみの言葉を伝えることが大切です。
感染症の流行時
感染症が流行している場合、参列を控えることは他者への配慮にもなります。特に高齢者や持病を持つ方が多く集まる葬儀では、感染リスクを避けるために参列しない選択も理解されやすいです。
緊急の家族事情
家族に緊急の事情がある場合も、無理に参列する必要はありません。例えば、子どもの病気や緊急手術など、家庭の事情を優先することが求められる場合は、その旨を伝えましょう。
喪主が了承している場合
喪主や遺族が参列を免除することを了承している場合も、問題にはなりません。事前に相談し、理解を得ておくことが大切です。
弔電や香典を送る場合
参列できない場合でも、弔電や香典を送ることでお悔やみの気持ちを示すことができます。気持ちを形にして伝えることで、誠意を示すことができ、参列しないことが問題視されることは少なくなります。
これらの状況を踏まえ、自分の状況に応じた対応を考えることで、葬式に行かないことが問題にならないようにすることができます。大切なのは、故人や遺族に対する思いやりを忘れないことです。
葬儀 行かない方がいい場合の判断基準
葬儀に参列しない方が良い場合があります。その判断基準について、以下で具体的に説明します。
遠方に住んでいる場合
葬儀が行われる場所が自宅から遠い場合、交通費や宿泊費の負担が大きくなります。特に長距離移動が必要な場合や、日程的に無理がある場合は、参列しない選択もあります。
体調不良や療養中の場合
体調が悪い、または療養中の場合、無理をして参列することは避けるべきです。自身の健康を優先し、感染症の拡大を防ぐためにも、家で静養することが大切です。
感染症の流行時
感染症が流行している時期には、多くの人が集まる葬儀場で感染リスクが高まります。他者への配慮としても、感染症対策を優先し、参列を控えるのが賢明です。
仕事や家庭の都合がつかない場合
どうしても外せない仕事や家庭の事情がある場合も、参列を控える理由になります。責任を果たすためには、仕事や家庭を優先せざるを得ない状況もあるでしょう。
故人との関係が薄い場合
故人との関係が薄い場合、例えば一度しか会ったことがない知人などであれば、無理に参列する必要はありません。この場合、香典や弔電を送ることで誠意を示すことができます。
家族葬が行われる場合
家族葬の場合、近親者だけが参列することが一般的です。家族葬の意向を尊重し、無理に参加しない方が配慮に繋がります。後日弔問するか、香典を送ることで対応しましょう。
高齢や体力の問題がある場合
高齢者や体力に不安がある方は、長時間の移動や葬儀での体力的な負担が大きくなります。無理をしないことが重要です。家族に相談し、自分の体調を優先しましょう。
遠方での葬儀に出席するための経済的負担
遠方での葬儀に出席するための経済的な負担が大きい場合、無理をして参列する必要はありません。予算の制約も考慮に入れ、他の形で故人への思いを伝える方法を選びましょう。
喪主や遺族の意向を尊重する場合
喪主や遺族が参列を免除する場合もあります。事前に相談し、了承を得た上で参列を控えることが大切です。これは遺族の負担を軽減することにもなります。
精神的な負担が大きい場合
故人との思い出が強く、精神的な負担が大きい場合、参列することが苦痛になることもあります。自身の精神状態を考慮し、無理をしない選択が必要です。
これらの基準をもとに、自分の状況に合わせて判断することが大切です。参列しない場合でも、香典や弔電を送ることで誠意を示し、遺族への配慮を忘れないようにしましょう。
葬式行かない非常識と呼ばれる
葬式 行かない 主義を貫く理由
葬式に行かないという主義を貫く理由には、いくつかの重要なポイントがあります。ここでは、その理由を具体的に説明します。

個人の信念や価値観
多くの人にとって、葬式に行かないという選択は個人の信念や価値観に基づいています。例えば、故人との別れは心の中で行うものであり、形式的な儀式に参加する必要はないと考える人もいます。このような価値観を持つ人々は、自分の信念を大切にし、他人の期待に左右されない生き方を選びます。
精神的な負担を避けるため
葬式は、精神的に非常に重い場であることが多いです。特に、過去のトラウマや感情的な負担が大きい場合、精神的な健康を守るために葬式に行かないという選択をすることがあります。このような人々は、故人との思い出を心の中で大切にしつつ、自分自身の精神的な安定を優先します。
宗教的または哲学的な理由
宗教や哲学的な理由から、葬式に行かないという選択をする人もいます。例えば、特定の宗教では、死後の儀式に参加することが求められていない場合があります。また、哲学的に、死は個人的な出来事であり、他者と共有するものではないと考える人もいます。
形式的な儀式への違和感
一部の人々は、葬式のような形式的な儀式に対して違和感を感じます。彼らは、形式よりも故人との個人的な思い出を大切にする傾向があります。例えば、故人との思い出の場所を訪れることや、個人的な追悼の時間を持つことで、故人を偲ぶ方法を選びます。
人間関係の負担を軽減するため
葬式に参加することで、人間関係の複雑さや緊張感を感じることがあります。特に、家族や親族との関係が複雑な場合、不必要なストレスや対立を避けるために葬式に行かない選択をすることがあります。このような選択は、自分自身の平和を保つための重要な手段となります。
自己のライフスタイルの一環
葬式に行かないという主義は、自己のライフスタイルの一部として確立されている場合もあります。例えば、ミニマリストやシンプルライフを実践する人々は、余計な儀式や集まりを避ける傾向があります。彼らは、必要最低限の活動に集中し、自分の時間やエネルギーを大切にします。
故人の意向を尊重する
場合によっては、故人自身が葬式を望まなかったという理由で葬式に行かないこともあります。故人の遺志を尊重し、故人の希望に沿った形で追悼することが、最も重要であると考える人々もいます。
これらの理由により、葬式に行かないという主義を貫く人々は、自分自身の信念や価値観を大切にし、他者の期待に左右されない選択をしています。自分にとって最も大切なものを守るために、このような判断をすることが理解されるべきです。
葬式 行きたくない ニートの場合
葬式に行きたくないと感じるニートの場合、特有の悩みや対処法があります。ここでは、その具体的な対応策について説明します。
心理的な負担の軽減
葬式に参加することに対して心理的な負担を感じるニートの方は多いです。人前に出ることや親族との対面がストレスになることがあります。事前に心の準備をすることが大切です。例えば、親しい友人や家族に相談して気持ちを整理することで、少しでも不安を軽減できます。
経済的な理由
ニートの場合、経済的な理由で葬式に行けないということもあります。交通費や礼服の購入費用が負担になることが多いです。このような場合、家族や親族に事情を説明し、理解を求めることが重要です。また、インターネットで調べて、低コストで葬儀に参加する方法を探すこともできます。
葬式への恐怖や不安
葬式そのものに対して恐怖や不安を感じる場合もあります。特に、葬儀場の雰囲気や死に対する恐怖が強いと感じる人も少なくありません。専門のカウンセラーに相談することで、恐怖心を和らげる手助けを得ることができます。
参加しない場合の配慮
どうしても葬式に参加できない場合、他の方法で弔意を表すことが大切です。弔電を送ったり、香典を郵送したりすることで、故人や遺族に対する気持ちを伝えることができます。このような配慮をすることで、参加できないことに対する罪悪感を軽減することができます。
家族とのコミュニケーション
家族や親族に対して、自分の状況や気持ちを正直に伝えることが重要です。理解と協力を求めることで、無理に参加することを避けられるかもしれません。家族とのコミュニケーションを大切にし、適切なサポートを受けることができるように努めましょう。
代替の方法を考える
直接葬式に参加しなくても、故人を偲ぶ方法は他にもあります。例えば、家で故人の写真を飾り、静かに思い出を振り返る時間を持つことも一つの方法です。自分に合った方法で故人を偲ぶことができます。
支援団体の利用
ニートの方を支援する団体やコミュニティが存在します。これらの団体に相談することで、適切なアドバイスやサポートを受けることができます。インターネットで検索し、自分に合った支援団体を見つけてみましょう。
このように、葬式に行きたくないと感じるニートの場合でも、さまざまな方法で対処することができます。無理をせず、自分のペースで適切な対応を考えましょう。
祖母の葬式に行かない孫の言い訳
祖母の葬式に行かない理由を説明する場合、家族や親族に対する配慮が必要です。ここでは、具体的な言い訳とその伝え方について説明します。
仕事の都合で行けない
多くの人が直面する理由の一つに仕事の都合があります。例えば、「重要な会議があり、どうしても外せない」と説明することが考えられます。この場合、事前に上司に相談し、可能であれば会議のスケジュールを調整する努力も見せると良いでしょう。
遠方に住んでいるため
遠方に住んでいる場合、移動が困難なこともあります。「遠方に住んでいて、交通費や時間の都合がつかない」と正直に伝えることが大切です。特に、高齢者や学生の場合、長距離の移動が体力的に厳しいこともあります。
体調不良による欠席
体調不良はやむを得ない理由です。「現在体調を崩しており、医師から安静が必要と言われている」と伝えることで、相手に無理をしてほしくないという意図を伝えられます。詳細な病状を話す必要はなく、「療養中」と説明するだけで十分です。
経済的な理由
経済的な事情で参列が難しい場合もあります。「現在の経済状況では、移動や宿泊の費用が捻出できない」と説明します。この場合、代替策として香典を送るなどの方法で弔意を示すことが重要です。
学業や試験のため
学生の場合、試験や重要な学業のイベントがあることを理由にすることもあります。「大学の試験期間中で、どうしても外せない」と伝えることができます。これにより、相手も理解を示しやすくなります。
家族の事情
家庭内の事情でどうしても行けない場合もあります。「小さい子どもの世話をしなくてはいけない」や「家族の介護が必要で、離れられない」など、具体的な理由を挙げることで相手に理解してもらいやすくなります。
感染症のリスク
現在の状況では、感染症のリスクを理由にすることもあります。「感染症対策として、人が多く集まる場所に行くのは避けたい」と伝えることで、自分自身と家族の健康を守る意図を説明できます。
フォローアップの提案
行けない理由を説明した後に、フォローアップの提案をすることが大切です。「後日お参りに伺います」や「別の日に弔問させていただきます」といった提案をすることで、弔意を示すことができます。
このように、祖母の葬式に行かない理由を説明する際は、相手に配慮しながら誠意を持って伝えることが重要です。具体的な状況と合わせて、適切な言い訳を考えましょう。
葬式に行かない理由の伝え方
葬式に行かない理由を伝える際には、相手への配慮と誠意が重要です。ここでは、具体的な伝え方について説明します。
早めに連絡をする
まず、葬式に行かないことを決めたら早めに連絡を入れましょう。遺族は葬儀の準備で忙しいため、早めに伝えることで相手の負担を軽減できます。例えば、「申し訳ありませんが、仕事の都合でどうしても参列できません」と事前に連絡することで、相手も対応しやすくなります。
理由を簡潔に伝える
次に、理由を簡潔に伝えることが大切です。詳細に説明する必要はなく、やむを得ない事情を強調することがポイントです。例えば、「遠方に住んでいて、移動が難しいため今回は欠席させていただきます」と簡潔に伝えましょう。
お悔やみの言葉を添える
理由を伝える際には、お悔やみの言葉を添えることを忘れないようにしましょう。例えば、「このたびはお悔やみ申し上げます。心からご冥福をお祈りいたします」と述べることで、相手に対する敬意を示すことができます。
具体的な対応策を提案する
行けない理由を伝えるだけでなく、具体的な対応策を提案することも大切です。例えば、「後日、お線香をあげに伺います」や「香典を送らせていただきます」といった提案をすることで、弔意を示すことができます。
配慮のある言い回しを心掛ける
伝え方には配慮のある言い回しを心掛けましょう。例えば、「どうしても外せない仕事があり」と伝えることで、やむを得ない事情であることを強調します。また、「療養中のため」といった体調不良の理由も丁寧に伝えることで、相手に理解してもらいやすくなります。
電話で直接伝える
可能であれば、電話で直接伝えることが最も誠意が伝わります。電話が難しい場合は、メールや手紙でも構いませんが、その際には丁寧な言葉遣いを心掛けましょう。例えば、「ご連絡が遅くなり申し訳ありません。体調不良により参列できないことをお許しください」といった形で伝えます。
葬儀後のフォローを忘れない
葬儀に行けなかった場合でも、後日のフォローを忘れないことが重要です。例えば、「後日、改めてお参りに伺います」と伝え、実際に訪問することで相手の心象も良くなります。
このように、葬式に行かない理由を伝える際は、相手への配慮と誠意を忘れずに、具体的かつ簡潔に伝えることが大切です。
葬式に行かない場合のマナー
葬式に行かない場合でも、適切なマナーを守ることで故人や遺族への敬意を示すことができます。ここでは、具体的なマナーについて説明します。
早めに連絡を入れる
まず、葬式に行かないことを決めたら早めに連絡を入れることが重要です。遺族は多忙な時期であり、早めに連絡することで相手の準備に余裕ができます。例えば、「申し訳ありませんが、仕事の都合で参列できません」と早めに伝えることで、相手も適切に対応できます。
理由を簡潔に伝える
理由は簡潔に伝えることが大切です。詳細に説明する必要はありません。例えば、「遠方に住んでいるため今回は欠席します」とやむを得ない事情を簡潔に伝えると良いでしょう。
お悔やみの言葉を添える
理由を伝える際には、お悔やみの言葉を添えることを忘れないようにしましょう。「このたびはお悔やみ申し上げます」といった言葉を添えることで、遺族への配慮を示すことができます。
弔電を送る
葬式に行けない場合は、弔電を送るのも良い方法です。弔電は、遺族に対してお悔やみの気持ちを伝える手段として効果的です。例えば、「遠方のため参列できませんが、心からお悔やみ申し上げます」といったメッセージを送ると良いでしょう。
香典を送る
香典を送ることも大切です。葬式に行けない場合でも、香典を送ることで故人への敬意を示せます。香典は現金書留で送り、お悔やみ状を添えるとさらに丁寧です。例えば、「葬儀に参列できず申し訳ありません。心からお悔やみ申し上げます」といったメッセージを添えます。
後日弔問する
後日、弔問に訪れることも考えましょう。遺族が落ち着いた頃に訪れ、お悔やみの気持ちを伝えることが大切です。事前に連絡を入れ、都合の良い日時を確認してから訪問します。
電話で直接伝える
可能であれば、電話で直接伝えることが最も誠意が伝わります。電話が難しい場合は、メールや手紙でも構いませんが、その際には丁寧な言葉遣いを心掛けましょう。「ご連絡が遅くなり申し訳ありません。体調不良により参列できないことをお許しください」といった形で伝えます。
適切な服装で弔問
弔問する際は、適切な服装で訪れることが大切です。喪服や黒のスーツを着用し、落ち着いた服装で訪問することで遺族への敬意を示します。
このように、葬式に行かない場合でも適切なマナーを守ることで、遺族や故人に対する敬意をしっかりと示すことができます。
葬式に行かないことを正当化する方法
葬式に行かないことを正当化するには、いくつかの方法があります。これらの方法を理解しておくことで、周囲の理解を得やすくなりますし、自分自身も納得しやすくなります。
健康上の理由を説明する
まず、健康上の理由を正直に説明することです。例えば、「現在療養中であるため、葬式に参加できません」と伝えることで、無理をせずに自分の健康を優先することができます。体調不良や感染症対策など、他人に影響を与えないための理由は特に理解されやすいです。
仕事や家庭の事情を伝える
仕事や家庭の事情を理由にすることも有効です。例えば、「重要な会議があるため」や「子供の世話が必要なため」といった具体的な状況を伝えると、周囲も納得しやすいでしょう。仕事や家庭の事情は多くの人が共感できる理由です。
遠方に住んでいることを伝える
遠方に住んでいる場合は、そのことを理由にすることができます。例えば、「葬式の場所が遠方で、交通費や時間の都合がつかないため」と説明することで、現実的な理由として理解されやすいです。距離と費用を理由にすると、無理のない範囲で行動できます。
故人との関係性を考慮する
故人との関係性が薄い場合、そのことを理由にすることも考えられます。例えば、「故人とはほとんど交流がなかったため」と説明することで、無理に参列する必要がないことを伝えられます。関係性の薄さを理由にすることで、合理的な判断ができます。
適切な代替手段を提示する
葬式に行かない場合でも、代替手段を提示することで理解を得やすくなります。例えば、「後日、弔問に伺います」や「香典を郵送させていただきます」といった対応をすることで、誠意を示すことができます。具体的な代替案を示すことで、欠席の正当性が高まります。
早めの連絡と誠意ある態度
欠席を決めた場合は、早めに連絡し、誠意ある態度を示すことが重要です。例えば、「申し訳ありませんが、事情があり参列できません」といった形で早めに連絡し、お悔やみの言葉を添えることで、遺族への配慮を示せます。早めの連絡と誠意が信頼を得るポイントです。
感謝の気持ちを伝える
欠席を正当化するためには、感謝の気持ちを伝えることも大切です。例えば、「故人には大変お世話になりました」と伝えることで、故人への敬意を示しつつ、欠席の理由を説明できます。感謝の気持ちを伝えることで、理解を得やすくなります。
以上の方法を用いることで、葬式に行かないことを正当化しやすくなります。自分自身の状況や理由をしっかりと伝え、誠意を持って対応することが大切です。
葬式に行かない場合の香典の送り方
葬式に行かない場合でも、香典を送ることで故人や遺族への気持ちを伝えることができます。ここでは、香典の送り方について具体的に説明します。
香典を現金書留で送る方法
まず、香典を送る際には現金書留を利用するのが一般的です。現金書留は郵便局で手続きができ、安全に現金を送ることができます。以下のステップで送るとスムーズです。
- 香典袋にお金を入れる:香典袋にお金を入れ、「御霊前」などの表書きを記入します。
- 現金書留用の封筒に入れる:香典袋を現金書留用の封筒に入れ、郵便局で手続きをします。
- 差出人と宛先を記入:差出人と宛先の情報を正確に記入します。宛先は喪主の名前を記載するのが一般的です。
- 郵便局で送付手続きをする:郵便局で現金書留の手続きを行い、安全に送付します。
お悔やみ状を添える
香典だけでなく、お悔やみ状を添えることで、より丁寧な印象を与えることができます。お悔やみ状には、以下のような内容を記載します。
- お悔やみの言葉:「このたびは誠にご愁傷さまです」といったお悔やみの言葉を入れます。
- 欠席の理由:「やむを得ない事情により参列できず、申し訳ありません」と欠席の理由を簡潔に述べます。
- 故人への感謝:「故人には大変お世話になりました」といった感謝の気持ちを伝えます。
送り先の確認
香典を送る前に、送り先の住所や喪主の名前を確認することが重要です。送り先が間違っていると、せっかくの香典が遺族に届かない可能性があります。確実な情報を得るために、遺族や葬儀の担当者に直接確認するのが良いでしょう。
送るタイミング
香典は、葬儀の前日までに届くように手配するのが理想です。もし間に合わない場合でも、葬儀後1週間以内には届くように心がけます。遅れることがないよう、できるだけ早めに手続きを開始しましょう。
香典の金額
香典の金額は、故人との関係性や自分の年齢、立場によって異なります。一般的には5,000円から1万円程度が多いですが、親しい関係であればそれ以上の金額を包むこともあります。適切な金額を選ぶことが重要です。
このように、葬式に行かない場合でも、香典を正しく送ることで遺族に対する礼儀を尽くすことができます。丁寧な手続きを行い、故人と遺族への配慮を示しましょう。
葬式に行かない場合の弔電の送り方
葬式に行かない場合でも、弔電を送ることで故人や遺族への思いを伝えることができます。ここでは、弔電の送り方について具体的に説明します。
弔電を送るタイミング
弔電は葬儀の前日までに届くように手配するのが理想です。できるだけ早めに手配し、遅れないように注意しましょう。もし間に合わない場合でも、遅くとも葬儀の当日の午前中までには届くようにします。
弔電の内容
弔電には、以下のような内容を含めます。
- お悔やみの言葉:「このたびはご愁傷さまです」といったシンプルなお悔やみの言葉を入れます。
- 故人への感謝:「故人には大変お世話になりました」と故人への感謝の気持ちを伝えます。
- 遺族への配慮:「どうかご自愛ください」と遺族への配慮も忘れずに記載します。
弔電の手配方法
弔電は、主に以下の方法で手配できます。
- 電話での手配:NTTなどの電報サービスに電話をかけて手配します。オペレーターに指示を伝えるだけで、簡単に弔電を送ることができます。
- インターネットでの手配:各電報サービスのウェブサイトからオンラインで手配することも可能です。インターネットでの手配は、24時間対応していることが多く、便利です。
送り先の確認
弔電の送り先は、葬儀会場や遺族の自宅が一般的です。送り先を間違えないように、葬儀の案内や遺族からの連絡を確認して正確に記載しましょう。
弔電の料金
弔電の料金は、文字数やオプションによって異なります。一般的には3,000円から5,000円程度が多いです。装飾付きの弔電や特別な文面を選ぶと料金が上がることもあるため、予算に応じて選びましょう。
弔電の例文
以下に、弔電の例文を示します。
このたびはご愁傷さまです。
突然の訃報に接し、言葉もございません。
故人には大変お世話になり、感謝の念に堪えません。
どうかご自愛ください。このように、弔電を送ることで故人や遺族への気持ちをしっかりと伝えることができます。適切な手配と丁寧な文面を心がけて、礼儀を尽くしましょう。
葬式に行かない場合の後日弔問の方法
葬式に行けなかった場合でも、後日弔問することで故人への敬意を表し、遺族へのお悔やみの気持ちを伝えることができます。ここでは、後日弔問の具体的な方法について説明します。
弔問のタイミング
弔問するタイミングは重要です。葬儀が終わってから3日後から四十九日までが一般的な時期とされています。この期間内で遺族の都合を考慮し、適切な日を選びましょう。
事前の連絡
弔問する前には、必ず遺族に連絡を入れましょう。突然の訪問は避け、事前にアポイントメントを取りましょう。「弔問に伺いたいのですが、ご都合はいかがでしょうか」といった形で尋ねると良いです。
持参するもの
弔問の際には、以下のものを持参すると良いでしょう。
- 香典:既に送っている場合は不要ですが、まだの場合は持参します。
- 供花または供物:故人のためにお花やお供え物を用意します。供花は白や黄色の花が一般的です。
- 弔問状:お悔やみの言葉を書いた手紙も添えると、遺族に丁寧な印象を与えます。
服装のマナー
弔問の際の服装は、落ち着いた色合いの平服が適しています。スーツやワンピースなど、シンプルで控えめな装いを心がけましょう。喪服は避ける方が無難です。
弔問の流れ
弔問の際は、まず遺族に挨拶をし、お悔やみの言葉を述べます。その後、持参した香典や供花を手渡し、故人をしのびます。遺族が許可すれば、仏壇や祭壇の前で手を合わせることも良いでしょう。
お悔やみの言葉
お悔やみの言葉はシンプルで心のこもったものを選びましょう。例えば、「このたびはご愁傷様です。心よりお悔やみ申し上げます」といった言葉が適しています。
滞在時間
弔問の滞在時間は、長くても30分程度が目安です。遺族の負担にならないよう、短時間で要点を伝えることが大切です。
フォローアップ
弔問後、遺族に対して改めて感謝の気持ちを伝えるために、お礼状を送ることも一つの方法です。「弔問の際はお忙しい中ありがとうございました」といった簡潔な内容で構いません。
このように、後日弔問することで故人や遺族への思いをしっかりと伝えることができます。丁寧な対応を心がけ、遺族への配慮を忘れないようにしましょう。
葬式行かない非常識のまとめ
- 社会的な礼儀を欠くとみなされるため
- 遺族の心情を傷つける可能性があるため
- 故人への敬意を欠いていると見なされるため
- 社会的な評価に影響するため
- 後々の人間関係に影響を及ぼすため
- 家族や親族との関係悪化を招くため
- 会社や職場での印象が悪くなるため
- 文化的・宗教的な背景も影響するため
- 故人や遺族に直接連絡をとることが重要
- 手紙やメールでお悔やみを伝えることが有効
- 花や供物を贈ることで哀悼の気持ちを示す
- 後日、遺族を訪ねてお悔やみを述べる
- 思い出や感謝の言葉を伝えることが大切
- 葬儀後に再度遺族に連絡を取ることが望ましい
- 香典を郵送する際は現金書留を利用する
- 弔電を送る場合、遅くとも葬儀当日午前中までに届くようにする
- 遠方の場合、移動が難しいことを理由にできる
- 体調不良や療養中の場合、無理をしないことが重要
- 家族葬の場合、参列しないことが配慮になる場合もある
- 仕事の都合がつかない場合、理解を求めることができる
- 感染症の流行時、参列を控えることが配慮になる
- 緊急の家族事情がある場合、事情を説明することが重要
- 喪主が了承している場合、参列しないことも問題にならない
- 後日弔問する際は、適切なタイミングを選ぶ
- 適切なフォローアップを行い、遺族を支えることが大切
- 故人との関係性が薄い場合、参列しないことが理解されやすい
参考
・墓じまいで親戚お金の負担を軽減する秘訣
・嫡出子読み方と認知手続き: 親子関係の法的な扱い
・代襲相続読方:相続放棄と甥姪への適用範囲
・相続登記戸籍謄本有効期限の解説と必要な手続き
・相続不動産売却確定申告不要のケースと手続き
・相続登記登録免許税計算法務局の手続き完全ガイド
・必見!共有名義方死亡相続登記申請書の完全マニュアル
・未登記建物相続登記自分で進める方法と注意点
・相続争い末路:家族を守るための遺産分けのコツ
・相続登記義務化猶予期間とは?詳しい説明と概要
・相続登記費用譲渡費用の詳細ガイドと税務対策
・相続登記義務化未登記建物の義務と過料解説

お問い合わせ・60分無料相談
サービスや終活・相続・不動産に関するご相談やお困りごとなどお気軽にお問い合わせください
何をどうすればいいの?など初歩的な事でもまずはお話を聞かせてください。
エンディングノート・終活・老後資金・医療・介護・保険・相続・葬儀・お墓・その他
相談することによりお気持ちの整理が可能になります!お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはお気軽に!
大阪不動産・FPサービス株式会社
info@ofps.co.jp
TEL:050-3576-2951
投稿者プロフィール

-
ファイナンシャルプランナー・終活ガイド・
エンディングノート講師幅広いサポートが可能です!
終活・相続・事業承継・生命保険・老後資金のご相談の専門家です
不動産・リフォーム・ファイナンシャルプランニング・保険の見直し・終活・相続・家族信託・任意後見・遺言作成・生前整理・不用品買取・デイサービス・老人ホーム・お葬式・お墓他お悩み事すべてご対応可能なサービスをご準備しておりますので安心してお気軽にご相談ください。
最新の投稿
 相続2024-06-16配偶者居住権相続財産評価対象外の条件と具体的な例を解説
相続2024-06-16配偶者居住権相続財産評価対象外の条件と具体的な例を解説 不動産購入2024-06-15不動産取得税軽減措置延長で知っておくべき具体的な内容と手続き
不動産購入2024-06-15不動産取得税軽減措置延長で知っておくべき具体的な内容と手続き お役立ち情報2024-06-15双眼鏡どこに売ってる?ドンキホーテやエディオンなど主要店の紹介
お役立ち情報2024-06-15双眼鏡どこに売ってる?ドンキホーテやエディオンなど主要店の紹介 お役立ち情報2024-06-14ピアッサーどこに売ってる?ドンキ、マツキヨ、ウエルシアでの購入方法
お役立ち情報2024-06-14ピアッサーどこに売ってる?ドンキ、マツキヨ、ウエルシアでの購入方法