ご家族の認知症と向き合う中で、情報収集や同じ悩みを持つ人との繋がりのために、良い認知症ブログを探していませんか?なかなか自分に合ったブログが見つからず、途方に暮れてしまうこともありますよね。
結論から言うと、あなたの状況に合った認知症ブログを見つけるには、目的別に探すのが一番の近道なんです。
ただし、ひと口にブログと言っても、アルツハイマー型認知症のブログもあれば、アメブロで人気の介護ブログ、赤裸々な体験談ブログなど様々です。
認知症ブログランキングを鵜呑みにするだけでは、本当に知りたい情報にたどりこけないこともあります。
この記事では、認知症介護のストレスを抱える方や、一人暮らしの親御さんが心配な方のために、具体的な認知症家族の体験談から、認知症で一番大変な時期はいつですか?
といった疑問、認知症のダメ3原則とは?のような介護の知識、ボケやすい人の口癖や認知症に良い趣味まで、介護者の悩みと解決法を専門家の視点で詳しく解説しますね。
この記事のポイント
- 自分に合った認知症ブログの見つけ方がわかる
- 認知症の方への接し方の基本が理解できる
- 介護者のよくある悩みとその対処法がわかる
- 認知症介護に役立つ公的な相談先がわかる

こんにちは、やえです!
親御さんの介護は、本当に毎日が手探りですよね。実は、介護が始まると同時に「実家の片付け」や「将来の相続」といった問題も少しずつ見えてきます。
認知症ブログで日々の介護のヒントを得ながら、少し先の未来についても考えるきっかけにしていただけたら嬉しいです。一緒に一歩ずつ進んでいきましょうね!
【内閣府の推計】2025年には高齢者の約5人に1人が認知症に
内閣府のデータによると、日本の65歳以上の認知症高齢者数は2020年時点で約600万人と推計されています。これは高齢者人口の約6人に1人にあたります。さらに、この数は増加し続け、団塊の世代が75歳以上となる2025年には約675万人(高齢者の約5.4人に1人)に達すると見込まれています。
認知症は、決して他人事ではなく、誰もが自分や家族の問題として向き合うべき社会的な課題であることがわかります。
(出典:内閣府「令和5年版高齢社会白書」)
おすすめの認知症ブログとランキング

認知症ブログランキングの活用法
認知症に関する情報を探す際、多くの方がまず「認知症ブログランキング」をチェックするのではないでしょうか。特に「にほんブログ村」のような大手ランキングサイトは、多くの介護者や当事者の方が登録しており、情報収集の出発点として非常に役立ちます。
ランキングは、読者からのアクセス数(INポイント)や、そのブログからのアクセス数(OUTポイント)などで順位がつけられており、今まさに注目されているブログが一目でわかります。
ただし、ランキングを眺めるだけで終わらせてはもったいないですよ。大切なのは、ランキングを「自分だけの情報源を探すためのカタログ」として活用することです。
例えば、タイトルや短い紹介文を見て「お、これは自分の状況と似ているかも?」と感じたブログをいくつかピックアップしてみましょう。そして、実際に記事を読んでみて、以下のポイントをチェックするのがおすすめです。
ランキングから自分に合うブログを見つけるチェックポイント
- 介護のステージ:診断直後なのか、長年介護しているのか。ご自身の状況と近いですか?
- 発信内容:日々の出来事を綴る日記形式か、介護の工夫や制度について解説する情報系か。
- ブログの雰囲気:ユーモアを交えた明るいトーンか、真摯に葛藤を綴るトーンか。
- 更新頻度:定期的に更新されているか。リアルタイムの情報を求めている場合は重要です。
ランキング上位のブログが必ずしもあなたにとってベストなブログとは限りません。少し順位が下でも、あなたと同じ悩みを抱え、心に寄り添ってくれるようなブログが見つかることもあります。
ランキングはあくまで参考と割り切り、宝探しをするような気持ちで、じっくりと自分に合ったブログを探してみてくださいね。
認知症介護ブログはアメブロに多い

数あるブログサービスの中でも、「Amebaブログ(アメブロ)」には認知症介護に関するブログが非常に多く集まっています。これは、アメブロが単なる情報発信ツールではなく、利用者同士の交流を促す「コミュニティ」としての機能が充実しているからなんです。
在宅での介護生活は、時に社会から孤立しているような感覚に陥りがちです。そんな時、アメブロの「いいね」やコメント機能を通じて、「この記事、すごくわかります」「うちも同じことで悩んでいました」といった反応があると、「悩んでいるのは自分だけじゃないんだ」と実感でき、大きな心の支えになります。また、フォロー機能を使えば、気になるブロガーさんの更新情報を逃さずチェックできます。
さらに、アメブロには「公式ジャンル」という制度があり、「介護・闘病」といった大きな枠組みの中に「介護日記」などのテーマが設定されています。このジャンルに参加しているブログをたどることで、効率的に同じテーマのブログを探すことができます。
イラストや漫画を交えた「絵日記」形式のブログが多いのも特徴で、文章だけでは伝わりにくい日々の様子が視覚的にわかりやすく、楽しみながら読めるのも嬉しいポイントですね。誰かとの繋がりや共感を大切にしたい方にとって、アメブロは最適なプラットフォームと言えるでしょう。
アルツハイマー型認知症ブログも参考に
日本の認知症患者さんのうち、最も多くの割合を占めるのがアルツハイマー型認知症です。厚生労働省のウェブサイト「みんなのメンタルヘルス」によると、認知症の原因疾患の約67%がアルツハイマー病とされています。そのため、この病気に特化したブログも数多く存在し、非常に貴重な情報源となります。
アルツハイマー型認知症は、脳の神経細胞が少しずつ壊れていくことで、記憶障害から始まり、時間や場所がわからなくなる見当識障害など、様々な症状がゆっくりと進行していくのが特徴です。ブログには、診断された日から現在に至るまでの、長期的な介護の記録や、症状の進行段階に応じた家族の対応の変化などが詳細に綴られていることが多くあります。
アルツハイマー型認知症ブログから得られる情報例
- アリセプトなど、処方された薬の効果や副作用に関するリアルな感想
- 記憶を補うための生活上の工夫(メモの活用法、声かけの仕方など)
- ご本人の不安な気持ちに、家族がどう寄り添っていったかの記録
- デイサービスやショートステイなど、社会資源をどう活用したか
ご家族がアルツハイマー型と診断された方はもちろんですが、まだ診断は受けていないけれど「もしかして?」と不安を感じている方にとっても、具体的な症状のイメージを掴む上で大変役立ちます。診断後の生活がどのように変わっていくのか、どんな公的サポートが受けられるのか、先輩方のリアルな日々の記録から学べることは非常に多いはずです。
参考になる認知症体験談ブログ

専門書や医療サイトには、認知症の症状や一般的な対応方法が詳しく解説されています。もちろん、そうした正確な知識を学ぶことは非常に重要です。しかし、日々の介護生活で直面するのは、マニュアル通りにはいかない、もっと人間味あふれる出来事ばかりですよね。そんな時、何より心に響き、実際の行動のヒントになるのが、同じ道を歩んできた人たちの「体験談」です。
体験談ブログには、机上の空論ではない、生活の中から生まれた知恵が詰まっています。例えば、「食事を拒否する母に、好物だったおやつの話をしたら一口食べてくれた」「徘徊する父のポケットに、連絡先を書いたお守りを入れた」といった具体的なエピソードは、すぐにでも真似できるアイデアの宝庫です。成功談だけでなく、うまくいかなかった失敗談もまた、貴重な教訓となります。
「こんなことで悩んでいるのは、うちだけかもしれない…」という孤独感は、介護者を精神的に追い詰めます。しかし、体験談ブログを読んで「ああ、みんな同じことで悩み、葛藤しているんだ」と知るだけで、心がふっと軽くなるものです。きれいごとではないリアルな日々の記録だからこそ、深く共感でき、明日への力をもらえるのです。
リアルな認知症家族の体験談
「家族の介護」と一言で言っても、その内実は非常に複雑です。特に認知症の方を支える家族の体験談には、介護そのものの苦労だけでなく、それに付随して起こる様々な問題が赤裸々に綴られています。こうした「きれいごとではない」リアルな情報こそ、これから介護を始める方や、今まさに壁にぶつかっている方にとって、心の準備や問題解決の糸口になります。
家族の体験談で語られるリアルなテーマ
- 経済的な問題:介護費用は誰がどれだけ負担するのか。親の年金だけで足りない分はどうするか。
- 仕事との両立:介護離職せざるを得なくなった話。職場の理解を得るための苦労。
- 兄弟姉妹間の葛藤:介護への関わり方の違いによる意見の対立。「お金は出すけど手は出さない」兄弟への不満。
- 夫婦間の問題:自分の親の介護に、配偶者が非協力的であることへの悩み。
- 近所付き合いの変化:認知症の症状が原因で、ご近所とトラブルになってしまった事例。
これらの問題は、なかなか他人には相談しにくいものばかりです。しかし、ブログという匿名性の高い場所だからこそ、本音が語られます。
また、介護の辛さだけでなく、家族だからこそ気づけるご本人のふとした笑顔や、昔の優しさが垣間見えた瞬間など、心温まるエピソードが綴られていることも少なくありません。
大変な毎日の中にも確かな愛情や喜びがあることを再認識させてくれるのも、リアルな家族の体験談ブログの大きな魅力です。
一人暮らしの認知症ブログから学ぶ

親が一人暮らしをしていて認知症を発症した場合、同居して介護するケースとはまた違った、特有の難しさや課題に直面します。特に、子どもが遠方に住んでいる「遠距離介護」では、日々の見守りをどうするか、緊急時にどう対応するかが大きな悩みとなります。そんな時、同じ境遇にある方々が発信するブログは、実践的な知恵の宝庫です。
ブログを読んでいると、皆さんが様々なサービスやツールを駆使して、離れていても親御さんの安全な在宅生活を支えようと奮闘している様子がわかります。例えば、人感センサー付きの電球やポットでさりげなく安否確認をしたり、訪問介護や配食サービスを組み合わせたりと、具体的な工夫が満載です。
一人暮らし・遠距離介護ブログで得られる情報例
- 見守り:月額料金が手頃な見守りカメラ、GPS機能付きの靴など、最新ガジェットのレビュー。
- お金の管理:本人のプライドを傷つけずに金銭管理をサポートする方法。成年後見制度の利用体験談。
- 医療連携:ケアマネジャーや訪問看護師と、離れた場所からどうやって情報共有しているか。
- 帰省時のタスク:限られた帰省時間で、役所の手続きや病院の付き添いを効率よくこなすための段取り。
これらの情報は、まさに「今すぐ知りたい!」と思うような実践的なものばかり。また、中には認知症のご本人が、ご自身の言葉で日々の暮らしや思いを綴っているブログもあります。当事者の視点から見える世界を知ることは、私たちの認知症に対する理解を一層深めてくれる、非常に貴重な機会となるでしょう。
認知症介護ストレスブログで共感
【厚労省の調査】介護者の約7割が「悩みやストレス」を抱えている
厚生労働省の調査によると、同居している主な介護者のうち、日常生活での悩みやストレスを「ある」と回答した人は69.4%にものぼります。具体的なストレスの原因としては、「家族の病気や介護」が最も多く、次いで「自分の病気や介護」が挙げられています。
このデータは、多くの介護者が精神的な負担を抱えながら日々奮闘している現実を浮き彫りにしています。ブログなどで同じ境遇の人と繋がることが、いかに重要かがうかがえます。
介護は愛情や責任感だけでは乗り切れない、過酷な現実を伴います。24時間365日続く緊張感、思うようにいかないことへの苛立ち、先の見えない不安…。こうしたストレスは、知らず知らずのうちに介護者の心と体を蝕んでいきます。
そんな時、溜め込んだ感情を正直に吐き出しているブログを読むと、「辛いのは、私だけじゃなかったんだ」と痛感し、張り詰めていた気持ちが少し和らぐことがあります。
ブログには、「今日も大声を出してしまった」「優しくできなかった」といった自己嫌悪の気持ちや、「もう全部投げ出して逃げ出したい」というギリギリの本音が綴られていることも少なくありません。
こうした言葉に触れることは、自分自身の感情を肯定し、過度に自分を責めることから解放してくれる効果があります。コメント欄で「お気持ち、痛いほどわかります」「無理しないでくださいね」といった温かいメッセージを送り合うことで、バーチャルな「家族会」のように、孤独感が癒されていくのを感じる方も多いでしょう。
もちろん、ブログを読むだけでなく、あなた自身がブログを始めて、日々の思いを書き出してみるのも非常におすすめです。言葉にすることで、自分の感情が整理されたり、客観的に状況を見つめ直せたりする効果(カタルシス効果)が期待できます。誰かに見せるためでなくても構いません。自分のための「心の置き場所」として、ブログを活用してみてはいかがでしょうか。

ブログで他の人の体験を知るのは、本当に心強いですよね。特に遠距離介護の場合、実家の状況がどうなっているか把握しきれないことも。
介護サービスを利用し始めると、実家の契約書などを確認する機会も増えます。その時に、不動産の権利証や保険証券なども一緒に整理しておくと、後々の不動産に関する手続きがスムーズになりますよ。介護は長期戦、少しずつ準備を進めていきましょう。
認知症ブログから学ぶ介護の知識

認知症で一番大変な時期はいつですか?
これは、介護をされているご家族から本当によく聞かれる質問ですが、「この時期が一番大変」と一概に定義することは非常に難しいのが現実です。なぜなら、症状の現れ方や進行のスピードは人それぞれですし、ご本人の元々の性格、そして何より家族の介護環境や受け止め方が大きく影響するからです。
ただ、一般的な傾向として、行動・心理症状(BPSD)が顕著に現れる「中期」が、介護者にとって心身の負担がピークに達しやすい時期だと言われています。BPSDとは、中核症状(記憶障害など)に付随して起こる、行動や心理面での症状のことです。
行動・心理症状(BPSD)の具体例
| 行動面の症状 | 徘徊、介護への抵抗、暴力・暴言、ものを集める、落ち着きなく動き回る など |
|---|---|
| 心理面の症状 | 物盗られ妄想、幻覚(幻視・幻聴)、抑うつ、不安・焦燥、睡眠障害 など |
今まで穏やかだった人が急に怒鳴ったり、家族を泥棒扱いしたりと、まるで人格が変わってしまったかのような言動に、ご家族は深く傷つき、どう対応していいかわからず疲弊してしまいます。
しかし、人によっては、物忘れが増え始めた「初期」に、ご本人が一番つらい思いをしており、その不安な気持ちを受け止めるのが大変だと感じる方もいます。また、寝たきりに近くなる「後期」には、食事や排泄、入浴といった身体的な介護の負担が大きくなり、この時期を最も大変だと感じる方も少なくありません。
大切なのは、e-ヘルスネット(厚生労働省)などの公的情報も参考にしつつ、それぞれの時期の困難さを理解し、一人で抱え込まずに専門家や支援サービスに積極的に相談することです。
知っておきたい認知症のダメ3原則とは?
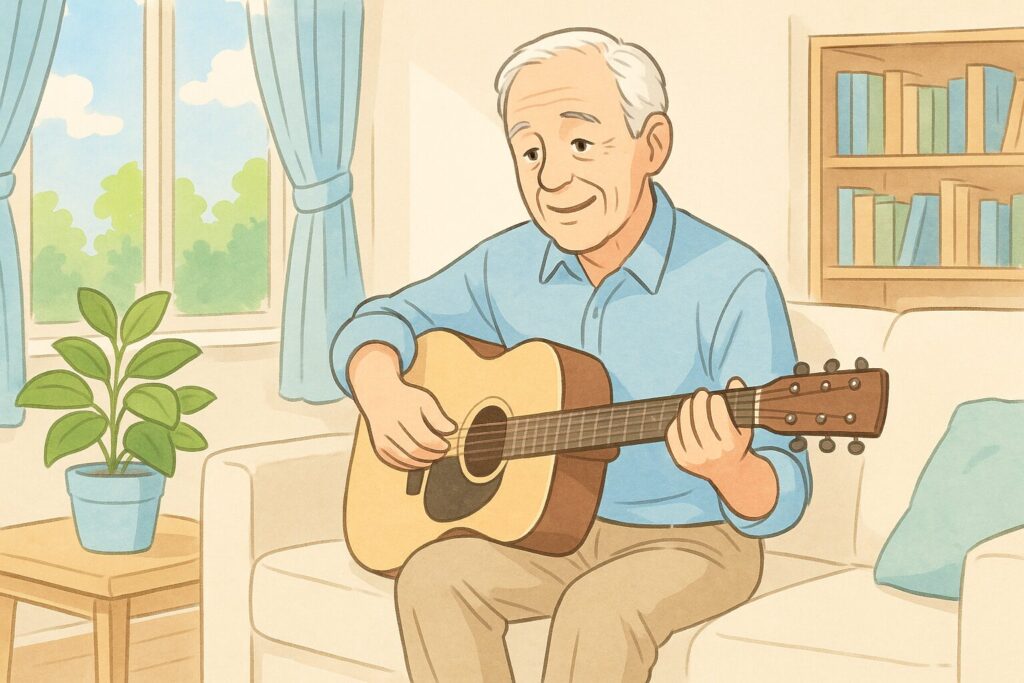
認知症の方と穏やかな関係を築き、ご本人が安心して日々を過ごせるようにするためには、家族の接し方が非常に重要になります。その基本となるのが、「驚かせない」「急がせない」「自尊心を傷つけない」という3つの原則です。これは、認知症ケアの世界では広く知られている考え方で、日々のコミュニケーションの指針となります。
1. 驚かせない(Don't surprise)
認知症の方は、見えないところからの物音や、予期せぬ出来事に対して非常に敏感で、強い不安を感じやすい状態にあります。例えば、良かれと思って後ろから「お母さん、着替えようか」と声をかけると、びっくりさせてしまい、かえって拒否につながることがあります。
話しかける時は、必ず相手の正面に回り、穏やかな表情でまず名前を呼び、「私だよ、やえだよ」と名乗ってから用件を伝えるようにしましょう。動作も一つひとつ「今から腕に触るね」と声に出して行うと、相手も心の準備ができます。
2. 急がせない(Don't hurry)
脳の機能低下により、認知症の方は一つの動作を終えるのに時間がかかるようになります。食事、着替え、トイレなど、日常生活のあらゆる場面で、私たちはつい「早く、早く」と急かしてしまいがちです。
しかし、急かされるとご本人は焦りと混乱でパニックになり、かえって時間がかかったり、失敗してしまったりします。介護する側には時間的な余裕がないことも多いですが、そこをぐっとこらえて、本人のペースを尊重することが大切です。時間に余裕を持ったスケジュールを組むこと自体が、有効なケアの一つと言えます。
3. 自尊心を傷つけない(Don't hurt their pride)
これが最も重要で、かつ難しい原則かもしれません。認知症になっても、長年培ってきたプライドや羞恥心は残っています。物忘れを厳しく指摘したり、「また同じこと言って」と呆れた態度をとったり、子どもを諭すような口調で話したりすることは、ご本人の自尊心を深く傷つけます。
たとえ失敗しても、「大丈夫だよ、誰にでもあることだよ」と肯定的に受け止め、「どうしてできないの?」ではなく「どうしたらできるか一緒に考えようか」というスタンスで接することが、信頼関係を築く上で不可欠です。
そんな時に心に届くねぎらいの言葉をかけることで、相手の気持ちに寄り添うことができます。「忘れても、感情は残る」という言葉を、常に心に留めておきたいですね。
気になるボケやすい人の口癖は?
「これを言うとボケやすい」といった特定の口癖が、認知症の直接的な原因になるという科学的な根拠はありません。ですので、あまり神経質になる必要はありませんよ。
ただ、認知機能の低下に伴って、会話の中に以前とは違う特徴的な変化が現れることがある、とは言われています。ご家族が「最近、口癖が変わったな」と感じた時は、もしかしたらそれは脳からの小さなサインかもしれません。あくまで一般的な傾向として、以下のようなものが挙げられます。
注意したい会話の変化とその背景
- 指示語の多用(「あれ」「それ」「あそこ」):物の名前が思い出せない「語想起障害」の現れである可能性があります。脳の記憶を司る部分の機能が低下しているサインかもしれません。
- 同じ話の繰り返し:新しいことを記憶する力が弱まっているため、話したこと自体を忘れてしまいます。これは、数分前の出来事も覚えていられない「短期記憶障害」の典型的な症状です。
- 否定的・無関心な言葉(「どうせ」「面倒」「何でもいい」):これは、認知症の前段階や初期に見られることがある「アパシー(意欲・自発性の低下)」という症状の可能性があります。脳の前頭葉の機能低下が関係していると言われています。
- 言い訳や取り繕い:失敗を指摘された時に、「いや、わざとだよ」「前からこうだった」などと、とっさに言い訳をすることがあります。これは、自分の能力の低下を無意識に感じており、プライドを守ろうとする心の働きです。
これらの口癖が見られたからといって、すぐに「認知症だ」と決めつけるのは禁物です。誰でも疲れていたり、ストレスが溜まっていたりすると、こうした話し方になることはあります。
大切なのは、こうした変化の背景にあるご本人の不安や戸惑いに思いを馳せることです。もし、これらの変化が頻繁に見られ、日常生活に支障が出始めているようであれば、一度、かかりつけ医や物忘れ外来などに相談してみることをお勧めします。
認知症に良い趣味はありますか?

認知症の進行を緩やかにしたり、予防したりするためには、日々の生活の中で脳を活性化させることが大切だと言われています。その有効な手段の一つが、本人が楽しみながら主体的に取り組める「趣味」を持つことです。
ただ、やみくもに何かを始めれば良いというわけではありません。特に、以下の要素をバランス良く含んだ活動が、脳にとって良い刺激になると考えられています。趣味と合わせて、記憶をサポートする便利なグッズを活用するのも良い方法です。
認知症ケアに役立つ趣味の要素と具体例
| 趣味の要素 | 具体例 | 脳への良い刺激と期待される効果 |
|---|---|---|
| 指先を細かく使う | 編み物、習字、ちぎり絵、楽器演奏、料理(野菜の皮むきなど) | 指先は「第二の脳」とも呼ばれ、指を動かすことで脳の広範囲が刺激されます。 |
| 頭で考える(思考・戦略) | 囲碁、将棋、麻雀、オセロ、簡単な計算ドリル、クロスワードパズル、読書して感想を話す | ルールを覚えたり、先を読んだりする作業が、思考力や記憶力を司る前頭葉を活性化させます。 |
| 他者と交流する | カラオケ、コーラス、老人クラブの集まり、ゲートボール、デイサービスのレクリエーション | 人と会話したり、笑ったりすることが最も高度な脳の活動です。社会的な孤立を防ぎ、精神的な安定にも繋がります。 |
| 体を動かす(有酸素運動) | 散歩(少し息が弾む程度)、ラジオ体操、簡単なダンス、ガーデニング | 脳の血流を促進し、神経細胞の栄養となります。特に、考えながら体を動かす「デュアルタスク」は効果的です。 |
ここでの最大のポイントは、決して無理強いしないことです。本人が「やらされている」と感じてしまうと、それは楽しい趣味ではなく、苦痛なトレーニングになってしまいます。
昔好きだったことや、得意だったことをヒントに、「お母さん、また編み物やってみない?」「お父さんの将棋、また見たいな」というように、本人の意欲を引き出すような声かけを工夫してみましょう。
そして、うまくできなくても決して責めず、小さな達成を一緒に喜ぶ姿勢が何よりも大切です。家族が一緒に楽しむことで、それは最高のコミュニケーションの時間になりますよ。
認知症介護者の悩みと解決法
認知症の方を在宅で介護するご家族は、本当に様々な悩みを抱えています。これらの悩みは一つひとつが重く、複雑に絡み合っているため、一人で抱え込んでしまうと、心身ともに追い詰められて「介護うつ」や「共倒れ」といった深刻な事態に陥りかねません。介護を長く続けていくためには、自分だけで頑張ろうとせず、外部の助けを上手に借りることが不可欠です。
介護者が抱える具体的な悩み
- 精神的な負担:「いつまで続くのか」という終わりが見えない不安。暴言や暴力、徘徊といった症状への対応による精神的ストレス。介護中心の生活による社会からの孤立感や、自分の人生を犠牲にしているという思い。
- 身体的な負担:食事、入浴、排泄、着替え、移乗といった介助による慢性的な腰痛や疲労。夜間の不眠や徘徊への対応による深刻な睡眠不足。
- 経済的な負担:介護保険サービスの自己負担分、医療費、おむつ代や介護用品費といった継続的な出費。介護のために仕事の時間を減らしたり、離職したりすることによる収入の減少。
- 情報・知識不足の悩み:どのような公的サービスが利用できるのかわからない。症状が悪化した時にどこに相談すればいいのかわからない。
悩みを解決するための第一歩
これらの多岐にわたる悩みを相談できる、地域の総合的な窓口が「地域包括支援センター」です。ここは、高齢者の介護、福祉、医療、健康など、様々な側面から暮らしを支えるために市区町村が設置している機関です。保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーといった専門職がチームを組んで、無料で相談に応じてくれます。
「何から相談していいかすら、わからない」という状態でも大丈夫です。「親の物忘れが心配で…」という一言からでも、専門家が親身に話を聞き、必要な情報提供やサービスへの橋渡しをしてくれます。まずはお住まいの地域のセンターに電話を一本入れてみることが、状況を打開する大きな一歩になります。
(参照:厚生労働省 介護事業所・生活関連情報検索)
その他にも、同じ境遇の介護者が集う「家族会」に参加して悩みを分かち合ったり、ショートステイ(短期入所生活介護)などを利用して、介護者自身が休息を取る時間(レスパイトケア)を意識的に確保したりすることも、燃え尽きを防ぐために非常に重要です。介護は短期決戦ではありません。様々な社会資源を上手に活用して、介護者自身の生活と心の健康も守っていきましょう。
認知症についてよくあるご質問FAQ

-
Q1. 認知症ブログは無料で読めますか?
-
A1. はい、ほとんどの個人ブログは無料で読むことができます。アメブロやブログ村などで公開されているブログは、登録なども不要で誰でも閲覧することが可能です。
-
Q2. 認知症の親のブログを家族が書くのは違法ですか?
-
A2. ご本人の尊厳を傷つけたり、個人が特定できる情報を無断で公開したりするとプライバシー侵害にあたる可能性があります。個人名や顔写真は伏せるなど、細心の注意を払う必要があります。
-
Q3. 介護の愚痴ばかりのブログを読むと、気が滅入りませんか?
-
A3. 人によってはネガティブな気持ちになる可能性もあります。しかし、「自分だけではない」という共感から、かえって気持ちが楽になる人も多いです。ご自身の精神状態に合わせて、読むブログを選ぶことが大切です。
-
Q4. 認知症の初期症状にはどんなものがありますか?
-
A4. 物忘れが目立つのが代表的ですが、他にも時間や場所の感覚が曖昧になる、段取りが立てられなくなる、好きだったことへの興味を失う、といった変化が見られることがあります。

介護は本当に様々な悩みが出てきますよね。特に経済的な負担は深刻です。介護費用を捻出するために、ご実家の売却を考える方もいらっしゃいます。
ただ、ご本人の意思確認が難しくなると手続きが複雑になることも。
介護が本格化する前に、一度ご家族で財産の状況や今後の希望について話し合っておくことを強くおすすめします。お困りの際は、当社の無料相談もご活用ください。
まとめ:認知症ブログを有効活用しよう
この記事では、様々な認知症ブログの種類から、介護に役立つ知識までを解説してきました。
最後に、今回の内容をリストで振り返ってみましょう。
- 認知症ブログは目的別に探すのが効率的
- ランキングは参考にしつつ自分に合うか見極める
- アメブロは他の介護者と繋がりやすいのが魅力
- アルツハイマー型など病名に特化したブログも参考になる
- リアルな体験談ブログは実践的なヒントの宝庫
- 一人暮らしや遠距離介護のブログは具体的な工夫が満載
- 介護ストレスを発信するブログは共感や心の支えになる
- 認知症で最も大変な時期は人それぞれ
- 一般的には行動・心理症状が出る中期が負担が大きい傾向
- 接し方の基本は「驚かせない」「急がせない」「自尊心を傷つけない」
- 「あれ」「それ」など指示語の多用は変化のサインかも
- 本人が楽しめる趣味は脳への良い刺激になる
- 指先や頭を使い、他者と交流できる活動がおすすめ
- 介護の悩みは一人で抱えず専門家に相談する
- 地域の相談窓口は「地域包括支援センター」
▼あわせて読みたい関連記事▼
親の介護ねぎらいの言葉例文15選|励ましではなく心に届く言葉とは

お気軽にご相談ください
相続は100人いれば、100通り
唯一無二の最適な相続をご提案いたします
CONTACT
専門家やえさん

- 専門家やえさん
-
堀川 八重(ほりかわ やえ)
大阪不動産・FPサービス株式会社 代表
15年以上にわたり1,500組を超えるご家族の相続や不動産のお悩みに、専門家として寄り添ってまいりました。私の信条は、法律や数字の話をする前に、まずお客様ご家族の歴史や言葉にならない想いを丁寧に「聞く」こと。信頼できる各分野の専門家チームと共に、皆様が心から安心できる最善の道筋をオーダーメイドでご提案します。一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。
最新の投稿
 お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説
お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説 相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説
相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説 お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例
お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例 お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説
お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説






