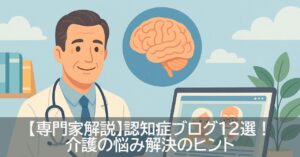相続の話になると「嫡出子」や「実子」といった言葉が出てきて、嫡出子と実子の違いがよくわからず悩んでいませんか?言葉は似ていますが、法律上の意味は少し異なり、この違いを理解しないと相続で思わぬトラブルに発展することもあるんです。
結論から言うと、嫡出子と実子の違いは、法律上の婚姻関係にある男女から生まれた子かどうかという点にあります。
ただし、相続実務では、実子なのに養子になるケースや、実子を養子縁組する場合、養子縁組で実子がいる場合の注意点、養子と実子の兄弟関係、さらには養子と実子の結婚と相続の問題など、複雑なケースがたくさんあります。
また、嫡出でない子のデメリットや、非嫡出子の養子縁組と実母の関係、相続における実子と養子の順位、孫養子と実子の扱いの違いなど、知っておくべき知識は多岐にわたります。
この記事では、「実子とは何か」という基本的な意味や、嫡出子と実子の読み方から、複雑な相続関係まで、終活・相続の専門家やえが、皆さんの疑問をスッキリ解決しますね!
この記事のポイント
- 嫡出子と実子の基本的な意味の違い
- 普通養子と特別養子の相続における違い
- 連れ子や非嫡出子がいる場合の相続ポイント
- 相続トラブルを避けるための具体的な対策

こんにちは!終活・相続の専門家やえです。
相続って、家族の形が多様化している現代だからこそ、基本的な言葉の意味をしっかり押さえておくことが大切なんですよ。
特に「嫡出子」と「実子」の違いは、相続の第一歩。ここを曖昧にしていると、後々「え、そんなはずじゃ…」なんてことになりかねません。
私の経験上、円満な相続の秘訣は、正しい知識と早めの準備に尽きます。一緒に一つずつ確認していきましょうね!
目次
嫡出子実子違いとは?基本的な関係を解説

実子とはどういう意味?
まずは基本中の基本、「実子(じっし)」という言葉の意味から、もう少し深く掘り下げてみましょう。実子とは、生物学的な血のつながりがある子どものことを指します。法律の世界では「自然血族」なんて呼ばれたりもしますね。親子関係の最も基本的な形と言えます。
そして、この実子は、ご両親が法律上の夫婦であるか否かによって、次の2種類に区別されるのが重要なポイントです。
- 嫡出子(ちゃくしゅつし):法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子。
- 非嫡出子(ひちゃくしゅつし):法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子。
なぜこの区別が大切かというと、特にお父さんとの親子関係を法律的に証明する方法や、それに伴う相続権の有無に直接関わってくるからです。
「血がつながっていればそれでOK」というわけではなく、法律上の手続きが求められるケースがある、ということをまずは押さえておきましょう。
ポイントの整理
「実子」という大きな枠組みの中に、「嫡出子」と「非嫡出子」という2つのカテゴリーが存在するイメージです。相続を考える上では、単に実子であるかだけでなく、嫡出子・非嫡出子のどちらにあたるのかが、最初のステップになります。
「実子」の正しい読み方
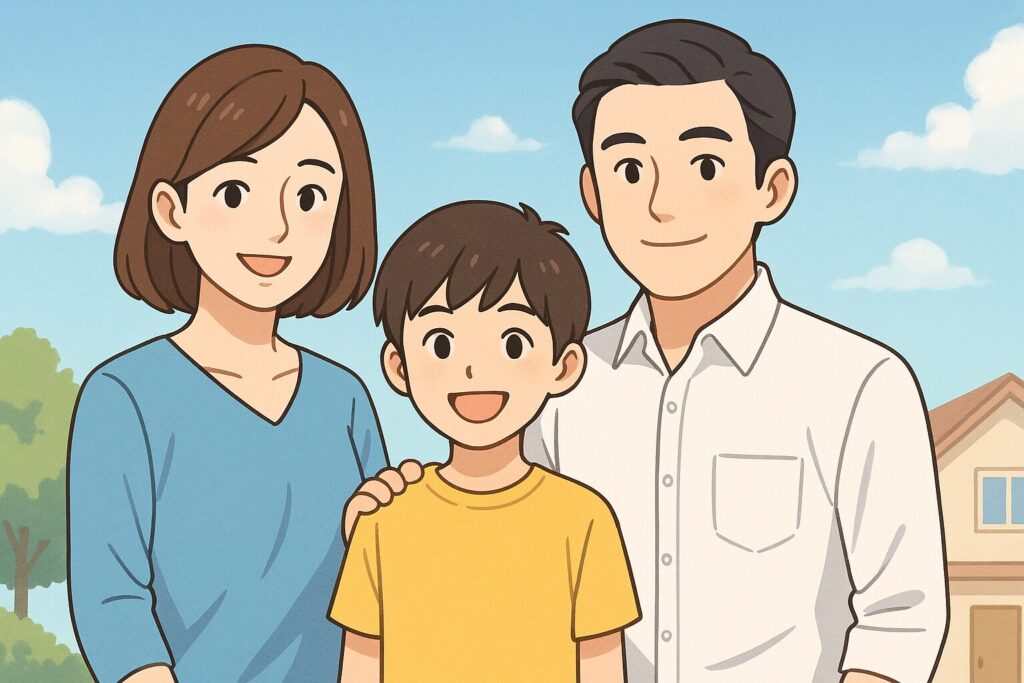
こちらはシンプルですが、大切なことなのでもう一度。「実子」は「じっし」と読みます。「じつこ」と読んでしまう方もたまにいらっしゃいますが、公的な手続きや専門家との話し合いの場では「じっし」と正しく使うのが一般的です。
言葉を正しく使うことは、スムーズなコミュニケーションの第一歩。ちょっとしたことですが、覚えておくと安心ですよ。
「嫡出子」の正しい読み方
こちらも少し馴染みのない漢字かもしれませんが、「嫡出子」は「ちゃくしゅつし」と読みます。「嫡」という字には「正統な」「本筋の」といった意味があり、法律上の正式な夫婦の間に生まれた子、という意味合いが込められています。
日本の民法では、子の身分関係を早期に安定させるため、「嫡出推定」という非常に重要なルールを設けています。
これは、妻が婚姻中に妊娠した子どもは、夫の子どもであると法律上推定する制度です。具体的には、次の条件を満たす子どもが嫡出子として扱われます。
- 婚姻の成立から200日を経過した後に生まれた子
- 婚姻の解消(離婚など)の日から300日以内に生まれた子
このルールがあるおかげで、ほとんどの子どもは出生届を提出するだけで、自動的に父親の戸籍に入り、法律上の親子関係が確定します。
嫡出でない子にあるデメリット
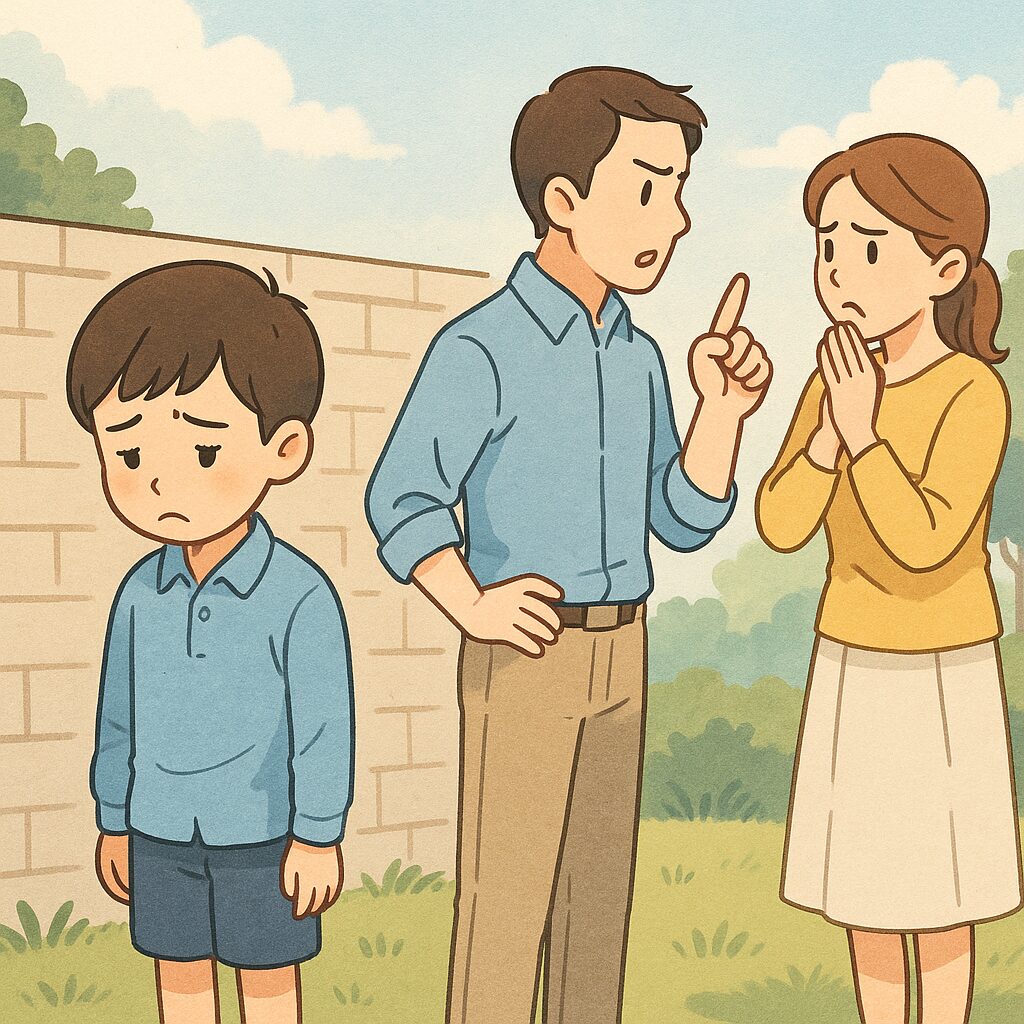
では、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた「非嫡出子(嫡出でない子)」には、どのような法的なデメリットがあるのでしょうか。愛情の深さとは関係なく、法律の世界では無視できない違いが存在します。
最大の違いは、父親との法律上の親子関係が自動的には発生しない点です。母親は出産の事実があるため、分娩の事実によって親子関係が明らかになりますが、父親の場合はそうはいきません。
父親が「この子は私の子です」と法的に認める「認知」という手続きをしなければ、法律上の親子にはなれないのです。
もし認知がされないままだと、以下のようなデメリットが生じます。
- 父親の財産に対する相続権がない
- 父親に対して扶養を請求する権利がない
- 父親の戸籍に入ることができない
- 父親が親権者になることができない
最も重要な注意点
愛情を持って育てていても、父親が法的な「認知」の手続きをしていなければ、その子は父親の相続人にはなれません。遺産分割協議に参加することすらできないのです。この点は、後々のトラブルを防ぐために絶対に押さえておく必要があります。
なお、以前は非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1とされていましたが、平成25年9月4日の最高裁判所の違憲決定を受け、民法が改正されました。
現在では、認知さえされていれば、嫡出子と非嫡出子の相続分は完全に平等になっています。時代の変化とともに、法律も家族の多様なあり方に合わせて変わってきているのですね。
日本の新生児の約43人に1人は「嫡出でない子」
近年、家族の形は多様化しており、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれる子どもの割合は増加傾向にあります。
厚生労働省の「令和4年(2022)人口動態統計」によると、総出生数770,747人のうち、嫡出でない子は2.4%にあたる18,483人でした。
この割合は昭和55年(1980年)には0.8%であり、時代の変化とともに非嫡出子をめぐる相続の問題が、より身近になっていることを示唆しています。
養子と実子の兄弟関係について
次に、血縁関係はないけれど家族の一員となる「養子」について見ていきましょう。養子縁組届が市区町村役場で受理されたその日から、養子は養親の「嫡出子」としての身分を取得します。
これは、単に「子として扱う」というレベルの話ではありません。法律上、完全に実子と同じ権利と義務を持つ親子関係が生まれるということです。
そのため、養親に実子がいる場合、その実子と養子は法律上「兄弟姉妹」となります。戸籍にも、養子は「長男」「二女」のように実子と同じ続柄で記載されます(ただし、養子である旨も併記されます)。
親子間の扶養義務や、親が亡くなった際の相続権など、あらゆる面で実子と養子の間に法的な区別は一切ありません。法律は、血のつながりだけでなく、社会的な家族関係も尊重していると言えますね。
相続における実子と養子の順位
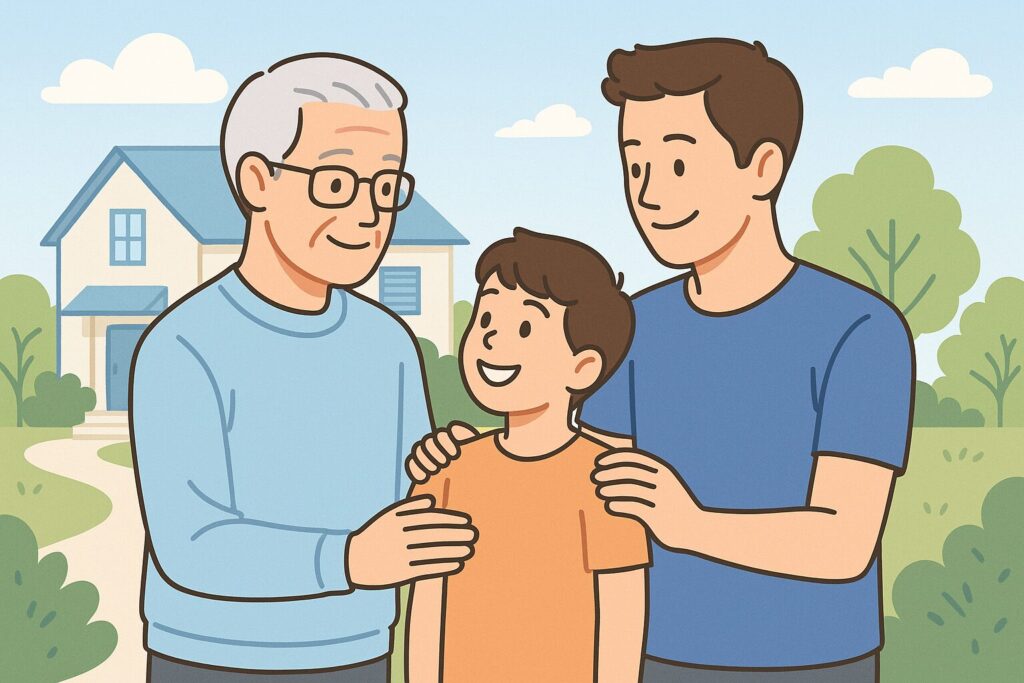
相続の場面における実子と養子の扱いは、非常に明確です。相続権の順位、そして法定相続分の割合において、実子と養子の間に一切の違いはありません。
民法で定められている相続順位では、亡くなった方(被相続人)の子どもは常に「第1順位」の相続人となります。そして、養子縁組をした子は、法律上「嫡出子」として扱われるため、当然この第1順位に含まれます。
例えば、遺産が6,000万円あり、相続人が配偶者と実子2人、養子1人の合計4人だった場合の法定相続分を計算してみましょう。
| 相続人 | 法定相続分(割合) | 具体的な相続額 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 1/2 | 3,000万円 |
| 子ども全体 | 1/2 | 3,000万円 |
| 実子A | 1/2 × 1/3 = 1/6 | 1,000万円 |
| 実子B | 1/2 × 1/3 = 1/6 | 1,000万円 |
| 養子C | 1/2 × 1/3 = 1/6 | 1,000万円 |
このように、子ども3人(実子2人+養子1人)で残りの2分の1を均等に分けるため、一人当たりの相続分は同じ1,000万円となります。「養子だから取り分が少ない」ということは絶対にありませんので、ご安心ください。

終活・相続・不動産相続の専門家 やえさん
ここまで基本的な言葉の意味を見てきましたが、いかがでしたか?「なんだかややこしい…」と感じたかもしれませんね。
でも大丈夫!私の経験から言えるのは、一つひとつの言葉の意味を正確に知ることが、後々の大きな安心につながるということです。
特に再婚されたご家庭や、ご家族の形が少し複雑な場合は、こうした知識がご家族を守る「お守り」になります。焦らず、ゆっくり理解を深めていきましょうね。
相続における嫡出子実子違いと注意点

実子がいる場合の養子縁組
実子がいるご家庭が、新たに養子縁組を行うことには、様々な背景が考えられます。最も一般的なのは、やはり再婚家庭における「連れ子養子」でしょう。
再婚相手の子どもを、法的な親子関係を結ぶことで名実ともに自分の子として迎え入れ、相続権をはじめとする様々な権利を保障するために行われます。愛情という気持ちの面だけでなく、法律面でも家族としての基盤を固める、とても大切な手続きです。
もう一つよくあるのが、相続税対策を目的とした「孫養子」です。後ほど詳しく触れますが、法定相続人の数を増やすことで、相続税の基礎控除額を増やそうという考え方ですね。
ただし、これには税法上の制限があるため注意が必要です。
他にも、子どもに恵まれなかった兄弟姉妹に自分の子どもを養子に出したり、家業や伝統芸能などを継承させるために、最も適した親族を養子に迎えたりするケースもあります。
養子縁組は、単なる相続対策にとどまらない、家族の形を未来へつなぐための多様な役割を担っているのです。
なぜ実子を養子縁組するのか
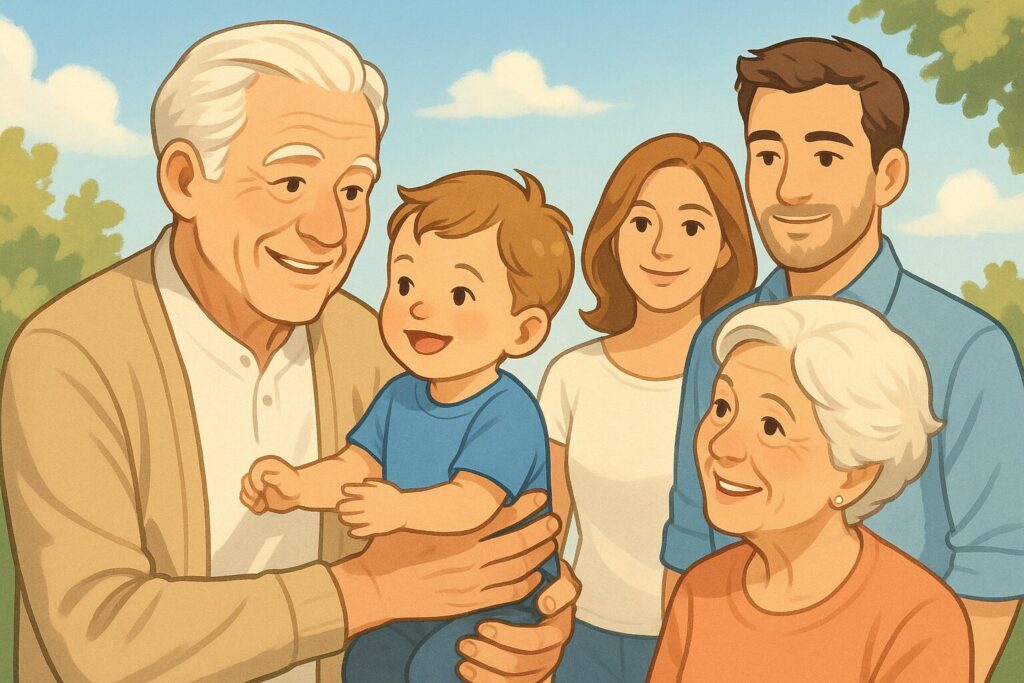
「血のつながった我が子を、わざわざ養子にするなんてことがあるの?」と、不思議に思われるかもしれませんね。これは確かに非常に稀なケースですが、法的には可能ですし、特定の目的のために行われることがあります。
例えば、旧来の「家」制度の考え方が色濃く残る旧家などで、本家の跡取りである長男夫婦に生まれた子(孫)を、跡継ぎのいない分家の次男夫婦の養子にする、といった事例が考えられます。
これは、分家の家系が途絶えるのを防ぎ、一族全体の安泰を図るという目的で行われるものです。
知っておきたい豆知識
このように、祖父母が孫を養子にする(孫養子)のではなく、おじ・おばが甥・姪を養子にするケースもあります。いずれの場合も、相続関係が複雑になるため、養子縁組をする際には、他の親族への十分な説明と理解を得ることが、後のトラブルを避けるために不可欠です。
ただし、このような縁組は、子どもの福祉の観点から慎重に判断されるべきですし、単に相続税を免れる目的など、不当な意図が明らかな場合は、縁組が無効と判断される可能性もゼロではありません。
実子なのに養子になるケースとは
「実子なのに養子」という言葉を聞くと少し混乱するかもしれませんが、これは「ある人にとっては実子であり、同時に、別の人にとっては養子である」という状況を指します。この最も典型的な例が、離婚した親の連れ子が、親の再婚相手と養子縁組をするケースです。
例を挙げてみましょう。
- Aさん(母)と前夫との間に、B子さん(子)がいます。B子さんはAさんの実子です。
- AさんがCさん(男性)と再婚しました。
- CさんがB子さんと養子縁組をしました。これにより、B子さんはCさんの養子となります。
この結果、B子さんは「母Aさんの実子」であり、かつ「養父Cさんの養子」という二つの身分を併せ持つことになります。
この状態の大きな特徴は、B子さんが二重の相続権を持つ点です。つまり、実母であるAさんが亡くなった際の相続権と、養父であるCさんが亡くなった際の相続権の、両方を取得することになるのです。
家族の形が変わっても、子どもの権利が守られるような仕組みになっているのですね。
孫養子と実子との扱いの違い
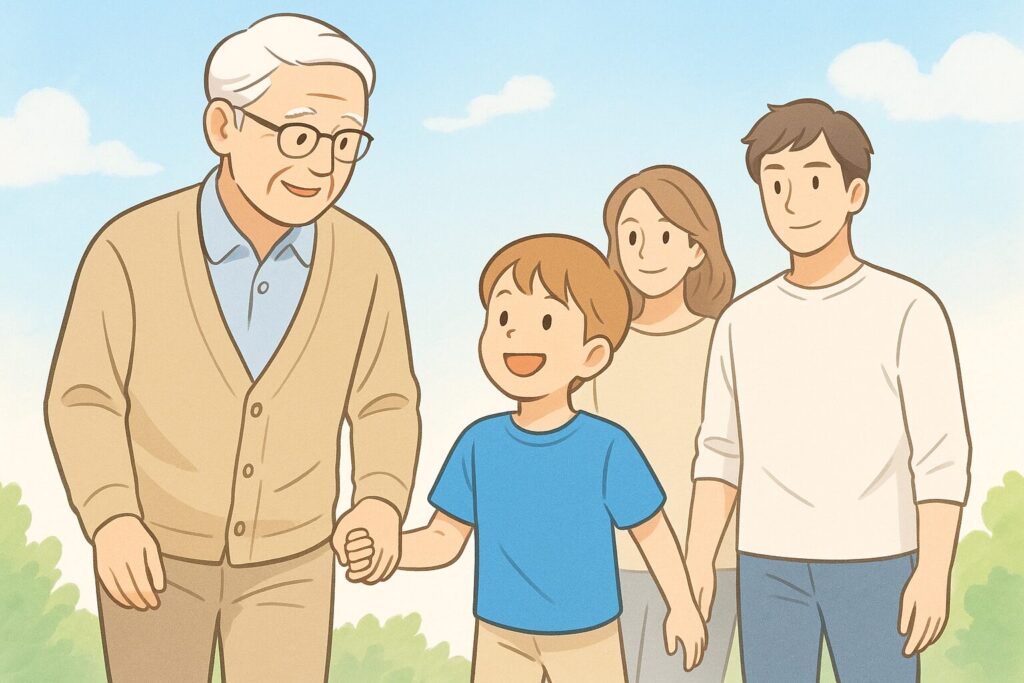
相続税対策として注目される「孫養子」。お孫さんを養子にすると、法定相続人が一人増えるため、相続税の基礎控除額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の計算式に基づき、600万円増えるというメリットがあります。
また、本来なら子ども→孫へと二世代にわたってかかるはずの相続税を、一回分スキップできる効果も期待できます。
しかし、民法上は問題なくとも、税法上ではいくつか重要な注意点があります。
孫養子に関する税法上の重要ルール
- 法定相続人に含められる養子の数に制限がある
相続税の基礎控除の計算上、法定相続人の数に含められる養子の数は、被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までと定められています。(出典:国税庁 No.4170 相続人の中に養子がいるとき) - 相続税が2割加算される
被相続人の配偶者、一親等の血族(子や親)以外が財産を相続する場合、相続税額が2割増しになるルールがあります。お孫さんは二親等の血族なので、たとえ養子になっていても、この2割加算の対象となります。
節税メリットばかりに目を向けていると、思わぬデメリットに気づかないこともあります。
特に、他の相続人(実子たち)からすれば、自分の子ども(被相続人の孫)だけが優遇されているように感じ、感情的なしこりを残す原因にもなりかねません。
孫養子を検討する際は、税理士などの専門家を交え、家族全員でよく話し合うことが極めて重要です。
非嫡出子の養子縁組と実母の関係
婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子)が、誰かの養子になった場合、産みの母親(実母)との法律上の親子関係はどうなるのでしょうか。
これは、養子縁組の種類によって結論が大きく異なります。
| 縁組の種類 | 実親との関係 | 主な目的・特徴 |
|---|---|---|
| 普通養子縁組 | 関係は存続する | 家系の維持や相続対策など、様々な目的で利用されます。養親との法的な親子関係が生まれますが、実親との親子関係もそのまま残ります。そのため、養親と実親の両方に対して相続権を持ちます。 |
| 特別養子縁組 | 関係は終了する | 実親による養育が困難な子どもの福祉を最優先する制度です。家庭裁判所の厳しい審判を経て成立し、実親およびその血族との法的な関係は完全に断ち切られます。そのため、実親の相続人にはなりません。 |
一般的な養子縁組はほとんどが「普通養子縁組」です。そのため、たとえ子どもが養子に出たとしても、実の母親との法的な親子関係がなくなることはありません。
一方、「特別養子縁組」は、子どものための特別な制度であり、利用できるケースも限定されています。この制度についてさらに詳しく知りたい方は、法務省のウェブサイトも参考にされると良いでしょう。
年間約700組の「特別養子縁組」が成立
記事で触れられている「特別養子縁組」は、実親による養育が困難な子どもの福祉を目的とした重要な制度です。
厚生労働省の発表によると、令和3年度に家庭裁判所で成立した特別養子縁組の件数は701件にのぼります。
これは、実の親との法的な関係を解消し、養親との間に安定した親子関係を築くことで、子どもの健全な成長を図るためのもので、一般的な相続目的の養子縁組とは根本的に趣旨が異なります。
養子と実子の結婚と相続の問題
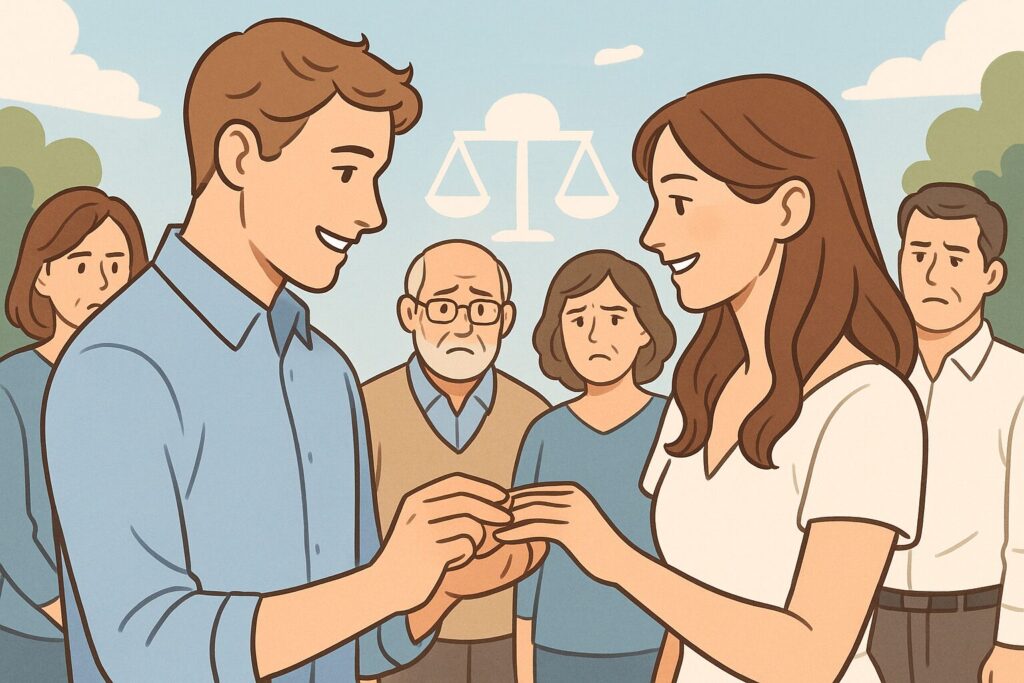
「養子と実子は法律上、兄弟姉妹になるのに、結婚できるの?」という点は、多くの方が疑問に思うポイントかもしれませんね。結論から言うと、血縁関係がなければ、養子と実子の結婚は法律上可能です。
日本の民法では、結婚できない相手として「近親婚の制限」を定めています。具体的には、①直系血族(親子、祖父母と孫など)、②三親等内の傍系血族(兄弟姉妹、おじ・おばと甥・姪など)との結婚を禁止しています。
しかし、この規定はあくまで血のつながりがある「血族」を対象としています。
養子縁組によって養子と実子は「法定血族」という法律上の親族にはなりますが、生物学的な血のつながりはありません。そのため、近親婚の制限には抵触せず、結婚が認められているのです。
ただし、注意点も…
法律上は可能であっても、一つ屋根の下で兄弟として育った二人が結婚することに対しては、社会通念上や倫理的な観点から様々な意見があります。また、結婚後の相続関係は非常に複雑になります。
例えば、夫(元養子)が亡くなった場合、妻(元実子)は配偶者として相続します。その後、妻の親(夫の元養親)が亡くなった場合、妻は実子として相続しますが、すでに亡くなっている夫の代襲相続は発生しません。このように、通常の相続とは異なる関係性が生まれるため、慎重な検討が必要です。
嫡出子と実子についてよくあるご質問FAQ
-
Q1. 嫡出子と実子の違いを簡単に教えてください。
-
A1. 実子は血のつながりのある子のことで、嫡出子は婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子のことです。嫡出子も非嫡出子も、どちらも実子に含まれますよ。
-
Q2. 非嫡出子でも父親の財産を相続できますか?
-
A2. 父親が子どもを「認知」していれば、非嫡出子でも嫡出子と同じ割合で相続できます。認知という法律上の手続きがされているかどうかがポイントになります。
-
Q3. 再婚相手の連れ子に財産を相続させるにはどうすればいいですか?
-
A3. 最も確実な方法は、連れ子と「養子縁組」をすることです。養子縁組をすれば法律上の親子となり、実子と同じように相続権が発生します。
-
Q4. 養子は何人いても相続税の計算上、相続人として認められますか?
-
A4. いいえ、相続税の計算に含められる養子の数には制限があります。実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までと法律で定められています。
まとめ:嫡出子実子違いを理解し相続に備えよう


ここまで本当にお疲れ様でした!たくさんの言葉が出てきて、頭がパンクしそうかもしれませんね(笑)
でも、嫡出子と実子の違いをしっかり理解できたあなたは、もう相続の初心者ではありません。この知識は、あなたとあなたの大切なご家族を、未来のトラブルから守るための大切な「武器」になります。
もし分からないことがあれば、いつでも専門家を頼ってくださいね。一人で抱え込まないことが、円満相続への一番の近道ですよ。
- 実子とは血縁関係のある子どものこと
- 実子は「じっし」と読む
- 嫡出子とは法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子
- 嫡出子は「ちゃくしゅつし」と読む
- 非嫡出子は父親の認知がないと相続権がない
- 法改正により嫡出子と非嫡出子の相続分は同等になった
- 養子と実子の兄弟関係は法律上平等である
- 相続順位や法定相続分も養子と実子で違いはない
- 再婚相手の連れ子と養子縁組をすることがある
- 孫を養子にすると相続税の基礎控除額が増える場合がある
- 税法上、相続人に含められる養子の数には制限がある
- 普通養子縁組では実母との親子関係は消滅しない
- 特別養子縁組では実親との法的な関係は終了する
- 養子と実子は血縁がなければ法律上結婚できる
- 嫡出子と実子の違いを正しく理解することが円満相続の鍵
▼あわせて読みたい関連記事▼
【相続税いくらから親子でかかる?】専門家が相続税の早見表や基礎控除・計算方法をわかりやすく解説

お気軽にご相談ください
相続は100人いれば、100通り
唯一無二の最適な相続をご提案いたします
CONTACT
専門家やえさん

- 専門家やえさん
-
堀川 八重(ほりかわ やえ)
大阪不動産・FPサービス株式会社 代表
15年以上にわたり1,500組を超えるご家族の相続や不動産のお悩みに、専門家として寄り添ってまいりました。私の信条は、法律や数字の話をする前に、まずお客様ご家族の歴史や言葉にならない想いを丁寧に「聞く」こと。信頼できる各分野の専門家チームと共に、皆様が心から安心できる最善の道筋をオーダーメイドでご提案します。一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。
最新の投稿
 お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説
お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説 相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説
相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説 お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例
お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例 お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説
お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説