「永代供養簿」について、何から調べたらいいか迷っているあなたへ、永代供養とはどんなものなのか、そして永代供養墓と納骨堂の違いなど、分かりやすくお話ししていきたいと思います。
実は、私自身も両親と一緒にお墓の終活を始めたばかりで、永代供養 墓じまい 費用のことや、永代供養墓 デメリットといった、ちょっと聞きにくいこともたくさん調べているんです。 特に永代供養墓 大阪で探している方も多いと聞きますが、正直、どれが良いのか迷ってしまいますよね。
この記事では、永代供養墓 後悔しないためのポイントや、永代供養墓 種類、そして意外と知られていない永代供養墓 読み方まで、ひとつずつ丁寧に解説していきます。 「永代供養」は「えいだい」と読みますか?という疑問や、なぜ永代供養は良くないのですか?といった、ちょっとネガティブな質問にもしっかりお答えします。
「永代供養費用 誰が払うの?」や、「永代供養のお墓はどうなるの?」という、ちょっと現実的な問題についても、私の経験談を交えてお話ししますね。 「永代供養の一般的な金額はいくらですか?」とか、「お墓がいらない永代供養とは?」という、一番気になる部分も、具体的にご紹介していきますので、ぜひ最後まで読んでみてください。
この記事のポイント
- 永代供養墓の種類とそれぞれの費用相場
- 永代供養墓を選ぶメリットと知っておきたいデメリット
- お墓を永代供養墓に変更する際の具体的な手続きと費用
- 永代供養墓が向いている人とそうでない人の特徴
目次
永代供養墓の基本と種類別の費用を徹底解説

永代供養墓とは?一般的なお墓との違い
永代供養墓とは、お墓の管理や供養を、ご遺族に代わって寺院や霊園が行ってくれるお墓のことです。 古くからある一般的なお墓は、ご先祖様のお墓を家族や親戚が代々引き継ぎ、管理していくのが一般的でした。 しかし、少子高齢化や核家族化が進み、お墓の承継者がいない、あるいは「子供たちに負担をかけたくない」という理由から、この永代供養という方法を選ぶ方が増えています。
私自身も最近、母から「お墓の管理って、あなたに全部任せたら大変よね…」と相談されたことがきっかけで、この永代供養墓について真剣に調べ始めました。 古くからあるお墓の場合、毎年の管理費や、お盆やお彼岸の時期のお掃除など、意外と手間や費用がかかるものです。
特に実家から離れた場所に住んでいると、お墓参りに行くこと自体が大変ですよね。 永代供養墓であれば、一度永代供養料を支払ってしまえば、その後の管理や供養は霊園側にお任せできるので、そういった心配がなくなります。
ただ、永代供養と聞くと「永遠に供養してくれる」というイメージを持つ方も多いかもしれません。 しかし、実際は契約期間が定められていることがほとんどで、その期間を過ぎると、他の遺骨と一緒に合祀(ごうし)されることが一般的です。 この点も、事前にしっかりと確認しておくことが大切ですね。
【豆知識】「永代供養」と「永代使用」は別物!
この2つの言葉、読み方が似ているので混同されがちです。
永代供養:管理・供養をお任せすること
永代使用:お墓を建てる土地を永代にわたって使用する権利のこと
永代使用の場合、毎年の管理費は別途支払う必要があります。
永代供養墓の主な4つの種類とそれぞれの費用相場

- 合祀タイプの永代供養墓
- 樹木葬
- 納骨堂
- 個人墓・夫婦墓
合祀タイプの永代供養墓
こちらは、永代供養墓の中でも最も費用を抑えられるタイプです。 最初から他の方々の遺骨と一緒に、大きなお墓や供養塔に合祀する埋葬方法になります。 個別の区画がないため、費用は一般的に3万円〜10万円程度と、かなりリーズナブルです。
知人がこのタイプの永代供養墓を選んだのですが、ご家族からは「故人の遺骨が誰のものか分からなくなってしまうのは寂しい」という声も聞かれました。 合祀してしまうと、後から遺骨を取り出して別のお墓に移すことはできなくなります。 そのため、ご家族や親族にしっかり相談してから決めることが重要です。
樹木葬
樹木葬とは、墓石の代わりに樹木を墓標として遺骨を埋葬する、自然に還ることを目的としたお墓です。 こちらも永代供養を前提としていることがほとんどで、後継ぎがいなくても安心です。 費用は、合祀タイプが5万円~20万円、個別の区画が用意されているタイプだと20万円〜80万円ほどと、幅があります。
私自身も「自然に囲まれて眠りたい」という気持ちがあるので、樹木葬はとても魅力的です。 ただ、知人から聞いた失敗談なのですが、シンボルとなる木の種類や、周囲の景観が思ったものと違っていて少し後悔した、という話を聞いたことがあります。 樹木葬を選ぶ際は、必ず現地見学をして、ご自身の目で雰囲気を確かめることをおすすめします。
納骨堂
納骨堂は、遺骨を建物の中に安置するお墓です。 ロッカー式、仏壇式、自動搬送式など、様々なタイプがあります。 駅の近くにある施設も多く、天候を気にせずお参りできるのが大きなメリットです。 費用相場は、10万円〜200万円程度と、こちらもタイプによって大きく異なります。
私の友人のご家族は、おばあ様が足が不自由になったため、納骨堂を選びました。 駅から近くてエレベーターもあるので、とてもお参りしやすくなったと喜んでいました。 ちなみに、納骨堂も永代供養を付けているところが多く、契約期間が終わると合祀されるのが一般的です。
個人墓・夫婦墓
こちらは、墓石を建てて個別に納骨するタイプで、見た目は一般的なお墓と似ています。 しかし、永代供養が付いているので、お墓の管理は霊園や寺院が行ってくれます。 家族ではなく、自分一人だけで、あるいは夫婦だけで入りたいという方に人気です。
費用は墓石を建てるため、他の永代供養墓と比較すると高めです。 相場は70万円〜150万円程度で、墓石の大きさやデザインによって変わります。 このタイプも、契約期間が過ぎると、最終的には合祀されることがほとんどです。
永代供養墓を選ぶ際は、どんなタイプの供養方法が自分や家族の希望に合っているのかをじっくり話し合うことが大切ですね。
【注意点】永代供養墓の価格は誰の費用?
永代供養墓の費用は、基本的に1人あたりの料金で設定されていることが多いです。 夫婦で入りたい場合は、2人分の費用がかかることがほとんどですので、事前にしっかりと確認してください。
永代供養墓の費用について、公的なデータも確認しておくと良いですね。
参考情報サイト: 厚生労働省「生活衛生関係営業の景況及び問題点に関する調査報告」
URL: https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001319289.pdf
永代供養墓のメリットとデメリット、そして選び方
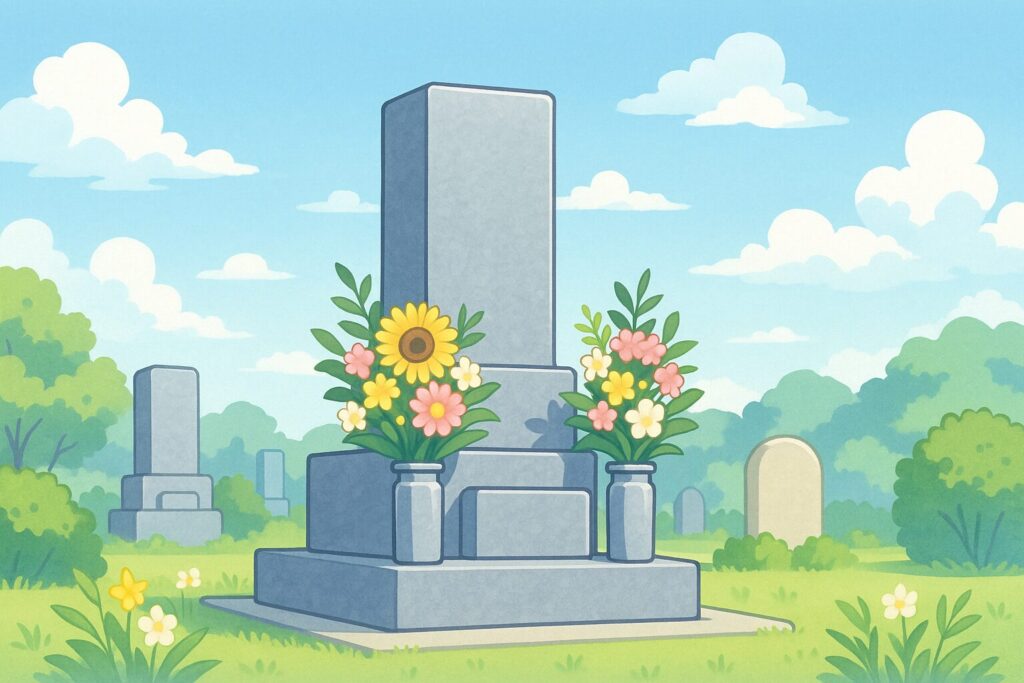
永代供養墓を選ぶメリット
永代供養墓には、家族やご自身にとってたくさんのメリットがあります。 主なメリットは、お墓の継承者が不要になること、費用を抑えられること、そして宗教や宗派を問わないことが多いことです。
まず、永代供養は後継者がいなくても、霊園や寺院が永代にわたって供養や管理をしてくれます。 そのため、「お墓をどうしよう…」という、家族や親戚に負担をかける心配がなくなります。 これは、現代のライフスタイルにとても合っていると言えるのではないでしょうか。
もちろん、費用面でも大きなメリットがあります。 一般的な墓石を建てるお墓だと、200万円前後かかることも珍しくありませんが、永代供養墓は10万円~100万円程度で済む場合が多いです。 これは、お墓の購入を考えている方にとっては、とても大きなポイントですよね。
さらに、多くの永代供養墓は、特定の宗教や宗派に縛られることがありません。 私のお友達も、ご家族がそれぞれ違う宗派だったので、どの寺院のお墓に入るかで悩んでいました。 しかし、永代供養墓を選んだことで、その問題が解決し、みんなが納得して供養できるようになったと話していました。
「でも、お墓参りってどうなるの?」
と、思う方もいるかもしれません。
もちろん、お参りはいつでもできます! 霊園によっては、合祀された後も共同の納骨塔などに手を合わせられる場所が用意されていることが多いですよ。
永代供養墓を選ぶ際の注意点やデメリット

永代供養墓には多くのメリットがありますが、事前に知っておくべきデメリットもいくつかあります。 主なデメリットは、一度合祀されると遺骨を取り出せないことと、ご家族や親戚の理解が得にくい場合があることです。
まず、永代供養墓は契約期間が過ぎると、他の方の遺骨と一緒に合祀されるのが一般的です。 私の知り合いも、お父様を合祀タイプの永代供養墓に納骨したのですが、後になって「やっぱり個別のお墓に入れてあげたかった」と後悔していました。 一度合祀されてしまうと、遺骨を識別して取り出すことはできなくなってしまいます。
次に、ご家族や親戚の理解です。 「お墓は代々受け継いでいくもの」という考えを大切にしている方もまだまだ多くいらっしゃいます。 永代供養という新しいスタイルに抵抗を感じる方もいらっしゃるかもしれません。 私の場合も、母に相談した時は、「ご先祖様に申し訳ない」と言われてしまいました。 こういった場合は、ご家族や親族と十分に話し合い、みんなが納得できる方法を見つけることが大切ですね。
他にも、永代供養墓の管理方法についてです。 寺院や霊園によって、どのくらいの頻度で合同供養祭が行われるか、お盆やお彼岸にどんなイベントがあるかなどが異なります。 契約する前に、管理体制をしっかり確認しておくことをおすすめします。
【注意】改葬を考えている人は要注意!
もし将来的に遺骨を別のお墓に移す「改葬」を考えているなら、合祀タイプの永代供養墓は避けた方が良いでしょう。 合祀された遺骨は、取り出すことができないからです。
永代供養墓が向いている人、向いていない人
永代供養墓を選ぶべきか迷っている方もいるかと思います。 そこで、どんな人が向いていて、どんな人には向いていないのか、具体的にまとめてみました。
向いている人
- お墓の後継者がいない人:お子様がいない、ご親戚付き合いがないなど、お墓を管理する方がいない場合に、永代供養墓は非常に適しています。
- 家族に負担をかけたくない人:お墓の管理や維持費の負担を、ご家族にかけたくないと考えている方にもおすすめです。
- 自分一人、あるいは夫婦だけで入りたい人:先祖代々のお墓に入るのではなく、自分らしい形で眠りたいと考えている方に選ばれています。
- 費用を抑えたい人:墓石を建てる一般的なお墓と比べて、費用をかなり抑えることができます。
向いていない人
- 家族や親戚の理解を得られない人:「お墓は先祖代々で守っていくもの」という考えが強いご家庭だと、永代供養に反対される可能性があります。
- 合祀に抵抗がある人:他の方の遺骨と一緒になることに抵抗がある方は、合祀されないタイプの永代供養墓や、他の納骨方法を検討することをおすすめします。
- 改葬を検討している人:将来的に遺骨を別のお墓に移す可能性がある方には、合祀タイプの永代供養墓は向きません。
今あるお墓から永代供養墓に変える手順と費用
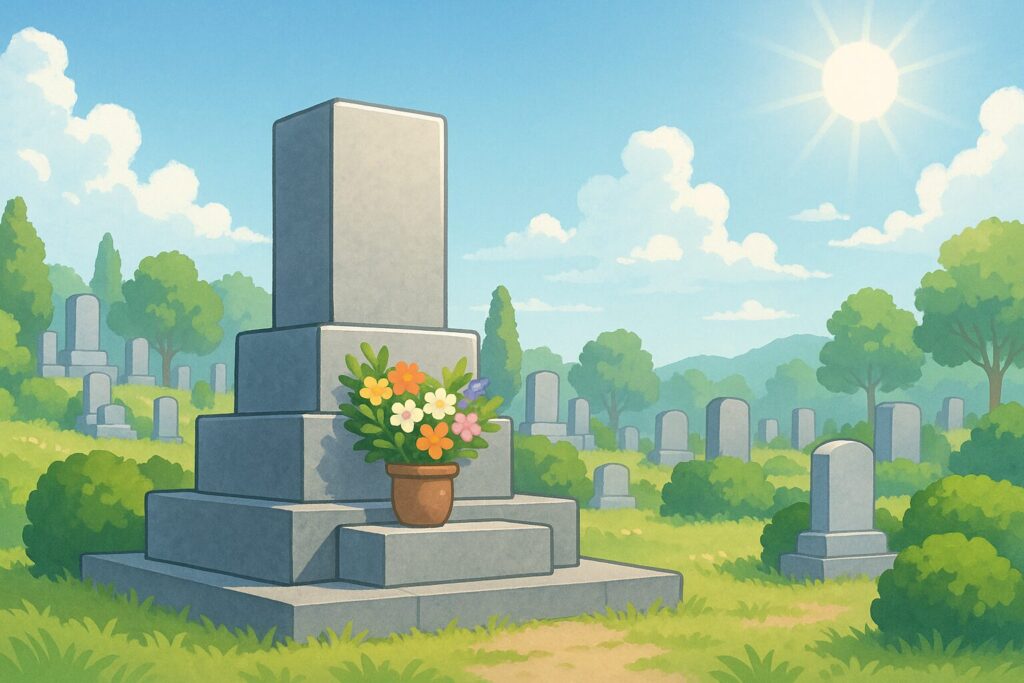
「今あるお墓が遠くてお参りに行けない」「後継者がいなくて困っている」という理由から、既存のお墓を永代供養墓に変更する「墓じまい」を検討している方も増えています。 私も、母の相談をきっかけに、この手続きについて詳しく調べてみました。
墓じまいの手続きは、少し複雑ですが、順を追って進めれば問題ありません。 まず、新しい納骨先の霊園や寺院と契約し、古いお墓の管理者に「埋葬証明書」を発行してもらいます。 次に、市区町村役場で「改葬許可申請書」に記入し、新しい霊園から受け入れ証明書をもらいます。 これら3つの書類を役場に提出して「改葬許可証」を発行してもらい、古いお墓の「魂抜き」(閉眼供養)をしてから、墓石を撤去します。 最後に、新しい永代供養墓に遺骨を納骨して、手続きは完了です。
この墓じまいにかかる費用は、主に「離檀料」「墓石の撤去費用」「永代供養墓に入るための費用」の3つに分けられます。 特に離檀料は、菩提寺との関係性によって金額が大きく変わることがあるので、事前に相談しておくと安心です。
| 項目 | 費用の目安 | 補足 |
|---|---|---|
| 離檀料 | お布施として10万円〜20万円程度 | 寺院に所属している場合のみ |
| 墓石の撤去費用 | 1㎡あたり10万円前後 | お墓の場所や大きさによる |
| 永代供養墓に入るための費用 | 3万円〜250万円程度 | 供養タイプや霊園による |
【ポイント】墓じまいの成功談
私が担当させていただいたお客様の中には、家族みんなで話し合い、古いお墓の管理が大変だったため、墓じまいを決断した方がいらっしゃいました。 新しい永代供養墓は、ご家族がいつでもお参りしやすいよう、アクセスが良い納骨堂を選びました。 手続きは少し大変でしたが、結果的に「これで子供たちに迷惑をかけずに済む」と、とても安心されていました。
永代供養墓まとめ
- 永代供養墓は、お墓の管理と供養を霊園や寺院に任せるお墓
- 永代供養墓には、合祀タイプ、樹木葬、納骨堂、個人墓の4種類がある
- 費用は合祀タイプが最も安く、個人墓が最も高くなる
- 永代供養墓は後継ぎ不要、費用を抑えられるなどのメリットがある
- デメリットは、一度合祀すると遺骨を取り出せないこと
- 家族や親戚の理解を得ることが重要
- 永代供養墓は「えいだい」と読むのが一般的
- お墓を永代供養墓に変更する際は、墓じまいの手続きと費用がかかる
- 永代供養墓は「永遠の供養」ではなく、期間が定められていることが多い
- 管理体制や合同供養の有無など、事前の確認が大切
- 生前契約が可能なので、ご自身で決めることができる
- 複数の遺骨をまとめて永代供養することも可能
- 「お墓がいらない」と考えている方にもおすすめ
- 納骨堂と永代供養墓は混同されがちだが、納骨堂はあくまで建物のこと
- 墓石がない供養方法を選ぶことで、費用を抑えられる
参考

お気軽にご相談ください
相続は100人いれば、100通り
唯一無二の最適な相続をご提案いたします
CONTACT
専門家やえさん

- 専門家やえさん
-
堀川 八重(ほりかわ やえ)
大阪不動産・FPサービス株式会社 代表
15年以上にわたり1,500組を超えるご家族の相続や不動産のお悩みに、専門家として寄り添ってまいりました。私の信条は、法律や数字の話をする前に、まずお客様ご家族の歴史や言葉にならない想いを丁寧に「聞く」こと。信頼できる各分野の専門家チームと共に、皆様が心から安心できる最善の道筋をオーダーメイドでご提案します。一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。
最新の投稿
 お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説
お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説 相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説
相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説 お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例
お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例 お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説
お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説






