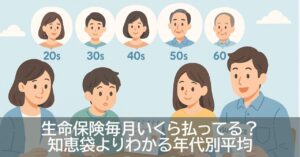「うちの親、何度話しても終活してくれないのよね…」「親の終活、考えただけでつらい…」そんなふうに、終活しない親との向き合い方で悩んでいませんか?大切な親のことだからこそ、将来を考えると不安になりますし、どう切り出せばいいか分からなくなってしまいますよね。
結論から言うと、親が終活しない理由の多くは、「死と向き合うのが怖い」「まだ元気だから必要ない」といった心理的なものなんです。だからこそ、頭ごなしに進めるのではなく、まずは親の気持ちを理解してあげることが、とっても大切なんですよ。
ただし、特に終活を始める方が多い80代になっても頑なに嫌いだと言ったり、終活の話題で怒るような場合は、将来ご家族が大変な思いをする可能性があるので注意が必要です。終活をしないとどうなるか、その先にあるリスクを少しだけ知っておくことも、親を守るための準備の一つかもしれません。
この記事では、終活しない親の心理から、危ない親の4タイプとは?といった具体的なケース、さらには20代やおひとりさまの終活事情、気軽に始められる終活ノートやエンディングノートの活用法、そして「終活は何歳までに終わらせるとされますか?」という疑問まで、皆さんの悩みに寄り添いながら、分かりやすく解説していきますね。
この記事のポイント
- 終活しない親の心理的な背景と理由がわかる
- 終活を放置した場合に家族が直面する具体的な問題点がわかる
- 親のタイプ別に効果的なアプローチ方法が見つかる
- エンディングノートなどを活用した具体的な始め方がわかる

こんにちは、終活・相続の専門家やえです!
「終活」って言葉だけ聞くと、なんだか重たいテーマに感じちゃいますよね。でも、実はこれって「死の準備」というよりは、「これからの人生をどう楽しく、安心して過ごすか」を考える、とっても前向きな活動なんです。
そして何より、残される家族への「最後で最高に優しいプレゼント」なんですよ。
この記事が、皆さんとご家族の未来を明るく照らす、小さなきっかけになれば嬉しいです。
終活しない親が抱える心理と放置するリスク

親が終活しない理由とは?
親がなかなか終活に乗り気になってくれないのには、実はいくつかの共通した理由があるんです。これを理解しないまま「なんでやってくれないの!」と責めてしまうと、余計に心を閉ざしてしまうかもしれません。
まずは「そっか、そういう気持ちなんだね」と、親の心に寄り添うところから始めてみましょう。ご両親の世代背景や性格を思い浮かべながら、どの理由が一番しっくりくるか考えてみてくださいね。
主な3つの理由
1. 死と向き合うのが怖い
これが一番大きな理由かもしれません。「終活」という言葉が、どうしても「死」を直接連想させてしまうため、「まだまだ元気でいたいのに、縁起でもない」「死の準備なんて考えたくない」と感じるのは、とても自然な感情です。
特に、戦後の日本を支え、高度経済成長期を働き抜いてきた世代の方々は、「弱音を吐かずに前向きに生きる」という価値観を強く持っていることが多く、自身の「終わり」について考えること自体に強い抵抗を感じることがあります。
話題にするだけでも、自分の人生が否定されるように感じてしまうのかもしれません。
2. 「まだ元気だから」必要ないと思っている
「足腰も達者だし、趣味も楽しんでいるし、まだまだ先のこと」と考えている親御さんは本当に多いです。実際に、さまざまな調査を見ると、終活に関心を持つ親世代は多い一方で、具体的な準備を始められている方はまだ少数派だという傾向が見られます。
この意識と行動のギャップは、「まだ大丈夫」「なんとかなる」という気持ちの表れなんですね。しかし、介護や相続の問題は、本当に突然、前触れもなくやってくるものなんです。元気な「今」だからこそ、落ち着いて話し合える最高のタイミングだということを、どう伝えられるかが鍵になります。
約7割が延命治療を望まない一方、意思表示しているのは約半数
内閣府の調査によると、60歳以上の男女のうち「自分の病気が治る見込みがなく死期が迫っていると告げられた場合、延命治療を「してほしくない」」と回答した人は68.8%にのぼります。
しかし、その意思を家族に伝えている人は55.9%、書面にしている人はさらに少ない5.9%に留まっています。この結果は、「心では決めているけれど、具体的な準備や共有はできていない」という、多くのご家庭が抱える意識と行動の大きなギャップを明確に示しています。
(出典:内閣府「平成29年度 高齢者の健康に関する調査結果」より算出)
3. 何をすればいいか分からず、面倒だと感じている
終活と聞くと、「遺言書作成」「相続税対策」「保険の見直し」「お墓の準備」など、何だか難しくて専門的な手続きがたくさんありそう…と感じていませんか?これは親御さん世代も同じです。
特に、パソコンやスマートフォンなどのデジタル機器に不慣れな世代にとっては、情報を調べること自体が一苦労。何から手をつけていいか分からず、その複雑さや手間の多さを想像しただけで思考が停止してしまい、結局「面倒だから後でいいや」と先延ばしになってしまうケースも少なくありません。
これらの理由を知ることで、親の言動の裏にある本音が見えてくるかもしれません。頭ごなしに否定せず、まずは共感から入るのが鉄則ですよ。
なぜ親は終活が嫌いなのか

「終活しない理由」と少し似ていますが、「終活が嫌い」とまで口にする背景には、もう少し根深い心理が隠れていることがあります。それは、「自分の人生を、自分の力で切り拓き、コントロールしてきた」という強い自負心やプライドです。
考えてみてください。親世代は、多くのことをご自身の判断で決断し、家族を守り、困難を乗り越えてきました。一家の大黒柱として、あるいは家庭を守る母として、その人生は決断の連続だったはずです。
そんな親御さんにとって、子どもから「終活」を提案されることは、まるで「もうあなたは自分のことも決められないでしょ?」と言われているように感じられ、自分の「弱さ」や「衰え」を認め、人生の主導権を子どもに明け渡す行為のように思えてしまうことがあるのです。
「まだお前に指図される歳じゃない」「自分のことは自分で決められる」といった反発の言葉は、実は「まだ頼られたい」「まだしっかりしている自分でいたいんだ」という心の叫びの裏返しなのかもしれません。
この繊細なプライドを傷つけずに、「親の人生の集大成を、最高の形で締めくくるお手伝いをしたい。だから、あなたの意思を尊重したいから、教えてほしい」というスタンスで接することが、何よりも大切になります。あくまで主役は親御さん自身だということを、言葉と態度で示してあげましょう。
終活の話で親が怒る心理
終活の話題を出した途端、それまで穏やかだった親が急に不機嫌になったり、時には声を荒げて怒り出したりすることもあります。子どもとしては、親を心配してのことなのに、そんな反応をされるとショックで、悲しい気持ちになりますよね。
なぜ親は怒ってしまうのでしょうか。その背景には、いくつかの心理的な地雷が隠れている可能性があります。
親が怒る心理的背景トップ3
1. 「財産目当て」だと勘違いされている
お金の話は、どんなに仲の良い家族間でも非常にデリケートな問題です。特に相続や財産の話を切り出すと、親の心には「もしかして、早く財産が欲しいのか?」「自分が汗水たらして築いたものを狙っているのか?」といった疑念が、悲しいことに生まれてしまうことがあります。
2. 「早く死んでほしい」という無言のメッセージに聞こえる
もちろん、子どもにそんなつもりは全くなくても、受け取る親の立場からすると、「自分の死後の話ばかりする」=「自分の死を望んでいる」かのような、非常にネガティブなメッセージとして受け取られてしまうことがあります。
「縁起でもないことを言うな!」という強い拒絶の言葉は、その代表的な反応であり、実は傷ついた心の現れでもあるのです。
3. 子どもに弱みを見せたくないという意地
前述の通り、親としてのプライドから、自分の判断力が鈍ったり、体の自由が利かなくなったりすることへの不安や恐れといった「弱み」を、最も身近な子どもにだけは見せたくないという強い気持ちがあります。
その「意地」が、照れ隠しや戸惑いを通り越して、「怒り」という分かりやすい形で表出してしまうことがあるのです。もし親が怒ってしまったら、まずは「売り言葉に買い言葉」で反論するのは絶対に避けましょう。
一度その場は「ごめん、そんなつもりじゃなかったんだ。ただ、お父さん(お母さん)の希望を大事にしたいだけだから、また今度聞かせてね」と、冷静に、そして優しく引くのが賢明です。
そして日を改めて、天気の良い日のお茶の時間など、リラックスした雰囲気の中で、雑談の中から少しずつ話してみるのが良いでしょうね。
終活をしないとどうなる?起こりうる問題

では、もし親が終活をしないまま、病気で倒れたり、万が一のことが起きてしまったら、残された家族には具体的にどのような負担がかかるのでしょうか。
これは決して脅しではなく、実際に私が相談を受けてきた多くのご家庭で起こっている、避けて通れない現実です。具体的な問題を知っておくことで、親に終活の必要性を伝える際の言葉にも重みと説得力が出てきます。
1. 葬儀やお墓のことで大慌て、後悔が残ることも
亡くなった直後、家族は深い悲しみに暮れる暇もなく、矢継ぎ早に決断を迫られます。病院からはすぐに退院を促され、葬儀社を決め、親戚や関係者への連絡に追われます。
「お父さんは、どんなお葬式を望んでいたんだろう?」「誰に声をかければ喜ぶかな?」と、故人の希望が何も分からないまま、限られた時間の中で多くのことを決定しなければなりません。
結果的に、「もっとこうしてあげればよかった」という後悔が、後々まで家族の心に残ってしまうことも少なくありません。
2. 相続で家族が揉める悲しい「争続」へ…
「うちは財産なんてないから大丈夫」と笑っていたご家庭ほど、相続トラブルは起こりやすいものです。預貯金や不動産、有価証券など、財産の全体像が分からないと、そもそも遺産分割の話し合いを始めることすらできません。
また、親の意思が不明確なために、わずかな財産や思い出の品をめぐって、それまで仲の良かった兄弟姉妹の関係に深い亀裂が入ってしまうケースは、本当に悲しいですが、決して少なくないのです。
実際に、裁判所が公表する司法統計によると、家庭裁判所での遺産分割事件の件数は、長期的に見て高い水準で推移しています。
相続トラブルの約75%は遺産5,000万円以下の家庭で発生
「うちは資産家じゃないから大丈夫」と思っていませんか?しかし、裁判所の司法統計によると、家庭裁判所で扱われる遺産分割事件のうち、遺産の価額が「5,000万円以下」のケースが全体の約75%を占めています。このデータは、相続トラブルが一部の富裕層だけの問題ではなく、ごく一般的な家庭でこそ起こりやすいという厳しい現実を物語っています。
(出典:裁判所 司法統計年報。各年度の「家事編」第75表「遺産分割事件のうち認容・調停成立件数-遺産価額別」より算出)
3. あらゆる手続きが煩雑化し、ストップする
人が亡くなると、想像以上に多くの手続きが発生します。銀行口座の凍結解除、生命保険金の請求、クレジットカードや公共料金の解約、スマートフォンの契約、SNSアカウントの閉鎖など、その数は数十種類に及ぶことも。
通帳や印鑑、各種契約書類がどこにあるのか、ネットバンクやサービスのID・パスワードが分からないと、一つ一つの手続きが非常に煩雑になり、家族に大きな時間的・精神的負担を強いることになります。
4. かけがえのないデジタル遺品や思い出が永遠に失われる
今や、パソコンやスマートフォンの中には、家族で撮影したたくさんの写真や動画、大切なメールのやり取りなど、お金には代えられない思い出がたくさん詰まっています。
しかし、持ち主以外はパスワードが分からず、これらの貴重なデータに二度とアクセスできなくなってしまう「デジタル遺品」の問題が深刻化しています。また、親が大切にしていた趣味のコレクションや骨董品なども、その価値が家族に分からずに、二束三文で処分されてしまうかもしれません。
要注意!危ない親の4タイプとは?
ひとくちに「終活しない親」と言っても、その性格や考え方は本当に様々ですよね。そこで、ちょっとユーモアを交えつつ、特に注意が必要かもしれない親御さんのタイプを4つに分類してみました。
皆さんの親御さんは、どのタイプに一番近いでしょうか?複数のタイプが混じっていることもありますから、人物像を思い浮かべながらチェックしてみてください。タイプを知ることで、効果的なアプローチのヒントが見つかるはずです。
| タイプ名 | 特徴 | 対処法のヒント |
|---|---|---|
| ①「まだ大丈夫」楽観主義タイプ | 「自分はまだまだ元気!」「大きな病気なんてしたことない」が口癖。終活の必要性を全く感じておらず、どこか他人事のように捉えている節がある。健康への自信が、未来への備えを遠ざけている。 | 正面から「もしもの話」をすると反発される可能性が。「最近テレビで見たんだけど…」と前置きし、第三者(親戚や有名人など)の事例を話して、「うちも他人事じゃないかもね」と客観的な事実から気づきを促すのが効果的です。 |
| ②「お前に指図されるな」頑固一徹タイプ | プライドが高く、子どもからの提案を「指図された」と捉えがちで、素直に聞けない。昔ながらの価値観が強く、「家長は自分だ」という意識が人一倍強い傾向がある。 | 説得しようとすると、かえって意固地になります。「お父さんの知恵を貸してほしいんだけど…」「お母さんの経験を教えて」と、相談を持ちかける形で、あくまで親を立てながら話を進めるのが最大のポイントです。 |
| ③「はいはい、また今度ね」話題そらしタイプ | 終活の話をすると、聞こえないふりをしたり、全く別の話題にすり替えたりする。真剣に向き合うことから、巧みに逃げようとする。根は優しいが、決断が苦手な場合も。 | 一度に全部話そうとせず、「今日はこれだけ教えてほしいな」と質問を一つに絞ってみましょう。「銀行の通帳、どこにまとめてる?」など、具体的な質問から入る。エンディングノートの項目を一つ埋めるなど、小さなゴールを設定するのがおすすめです。 |
| ④「全部お前に任せる」丸投げタイプ | 一見、協力的かと思いきや、「面倒だから全部やっておいて」「お前の好きにしていいよ」と無関心な態度を示す。「何でもいいよ」と言われるのが、残される側にとっては実は一番困りますよね。 | 「任せてくれるのは嬉しいけど、お母さんの希望通りにしてあげたいから、一緒に考えてほしいな」と伝え、選択肢を2~3個提示して「AとBならどっちがいい?」と選んでもらう形式にすると、少しずつ主体的に考えてもらいやすくなります。 |
もちろん、これはあくまでもコミュニケーションを円滑にするためのヒントの一つです。大切なのは、自分の親がどのタイプに近いかを理解し、その性格や価値観を尊重しながら、根気強く、そして愛情を持ってアプローチを試してみることですね。
親の終活がつらいと感じる子供の気持ち

親に終活を勧め、将来について話し合うことは、時として精神的に大きな負担を伴います。「親の終活を考えるのがつらい」「話をするのがしんどい」と感じてしまうのは、あなたが冷たいからでも、親不孝だからでもありません。
むしろ、親を大切に思う気持ちが強いからこそ、そのように感じてしまうのです。
親が老いていく姿を目の当たりにし、その「死」を具体的に想像することは、誰にとっても辛く、悲しいことです。それに加え、こちらの想いが伝わらないもどかしさ、話を聞いてもらえない焦り、そして刻一刻と過ぎていく時間への不安、さらには兄弟姉妹との終活に対する温度差など、様々な感情が入り混じり、心が疲れてしまうのは当然のことと言えるでしょう。
「つらい」と感じたら…
何よりも大切なのは、その辛い気持ちを一人で抱え込まないことです。
- 兄弟姉妹と気持ちを共有する:もし兄弟姉妹がいるなら、「最近、親のことでこんな風に感じていて…」と、まずは自分の気持ちを正直に話してみましょう。「今度、みんなで実家に集まった時に、少しだけ親の将来の話をしてみない?」と協力をお願いすることで、一人で背負っていた重荷が軽くなるはずです。
- 信頼できる第三者に相談する:一人っ子の方や、頼れる兄弟がいない場合は、叔父・叔母など信頼できる親戚や、私たちのような終活の専門家に相談するのも一つの有効な手です。客観的な意見を聞くだけで、新たな視点が見つかることもあります。
- 少し距離を置く:あまりに思いつめてしまうようなら、一時的に終活の話題から離れてみる勇気も必要です。まずはあなた自身の心を休ませてあげてください。
つらい気持ちを誰かに話すだけでも、心は少し軽くなります。親を思うあなたの優しい気持ちは、決して無駄にはなりませんから、どうか自分を責めすぎないでくださいね。

本当にそうですよね。親御さんのタイプによって、アプローチ方法は全然違ってきます。
私の経験上、特に頑固一徹タイプのお父様には、娘さんから「お父さんがいないと、私どうしたらいいか分からないから、元気なうちに教えて?」と、少し頼りない感じでお願いするのが効果的なことが多い気がします(笑)
逆に、しっかり者の息子さんが正面から正論を言うと、意地になってしまうことも。相手の性格を考えた「伝え方の工夫」が、意外な突破口になることも多いんですよ。
終活しない親への効果的なアプローチと進め方
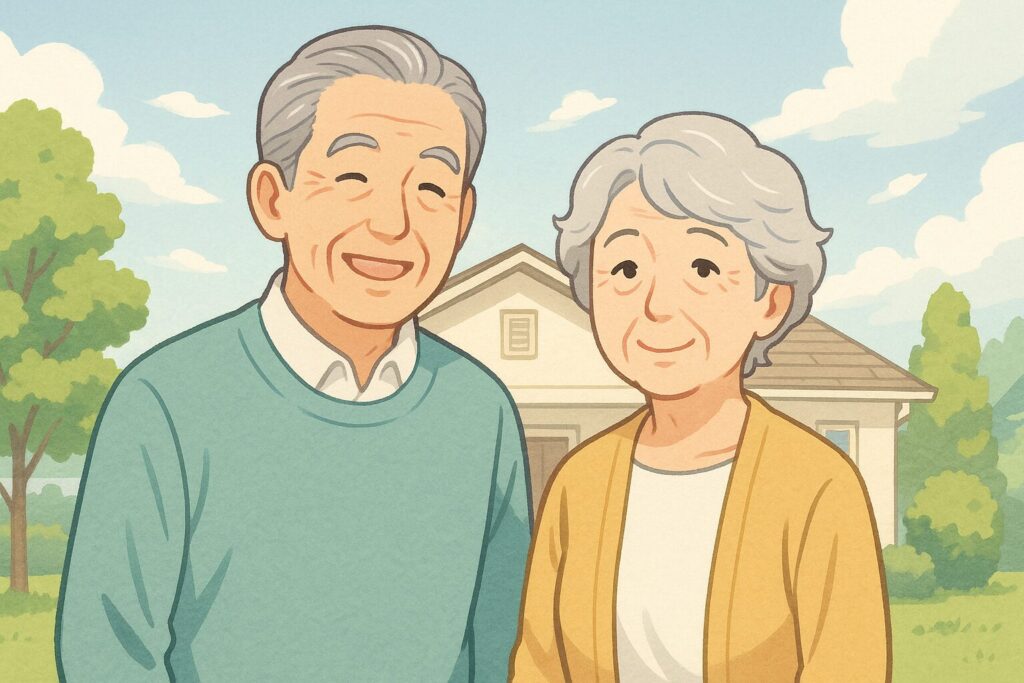
終活は何歳までに終わらせるとされますか?
「終活って、結局いつまでにやればいいの?」というご質問は、本当によくいただきます。
テレビや雑誌で特集が組まれることも増えましたが、具体的な年齢については様々な意見がありますよね。結論から言うと、「何歳までに終活を終わらせなければならない」という明確なタイムリミットや法律上の決まりは一切ありません。
しかし、最も重要な指針はあります。それは、年齢という数字よりも「心身ともに元気で、物事を冷静に、そして客観的に判断ができるうちに始める」ということです。
一般的には、人生の大きな節目をきっかけに意識し始める方が多いようです。
年代別・終活を意識するきっかけ
- 50代:子育てが一段落し、自分の時間が持てるようになる。親の介護や相続を経験し、自身の将来を具体的に考え始める。
- 60代:定年退職を迎え、仕事中心だった生活からライフスタイルが大きく変化する。体力や気力がまだ充実しており、第二の人生設計の一環として終活を捉える。
- 70代:友人や同世代の訃報に接する機会が増え、「自分の番」をより現実的に感じるようになる。身体的な衰えを感じ始め、本格的に準備の必要性を痛感する。
なぜ元気なうちが良いのかというと、例えば遺言書を作成するにも、自分の財産を正確にリストアップし、誰に何をどう残したいかを冷静に考える高度な判断能力が求められます。
認知症などを発症してしまうと、残念ながら法的に有効な意思表示ができなくなる可能性もあります。
そのため、「まだ早いかな?」と感じるくらいのタイミングで、まずは情報収集からでも始めてみるのが、実は後悔しないためのベストタイミングなのかもしれません。
介護が必要になる原因のトップは「認知症」、2位は「脳卒中」
厚生労働省の調査では、介護が必要となった主な原因として最も多いのは「認知症(16.6%)」、次いで「脳血管疾患(脳卒中など)(16.1%)」、そして「骨折・転倒(13.9%)」と続きます。
特に脳卒中や転倒による骨折は、昨日まで元気だった人にも突然起こりうる事態です。こうした予期せぬ出来事に備え、医療や介護に関する希望を元気なうちに話し合っておくことが、いかに重要であるかが分かります。
終活を始めるべき80代の現実

では、「もう80代になってしまったら、終活は手遅れなの?」と心配される方もいらっしゃるかもしれませんね。決してそんなことはありません。80代から一念発起して、ご自身の人生の整理を始める方も、たくさんいらっしゃいますのでご安心ください。
ただし、80代からの終活には、若い頃と同じようにはいかない、いくつか現実的な課題も出てくることを理解しておく必要があります。
80代から始める終活の注意点
- 想像以上の体力的な負担:家の隅々まで片付けたり、銀行や役所など複数の窓口へ何度も出向いたりする手続きは、想像以上に体力を消耗します。一日でやろうとせず、週に一度、一時間だけなど、細切れに進める工夫が必要です。
- 複雑な情報の理解と判断力の低下:保険の契約内容や、施設の利用規約など、細かい文字で書かれた複雑な文章を正確に理解したり、多くの情報の中から自分にとって最適なものを選択したりすることが、年齢とともにかつてより難しくなってくることがあります。
- 残された時間の制約:これは考えたくないことかもしれませんが、いつ病気や怪我で健康状態が変化するか分からないという、時間的なプレッシャーも考慮に入れる必要があります。「また今度」が、いつまでも続くとは限らないのです。
これらの現実を踏まえると、80代から終活を始める場合は、何もかも完璧にやろうと気負うのではなく、「これだけは絶対に家族に伝えておきたい」という優先順位を決めることが何よりも重要です。
例えば、「財産がどこにあるかを示す簡単なリストの作成」「延命治療に関する意思表示」「お葬式で呼んでほしい友人の連絡先リスト」など、残された家族が最も困りそうなことから手をつけるのが良いでしょう。
そして、お子さん世代が、情報収集を手伝ったり、手続きを代行してあげたりと、積極的にサポートしてあげる優しさが、スムーズに進めるための最大の鍵となります。
終活を意識し始める20代の視点
「終活」というと、これまではシニア世代のテーマというイメージが強かったかもしれません。
しかし最近では、驚くことに20代や30代といった若い世代でも、終活に関心を持ち、自分事として考え始める人が増えているんです。これは、決して珍しいことではなく、現代社会の変化を反映した自然な流れとも言えます。
その背景には、いくつかの理由が考えられます。一つは、「親や祖父母の介護や相続を手伝った経験」から、準備をしておくことの重要性を目の当たりにし、その大変さを実感したというケース。
もう一つは、「自分の人生をより良く、後悔なく生きるため」に、終活を前向きな自己分析やライフプランニングのツールとして捉えているという新しい価値観です。
もちろん、20代の終活は、シニア世代のそれとは少し意味合いが異なります。
20代・30代の「プレ終活」
- デジタル遺品の整理:今や生活に欠かせないSNSアカウントや、ネット銀行、各種サブスクリプションサービスのID・パスワードを整理し、万が一の際に家族が困らないようにリスト化しておく。
- 人生の価値観の明確化:エンディングノートなどを活用し、「自分のキャリアプラン」「将来の夢」「大切にしたい人間関係」などを見つめ直し、人生の羅針盤を作成する。
- 親への自然な働きかけ:自分自身が終活に関心を持つことで、親世代に対しても「最近、こういうのが流行ってるんだって。面白いから一緒にやってみない?」と、深刻にならずに自然な形で話題を振ることができる。
このように、若い世代が終活に関心を持つことは、家族全体の終活意識を高める、非常に良いきっかけにもなり得ます。もしあなたが20代、30代であれば、「自分のために始めたんだけど…」というスタンスで、情報提供という形で親御さんに話してみるのも、とても良いアプローチ方法ですね。
終活でおひとりさまが準備すべきこと
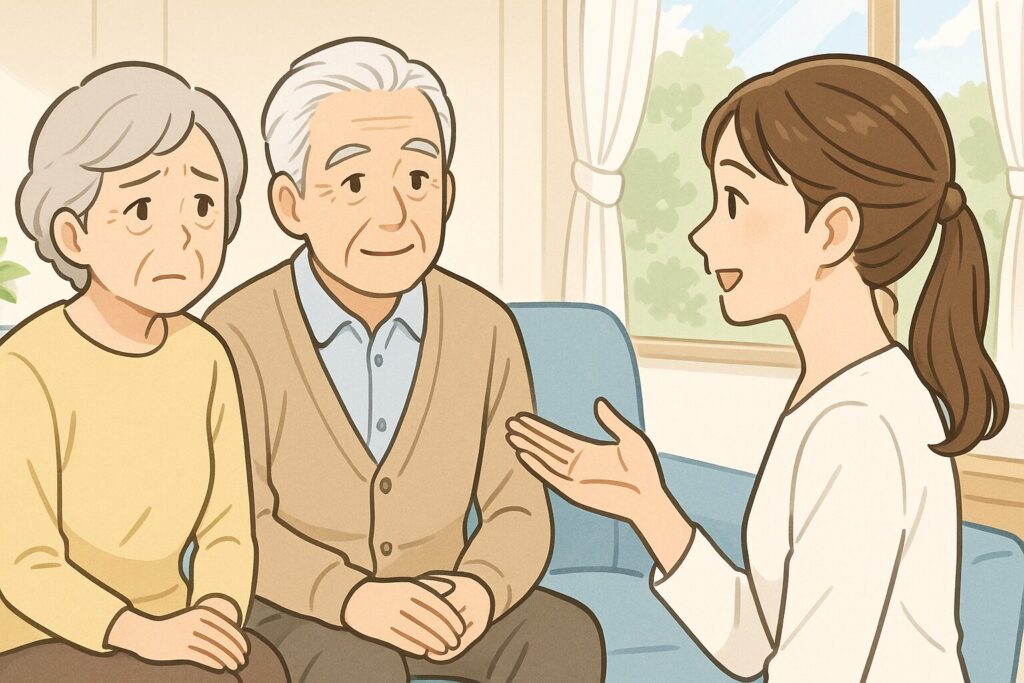
生涯独身を謳歌されている方や、お子さんがいらっしゃらないご夫婦など、いわゆる「おひとりさま」や「おふたりさま」にとって、終活はより切実で、そして何よりも重要な人生のプロジェクトとなります。
なぜなら、病気で倒れた時や、万が一のことがあった時に、法的な手続きや様々な判断を頼める直系の家族がいない、あるいは少ないためです。あらゆる手続きをご自身で、元気なうちに、計画的に進めておく必要があるのです。
多くの準備項目がありますが、特に以下の3点は、ご自身の尊厳を守り、周りに迷惑をかけないためにも、必ず準備しておきたい最重要項目です。
1. いざという時の「身元保証・身元引受人」の確保
病院への入院時や、介護施設への入所の際には、多くの場合「身元保証人」や「身元引受人」を求められます。頼れる親族がいない場合、どうすればよいのでしょうか。近年では、NPO法人や一般社団法人、企業などが有償で身元保証サービスを提供しています。サービス内容や費用は様々ですので、複数の団体から資料を取り寄せ、比較検討することが大切です。
2. 亡くなった後の手続きを託す「死後事務委任契約」
ご自身が亡くなった後の、葬儀・納骨の手配、役所への死亡届などの届け出、住んでいた家の片付けや家財道具の処分、公共料金や各種契約の解除といった、煩雑な事務手続きを、生前のうちに第三者(弁護士や行政書士、司法書士、信頼できる友人など)に公式に依頼しておく契約です。
これがないと、残された財産が宙に浮いてしまったり、疎遠だった遠い親戚に大きな負担をかけてしまったりする可能性があります。
3. 大切な財産の行き先を決めておく「遺言書」の作成
遺言書を作成し、ご自身が築き上げてきた大切な財産を、誰に、どのように残したいのか(お世話になったご友人、応援したいNPO法人、母校への寄付など)を明確にしておくことが非常に重要です。
法的に有効な遺言がない場合、法律に基づいて相続人が広範囲にわたって探されることになりますが、相続人が誰もいないと判断された場合、最終的に財産は国庫に帰属することになります。
せっかくの財産を、ご自身の意思で有効に活用するためにも、遺言書の作成は不可欠です。作成した遺言書は、法務局で保管してもらえる制度もあります。(参照:法務省 自筆証書遺言書保管制度)
これらの準備は、専門的な法律知識が必要になる場面も多いため、できるだけ早めに弁護士や行政書士などの専門家へ相談することをおすすめします。
親の終活についてよくあるご質問FAQ
ここでは、皆さんが親御さんの終活を進める上で、特によく疑問に思われる点について、Q&A形式でお答えしていきますね。
-
親が「縁起でもない」と言って話を聞いてくれません。どうすれば?
-
まずは親の気持ちを否定せず、「そうだよね」と共感することが大切です。その上で、「もしもの時に備えておくと、私たちが安心できるから」と、子どものための準備だと伝えてみてください。
-
エンディングノートと遺言書の違いは何ですか?
-
エンディングノートには法的な効力はなく、遺言書には法的な効力があるという点が最大の違いです。エンディングノートは家族へのメッセージ、遺言書は法的な手続きのための書類と考えると分かりやすいですよ。
-
財産がほとんどない場合でも終活は必要ですか?
-
はい、必要です。終活はお金のことだけでなく、医療や介護の希望、葬儀の形式などを伝える重要な機会です。財産が少なくても、残された家族が迷わないための道しるべになります。
-
認知症になってからでは終活は遅いですか?
-
認知症の診断を受けると、契約などの法律行為が難しくなるため、多くの面で終活は困難になります。だからこそ、判断能力がはっきりしている元気なうちに始めることがとても重要なんです。
エンディングノートから始めてみる

いきなり「さあ、終活を始めよう!遺言書を書こう!」と親に切り出しても、ほとんどの場合、身構えられてしまいますよね。その高いハードルをひょいっと乗り越えるための、魔法のようなアイテムがあります。それが「エンディングノート」です。
エンディングノートとは、ご自身の人生の終末期や死後に備え、ご自身の希望や、家族に伝えておきたい様々な情報を自由に書き留めておくノートのこと。
何度かお伝えしている通り、遺言書と違って法的な効力はありませんが、それ以上に家族への愛情やメッセージを伝えるための、とても強力なコミュニケーションツールになります。
なぜエンディングノートが最初の一歩として最適かというと、その最大の魅力は「気軽に、書けるところから、楽しく書ける」からです。
例えば、「私の好きな食べ物リスト」や「もう一度行きたい思い出の旅行先」「人生で一番嬉しかったこと」といった、ポジティブで楽しい項目から始めることで、親も抵抗なくペンを手に取ることができます。
そして、少しずつ慣れてきたら「かかりつけの病院の連絡先」や「大切な友人の連絡先リスト」といった、いざという時に役立つ実用的な情報を書き足していくのです。
「エンディングノートを一緒に書かない?」と誘うのは、「終活しよう」と言うよりも、ずっと柔らかく、前向きな響きがありますよね。終活という言葉を使わずに、終活を始めることができる、優れた入り口なんです。
市販の終活ノートの選び方と活用法
最近では、「終活ノート」や「エンディングノート」という名前で、大手書店や文房具店はもちろん、100円ショップでも、本当に様々な種類のノートが販売されています。
いざ選ばうとすると、どれがいいか迷ってしまいますが、選ぶ際のたった一つの大切なポイントは「親御さん自身が、これなら書けそう、書きたい、と感じるかどうか」です。
終活ノート選びの3つのポイント
- 見やすさ・書きやすさ:高齢の親御さんでも読み書きしやすいように、文字が大きく、行間が広く取られているなど、ゆったりとしたレイアウトのものを選びましょう。書き込みスペースが十分にあるかもチェックポイントです。
- 項目のバランス:項目が多すぎると、書く前にうんざりしてしまうかもしれません。最初は、自分史、医療・介護、財産、葬儀など、必要最低限の項目がバランス良く網羅されているシンプルなものがおすすめです。物足りなければ、後から別のノートに書き足せば良いのです。
- デザインや雰囲気:親御さんの好きな色や、優しいイラストが入っているもの、あるいは格調高い装丁のものなど、持っているだけで少し楽しい気持ちになれるようなデザインを選ぶのも、継続するための大切な要素です。
そして、購入した後の活用法の最大のコツは、「親子で一緒に、お茶でも飲みながら書く時間を作ること」です。
「この項目、お母さんはなんて書く?」「お父さんの若い頃の話、もっと聞きたいな」と、子どもから親に質問する形で進めると、そこから自然なコミュニケーションが生まれます。
ノートを書きながら、忘れていた昔の思い出話に花が咲くこともあり、それは家族にとって、何物にも代えがたいかけがえのない時間になるはずです。
また、公的な情報としては、各自治体がオリジナルのエンディングノート(名称は様々です)を無料で配布している場合もありますので、お住まいの市区町村の役所のホームページを確認してみるのも良いでしょう。

終活は、決して一人で抱え込むものではありません。
特に、これからの人生をどう過ごしたいか、どんな医療や介護を受けたいか、といったデリケートな問題は、元気なうちに家族みんなで話し合っておくことが、将来の「後悔」を減らす一番の薬になります。
最初は気まずいかもしれませんが、一度話し始めると「なんだ、もっと早く話せばよかったね」となるご家族がほとんどです。そのきっかけ作りとして、この記事を役立ててくださいね。
まとめ:終活しない親と向き合うための第一歩

ここまで、終活しない親の心理から具体的な進め方まで、様々な角度からお話ししてきました。情報がたくさんあって、何から手をつければいいか混乱してしまったかもしれませんね。
最後に、この記事の要点をリストでまとめておきましょう。
- 終活しない親の多くは「死への恐怖」や「まだ元気」という気持ちを抱えている
- 親のプライドを尊重し、「教えてほしい」という姿勢で接することが大切
- 終活をしないまま放置すると、葬儀、相続、各種手続きで家族に大きな負担がかかる
- 「楽観主義」「頑固一徹」など、親のタイプに合わせたアプローチを考えるのが効果的
- 親の終活がつらいと感じたら、一人で抱え込まず兄弟や専門家に相談する
- 終活を始めるのに「何歳から」という決まりはなく、元気なうちがベストタイミング
- 80代からでも終活は可能だが、優先順位を決めて家族のサポートが不可欠
- 20代など若い世代が関心を持つことも、家族の意識を高めるきっかけになる
- おひとりさまの終活では「身元保証」「死後事務委任契約」「遺言書」が特に重要
- 何から始めるか迷ったら、気軽に書けるエンディングノートがおすすめ
- 終活ノートは、親が書きやすいレイアウトやデザインのものを選ぶ
- ノートは親子で一緒に書くことで、大切なコミュニケーションの時間になる
- 終活は「死の準備」ではなく「これからの人生と家族のための準備」である
- まずは雑談から、少しずつ終活の話題に触れていくことが成功の秘訣
- 完璧を目指さず、できることから一歩ずつ進めていくことが何より重要
今日からできるアクションプラン
- 親との雑談に「終活のタネ」をまいてみる
いきなり本題に入るのではなく、テレビのニュースやご近所の話題に絡めて、「〇〇さん、生前に色々準備してたから、ご家族が助かったんだって」というように、まずは情報として話してみましょう。 - 「手伝いたい気持ち」を素直に伝える
「もしもの時に、お父さん(お母さん)の希望通りにしてあげたいから、手伝わせてほしいな」と、あくまで親のため、そして自分が助かるから、というスタンスを伝えてみてください。 - 親子で一緒にエンディングノートを1ページだけ書いてみる
本屋さんに行ったついでに、「こんなのあるんだね、試しに一冊買ってみない?」と提案してみましょう。そして、「思い出の旅行」のページなど、楽しい項目を一つだけ、その日のうちに一緒に書いてみてください。
▼あわせて読みたい関連記事▼
60代からのエンディングノート活用術|遺言との違いと正しい使い方

お気軽にご相談ください
相続は100人いれば、100通り
唯一無二の最適な相続をご提案いたします
CONTACT
専門家やえさん

- 専門家やえさん
-
堀川 八重(ほりかわ やえ)
大阪不動産・FPサービス株式会社 代表
15年以上にわたり1,500組を超えるご家族の相続や不動産のお悩みに、専門家として寄り添ってまいりました。私の信条は、法律や数字の話をする前に、まずお客様ご家族の歴史や言葉にならない想いを丁寧に「聞く」こと。信頼できる各分野の専門家チームと共に、皆様が心から安心できる最善の道筋をオーダーメイドでご提案します。一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。
最新の投稿
 お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説
お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説 相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説
相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説 お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例
お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例 お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説
お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説