「年金をもらいながら働くのって、社会保険はどうなるの?」「パートの社会保険料はいくら引かれるか心配…」そんなお悩みをお持ちではありませんか?こんにちは、終活・相続・不動産専門家のやえです。
私もお客様から、年金とパート収入のバランスについて、本当にたくさんのご相談をいただくんです。
特に、年金をもらいながらパートで働くとなると、扶養の問題や、65歳以上での扱いの違いなど、考えることがいっぱいですよね。「パートで厚生年金に入れないケースもあるの?」「パートで社会保険に加入したくないけど、どうすれば…」なんて声もよく聞きます。
また、年金とパート収入が130万以上だとどうなるのか、社会保険に入ると年金はどうなるのか、厚生年金の加入条件や、パートの厚生年金が何年で元が取れるのかなど、疑問は尽きないと思います。この記事では、そんなあなたのモヤモヤをスッキリ解決します!
この記事のポイント
- 年金受給者がパートで社会保険に加入する具体的な条件
- 収入の壁(106万円・130万円)を超えた場合の変化
- 社会保険に加入するメリットとデメリットの両側面
- 自身の希望に合わせた働き方の調整方法

年金生活中のパートと社会保険の問題は、多くの方が悩むポイントです。知らずに働いて「損をした!」なんてことにならないよう、制度の基本をしっかり押さえることが大切。この記事では、難しい制度の話を、私自身の経験も交えながら、どこよりも分かりやすく解説しますので、安心して読み進めてくださいね。
年金もらいながらパート健康保険の加入条件

厚生年金にパートで加入する条件
「パートだから社会保険は関係ないわ」なんて思っていたら、実は大間違いかもしれませんよ。最近は制度が変わって、パートやアルバイトの方でも厚生年金や健康保険に加入するケースが増えているんです。まずは、どんな場合に加入することになるのか、基本のキから見ていきましょう。
ポイントは大きく分けて2つあります。
パートタイマーの社会保険加入基準
- 週の所定労働時間と月の所定労働日数が正社員の4分の3以上
これが昔からの基本的なルールです。例えば、正社員が週40時間勤務の会社なら、週30時間以上働く場合は原則として加入対象になります。 - 「4分の3基準」を満たさなくても、特定の条件を満たす場合
こちらが近年拡大されている部分です。たとえ労働時間が短くても、以下の条件をすべて満たすと加入対象になります。
| 条件1 | 週の所定労働時間が20時間以上であること |
|---|---|
| 条件2 | 所定内賃金が月額8.8万円以上であること(年収換算で約106万円) |
| 条件3 | 勤務期間が2ヶ月を超える見込みであること |
| 条件4 | 学生でないこと |
| 条件5 | 勤務先の従業員数が51人以上であること(※2024年10月以降) |
特に、年金もらいながらパート健康保険を考える上で、この「月額8.8万円」という収入のラインは非常に重要です。賞与や残業代は含まず、あくまで決められた時給や日数で計算した月収が基準になるんですよ。
やえさん:「私の知り合いも、シフトを調整していたつもりが、うっかり月額8.8万円を超えてしまって、社会保険に加入することになった、なんて話をしていました。意外と身近な話なので、ご自身の働き方を一度チェックしてみるのがおすすめですよ。」
参考情報サイト: 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
URL: https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html
年金とパート収入はいくらまで社会保険に加入?

さて、先ほどの条件で出てきた「月額8.8万円(年収約106万円)」や、よく耳にする「130万円の壁」。この数字、一体何が違うのか混乱してしまいますよね。年金もらいながらパート健康保険について考えるとき、この「収入の壁」の理解は避けて通れません。一つずつ整理していきましょう。
通称「106万円の壁」とは?
これは、先ほどご説明したパート先の社会保険(厚生年金・健康保険)に加入するかどうかの収入ボーダーラインです。正確には月額8.8万円以上ですね。この壁を超えると、ご自身のパート先の社会保険に加入し、お給料から保険料が天引きされることになります。
通称「130万円の壁」とは?
こちらは、配偶者の扶養に入れるかどうかのボーダーラインです。年収が130万円以上になると、たとえパート先の社会保険加入条件を満たしていなくても、配偶者の扶養から外れなければなりません。その場合、ご自身で国民健康保険と国民年金に加入し、保険料を支払う義務が発生します。
ポイント整理
- 106万円の壁:自分の職場で社会保険に入るかどうかの壁
- 130万円の壁:配偶者の扶養でいられるかどうかの壁
勤務先の規模などによっては、106万円を超えても130万円未満であれば、扶養のままでいられるケースもあります。ご自身の状況をしっかり確認することが重要です。
年金をもらいながら働く場合、このパート収入にご自身の年金収入も合算して判断されるのか?という疑問が湧きますよね。社会保険の扶養の認定では、通常、年金も恒常的な収入と見なされることが多いです。そのため、合計収入が130万円(60歳以上は180万円)を超えないように注意が必要です。
年金とパート収入が130万以上だとどうなる?
もし、年金とパート収入の合計が130万円以上になった場合、具体的にどのような変化があるのでしょうか。これは手取り額に直結する、とても大切なポイントです。
結論から言うと、配偶者の社会保険の扶養から外れることになります。
扶養から外れると、ご自身で公的な医療保険と年金制度に加入しなければなりません。選択肢は主に2つです。
扶養から外れた後の選択肢
- パート先の社会保険に加入する
前述の加入条件(週20時間以上、月収8.8万円以上など)を満たす場合は、こちらの選択肢になります。保険料は会社と折半になるため、個人負担は軽くなる傾向があります。 - 国民健康保険と国民年金に加入する
パート先の加入条件を満たさない場合は、お住まいの市区町村で国民健康保険と国民年金の手続きをご自身で行う必要があります。保険料は全額自己負担です。
どちらのケースでも、これまでかからなかった保険料の負担が新たに発生するため、年収が130万円を超えたのに、手取り額が減ってしまう「働き損」という現象が起こる可能性があります。
やえさん:「お客様の中にも、『収入を増やしたくて頑張ったのに、扶養を外れて保険料を払ったら、結局手元に残るお金が減っちゃった…』とがっかりされる方がいらっしゃいます。収入の壁を越えて働くなら、この保険料負担分以上に収入を増やせるかどうかが、賢い働き方を考える上でのカギになりますね。」
【年収別】手取り額比較シミュレーション(妻が夫の扶養の場合)
年収の壁を越えると、手取り額がどう変わるのか見てみましょう。
| 年収 | 社会保険 | 手取り額(概算) | ★注目ポイント |
|---|---|---|---|
| 129万円 | 加入なし(扶養内) | 約129万円 | 手取りが最も多いゾーン |
| 130万円 | 国民健康保険・国民年金に加入 | 約106万円 | 働き損が発生! |
| 150万円 | 国民健康保険・国民年金に加入 | 約124万円 | 129万円の時より手取りが少ない |
| 160万円 | 職場の社会保険に加入 | 約130万円 | ようやく129万円の手取りを超える! |
※あくまで概算です。お住まいの地域や年齢により変動します。
年金もらいながらパート健康保険の制度は複雑ですが、この「働き損」を避けるには、中途半端に収入を増やすのではなく、年収160万円以上を目指すのが一つの目安になる、ということが分かりますね。
年金をもらいながらパートする扶養と65歳以上
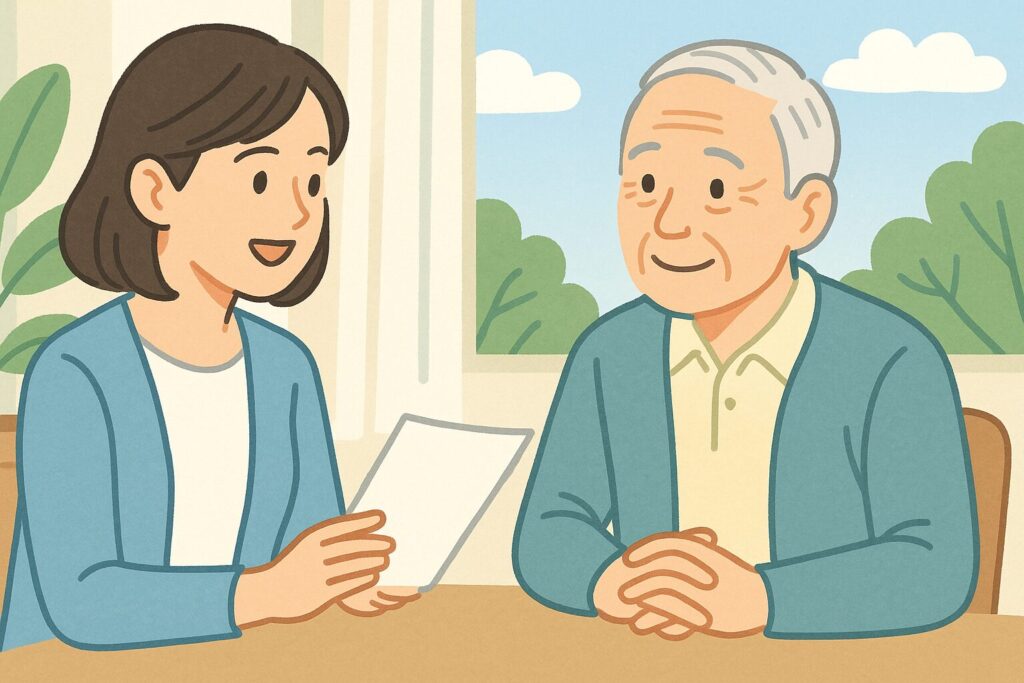
さて、ここまでは主に65歳未満の方を想定してお話ししてきましたが、「65歳を過ぎてからの働き方はどうなるの?」という疑問も多いですよね。特に、年金をもらいながらパートで働き、扶養の範囲内でいたいと考える場合、年齢によって少しルールが変わってくるので注意が必要です。
60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合
まず、社会保険の扶養(被扶養者)の認定基準が少し緩和されます。通常は年間収入130万円未満が基準ですが、60歳以上の方などは年間収入180万円未満が基準となります。
注意!
この「180万円」という基準は、あくまで配偶者などの社会保険の「扶養」に入れるかどうかの基準です。ご自身のパート先で社会保険に加入するかどうかの基準(月額8.8万円など)は、60歳以上でも基本的に変わりませんので、混同しないようにしましょう。
65歳以降の社会保険加入
65歳以降にパート先で社会保険に加入する場合、年金制度の扱いが変わります。
- 厚生年金保険:70歳になるまで加入できます。70歳を過ぎると加入資格を失いますが、働き続ける場合は「高齢任意加入」という制度もあります。
- 健康保険:75歳になるまで加入できます。75歳になると、それまでの健康保険から抜けて、全員が「後期高齢者医療制度」に移行します。
年金もらいながらパート健康保険を考える上で、特に65歳以上の方は、厚生年金保険料を払い続けることで将来の年金額を増やせるメリットがあります。一方で、在職老齢年金という制度により、お給料とご自身の年金受給額の合計額によっては年金の一部が支給停止になる可能性もあります。ご自身の年金受給額とパート収入のバランスを考えることが、より一層重要になってきます。
💡 ちょっと専門知識:在職老齢年金とは?
60歳以降、厚生年金に加入しながら働く場合、「年金の月額」と「給与・賞与を12で割った額」の合計が一定額を超えると、年金の一部または全額が支給停止になる制度です。
- 2025年度の基準額:50万円
合計額が50万円を超えない限り、年金は全額支給されます。高収入のパートでない限り、多くの方は心配ありませんが、こういう制度があることは知っておくと安心ですよ。
パートで国民健康保険を自分で払うケース
「パート先の社会保険には入りたくないし、扶養からも外れてしまった…」そんな場合は、ご自身で国民健康保険に加入し、保険料を支払うことになります。これまで保険料を払っていなかった方にとっては、毎月の支出が増えるため、大きな変化に感じられますよね。
国民健康保険料はいくらくらい?
国民健康保険料は、お住まいの市区町村によって計算方法や料率が異なりますが、基本的には前年の所得に応じて決まります。一般的に、以下の要素を組み合わせて計算されます。
- 所得割:加入者の所得に応じて計算される部分
- 均等割:加入者一人ひとりにかかる定額の部分
そのため、収入が同じでも、住んでいる場所によって保険料が数万円単位で変わることも珍しくありません。正確な金額を知りたい場合は、お住まいの市区町村の役所の窓口やホームページで試算してみることを強くおすすめします。
国民年金保険料について
国民健康保険とセットで、国民年金(第1号被保険者)への加入も必要になります。国民年金の保険料は、収入にかかわらず一律で、令和6年度は月額16,980円です。こちらも決して小さな負担ではありませんね。
年金もらいながらパート健康保険に加入する場合、保険料は会社と折半になりますが、国民健康保険は全額自己負担です。この負担額を考慮した上で、扶養を外れて働くかどうかを慎重に判断することが大切です。手取り額が減ってしまわないよう、事前にしっかりとシミュレーションしておきましょう。

ここまで、社会保険の「加入条件」という、少し複雑なルールについて見てきました。数字がたくさん出てきて難しく感じたかもしれませんが、ご自身の働き方を左右する大切な知識です。ここからは、実際に加入した場合のメリットや具体的な保険料など、より身近な疑問を解消していきますので、一緒に見ていきましょう!
年金もらいながらパート健康保険加入後の変化

年金をもらいながら働く社会保険の概要
パート先で社会保険に加入すると聞くと、「保険料で手取りが減る…」というデメリットばかりに目が行きがちではありませんか?でも、実はそれ以上に大きなメリットがたくさんあるんですよ。年金をもらいながら働く上で、社会保険がどれだけ心強い味方になってくれるか、ここでご紹介しますね。
社会保険に加入する最大のメリットは、保障が手厚くなることです。国民健康保険や国民年金だけでは得られない、充実した給付が受けられます。
健康保険の主なメリット
- 傷病手当金:業務外の病気やケガで4日以上仕事を休んだ場合、給与の約3分の2が最長1年6ヶ月間支給されます。フリーランスや扶養内パートにはない、とても手厚い制度です。
- 出産手当金:出産のために仕事を休んだ期間、給与の約3分の2が支給されます。
厚生年金の主なメリット
- 老齢厚生年金:将来受け取る年金が、国民年金(老齢基礎年金)に上乗せされて「2階建て」になります。
- 障害厚生年金:万が一の病気やケガで障害が残った場合、国民年金の障害基礎年金に上乗せして給付が受けられます。保障の範囲も広いです。
- 遺族厚生年金:加入者が亡くなった場合、残された遺族に支給されます。こちらも遺族基礎年金に上乗せされます。
やえさん:「私の友人がパート中に骨折して1ヶ月ほどお休みしたのですが、社会保険に入っていたおかげで傷病手当金がもらえて、本当に助かったと言っていました。いざという時の安心感が全然違うんですよね。年金もらいながらパート健康保険に加入することは、未来への保険でもあるんです。」
保険料の負担はありますが、それに見合うだけの、あるいはそれ以上の安心を得られるのが社会保険の大きな魅力と言えるでしょう。
社会保険に入ると将来の年金はどうなる?

「今、保険料を払って、将来の年金は本当に増えるの?」これは、社会保険への加入を考える上で、誰もが気になるポイントだと思います。結論から申し上げると、厚生年金に加入して保険料を納めれば、その分だけ将来の年金額は増えます。
日本の公的年金は「2階建て」の構造になっています。
- 1階部分:国民年金(老齢基礎年金)… 20歳から60歳までの全ての人が加入。
- 2階部分:厚生年金(老齢厚生年金)… 会社員や公務員などが加入。
パートで社会保険に加入するということは、この「2階部分」である厚生年金に加入するということです。これまで国民年金のみだった方は、厚生年金が上乗せされるため、将来受け取れる年金の合計額が増える仕組みになっています。
増える年金額の目安
厚生年金で増える年金額は、加入期間中の給与(標準報酬月額)と加入期間によって決まります。あくまで概算ですが、参考にしてみてください。
| 加入期間 | 年間給与120万円 | 年間給与150万円 |
|---|---|---|
| 5年間 | 約3.3万円 | 約4.1万円 |
| 10年間 | 約6.6万円 | 約8.2万円 |
| 15年間 | 約9.9万円 | 約12.3万円 |
※厚生労働省の資料を基に作成した概算です。
「月々にすると数千円か…」と感じるかもしれませんが、年金は生涯にわたって受け取れるものです。これが何十年と続くと考えると、総受給額には大きな差が生まれます。年金もらいながらパート健康保険に加入し、厚生年金の保険料を納めることは、長生き時代のお守りを育てるようなものですね。将来の安心な生活のためにも、エンディングノートに自身の年金情報をまとめておくことも大切です。
パートの社会保険料はいくら引かれるのか
メリットは分かったけれど、やっぱり気になるのは「毎月お給料からいくら引かれるの?」という点ですよね。社会保険料は、健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料(40歳以上65歳未満の方)、雇用保険料などを合計したものです。
このうち、金額の大きい健康保険料と厚生年金保険料は、「標準報酬月額」という、お給料を一定の幅で区切った金額を基に計算されます。そして最大のポイントは、保険料の半額を勤務先の会社が負担してくれる(労使折半)ということです。
月収別の社会保険料自己負担額の目安
以下は、東京都の協会けんぽ(令和6年度)に加入し、介護保険第2号被保険者に該当しない場合の概算です。お住まいの地域や加入する健康保険組合によって金額は異なります。
| 月収(標準報酬月額) | 健康保険料(自己負担) | 厚生年金保険料(自己負担) | 合計(月額) |
|---|---|---|---|
| 88,000円 | 約4,400円 | 約8,052円 | 約12,452円 |
| 104,000円 | 約5,200円 | 約9,516円 | 約14,716円 |
| 126,000円 | 約6,300円 | 約11,529円 | 約17,829円 |
例えば月収10万円の方なら、毎月1万5千円弱が保険料として引かれるイメージですね。この金額を見て「やっぱり高い…」と感じるか、「手厚い保障がついて、将来の年金も増えてこの金額なら」と感じるかは、人それぞれだと思います。
年金もらいながらパート健康保険の制度を利用するかどうかは、この負担額とメリットを天秤にかけて、ご自身のライフプランと照らし合わせて考えることが何より大切です。
パートで社会保険に加入したくない場合

「手取りが減るのは困る」「扶養の範囲内で働きたい」など、様々な理由で社会保険への加入を希望しない方もいらっしゃるでしょう。その場合は、加入条件に当てはまらないように働き方を調整する必要があります。
具体的な調整方法としては、以下のようなものが考えられます。
社会保険に加入しないための働き方調整
- 週の労働時間を20時間未満に抑える
シフト制のパートであれば、勤務時間を調整してもらうのが最も確実な方法です。 - 月収を8.8万円未満に調整する
時給や勤務日数から月収を計算し、超えないようにシフトを減らしてもらうなどの対応が必要です。 - 年収を130万円未満に抑える
配偶者の扶養でい続けたい場合は、年間の合計収入(パート収入+年金収入など)が130万円(60歳以上は180万円)を超えないように管理します。
ただし、これらの調整を行う際には、必ず勤務先の担当者(店長や人事部など)に事前に相談することが不可欠です。「社会保険に加入したくないので、労働時間を調整したい」という意思をはっきりと伝え、お互いに納得の上で働き方を決めるようにしましょう。

何も言わずにいると、会社側は『もっと働けるならシフトを増やしてあげよう』と考えてくれるかもしれません。後から『知らなかった』では済まないこともあるので、働き始める前や、契約更新のタイミングで、きちんとコミュニケーションを取っておくことがトラブルを防ぐコツですよ。」
自分の希望を伝えることは、決してわがままではありません。年金もらいながらパート健康保険の制度を理解した上で、自分に合った働き方を選択するための大切な一歩です。
パートでも社会保険に加入したいとき
逆に、「手厚い保障が魅力的だから、ぜひ社会保険に加入したい!」と考える方もいらっしゃいますよね。特に、ご自身が世帯主であったり、将来の年金を少しでも増やしたいと考えていたりする場合には、積極的に加入を検討する価値は十分にあります。
社会保険に加入したい場合は、加入条件を満たすように働き方を増やすことが基本的な考え方になります。
社会保険に加入するためのステップ
- まずは勤務先に相談する
「社会保険に加入したいので、週20時間以上働けますか?」など、ご自身の希望を伝えてみましょう。人手不足の職場などでは、歓迎されるケースも多いです. - 求人を探す際に条件を確認する
これからパートを探す場合は、「社会保険完備」と明記されている求人を選ぶのが確実です。面接の際にも、加入条件や見込みの労働時間について確認しておくと安心です。 - 「任意特定適用事業所」の制度を活用する
勤務先の従業員数が50人以下で、本来は社会保険の適用拡大の対象外であっても、労使の合意があれば任意で社会保険に加入できる制度があります。もし希望する同僚が他にもいるなら、会社に働きかけてみるのも一つの手です。
年金もらいながらパート健康保険に加入することは、目先の手取りは減るかもしれませんが、将来への投資と捉えることができます。特に、ご家族の状況やご自身の健康状態などを考慮し、万が一の際のセーフティーネットを確保しておきたいと考える方にとっては、非常に心強い制度と言えるでしょう。ご自身の人生設計、例えば実家の不動産相続などを考える上でも、安定した収入と保障は重要な基盤となります。
よくあるご質問(FAQ)

-
夫の会社の扶養から外れたくないのですが、どうすればいいですか?
-
年金収入とパート収入の合計が、年間で130万円(60歳以上の場合は180万円)を超えないように働き方を調整する必要があります。勤務先に扶養内で働きたい旨を伝え、シフトなどを管理してもらうのが最も確実です。
-
短期間だけ社会保険に加入するメリットはありますか?
-
はい、あります。例えば、厚生年金は加入期間が1ヶ月でもあれば、その分が将来の年金に反映されます。また、健康保険も加入中に病気やケガで働けなくなった場合に傷病手当金を受けられる可能性があるため、短期間でも保障があるのは大きな安心材料になります。
-
複数のパートを掛け持ちしている場合、社会保険はどうなりますか?
-
複数のパート先でそれぞれ社会保険の加入条件を満たすことは稀ですが、もし満たした場合、主に収入の多い方の勤務先で加入することになります。ただし、労働時間などを合算して加入条件を満たす場合は、ご自身でメインの事業所を選択して加入手続きを行います。判断が難しい場合は、年金事務所に相談することをおすすめします。
-
年金とパート収入がある場合、確定申告は必要ですか?
-
はい、多くの場合で必要になります。公的年金の収入金額が400万円以下で、かつパート収入が20万円以下であれば確定申告は不要ですが、パート収入が20万円を超える場合は確定申告が必要です。忘れると追徴課税の対象になる可能性もあるので注意しましょう。
-
106万円と130万円の違いは?
-
106万円は「自分の職場で社保に入る」基準、130万円は「配偶者の扶養でいられる」基準です。
-
65歳以上だと何が変わる?
-
扶養判定が180万円に緩和。厚生年金は70歳まで、健康保険は75歳まで加入可。
年金もらいながらパート健康保険の賢い利用のまとめ
ここまで、年金もらいながらパート健康保険に加入する際の条件や、加入後の変化について詳しく見てきました。様々なルールがあって少し難しかったかもしれませんが、ポイントを整理して、ご自身の働き方に活かしていきましょう。
- 社会保険の加入は働き方や収入によって決まる
- 「106万円の壁」と「130万円の壁」の違いを理解する
- 65歳以上は扶養の収入基準が180万円に緩和される
- 社会保険加入は手取りが減るが保障は手厚くなる
- 将来の年金が国民年金との2階建てになり受給額が増える
- 健康保険の傷病手当金などいざという時のセーフティーネットになる
- 保険料は会社と折半で負担してくれる
- 月収8.8万円の場合の自己負担は月額1.2万円程度が目安
- 加入したくない場合は週20時間未満など働き方の調整が必要
- 働き方の調整は必ず事前に勤務先に相談する
- 加入したい場合は積極的に会社に意思を伝えシフトを増やす
- 社会保険完備の職場を選ぶのも一つの方法
- ご自身のライフプランや価値観に合わせて選択することが最も重要
- 働き損にならないよう事前に収入と保険料をシミュレーションする
- 不明な点は年金事務所や勤務先に確認する

いかがでしたでしょうか。年金をもらいながらの働き方は、まさに十人十色です。正解は一つではありません。大切なのは、制度を正しく理解し、ご自身の希望や将来設計に合った選択をすること。この記事が、あなたが前向きな一歩を踏み出すための、心強い羅針盤となれば、これほど嬉しいことはありません。
▼あわせて読みたい関連記事▼
年金いくらもらえる調べ方|スマホで簡単!5分でわかる試算ガイド

お気軽にご相談ください
相続は100人いれば、100通り
唯一無二の最適な相続をご提案いたします
CONTACT
専門家やえさん

- 専門家やえさん
-
堀川 八重(ほりかわ やえ)
大阪不動産・FPサービス株式会社 代表
15年以上にわたり1,500組を超えるご家族の相続や不動産のお悩みに、専門家として寄り添ってまいりました。私の信条は、法律や数字の話をする前に、まずお客様ご家族の歴史や言葉にならない想いを丁寧に「聞く」こと。信頼できる各分野の専門家チームと共に、皆様が心から安心できる最善の道筋をオーダーメイドでご提案します。一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。
最新の投稿
 お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説
お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説 相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説
相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説 お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例
お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例 お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説
お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説






