「故人様との思い出の場所に、もう一度一緒に行きたいな…」「でも、遺骨と旅行なんて、そもそもしてもいいのかしら?」と、大切な方を亡くされた後、ふとそんな風に悩んでいませんか?故人様を偲ぶ気持ちが強いほど、一緒に旅をしたいと願うのは、とても自然なことですよね。
結論から言うと、故人様の遺骨と一緒に旅行することは、法律上も宗教的にも何の問題もありませんよ。ご安心くださいね。ただし、亡くなった人と一緒に旅する想いを大切にするためには、いくつか知っておくべきマナーや注意点があるんです。
例えば、遺骨を持ち歩くのは良くないのか?という周囲の目や、喪中に旅行へ行くのは良いのか悪いのかといった一般的な慣習、納骨前に旅行へ行くときのマナーなど、気になる点は多いかもしれません。
また、実際にどうやって運ぶのか、遺骨を運ぶバッグやケースの選び方、遺骨を持ち運ぶ際の風呂敷活用法、遺骨を持って新幹線や飛行機に乗るときのルールなど、具体的な方法も知っておきたいですよね。
この記事では、終活と相続の専門家である私「やえ」が、遺骨と旅行に関するあらゆる疑問にお答えします。遺骨ペンダントで旅先に同行させる方法や、ペット遺骨を持ち歩いて旅行する方法、さらには遺骨を持ち歩くスピリチュアルな考え方まで、あなたの不安を解消し、故人様との素敵な旅を実現するためのお手伝いをしますね。
この記事のポイント
- 故人と一緒に旅行することの基本的な考え方がわかる
- 遺骨を持ち運ぶ際の具体的な方法と注意点がわかる
- 公共交通機関を利用する際のルールがわかる
- 周囲へ配慮したマナーを身につけられる

こんにちは!終活・相続の専門家やえです。
私も父を亡くした時、父が好きだった温泉に遺骨ペンダントを連れて行った経験があります。最初は少し戸惑いましたが、父も喜んでくれているような気がして、心が温かくなったのを覚えています。
この記事が、あなたと故人様にとって、心安らぐ旅のきっかけになれば嬉しいです。
故人との遺骨と旅行|基本的な考え方

亡くなった人と一緒に旅する想い
大切な方がこの世を去った後、「生前よく行ったあの場所に、もう一度一緒に行きたい」「この素晴らしい景色を、叶うなら見せてあげたかった」…そう感じるのは、故人様を深く愛しているからこその、ごく自然で美しい感情です。故人様を亡くした悲しみは、時間が経っても簡単に癒えるものではありません。
しかし、一緒に旅をすることで、その深い悲しみが少し和らいだり、複雑な気持ちの整理がついたりすることがあります。言ってしまえば、これは「グリーフケア」の一環であり、新しい供養の形の一つなんです。
【調査データ】広がる「手元供養」という選択肢
供養の形は多様化しており、「手元供養」も一般的な選択肢の一つとして認識されつつあります。
大手仏壇・仏具店ポータルサイトを運営する株式会社鎌倉新書が2024年に行った調査によると、お墓の購入においても、一般墓だけでなく納骨堂や樹木葬など多様な選択肢が検討されています。
このような背景の中、遺骨の一部を手元に残し、故人を身近に感じる「手元供養」を選ぶ人も増えており、特別なことではなくなっています。これは、故人と常に一緒にいたいという遺族の自然な想いの表れと言えるでしょう。
もちろん、そこにあるのは物理的には「お骨」という形かもしれません。でも、多くの人はそこに故人様の魂や存在そのものを感じ、心の中で対話するように旅をします。これは、残された私たちが、これからも前を向いて自分の人生を生きていくための、かけがえのない大切な時間になる可能性があります。
旅先で出会う美しい風景、心和む温泉、美味しい食事。それらを「一緒に」分ち合う気持ちで過ごすことで、故人様との絆を再確認し、心の中に温かい思い出を新たに灯すことができるでしょう。だからこそ、その「一緒に旅をしたい」という純粋な想いを、何よりも大切にしていただきたいなと思います。
喪中に旅行へ行くのは良いのか悪いのか

「喪中の期間に旅行だなんて、不謹慎だと思われないかしら…」と、世間体を心配される方は少なくありません。日本の古くからの慣習では、喪中、特に忌中(きちゅう)と呼ばれる期間は、故人を偲び、身を慎むべき時間とされてきました。
「忌中」と「喪中」の違いって?
忌中:故人が亡くなってから仏式では四十九日間、神式では五十日間を指します。この期間は、故人の魂がまだこの世とあの世の間をさまよっていると考えられ、遺族は穢れ(けがれ)の中にあるとして、結婚式などのお祝い事への出席や、神社への参拝などを控えるのが一般的です。
喪中:故人が亡くなってから約一年間を指します。忌中が明けた後も、故人を偲び、派手な行動は慎む期間とされています。年賀状を控え、喪中はがきを出すのはこのためです。
このように、本来は静かに過ごすべき時間とされていますが、現代では価値観も大きく変化しています。故人を偲ぶことを目的とした旅行や、深い悲しみで傷ついた心を癒すための旅(グリーフケア旅行)であれば、一概に「悪いこと」とは言えなくなってきました。
むしろ、自宅にずっと閉じこもって悲しみに暮れるよりも、故人様との思い出の地を巡ることで心が安らぎ、明日への活力が湧いてくるのであれば、それもまた故人様が喜んでくれる、立派な供養の形と言えるでしょう。
ご親族への配慮は忘れずに
ただし、ご親族の中には、昔ながらの伝統や慣習を非常に重んじる方もいらっしゃるかもしれません。
特にご年配の方にその傾向が見られます。旅行に行くことを決めた際は、「故人との約束だった場所に報告に行きたいんだ」というように、その目的と想いを事前にご家族や近しい親族に丁寧に伝え、理解を得ておくことが、後々の無用なトラブルを避けるための大切な配慮ですよ。
最終的には、ご自身の気持ちと、故人様を想う心が一番大切です。その気持ちがあれば、その行動が不謹慎にあたることは決してない、と私は信じています。
遺骨を持ち歩くのは良くないのか?注意点
「遺骨を持ち歩くと、故人様が成仏できないのでは?」「縁起が悪いことだと聞いたけど…」といった不安を耳にすることがあります。これは長年、日本の文化に根付いてきた考え方の一つですが、どうぞ安心してください。遺骨を持ち歩くことは、法律上、全く問題ありません。
「墓地、埋葬等に関する法律」という法律では、遺骨を「埋葬(土に埋めること)」または「収蔵(納骨堂などに納めること)」する場所について定めていますが、自宅で保管すること(自宅供養)や、一時的に持ち運ぶことを禁じる条文は一切ないのです。
【法律の視点】遺骨の持ち運びは法律違反にならない?
「墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)」では、遺骨を「埋葬」または「収蔵」する場所について定めていますが、遺骨を自宅で保管したり、一時的に持ち運んだりすることを禁止する規定は存在しません。法律違反となるのは、許可されていない土地(公園や他人の私有地など)に無断で遺骨を埋めたり、遺棄したりする行為です。故人を偲ぶために大切に持ち運ぶことは、法律上何ら問題ありません。
つまり、法的には「OK」ということです。ただ、実際に持ち運ぶ際には、いくつか注意しておきたい大切なポイントがあります。
遺骨を持ち歩く際の3大注意点
- ①紛失・盗難のリスク:これが何よりも一番避けたい事態です。旅先での気の緩みから、手荷物を置き忘れてしまったり、車上荒らしに遭ったりする可能性はゼロではありません。遺骨は常に手元から離さず、貴重品として慎重に取り扱いましょう。
- ②破損のリスク:一般的な骨壷は陶器でできているため、衝撃に非常に弱いです。スーツケースに入れて預け荷物にするのは絶対に避けましょう。手荷物として運ぶ際も、緩衝材(タオルやエアキャップなど)で骨壷をしっかり保護する工夫が必要です。
- ③周囲への配慮:遺骨に対しては、本当にさまざまな考えを持つ方がいらっしゃいます。肯定的な方もいれば、不快に感じる方や、怖がる方もいるのが現実です。公共の場で安易に骨壷を取り出したり、「遺骨が入っているんです」と公言したりするのは、無用なトラブルを避けるためにも控えた方が無難です。
これらの点にしっかりと気を配れば、故人様を身近に感じながら、心穏やかに過ごすことができます。遺骨を持ち歩くという行為は、故人を心から大切に想う気持ちの表れであり、決して非難されるようなことではありませんよ。
遺骨を持ち歩くスピリチュアルな考え方

遺骨を持ち歩くことについて、スピリチュアルな観点からはいろいろな考え方があります。どれが絶対的な正解というわけではありませんので、ご自身が「こう考えたいな」としっくりくる方を大切にするのが一番良いでしょう。
ポジティブな考え方:「守護」と「安心感」
一つ目のポジティブな考え方として、「故人様が守護霊のように常に寄り添い、自分たちを見守ってくれる」というものがあります。遺骨を手元に置くことで、故人様の温かいエネルギーを身近に感じ、不思議と心が落ち着き、大きな安心感を得られるという方は少なくありません。
旅先での安全を祈ってくれたり、美しい景色を一緒に楽しんでくれたり…そう考えると、一人旅でも心強いパートナーがいるようで、なんだか嬉しい気持ちになりますよね。
ネガティブな考え方:「未練」と「成仏」
一方で、その逆の考え方もあります。「いつまでも遺骨を現世に留めておくことは、故人の魂の執着を生み、成仏の妨げになってしまう」というものです。この世への未練が断ち切れず、安らかに次のステージへ進めなくなってしまう、という解釈ですね。
このため、故人様の魂の安寧を願うのであれば、できるだけ早く納骨し、静かに眠ってもらうべきだと考える方もいらっしゃいます。
「分骨」という折衷案
どちらの考え方も、根底にあるのは故人を深く想う優しい気持ちです。もし「成仏の妨げになるかも…」という不安が少しでもあるのなら、「分骨」という方法を検討してみてはいかがでしょうか。
遺骨の大部分はきちんとお墓や納骨堂に納骨して故人様の安らかな眠りを確保し、ほんの一部だけを小さなお骨壷やペンダントに入れて手元に残すのです。こうすれば、故人様の成仏を願いつつ、自分の「そばにいてほしい」という気持ちも満たすことができ、心の平穏を保ちやすくなりますよ。
遺影を持って旅行する意味
「遺骨を持ち運ぶのは、やっぱり少し抵抗がある…」「骨壷は大きくて、物理的に持ち運びが大変」と感じる方もいらっしゃるでしょう。そんな場合には、遺影を持って旅行するという選択肢も、故人と一緒に旅をするための、とても素敵で立派な方法の一つです。
遺影には、故人様の最も元気だった頃、輝いていた頃の姿が写し出されています。その優しい笑顔と一緒に旅をすることで、まるで生前の故人様と直接会話しながら旅をしているような、温かく、そして懐かしい気持ちに包まれることでしょう。
何より、遺骨に比べて持ち運びが格段に手軽で、紛失や破損のリスクも低く、周囲の目を気にする必要もほとんどありません。旅先で写真を撮る際に、そっと遺影を風景に重ねて撮影すれば、本当に一緒にその場を訪れたかのような、特別な記念写真を残すこともできます。
現代的な遺影の持ち運び方
- ミニ写真立て:手のひらサイズのコンパクトな写真立てなら、バッグの中にそっと忍ばせておけます。
- デジタルフォトフレーム:キーホルダー型の小さなデジタルフォトフレームなら、複数の思い出の写真をスライドショーで表示することも可能です。
- スマートフォンの待ち受け画面:最も手軽な方法です。いつでもどこでも、故人様の笑顔を見ることができます。
大切なのは「一緒にいたい」「この景色を見せてあげたい」という、あなたのその気持ちです。その気持ちを表現する方法は、決して一つではありません。ご自身が最も心地よいと感じる方法を選んでくださいね。
納骨前に旅行へ行くときのマナー

一般的に、葬儀後、四十九日の法要を終えて納骨するまでの期間、特に亡くなってから七日ごとの法要を行う「忌中」は、故人様がまだこの世とあの世の間を旅している大切な期間と考えられています。
この期間、遺族は外出を極力控え、静かに故人を偲び、供養に専念すべき、という考え方が日本の古くからの慣習としてあります。
このため、納骨前の、とりわけ忌中の期間に遺族が旅行をすることを、快く思わないご親族、特にご年配の方がいらっしゃる可能性は十分に考慮しておく必要があります。もし、どうしてもこの期間に旅行を計画するのであれば、以下の点に配慮することで、周囲の理解を得やすくなります。
納骨前・忌中の旅行で配慮したい3つのこと
- 旅行の目的を誠実に伝える:単なる気晴らしや娯楽目的の旅行ではなく、「故人が生前、もう一度行きたいと願っていた温泉へ、報告を兼ねて連れて行ってあげたい」「結婚記念日を過ごした思い出の場所に、感謝を伝えに行きたい」というように、故人を偲ぶための旅であることを明確に、そして誠実に伝えましょう。その目的であれば、多くの方が理解を示してくれます。
- 親族への丁寧な事前相談:事が起きてから「実は…」と話すのではなく、計画段階で近しい親族には事情を話し、相談しておくことが非常に大切です。「黙って行っていた」という事実は、後々まで関係にしこりを残す原因になりかねません。事前に一言相談があるだけで、相手の受け取り方は全く違ってきます。
- 遺骨や自宅の管理を徹底する:もし遺骨を自宅に残して旅行に行く場合は、お線香の火の元やロウソクの管理、家の戸締りなど、安全管理を徹底しましょう。長期間家を空ける場合は、信頼できる親族に時々様子を見てもらうようお願いするのも良い方法です。もちろん、遺骨を一緒に旅行に連れて行くという選択肢もありますが、その際は紛失や破損に最大限の注意が必要です。
伝統的なマナーを尊重する心と、深い悲しみの中にいる残された家族の心のケア。この両方のバランスを考えながら、ご家族にとって最善の方法を選んでくださいね。

ここまで、遺骨と旅行に関する基本的な考え方についてお話ししてきました。故人を想う気持ちに「こうでなければならない」という絶対的な決まりはありません。
大切なのは、ご自身が納得し、心が安らぐ方法を見つけることです。次の章では、もっと具体的に、どうやって遺骨を運ぶのか、その方法と注意点を見ていきましょうね!
遺骨と旅行する方法と移動時の注意点

納骨前の遺骨の運び方と注意点
火葬後、納骨の日までご自宅で安置されている遺骨を旅行などで運ぶ際には、故人様への敬意を払い、安全に細心の注意を払うことが最も重要です。通常、火葬場で収骨した骨壷は、桐などで作られた「骨箱」に納められ、さらに美しい刺繍などが施された「覆い袋(おおいぶくろ)」という布製の袋で覆われています。この一式を丁寧に持ち運ぶのが基本の形となります。
自家用車で運ぶ場合
自家用車での移動は、公共交通機関のように他の方の視線を気にする必要がなく、最も気を使わずに済む方法と言えるでしょう。移動の際は、喪主や故人に最も近しい方が、助手席や後部座席で膝の上にしっかりと抱えて運ぶのが、最も丁寧で安全な方法とされています。
もし、どうしても座席に置く必要がある場合は、平らで安定した場所に置き、急ブレーキやカーブで倒れたり滑ったりしないように、シートベルトで固定したり、クッションやタオルで周囲を囲んで動かないように工夫したりすると安心です。
公共交通機関で運ぶ場合
電車やバス、タクシーなどを利用する場合は、骨壷と一目でわからないように周囲へ配慮することが大人のマナーです。後ほど詳しく解説しますが、落ち着いた色の風呂敷で包んだり、中身が透けないしっかりとした紙袋や、底が安定したトートバッグなどに入れたりして運びます。
電車内で足元に置くと、不意に蹴飛ばしてしまったり、他の方の邪魔になったりする可能性があるので避けましょう。基本的には膝の上に抱えるのが望ましいですが、網棚に置く場合は、他の乗客の荷物で圧迫されたり、滑り落ちたりしないよう、置き方には十分な注意が必要です。
「分骨証明書」はどんな時に必要?
前述の通り、遺骨の一部(分骨)を持ち運ぶ際に、法的に「分骨証明書」の携帯が義務付けられているわけではありません。しかし、万が一の事態、例えば旅先で職務質問を受けたり、事故に巻き込まれたりした際に、その遺骨の正当な所有者であることを証明するために、持っていると非常に心強いお守り代わりになります。
また、将来的にその分骨した遺骨を別のお墓や納骨堂に納めたいと考えた場合、この証明書が必要不可欠になります。分骨証明書は、分骨を行った火葬場や、すでにお墓がある場合はその墓地の管理者から、通常は無料か若干の手数料で発行してもらえますので、念のため取得しておくことをお勧めします。
遺骨ペンダントで旅先に同行させる方法

「骨壷ごと持ち運ぶのは、少し大げさに感じるし、管理も大変そう…」「もっとさりげなく、いつでも故人と一緒にいたいな」…そうお考えの方に心からお勧めしたいのが、遺骨ペンダントです。これは「手元供養」と呼ばれる新しい供養の形の一つで、ここ数年で急速に広まり、多くの方に選ばれています。
遺骨ペンダントは、ペンダントのトップ部分が小さな容器状になっていて、ネジ式の蓋などを開けて、ごく少量の粉骨した遺骨や遺灰を納めることができるようになっています。最大の魅力は、そのデザイン性の高さです。
一見しただけでは中に遺骨が入っているとは全く分からないような、普通のファッションアクセサリーと変わらないモダンで洗練されたデザインのものが非常に多いのです。
これにより、周囲の目を一切気にすることなく、仕事中もプライベートの時間も、そしてもちろん旅行中も、常に故人様を胸元で感じ、身に着けていることができます。
旅行の際も、特別な準備は何も必要なく、普段通りアクセサリーとして身に着けていくだけです。ただし、空港の保安検査場では、素材によっては金属探知機に反応する可能性があります。
その際は慌てずに係員に「これは遺骨の入った大切なペンダントです」と事情を説明するか、事前に外してトレーに乗せ、X線検査に通せばスムーズに通過できます。遺骨ペンダントは、遺された人の深い悲しみにそっと寄り添い、大きな心の支えとなってくれる、温かいアイテムです。
遺骨を運ぶバッグやケースの選び方
骨壷を覆い袋や骨箱のまま持ち運ぶことに抵抗がある場合や、さらなる安全性を確保したい場合には、適切なバッグやケースに入れることをお勧めします。
これにより、見た目にも周囲への配慮ができ、何より大切な遺骨を衝撃から守ることができます。どのようなものを選べば良いか、具体的なポイントをいくつかご紹介しますね。
バッグ・ケース選びの4つの重要ポイント
- 衝撃を吸収できる素材か:骨壷は陶器製で非常に割れやすいものです。バッグを選ぶ際は、内側にクッション性のある素材が使われているものや、カメラバッグのように仕切りを調整できるものが理想的です。そうでなければ、タオルやエアキャップ(プチプチ)などを緩衝材として十分に入れられるよう、骨箱に対して少し余裕のあるサイズのものを選びましょう。
- 安定して自立するか:移動中、少し床に置きたい場面は意外と多いものです。バッグの底に鋲が打ってあるなど、底面がしっかりしていて、置いたときにぐらつかずに安定して自立するものが望ましいです。これにより、不意に倒れてしまう心配が格段に少なくなります。
- 遺骨と分かりにくいデザインか:周りの方に余計な気を使わせないためにも、一見して骨壷が入っているとは分からないような、普通のボストンバッグや、少し大きめのトートバッグのようなデザインを選ぶのがスマートです。最近では、見た目はお洒落なバッグでありながら、内部は骨壷を固定できるようになっている専用の「骨壷バッグ」も市販されています。
- 持ち運びやすい形状か:遺骨と骨壷、骨箱を合わせると、意外と重量があります(成人男性で3kg前後)。ご自身の体力に合わせ、長時間持っていても腕や肩に負担がかからない持ち手や、ショルダーベルトが付いているものを選びましょう。長距離の移動であれば、キャリーケースを利用するのも賢い選択です。
高価な専用品でなくても、これらのポイントを押さえていれば、お手持ちのバッグで工夫して代用することも十分可能ですよ。大切なのは、故人様を安全・安心に運ぶ、という気持ちです。
遺骨を持ち運ぶ際の風呂敷活用法

日本の伝統的な美しい布、風呂敷は、実は大切な遺骨を運ぶ際に非常に役立つ、優れたアイテムなのです。骨箱を風呂敷で丁寧に包むことで、より一層の敬意を示すことができ、見た目にも非常にスマートで、周囲への配慮も行き届きます。
風呂敷を使う最大のメリットは、その柔軟性です。骨箱の大きさが様々でも、どんなサイズにも合わせてぴったりと美しく包むことができます。結び方を少し工夫すれば、安定した持ち手を作ることもでき、電車の手すりなどにかけた際も滑りにくくなります。
色や柄については、弔事の際には紫や紺、深緑、グレーといった、なるべく落ち着いた色合いの無地や、派手すぎない伝統柄のものを選ぶのが一般的です。
おすすめの包み方「平包み」
最も基本的で丁寧な包み方として「平包み」があります。これは結び目を作らない包み方で、相手に物を差し出す際に使われる最も格式の高い方法です。持ち運びの際は、包んだ風呂敷を両手で底から支えるようにして持ちます。
持ち運びやすさを優先するなら、結び目を作る「お使い包み」や「四つ結び」も便利です。インターネットで「風呂敷 包み方」と検索すると、たくさんの分かりやすい動画なども見つかりますので、ぜひ一度参考にしてみてください。
風呂敷一枚を準備しておくだけで、故人様への敬意も示せ、とてもスマートに持ち運ぶことができますよ。
ペット遺骨を持ち歩いて旅行する方法
犬や猫など、長年連れ添ったペットは、もはや家族同然、いえ、家族そのものです。その大切な家族の一員の遺骨と一緒に、思い出の場所へ旅行したいと考える方が増えるのは、とても自然なことです。
ペットの遺骨の取り扱いについては、人間の遺骨とは異なり、法律上は「モノ」として扱われるため、「墓地、埋葬等に関する法律」の規制は受けません。そのため、基本的にはご自身の判断で自由に持ち運ぶことができます。
ただし、自由に運べるからといって、どこにでも無条件で持ち込めるわけではありません。特に注意が必要なのが、宿泊施設や公共交通機関など、他の方も利用する施設を利用する場合です。
トラブルを未然に防ぐためにも、予約の段階で正直に「実は、亡くなったペットの遺骨を一緒に連れて行きたいのですが、問題ないでしょうか?」と一言、電話やメールで確認しておくことを強くお勧めします。
最近ではペットフレンドリーな施設が増えており、事情を話せば快く受け入れてもらえるケースがほとんどですが、中には動物アレルギーの方や、他のお客様への配慮から、遺骨であっても持ち込みを遠慮してほしいというルールを設けている施設も存在するかもしれません。事前の確認は、お互いが気持ちよく過ごすための大切なマナーです。
持ち運び方は、人間の遺骨の場合と同様に、衝撃から守れるようにタオルで包んだり、周りの人に配慮してバッグに入れたりする形で行いましょう。
最近はペット用の本当に可愛らしいデザインの小さな骨壷や、遺骨を納められるキーホルダー、アクセサリーもたくさん販売されていますので、そういったものを利用するのも、ペットとの新しい旅の形としてとても素敵ですね。
遺骨を持って新幹線や飛行機に乗るときのルール

故郷への帰省や、遠方への旅行で、新幹線や飛行機を利用して遺骨を運ぶこともあるでしょう。その際の基本的なルールと、特に注意すべき点をまとめました。
まず大前提として、遺骨はスーツケースなどに入れて貨物として預ける「預け荷物」には絶対にせず、必ずご自身で管理できる「手荷物」として機内や車内に持ち込むようにしてください。
預け荷物にすると、他の荷物と乱暴に扱われて骨壷が破損したり、万が一の紛失(ロストバゲージ)で大切な遺骨が行方不明になったりするリスクがあるためです。これは絶対に避けなければなりません。
| 交通機関 | ルールと注意点 |
|---|---|
| 新幹線・電車 | 特別な乗車手続きや、運賃とは別の追加料金は一切必要ありません。JR各社が定める手荷物のサイズ・重量制限(縦・横・高さの合計が250cm以内、重さ30kg以内など)の範囲内であれば、問題なく無料で持ち込めます。繰り返しになりますが、他の乗客に配慮し、骨壷と分からないようにバッグや風呂敷で丁寧に包み、膝の上で抱えるか、網棚で安定させて管理しましょう。 |
| 飛行機(国内線) | こちらも特別な搭乗手続きは基本的に不要で、手荷物として機内に持ち込めます。ただし、必ず通過しなければならない保安検査場でのX線検査には注意が必要です。骨壷の材質(陶器、金属、大理石など)や厚みによっては、X線で中身がはっきりと確認できず、係員から中身について質問されたり、場合によっては蓋を開けての目視確認を求められたりする可能性があります。その際は慌てず、落ち着いて「故人の遺骨です」と説明すれば、係員も丁寧に対応してくれます。念のため「火葬許可証」や「埋葬許可証」のコピーを手荷物に入れておくと、よりスムーズな証明が可能です。 |
| 飛行機(国際線) | これが最も注意が必要で、入念な事前準備が不可欠です。遺骨の国外への持ち出し、および他国への持ち込みに関するルールは、国によって大きく異なります。検疫証明書や死亡診断書(英訳版)、大使館や領事館が発行する特別な許可証など、様々な書類の提出が求められる場合があります。また、利用する航空会社によっても独自の規定が定められています。 このため、ご出発の前には必ず①渡航先の国の在日大使館・領事館と、②利用する航空会社の両方に、電話などで直接問い合わせ、必要な手続きと書類を正確に確認してください。これらの公的な機関から得られる一次情報が、最も確実な情報源となります。この確認を怠ると、最悪の場合、空港で遺骨を没収されてしまったり、入国を拒否されたりする深刻な事態になりかねませんので、くれぐれもご注意ください。 |
【外務省の公式見解】遺骨の海外持ち出しで絶対に確認すべきこと
まず前提として、日本から遺骨を海外へ持ち出すこと自体に、日本の法律で定められた特別な出国手続きはありません。
しかし、重要になるのは受け入れ側である渡航先国のルールです。国によっては遺骨の持ち込みに際して特別な手続きを定めている場合があり、必要な書類も様々です。一般的には、死亡診断書(英訳付き)や火葬許可証のほか、在外公館(渡航先国の在日大使館・領事館)での認証手続きなどが求められることがあります。
この点について外務省も、手続きは国や地域によって大きく異なるため、事前に必ず渡航先の国の在日大使館・領事館に直接確認するよう公式に案内しています。この確認を怠ると、現地の空港でトラブルになったり、最悪の場合、入国が拒否されたりする可能性があります。
遺骨の持ち運びについてよくあるご質問FAQ
-
遺骨を旅行に持っていくとき、分骨証明書は絶対に必要ですか?
-
国内旅行であれば、法的に分骨証明書の携帯義務はありません。しかし、万が一の際に遺骨の身元を証明できるため、持っているとより安心です。
-
遺骨を運ぶのに料金はかかりますか?
-
ご自身で手荷物として運ぶ場合、追加料金は一切かかりません。新幹線や飛行機でも、規定のサイズ・重量内であれば無料の手荷物として扱われます。
-
遺骨を郵送することはできますか?
-
遺骨の郵送は、日本郵便の「ゆうパック」でのみ可能です。他の宅配業者は基本的に受け付けていません。送る際は、品名に「遺骨」と明記する必要があります。
-
全ての遺骨を旅行に持っていくべきですか?
-
全ての遺骨(全骨)を持ち運ぶ必要はありません。紛失のリスクなどを考えると、一部だけを分骨して持ち運ぶ「手元供養」の形が一般的でおすすめです。

具体的な持ち運び方がイメージできましたか?大切なのは、安全と周囲への配慮です。
しっかり準備すれば、何も怖いことはありませんよ。
さて、最後のまとめとして、故人様を偲ぶための旅の心得と、今日からできるアクションプランをお伝えしますね!
まとめ:故人を偲ぶための遺骨と旅行の心得
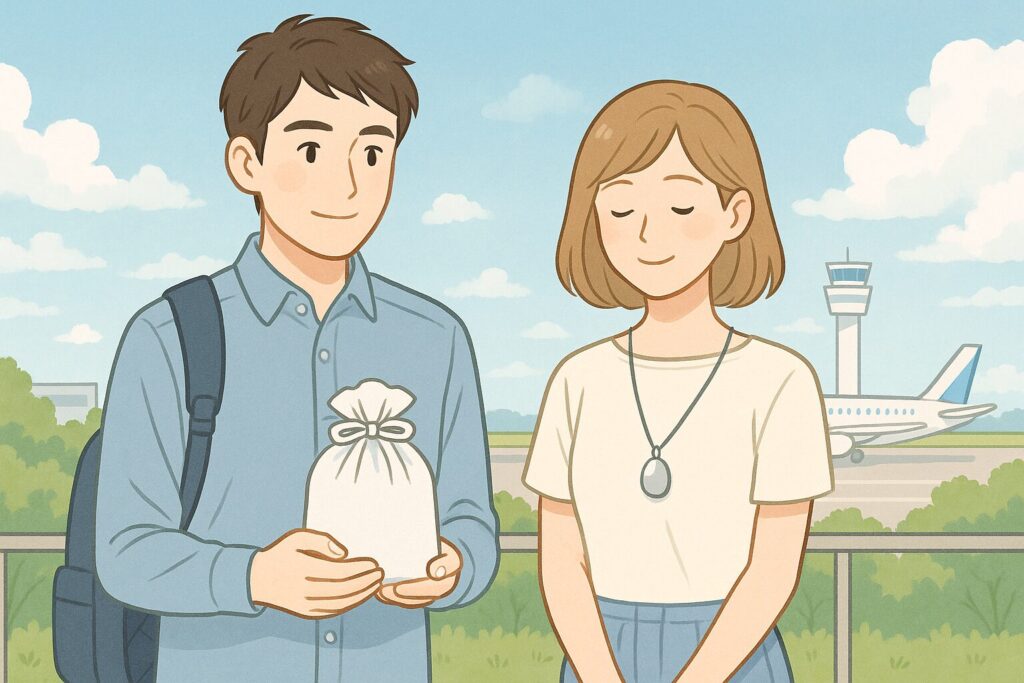
- 遺骨との旅行は法律的にも宗教的にも問題ない
- 大切なのは故人を偲び、一緒にいたいという気持ち
- 喪中の旅行は一概に悪くなく、心のケアになる場合もある
- 旅行に行く際は、事前に親族へ相談すると丁寧
- 遺骨を持ち歩くこと自体は縁起の悪いことではない
- 持ち運びの際は紛失、盗難、破損のリスクに注意する
- スピリチュアルな考え方は、自分が心地よいものを信じる
- 遺骨が難しい場合は遺影を代わりにするのも良い方法
- 納骨前、特に忌中の旅行は慎重に検討する
- 遺骨を運ぶ際は骨箱と覆い袋のままが基本
- 自家用車が最も安全で気を使わない移動手段
- 公共交通機関では風呂敷やバッグで人目に配慮する
- 遺骨ペンダントはさりげなく同行できる便利なアイテム
- 遺骨を運ぶバッグは衝撃吸収性と安定性が重要
- ペット遺骨の旅行は可能だが施設への事前確認を
- 新幹線や国内線飛行機は手荷物として持ち込み可能
- 国際線は渡航国と航空会社への事前確認が必須
今日からできるアクションプラン
- 故人様とどこへ行きたいかリストアップしてみる:思い出の場所、見せてあげたかった景色などを書き出して、旅の計画を具体的に想像してみましょう。
- どんな形で故人様と旅をするか決める:遺骨ペンダント、分骨した小さな骨壷、遺影など、ご自身に合った方法を選んでみましょう。手元供養の品を探してみるのも第一歩です。
- ご家族や親しい人に話してみる:「故人様と〇〇へ旅行に行こうと思うんだけど…」と、あなたの気持ちを打ち明けてみましょう。きっと理解し、応援してくれますよ。
故人様との旅は、きっとあなたにとってかけがえのない、温かい時間になるはずです。一歩踏み出して、素敵な思い出を作ってくださいね!
▼あわせて読みたい関連記事▼
終活とは?意味と始め方をわかりやすく解説|初心者が損しない準備法

お気軽にご相談ください
相続は100人いれば、100通り
唯一無二の最適な相続をご提案いたします
CONTACT
専門家やえさん

- 専門家やえさん
-
堀川 八重(ほりかわ やえ)
大阪不動産・FPサービス株式会社 代表
15年以上にわたり1,500組を超えるご家族の相続や不動産のお悩みに、専門家として寄り添ってまいりました。私の信条は、法律や数字の話をする前に、まずお客様ご家族の歴史や言葉にならない想いを丁寧に「聞く」こと。信頼できる各分野の専門家チームと共に、皆様が心から安心できる最善の道筋をオーダーメイドでご提案します。一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。
最新の投稿
 お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説
お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説 相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説
相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説 お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例
お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例 お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説
お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説






