「親からの相続、一体いくらから税金がかかるの?」と考え始めると、現金3000万の遺産で相続税はいくらですか?とか、銀行預金なら相続税はいくらから?親から500万円もらったら税金はかかりますか?など、疑問が次々湧いてきて不安になりますよね。
特に、相続税がいくらまで無税なのか、子供はいくらまで無税なのか、その基準ははっきり知っておきたいところ。この記事を読めば、相続税の早見表の見方も分かり、5000万円の相続税はいくらになるか、子供2人だとどうなるか、1億円の相続税はいくらかかるかといった具体的な疑問もスッキリ解消します。
相続税いくらから親子でかかるかのモヤモヤ、一緒に晴らしていきましょう。
この記事のポイント
- 親子間の相続税がかかる基本の仕組みがわかる
- 知らないと損する具体的な節税対策がわかる
- 相続発生から申告・納税までの具体的な流れがわかる
- よくある失敗例と、それを避けるための注意点がわかる

こんにちは、終活・相続専門家のやえです。相続税って、言葉だけで難しく感じますよね。でも大丈夫!基本の「基礎控除」さえ理解すれば、ほとんどのケースはスッキリ解決します。この記事では、私が経験したリアルな事例も交えながら、皆さんの「?」を「!」に変えていきますね。
相続税いくらから親子でかかる?基本を解説
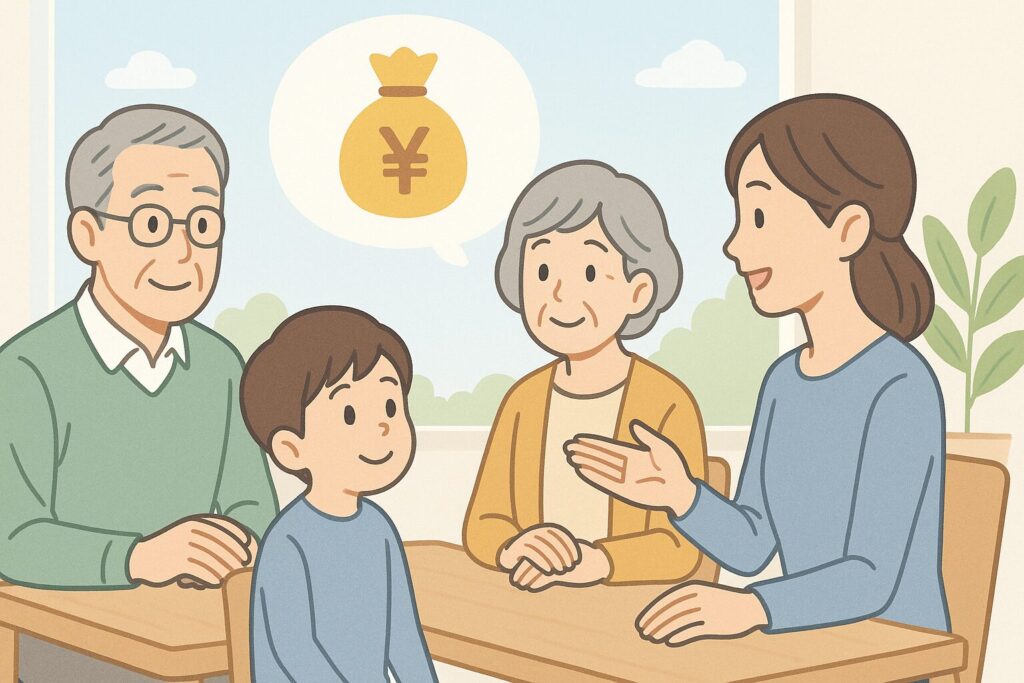
親からの相続でいくらまで無税ですか?
いきなり核心からお話ししますね!親からの相続でいくらまで無税かというと、その答えは「基礎控除額」という魔法の数字にかかっています。この金額以下の財産であれば、相続税は1円もかかりませんし、申告の必要もありません。
じゃあ、その基礎控除額って一体いくらなの?と思いますよね。計算は意外とシンプルなんですよ。
基礎控除額の計算式
3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数) = 基礎控除額
例えば、お父様が亡くなって、相続人がお母様と子供2人(合計3人)だったとします。この場合の計算は…
3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円
となり、相続財産の総額が4,800万円以下であれば、相続税はかからない、ということになります。相続税いくらから親子で、という疑問の最初の答えは、この計算式にあるわけですね。
やえさん
法定相続人っていうのは、民法で定められた相続する権利がある人のことです。通常は配偶者と子供、親、兄弟姉妹の順になります。誰が相続人になるかで基礎控除の額が変わるので、ここはとても大事なポイントですよ!>>相続権の範囲と順位について詳しくはこちら
私が以前ご相談に乗ったお客様で、お父様の財産が預金と少しの有価証券で、合計4,000万円ほどだった方がいらっしゃいました。相続人は奥様とご長男のお二人。「うちは4,000万円もあるから絶対に相続税がかかる!」と心配されていましたが、計算してみると基礎控除額は4,200万円(3,000万円+600万円×2人)。
「え、払わなくていいんですか!?」と、とても安心されたのを覚えています。このように、まずは相続税の基礎知識として、ご自身のケースで基礎控除額がいくらになるか把握することが第一歩ですね。
相続税で子供はいくらまで無税になる?

「じゃあ、子供一人あたりいくらまで、という決まりはあるの?」というご質問もよく受けます。これも先ほどの「基礎控除」の考え方が基本になります。
結論から言うと、「子供一人につきいくらまで無税」という個別の非課税枠があるわけではありません。相続人全員で使える「基礎控除」という大きな枠があって、その範囲内なら結果的に子供も税金を払わずに済む、という仕組みなんです。
例えば、お母様が亡くなり、子供1人だけが相続人だった場合。
3,000万円 + (600万円 × 1人) = 3,600万円
この3,600万円が基礎控除額です。お母様の遺産総額が3,600万円以下なら、お子さんは相続税を払う必要はありません。
注意点:遺産の分け方で税額は変わる!
基礎控除額を超えた場合、誰がどの財産をどれだけ相続するか(遺産分割協議)によって、各人が支払う税額は変わってきます。相続税の総額を計算してから、それぞれの取得割合に応じて按分する、という流れになるためです。
相続税いくらから親子でという問題は、相続人の数だけでなく、遺産の分け方も関係してくる、と覚えておいてくださいね。
銀行預金の場合、相続税はいくらから?
「タンス預金ならバレないかもしれないけど、銀行預金はごまかせないわよね…。いくらから税務署にチェックされるのかしら?」なんて、こっそり聞かれることがあります(笑)。実は最近、タンス預金を銀行に預ける際のリスクについてのご相談も増えているんですよ。
これも答えは同じで、財産の種類(銀行預金、不動産、現金など)に関係なく、全ての財産の合計額が基礎控除額を超えた場合に相続税の課税対象となります。
銀行預金だから特別にいくらから、という基準があるわけではありません。相続が開始されると(つまり、亡くなられると)、金融機関は故人の口座を凍結します。
そして、相続人がその預金を引き出すためには、戸籍謄本などを提出して正規の手続きを踏む必要があります。この過程で、税務署は金融資産の動きを把握できる仕組みになっているんです。
ですから、銀行預金も正直に全体の財産に含めて計算することが大切です。相続税の申告が必要になった場合、預金残高証明書などを添付して、正確な金額を報告する必要がありますよ。
親から500万円もらったら税金はかかる?
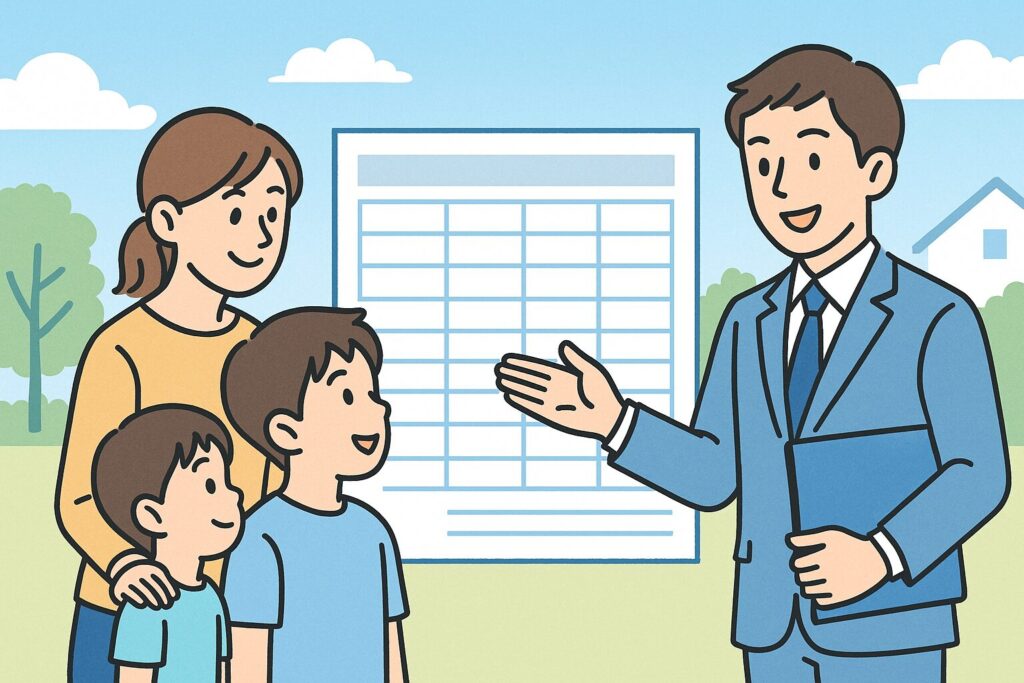
このご質問、実は「相続税」と「贈与税」が少し混ざっているかもしれませんね。状況によって答えが変わってくる、とても良い質問です!
ケース1:親が生きている時にもらう場合(贈与)
親御さんがご健在のうちに500万円をもらった場合、これは「贈与」にあたります。贈与税には年間110万円の基礎控除があります。つまり、1年間(1月1日~12月31日)にもらった財産の合計が110万円以下なら贈与税はかかりません。
500万円もらった場合は、基礎控除の110万円を引いた390万円に対して贈与税がかかります。最近ではPayPayのようなキャッシュレスでの贈与も増えていますが、現金と同じく贈与税の対象になるので注意が必要ですね。
計算式:(500万円 - 110万円)× 税率20% - 控除額25万円 = 53万円(※特例贈与の場合)
ケース2:亡くなる直前にもらっていた場合(相続財産への加算)
ここが要注意ポイントです!亡くなる前の一定期間内(現在は3年、段階的に7年に延長)に行われた贈与は、相続財産に持ち戻して相続税の計算に加算されるルールがあります。
例えば、お父様が亡くなる2年前に500万円の贈与を受けていたとします。この500万円は、お父様の遺産総額にプラスして相続税を計算しなくてはなりません。これを「生前贈与加算」と呼びます。
「じゃあ、払った贈与税は損しちゃうの?」というと、そんなことはありません。その場合は、計算した相続税額から、すでに支払った贈与税額を差し引くことができます(贈与税額控除)。
豆知識:相続時精算課税制度
原則60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子や孫へ贈与する場合に選択できる制度です。2,500万円まで贈与税がかからず、超えた分は一律20%の税率になります。ただし、この制度を使って贈与した財産は、全額が相続税の課税対象になる点に注意が必要です。
このように、親からお金をもらうタイミングによって、かかる税金の種類や扱いが変わってくるんですね。
300万円の相続税はいくらになるのか
「300万円の相続があったら、税金はいくら?」というご質問ですね。ありがとうございます。
もし、相続する財産の総額が300万円だった場合、先ほどご説明した基礎控除額を思い出してみてください。基礎控除の最低額は、相続人が1人の場合でも3,600万円です。
300万円は3,600万円よりもずっと少ないですよね。ですから、遺産総額が300万円の場合、相続税はかかりません。
もしかしたら、「相続税が300万円になるのは、いくらの遺産をもらった時?」というご質問だったかもしれませんね。それはまた後の項目で、具体的な計算例と一緒にお見せしますので、そちらを参考にしてください!
現金3000万の遺産で相続税はいくら?
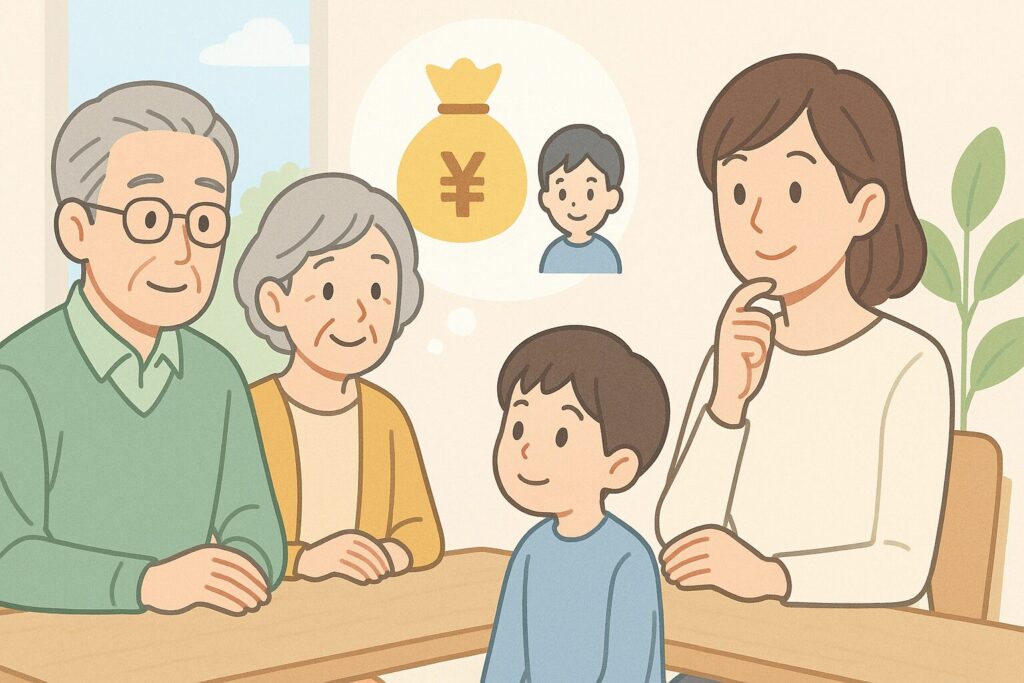
「手元に現金で3,000万円の遺産が!これって税金かかるの?」というケースですね。これも基礎控除額がカギを握ります。
もし、相続人がお子さん1人だけだったとしましょう。その場合の基礎控除額は…
3,000万円 + (600万円 × 1人) = 3,600万円
遺産が現金3,000万円のみで、他に財産がなければ、基礎控除額の3,600万円を下回っています。そのため、このケースでも相続税はかかりません。
では、相続人が配偶者とお子さん2人(合計3人)だったらどうでしょう?
3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円
基礎控除額がさらに大きくなるので、もちろん相続税はかかりませんね。
相続税いくらから親子で、という疑問に対しては、「最低でも3,600万円を超えないとかからない」と覚えておくと、多くのケースで安心できるのではないでしょうか。

どうでしょう?基礎控除の考え方、少し掴めてきましたか?「3,000万円+600万円×人数」この式さえ覚えておけば、大まかな判断はできます。でも、不動産が入ってくると話は別。評価額の計算が少し複雑になるので、次の章で具体的な金額例を見ていきましょうね!
相続税いくらから親子でかかる?具体例で確認

ここからは、基礎控除額を超えるケースを想定して、具体的な金額でシミュレーションしていきましょう。「相続税いくらから親子」で税額がどう変わるか、リアルに感じていただけると思います。
4000万の相続税は子供にかかりますか?
遺産総額4,000万円。相続人は子供1人のみ。このケースを考えてみましょう。
まず基礎控除額を計算します。
3,000万円 + (600万円 × 1人) = 3,600万円
遺産総額4,000万円は、基礎控除額3,600万円を超えていますね。ですので、この場合は相続税がかかります。
では、いくらかかるのでしょうか?計算してみましょう。
相続税の計算ステップ
- 課税遺産総額を出す
4,000万円(遺産総額) - 3,600万円(基礎控除) = 400万円 - 相続税率をかけて税額を計算する
課税遺産総額が1,000万円以下の部分の税率は10%です。
400万円 × 10% = 40万円
ということで、このケースでお子さんが支払う相続税は40万円となります。遺産が4,000万円あっても、税金は40万円で済むのですね。意外と少ない、と感じた方もいるのではないでしょうか。

そうなんです!「超えた分にだけ」税金がかかる、というのがポイントです。4,000万円まるまるに税金がかかるわけではないので、ご安心くださいね。
子供2人だと5000万円の相続税はいくら?

次はもう少し複雑なケースです。遺産総額5,000万円。相続人は子供2人のみ。お父様が亡くなって、お子さん二人が相続するイメージですね。
まずは、しつこいようですが基礎控除の計算から(笑)。これが全ての始まりです!
3,000万円 + (600万円 × 2人) = 4,200万円
やはり遺産総額5,000万円が基礎控除額を超えていますね。では、計算に進みましょう。
ステップ1:課税遺産総額を出す
5,000万円(遺産総額) - 4,200万円(基礎控除) = 800万円
ステップ2:法定相続分で仮に分けて、それぞれの税額を出す
ここが少しややこしいところです。一度、法律で決まった相続分(法定相続分)で分けたとして、全体の税額(相続税の総額)を計算します。子供2人の場合、相続分は1/2ずつです。
- 長男の仮の取得分:800万円 × 1/2 = 400万円
- 次男の仮の取得分:800万円 × 1/2 = 400万円
それぞれの税額を計算します(税率10%)。
- 長男の仮の税額:400万円 × 10% = 40万円
- 次男の仮の税額:400万円 × 10% = 40万円
ステップ3:相続税の総額を出す
仮の税額を合計します。
40万円 + 40万円 = 80万円
これが、この相続全体でかかる「相続税の総額」です。
ステップ4:実際の取得割合で按分する
最後に、この総額80万円を、実際に財産をもらった割合で分けます。もし、お子さんたちが話し合って、ちょうど半分(2,500万円)ずつ相続したとしたら、それぞれが支払う税金は…
長男:40万円、次男:40万円 となります。
もし分け方が違ったら?
例えば、ご長男が事業資金として多く相続したい、ということで遺産の4/5(4,000万円)を相続し、次男が1/5(1,000万円)を相続したとします。その場合、支払う税額も変わります。
- 長男の納税額:80万円 × 4/5 = 64万円
- 次男の納税額:80万円 × 1/5 = 16万円
このように、相続税いくらから親子で負担するかの割合は、遺産の分け方次第で調整できるのです。
遺産1億円の相続税はいくらになる?
では、金額が大きくなった場合はどうでしょう。遺産総額1億円。相続人は配偶者と子供2人(合計3人)とします。
基礎控除額は、3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円です。
課税遺産総額は、1億円 - 4,800万円 = 5,200万円となります。
これを法定相続分(配偶者1/2、子供は各1/4)で仮に分けます。
- 配偶者:5,200万円 × 1/2 = 2,600万円
- 子供A:5,200万円 × 1/4 = 1,300万円
- 子供B:5,200万円 × 1/4 = 1,300万円
それぞれの税額を、税率表(後述します)を使って計算します。
- 配偶者:2,600万円 × 15%(税率) - 50万円(控除額) = 340万円
- 子供A:1,300万円 × 15%(税率) - 50万円(控除額) = 145万円
- 子供B:1,300万円 × 15%(税率) - 50万円(控除額) = 145万円
相続税の総額は、340万円 + 145万円 + 145万円 = 630万円です。
「え、630万円も払うの!?」と驚かれたかもしれません。でも、ここからが重要です!
配偶者の税額軽減(配偶者控除)
配偶者が相続した財産については、最低でも1億6,000万円まで、または法定相続分までであれば、相続税がかからないという、非常に強力な特例があります。
ですので、今回のケースで配偶者が法定相続分通り5,000万円(1億円の半分)を相続した場合、配偶者の納税額は0円になります。
結果、子供2人が残りの630万円を実際に相続した割合に応じて支払うことになります。もし子供たちが2,500万円ずつ相続したとしたら、それぞれ157.5万円ずつ納税する、という計算になります。(※実際の按分計算はもう少し複雑ですが、ここでは概算としてご理解ください)
配偶者がいるかどうかで、子供の負担は大きく変わってくるのですね。相続税いくらから親子で、という視点では、この配偶者控除は絶対に知っておきたい制度です。
相続税の計算に役立つ早見表

毎回こうして計算するのは大変ですよね。そこで、おおよその税額がパッとわかる「相続税の早見表」というものがあります。あくまで目安ですが、ご自身の状況に近いものを見て、参考にしてみてください。
| 遺産総額 | 配偶者と子1人 | 配偶者と子2人 | 子1人のみ | 子2人のみ |
|---|---|---|---|---|
| 5,000万円 | 40万円 | 10万円 | 160万円 | 80万円 |
| 8,000万円 | 235万円 | 188万円 | 620万円 | 470万円 |
| 1億円 | 385万円 | 315万円 | 1,220万円 | 770万円 |
| 2億円 | 1,670万円 | 1,350万円 | 4,860万円 | 3,340万円 |
| 3億円 | 3,460万円 | 2,860万円 | 9,180万円 | 6,920万円 |
※この表は法定相続分で分割し、配偶者の税額軽減を適用した場合の概算です。実際の税額は財産の状況や分割方法により変動します。
より詳しい情報や税率については、国税庁のウェブサイトで確認することをお勧めします。
参考情報サイト: 国税庁「No.4155 相続税の税率」
URL: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
知らないと損!相続税いくらから?親子間の相続税を軽くする2つの特例
さて、ここまでは相続税の基本的な計算についてお話ししてきましたが、実は知っているだけで税金の負担を大きく減らせる可能性がある、強力な節税対策があるんです。「相続税いくらから親子でかかるか分かったけど、できれば安くしたい!」というのが本音ですよね。ここでは代表的な2つの特例をご紹介します。
①生命保険の非課税枠を活用する
「え、生命保険って相続税対策になるの?」と驚かれる方も多いのですが、これは相続対策の王道とも言える方法です。
故人が保険料を負担していた生命保険金は「みなし相続財産」として課税対象になりますが、素晴らしいことに非課税枠が用意されています。
生命保険金の非課税枠
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
例えば、法定相続人が奥様とお子さん2人(合計3人)の場合、500万円 × 3人 = 1,500万円までが非課税になります。もしお父様が3,000万円の生命保険を遺してくれたとしたら、1,500万円分は相続財産の総額から差し引いて計算できるのです。

私が担当したお客様で、預金が5,000万円、生命保険金が1,500万円という方がいました。相続人はお子さん3人。基礎控除は4,800万円なので、預金だけだと200万円が課税対象です。でも、生命保険金の非課税枠が1,500万円(500万円×3人)あったので、保険金はまるまる非課税!結果的に相続税はゼロになったんですよ。これは本当に大きな差ですよね。
この制度は、現金をただ預金しておくのではなく、生命保険という形に変えておくだけで適用できる、非常に有効な対策です。
②小規模宅地等の特例で自宅の評価額を下げる
そして、こちらが最も強力な節税対策と言っても過言ではない「小規模宅地等の特例」です。特に、遺産の大部分がご自宅の土地・建物という場合に絶大な効果を発揮します。
簡単に言うと、一定の条件を満たせば、ご自宅の敷地の評価額を最大で80%も減額できるという制度です。
例えば、評価額が5,000万円の土地があったとします。この特例が適用できれば、なんと評価額を1,000万円(5,000万円 × 20%)として相続税を計算できるのです。4,000万円も評価額が下がるなんて、すごいですよね!
適用には厳しい条件が!
ただし、この特例は誰でも使えるわけではありません。「亡くなった方と同居していた親族が相続して住み続ける」など、細かい要件がいくつもあります。適用できるかどうかは、専門家による判断が不可欠です。
以前、相続した実家をどうするかで悩んでいたお客様がいらっしゃいました。財産は評価額6,000万円のご自宅のみ。相続人はお子さん一人で、基礎控除は3,600万円。通常なら2,400万円が課税対象となり、数百万円の相続税がかかる計算でした。
しかし、そのお子さんはお父様と同居されていたため、この特例を適用。土地の評価額が大幅に下がり、基礎控除の範囲内に収まったことで、相続税がゼロになりました。もしこの制度を知らなかったら…と考えると、本当に大きな違いです。
相続税いくらから親子で、という問題は、こうした特例を知っているか否かで結論が全く変わってくるのです。
相続税いくらから?親子の場合相続税申告までの6つのステップと注意点

「うちは相続税がかかりそう…」と分かったら、次に気になるのは「じゃあ、具体的に何をすればいいの?」ということですよね。相続税の申告と納税には「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」という期限があります。意外と短いので、段取り良く進めることが大切です。ここでは、全体の流れを6つのステップで解説します。
ステップ1:相続人と財産の確定
まず、誰が相続人になるのかを確定させる必要があります。そのために、故人が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)を全て集めます。これによって、知らなかった子供がいないかなどを法的に確認するのです。
並行して、どんな財産がどれくらいあるのか、財産の調査を行います。預金通帳、不動産の権利証、有価証券の取引報告書、借金の契約書など、あらゆるものをリストアップしていきます。
ステップ2:遺言書の有無の確認と遺産分割協議
故人が遺言書を遺している場合は、原則としてその内容に従って財産を分けます。遺言書がない場合は、相続人全員で話し合って、誰がどの財産をどれだけ相続するかを決めます。これを「遺産分割協議」と呼びます。
全員が合意したら、その内容を「遺産分割協議書」という書類にまとめ、全員が署名し、実印を押します。これは後の不動産の名義変更や預金解約の際に必須となる重要な書類です。
ステップ3:申告書の作成と提出
財産の分け方が決まったら、それに基づいて相続税の計算を行い、相続税の申告書を作成します。申告書は国税庁のホームページからダウンロードできますが、非常に複雑です。多くの場合は税理士に作成を依頼することになります。
完成した申告書は、故人の最後の住所地を管轄する税務署に提出します。申告期限に間に合うように、余裕を持って進めましょう。
納税も忘れずに!
申告書の提出と納税はセットです。原則として、申告期限までに現金で一括納付します。納税が遅れると延滞税がかかってしまうので注意してくださいね。
【要注意】相続でよくある3つの失敗談

知識がないばかりに、後から大きなトラブルになってしまう…。そんなケースを私はたくさん見てきました。ここでは、特に多い失敗談を3つご紹介します。皆さんは同じ轍を踏まないようにしてくださいね。
失敗談①:名義預金の申告漏れ
「これは妻名義の通帳だから、夫の相続財産じゃないですよね?」という勘違い。これが本当に多いんです!たとえ名義が奥様やお子さんでも、その預金の原資が亡くなったご主人の給料などであった場合、それは「名義預金」としてご主人の相続財産と見なされます。
税務署は個人の過去の所得を把握していますから、「収入に対して預金が少ないな…」となれば、家族名義の口座を調査します。ここで申告漏れが発覚し、追徴課税されるケースは後を絶ちません。
失敗談②:不動産評価の自己判断ミス
「固定資産税の評価額で申告しちゃいました」というのも、よくある失敗です。相続税の計算で使う土地の評価額は、原則として「路線価」で計算します。これは固定資産税評価額よりも高くなることがほとんどです。
自己判断で低い評価額で申告してしまうと、税務調査でほぼ100%指摘されます。過少申告加算税や延滞税の対象となり、余計な税金を払う羽目に…。不動産の評価は、必ず専門家に依頼しましょう。
失敗談③:遺産分割で揉めて申告期限オーバー
これが最も悲しい失敗談かもしれません。相続人同士で感情的な対立が生まれ、遺産の分け方が決まらないまま10ヶ月の申告期限が過ぎてしまうケースです。
期限までに分割が決まらないと、先ほど紹介した「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といった強力な節税特例が使えません。とりあえず法定相続分で申告・納税し、後から修正申告することになりますが、一時的に多額の税金を納める必要があり、精神的にも金銭的にも大きな負担となります。
相続税いくらから親子で、という税金の問題以前に、円満な家族関係を維持することが、実は一番の相続対策なのかもしれませんね。
よくあるご質問(FAQ)
-
相続税の申告をしなかったら、どうなりますか?
-
税務調査で無申告が発覚した場合、本来の税金に加えて「無申告加算税」や「延滞税」といったペナルティが課せられます。悪質な財産隠しと判断されると、さらに重い「重加算税」がかかることもあります。申告義務がある場合は、期限内(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)に必ず申告しましょう。
-
相続税は現金で一括払いしないといけないのですか?
-
原則は現金一括での納付ですが、難しい場合は「延納」(分割払い)や「物納」(不動産などで納める)という制度を利用できる可能性があります。ただし、それぞれ厳しい条件があるので、利用を考えたい場合は早めに税務署や税理士に相談してください。
-
借金やローンも相続財産になりますか?
-
はい、なります。借入金や未払金といったマイナスの財産も相続の対象です。プラスの財産からマイナスの財産を差し引いて、残った額が相続税の課税対象となります。もしプラスの財産よりマイナスの財産のほうが多い場合は、「相続放棄」という選択肢も検討することになります。
まとめ:相続税いくらから親子でかかるかの最終チェックと専門家への相談

ここまで、相続税の基本から具体的な計算、節税対策、手続きの流れまで、網羅的に解説してきました。最後に、この記事の要点をリストで確認し、専門家へ相談する重要性についてお伝えします。
- 相続税がかかるかの第一関門は「基礎控除」
- 基礎控除の計算式は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」
- 子供一人だからいくらまで、という個別の非課税枠はない
- 基礎控除額以下なら相続税はゼロで申告も不要
- 銀行預金や現金など財産の種類を問わず合計額で判断する
- 亡くなる直前の贈与は相続財産に加算されることがある
- 生命保険金には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠がある
- 小規模宅地等の特例を使えば土地の評価額を最大80%減額できる可能性がある
- 具体的な税額は遺産の分け方(遺産分割)によって変わる
- 配偶者には「1億6,000万円まで非課税」という強力な特例がある
- 不動産など評価が難しい財産がある場合は専門家への相談が安心
- 申告が必要な場合の期限は「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」
- 申告期限までに遺産分割がまとまらないと節税特例が使えず損をする
- 名義預金や不動産の自己評価は税務調査で指摘されやすい要注意ポイント
- 相続税いくらから親子でかかるかの不安は事前の知識と準備で解消できる
もし、少しでも「うちのケースは複雑かも」「計算に自信がないな」と感じたら、無理せず税理士などの専門家に相談することをお勧めします。相談料はかかりますが、間違った申告をして後から追徴課税や延滞税を取られるリスクや、節税のチャンスを逃す損失を考えれば、結果的に安く済むことも多いのです。
初回の相談は無料、という事務所もたくさんありますから、まずは気軽に問い合わせてみてはいかがでしょうか。相続税いくらから親子でかかるか、その最終的な答えと最善の対策は、プロの目で財産全体を正確に評価して初めて見えてくるものなのです。

お疲れ様でした!相続税の基本から具体的な計算、そして節税や手続きまで、本当にたくさんの情報でしたね。でも、これだけの知識があれば、もう漠然とした不安に悩まされることはないはずです。大切なのは、慌てず、そして家族で話し合うこと。この記事が、皆さんの「相続」という大きな一歩を、確かなものにするお手伝いができれば、これほど嬉しいことはありません。
▼あわせて読みたい関連記事▼
不動産の評価額はどう決まる?相続や売買で損しないための全知識

お気軽にご相談ください
相続は100人いれば、100通り
唯一無二の最適な相続をご提案いたします
CONTACT
専門家やえさん

- 専門家やえさん
-
堀川 八重(ほりかわ やえ)
大阪不動産・FPサービス株式会社 代表
15年以上にわたり1,500組を超えるご家族の相続や不動産のお悩みに、専門家として寄り添ってまいりました。私の信条は、法律や数字の話をする前に、まずお客様ご家族の歴史や言葉にならない想いを丁寧に「聞く」こと。信頼できる各分野の専門家チームと共に、皆様が心から安心できる最善の道筋をオーダーメイドでご提案します。一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。
最新の投稿
 お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説
お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説 相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説
相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説 お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例
お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例 お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説
お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説






