「遺族年金を受け取ることになったけれど、これって確定申告は必要なの?」「確定申告で遺族年金は雑所得として扱われるのかしら?」と、税金に関する手続きで不安に感じていませんか。特に、年金以外の収入がある場合や、遺族年金と他の年金を一緒に受け取っていると、どうすればいいのか迷ってしまいますよね。
結論から言うと、遺族年金は非課税所得のため、原則として確定申告は不要ですし、雑所得にもなりません。ただし、遺族年金受給者でも確定申告が必要な場合があったり、医療費控除などで税金が戻ってくる可能性があったりするケースでは注意が必要です。確定申告をしないとどうなるのか、住民税の申告はどうすればいいのか、といった点も気になるところだと思います。
この記事では、確定申告と遺族年金、そして雑所得の関係について、遺族厚生年金の場合も含め、確定申告の書き方のポイントから申告が必要なケースまで、専門家の視点から分かりやすく解説しますね。
この記事のポイント
- 遺族年金が確定申告でどのように扱われるか
- 遺族年金受給者で確定申告が必要になる具体的なケース
- 確定申告が不要でも住民税の申告が必要な場合
- 確定申告をしない場合に考えられること

こんにちは、やえです!
大切なご家族を亡くされたばかりで、お金や手続きの話は頭が痛いかもしれませんね。でも、税金の話は後回しにするとかえって大変なことも。遺族年金と確定申告の関係は、一見複雑そうに見えますが、基本的なポイントさえ押さえておけば大丈夫ですよ。
この記事で、あなたの不安が少しでも軽くなるよう、しっかりサポートさせていただきますね!
確定申告で遺族年金は雑所得になるか解説

遺族年金は雑所得になりますか
まず、一番気になるポイントからお話ししますね。遺族年金は雑所得にはなりません。なぜなら、遺族基礎年金や遺族厚生年金は、残されたご遺族の生活を守るという大切な目的のために支給されるものであり、法律によって所得税がかからない「非課税所得」と定められているからです。
確定申告で計算する「所得」には、給与所得や事業所得、そして老齢年金などが該当する「雑所得」など様々な種類があります。雑所得は、他の9種類の所得のいずれにも当てはまらない所得を指し、公的年金等のほか、副業による所得などがこれに該当します。
しかし、遺族年金はこれらのどの所得にも分類されません。したがって、確定申告書を作成する際も、遺族年金の金額を収入や所得の欄に記入する必要は一切ないんです。これはとても重要なポイントなので、ぜひ覚えておいてくださいね。
根拠となる法律
遺族年金が非課税であることは、国民年金法第25条や厚生年金保険法第41条で「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、これを課することができない」と定められています。
さらに所得税法第9条でも、非課税とされる所得として具体的に挙げられています。公的な機関の情報も確認しておくと、より安心できますね。
(参照:国税庁「No.1604 遺族の方に支給される公的年金等」)
遺族年金は確定申告必要か

前述の通り、遺族年金は非課税所得です。そのため、受け取っている収入が遺族年金のみである場合は、確定申告は必要ありません。
確定申告は、1年間の所得(1月1日から12月31日まで)を計算し、それに対する所得税額を確定させて納税するための一連の手続きです。遺族年金には所得税がかからないため、申告する対象の所得がそもそも存在しない、ということになります。
毎年2月16日から3月15日に行われる確定申告の時期に、「自分も申告しなくては」と焦る必要はないので、ご安心ください。
ただし、これはあくまで「収入が遺族年金だけ」の場合です。他の所得がある場合は話が変わってくるので、注意が必要ですよ。その点については、後ほど詳しく解説しますね。
遺族年金は年収に入るのか
「遺族年金は年収に入るのか?」というご質問もよくいただきます。これは非常に重要なポイントで、「税法上」と「社会保険上」で扱いが異なるため、注意が必要です。
税法上の扶養の場合
税法上の観点から言うと、遺族年金は課税対象の「年収(所得)」には含まれません。
例えば、配偶者控除や扶養控除の対象になれるかどうかを判断する際には、合計所得金額が48万円以下(給与収入のみなら103万円以下)であることが基準となります。
この「合計所得金額」の計算に、非課税である遺族年金の額は含まれないのです。そのため、遺族年金を受け取っていることで、ご家族の税法上の扶養から外れてしまう心配は基本的にありません。
社会保険上の扶養の場合
社会保険の扶養には注意が必要
一方で、健康保険などの社会保険上の扶養は基準が異なります。社会保険の扶養を判断する際の「年収」には、遺族年金が含まれるのが一般的です。
年収の基準額(60歳未満は130万円、60歳以上は180万円が目安)を超えると、ご家族の健康保険の扶養から外れ、ご自身で国民健康保険などに加入する必要が出てくる場合があります。この点は、ご家族がお勤めの会社の健康保険組合や、日本年金機構などに確認することをおすすめします。
(参照:日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、されたときの手続き」)
遺族厚生年金の確定申告について

遺族年金には、働き方などに応じて「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類がありますが、どちらも税法上の扱いは同じです。つまり、会社員や公務員だった方の遺族が受け取る遺族厚生年金のみを受給している場合も、確定申告は原則として不要です。
遺族基礎年金は国民年金から、遺族厚生年金は厚生年金から支給されるという違いはありますが、どちらも残されたご遺族の生活保障という目的は変わりません。そのため、税法上は同じ非課税所得として扱われます。
「厚生年金だから何か特別な手続きが必要かも?」と心配される方もいらっしゃいますが、税金の面では基礎年金との違いはありませんので、安心してくださいね。
年金の雑所得はいくらまでなら確定申告不要?
ここで少し、遺族年金と混同されやすい「老齢年金」の話をしますね。ご自身が長年保険料を納めて受け取る老齢基礎年金や老齢厚生年金は、遺族年金とは違って課税対象となり、「公的年金等に係る雑所得」に分類されます。
この公的年金については、受給者の負担を減らすための「確定申告不要制度」が設けられています。具体的には、以下の2つの条件を両方満たす場合、確定申告が不要になります。
公的年金等の確定申告不要制度の条件
- 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であること
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であること
この制度を適用する際、非課税である遺族年金は、この400万円の収入金額に含める必要はありません。例えば、65歳以上の方で、老齢厚生年金の収入が200万円、遺族厚生年金の収入が100万円、他に所得がない場合、判断基準となるのは老齢厚生年金の200万円だけです。これは400万円以下なので、確定申告は不要となります。この違いをしっかり理解しておくことが大切です。
遺族年金受給者で確定申告が必要な場合
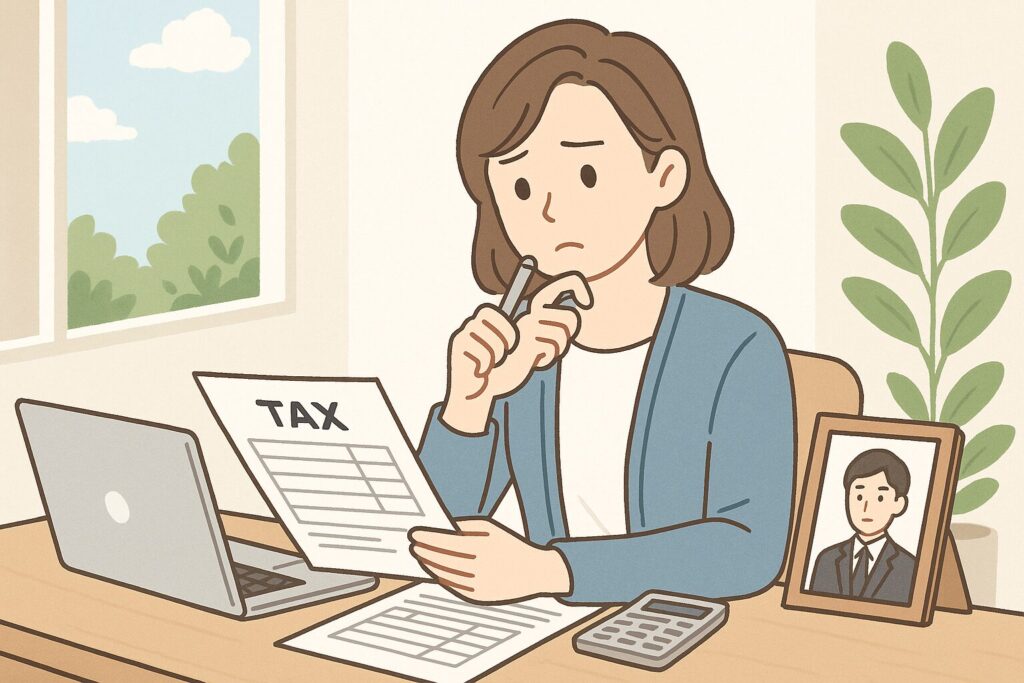
これまで「遺族年金は確定申告が不要」と説明してきましたが、もちろん例外もあります。遺族年金を受け取っていても、他に所得がある場合など、特定のケースでは確定申告が必要になります。
具体的にどのような場合に申告が必要になるのでしょうか。状況は人それぞれですが、大きく分けると以下の3つのパターンが考えられます。ご自身がどれかに当てはまらないか、確認してみましょう。
| パターン | 具体的な内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 義務として申告が必要な場合 | 遺族年金以外の所得(給与、パート、事業、不動産、課税対象の個人年金など)があり、その所得金額が一定額を超える場合。または、ご自身の老齢年金など課税対象の公的年金を受け取っており、確定申告不要制度の対象外となる場合。 | 申告しないとペナルティの対象になります。 |
| 申告した方が得になる場合 | 多額の医療費を支払った(医療費控除)、ふるさと納税をした(寄附金控除)、生命保険料を支払った(生命保険料控除)などで、所得税の還付を受けたい場合。 | 申告は任意ですが、手続きをしないと税金は戻ってきません。 |
| 住民税の申告が必要な場合 | 所得税の確定申告は不要でも、遺族年金以外に少しでも所得がある場合。 | 所得税とは別の手続きで、市区町村への申告が必要です。 |
これらのケースに当てはまる方は、確定申告の手続きが必要になる可能性があります。次の章で、それぞれのケースについて、さらに詳しく見ていきましょう。

どうでしょう、少し整理できてきましたか?「遺族年金だけなら申告不要」というのが大原則です。でも、「もし自分に他の収入があったら…?」と気になりますよね。
手続きが難しいと感じるかもしれませんが、ポイントさえ押さえれば大丈夫ですよ。特に税金が戻ってくる「還付申告」は、知っていると得をする大切な制度。見逃さないように、しっかりチェックしていきましょうね!
確定申告と遺族年金、雑所得の注意点

遺族年金で収入がある場合の確定申告
ここでの「収入」とは、遺族年金以外の課税対象となる収入のことです。最も代表的な例が、ご自身の老齢年金(老齢基礎年金や老齢厚生年金)も一緒に受け取っているケースです。
この場合、遺族年金は非課税なので計算に含めず、課税対象である老齢年金の収入だけで確定申告が必要かどうかを判断します。前述した「確定申告不要制度」の条件(公的年金収入400万円以下、かつ、その他の所得20万円以下)に当てはまらなければ、確定申告が必要です。
例えば、65歳以上の方で、老齢基礎年金を年間70万円、老齢厚生年金を年間80万円(合計150万円)、そして遺族厚生年金を年間80万円受け取っているとします。
この場合、確定申告の要否を判断するのは、課税対象である老齢年金の合計150万円だけです。この金額は400万円以下なので、他に20万円を超える所得がなければ申告は不要となります。
年金以外の収入がある場合の確定申告
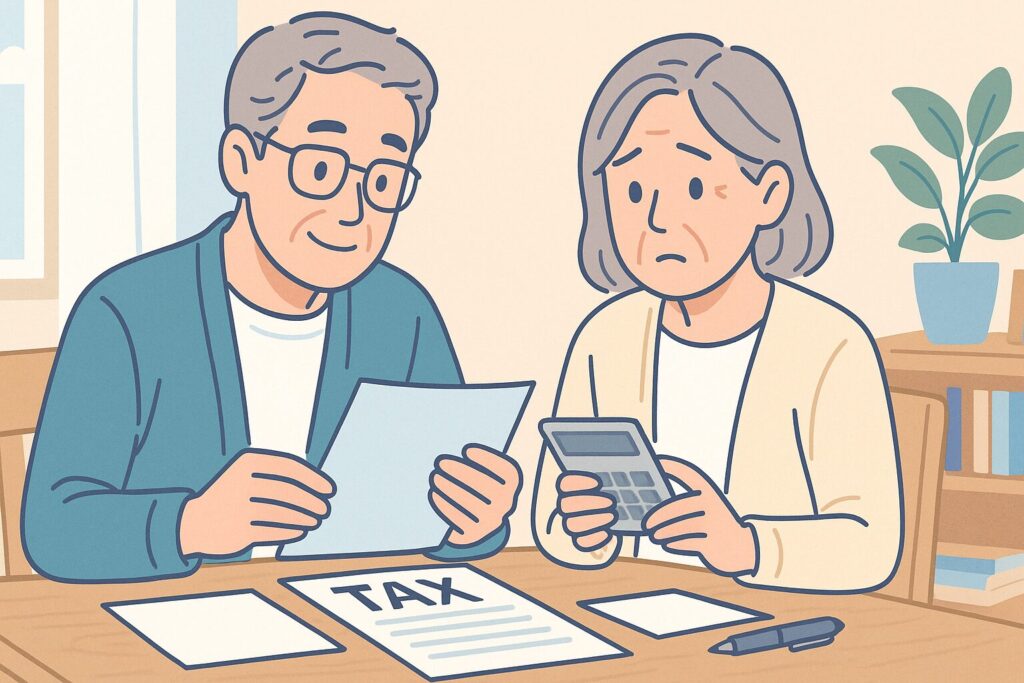
パートやアルバイトによる給与所得、個人事業による事業所得、アパート経営による不動産所得など、年金以外の所得がある場合は、確定申告が必要になる可能性が高まります。
これらの所得金額(収入から必要経費等を差し引いた後の金額)の合計が20万円を超える場合は、原則として確定申告をしなければなりません。ここでも、遺族年金の額は計算に含める必要はありません。あくまで、課税対象となる所得だけで判断します。
確定申告が必要になる例
遺族年金を受け取りながら、パートで年間100万円の給与収入があるとします。この場合、給与所得控除(最低55万円)を差し引いた給与所得は45万円となります。この45万円が20万円を超えているため、確定申告が必要です。
よくある誤解として、「パート先で年末調整を受けているから確定申告は不要」と考えてしまうケースがあります。しかし、年末調整はあくまでその給与所得についてのみの手続きです。
他に20万円を超える所得がある場合や、医療費控除などを受けたい場合は、ご自身で確定申告を行う必要がありますので注意してくださいね。
遺族年金の確定申告で医療費控除を受ける
これは、申告義務はないけれど、申告した方がお得になる代表的なケースです。ご自身や生計を同じにするご家族のために支払った1年間の医療費が10万円(または総所得金額等の5%)を超えた場合、確定申告で「医療費控除」を申請すると、納めすぎた所得税が戻ってくる(還付される)可能性があります。
この還付を受けられるのは、課税対象の所得があり、所得税を納めている方です。例えば、遺族年金を受け取りながらパートで働いていて、給与から所得税が源泉徴収されている場合や、課税対象の老齢年金から所得税が天引きされている場合などが対象になります。
収入が非課税の遺族年金のみの方は、そもそも納めている所得税がないため、還付を受けることはできません。
還付申告は5年間可能!
医療費控除のほかにも、ふるさと納税をした際の「寄附金控除」や、生命保険料を支払っている場合の「生命保険料控除」なども、確定申告をすることで税金の負担を軽くできる場合があります。
このような還付を受けるための申告を「還付申告」といい、通常の確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間行うことができます。もし過去の分で申告し忘れているものがあれば、今からでも間に合うかもしれませんよ。
遺族年金の確定申告の書き方

もし確定申告が必要になった場合、書き方で一番注意すべき点は、確定申告書の収入金額や所得金額の欄に、遺族年金の金額を記入しないことです。これは何度もお伝えしたい重要なポイントです。
申告書には、給与所得や公的年金等に係る雑所得など、課税対象となる所得だけを記入します。もし間違って非課税である遺族年金の額を収入に含めてしまうと、所得が過大に計算され、余分な税金を納めることになってしまうので、十分に注意してください。
初めての方や手続きに不安がある方は、国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」を利用するのがとても便利です。画面の案内に従って、源泉徴収票などの内容を入力していくだけで、自動的に税額が計算され、申告書を作成できます。マイナンバーカードとスマートフォンがあれば、e-Tax(電子申告)を使って、自宅からオンラインで提出まで完結できますよ。
(参照:国税庁 確定申告書等作成コーナー)
年金受給者が確定申告しないとどうなる?
確定申告の義務があるにもかかわらず、正当な理由なく期限(原則3月15日)までに申告をしなかった場合、いくつかのペナルティが課される可能性があります。
まず、本来納めるべき税額に加えて「無申告加算税」が課されます。これは原則として、納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合で計算されます。(ただし、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合は5%に軽減されます)。
さらに、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて「延滞税」も発生します。税率は年によって変動しますが、納期限の翌日から2か月を経過する日までは比較的低い利率、それ以降は高い利率が適用されます。
ペナルティは重い負担に
税務署の調査を受けてから期限後申告をしたり、税務署から納税額の決定を受けたりすると、これらのペナルティはさらに重くなることがあります。また、意図的に所得を隠していたと判断された場合には、「重加算税」というさらに重い税金が課されることもあります。申告義務がある場合は、必ず期限内に手続きを済ませるようにしましょう。
もちろん、収入が遺族年金のみの方など、申告義務がない場合はこれらのペナルティの心配はありません。
年金受給者が住民税申告しないとどうなる?

所得税の確定申告が不要な方でも、住民税の申告は別途必要になるケースがあるので注意が必要です。これは見落としがちなポイントです。
所得税の確定申告をした場合は、その情報が税務署からお住まいの市区町村にデータで送られるため、改めて住民税の申告をする必要はありません。しかし、確定申告をしておらず、かつ遺族年金以外に少しでも所得がある場合(例:所得が20万円以下のため確定申告は不要だが、パート収入が多少ある場合など)は、市区町村の役所に住民税の申告をする必要があります。
もしこの申告をしないと、市区町村があなたの正確な所得状況を把握できません。その結果、国民健康保険料(税)や後期高齢者医療保険料、介護保険料などが正しく計算されなかったり、非課税証明書や所得証明書といった行政サービスに必要な書類が発行できなかったりするといった不都合が生じる可能性があります。
所得税の確定申告が不要な場合でも、「住民税の申告は必要か?」という視点を持つことが大切です。不明な点は、お住まいの市区町村の担当窓口に一度確認してみることをおすすめします。
確定申告と遺族年金についてよくあるご質問FAQ
ここでは、皆さんが特に疑問に思う点をQ&A形式でまとめてみました!
-
遺族年金と自分のパート収入を合わせると130万円を超えます。扶養から外れますか?
-
社会保険の扶養は外れる可能性が高いです。税法上の扶養と社会保険の扶養は基準が異なり、後者の年収計算には遺族年金が含まれるため、年収130万円の壁を超えると扶養から外れることが一般的です。
-
遺族年金と老齢年金を両方もらっている場合、確定申告はどうなりますか?
-
課税対象の老齢年金の額で判断します。老齢年金の収入が400万円以下で、かつ他の所得が20万円以下なら申告不要です。遺族年金の額は計算に含める必要はありません。
-
亡くなった父の準確定申告に、遺族年金は含める必要はありますか?
-
準確定申告に遺族年金を含める必要はありません。準確定申告は亡くなった方の所得税を計算する手続きであり、遺族年金は亡くなった方の所得ではなく、ご遺族の非課税所得だからです。
-
確定申告の書類に遺族年金の金額を書く欄はありますか?
-
確定申告書に遺族年金の金額を記入する欄はありません。遺族年金は非課税所得であり、所得税の計算対象外だからです。間違って他の収入欄に記入しないよう注意しましょう。

ここまでお読みいただき、ありがとうございます!遺族年金と確定申告の関係、だいぶスッキリしたのではないでしょうか。
大切なのは、「自分の場合はどうなのか?」を正しく知ることです。もし分からないことがあれば、一人で抱え込まずに税務署やお住まいの役所に相談するのも一つの手ですよ。
最後のまとめで、今日お話しした内容をもう一度おさらいしましょうね!
確定申告遺族年金雑所得のポイントまとめ

最後に、この記事の重要なポイントをリストで確認しましょう。
- 遺族年金は所得税がかからない非課税所得
- 遺族年金は雑所得には分類されない
- 収入が遺族年金のみの場合は確定申告は不要
- 遺族年金は税法上の年収(所得)には含まれない
- 社会保険の扶養を判断する際の年収には遺族年金が含まれる場合がある
- 遺族厚生年金も遺族基礎年金と同様に非課税で申告不要
- 課税対象の老齢年金などには確定申告不要制度がある
- 遺族年金受給者でも他の所得が20万円を超えると確定申告が必要
- パートなどの給与所得がある場合は確定申告が必要になることがある
- 医療費控除などで税金の還付を受けるためには確定申告(還付申告)が必要
- 確定申告書に遺族年金の金額を記入してはいけない
- 申告義務があるのに無申告だと無申告加算税や延滞税がかかる
- 所得税の確定申告が不要でも住民税の申告が必要な場合がある
- 住民税の申告をしないと国民健康保険料の算定などに影響が出る可能性がある
- 不明な点は税務署やお住まいの市区町村に確認することが大切
▼あわせて読みたい関連記事▼
- 遺族年金パート収入いくらまで?税金と扶養に注意して働く方法
- 年金もらいながらパート健康保険は損?106万円・130万円の壁を専門家が徹底解説!
- 遺族年金65歳になったら手続き|金額は減る?専門家が解説
- 【相続税いくらから親子でかかる?】専門家が相続税の早見表や基礎控除・計算方法をわかりやすく解説
- 【相続放棄手続きどこで?】家庭裁判所での流れを専門家が解説

お気軽にご相談ください
相続は100人いれば、100通り
唯一無二の最適な相続をご提案いたします
CONTACT
専門家やえさん

- 専門家やえさん
-
堀川 八重(ほりかわ やえ)
大阪不動産・FPサービス株式会社 代表
15年以上にわたり1,500組を超えるご家族の相続や不動産のお悩みに、専門家として寄り添ってまいりました。私の信条は、法律や数字の話をする前に、まずお客様ご家族の歴史や言葉にならない想いを丁寧に「聞く」こと。信頼できる各分野の専門家チームと共に、皆様が心から安心できる最善の道筋をオーダーメイドでご提案します。一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。
最新の投稿
 お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説
お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説 相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説
相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説 お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例
お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例 お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説
お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説






