「遺言書一人に相続書き方」について調べていらっしゃるのですね。きっと、ご自身の財産を特定の誰か、例えば長年連れ添った配偶者の方や、事業を継いでくれるお子様、はたまた献身的に介護をしてくれた方などに、すべて託したいとお考えのことでしょう。
そういった時、「遺言書で全ての財産を相続させる書き方は?」「そもそも遺言書で全財産を子供に与えることはできますか?」といった疑問が浮かびますよね。
簡単な遺言書の書き方や、遺言書書き方例文を見てみても、いざご自身のこととなると、本当にこれで良いのかなと不安になりますよね。
また、他の相続人である兄弟から「そんなの聞いていない!」と揉め事が起きないか心配になったり、「遺言書全財産が無効になることはないかしら?」と心配になる方もいらっしゃいます。
特に、遺言書一人に相続する場合、他の相続人が持つ遺留分という権利が気になりますよね。自筆や手書きで遺言書書き方についてお悩みの皆様へ、今回の記事でそういった不安を一つずつ解消していきますので、安心して読み進めてみてくださいね。
この記事のポイント
- 遺言書で特定の誰か一人に全財産を相続させる方法がわかります。
- 遺言書が無効になってしまう原因とその対策について理解が深まります。
- 特定の相続人に財産を集中させる際の遺留分への配慮の重要性がわかります。
- ご自身の状況に合わせた遺言書の作成方法や、トラブル回避のポイントを把握できます。
遺言書で一人に全財産を相続させる書き方とは

簡単な遺言書の書き方を例文付きで解説
遺言書とは、ご自身の財産の相続について、どのように分けるかを記した最後の意思表示となります。特定の相続人一人にすべての財産を託したい場合、その意思を明確に記載した遺言書を作成することが大切です。
ここでは、これから遺言書を書いてみようとお考えの方に向けて、簡単な遺言書の書き方を例文を交えてご説明します。
遺言書を書く際に必要な3つの基本要素
・遺言書の全文
・作成した日付
・ご自身の氏名と押印
これらの要素は、ご自身で手書きされる自筆証書遺言の場合、すべて自筆でなければなりません。もし、パソコンで作成したり、誰かに代筆してもらったりすると、せっかく作った遺言が無効になってしまうため注意が必要です。
【補足】自筆証書遺言書保管制度について
以前はご自身で保管しなければならなかった自筆証書遺言ですが、今では法務局に預けることができる制度があります。これを利用すれば、紛失や偽造、改ざんのリスクを避けることができます。 (参考:法務省「自筆証書遺言書保管制度について」)
遺言書で全ての財産を相続させる書き方は?
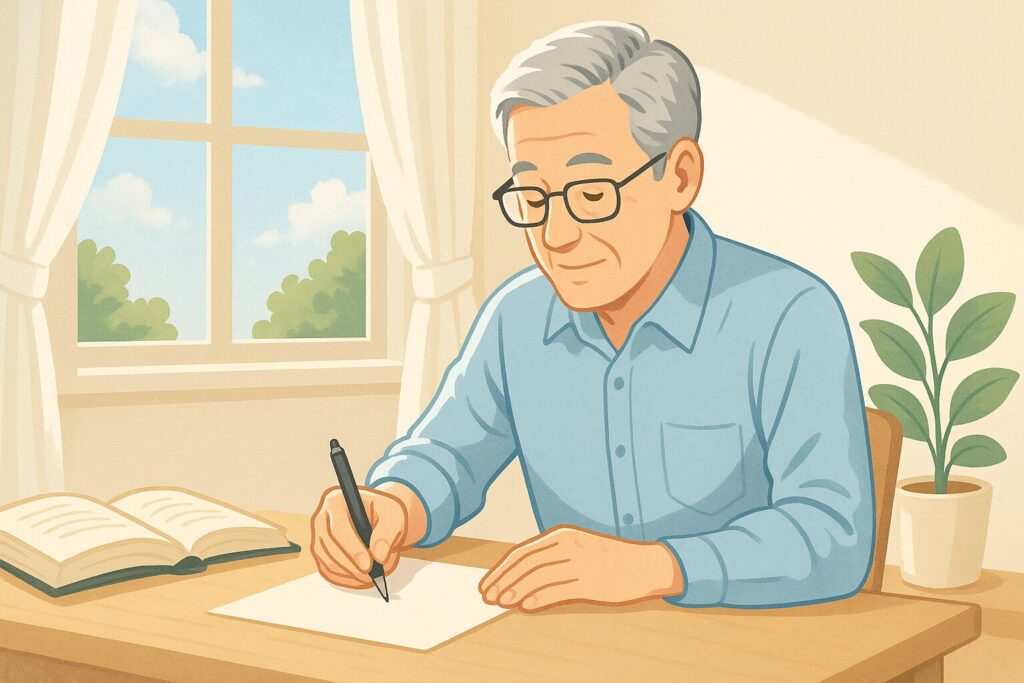
「遺言書で全ての財産を相続させる」という意思を記載する際には、誰がどの財産を相続するのかを具体的に書くことが大切です。曖昧な表現では、遺言者の意図が不明確になり、後から遺産をめぐって相続人同士でトラブルに発展してしまう恐れがあります。
例えば、複数の不動産や預貯金がある場合、それぞれの詳細情報を明記することをおすすめします。そうすることで、相続手続きをスムーズに進めることができますし、遺言書に記載されていない財産が後から見つかった場合でも、「その他一切の財産を相続させる」といった一文を入れておけば、遺産分割協議の必要がなくなります。
「その余の一切の動産類」という表現に注意!
特定の財産を記載したうえで、「その余の一切の動産類を〇〇に相続させる」といった表現を使うと、後から見つかった不動産や債権などがその範囲に含まれないと解釈され、別途遺産分割協議が必要になる可能性があります。
「全財産」とひとくくりにせずに、財産の種類や所在地、口座番号などを具体的に記載することで、より確実な遺言になります。
遺言書書き方で押さえるべき自筆と手書きのポイント
遺言書を手書きで作成する自筆証書遺言には、法的に有効とされるための厳格なルールがあります。これらを守らないと、せっかく書いた遺言が無効となってしまうため、十分に注意する必要があります。
自筆証書遺言の作成ポイント
1. 遺言書の全文をご自身の手書きで書く。
2. 遺言書を作成した日付を正確に書く。「令和○年○月吉日」といった曖昧な表現はNGです。
3. ご自身の氏名を自筆で書き、押印する。印鑑は実印である必要はありませんが、認印やスタンプ印は避けた方が安全です。
また、遺言書が複数枚にわたる場合は、改ざんや差し替えを防ぐために、契印や割印を押すことが望ましいです。これにより、書類の連続性や関連性を示すことができます。これらのルールは、遺言書の有効性を保つために非常に重要な点です。
私であれば…
遺言書の作成は、ご自身の最後の意思を伝えるとても大切な手続きです。もし少しでも不安を感じることがあれば、専門家にご相談いただくのが一番安心です。
遺言書で全財産を子供に与えることはできますか?

はい、できます。遺言書で特定の子供一人に全財産を与えることは法的に可能です。ご質問の「遺言書で全財産を子供に与えることはできますか?」という問いへの答えは「はい、可能です」となります。
例えば、ご自身が経営している会社の事業を継いでくれるお子様や、長い間ご自身の面倒を見てくれたお子様に多くの財産を譲りたいと考えることは自然なことですよね。
ただし、この場合、他の相続人(ご自身の配偶者や他の子供)の「遺留分」を侵害してしまう可能性があります。遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に最低限保障されている遺産の取り分のことです。
遺言書によってこの権利が侵害された場合、権利を持つ相続人は、遺留分侵害額に相当する金銭を請求することができます。そのため、トラブル回避のためには、遺留分への配慮が不可欠になります。
遺留分侵害額請求のトラブルを避けるために
遺言の内容を事前に相続人に説明しておく、遺留分に相当する額の財産を渡すよう遺言書に記載しておく、付言事項で感謝の気持ちを伝えるといった工夫が有効です。
遺言書全財産を相続させる際の注意点
特定の誰か一人に遺言書全財産を相続させる際には、いくつかの注意点があります。これらを理解して遺言書を作成することが、相続が開始された後のトラブルを未然に防ぐ上でとても大切になってきます。
トラブルを避けるための注意点
・遺留分に配慮した内容にする
・付言事項で遺言の理由や想いを伝える
・遺言執行者を指定しておく
・財産の詳細を明確にする
特に、付言事項は法的な効力はありませんが、なぜ特定の誰かに全財産を託すことにしたのか、ご自身の想いや感謝の気持ちを伝えることができます。これにより、他の相続人が感情的になるのを防ぎ、遺産分割の話し合いがスムーズに進むことも期待できます。
また、遺言執行者を指定しておくことで、相続手続きが円滑に進みます。遺言執行者は、遺言書の内容を実現するための手続きを行う役割を担います。
遺言書一人に相続書き方をケース別に詳しく解説

遺言書書き方で全財産を妻に渡す際のポイント
ご自身の財産を妻に全財産渡したいとお考えの場合、「遺言書書き方」で全財産を妻に相続させるという意思を明確に記載する必要があります。
夫婦には、お互いを支え、協力し合って長い人生を歩んできたという歴史がありますよね。だからこそ、ご自身が亡くなった後も、妻が安心して暮らしていけるようにしてあげたいと思うのは当然のことです。
遺言書の例文としては、「遺言者の有するすべての財産を、妻〇〇に相続させる」といった一文を入れるのが一般的です。これだけでも効力はありますが、より確実に意思を伝えるためには、遺産の内容を具体的に記載しておくことをおすすめします。
不動産や預貯金の詳細を記載しておくことで、妻が一人で相続手続きを行う際の負担を軽減することができます。
また、遺留分に配慮して、他の相続人に一定の財産を渡すのか、それとも付言事項で遺留分侵害額請求を行わないようお願いするのか、ご自身の状況に合わせて検討することが大切です。
遺言書書き方で全財産を子供に渡す際の注意点

遺言書書き方で全財産を子供に相続させる場合、特に注意したいのは、他の相続人との間に生じうるトラブルです。ご自身の遺言の内容が、他の相続人にとって想定外だった場合、感情的な対立を生んでしまう可能性があります。
例えば、ご自身が経営している会社の事業承継を考えて、その財産を特定の子供一人に相続させたいと作成したとします。この時、他の子供たちは「なぜ自分だけ何ももらえないのか」と不満を持つかもしれません。
この問題を避けるためには、以下のポイントを検討してみてはいかがでしょうか。
トラブル回避のための具体的な工夫
・遺言書に、特定の子供に全財産を渡すに至った説得的な理由を記載する。
・遺留分に相当する額の財産を他の子供にも渡すように遺言する。
・生前に相続について相続人と話し合い、理解を求めておく。
これらの工夫は、単に法的な手続きを進めるだけでなく、ご自身の家族が相続後に円満な関係を維持していくためにも重要です。
遺言書一人に相続する場合の兄弟間のトラブル
遺言書一人に相続させる場合、兄弟間でトラブルになるケースは少なくありません。兄弟には遺留分がないため、遺言書によって相続の権利を完全に失ってしまう可能性があります。
遺言にそういった内容が記載されていれば、兄弟は「なぜ自分は何ももらえないのか」と感じ、不満が蓄積しやすくなります。
具体例として、長男が家業を継ぎ、全財産を相続する場合を考えてみましょう。他の兄弟は、家業に携わっていなかった場合でも、遺産を受け取ることを期待しているかもしれません。
しかし、遺言書に「全財産を長男に相続させる」と記載されていれば、他の兄弟は遺産を一切受け取ることができません。
このような事態を防ぐためには、付言事項を活用し、「長男に家業を任せるために財産を集中させることにした」など、遺言の意図を丁寧に説明することで、兄弟の理解を求めることが期待できます。

相続問題は、家族の歴史そのものです。 「なぜ、私だけ...」という感情は、金銭的な問題以上に深刻な溝を生むことがあります。遺言書で感謝の気持ちを伝えることは、後悔のない終活の一歩となります。
遺言書一人に相続させると遺留分はどうなる?

遺言書一人に相続させる場合、遺留分を侵害する可能性があります。遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子、直系尊属)に法律で保障された最低限の遺産の取り分です。この権利は、遺言書の内容によっても侵害することができません。
例えば、夫婦と子供が3人いる家庭で、「遺産の全てを長男に相続させる」という遺言があったとします。この場合、長男以外の子供2人と配偶者には、それぞれ遺留分があります。
遺言で遺留分を侵害された相続人は、遺産を受け取った長男に対して、遺留分に相当する金銭を請求する手続きをすることができます。
これを「遺留分侵害額請求」といいます。遺留分の割合は、相続人の関係によって異なりますので、事前にご自身の相続関係を把握しておくことが大切です。
| 相続人 | 遺留分の割合 |
|---|---|
| 配偶者と子 | 配偶者:1/4 子:1/4 |
| 配偶者のみ | 1/2 |
| 子のみ | 1/2 |
| 配偶者と父母 | 配偶者:1/3 父母:1/6 |
| 父母のみ | 1/3 |
| 兄弟姉妹 | なし |
このように、遺留分を考慮せずに遺言書を作成してしまうと、後から金銭の請求をされ、思わぬトラブルに発展する可能性があることを覚えておきましょう。
遺言書全財産を無効にしないための対策
せっかくの遺言書が「遺言書全財産無効」と判断されてしまったら、これまでの努力が水の泡になってしまいますよね。遺言書が無効になる原因は主に以下の3つが考えられます。
遺言書が無効になる主なケース
・方式の不備:自筆証書遺言の場合、全文が自筆でなかったり、日付や氏名、押印が欠けていたりするケースです。
・遺言能力がないと判断される場合:認知症などで判断能力が不十分な時に作成された遺言は無効になる可能性があります。
・内容が公序良俗に反する場合:極端に不公平な内容や、愛人への多額の遺贈などは無効になる可能性があります。
これらの問題を避けるためには、まず、遺言書の書き方を民法で定められた形式に沿って正しく作成することが重要です。また、遺言能力が心配な場合は、医師の診断書を添付したり、公正証書遺言の作成を検討したりすることをおすすめします。
公正証書遺言は、公証人が作成に関与するため、方式の不備で無効になる心配がありません。(参照:日本公証人連合会)
私であれば…
「誰に相続させるか」だけでなく、「なぜその人に相続させるのか」という気持ちを遺言書に込めることで、遺言書が持つ法的効力以上の効果を発揮することがあります。
遺言書一人に相続書き方で悩んだら専門家へ

遺言書一人に相続書き方について悩んだり、不安を感じたりした場合は、専門家に相談することをおすすめします。専門家に相談するメリットは、法的トラブルを未然に防ぎ、ご自身の意思を確実に実現できる点です。
専門家への相談がおすすめなケース
・遺産の額が多岐にわたる
・相続人間の関係が複雑
・事業や農地など、特別な財産がある
・遺言書の作成を急いでいる
また、専門家は遺言書の作成だけでなく、相続税対策や事業承継など、ご自身の状況に合わせた最適なプランを提案してくれます。弁護士や税理士、司法書士といった専門家は、それぞれの分野の知識を活かし、あなたの遺言を実現するためのサポートをしてくれます。
遺言書一人に相続書き方についてよくあるご質問FAQ
-
遺言書で一人に全財産を渡したいのですが、他の相続人から文句を言われませんか?
-
はい、他の相続人から不満が出る可能性はあります。特に、遺留分を持つ相続人からは遺留分侵害額請求をされる可能性があります。付言事項で感謝の気持ちや理由を伝えておくことで、理解を求めることは可能です。
-
遺言書の手続きで、費用はどのくらいかかりますか?
-
ご自身で手書きする自筆証書遺言であれば、費用はほぼかかりません。一方で、公証役場で作成する公正証書遺言の場合は、財産額に応じて手数料がかかります。
-
遺言書が無効になるのはどのような時ですか?
-
遺言書の全文が自筆でない、日付や氏名、押印がないなど、民法で定められた形式を守らなかった場合に無効となります。また、遺言能力がないと判断された場合も無効になることがあります。
-
遺言書作成の際、財産目録は必ず手書きですか?
-
2020年7月10日の法改正により、財産目録についてはパソコンで作成したり、通帳のコピーを添付したりすることが可能になりました。ただし、財産目録の各ページに署名と押印が必要です。
-
遺言書を専門家にお願いする場合、誰に相談すればいいですか?
-
遺言書作成の法的側面については弁護士や司法書士、相続税に関するご相談は税理士にご相談されると良いでしょう。

「大丈夫だろう」と安易に考えていると、残されたご家族が大変な思いをすることもあります。遺言書は、ご自身の想いを形にするだけでなく、大切なご家族への最後の贈り物です。
まとめ:遺言書一人に相続書き方を押さえて安心の未来へ

- 遺言書は、ご自身の財産を特定の誰か一人に相続させるための最も確実な方法です。
- 遺言書の作成にあたっては、全文を手書きで書くなど、民法で定められた書き方のルールを遵守することが不可欠となります。
- 「遺言書全財産無効」とならないよう、方式の不備や遺言能力に注意が必要です。
- 特定の相続人に全財産を渡す場合でも、遺留分を持つ他の相続人に配慮した内容にすることが大切です。
- 遺留分を侵害すると、後から金銭の請求をされるリスクがあるため、事前の対策が重要となります。
- 付言事項を活用し、なぜそのように遺産を分けることにしたのか、ご自身の想いを伝えることで相続人間のトラブルを回避できる可能性があります。
- 遺言執行者を指定しておくと、相続手続きがスムーズに進むことが多いです。
- 夫婦間、兄弟間など、相続人の関係性に応じて適切な遺言の内容を検討することが大切です。
- 遺言の内容に不安がある、複雑な財産がある、といった場合は、専門家に相談することで、安心して遺言書を作成できます。
- 遺言書はご自身の意思を明確にし、残された家族が円満な相続を迎えられるようにするための大切な手続きです。

財産を託す行為は、ご自身の人生の証を次に繋げることです。ご家族の笑顔のために、ほんの少しの勇気を出して、遺言書作成という一歩を踏み出してみませんか。

お気軽にご相談ください
相続は100人いれば、100通り
唯一無二の最適な相続をご提案いたします
CONTACT
専門家やえさん

- 専門家やえさん
-
堀川 八重(ほりかわ やえ)
大阪不動産・FPサービス株式会社 代表
15年以上にわたり1,500組を超えるご家族の相続や不動産のお悩みに、専門家として寄り添ってまいりました。私の信条は、法律や数字の話をする前に、まずお客様ご家族の歴史や言葉にならない想いを丁寧に「聞く」こと。信頼できる各分野の専門家チームと共に、皆様が心から安心できる最善の道筋をオーダーメイドでご提案します。一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。
最新の投稿
 お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説
お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説 相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説
相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説 お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例
お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例 お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説
お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説






