「遺族年金をもらっている人が65歳になったら年金はどうなるの?」、「遺族厚生年金は65歳以降、金額が減るって本当?」…そんな疑問や不安を抱えて、このページにたどり着いたのではないでしょうか。
こんにちは!終活・相続・不動産の専門家、カズです。65歳という節目は、年金の仕組みがガラッと変わる大切なタイミング。遺族年金と自分の年金が両方もらえるのか、もし夫が70歳以上で亡くなった場合はどうなるのか、色々な情報が飛び交っていて混乱してしまいますよね。
特に、遺族厚生年金の金額の早見表や65歳以上の平均額、具体的なシミュレーションが見たい、というお声もよくいただきます。このままでは、知らないうちに損をしてしまうかも…なんて考えると、夜も眠れなくなってしまいます。
でも、ご安心ください。この記事で、あなたのモヤモヤをスッキリ解消します!
この記事のポイント
- 65歳になると遺族年金の受け取り方がどう変わるか
- 遺族年金と自分の老齢年金を両方もらえる場合の計算方法
- モデルケース別の具体的な年金シミュレーション
- 手続きの注意点や知っておくべきポイント

65歳は年金の大きな転換期。遺族年金とご自身の老齢年金の仕組みがどう変わるのか、不安に感じるのは当然です。この記事では、制度の基本から具体的な金額の計算方法まで、一歩ずつ丁寧に解説していきます。まずは正しい知識を身につけることが、将来の安心への第一歩ですよ。
遺族年金65歳になったら手続きの基本知識

65歳になったら遺族年金はどうなるの?
こんにちは!終活・相続の専門家、カズです。さて、早速ですが核心の部分からお話ししますね。これまで遺族年金を受け取っていた方が65歳になると、年金の受け取り方にいくつかの変化が生じます。一番大きな変更点は、「ご自身の老齢年金を受け取る権利」が発生することです。
これにより、年金の受け取り方が一本ではなくなり、ご自身の年金と遺族年金を調整しながら受け取ることになります。お客様からも「手続きが複雑そうで…」というお声をよくいただきますが、ポイントさえ押さえれば大丈夫ですよ。
65歳で変わる主なポイント
- ご自身の「老齢基礎年金」の支給が開始される
- 遺族厚生年金に上乗せされていた「中高齢寡婦加算」が終了する
- ご自身の「老齢厚生年金」と「遺族厚生年金」の金額が調整される
特に重要なのが、3番目の調整です。基本的にはご自身の老齢厚生年金が優先的に支払われ、遺族厚生年金との差額分を受け取る形になります。具体的な計算方法は後ほど詳しく解説しますので、まずは「65歳からは自分の年金がメインになるんだな」とイメージを持っていただければと思います。
【Q&A】遺族年金のよくある質問

-
65歳になる月の何日から年金の仕組みが変わりますか?
-
65歳の誕生日の前日が含まれる月から変更になります。例えば、誕生日が8月10日なら8月分から、誕生日が8月1日なら7月分から年金の計算方法が変わります。少しややこしいですが、覚えておくと便利ですよ。
-
何か特別な手続きは必要ですか?
-
原則として、ご自身の老齢年金を受け取るための「年金請求書(裁定請求書)」を提出する必要があります。通常は65歳になる3ヶ月前に日本年金機構から書類が送られてきますので、必要事項を記入して提出します。これによって、遺族年金との調整も自動的に行われることが多いです。ご自身の年金額をスマホで簡単に確認する方法もありますので、こちらの年金いくらもらえる調べ方ガイドも参考にしてください。
-
遺族基礎年金も変わりますか?
-
遺族基礎年金は、18歳年度末までのお子さんがいる場合に支給されるものです。そのため、65歳になったという理由だけで遺族基礎年金の支給額や要件が変わることはありません。ただし、お子さんが18歳の年度末を迎えると支給は終了します。
遺族年金は65歳になったら減るって本当?
「65歳になったら遺族年金が減る」という話、よく耳にしますよね。これは半分本当で、半分は少し誤解があるかもしれません。結論から言うと、年金の総額が必ずしも減るとは限りませんが、「遺族厚生年金」という名目での支給額は減るケースが多いです。
どういうことかと言いますと、先ほどお話しした「中高齢寡婦加算」(令和5年度で年額596,300円)が65歳で終了するのが大きな理由です。この加算は、いわば老齢基礎年金がもらえるまでのつなぎのような役割を果たしていました。
私のお客様のA子さん(64歳)も、「来年からガクッと収入が減るんじゃないか」と心配されていました。でも、計算してみると、A子さんご自身の老齢基礎年金が始まるため、年金全体の収入としては、そこまで大きな落ち込みにはなりませんでした。むしろ、ご自身が長年保険料を納めてきた国民年金が形になるわけですから、これは喜ばしいことでもあるんですよね。
ただし、生年月日によっては「経過的寡婦加算」という形で、金額の急激な減少を緩和する措置が取られる場合もあります。いずれにしても、「遺族厚生年金が減る」=「全体の収入が減る」と直結するわけではない、ということを覚えておいてくださいね。
参考情報サイト: 日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」
URL: https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html
遺族年金と自分の年金は両方もらえる?
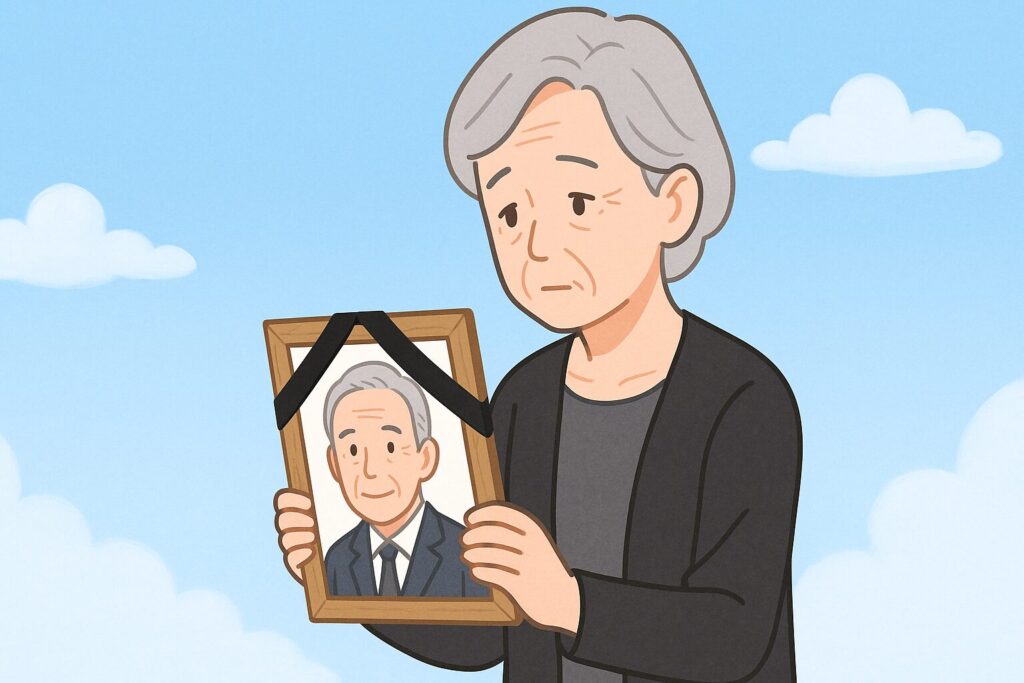
これも非常によくいただく質問です。答えは、「両方もらえますが、全額ずつではありません」というのが正確なところです。65歳以降の年金の受け取り方は、以下の3つの組み合わせで構成されるとイメージすると分かりやすいですよ。
65歳以降の年金の組み合わせ
- ①ご自身の老齢基礎年金:これは全額支給されます。
- ②ご自身の老齢厚生年金:これも全額支給されます。
- ③遺族厚生年金:亡くなった方の老齢厚生年金の3/4が基本ですが、ここから調整が入ります。
具体的な調整方法は、次のようになります。
まず、ご自身の①老齢基礎年金と②老齢厚生年金は、そのまま全額受け取ります。
その上で、③遺族厚生年金の額と、ご自身の②老齢厚生年金の額を比較します。
もし、③遺族厚生年金の額が、ご自身の②老齢厚生年金の額よりも多い場合、その差額分が遺族厚生年金として上乗せで支給されます。
(例:遺族厚生年金が60万円、ご自身の老齢厚生年金が40万円の場合、差額の20万円が遺族厚生年金として支給される。合計の受給額は「老齢基礎年金+老齢厚生年金40万円+差額の遺族厚生年金20万円」となる)
もしご自身の老齢厚生年金の額のほうが多い場合は、遺族厚生年金の支給は0円となり、ご自身の年金(老齢基礎年金+老齢厚生年金)のみを受け取ることになります。これは、ご自身が頑張って働いて保険料を納めてきた分が、きちんとご自身の年金に反映される、という考え方に基づいています。年金だけでは不安という方は、65歳以上の生命保険の必要性についても考えてみると良いでしょう。
遺族厚生年金の65歳以降の仕組みを解説
前述の通り、65歳以降の遺族厚生年金は、ご自身の老齢厚生年金を補うような形で支給される仕組みになっています。この仕組みを理解するために、もう少しだけ深掘りしてみましょう。
以前は、いくつかの選択肢の中から有利なものを選ぶ方式でしたが、現在は「ご自身の老齢年金を優先する」という考え方が基本です。これは、ご自身の保険料納付実績をまずは給付に反映させましょう、という趣旨から来ています。
私、カズがこの仕事で大切にしているのは、制度の「なぜ?」をお伝えすることなんです。なぜこういう仕組みになっているのかが分かると、ただ「損した」「得した」ではなく、ご自身の人生設計に活かせるようになりますからね。ご自身が納めてきた保険料が、まずはご自身の老齢厚生年金としてしっかり返ってくる。その上で、亡くなったパートナーが遺してくれた保障(遺族厚生年金)が生活を支えてくれる、と考えると、少し納得感がありませんか?こうした知識は、元気なうちから終活を始める上でも非常に大切です。
この仕組みは、特に共働きで、奥様ご自身も厚生年金に長く加入していた場合に影響が大きくなります。ご自身の老齢厚生年金が高額になるほど、差額として支給される遺族厚生年金は少なくなる傾向にあります。
夫死亡時の遺族年金は65歳以上でも対象

ご主人様が亡くなられたのが、ご自身が65歳を過ぎてから、というケースももちろんあります。この場合でも、遺族厚生年金の受給要件を満たしていれば、当然対象となりますのでご安心ください。
受給要件は、亡くなったご主人様の年金の加入状況などによって決まります。主な要件は以下の通りです。
遺族厚生年金の主な受給要件(亡くなった方)
- 厚生年金の被保険者である間に死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある方が死亡したとき
- 1級・2級の障害厚生年金を受けとっている方が死亡したとき
これらの要件を満たした上で、亡くなった方によって生計を維持されていた遺族(配偶者や子など)が年金を受け取ることができます。「生計を維持されていた」とは、一般的に同居しており、年収が850万円未満であることが目安となります。
ですので、ご自身が65歳を過ぎてご自身の年金を受け取っていても、年収要件などを満たしていれば、新たに遺族厚生年金を申請することが可能です。これは相続手続きの一部とも言えますので、相続サポートの専門家にご相談いただくのも一つの手です。
夫死亡時の遺族年金は70歳以上でも同様
「夫が70歳や80歳で亡くなった場合、もう遺族年金はもらえないのでは?」というご質問をいただくこともありますが、これもご安心ください。ご主人様が亡くなられた年齢に上限はありません。
前述の受給要件を満たしていれば、たとえご主人様が70歳、80歳、あるいはそれ以上で亡くなられた場合でも、生計を維持されていた配偶者の方は遺族厚生年金を受け取ることができます。
実際に私のお客様でも、80代のご主人様を亡くされた70代後半の奥様が、新たに遺族厚生年金の手続きをされたケースがあります。その方は「もう年金はもらえないものと諦めていた」とおっしゃっていましたが、きちんと手続きをして、ご主人様が遺してくれた保障を受け取ることができ、大変安心されていました。
ただし、注意点として、亡くなった方が老齢年金を「繰下げ受給」している途中で亡くなった場合、遺族厚生年金の計算基礎となるのは、繰下げによる増額分を含まない、本来の年金額(65歳時点の額)となります。この点は少し複雑なので、年金事務所などで確認することをおすすめします。

ここまで、65歳以降の遺族年金の基本的な仕組みについて見てきました。ご自身の年金が優先されること、年金額が調整されることなど、少し複雑に感じられたかもしれませんね。次のセクションでは、皆さんが一番気になる「で、結局いくらもらえるの?」という具体的な金額について、分かりやすく解説していきます。
遺族年金65歳になったら手続き後の金額目安

65歳以上の遺族厚生年金の平均金額は?
さて、ここからはお待ちかねの具体的な金額のお話です。「周りの人は、一体いくらくらいもらっているのかしら?」と気になりますよね。
厚生労働省の調査によると、厚生年金保険(第1号)の遺族年金の平均年金月額は、約8万円強とされています。
ただし、これはあくまで全体の平均値です。遺族年金の金額は、亡くなった方の現役時代の収入(平均標準報酬額)や厚生年金の加入期間によって大きく変わるため、個人差が非常に大きいのが実情です。
私の経験上、ご相談に来られる方のケースを見ても、月額5万円程度の方もいらっしゃれば、15万円以上になる方もいらっしゃいます。平均額はあくまで参考程度に捉え、「ご自身のケースではいくらになるのか」を把握することが豊かな老後資金を計画する上で何より大切ですよ。
参考情報サイト: 厚生労働省「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
URL: https://www.mhlw.go.jp/content/001233406.pdf
遺族厚生年金の金額早見表【65歳以上】

遺族厚生年金の額は、亡くなった方の「老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3」が基本となります。そう言われても、なかなかピンとこないですよね。そこで、亡くなった方の現役時代の平均月収別に、遺族厚生年金の目安額を簡単な早見表にしてみました。
| 亡くなった方の現役時代の平均月収(目安) | 遺族厚生年金の年額(目安) | 遺族厚生年金の月額(目安) |
|---|---|---|
| 20万円 | 約25万円 | 約2.0万円 |
| 30万円 | 約37万円 | 約3.1万円 |
| 40万円 | 約49万円 | 約4.1万円 |
| 50万円 | 約62万円 | 約5.1万円 |
| 60万円 | 約74万円 | 約6.2万円 |
【ご注意】
この表は、厚生年金加入期間を300月(25年)とみなして計算した、あくまで簡易的な目安です。実際の金額は加入期間や加入時期によって変動します。また、これは65歳以降の差額調整が入る前の金額です。
この表の金額と、ご自身の老齢厚生年金の額を比べることで、差額がいくらくらいになるか、大まかなイメージを掴むことができるかと思います。正確な金額は、ぜひ「ねんきん定期便」や年金事務所で確認してくださいね。
夫が年金15万だと遺族年金はいくら?
「亡くなった夫が、月15万円の老齢厚生年金をもらっていました。私の遺族年金はいくらになりますか?」という、具体的なご質問もよく受けます。このケースで考えてみましょう。
遺族厚生年金の基本額は、亡くなった方の老齢厚生年金額の4分の3です。したがって、
月額15万円 × 3/4 = 月額11.25万円
これが、あなたが受け取る遺族厚生年金の「基準額」になります。
ここからが65歳以降のポイントです。この11.25万円と、あなたご自身の老齢厚生年金の額を比較します。
ケーススタディ
- あなた自身の老齢厚生年金が月額4万円の場合
差額は 11.25万円 - 4万円 = 7.25万円。この7.25万円が遺族厚生年金として支給されます。あなたの年金収入は「ご自身の老齢基礎年金+ご自身の老齢厚生年金4万円+遺族厚生年金7.25万円」となります。 - あなた自身の老齢厚生年金が月額12万円の場合
ご自身の年金額が基準額を上回っているため、差額は発生しません。この場合、遺族厚生年金の支給は0円となり、年金収入は「ご自身の老齢基礎年金+ご自身の老齢厚生年金12万円」のみとなります。
このように、ご自身の年金額によって、実際に受け取る遺族厚生年金の額が変わってくる、というわけですね。遺族年金を受け取りながらパートで働く場合は、収入の壁にも注意が必要です。
遺族年金の金額を65歳以上でシミュレーション

それでは、もう少し具体的な家族モデルでシミュレーションをしてみましょう。終活や相続のご相談を受けていると、こうした具体的なシミュレーションが一番イメージが湧くと好評です。
【モデルケース】
- 夫(死亡時75歳):老齢基礎年金 約6.5万円/月、老齢厚生年金 10万円/月
- 妻(現在65歳):老齢基礎年金 約6.5万円/月、老齢厚生年金 3万円/月(パート主婦だった)
この場合、妻が受け取る年金を計算してみましょう。
1. 夫の遺族厚生年金の基準額を計算
夫の老齢厚生年金10万円 × 3/4 = 7.5万円
2. 妻自身の老齢厚生年金と比較
遺族厚生年金の基準額(7.5万円)は、妻自身の老齢厚生年金(3万円)よりも多いですね。
3. 差額を計算
7.5万円 - 3万円 = 4.5万円
この4.5万円が、妻に「遺族厚生年金」として支給されます。
4. 妻が受け取る年金の合計額
妻の年金収入は、以下の合計になります。
| ①妻の老齢基礎年金 | 6.5万円 |
| ②妻の老齢厚生年金 | 3.0万円 |
| ③差額分の遺族厚生年金 | 4.5万円 |
| 合計月額 | 14.0万円 |
このケースでは、妻は月額14万円の年金を受け取ることになります。もし遺族年金の制度がなければ、妻の年金は月額9.5万円(①+②)だけでした。ご主人様が遺してくれた保障が、月々4.5万円の生活の支えになっていることが分かりますね。ご自身の状況に合わせて、ぜひ一度相続税はいつまでに払うかなども含めて確認してみることをお勧めします。
まとめ:遺族年金65歳になったら手続きを
今回は、65歳になったときの遺族年金について、仕組みから具体的な金額まで詳しく解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。最後に、この記事の重要なポイントをまとめておきます。
- 65歳になると自分の老齢年金の受給が始まる
- それに伴い遺族年金の受け取り方が変わる
- 中高齢寡婦加算は原則として65歳で終了する
- 65歳以降は自分の老齢厚生年金が優先的に支給される
- 遺族厚生年金は自分の老齢厚生年金との差額が支給される
- 自分の老齢厚生年金の方が多い場合、遺族厚生年金の支給は0円になる
- 遺族年金が減っても年金全体の収入が減るとは限らない
- 夫が亡くなった年齢に上限はなく70歳以上でも対象になる
- 手続きには65歳になる前に届く年金請求書の提出が必要
- 遺族年金の平均月額は約8万円だが個人差が大きい
- 遺族厚生年金の基準額は亡くなった方の老齢厚生年金の4分の3
- 正確な金額はねんきん定期便や年金事務所で確認することが重要
- 制度を正しく理解することが将来の安心につながる
- 不安な点があれば専門家への相談も有効な選択肢
- ご自身の状況に合わせて一度シミュレーションしてみよう

遺族年金の仕組みは、人生のセーフティネットとして非常に重要です。特に65歳からの受け取り方は、その後の生活設計に直結します。今回の記事を参考に、ご自身の年金がどうなるのかをぜひ一度確認してみてください。もし少しでも不安や疑問があれば、一人で抱え込まず、年金事務所や私たちのような専門家に気軽に相談してくださいね。
▼あわせて読みたい関連記事▼

お気軽にご相談ください
相続は100人いれば、100通り
唯一無二の最適な相続をご提案いたします
CONTACT
専門家やえさん

- 専門家やえさん
-
堀川 八重(ほりかわ やえ)
大阪不動産・FPサービス株式会社 代表
15年以上にわたり1,500組を超えるご家族の相続や不動産のお悩みに、専門家として寄り添ってまいりました。私の信条は、法律や数字の話をする前に、まずお客様ご家族の歴史や言葉にならない想いを丁寧に「聞く」こと。信頼できる各分野の専門家チームと共に、皆様が心から安心できる最善の道筋をオーダーメイドでご提案します。一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。
最新の投稿
 お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説
お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説 相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説
相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説 お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例
お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例 お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説
お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説






