「お墓の建立者が亡くなったら、墓石に彫られた名前や朱色はどうなるの?」
大切なご家族のお墓のことですから、こんな疑問が頭をよぎることはありませんか?墓石の建立者名が朱色になっているのを見ると、「このままでいいのかな?」と少し不安になりますよね。
墓石の赤字が持つ意味や、墓石の赤字消しはいつ行うべきなのか、そして墓石の赤字消し費用はどれくらいかかるのか、さらに墓石の赤字消しを自分でできるのかといった具体的な方法まで、気になることは尽きません。
また、お墓の建立者名を連名にする場合や、お墓の建立者が赤字のままで良いのか、お墓の建立者は亡くなった人はどうなりますか?といった疑問もよく耳にします。墓石に彫刻される亡くなった方の名前は?と、その後の対応に迷う方もいらっしゃるかもしれませんね。
ご安心ください。この記事では、そんな皆様の疑問に寄り添い、墓地や霊園での手続き、戒名の扱い、彫刻の必要性など、気になるポイントをユーモアを交えながら優しく解説していきます。これを読めば、もう迷うことはありません!安心して供養できるよう、一緒に見ていきましょう。
この記事のポイント
- お墓の建立者が存命の場合、名前は朱色で表されます。
- 生前戒名で彫られている場合、死亡すると朱色は抜かれます。
- 俗名で彫られている場合、死亡しても朱色を抜く必要はありません。
- お墓の文字が消えた場合、石材店へ補修を依頼するか、自分で手直しもできます。
目次
お墓建立者死亡後の名前の扱い

お墓に彫刻される建立者名とは
お墓を建立する際、その墓石には「〇〇家之墓」といった家名だけでなく、建立者の名前や建立年月日を彫刻するのが一般的です。多くの場合、お墓を代々受け継ぐ「祭祀承継者」が建立者となるケースが多いですが、必ずしもそうである必要はありません。
例えば、亡くなった親のために子どもがお墓を建立する場合、故人である親の名前を建立者として彫刻することも珍しくありません。これは、親の遺志を継ぎ、その財産でお墓を建てたという意味合いも含まれているからです。
また、建立者の名前は一人だけでなく、複数人の連名で彫刻することも可能です。もしお墓の建立費用を複数人で負担した場合、連名で名前を彫刻することで、皆で力を合わせてお墓を建てたという気持ちを表すことができます。
私の知人のお話ですが、ご兄弟でお墓を建立された際、当初は長男の方だけの名前を彫刻する予定だったそうです。しかし、他のご兄弟も「私たちも一緒に建立した証を残したい」と希望され、最終的には全員の名前を連名で彫刻することになりました。
このように、ご家族の絆や想いを形にする意味でも、連名での彫刻はとても素敵な選択肢だと感じます。
「お墓って、家族の歴史を刻む場所だから、誰が建てたかを残すって大切ですよね。連名にすると、みんなの想いが詰まっている感じがして、温かい気持ちになります。」
墓石の建立者名が朱色である理由

墓石に彫刻された建立者の名前が朱色で表されているのを見たことはありませんか?これは、その建立者がまだご存命であることを示しています。一般的には、姓名ともに朱色で記されることが多いですが、最近では名前のみを朱色で表すケースも増えています。
この朱色の慣習には、古くからの理由があります。もともとは、寺院から生前に授かる「生前戒名」が由来していると言われています。戒名とは、仏門に入り、戒律を守る証として寺院より授けられる名前のことです。
生前戒名を授かった方は、まだ仏門に正式に入ったわけではないため、その戒名に朱色を入れることで、「仮」の状態であることを示していました。これと同じように、お墓の建立者の名前に朱色を入れることで、「まだご存命ですよ」という意味合いを持たせるようになったのです。
豆知識:生前戒名とは?
生前戒名とは、生きている間に仏様の弟子となる証として授かる戒名のことを指します。これにより、生前から仏縁を結び、より深く仏教の教えに触れることができるとされています。
墓石の赤字が持つ意味とは
墓石の建立者名に使われる赤字には、「まだ生きている」という意味が込められています。これは、前述の生前戒名の考え方と通じるものです。生前戒名は、故人となって仏門に入る前に授かる戒名であり、まだ現世にいるため「仮」の意味で朱色が用いられます。同様に、建立者もご存命であるため、名前に朱色を施すことで、その方が現在もこの世に存在していることを示しているのです。
この習慣は、特に仏教の教えに基づいたものであり、お墓に故人の名前が彫刻されることと対比して、生者の名前を区別する意味合いがあります。私の祖母の墓石にも、祖父が建立した際に祖父の名前が朱色で彫刻されていました。
幼い頃は「なんでおじいちゃんの名前だけ赤いの?」と不思議に思っていましたが、大人になってその意味を知り、ご先祖様への敬意と、今を生きる家族への想いが込められていることを感じました。
お墓の建立者が死亡したらどうなる?
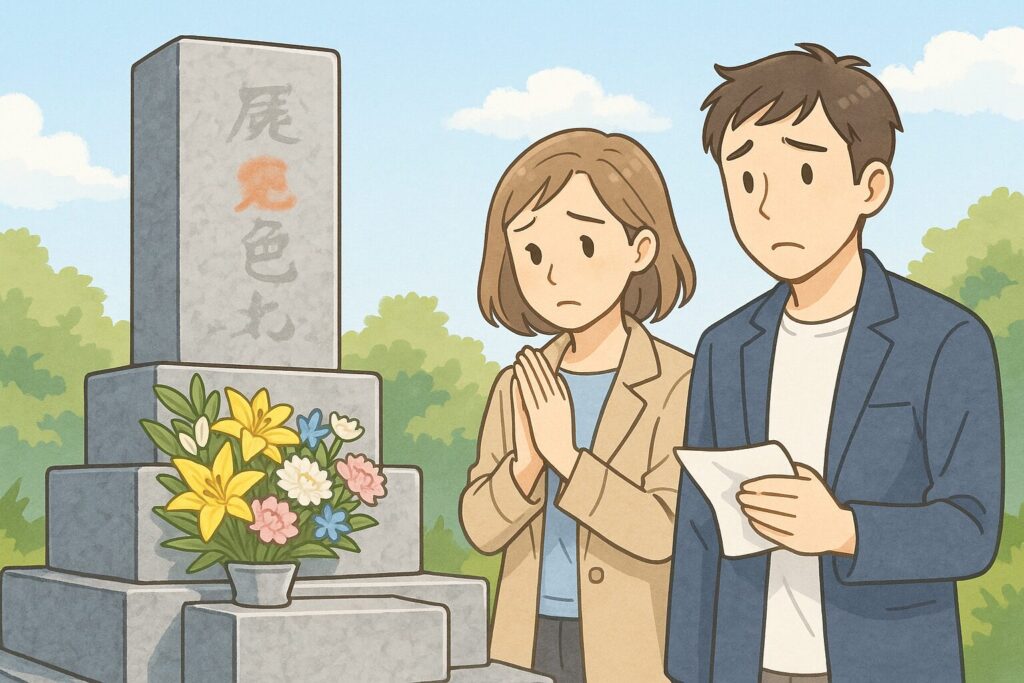
さて、お墓の建立者が死亡した場合、墓石に彫刻されている名前はどのように扱われるのでしょうか。これは、建立者の名前が「俗名」で彫刻されているか、「戒名」で彫刻されているかによって対応が異なります。
まず、建立者の名前が「俗名」(私たち自身の本名)で彫刻されている場合です。この場合、建立者が亡くなったとしても、朱色を抜いても抜かなくても、どちらでも構いません。その理由としては、俗名は仏教とは直接関係がないため、朱色を抜くことに宗教的な必要性がないからです。ご親族と相談し、皆で納得できる形で判断するのが良いでしょう。
一方、建立者の名前が「戒名」で彫刻されている場合、特に「生前戒名」を授かっていた場合は、建立者が亡くなると朱色を抜くのが一般的です。生前戒名は、生きているうちに授かる戒名であり、まだ正式な仏弟子とはみなされないため、朱色で表されています。建立者が亡くなり、仏門に入ることによって、墓石に彫刻されている戒名の朱色を抜くことになります。これは、故人が正式に仏の世界へ旅立ったことを示す意味合いがあります。
注意点:親族との相談は大切
朱色を抜くかどうかの判断は、ご親族間での意見が分かれることもあります。後々のトラブルを避けるためにも、必ず事前に話し合い、合意形成をしておくことが大切です。
墓石に彫刻される亡くなった方の名前は?
お墓に彫刻される亡くなった方の名前は、一般的に「戒名(または法名、法号)」と「俗名(本名)」、そして没年月日や享年などが記されます。建立者の名前が朱色で彫刻されていた場合、その方が亡くなると、朱色を抜いた上で、没年月日や享年などの情報が追加で彫刻されることになります。
この追加彫刻は、故人の生涯を墓石に刻み、永く後世に伝えるための大切な工程です。私の担当させていただいたお客様の中に、ご主人が亡くなられた後、奥様がご自身の生前戒名を彫刻し、ご主人の戒名の隣に朱色で名前を刻まれた方がいらっしゃいました。
数年後、奥様が亡くなられた際には、その朱色を抜き、没年月日を追記する作業をお手伝いさせていただきました。このように、墓石は家族の歴史を刻み続ける大切な存在なのです。
お墓の建立者名が赤字の場合

お墓の建立者の名前が赤字で彫刻されている場合、それは「生きていらっしゃる方」の名前であるという意味になります。この赤字は、ご存命の間に建てられたお墓、つまり「寿陵(じゅりょう)」という生前建立のお墓によく見られます。
ご自身の終の棲家を建立し、名前を彫刻しておくことで、残されたご家族への負担を減らすことができますし、何よりご自身が納得のいくお墓を準備できるというメリットがあります。
ただし、赤字のままで良いかどうかは、前述の通り、その名前が俗名か戒名かによって判断が異なります。俗名であれば抜く必要はありませんが、生前戒名であれば故人となられた際に抜くのが通例です。
この点について、ご不明な場合は、お墓を建立した石材店や、お付き合いのある寺院に相談されるのが最も確実です。地域によっては、独自の慣習がある場合もありますので、確認しておくと安心ですね。
お墓や墓石に建立者名を連名で彫刻
お墓や墓石に建立者名を連名で彫刻することは、全く問題ありません。むしろ、ご家族やご兄弟、あるいは複数の親族で費用を出し合って建立した場合など、皆の想いを形にする素晴らしい方法です。連名にすることで、お墓が特定の誰か一人のものではなく、家族みんなで守っていくものだという意識も高まります。
私の経験ですが、以前、ご両親のためにご兄弟3人で建立されたお客様がいらっしゃいました。当初は長男の方の名前だけを彫刻する予定でしたが、話し合いの結果、ご兄弟全員の名前を連名で彫刻することになりました。その際、「これでみんなで両親を供養できるね」と、とても温かい雰囲気になったのを覚えています。連名での彫刻は、ご家族の絆を深める意味でも、とても良い選択肢だと感じます。
連名彫刻のメリット
- 費用負担を分担できる
- 家族全員の想いを形にできる
- お墓を共同で守る意識が高まる
お墓建立者死亡後の墓石文字の補修

墓石の赤字を自分で消す方法
もし墓石に彫刻された赤字が薄くなったり、消えてしまったりした場合、ご自身で手直しすることも可能です。ただし、墓石は大切なものですので、慎重に行う必要があります。
ご自身で手直しする際に必要なものは、以下の通りです。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 白ペンキまたはラッカースプレー | 文字の色に合わせて選びます。 |
| ペイント落とし | 古い塗料を落とすために使います。 |
| 歯ブラシ、雑巾 | 汚れ落としや拭き取り用です。 |
| カッターナイフ | はみ出した塗料を削り取る際に使用します。 |
| 養生テープ | 文字以外の部分を保護するために使います。 |
| 筆や綿棒 | 細かい部分の塗料塗布に便利です。 |
作業の手順としては、まず歯ブラシや雑巾を使って、塗り直す部分の汚れを丁寧に落とします。水分をしっかりと拭き取ったら、ペイント落としを含ませた筆や綿棒で古い塗料を落としていきます。
その後、彫刻部分の周りに養生テープを貼り、筆で白ペンキなどの塗料を重ね塗りします。塗料が完全に乾いたら、カッターで、はみ出している部分の塗料を慎重にそぎ落とせば完成です。
私の友人がご自身の墓地でこの作業を試みた際、「意外と細かい作業で集中力いるね!」と笑っていましたが、きれいに仕上がった墓石を見てとても満足そうでした。ただし、慣れない作業で不安な場合は、無理せず専門の石材店に依頼することをおすすめします。
墓石の赤字消しにかかる費用
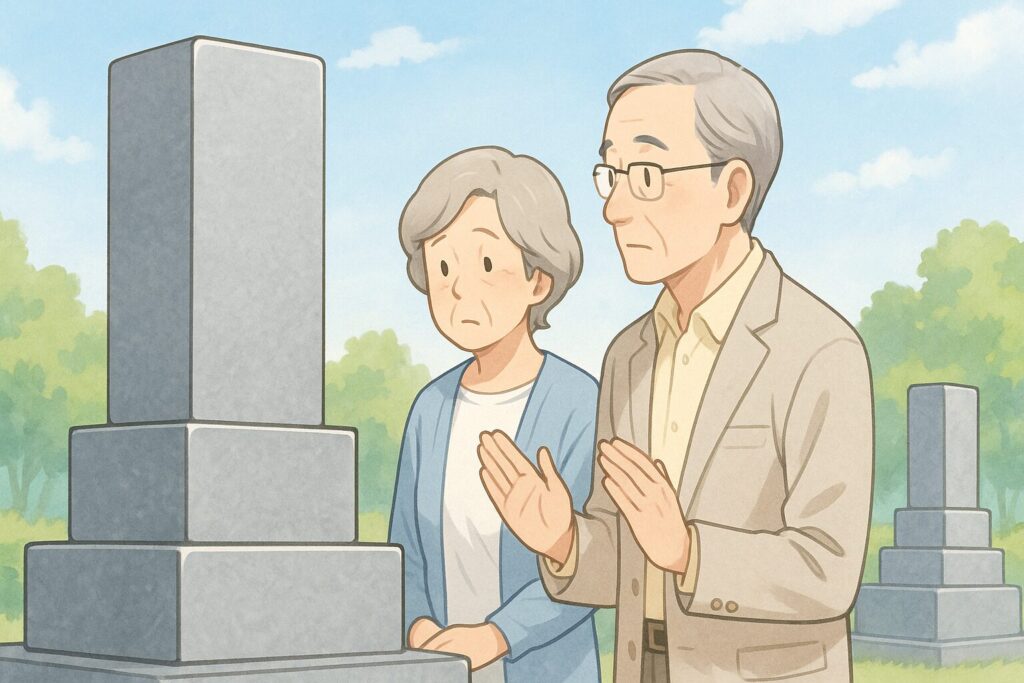
墓石の赤字を消したり、文字の塗り直しを専門の石材店に依頼する場合、費用は一般的に1万円から3万円程度が相場とされています。この費用には、作業費だけでなく、出張費や材料費なども含まれることが多いです。
自分で手直しする方法もありますが、やはりプロに任せる方が仕上がりは格段にきれいですし、耐久性も期待できます。特に、墓石の状態や文字の彫刻の深さによっては、専門的な技術が必要になる場合もあります。
「私も以前、実家のお墓の文字が薄くなっているのを見て、自分でやろうか迷ったんです。でも、失敗して大切な墓石を傷つけたら…と思うと、やっぱりプロにお願いするのが一番安心だなと感じました。」
費用は石材店や地域によって異なる場合がありますので、まずは複数の石材店に見積もりを依頼し、比較検討することをおすすめします。
参考情報サイト:
一般社団法人 日本石材産業協会では、石材店選びのポイントや、お墓に関する様々な情報を提供しています。
URL: https://www.japan-stone.org/
墓石の赤字を消すタイミング
墓石の赤字を消すタイミングは、主に建立者が亡くなられた後、四十九日や一周忌などの法要に合わせて行うことが多いです。これは、故人が正式に仏の世界へ旅立った区切りとして、朱色を抜くという意味合いがあるからです。
しかし、厳密な決まりがあるわけではありません。ご家族やご親族の意向、あるいは石材店のスケジュールに合わせて、都合の良いタイミングで行うことができます。私の経験では、遠方に住むご家族が全員集まる一周忌の法要に合わせて、赤字を抜く作業を依頼されるケースが多く見られます。法要の際に、故人が完全に仏様になられたことを皆で確認し、新たな気持ちでお墓と向き合う良い機会になるようです。
俗名の場合であれば、朱色を抜く必要がないため、急いで行う必要もありません。ご家族で話し合い、最も適切なタイミングを決めることが大切です。
お墓建立者死亡時の対応まとめ
ここまで、お墓の建立者が死亡した場合の名前の扱い、特に朱色の意味やその後の対応について詳しくお伝えしてきました。墓石に彫刻された名前一つにも、深い意味や慣習があることをご理解いただけたのではないでしょうか。
大切なご家族のお墓のことですから、疑問や不安を感じるのは当然のことです。このまとめで、もう一度ポイントを確認し、今後の参考にしていただければ幸いです。
- お墓の建立者名は、家名と共に墓石に彫刻される
- 建立者名は連名で彫刻することも可能
- 墓石の建立者名が朱色なのは、存命の証
- 生前戒名の場合、死亡後に朱色を抜くのが一般的
- 俗名の場合、死亡後も朱色を抜く必要はない
- 墓石の赤字を消すタイミングは、四十九日や一周忌など法要時が多い
- 墓石の文字が消えたら、石材店に補修を依頼できる
- 自分で墓石の文字を補修することも可能だが、慎重な作業が必要
- 石材店への補修依頼費用は1万円から3万円程度が相場
- お墓の建立は、家族の歴史と絆を刻む大切な行為
- 墓地や霊園のルール、地域の慣習も確認することが重要
- 戒名に関する疑問は、お寺や石材店に相談するのが確実
- お墓の建立者死亡に関する疑問は、専門家への相談が安心
参考

お気軽にご相談ください
相続は100人いれば、100通り
唯一無二の最適な相続をご提案いたします
CONTACT
専門家やえさん

- 専門家やえさん
-
堀川 八重(ほりかわ やえ)
大阪不動産・FPサービス株式会社 代表
15年以上にわたり1,500組を超えるご家族の相続や不動産のお悩みに、専門家として寄り添ってまいりました。私の信条は、法律や数字の話をする前に、まずお客様ご家族の歴史や言葉にならない想いを丁寧に「聞く」こと。信頼できる各分野の専門家チームと共に、皆様が心から安心できる最善の道筋をオーダーメイドでご提案します。一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。
最新の投稿
 お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説
お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説 相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説
相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説 お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例
お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例 お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説
お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説






