「亡くなった親に借金が…!相続放棄したいけど、手続きはどこでするの?」
突然のことで、何から手をつけていいか分からず、不安でいっぱいになりますよね。相続放棄には3ヶ月という期間の定めもあって、焦るお気持ち、本当によく分かります。相続放棄の手続きは自分でもできますが、相続放棄の必要書類を集めたり、相続放棄申述書を作成したりと、意外とやることがたくさんあるんです。
家庭裁判所での相続放棄がスムーズに進むか心配な方や、相続放棄の手続きにかかる司法書士の費用が気になる方もいらっしゃるでしょう。また、相続放棄が認められない事例や、ご兄弟がいる場合の注意点も気になるところですよね。
「相続放棄申述書のダウンロードはどこから?」「そもそも相続放棄の手続きは自分でできますか?」「相続放棄の書類は市役所でもらえますか?」そんな疑問を、この記事で一つひとつ丁寧に解消していきますので、安心してくださいね。
こうした手続きは終活の一環としても、知っておくと安心な知識です。
この記事のポイント
- 相続放棄の手続きを行う具体的な場所がわかる
- 自分で手続きする場合の流れと必要書類がわかる
- 手続きにかかる費用や期間の目安がわかる
- 専門家に依頼するメリットと注意点がわかる

はじめまして!終活・相続・不動産相続の専門家、やえです。多くの方が「相続」と聞くと、難しくて大変そう…と感じてしまいますよね。特に相続放棄は、期限もあって精神的な負担も大きいものです。でも、大丈夫。正しい知識と手順さえ分かれば、決して乗り越えられない壁ではありません。私自身、これまで多くの方の相続に関するお悩みに寄り添ってきました。その経験から言えるのは、一人で抱え込まず、まずは正確な情報を知ることが第一歩だということです。この記事が、あなたの不安を少しでも和らげるお手伝いができれば嬉しいです。
目次
相続放棄手続きどこで?基本の流れを解説

相続放棄の手続きは自分でできますか?
結論から言うと、相続放棄の手続きはご自身で行うことが可能です。実際に、弁護士や司法書士といった専門家に依頼せず、ご自身で書類を揃えて家庭裁判所に申述される方もたくさんいらっしゃいますよ。
自分で手続きを行う一番のメリットは、やはり専門家へ支払う報酬を節約できる点でしょう。手続き自体にかかる費用は数千円程度で済むため、経済的な負担を大きく減らすことができます。また、ご自身のペースで手続きを進められるという利点もありますね。
一方で、デメリットも理解しておく必要があります。それは、必要書類の収集に手間がかかることです。特に、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を集めるのは、本籍地が各地に点在している場合、時間と労力がかかります。
また、裁判所に提出する相続放棄申述書の書き方に不備があったり、のちに裁判所から送られてくる「照会書」への回答が不適切だったりすると、最悪の場合、相続放棄が受理されない可能性もあるのです。
自分で手続きするメリット・デメリット
- メリット:専門家への依頼費用を節約できる。
- デメリット:書類収集に手間がかかる。手続きに不備があると受理されないリスクがある。
時間的に余裕があり、書類の準備などを正確に行う自信がある場合には、ご自身での手続きを検討してみるのが良いかもしれません。ただ、少しでも不安があるなら、当社の相続サポートサービスのような専門家への相談も視野に入れることをおすすめします。
家庭裁判所での相続放棄の手順

相続放棄は、市区町村の役場ではなく、「家庭裁判所」で行う手続きです。どこの家庭裁判所でも良いわけではなく、亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。ここを間違えてしまうと、書類が受け付けてもらえないので注意が必要ですよ。
手続きの具体的な流れは、以下のようになります。
ステップ1:必要書類の収集
まずは、申述に必要な書類を集めます。亡くなった方との関係によって必要な戸籍謄本などが異なりますので、事前にしっかり確認しましょう。詳しくは次の見出しで解説しますね。
ステップ2:相続放棄申述書の作成
必要書類が揃ったら、「相続放棄申述書」を作成します。申述書は裁判所のウェブサイトからダウンロードできます。記入例を参考に、正確に情報を記載していきましょう。
ステップ3:家庭裁判所への提出
作成した申述書と集めた必要書類を、管轄の家庭裁判所に提出します。提出方法は、裁判所の窓口へ直接持参する方法と、郵送する方法のどちらでも大丈夫です。遠方にお住まいの場合や、日中時間が取れない場合は郵送が便利ですね。
ステップ4:照会書への回答・返送
書類を提出してしばらくすると、家庭裁判所から「照会書(回答書)」という書類が郵送されてきます。これは、「本当にご自身の意思で相続放棄をするのですか?」といった意思確認のための質問状です。内容をよく読んで、事実に基づいて回答し、署名・捺印して返送します。
ステップ5:相続放棄申述受理通知書の受領
照会書を返送し、内容に問題がなければ、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。この通知書を受け取った時点で、正式に相続放棄の手続きが完了したことになります。この書類は、債権者(お金を貸した側)に対して相続放棄したことを証明する大切な書類になるので、なくさないように保管してください。
相続放棄の期間と費用について
相続放棄を検討する上で、特に気をつけておきたいのが「期間」と「費用」です。うっかりしていると、取り返しのつかないことにもなりかねませんので、しっかり押さえておきましょう。
相続放棄ができる期間(熟慮期間)
相続放棄の手続きは、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に行う必要があります。この3ヶ月の期間を「熟慮期間」と呼びます。これは相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)とは異なるため、混同しないように注意が必要です。
「知った時」とは?
多くの場合、「被相続人が亡くなったことを知り、かつ、それによって自分が相続人になったことを知った時」からカウントが始まります。例えば、疎遠だった親族が亡くなり、しばらくしてから自分が相続人であることを知った場合は、その知った時から3ヶ月となります。
この期間はあっという間に過ぎてしまいます。もし、財産調査に時間がかかり、3ヶ月以内に放棄するかどうかを決められない場合は、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることで、期間を延長してもらえる場合があります。
手続きにかかる費用
ご自身で手続きを行う場合にかかる実費は、それほど高額ではありません。主な費用は以下の通りです。
| 項目 | 費用の目安 | 備考 |
| 収入印紙代 | 800円 | 申述人1人につきかかります。 |
| 連絡用の郵便切手代 | 400円~500円程度 | 申述先の家庭裁判所によって金額が異なりますので、事前に確認が必要です。 |
| 戸籍謄本などの取得費用 | 合計で数千円程度 | 取得する書類の種類や通数によって変動します。 |
合計すると、おおよそ3,000円から5,000円程度を見ておくと良いでしょう。専門家に依頼する場合は、これに加えて司法書士や弁護士への報酬が必要になります。

相続手続きって、本当に書類集めが大変なんですよね。「戸籍謄本」と一言で言っても、亡くなった方の出生から死亡までの全てとなると、結婚や転籍で本籍地が変わっていることも多く、あちこちの役所に請求しなければならないケースも珍しくありません。特に、お仕事や家事で忙しい中で、平日の昼間に役所へ連絡したり、郵便局で定額小為替を用意したりするのは一苦労です。もし書類集めが難しいと感じたら、無理せず専門家の力を借りるのも一つの賢い選択ですよ。時間と手間、そして精神的な安心感をお金で買う、という考え方ですね。
相続放棄の必要書類一覧

相続放棄の申述に必要な書類は、亡くなった方(被相続人)と申述する方(相続人)の関係によって異なります。そもそも誰が法定相続人になるのかという点も、ここで重要になります。ここでは、関係性ごとに必要な書類を一覧でご紹介しますね。
まず、どの場合でも共通して必要になる書類は以下の3点です。
【全相続人共通】の必要書類
- 相続放棄の申述書
- 被相続人の住民票除票 または 戸籍附票
- 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
これに加えて、亡くなった方との関係に応じて、以下の書類が必要になります。
| 申述する方 | 追加で必要な書類 |
| 配偶者 | ・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 |
| 子または孫など(第1順位) | ・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本<br>・(孫などが申述する場合)本来の相続人(子)の死亡の記載のある戸籍謄本 |
| 父母または祖父母など(第2順位) | ・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本<br>・亡くなっている子(とその代襲者)がいる場合、その方の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本<br>・亡くなっている直系尊属(父母など)がいる場合、その方の死亡の記載のある戸籍謄本 |
| 兄弟姉妹または甥姪(第3順位) | ・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本<br>・亡くなっている子(とその代襲者)がいる場合、その方の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本<br>・被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)の死亡の記載のある戸籍謄本<br>・(甥姪が申述する場合)本来の相続人(兄弟姉妹)の死亡の記載のある戸籍謄本 |
特に、第2順位や第3順位の方が相続放棄をする場合は、先順位の相続人がいないこと(または全員が相続放棄したこと)を証明する必要があるため、集める戸籍謄本の数が多くなり、複雑になります。詳しくは、申述先の家庭裁判所のウェブサイトで確認するか、直接問い合わせてみるのが確実です。
これらの書類の取得方法については、裁判所のウェブサイト「相続の放棄の申述」にも詳しい案内がありますので、参考にしてください。
相続放棄の書類は市役所でもらえますか?
これは、本当によくあるご質問なのですが、相続放棄の申述書自体は、市役所や区役所ではもらえません。
相続放棄は家庭裁判所マターの手続きなので、申述書は家庭裁判所の窓口で直接受け取るか、裁判所のウェブサイトからダウンロードして入手する必要があります。
ただ、申述に必要な添付書類である
- 戸籍謄本
- 住民票の除票
- 戸籍の附票
といった書類は、市区町村の役場で取得します。戸籍謄本は本籍地、住民票関連は最後の住所地の役場が窓口になります。
書類の入手場所まとめ
- 家庭裁判所で入手するもの:相続放棄申述書
- 市役所・区役所などで入手するもの:戸籍謄本、住民票の除票など
このように、手続きに必要な書類の入手先が分かれているので、少しややこしく感じてしまうかもしれませんね。「役所に行けば全部揃う」というわけではない、という点を覚えておくとスムーズです。
相続放棄申述書の入手とダウンロード
前述の通り、相続放棄の申述書は家庭裁判所で入手します。直接窓口へ行ける方はそれでも良いのですが、多くの方にとってはウェブサイトからのダウンロードが便利でしょう。
申述書は、裁判所のウェブサイト内にある「相続の放棄の申述」のページから、書式と記載例をダウンロードすることができます。
書式は申述人が「成人」の場合と「未成年者」の場合で分かれていますので、ご自身の状況に合ったものをダウンロードしてくださいね。
ダウンロードした申述書は、ご自宅のプリンターやコンビニのネットプリントなどを利用して印刷します。記載例をよく見ながら、間違いのないように記入していきましょう。特に、被相続人の最後の住所や本籍、ご自身の情報などは、戸籍謄本や住民票の通りに正確に書くことが大切です。
もし書き方で分からないことがあれば、家庭裁判所に電話で問い合わせることも可能です。ただし、法律的な判断に関する相談には乗ってもらえないので、その点は注意してくださいね。
相続放棄手続きどこで相談?注意点と費用
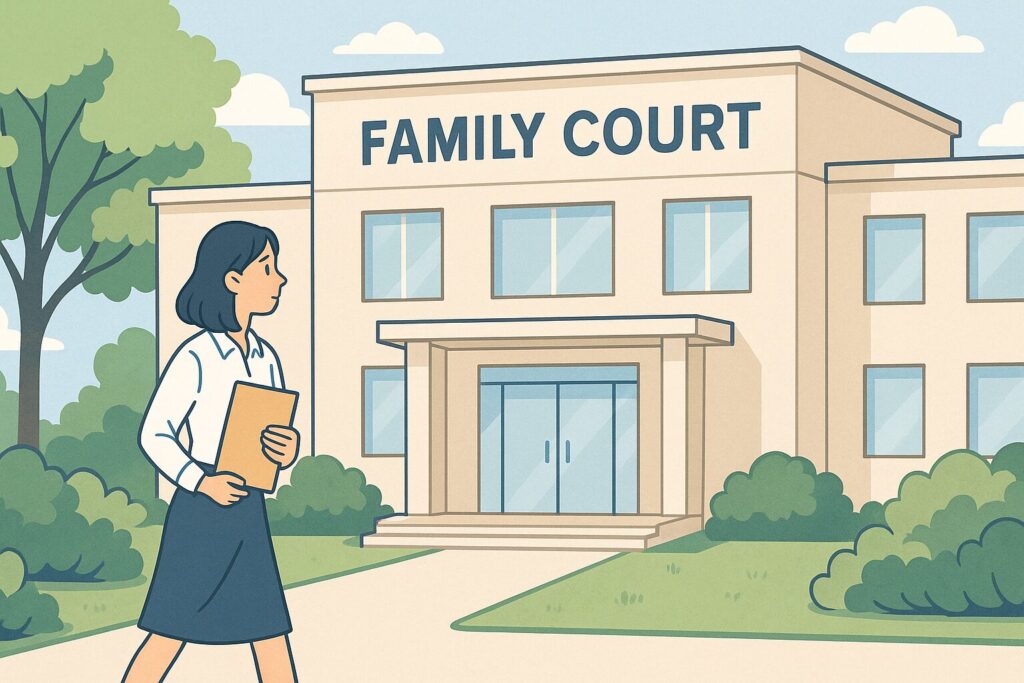
相続放棄の手続きを自分で行う際の注意点
ご自身で手続きを進める際には、いくつか注意しておきたいポイントがあります。これを知らないと、思わぬ落とし穴にはまってしまう可能性もあるので、ぜひ覚えておいてください。
単純承認とみなされる行為をしない
最も注意すべきなのが、「法定単純承認」とみなされる行為です。これは、相続人が亡くなった方の財産を処分したり、使ってしまったりした場合に、「相続することを承認した」と法律上みなされてしまい、それ以降は相続放棄ができなくなるというルールです。
こんな行為は要注意!
- 亡くなった方の預貯金を引き出して、自分の生活費や借金の返済に使う。
- 亡くなった方の不動産や自動車を売却したり、名義変更したりする。
- 亡くなった方の借金を、遺産の中から支払う。
- 形見分けのつもりで、高価な遺品(骨董品や貴金属など)をもらってしまう。
葬儀費用を亡くなった方の預金から支払うことなどは、社会通念上相当な範囲であれば問題ないとされることが多いですが、判断が難しいケースもあります。相続放棄を考えている間は、亡くなった方の財産には一切手を付けないのが一番安全です。
照会書(回答書)には慎重に回答する
申述後に家庭裁判所から送られてくる「照会書」は、いわば最終確認のようなものです。ここでの回答内容によっては、相続放棄が認められないこともあります。
例えば、「相続財産の存在をいつ知りましたか?」という質問に対して、亡くなってすぐに財産の存在を知っていたにもかかわらず、3ヶ月以上経ってから申述した場合、その理由を合理的に説明できなければ、申述が却下される可能性があります。事実に沿って、正直に、そして慎重に回答することが重要です。
相続放棄が認められない事例とは

「書類さえ出せば、相続放棄は必ず認められる」と思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、残念ながらそうではありません。家庭裁判所に申述が「却下」され、相続放棄が認められないケースも存在します。
どのような場合に認められない可能性があるのか、具体的な事例を見ていきましょう。
3ヶ月の熟慮期間を過ぎてしまった
これは最も多い理由です。特別な事情なく、3ヶ月の期間内に申述をしなかった場合、原則として相続放棄は認められません。「仕事が忙しくて忘れていた」「借金があるとは知らなかったが、調査を怠っていた」といった理由では、却下される可能性が高いでしょう。
法定単純承認にあたる行為をしてしまった
前の見出しでも触れましたが、亡くなった方の財産を処分してしまった後に相続放棄をしようとしても、「すでに相続を承認した」とみなされ、申述は受理されません。
申述書や照会書への回答に不備・虚偽があった
提出した書類に不備があったり、照会書への回答内容に矛盾があったり、明らかに虚偽の記載があったりした場合も、裁判所は申述を受理しません。誠実な手続きが求められます。
もし一度、相続放棄の申述が却下されてしまうと、不服申し立て(即時抗告)はできますが、再度の申述が認められるのは非常に困難です。一回の手続きで確実に受理してもらうためにも、慎重な準備が必要になりますね。
相続放棄すると兄弟はどうなる?
相続放棄をすると、その人は「初めから相続人ではなかった」とみなされます。これが非常に重要なポイントで、ご自身が相続放棄をすることによって、他の親族に影響が及ぶことがあるのです。
特に、お子さんがいる方が亡くなったケースで考えてみましょう。相続人には法律で順位が定められています。
- 第1順位:子(子が亡くなっていれば孫)
- 第2順位:父母(父母が亡くなっていれば祖父母)
- 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっていれば甥・姪)
例えば、亡くなった方に配偶者と子(第1順位)がいた場合、この方々が相続人になります。しかし、もし配偶者と子が全員相続放棄をすると、相続権は次の順位である第2順位の父母に移ります。
そして、第2順位の父母もすでに亡くなっている、あるいは相続放棄をした場合、最終的に第3順位である兄弟姉妹に相続権が移るのです。
つまり、あなたが借金を相続したくないからと相続放棄をすると、その借金の支払い義務が、次はあなたのご両親やご兄弟に向かう可能性がある、ということです。
このことを知らないで自分だけ手続きをしてしまうと、後から親族間で大きなトラブルに発展しかねません。「自分は放棄したから関係ない」とせず、相続放棄をする際は、必ず次の順位の相続人になる可能性のある方に、事前に連絡・相談をしておくことが、とても大切です。思いやりを持って対応したいですね。
司法書士に依頼する手続きと費用

「自分で手続きするのは、やっぱり難しそう…」と感じた方は、司法書士などの専門家に依頼することを検討してみましょう。司法書士は、相続放棄に関する書類作成のプロです。
司法書士に依頼できること
司法書士に依頼すると、主に以下のようなことを代行またはサポートしてくれます。
- 必要書類(戸籍謄本など)の収集代行
- 相続放棄申述書の作成
- 家庭裁判所への書類提出
- 裁判所からの照会書への回答サポート
面倒な書類集めから、専門的な知識が必要な書類作成まで任せられるので、時間的・精神的な負担を大幅に軽減できるのが最大のメリットです。また、専門家が関わることで、書類の不備などによる不受理のリスクを大きく減らすことができます。
依頼費用の相場
司法書士に相続放棄の手続きを依頼した場合の費用は、事務所によって異なりますが、だいたい1人あたり3万円~5万円程度が相場とされています。
この費用には、戸籍謄本などの取得実費や裁判所に納める印紙代などが含まれている場合と、別途請求される場合がありますので、依頼する前に費用の内訳をしっかり確認しておきましょう。
「高い」と感じるかもしれませんが、確実に手続きを完了させたい方や、平日に時間が取れない方、親族関係が複雑で集める書類が多い方にとっては、費用を払う価値は十分にあると言えるでしょう。
相続放棄についてよくあるご質問FAQ
-
亡くなってから3ヶ月を過ぎてしまったら、もう相続放棄はできませんか?
-
原則として3ヶ月の熟慮期間を過ぎると相続放棄は難しくなります。しかし、「相続財産が全くないと信じており、そのように信じたことに相当な理由がある」といった特別な事情がある場合は、借金の存在などを知った時から3ヶ月以内であれば、申述が受理される可能性があります。諦めずに、まずは弁護士などの専門家に相談してみることをおすすめします。
-
相続放棄をしたら、生命保険金も受け取れなくなりますか?
-
受け取れます。生命保険金は、保険契約によって受取人として指定された人の「固有の財産」と考えられているため、相続財産には含まれません。したがって、相続放棄をしても、ご自身が受取人に指定されていれば生命保険金を受け取ることが可能です。
-
相続人全員が相続放棄をしたら、残された借金や家財はどうなるのですか?
-
相続人全員が相続放棄をし、他に相続する人がいなくなった場合、利害関係者(債権者など)の申し立てによって「相続財産清算人」が家庭裁判所によって選任されることがあります。この清算人が、残された財産(預貯金や不動産など)を換金して借金の返済などに充て、それでも財産が残れば最終的に国のもの(国庫に帰属)となります。この過程で、遺品の整理も行われます。
-
相続放棄が受理されたかどうかは、どうすれば確認できますか?
-
手続きが完了すると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が郵送されてきます。これが受理されたことの証明になります。もし、債権者などに証明書を提出する必要がある場合は、別途、家庭裁判所に「相続放棄申述受理証明書」の発行を申請することができます(手数料がかかります)。

相続放棄を無事に終えた後、多くの方が「肩の荷が下りた」とおっしゃいます。それだけ、この手続きは精神的にも大きなプレッシャーがかかるものなのですね。この記事を読んで、手続きの全体像が見え、少しでも不安が軽くなっていれば幸いです。大切なのは、一人で悩まず、分からないことはそのままにしないこと。そして、ご自身の状況に合わせて、自分で挑戦するのか、専門家の力を借りるのかを冷静に判断することです。あなたのこれからの人生が、相続の問題に縛られることなく、晴れやかなものになることを心から願っています。
相続放棄手続きどこですべきか総まとめ

最後に、この記事の重要なポイントをまとめました。相続放棄の手続きを進める際のチェックリストとしてご活用ください。
- 相続放棄の手続きは市区町村役場ではなく家庭裁判所で行う
- 管轄は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
- 手続きは自分でもできるが専門家に依頼することも可能
- 自分でやるメリットは費用が安いこと、デメリットは手間とリスクがあること
- 手続きの期間は相続の開始を知った時から3ヶ月以内
- 期間内に判断が難しい場合は期間の延長を申し立てできる
- 自分でやる場合の費用は数千円程度の実費
- 申述書は裁判所のウェブサイトからダウンロードできる
- 戸籍謄本などの必要書類は市区町村の役場で取得する
- 必要書類は亡くなった方との関係によって異なる
- 遺産を処分すると相続放棄ができなくなる可能性があるので注意
- 自分が放棄すると次の順位の人(親や兄弟など)に相続権が移る
- 次の順位の相続人には事前に連絡を入れておくのがマナー
- 手続きに不安があれば司法書士などの専門家に相談するのも一つの手
- 専門家への依頼費用は3万円から5万円程度が目安
▼あわせて読みたい関連記事▼
終活とは?意味と始め方をわかりやすく解説|初心者が損しない準備法

お気軽にご相談ください
相続は100人いれば、100通り
唯一無二の最適な相続をご提案いたします
CONTACT
専門家やえさん

- 専門家やえさん
-
堀川 八重(ほりかわ やえ)
大阪不動産・FPサービス株式会社 代表
15年以上にわたり1,500組を超えるご家族の相続や不動産のお悩みに、専門家として寄り添ってまいりました。私の信条は、法律や数字の話をする前に、まずお客様ご家族の歴史や言葉にならない想いを丁寧に「聞く」こと。信頼できる各分野の専門家チームと共に、皆様が心から安心できる最善の道筋をオーダーメイドでご提案します。一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。
最新の投稿
 お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説
お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説 相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説
相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説 お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例
お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例 お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説
お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説






