「うちの宗派、浄土真宗なんだけど、墓じまいの費用って他の宗派と違うのかしら…?」そんな疑問をお持ちではないですか?浄土真宗の墓じまいにかかる費用は?と調べてみると、浄土真宗はお墓いらない、なんて話も出てきたり…。
浄土真宗の墓じまいのお経や、閉眼供養のお布施はどうなるの?そもそも浄土真宗で墓じまいをしたら永代供養は必要ですか?という疑問もありますよね。墓じまいの費用総額や、もしあれば補助金についても知りたいし、浄土真宗の離檀料はいくらですか?というのも気になるところ。
墓じまいの費用を曹洞宗と比べたり、浄土真宗大谷派の場合で考えたり…考え始めるとキリがありません!この記事では、そんなあなたの疑問をまるっと解決します。読み終わる頃には、きっと不安もスッキリしているはずですよ。
この記事のポイント
- 浄土真宗の墓じまいに関する独特の考え方がわかる
- 具体的な費用の内訳と総額の目安が把握できる
- 他宗派との費用の違いについて理解できる
- 墓じまいをスムーズに進めるための手順がわかる

こんにちは!浄土真宗の墓じまいは「魂抜きをしない」といった独自の考え方があるため、初めての方は特に戸惑われることが多いですよね。でも、ご安心ください。基本的な流れや費用の考え方は他の宗派と大きくは変わりません。大切なのは、ご自身の宗派の特徴をきちんと理解し、菩提寺のご住職様やご家族と丁寧にお話を進めることです。この記事では、専門家の視点から、後悔しないための具体的な知識と円満に進めるコツをお伝えしますので、一緒に一歩ずつ進んでいきましょう。
目次
墓じまい費用、浄土真宗の考え方と特徴
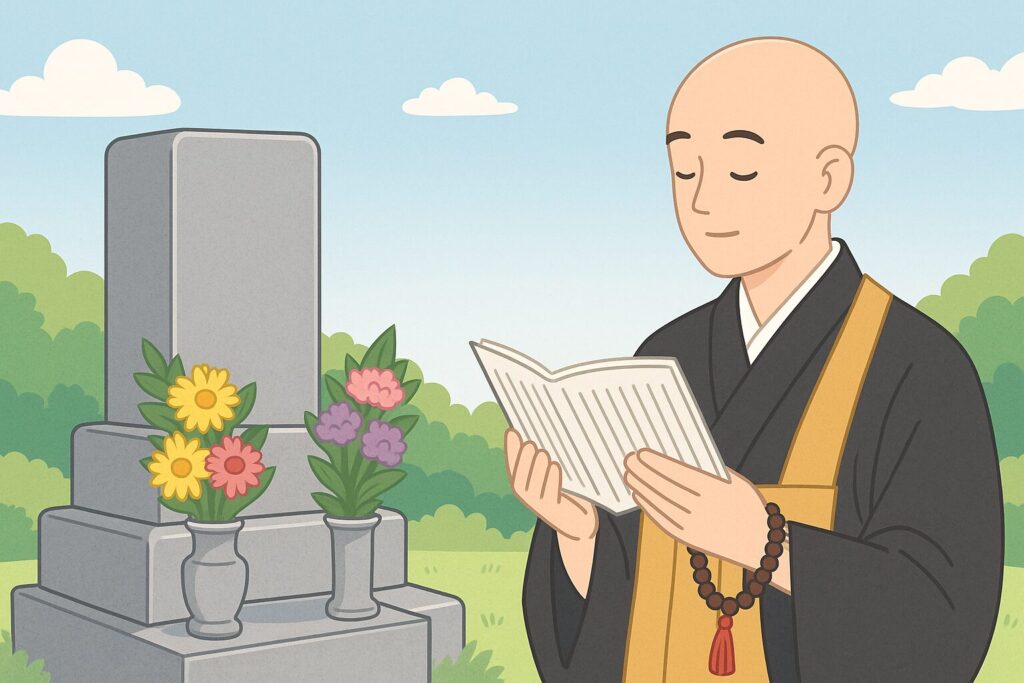
浄土真宗ではお墓はいらないって本当?
「浄土真宗はお墓がいらない」なんて話、耳にしたことはありませんか?これは半分本当で、半分は少し違う、といったところでしょうか。
浄土真宗の教えでは、亡くなった方は阿弥陀如来の力によって、すぐに極楽浄土へ往生すると考えられています。これを「往生即成仏(おうじょうそくじょうぶつ)」と言います。
そのため、他の宗派のように、故人の魂がお墓に宿るという考え方はありません。ですから、故人を供養するためにお墓が「絶対に必要」というわけではない、というのが教義上の考え方なんです。ご家族にとって心の拠り所であることは言うまでもありません。
ただ、だからといって本当にお墓を建てない方が多いかというと、そうでもありません。多くの方にとってお墓は、亡くなった大切な家族を偲び、手を合わせるための場所ですよね。
浄土真宗でも、お墓は故人を偲ぶ場であり、阿弥陀如来の教えに触れる大切な場所として、古くから建てられてきました。
結論としては、「教義上は必須ではないけれど、心の拠り所として大切にされてきた」というのが実情に近いかと思います。より詳しい内容は「【お墓いらない知恵袋】葬式なしの選択肢と費用を専門家が解説」で解説しています。
ポイント
- 浄土真宗では、亡くなるとすぐに成仏するという考え方(往生即成仏)があります。
- お墓に魂が宿るという概念がないため、教義上は必須ではないとされています。
- しかし、故人を偲び、教えに触れる場として、家族にとって大切な場所です。
浄土真宗の墓じまいで読まれるお経
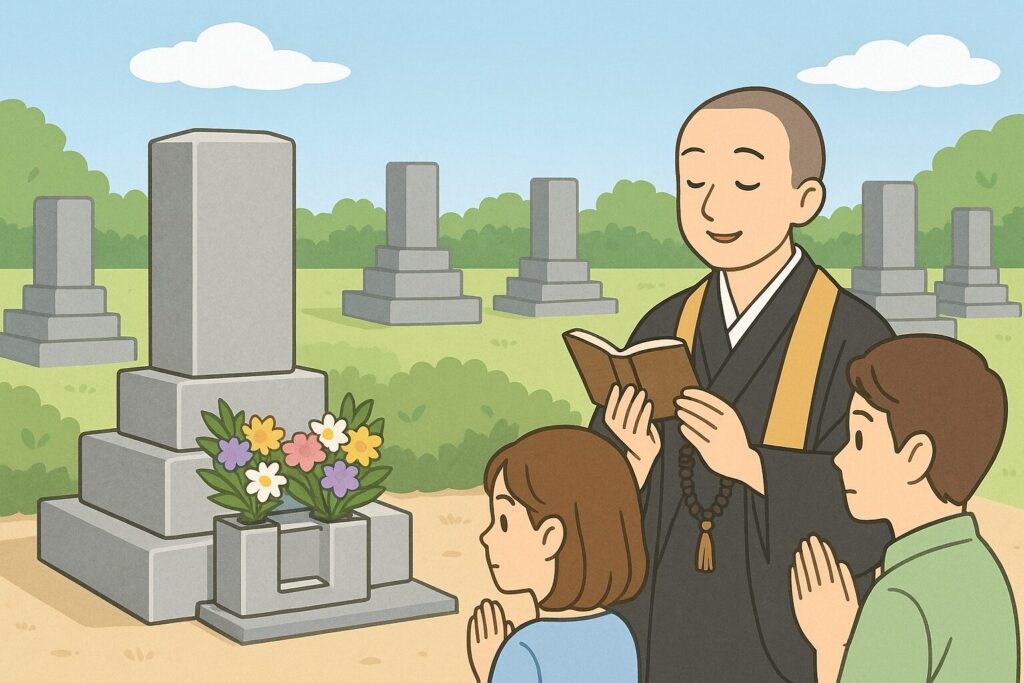
墓じまいをするとき、他の宗派では「閉眼供養(へいがんくよう)」や「魂抜き」といって、お墓に宿った魂を抜くための儀式を行います。しかし、前述の通り、浄土真宗ではお墓に魂が宿るという考え方がありません。そのため、閉眼供養は行いません。
では、何もしないのかというと、そうではありません。浄土真宗では、閉眼供養の代わりに「遷仏法要(せんぶつほうよう)」や「遷座法要(せんざほうよう)」という法要を行います。これは、お墓に宿る魂を抜くためではなく、「ご本尊(仏様)に場所を移っていただく」ための儀式です。この方法が一般的です。
読まれるお経は、お勤めの基本である「正信偈(しょうしんげ)」などが一般的ですが、これは故人の魂を供養するためではなく、阿弥陀如来の教えを皆で再確認し、感謝するためのもの。儀式の呼び方やお経の意味合いは異なりますが、僧侶に依頼して法要を行うという流れ自体は、他の宗派と大きくは変わりません。ちなみに浄土真宗では線香を寝かせる独特の作法もあります。
豆知識:法要の呼び方
浄土真宗の中でも、宗派によって法要の呼び方が若干異なる場合があります。例えば、本願寺派では「遷仏法要」、大谷派では「遷座法要」と呼ばれることが多いようです。ご自身の菩提寺の宗派を確認しておくと、よりスムーズに話が進むかもしれませんね。
墓じまい費用は曹洞宗とどう違う?
「浄土真宗の墓じまい費用は、曹洞宗など他の宗派と比べて高いの?安いの?」と気になる方もいらっしゃるかもしれませんね。結論から言うと、墓じまいにかかる費用の総額に、宗派による大きな違いはほとんどありません。
墓じまいの主な費用は、以下の3つで構成されています。
- 墓石の撤去費用:石材店に支払う工事費
- 法要のお布施:僧侶にお渡しするお礼
- 新しい納骨先の費用:永代供養墓など
この中で、宗派による違いが出る可能性があるのは「2. 法要のお布施」の部分ですが、これも金額が大きく変わることは稀です。
例えば、曹洞宗では「閉眼供養」、浄土真宗では「遷仏法要」と儀式の名前は違いますが、僧侶に来ていただく手間は同じですので、お布施の相場も大きくは変わらないのが一般的です。
つまり、墓じまいの費用は、お墓の大きさや立地、そして次にどのような供養を選ぶかによって決まる部分が大きく、宗派による差はそれほど気にしなくても大丈夫、と考えてよいでしょう。
浄土真宗の墓じまいと永代供養の関係
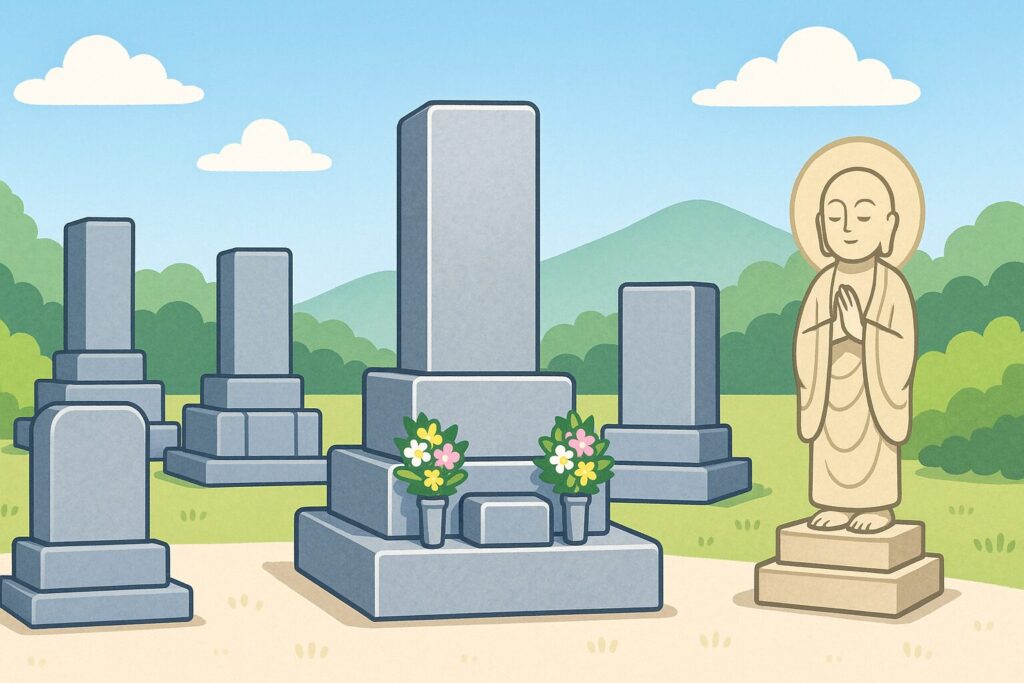
実は、厳密に言うと浄土真宗には「永代供養」という考え方もありません。これも「往生即成仏」の教えに基づいています。故人はすでに成仏しているので、残された家族が供養する必要はない、という考え方だからです。
しかし、近年はお墓の継承者がいないなどの理由から、「お寺に永代にわたって遺骨の管理と供養をお願いしたい」というニーズが非常に高まっています。この社会的な変化を受けて、浄土真宗のお寺でも、永代供養墓や納骨堂を設けているところが増えてきました。
この場合、浄土真宗では「永代供養」という言葉の代わりに「永代経(えいたいきょう)」という言い方をすることがあります。
これは、故人の冥福を祈るためというよりは、「永代にわたってお経が読まれ、仏様の教えが受け継がれていく」という意味合いが強いです。
言葉の意味は少し違いますが、お寺が永続的に遺骨を管理・供養してくれるという点では、実質的に他の宗派の永代供養と同じと考えて差し支えないでしょう。
終活・相続・不動産相続の専門家やえです。最近は「宗旨・宗派不問」の霊園も多く、浄土真宗の方でも気兼ねなく永代供養を選べる環境が整っています。
菩提寺に永代供養墓がなくても、選択肢はたくさんあります。例えば、故郷のお墓をしまい、今のお住まいの近くの霊園に改葬する方も増えています。
大切なのは、ご自身がこれからどのように故人と向き合っていきたいか、という点です。ご自身の希望に合った場所を、焦らずじっくり探すことが後悔しないための鍵ですよ。
浄土真宗で墓じまいをしたら永代供養は必要か
「墓じまいをしたら、必ず永代供養をしないといけないの?」というご質問もよくいただきます。これは、浄土真宗に限らず、すべての宗派に共通することですが、答えは「必ずしも必要ではありません」です。
墓じまいで取り出したご遺骨の供養方法には、さまざまな選択肢があります。
- 永代供養墓や納骨堂に納める:最も一般的な選択肢です。
- 樹木葬:自然に還るイメージで近年人気です。
- 本山納骨:浄土真宗の総本山(西本願寺や東本願寺など)に納骨する方法です。
- 手元供養:自宅でミニ骨壺などで供養する方法です。
- 散骨:海や山に遺骨を撒く方法です。
墓じまい後の埋葬方法は、故人の遺志やご自身のライフスタイルに合わせて選ぶことができます。
永代供養は、お墓の管理の負担をなくしたい方にとっては非常に有効な選択肢ですが、それが唯一の答えではありません。
ご家族や親族とよく話し合って、みなさんが納得できる方法を選ぶことが何よりも大切ですね。
墓じまい費用、浄土真宗の金額内訳を解説

浄土真宗の墓じまいにかかる費用は?
さて、ここからは一番気になるお金の話、具体的な費用の内訳を見ていきましょう。浄土真宗の墓じまい費用は、大きく分けて「お墓の撤去」「行政手続き」「新しい納骨」の3つのカテゴリーで費用が発生します。
全体の相場としては、30万円~300万円程度と幅がありますが、これは新しい納骨先に何を選ぶかによって大きく変わるためです。
まずは、それぞれの内訳を詳しく見ていきましょう。
| 費用の種類 | 内容 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 墓石の撤去費用 | 墓石を解体し、更地に戻す工事の費用。 | 1㎡あたり10万円~15万円 |
| 法要に関する費用 | 遷仏法要のお布施や、離檀する場合の離檀料。 | 5万円~20万円程度 |
| 行政手続き費用 | 改葬許可証の取得に必要な書類の発行手数料など。 | 数百円~数千円程度 |
| 新しい納骨先の費用 | 永代供養墓、樹木葬、納骨堂などの費用。 | 5万円~150万円以上 |
注意点
墓石の撤去費用は、お墓の立地(重機が入りにくい場所など)や石の量によって変動します。また、お寺によっては石材店が指定されている場合もあるため、事前に管理者へ確認が必要です。
墓じまい費用の総額と補助金について

前述の通り、墓じまい費用の総額は、新しい納骨先の選択によって大きく変動します。例えば、最も費用を抑えられる合祀墓(ごうしぼ:他の方の遺骨と一緒に埋葬されるお墓)であれば、総額30万円程度で済む場合もあります。
一方、個別の永代供養墓や都心部の納骨堂などを選ぶと、150万円以上になることもあります。
「少しでも費用を抑えたい…」というのが本音ですよね。そこで気になるのが補助金の存在です。結論から言うと、国からの補助金制度はありませんが、自治体によっては独自の補助金や助成金制度を設けている場合があります。
これは、管理されなくなったお墓(無縁仏)を減らすための取り組みの一環です。ただし、制度がある自治体はまだ少なく、条件も様々です。
一度、ご自身のお墓がある市区町村の役所のホームページを確認したり、問い合わせてみることをお勧めします。もしかしたら、対象になるかもしれませんよ。
墓じまいに必要な「改葬許可」の手続きについては、厚生労働省のウェブサイトにも情報が掲載されていますので、参考にしてみてください。(出典:厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律の概要」)
浄土真宗の墓じまいのお布施と閉眼供養
繰り返しになりますが、浄土真宗では閉眼供養は行いません。その代わりに行うのが「遷仏法要(せんぶつほうよう)」です。この法要の際、僧侶に依頼してお勤めいただき、お渡しするのがお布施です。
お布施の金額に決まりはありませんが、一般的な相場としては3万円~10万円程度とされています。これは、これまでお墓を守っていただいた感謝の気持ちを表すものです。
菩提寺との関係性や地域によっても異なりますので、もし金額に迷うようであれば、親族に相談したり、石材店の方に地域の相場を尋ねてみるのも良いでしょう。
お布施は、白い封筒か奉書紙に包み、表書きは「お布施」または「永代経懇志」などと書きます。僧侶に直接手渡しするのがマナーです。
墓じまい費用、浄土真宗大谷派の場合

浄土真宗には、本願寺派(お西さん)や真宗大谷派(お東さん)など、いくつかの宗派があります。「宗派によって費用は変わりますか?」という質問もいただきますが、これも大きな違いはありません。
例えば、真宗大谷派の墓じまいであっても、基本的な費用の内訳(墓石撤去、法要、新しい納骨先)は同じです。
法要の呼び方が「遷座法要」となったり、儀式の作法に細かい違いはありますが、それによってお布施の金額が倍になる、といったことは通常考えられません。
ただし、本山納骨を希望する場合の納骨先は異なります。真宗大谷派の場合は、京都にある「大谷祖廟(おおたにそびょう)」が本山納骨の場所となります。費用や手続きについては、公式サイトなどで確認が必要です。
詳細な情報については、真宗大谷派(東本願寺)の公式サイトでご確認いただけます。(出典:真宗大谷派(東本願寺)公式サイト「大谷祖廟」)
浄土真宗の離檀料はいくらですか?
墓じまいをすると、これまでお世話になった菩提寺との関係を終える「離檀(りだん)」をすることになります。その際に、感謝の気持ちとしてお渡しするのが離檀料です。
離檀料も、お布施と同様に金額が決まっているわけではありませんが、一般的な相場は5万円~20万円程度、あるいは年間管理費の3~5年分などが目安と言われています。これも、お寺との関係性や地域の慣習によって大きく異なります。
離檀トラブルに注意!
残念ながら、離檀の際に高額な離檀料を請求されるといったトラブルも耳にします。離檀料はあくまで「感謝の気持ち」であり、法的な支払い義務はありません。
しかし、一方的に支払いを拒否すると、墓じまいに必要な「埋蔵証明書」の発行をしてもらえないなど、手続きが滞る原因にもなりかねません。
トラブルを避けるためにも、墓じまいを決めたら、まずはご住職に真摯に事情を説明し、円満な話し合いを心がけることが最も大切です。
もし話し合いがこじれてしまった場合は、石材店や行政書士などの専門家に相談するのも一つの方法です。
墓じまい費用についてよくあるご質問FAQ
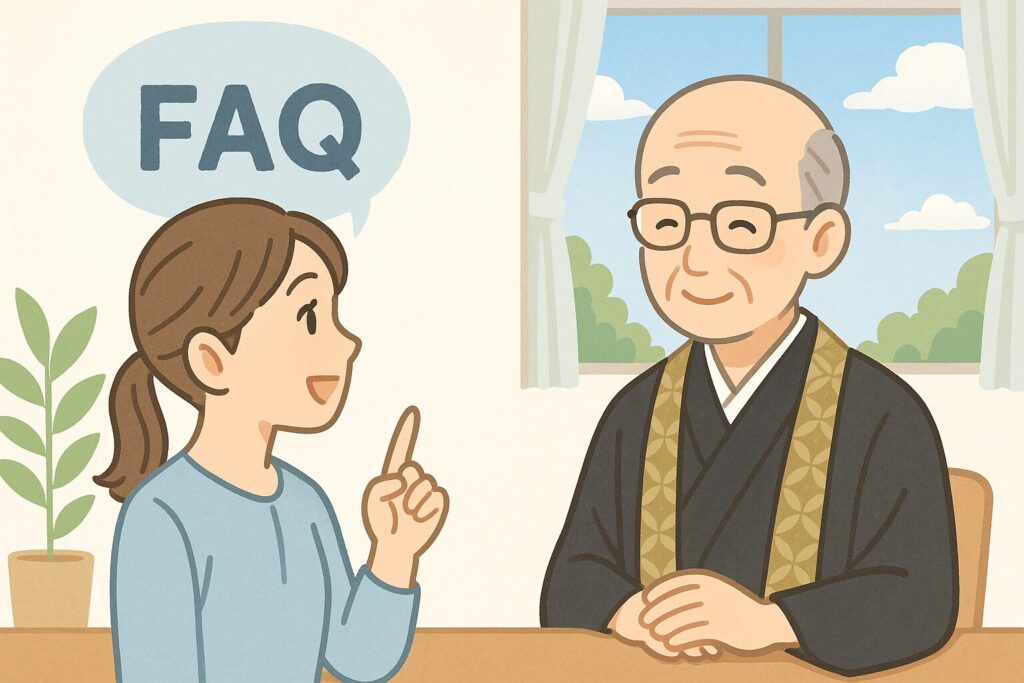
- 浄土真宗の墓じまい、何から始めたらいいですか?
-
まずは、ご家族やご親族との話し合いから始めるのが一番です。お墓はご自身だけのものではありません。なぜ墓じまいをしたいのか、その後の供養はどうするのかを丁寧に説明し、皆様の合意を得ることが、トラブルなく進めるための最大のポイントです。その後、現在の墓地の管理者に相談し、新しい納骨先を探す、という流れになります。
- 離檀料を払わないと、墓じまいはできませんか?
-
法的には離檀料に支払い義務はありません。しかし、支払わないことでお寺との関係が悪化し、墓じまいに必要な書類(埋蔵証明書)の発行を拒否されるなど、手続きが困難になる可能性があります。高額な請求など問題がある場合は別ですが、基本的にはこれまでお世話になった感謝の気持ちとして、相場の範囲内でお渡しするのが円満な解決につながります。
- 墓石を撤去せず、そのままにしておくことはできますか?
-
墓地の使用契約を続ける限りは可能ですが、管理費を滞納し続けると、最終的には墓地管理者によって無縁仏として整理されてしまう可能性があります。その場合、ご遺骨は合祀墓に移され、二度と取り出すことはできなくなります。将来的に管理できなくなることが分かっている場合は、ご自身の代で責任をもって墓じまいをされることをお勧めします。

です。墓じまいは、物理的なお墓を片付けるだけでなく、ご先祖様から受け継いできた歴史や家族の想いを整理する大切な機会でもあります。費用や手続きはもちろん重要ですが、「なぜ墓じまいをするのか」「これからどうしていきたいのか」をご家族で共有する時間をぜひ大切にしてください。それが、皆さんにとって最良の選択につながるはずです。何か困ったことがあれば、一人で抱え込まず、専門家を頼ることも忘れないでくださいね。あなたの新しい一歩を応援しています。
墓じまい費用浄土真宗のポイントまとめ
- 浄土真宗では「往生即成仏」の教えからお墓に魂は宿らないと考える
- そのため墓じまいでは「閉眼供養」の代わりに「遷仏法要」という儀式を行う
- 宗派による墓じまい費用の総額に大きな違いはない
- 費用の大半は墓石撤去費用と新しい納骨先の費用で決まる
- 厳密には「永代供養」の概念はないが実質的に同様の永代経がある
- 墓じまい後の供養方法は永代供養以外にも樹木葬や手元供養など様々
- 費用の総額は30万円から300万円と納骨先により大きく変動する
- 国からの補助金はないが自治体によっては独自の制度がある場合も
- 遷仏法要のお布施相場は3万円から10万円程度
- 離檀料の相場は5万円から20万円程度が目安
- 真宗大谷派など宗派が違っても費用に大きな差はない
- トラブル回避のためには親族と菩提寺への丁寧な相談が最も重要
- 離檀料は法的な義務はないが円満解決のために支払うのが一般的
- 高額請求などのトラブル時は専門家への相談も視野に入れる
- 何から始めるか迷ったらまずは家族や親族への相談から
▼あわせて読みたい関連記事▼
- 墓じまい知恵袋:費用・手続きの疑問を解決!
- 【例文あり】墓じまい挨拶状例文|書き方と親戚トラブル回避術
- 永代供養簿はどんなお墓?費用とメリット・デメリットを解説
- 東本願寺永代供養費用まとめ|後悔しない納骨のために知るべきこと
- 浄土真宗線香寝かせると消える理由と対策|知らないと損する基本知識

お気軽にご相談ください
相続は100人いれば、100通り
唯一無二の最適な相続をご提案いたします
CONTACT
専門家やえさん

- 専門家やえさん
-
堀川 八重(ほりかわ やえ)
大阪不動産・FPサービス株式会社 代表
15年以上にわたり1,500組を超えるご家族の相続や不動産のお悩みに、専門家として寄り添ってまいりました。私の信条は、法律や数字の話をする前に、まずお客様ご家族の歴史や言葉にならない想いを丁寧に「聞く」こと。信頼できる各分野の専門家チームと共に、皆様が心から安心できる最善の道筋をオーダーメイドでご提案します。一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。
最新の投稿
 お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説
お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説 相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説
相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説 お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例
お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例 お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説
お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説






