こんにちは!最近、実家の片付け、いわゆる実家じまいについて考え始めたんです。そうすると、自然とお墓のことも気になってきますよね。「うちのお墓、この先どうしよう…」なんて。いざ墓じまいを決意しても、次から次へと疑問が湧いてきませんか?
そもそも「墓じまい」の丁寧な言い方ってあるのかしら?とか、墓じまいをするにあたって親族の同意はどこまで必要なの?なんて悩みますよね。それに、手続きに必要な墓じまい同意書の書き方なんて、学校では教えてくれませんでしたし(笑)。
手続きと並行して考えないといけないのが、関係各所へのご挨拶です。これまでお世話になったお寺への手紙や、墓石の撤去をお願いする石屋さんへのお礼もきちんとしたいものです。
親戚への墓じまい案内状はもちろん、改葬した場合は、新しいお墓の場所を教える手紙も必要になります。永代供養にするなら、その旨を伝える挨拶状も考えないといけません。
もう、考えただけで頭がパンクしそう!結局、墓じまいの挨拶文の例文はどこを見ればいいの?墓じまいのお礼状ってどう書くの?…そんな、終活の「?」でいっぱいになっているあなたのための記事です。この記事を読めば、きっとスッキリしますよ!
この記事のポイント
- 墓じまい挨拶状の基本的な書き方とマナーがわかる
- 送る相手や状況に応じた具体的な例文が見つかる
- 親族とのトラブルを避けるための事前準備が理解できる
- お寺や石材店など関係者へのお礼状の書き方も学べる

墓じまいを考えるとき、多くの方が手続きや費用に目が行きがちですが、実は最も大切なのは「関わる方々への心配り」です。ご先祖様が繋いでくれたご縁を大切にし、親戚やお寺様と丁寧に対話を重ねることが、円満な墓じまいの第一歩。手続き書類も大切ですが、まずは「ありがとう」の気持ちを伝える手紙から準備を始めてみてはいかがでしょうか。その想いが、きっと皆さんの心を繋いでくれますよ。
目次
墓じまい挨拶状例文の基本と事前準備

「墓じまい」の丁寧な言い方は?
墓じまいという言葉、最近よく耳にしますが、いざ親戚や目上の方に伝えるとなると「この言葉でいいのかしら?」と少し不安になりますよね。結論から言うと、「墓じまい」という言葉を使っても失礼にはあたりません。
ただ、より丁寧に、そしてこちらの事情を汲んでもらいやすくするためには、少し言葉を添えるのがおすすめです。言葉の選び方一つで、相手に与える印象は大きく変わりますからね。
私も最初は「お墓を閉めることになりました」なんて、ちょっと直接的すぎるかな?と悩んだんです。でも、難しく考えすぎなくても大丈夫ですよ。
言い換え・丁寧な表現の具体例
単に「墓じまいします」と伝えるのではなく、以下のような表現を使うと、より丁寧な印象になります。
- お墓を整理させていただくことになりました
- 墓所を返還することにいたしました
- 先祖代々のお墓を閉じることになりました
これらの表現に加えて、「誠に勝手ながら」や「大変恐縮ですが」といったクッション言葉を添えると、さらに相手を敬う気持ちが伝わります。挨拶状や手紙では、こうした細やかな配慮がとても大切になりますよ。
ポイント:理由を簡潔に添える
なぜ墓じまいをするのか、その理由を簡潔に伝えることも重要です。「お墓が遠方で管理が難しくなり…」や「後継者がいないため…」といった具体的な理由を添えることで、相手の理解を得やすくなります。家族や親戚も、事情が分かれば納得してくれるはずです。
墓じまい 親族の同意と同意書の書き方

墓じまいを進める上で、最大の難関とも言えるのが「親族の同意」です。お墓は、法律上は祭祀承継者(お墓を主宰する人)の所有物ですが、感情的には「一族みんなのもの」と考えている方が多いですからね。ここでつまずかないように、慎重に進めていきましょう。
同意を得るべき親族の範囲は?
「親族の同意はどこまで必要?」これは本当に悩ましい問題です。法律で明確に定められているわけではありませんが、一般的には「お墓に納骨されている方からみて、血縁の近い親族」には事前に相談し、同意を得ておくのが望ましいとされています。
具体的には、ご自身の兄弟姉妹、両親の兄弟姉妹(叔父・叔母)、そしてその子ども(いとこ)あたりまでが目安でしょうか。特に、これまで熱心にお墓参りをしてくれていた方には、必ず声をかけるようにしましょう。連絡を怠ると、後々「聞いてない!」と大きなトラブルに発展しかねません。
注意:連絡がつかない親戚への配慮
疎遠になっている親戚がいる場合でも、可能な限り連絡を取る努力をしましょう。手紙を送るなど、「こちらとしてはきちんと連絡しようとしました」という姿勢を示すことが大切です。誠意ある対応が、万が一のトラブルを防ぐ防波堤になります。
墓じまい同意書の書き方
親族から同意が得られたら、「墓じまい同意書」を作成しておくと安心です。これも法律で義務付けられているわけではありませんが、後々のトラブル防止や、霊園・墓地の管理者から提出を求められるケースがあるため、準備しておくとスムーズです。
決まった書式はありませんが、以下の項目を盛り込んでおけば問題ないでしょう。
| 項目 | 記載内容の例 |
|---|---|
| 対象となるお墓の情報 | 〇〇霊園 〇区〇番 〇〇家之墓 |
| お墓の承継者 | 住所・氏名 |
| 同意の内容 | 上記のお墓を墓じまいし、遺骨を(改葬先の名称)へ改葬することに同意いたします。 |
| 同意者の署名・捺印 | 同意年月日、住所、氏名、承継者との続柄、捺印 |
同意書は、墓じまいや改葬手続きの円滑化、そして何より「家族・親戚間でしっかりと話し合い、合意の上で進めました」という証になります。ぜひ作成しておくことをおすすめします。
参考情報サイト:法務省「親族の範囲」
URL: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji15.html
事前に送る墓じまい案内状について
親族への根回しが済み、墓じまいの具体的な日程が決まったら、次は「案内状」の出番です。これは、墓じまいが完了した後に送る「挨拶状(報告の手紙)」とは少し役割が異なります。
案内状の主な目的は、「墓じまいの日程や閉眼供養(魂抜き)の法要について事前にお知らせすること」です。特に、法要に参列してほしい親戚がいる場合には、必ず送る必要があります。
事前の案内と事後の報告、2回も手紙を出すのは少し手間に感じるかもしれません。でも、このひと手間が、親戚との良好な関係を保つ秘訣だったりするんですよ。
案内状に記載すべき内容
案内状は、あまり長文にする必要はありません。時候の挨拶とともに、以下の情報を簡潔に記載しましょう。
- 墓じまいを行う旨とその理由
- 閉眼供養の日時と場所
- 出欠の確認(返信期限を設けると親切です)
- 服装や持ち物について(平服で良い、など)
- 墓じまい後の供養先(決まっている場合)
特に、遠方から来ていただく方のためにも、場所の地図を同封したり、会食の有無を記載したりすると、より親切な案内状になります。相手の立場に立った丁寧な案内を心がけたいですね。
墓じまいの挨拶文の基本的な例文は?
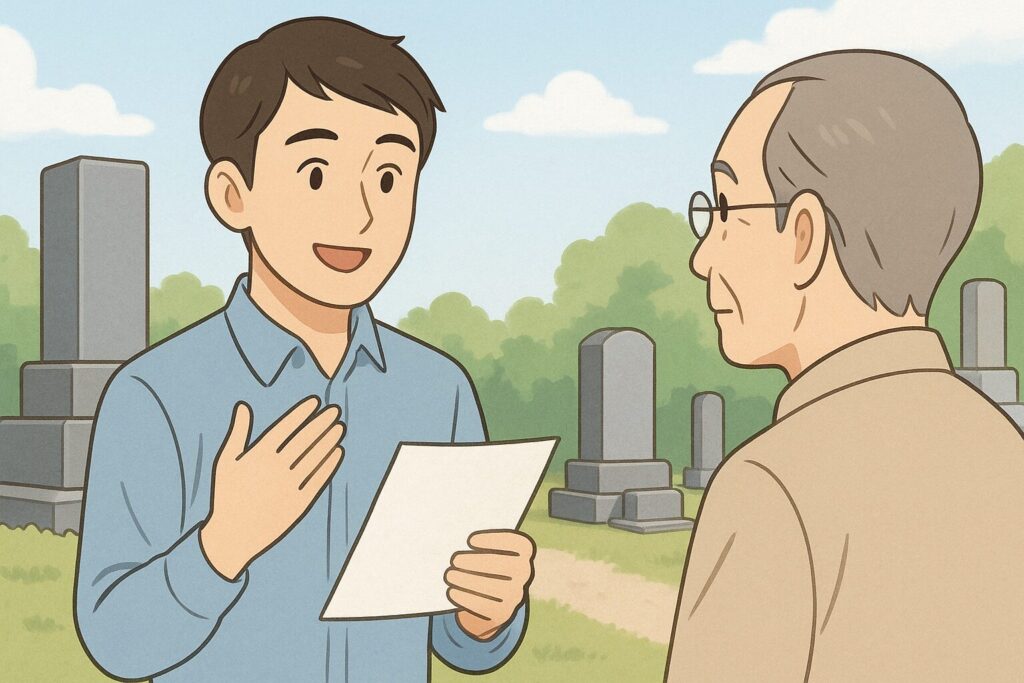
さて、いよいよ墓じまいが無事に完了した後に送る「挨拶状」の基本例文をご紹介します。これは、墓じまいを執り行ったことを親戚やお世話になった方々へ正式に報告するための大切な手紙です。
ポイントは、①墓じまいを完了した報告、②その理由、③これまでの感謝、④今後の供養先、この4つの要素を分かりやすく盛り込むことです。
【基本例文】墓じまい完了の挨拶状
拝啓 〇〇の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
さて、かねてより懸案となっておりました〇〇家先祖代々の墓所(〇〇県〇〇霊園)につきまして、去る〇月〇日に墓じまいを滞りなく執り行いましたことをご報告申し上げます。
墓所が遠方にあり、お墓参りや管理を続けることが困難になったため、家族で相談を重ねた結果、このような決断に至りました。皆様には、長年にわたりお墓をお守りいただき、心より感謝申し上げます。
なお、ご先祖様の遺骨は、新たに〇〇(新しい供養先の名称)にて永代供養を執り行うこととなりました。皆様にはご心配をおかけいたしましたが、これからは私どもの住まいの近くで、心を込めて供養を続けてまいります。
誠に勝手ながら、書中をもちましてご挨拶とさせていただきます。今後とも変わらぬお付き合いを賜りますようお願い申し上げます。
敬具
令和〇年〇月〇日
住所
氏名
この例文をベースに、ご自身の状況に合わせて文章を調整してみてください。大切なのは、誠意と感謝の気持ちを込めて自分の言葉で綴ることです。
新しいお墓の場所を教える手紙
墓じまいの挨拶状の中でも、特に重要なのが「新しい供養先をお知らせする」部分です。前述の基本例文にも含まれていますが、より丁寧に伝えたい場合は、挨拶状とは別に案内状を作成したり、挨拶状に詳細な情報を記した別紙を同封したりすると良いでしょう。
「お墓がなくなって、どこに手を合わせればいいのか分からなくなった…」と親戚を不安にさせないための、大切な配慮ですね。
せっかく新しい場所で供養するのですから、「いつでもお参りに来てくださいね」という気持ちが伝わるようにしたいですよね。
記載すると親切な情報
新しい供養先の情報を伝える際には、以下の点を明記すると、受け取った方がお墓参りをしやすくなります。
- 霊園や納骨堂の正式名称
- 詳しい住所
- 連絡先の電話番号
- 最寄り駅からのアクセス方法や駐車場の有無
- 開園時間やお参りの作法(お花やお線香の決まりなど)
- 現地の分かりやすい地図
霊園や寺院が発行しているパンフレットがあれば、それを同封するのも非常に良い方法です。新しい供養先がどんな場所なのかが写真で分かると、親戚の方々もより一層安心してくれるはずです。

墓じまいは、物理的にお墓を整理するだけではありません。それは、ご先祖様との向き合い方、そしてこれからの家族の供養の形を再構築する大切な機会です。挨拶状ひとつとっても、どの親戚に、どんな言葉で伝えるか、家族で話し合う時間そのものが、家族の絆を深めることに繋がります。この機会を、ぜひご家族の未来を考えるポジティブなステップと捉えて、丁寧に進めていってくださいね。
墓じまいの挨拶に関するQ&A
-
挨拶状はいつ送るのがベストタイミングですか?
-
墓じまいのすべての作業(お墓の撤去、新しい場所への納骨など)が完了してから、1ヶ月以内を目安に送るのが一般的です。あまり時間が経ちすぎないうちに、きちんと報告することが大切です。
-
電話やメールでの挨拶は失礼にあたりますか?
-
ごく親しい間柄であれば、まずは電話で一報を入れるのも良いでしょう。ただし、墓じまいという大切な節目ですので、電話やメールだけで済ませるのではなく、後日改めて書面(封書やハガキ)で挨拶状を送るのが丁寧なマナーです。形に残るもので報告することで、誠意が伝わります。
-
挨拶状を送る範囲は親戚だけですか?
-
基本的には親戚が中心ですが、故人と特に親しかったご友人や、生前お世話になった方など、これまでお墓参りに来てくださっていた方々にも送ると良いでしょう。誰に送るべきか迷った場合は、ご両親や他の親戚に相談してみることをおすすめします。
墓じまい挨拶状例文と礼状ケース別で見る
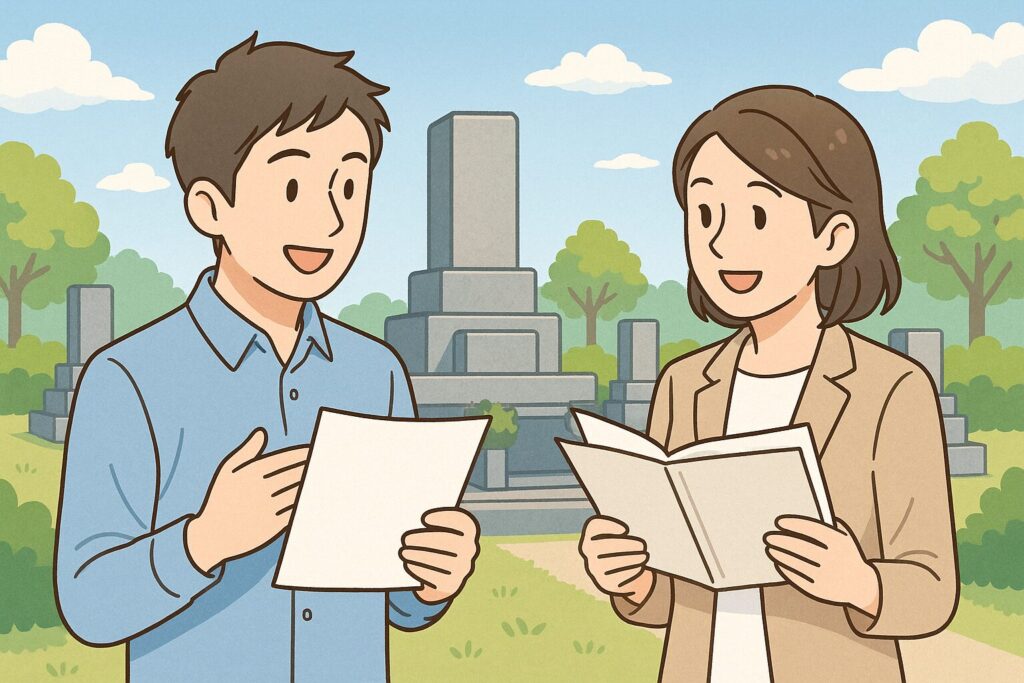
永代供養を選んだ際の挨拶状
墓じまい後の供養方法として、「永代供養」を選ぶ方が増えています。お墓の承継者がいない場合や、残された家族に負担をかけたくない場合に選ばれることが多いですね。挨拶状では、なぜ永代供養を選んだのか、そしてそれがご先祖様にとって良い供養になるという点を丁寧に説明することが大切です。
【例文】永代供養の報告
(前文は基本例文と同様)
さて、この度の墓じまいに伴い、ご先祖様の遺骨は〇〇寺の永代供養墓に合祀させていただき、今後はご住職様のもとで永代にわたり手厚くご供養いただくこととなりました。
私どももこれからは安心してお任せすることができ、故人も安らかに眠ってくれるものと安堵しております。皆様にもご安心いただければ幸いです。
(後文は基本例文と同様)
挨拶状では、「無縁仏になるのでは?」という親戚の心配を払拭することがポイントです。「お寺や霊園が責任を持って供養してくれる」という点を明確に伝えることで、皆さんに安心してもらえます。
改葬のお知らせに使える例文

「改葬」とは、お墓のお引越しのこと。遠方にあったお墓を、自宅の近くなど、お参りしやすい場所に移すケースですね。この場合は、「お墓がなくなった」のではなく「お参りしやすい場所に移った」というポジティブな報告になります。
【例文】改葬の報告
(前文は基本例文と同様)
さて、この度の墓じまいに伴い、〇〇霊園(旧墓所)にありましたご先祖様の遺骨を、新たに私どもの住まいに近い〇〇霊園(新墓所)へと移転(改葬)いたしました。
これまでは墓所が遠く、思うようにお墓参りができず心苦しく思っておりましたが、これからはいつでも足を運べるようになり、ご先祖様も喜んでくれていることと存じます。
お近くにお越しの際は、ぜひ新しいお墓にお参りいただければ幸いです。
(後文は基本例文と同様、新しい墓所の地図などを同封)
改葬の挨拶状では、「これからは、より手厚く供養ができます」という前向きな姿勢を伝えることが、親戚の理解と安心に繋がります。
実家じまいの挨拶状に使える例文
近年は、ご両親が亡くなったり施設に入居されたりしたタイミングで、実家を整理する「実家じまい」と「墓じまい」を同時に進めるケースも増えています。その場合、挨拶状もまとめて一通で報告することが多いでしょう。
この場合の挨拶状は、「実家をたたむこと」と「お墓をしまうこと」の二つの大きな報告を、分かりやすく伝える必要があります。情報量が多くなるので、何がどうなったのかを明確に記載することが大切です。
【例文】実家じまいと墓じまいを併せて報告
(前文は時候の挨拶)
さて、この度、父〇〇の逝去(あるいは施設入居)に伴い、長年皆様にご厚情を賜りました〇〇(地名)の住まいを整理し、実家をたたむことといたしました。
それに伴い、先祖代々のお墓の管理も困難となりましたため、〇〇霊園にありました墓所も墓じまいをさせていただきましたことを併せてご報告申し上げます。
(今後の供養先についての説明が続く)
皆様には、長きにわたり実家並びにお墓のことで大変お世話になりましたこと、家族一同、心より御礼申し上げます。
(後文が続く)
少し寂しいご報告にはなりますが、これまでの感謝の気持ちをしっかりと伝え、今後の連絡先なども明記しておくことで、丁寧なご挨拶となります。
墓じまいのお礼状を送る相手と文例

墓じまいに際して、閉眼供養の法要などに参列していただいた親戚や、特に相談に乗ってもらった方には、挨拶状とは別に、あるいは挨拶状に一筆添える形で、個別のお礼状をお送りするとより丁寧です。
「あの時はありがとう」の一言があるだけで、受け取った側はとても嬉しい気持ちになるものです。人間関係を円滑にする魔法の言葉ですね!
お礼状に決まった形式はありませんが、感謝の気持ちがストレートに伝わるような、心のこもった文章を心がけましょう。相続の際のお礼状も参考になりますので、こちらの記事も併せてご覧ください。
【文例】法要に参列いただいた方へのお礼
先日はご多忙の折、〇〇家の墓じまいに伴う閉眼供養にご列席いただき、誠にありがとうございました。
おかげさまで、滞りなくご先祖様のご供養を執り行うことができました。〇〇様にお見送りいただけたこと、ご先祖様もさぞ喜んでいることと存じます。
心ばかりの品をお贈りいたしましたので、どうぞご笑納ください。
今後とも変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。
このように、具体的なお礼の言葉を添えることで、相手への感謝の気持ちがより深く伝わります。
お寺への手紙と石屋さんへのお礼
親戚への挨拶と同時に忘れてはならないのが、お世話になったお寺(菩提寺)や、墓石の撤去工事を依頼した石材店へのお礼です。これまで先祖代々の供養をしていただいたお寺には、感謝の気持ちを込めた手紙(お礼状)をお渡しするのがマナーです。
お寺への手紙(離檀の挨拶)
墓じまいに伴い、お寺との檀家関係がなくなることを「離檀(りだん)」と言います。これまでのお礼とともに、離檀の挨拶を丁寧に行いましょう。離檀料をお渡しする際に、手紙を添えるとより気持ちが伝わります。
【文例】お寺(ご住職様)への手紙
拝啓 〇〇の候、〇〇寺様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、この度は私どもの都合により、先祖代々のお墓を墓じまいすることとなり、長年お世話になりました檀家を離れることとなりました。
これまでのご厚情に深く感謝申し上げますとともに、何卒ご容赦いただけますようお願い申し上げます。
末筆ではございますが、貴寺の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。
敬具
石材店へのお礼
墓石の撤去工事は、ご先祖様が眠っていた場所を更地に戻す、墓じまいの最終段階となる大切な作業です。工事が無事に完了したら、石材店の方にも一言お礼を伝えるのが良いでしょう。電話でも構いませんし、お礼状をお送りすれば、より丁寧な印象になります。「丁寧な作業、ありがとうございました」の一言が、お互い気持ちの良い締めくくりに繋がります。
まとめ:最適な墓じまい挨拶状例文とは

この記事では、墓じまいの挨拶状について、基本的なマナーから具体的な例文まで詳しく解説してきました。最後に、円満な墓じまいを実現するためのポイントをまとめておきましょう。
- 墓じまいを伝える際は丁寧な言葉遣いを心がける
- 親族への事前相談と同意はトラブル回避の鍵
- 同意書を作成しておくと後々の安心材料になる
- 事前の案内状と事後の挨拶状は役割が異なる
- 挨拶状には報告・理由・感謝・今後の供養先の4点を盛り込む
- 新しいお墓の情報は分かりやすく地図などを添える
- 永代供養の場合は安心感を伝える説明を加える
- 改葬の場合はお参りしやすくなるポジティブな報告にする
- 実家じまいと同時に報告する場合は情報を整理して伝える
- 法要参列者には個別にお礼状を送るとより丁寧
- お世話になったお寺や石材店への感謝も忘れない
- 挨拶状はご自身の言葉で誠意を込めて綴ることが最も大切
- タイミングを逃さず墓じまい後1ヶ月以内を目処に送る
- 電話やメールだけでなく書面で報告するのが正式なマナー
- 挨拶状はご先祖様が繋いだ縁を大切にするためのツールである
墓じまいは、単なる手続きではありません。家族や親戚、ご先祖様との絆を見つめ直す大切な機会です。この記事が、あなたの円満な墓じまいの一助となれば幸いです。

墓じまいと挨拶状の作成、本当にお疲れ様でした。一連の作業を通して、ご先祖様のこと、家族のこと、そしてご自身の未来について、深く考える時間になったのではないでしょうか。供養の形は時代と共に変わっていきますが、大切な人を想う心は変わりません。あなたが心を込めて選んだ新しい供養の形は、きっとご先祖様にも届いているはずです。これからは、より身近になったご先祖様との対話を楽しんでくださいね。
▼あわせて読みたい関連記事▼
終活とは何か?始め方がわかる!やることリスト完全版
相続権どこまで?法定相続人の範囲と順位を図解でやさしく解説
相続した実家、売却か賃貸か?判断ミスで損しないための全知識
永代供養簿はどんなお墓?費用とメリット・デメリットを解説
お墓の花は一対でないとダメ?現代マナーと失礼にならない供え方

お気軽にご相談ください
相続は100人いれば、100通り
唯一無二の最適な相続をご提案いたします
CONTACT
専門家やえさん

- 専門家やえさん
-
堀川 八重(ほりかわ やえ)
大阪不動産・FPサービス株式会社 代表
15年以上にわたり1,500組を超えるご家族の相続や不動産のお悩みに、専門家として寄り添ってまいりました。私の信条は、法律や数字の話をする前に、まずお客様ご家族の歴史や言葉にならない想いを丁寧に「聞く」こと。信頼できる各分野の専門家チームと共に、皆様が心から安心できる最善の道筋をオーダーメイドでご提案します。一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。
最新の投稿
 お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説
お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説 相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説
相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説 お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例
お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例 お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説
お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説






