「専業主婦遺族年金ずるい」と検索された方へ。ご自身の年金や将来の生活に不安や疑問を感じていらっしゃるのではないでしょうか。最近では、遺族年金の構造が「専業主婦の方が得」とされる背景や、共働き世帯との制度上の格差に注目が集まっています。
特に、専業主婦で夫が死亡した場合の遺族年金の受給額や、65歳以上・70歳以上の受給条件、さらには子なし専業主婦が対象となるかどうかなど、知っておくべき情報は多岐にわたります。
加えて、遺族厚生年金の金額早見表や、2025年の遺族年金改正、さらには「年金 専業主婦 3号 廃止」「専業主婦年金の廃止はいつからですか?」といった将来的な変更の可能性まで、気になる点が山積みです。この記事では、それらの疑問に丁寧にお答えしていきます。
この記事のポイント
- 専業主婦が遺族年金で優遇されている仕組み
- 共働き世帯が遺族年金で不利になる理由
- 子なしや高齢専業主婦の遺族年金受給条件
- 遺族年金や第3号被保険者制度の見直し動向
専業主婦遺族年金ずるいと感じる理由とは

遺族年金 専業主婦の方が得になる仕組み
遺族年金制度は、専業主婦が「得」と感じやすい構造になっています。
そう聞くと、「働いてきた私より、なぜ専業主婦の方が?」と感じる方もいるかもしれません。
しかしこの構図は、決して偶然ではなく、制度設計そのものに起因する歴史的な背景と仕組みにあります。
まず前提として、遺族年金は家計を支える大黒柱を失ったときに、残された家族が生活を維持できるように支給される制度です。
ここでいう「家計を支える者」とは、主に厚生年金に加入していた会社員や公務員の夫を指しています。
つまり、専業主婦である妻が働かずに家計を支えてもらっていた場合、夫が亡くなると生活が立ち行かなくなるため、厚生年金に加入していた夫の保険料によって、妻に遺族厚生年金が支給されるという仕組みです。
一方で、共働き家庭ではどうなるかというと、妻自身も厚生年金に加入し、自分の年金を形成している分、夫が亡くなっても“遺族”としての支給対象からは相対的に不利になります。
これを具体例で見てみましょう。
たとえば夫が厚生年金に40年加入し、老齢年金として月18万円を受給していたとします。
専業主婦で年金の加入歴が少ない妻が夫に先立たれた場合、以下のように支給されます。
| 項目 | 金額(月額) | 備考 |
|---|---|---|
| 遺族厚生年金 | 約13.5万円 | 夫の厚生年金の報酬比例部分の3/4 |
| 老齢基礎年金 | 約6.5万円 | 加入期間が満たされていれば支給 |
合計で月20万円程度が見込まれるケースもあります。
一方、共働きの妻が夫を亡くした場合、どうでしょうか。
妻自身が厚生年金に加入し、すでに自分の老齢厚生年金を受給している場合、遺族厚生年金と併給調整がかかるため、自分の年金と比べて高い方しか受け取れないのです。
たとえば、
- 妻の老齢厚生年金が月14万円
- 夫の遺族厚生年金が月13万円
だった場合、高い方の14万円が支給され、遺族年金の分は打ち切りとなります。
このように、制度上では自分で年金を積み立ててきた共働きの妻のほうが、かえって不利に扱われることがあるのです。
これはまさに、「専業主婦の方が得」と言われる原因のひとつです。
そしてもう一つの要因が中高齢寡婦加算です。
これは、40歳以上65歳未満の妻が子のない状態で夫を亡くしたときに、**年間約61万円(2024年度)**が追加で支給される仕組みです。
共働き世帯の場合、この加算を受けるには妻自身が基礎年金しか受け取れない状態である必要があるため、事実上は専業主婦向けの手当とも言えます。
言ってしまえば、この制度は昭和の「夫が働き、妻が家庭を守る」というライフスタイルをモデルに作られたものであり、現代の共働き世帯の実情とはズレが生じているのです。
こうした制度の“ズレ”は、2025年の見直しで一部是正される方向にありますが、今なお**「専業主婦が得」「共働きが損」**という状況が続いています。
次に、この遺族年金を実際に受け取るための条件について、特に子どもがいない専業主婦の場合に焦点をあてて解説していきます。
子なし 専業主婦 遺族年金の受給条件とは

子どもがいない専業主婦の場合でも、遺族年金を受給できるかどうかは明確な条件があります。
ここでは、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」に分けてわかりやすく説明します。
まず、遺族基礎年金は原則として子どもがいる遺族のみが対象です。
この「子ども」とは、
- 18歳の誕生日後最初の3月末までの子
- または、20歳未満で障害等級1級または2級に該当する子
と定義されています。
そのため、子なしの専業主婦は遺族基礎年金を受給することができません。
ここで重要になるのがもう一つの制度、遺族厚生年金です。
遺族厚生年金の受給条件は以下の通りです。
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 対象者 | 配偶者・子・孫・父母・祖父母のうち、一定の条件を満たす者 |
| 妻の場合 | 年齢・子の有無に関係なく原則受給可能 |
| 受給開始年齢 | 制限なし(ただし再婚などで資格を失う可能性あり) |
たとえば、夫が厚生年金に30年加入し、亡くなったとします。
子どものいない専業主婦である妻は、遺族基礎年金の対象にはなりませんが、夫の老齢厚生年金の4分の3に相当する金額を遺族厚生年金として受け取ることができます。
このように「子がいないから一切受け取れない」と誤解している方も多いのですが、実際には遺族厚生年金がある限り、子の有無に関係なく妻は受給できる可能性が高いのです。
しかしながら注意点もあります。
たとえば、遺族厚生年金の受給資格があっても、妻自身の年金(老齢厚生年金など)との併給調整によって受給額が減る可能性がある点です。
また、再婚すると資格を失うこともあるため、制度の細かい点を事前に理解しておく必要があります。
ちなみに、現在は「配偶者が55歳以上でないと遺族厚生年金を受け取れない」という誤解もありますが、これは男性配偶者(夫)の場合に限られた条件です。
女性(妻)は基本的に年齢にかかわらず受給権があります。
つまり、**「子がいない専業主婦でも、遺族厚生年金を受け取ることはできる」**というのが正しい理解です。
このように制度の概要を整理しておくことで、「私の場合は受け取れるのか?」という疑問にも、しっかりと答えられるようになります。
次は、専業主婦が受け取れる遺族年金の金額やその早見表について、より詳しく見ていきましょう。
専業主婦で夫が死亡した場合、年金はいくらもらえる?
専業主婦の方が夫を亡くした場合、受け取れる年金額は大きく2つに分かれます。
それは「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」です。
ただし、受給の可否や金額には年齢や子どもの有無、夫の加入していた年金制度(厚生年金・国民年金)などによって大きな差が出ます。
まず、専業主婦の方は一般的に**「第3号被保険者」とされており、自身では保険料を納めずに国民年金に加入した形となっています。**
そのため、受給できる遺族年金は、夫が加入していた年金制度に連動して支給されるものになります。
たとえば、夫が会社員や公務員として厚生年金に40年加入していたと仮定した場合、以下のような計算が想定されます。
| 項目 | 支給額(2024年度) | 補足説明 |
|---|---|---|
| 遺族基礎年金 | 約105万円(年額) | 子どもが18歳未満である場合のみ |
| 遺族厚生年金 | 約90万円〜130万円(年額) | 夫の報酬比例部分の3/4程度 |
※なお、遺族基礎年金は子どもがいない専業主婦の場合は支給対象外です。
たとえば、Aさん(専業主婦・年齢60歳)が、会社員だった夫を亡くした場合を例に考えてみましょう。
夫の年金額が年間180万円(うち厚生年金分が120万円)だった場合、Aさんが受け取る遺族厚生年金はその4分の3、つまり年間90万円となります。
子どもがいない場合、これがAさんの唯一の年金収入となります。
ところが、Bさん(同じく専業主婦)には18歳未満の子どもが1人いた場合、遺族基礎年金が加わり年間195万円程度を受け取ることができます。
つまり、子の有無だけで年間で約105万円の差が出ることになります。
これを図にすると、以下のようになります。
【夫が亡くなった後の年金比較(専業主婦の場合)】
| 状況 | 遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 | 合計年金額(年) |
|---|---|---|---|
| 子どもあり | 約105万円 | 約90万円 | 約195万円 |
| 子どもなし | なし | 約90万円 | 約90万円 |
また、40歳以上65歳未満の女性には**中高齢寡婦加算(年間約61万円)**が上乗せされるケースがあります。
たとえば60歳の専業主婦Cさんの場合は、
- 遺族厚生年金:90万円
- 中高齢寡婦加算:61万円
合計で年間151万円の支給が見込まれます。
たとえ話として、こんなシチュエーションも考えられます。
たとえば、定年退職後にのんびり過ごしていたご夫婦がいたとします。
夫が病気で急逝し、収入が絶たれたと感じた妻は「私に年金っていくら入ってくるの?」と年金事務所で相談したところ、子どもがいなければ遺族基礎年金はもらえないと説明され、驚きの表情を浮かべたそうです。
一方で、40代の専業主婦でまだ子どもが高校生だった場合、遺族基礎年金と中高齢寡婦加算の両方が付き、生活費の大きな支えとなっていたと言います。
このように、一見すると「夫が厚生年金に加入していれば安心」と思われがちですが、遺族年金の内容は家庭構成によって大きく異なるため、事前に正確な知識を持つことが大切です。
次に、専業主婦の方が65歳以上になったときに、遺族年金がどうなるのかを詳しく見ていきましょう。
専業主婦 遺族年金 65歳以上はどうなるのか
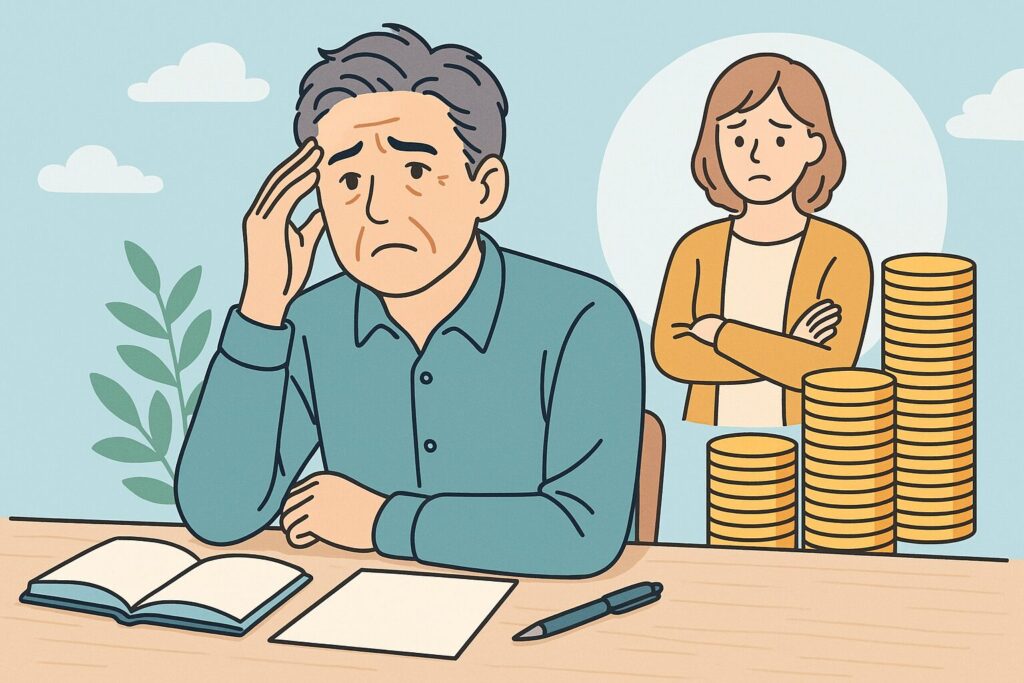
65歳以上になった専業主婦が遺族年金をどう受け取れるのかは、「自分の老齢年金との関係」に大きく左右されます。
特にここで重要なのは、「併給調整」と呼ばれる制度です。
これは、遺族厚生年金と自分の老齢厚生年金を同時に満額で受け取ることができないというルールです。
たとえば、65歳になった時点で専業主婦Dさんに以下のような年金受給があったとしましょう。
| 年金の種類 | 金額(年額) |
|---|---|
| 老齢基礎年金 | 約78万円 |
| 老齢厚生年金 | 約50万円 |
| 遺族厚生年金 | 約90万円 |
このようなケースでは、老齢厚生年金と遺族厚生年金は併給調整がかかり、高い方のみが支給されるため、老齢厚生年金50万円は不支給となり、差額の40万円が遺族厚生年金として支給されるかたちになります。
結果として、実際にDさんが受け取れる年金は、
- 老齢基礎年金:78万円
- 遺族厚生年金(差額調整済):40万円
→ 合計:118万円(年額)
となります。
一方、Dさんが老齢厚生年金を受け取っていなかった場合は、
- 遺族厚生年金:90万円
- 老齢基礎年金:78万円
→ 合計:168万円(年額)
となり、大きな違いが生じます。
この仕組みを知らないと、「65歳になれば、すべての年金が満額で受け取れる」と誤解しがちです。
しかし、実際には年金制度の仕組みによって差し引きされるケースがほとんどです。
たとえば、60代後半の専業主婦Eさんが「これで安心」と思っていた矢先、年金額を確認して驚いたことがありました。
遺族年金と自分の年金の両方が入ると思い込んでいたものの、実際には差額だけしか支給されなかったのです。
このようなことが起きないためにも、事前に日本年金機構や年金事務所に具体的な試算を依頼することが推奨されます。
ちなみに、65歳以降は自分の年金を受け取る人が増えるため、「遺族厚生年金」は徐々に影が薄くなる印象を受けるかもしれません。
ですが、配偶者が老後の生活費の大部分を担っていた場合、残された専業主婦にとって遺族年金は非常に重要な柱です。
特に2025年以降、男女差の見直しや中高齢寡婦加算の段階的な廃止が予定されており、65歳以降の年金受給にも影響が出る可能性があります。
そのため、制度の改正動向にも注意を払いながら、今後のライフプランを見直すことが必要です。
それでは次に、専業主婦でも年金額の早見表があれば便利だと感じる方のために、遺族厚生年金の金額を具体的に把握する方法をご紹介していきます。
遺族年金 夫死亡 70歳以上 専業主婦は損をする?
まず多くの方が疑問に思うのは、**「70歳以上で夫を亡くした専業主婦は、遺族年金で損をしているのではないか?」**という点です。
確かに、年齢や婚姻状況によって受け取れる遺族年金の内容は大きく変わるため、制度をしっかり理解しておかないと「知らないうちに損をしていた」という結果にもなりかねません。
ここでは、専業主婦が高齢で夫を亡くした場合、遺族年金の受給内容がどう変化するのかを詳しく見ていきましょう。
70歳以上の専業主婦は遺族基礎年金を受給できない
まず知っておいていただきたいのが、遺族基礎年金は「子どもがいる配偶者」または「子ども本人」に限られるという点です。
ここでいう「子ども」とは、18歳到達年度末(高校卒業まで)か、障害等級1級または2級の状態にある20歳未満の子どもを指します。
つまり、
- すでに子どもが成人している場合
- 子どもがいない夫婦の場合
このどちらかに当てはまる専業主婦は、遺族基礎年金を一切受け取ることができません。
受給できるのは遺族厚生年金のみ
では、代わりに何がもらえるのかというと、遺族厚生年金です。
これは、亡くなった夫が会社員や公務員として厚生年金に加入していた場合に支給される年金です。
実際に受け取れる金額は、夫が受けていた(または受ける予定だった)老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。
たとえば、夫の厚生年金が年120万円だった場合、
- 年90万円(120万円 × 0.75)が専業主婦の妻に支給される金額となります。
表でまとめると次のようになります:
| 内容 | 金額(例) |
|---|---|
| 夫の老齢厚生年金 | 年120万円 |
| 妻の遺族厚生年金 | 年90万円 |
年齢が70歳以上でも金額は変わらないのか?
よくある誤解として、「70歳を過ぎると遺族年金の額が減るのではないか?」といった声がありますが、年齢によって金額が直接減るわけではありません。
ただし、70歳以上になると、
- 自分の老齢基礎年金や老齢厚生年金をすでに受給している場合が多く、
- 遺族厚生年金との「併給調整」が行われるため、
場合によっては「差額支給のみ」になることがあります。
具体的には、
- 自分の老齢厚生年金が遺族厚生年金より多いと、遺族厚生年金は支給停止
- 自分の老齢厚生年金の方が少なければ、その差額だけが支給
たとえば、妻自身の年金が年間95万円で、夫の遺族厚生年金が90万円の場合:
→ 支給されるのは妻の老齢年金のみで、遺族年金は0円です。
逆に、妻の年金が年70万円だった場合:
→ 夫の遺族年金との差額20万円だけが支給される、という仕組みです。
| 妻の年金 | 夫の遺族厚生年金 | 支給内容 |
|---|---|---|
| 95万円 | 90万円 | 妻の年金のみ(遺族年金なし) |
| 70万円 | 90万円 | 70万+差額20万円=90万円 |
専業主婦が「損をした」と感じやすい3つの理由
1つ目は、遺族基礎年金がもらえないこと。
2つ目は、自分の年金との併給調整で支給額が減ること。
3つ目は、「長年夫を支えたのに報われない」という感情的な不公平感です。
たとえば、30年ずっと家計と子育てを担ってきた専業主婦の方が「自分の年金額が低いから、遺族年金の一部しかもらえない」と知ったとき、複雑な気持ちを抱くのは無理もありません。
しかしながら、これは現行制度が「片働き家庭」を前提とした昭和のモデルに基づいているため、時代とのギャップが生じていることも背景にあります。
制度の今後に注目が必要
近年、男女平等を目的とした制度見直しが進められており、2025年には遺族年金の改正も予定されています。
たとえば、年齢による受給制限や「中高齢寡婦加算」の段階的廃止といった動きがありますので、今後の制度改正によってさらに専業主婦が不利になる可能性もあるでしょう。
したがって、早めに情報を整理しておくことが重要です。
ちなみに、将来的に備える方法として、
- iDeCo(個人型確定拠出年金)
- つみたてNISA
- 保険料控除を活かした私的年金づくり
なども視野に入れると安心です。
それでは次に、制度改正によって専業主婦の受給環境がどう変わるのか、さらに深掘りしていきましょう。
専業主婦遺族年金ずるいと検索する前に知るべき制度の矛盾

専業主婦 遺族年金 廃止の議論と今後の動向
専業主婦の遺族年金については、「制度が時代に合っていないのではないか」という声が、年々強まっています。
この背景には、家庭の在り方や働き方が多様化した現代社会と、制度が想定していた「昭和型の家族モデル」とのズレがあります。
かつては「夫は会社員として厚生年金に加入し、妻は家庭を守る」という構図が一般的でした。
このとき、専業主婦は自ら保険料を支払わずとも、国民年金の第3号被保険者として基礎年金の受給権を得られる制度が整えられてきました。
ところが、現在では共働きが主流となり、「厚生年金に加入して保険料を納めてきた女性の方が損をしているのではないか」という不公平感が社会問題となっています。
たとえば、同じ年収の夫婦であっても、妻が専業主婦なら遺族年金を生涯受け取れるのに対し、夫が専業主夫だった場合には年齢や条件によって受給できないケースもあるのです。
こうした問題を受けて、厚生労働省は2024年に遺族年金制度の見直し案を審議会に提示。
具体的には、以下のような改正が検討されています。
| 改正内容 | 現行制度 | 今後の見直し案(段階的実施) |
|---|---|---|
| 妻の年齢が29歳以下の場合 | 遺族厚生年金は5年のみ支給 | →そのまま維持 |
| 妻の年齢が30歳以上の場合 | 原則「生涯」受給可能 | →段階的に「59歳までの5年限定」へ変更 |
| 中高齢寡婦加算(61.2万円) | 40歳~65歳未満の妻に加算 | →将来的に廃止を検討 |
つまり、今後の制度改正によっては、専業主婦の遺族年金は「生涯保障」から「有期保障」へと変わっていく可能性があるということです。
このような流れは、制度の公平性を重視した調整とも言えますが、年金生活を想定していた世帯には大きな影響を与えるため、慎重な情報収集と対策が求められます。
ちなみに、すでに遺族年金を受け取っている人や、60歳以上の方にはこの見直しの影響はありません。
それでは次に、専業主婦に関係するもう一つの重要な見直し対象である「第3号被保険者制度」の廃止時期について見ていきましょう。
年金 専業主婦 3号 廃止はいつから始まるのか?
「第3号被保険者」は、主に会社員や公務員の配偶者(主に専業主婦)を対象とした特例制度です。
この制度では、専業主婦が自分で保険料を納めなくても、国民年金に加入した扱いとなり、将来的に老齢基礎年金を受け取れるという仕組みになっています。
しかし近年、これが「不公平だ」という批判にさらされています。
たとえば、同じく国民年金に加入している自営業の配偶者や非正規労働者の女性は、自ら毎月16,520円(2024年度)の保険料を納めているにも関わらず、第3号の人は0円で同じ年金額(満額:年78万円)を得られることが問題視されています。
このような背景を受けて、政府や厚労省内では第3号被保険者制度の見直しや廃止がたびたび議論されてきました。
具体的には以下のような意見が出されています。
- 制度の廃止や縮小
- 保険料の一部自己負担化
- 所得に応じた負担方式への移行
- 企業主に対する代替的な補助制度の創設
とはいえ、現時点(2025年4月)で制度廃止の具体的な開始時期は明言されていません。
厚生労働省の方針としては、今後の年金制度全体の改革に合わせて段階的に進める方針であり、次回の財政検証(通常5年ごと、前回は2019年実施)や法改正の動向が大きなカギとなります。
また、制度見直しの影響が大きいため、一律に廃止するのではなく、所得水準や夫婦の就業状況に応じた「選択的な負担調整」が検討される可能性が高いです。
たとえば、共働き世帯の妻がパート勤務からフルタイムに切り替えるタイミングで、保険料の免除から自己負担への移行を促す仕組みが導入されるかもしれません。
なお、今後の国会審議や選挙結果によっては議論の流れが一変する可能性もあるため、柔軟な心構えが必要です。
ちなみに、現行制度では「第3号被保険者」から「第1号」または「第2号」へと変更する場合、自身で手続きを行う必要があります。
次は、こうした見直しの流れのなかで特に注目されている「専業主婦の受け取る遺族年金の金額や条件の変化」について掘り下げていきましょう。
遺族厚生年金 金額 早見表で見る受給額の違い

遺族厚生年金は、会社員や公務員として厚生年金に加入していた夫が亡くなったとき、その収入に応じた金額が遺族に支給される年金です。
この年金の金額は、基本的に「報酬比例部分の4分の3」で決まります。
たとえば、夫が年120万円の厚生年金を受給していたとすれば、遺族はその4分の3である90万円/年(7万5,000円/月)を受給できる仕組みです。
以下の早見表を参考にしてみてください。
| 夫の年間厚生年金額(万円) | 遺族厚生年金(4分の3)万円 |
|---|---|
| 80 | 60 |
| 100 | 75 |
| 120 | 90 |
| 140 | 105 |
| 160 | 120 |
たとえばAさん(70歳・専業主婦)は、会社員だった夫の死亡後、年120万円の厚生年金を基に遺族厚生年金を申請しました。
その結果、年間約90万円が支給され、月額ではおよそ7万5,000円が振り込まれることになりました。
この金額は、厚生年金の加入年数や報酬に応じて増減するため一律ではありません。
同じ年齢や生活環境でも、夫が高収入だった家庭ほど、遺族年金の金額が高くなるのが特徴です。
また、中高齢寡婦加算(年額約61,200円)が適用される条件に該当すれば、さらに上乗せされます。
ただし、この加算も段階的に廃止される方向にあり、将来的には受給できない可能性もあります。
このように、単に「4分の3」と覚えてしまうだけでなく、夫の年金額・加入年数・報酬履歴をふまえて把握しておくことが大切です。
次に、専業主婦の立場から実際にどれくらいの遺族年金がもらえるのかを見ていきましょう。
専業主婦がもらえる遺族年金はどのくらい?
専業主婦が夫を亡くしたときに受給できる年金は、主に**「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」**の2種類があります。
ただし、受給条件によっては片方のみ、または受給ゼロとなる場合もあるため注意が必要です。
1. 遺族基礎年金の対象になるケース
遺族基礎年金は、次のどちらかに該当する必要があります。
- 18歳未満の子がいる配偶者
- 18歳未満の子自身
つまり、子どもがいない、またはすでに成人している専業主婦の場合は、この遺族基礎年金は受け取れません。
たとえば、Bさん(72歳)は成人した子どもしかおらず、遺族基礎年金の対象外でした。
そのため、受給できるのは「遺族厚生年金」のみです。
2. 遺族厚生年金の受給額の目安
こちらは夫の厚生年金の金額の約4分の3です。
仮に夫が厚生年金120万円を受給していた場合、専業主婦の妻は年間で90万円が受給の目安になります。
【比較表】
| 状況 | 年金種類 | 年間金額の目安 |
|---|---|---|
| 子あり・専業主婦 | 基礎+厚生 | 105万円+厚生年金75万 |
| 子なし・専業主婦(65歳) | 厚生のみ | 90万円程度 |
| 子なし・共働き妻(厚生あり) | 自分の老齢厚生年金と調整 | 差額支給(条件あり) |
特に注意が必要なのは、**自分に厚生年金加入歴がある女性(元パートなど)**です。
この場合、65歳を超えると自分の年金と併給調整が入るため、「せっかく夫が残した遺族年金が支給停止になる」ことがあります。
たとえば、Cさん(67歳)は自分の老齢厚生年金が年間80万円ありました。
夫の遺族厚生年金は90万円でしたが、差額の10万円しか受け取れませんでした。
つまり、専業主婦の方が「自分の年金額が低いため、まるまる遺族厚生年金を受け取れる」構造になっており、共働きだった女性からすると「専業主婦の方が得」と感じることもあるわけです。
これらの条件を理解しておくことで、遺族年金制度の不公平感や今後の備えについても、より的確に判断できるようになります。
次に、専業主婦の遺族年金制度が将来的にどのように変化していくか、その最新動向について見ていきましょう。
専業主婦年金の廃止はいつからですか?

「専業主婦年金の廃止」という表現は、正確には「第3号被保険者制度の見直し」を指すことが多いです。この制度は、厚生年金に加入している会社員や公務員の配偶者で、一定の条件を満たす専業主婦(または主夫)が、自ら保険料を納めることなく国民年金に加入できる仕組みです。しかし、近年、この制度の公平性や持続可能性について議論が高まっています。
現在のところ、専業主婦年金(第3号被保険者制度)の廃止が正式に決定されたわけではありません。ただし、政府や有識者の間で見直しの必要性が提起されており、今後の動向に注目が集まっています。
たとえば、厚生労働省の審議会では、制度の見直しについての議論が行われており、具体的な改革案が検討されています。また、2025年の年金制度改正に向けて、制度の持続可能性を高めるための議論が進められています。
このような背景から、専業主婦年金の廃止や見直しがいつから始まるのかは、今後の政策決定や法改正の動向によって左右されることになります。制度の変更が決定された場合でも、一定の経過措置や周知期間が設けられることが予想されます。
したがって、専業主婦年金の廃止がいつから始まるのかについては、現時点では明確な時期は示されていません。今後の政府の発表や報道を注視し、最新の情報を把握することが重要です。
遺族年金の改正は2025年にどうなるのか?
遺族年金は、被保険者が亡くなった際に、その遺族に支給される年金制度です。2025年には、年金制度全体の見直しが予定されており、遺族年金についても改正が検討されています。
具体的な改正内容は、政府の審議会や専門家の意見を踏まえて決定されるため、現時点では確定していません。ただし、以下のような点が議論の対象となっています。
- 支給対象の見直し:現在の遺族年金制度では、主に配偶者や子どもが支給対象となっていますが、家族構成の多様化に対応するため、支給対象の拡大や条件の見直しが検討されています。
- 支給額の調整:遺族年金の支給額について、被保険者の収入や保険料納付状況に応じた柔軟な設定が議論されています。
- 制度の簡素化:複雑な制度設計を見直し、申請手続きの簡素化や支給の迅速化が求められています。
これらの改正は、遺族年金制度の公平性や持続可能性を高めることを目的としています。2025年の年金制度改正に向けて、政府や関係機関の動向を注視し、最新の情報を把握することが重要です。
なお、制度改正が実施された場合でも、既存の受給者に対しては経過措置が設けられることが一般的です。そのため、急激な変更による影響を最小限に抑える配慮がなされることが期待されます。
いずれにしても、遺族年金の改正については、今後の政府の発表や報道を注視し、必要に応じて専門家に相談することが望ましいでしょう。
共働き世帯は遺族年金で損するのか?

共働き家庭の中には、「うちは夫婦ともに厚生年金に加入しているし、将来も安心」と感じている方も多いかもしれません。
しかし、遺族年金の制度設計は“昭和モデル”が基本になっているため、現在の共働き世帯にとっては、思わぬ"損"を感じる場面もあります。
ここでは、その具体的な仕組みや実例をもとに、どこで差が出るのかを丁寧に解説していきます。
遺族年金制度の基本設計は「片働き」想定
遺族年金には大きく分けて「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。
- 遺族基礎年金:国民年金に加入していた人が亡くなった場合に、18歳未満の子どもがいる配偶者または子どもに支給されます。
- 遺族厚生年金:厚生年金に加入していた人が亡くなった場合に、その配偶者・子・父母などに支給されます。
ここで重要なのが、厚生年金加入者の配偶者が、厚生年金に加入していない専業主婦(第3号被保険者)であるケースを前提に制度が構築されてきたという点です。
つまり、専業主婦世帯を想定した制度に、共働き世帯をそのまま当てはめると、バランスが取れなくなってしまうのです。
共働きだと「併給調整」で差が出る

共働き世帯でよく問題になるのが、「併給調整」という仕組みです。
たとえば、夫婦それぞれが厚生年金に加入していた場合、どちらかが亡くなると、遺族厚生年金と自分の老齢厚生年金を両方満額受け取ることはできません。
具体的には、以下のように調整されます。
| 年金種別 | 支給の有無 |
|---|---|
| 老齢基礎年金 | 両方支給される |
| 老齢厚生年金 | 本人の分が支給される |
| 遺族厚生年金 | 差額分のみ支給される |
つまり、遺族厚生年金が自分の老齢厚生年金より高い場合のみ、差額が支給されるしくみになっているのです。
具体例:夫婦ともに会社員だった場合
以下のようなケースを考えてみましょう。
- 夫:厚生年金に40年加入、年金額月20万円
- 妻:厚生年金に20年加入、年金額月12万円
夫が先に亡くなった場合、妻は自身の老齢年金(月12万円)を受給します。
そして、夫の遺族厚生年金は原則として4分の3なので、月15万円相当です。
しかし実際に受け取れるのは、
- 遺族厚生年金(15万円)- 妻の老齢厚生年金(12万円)= 差額3万円
つまり、夫が亡くなったことで増える年金は月3万円にとどまります。
一方、専業主婦だった場合、遺族厚生年金15万円がそのまま受給できるので、月額で12万円と3万円の差が出るのです。
共働き世帯が損を感じる背景

- 制度が専業主婦モデルを想定しており、働いて保険料を納めても恩恵が小さい
- 併給調整のため、自分の年金額が高いと遺族年金が実質的にゼロになるケースがある
- 長寿社会で、女性が長く一人になる期間が増え、年金収入が少ないままになる
こういった背景から、共働き夫婦は、「まじめに保険料を納めていたのに、専業主婦の方が得をしている」という印象を持ちやすくなります。
このように、現行の年金制度では、共働き世帯が損をしているように見える構造が内在しています。
しかしながら、それはあくまで「遺族年金」に限った話であり、トータルの生涯収入で見れば、必ずしも専業主婦の方が得とは限りません。
専業主婦遺族年金ずるいと感じる人が知っておきたい制度の要点まとめ
- 遺族年金制度は専業主婦モデルを前提に設計されている
- 厚生年金に加入していた夫の年金の3/4が遺族厚生年金として支給される
- 共働きの妻には併給調整があり遺族年金を満額もらえない場合がある
- 子どもがいない場合、遺族基礎年金は一切支給されない
- 40歳〜65歳未満の専業主婦には中高齢寡婦加算が支給される
- 共働き世帯は自分の老齢厚生年金があると差額しか遺族年金を受け取れない
- 再婚すると遺族厚生年金の受給資格を失う
- 子どもが成人していると遺族基礎年金の対象外となる
- 老齢厚生年金と遺族厚生年金はどちらか高い方のみが支給される
- 遺族厚生年金の支給額は夫の報酬比例部分に基づくため収入差が出る
- 第3号被保険者制度は現在も維持されているが将来的な廃止議論が進行中
- 2025年の制度改正で中高齢寡婦加算の廃止や支給期間の見直しが予定されている
- 遺族年金の支給内容は世帯構成や本人の年金加入歴によって大きく異なる
- 共働き女性ほど保険料を納めているにもかかわらず損を感じやすい制度設計
- 遺族年金制度全体が「専業主婦が得、共働きが損」という構造を生みやすい
参考
・60歳から良くなる手相の特徴15選|老後に金運・健康運が伸びる線とは
・老後旦那といたくない理由とは?離婚せずにできる現実的対処法
・親の介護ねぎらいの言葉例文15選|励ましではなく心に届く言葉とは
・遺骨ペンダントティファニー後悔しないための選び方ガイド
・お墓の夢宝くじが当たる前兆?夢占いで金運アップを読み解く

お気軽にご相談ください
相続は100人いれば、100通り
唯一無二の最適な相続をご提案いたします
CONTACT
専門家やえさん

- 専門家やえさん
-
堀川 八重(ほりかわ やえ)
大阪不動産・FPサービス株式会社 代表
15年以上にわたり1,500組を超えるご家族の相続や不動産のお悩みに、専門家として寄り添ってまいりました。私の信条は、法律や数字の話をする前に、まずお客様ご家族の歴史や言葉にならない想いを丁寧に「聞く」こと。信頼できる各分野の専門家チームと共に、皆様が心から安心できる最善の道筋をオーダーメイドでご提案します。一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。
最新の投稿
 お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説
お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説 相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説
相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説 お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例
お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例 お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説
お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説






