親の介護をしている方へのねぎらいの言葉、どうかけたら良いか悩まれたことはありませんか?本記事では「親の介護ねぎらいの言葉例文」を中心に、介護をしてる人にかける言葉はどうあるべきかを具体的に解説していきます。
夫の介護をしている人にかける言葉や、介護疲れの人にかける言葉の選び方、さらには介護者へのねぎらいの言葉をどう届けるかについても詳しくまとめています。
また、介護 ねぎらい ビジネスや介護 メール ねぎらい ビジネスのようなビジネスシーンでの配慮表現、夫の介護 ねぎらい メールの文例、親から送る応援メッセージの例は?といった声にも丁寧に応えます。
労いの言葉の手紙の例文は?や親の介護で仕事を休むときの例文は?まで網羅した内容で、初めての方でも安心して読めるように構成しております。
この記事のポイント
- 状況別に適したねぎらいの言葉の選び方
- 介護者を傷つけない言葉の配慮ポイント
- ビジネスやメールでのねぎらい表現の実例
- 手紙で気持ちを伝える具体的な文章構成
目次
親の介護ねぎらいの言葉例文の基本まとめ

親の介護してる人にかける言葉の選び方
介護をしている人にかける言葉は、とても慎重に選ぶ必要があります。
というのも、言葉ひとつでその人の気持ちを軽くも重くもできてしまうからです。
まず大切なのは、「相手が今どんな気持ちか」を想像することです。
親の介護をしている方の多くは、家族に対する責任感から「自分がやらなければ」と感じています。
そのため、疲れていても弱音を吐けない状況にある方が少なくありません。
たとえば、あなたが「がんばってね」と何気なく声をかけたとします。
その言葉は応援のつもりだったとしても、介護者にとっては「まだ頑張らなきゃいけないのか」と感じさせるプレッシャーになることもあります。
そこで、おすすめの言葉としては次のようなものがあります。
- 「いつも気にかけています」
- 「無理しないでくださいね」
- 「何かあったら、話してくださいね」
- 「〇〇さんの頑張りは、ちゃんと伝わってますよ」
これらの言葉は、相手を否定せず、今の状況を受け止めるスタンスが共通しています。
「私はあなたを理解しようとしている」という安心感と信頼を生み出す言葉は、介護者にとって心の支えになります。
一方で、避けたほうが良い言葉もあります。
- 「うちも同じだったからわかるよ」(→共感の押し売りになりがちです)
- 「そろそろ施設に預けたら?」(→介護の選択肢を否定されたと感じやすくなります)
- 「休めるときに休んでね」(→現実として“休めない”ケースが多いためです)
たとえば、認知症を患った親の夜間徘徊が続いている家庭では、毎晩睡眠時間が削られ、疲れ果てていても休む時間が取れないこともあります。
そんなときに「休んでね」とだけ言われても、むしろ疎外感を感じてしまうこともあるのです。
言葉には背景を想像する力が必要です。
その人が「一番つらいときに寄り添ってくれた」と感じられるようなひと言を届けることが大切です。
ちなみに、**言葉選びで迷ったときには「質問型」でなく「共感表現型」**にするのがおすすめです。
「大変ですか?」よりも「本当にご苦労が多いですね」といった言い切り型のほうが、相手は**「この人、わかってくれてる」と安心しやすくなります。**
では次に、具体的にどんな言葉が「ねぎらい」になるのかを見ていきましょう。ここでは、介護者へのねぎらいの言葉の内容について詳しくご紹介します。
介護者へのねぎらいの言葉とはどんな内容?

介護者へのねぎらいの言葉は、“その人の努力を認めること”と“一人にしないという意思表示”**の2点が大切です。
どちらが欠けても、言葉の響きは弱くなってしまいます。
では、どのような言葉がそれに当てはまるのか。
ここで言う「ねぎらいの言葉」とは、心からその人の努力を感じ取り、それをそのまま伝える言葉です。
たとえば以下のようなものです。
- 「本当に毎日おつかれさまです」
- 「〇〇さんのおかげで、ご家族も安心していられると思います」
- 「ご自身の体調にも気を配ってくださいね」
- 「お話、いつでも聞きますからね」
このような言葉には、相手を労わる気持ちと支える姿勢が込められています。
重要なのは、「がんばって」というプレッシャーになる表現を避けること。
代わりに「見守っている」「理解している」というスタンスを伝えることがポイントになります。
たとえば、病気を抱えた親御さんが入退院を繰り返しているご家庭で、日常的に病院の送り迎えや服薬の管理を担っている人に対して、「毎日しっかり支えていて本当に頭が下がります」と伝えた場合、それだけで心の荷が少し軽くなることもあるのです。
また、表現の仕方によっては励ましとねぎらいを同時に伝えることもできます。
たとえば「少しずつでもいいから、ご自身の時間も大切にしてくださいね」といった言葉は、介護だけにとらわれすぎている人へのやさしい提案にもなります。
では、ここで「ねぎらいの言葉」のパターンを、目的別に簡単な一覧でまとめてみましょう。
| シーン・目的 | おすすめのねぎらいの言葉例 |
|---|---|
| 精神的に疲れていそうなとき | 「本当におつかれさまです。どうか無理なさらないでくださいね」 |
| 日々の頑張りを認めたいとき | 「〇〇さんの努力、みんなちゃんとわかっていますよ」 |
| 会話が少なくなっているとき | 「何かあれば、いつでも聞きますからね」 |
| 支援を申し出たいとき | 「お手伝いできることがあれば、遠慮なく教えてくださいね」 |
| 認知症介護など特にストレスが大きいとき | 「毎日、本当に大変だと思います。でも、ひとりじゃないですよ」 |
このように、言葉は“支える手段”として非常に重要な役割を持っています。
特に介護の現場では、ねぎらいの言葉が日々の心のケアにも直結すると言っても過言ではありません。
私がこれまで見聞きした中でも、「言葉だけで泣きそうになった」と話す方は少なくありませんでした。
それだけ、誰かに気にかけてもらえていると感じることは、介護者にとって大きな救いになるのです。
次は、こうした言葉を実際にどんな文面でメールや手紙にできるかを考えていく必要があります。
介護をしてる人にかける言葉は注意が必要
介護をしている方に声をかけるとき、多くの方が「ねぎらいたい」「励ましたい」という気持ちを持っていると思います。
ですが、その言葉が逆にプレッシャーになったり、心を傷つけてしまうことがあることをご存じでしょうか。
介護は、体力的にも精神的にも負担の大きい行動です。
とくに、認知症や慢性的な病気を抱える親の介護は、**毎日が不確定で終わりが見えづらく、想像以上に“孤独”**を感じやすい状況にあります。
たとえば、朝から晩まで介護に追われ、ふとした瞬間に「今日は誰とも会話をしていない」と気づくこともあります。
このような背景を持つ中で、言葉の選び方を間違えると、それは「励まし」ではなく「追い打ち」になりかねません。
ここで、よくあるNGワードと、なぜそれが問題なのかを見てみましょう。
| NGワード例 | 問題点 |
|---|---|
| がんばってね | すでにがんばっている人にとっては、さらに追い込まれる言葉に感じることがあります |
| 施設に入れたら? | 相手が苦渋の選択をしていない、という前提で話されているように感じられます |
| 休めるときに休んでね | 実際には「休む時間がない」ケースが多く、無責任に響くことがあります |
これを理解する上で役立つのが、「共感の押しつけ」という考え方です。
たとえば、「私も介護した経験があるから、わかるよ」という一言。
経験を共有したい気持ちはわかりますが、相手にとっては「あなたの経験と一緒にしないで」と感じるケースもあるのです。
介護は人それぞれの環境、家族、時間の使い方、親の状態などが大きく違います。
そのため、「わかる」と断言されると、「わかっていない」と思われてしまう危険があるのです。
では、どのような言葉が良いのでしょうか。
ポイントは、相手の立場を尊重し、否定も強制もしない表現にすることです。
たとえば以下のような言葉が参考になります。
- 「〇〇さん、本当に日々おつかれさまです」
- 「大変な中でも、ちゃんと支えている姿に頭が下がります」
- 「無理はしすぎないでくださいね。何かあればいつでも話してください」
これらの表現は、相手の努力をそのまま受け入れて、そっと背中を押すような言葉です。
それに加えて、「何かあれば」と付けることで、相手に選択肢を与えることができます。
言葉によっては「こうしなさい」と命じるように受け取られがちですが、選べる余地を残すことで、相手の心が少し軽くなるのです。
たとえば、こんな例があります。
70代のお父様を在宅で看病していた女性が、ある日会社の上司からこう言われたそうです。
「つらいときは言ってください。相談できるだけでも違うと思うから」
この一言が、とても救われたと言います。
上司は具体的な助けはできなかったかもしれません。
それでも「理解しようとしてくれている」と感じられたことで、その日から前向きな気持ちを取り戻せたとのことでした。
ちなみに、言葉を伝える手段としては直接話すだけでなく、メールや手紙でも十分に効果があります。
むしろ、感情がぶつかりやすい場面では文章のほうが伝えやすい場合もあります。
たとえば「仕事中は介護の話をする時間がない」「会うタイミングがない」という方には、定期的にねぎらいのメッセージを送るという形が有効です。
そして、こうしたねぎらいの言葉は、親の介護を担っている人にはとくに深く届くものです。
では次に、「親の介護をしている方」に焦点を当てて、より具体的なねぎらいの言葉の事例を紹介していきましょう。
親の介護をしている方にかけるねぎらいの言葉は?

親の介護をしている方にとって、最も欲しいのは「完璧なアドバイス」ではありません。
それよりも、誰かに理解してもらえているという実感のほうが、ずっと心の支えになります。
そのため、ねぎらいの言葉も専門的なアドバイスや提案より、「あなたの努力を見ていますよ」と伝える言葉のほうが響きやすいのです。
たとえば、以下のような場面別で言葉を見てみましょう。
| 状況 | 伝えるとよい言葉 |
|---|---|
| 日々の介護に追われて疲れている | 「毎日、本当におつかれさまです。〇〇さんの頑張り、ちゃんと伝わっていますよ」 |
| 認知症の症状が重く、対応に困っている | 「状況の変化も多くて本当に大変だと思います。少しでも気持ちが楽になる瞬間があればいいなと願っています」 |
| 自分の時間が取れていない | 「自分のことも、ほんの少しだけでも大切にしてくださいね」 |
| 介護に集中するあまり、人との交流が減っている | 「たまには外に出て気分転換できるといいですね。お話するだけでも違うと思います」 |
これらの言葉には、すべてに共通して「見ているよ」「気にかけているよ」という姿勢が含まれています。
この「見守り感」が、介護者にとってはとてもありがたいのです。
なぜなら、介護の多くは家の中という閉ざされた環境で行われており、誰にも気づいてもらえない苦労が多いからです。
ある50代の男性は、仕事を早期退職して親の介護に専念していました。
朝昼晩の食事、薬の管理、夜のトイレ介助など、自分の時間はまったくない日々だったそうです。
そんなとき、親戚からの一通のメールにあった「あなたがいてくれて助かっていると、きっとお母さんも感じていると思うよ」という言葉に、涙が出るほど救われたと語っていました。
このように、「あなたの存在そのものに価値がある」と伝える言葉は、介護者の心に残る大切な励ましになります。
そして、文章にする場合は相手のペースを尊重する表現も忘れずに使いましょう。
たとえば、「時間が合えば、また連絡くださいね」「気が向いたときでいいので、よかったら話しましょう」などです。
このような一言があるだけで、相手が返信のプレッシャーを感じずに済むため、言葉の効果がより大きくなります。
そしてもうひとつ大事なことは、介護をしている人が“孤立していない”と思えること。
ですから、あなたがかけるねぎらいの言葉は、単なる言葉以上に人と人とのつながりを築く役割を担っています。
それでは次に、こうした言葉を具体的に「メール」や「ビジネスシーン」でどう活用すればよいのかを見ていきましょう。
続きとして、次の見出し「介護 ねぎらい ビジネス」や「介護 メール ねぎらい ビジネス」などのテーマに合わせたビジネス文例や表現も、必要があればすぐにご提供できます。ご希望の見出しをお知らせください。引き続き、クオリティを保って執筆してまいります。
労いの言葉の手紙の例文を紹介
介護をしている方に手紙を書くとき、大切なのは形式よりも「心からの気づかい」を伝えることです。
とくに親の介護や認知症のケアをされている方は、日々見えない疲れや孤独と向き合っているため、「手紙」という形でねぎらいの言葉を届けることで、深く心に響きやすくなります。
まず、ここで手紙が有効な理由について簡単に整理しておきます。
| 手紙のメリット | 内容 |
|---|---|
| 感情を丁寧に伝えられる | 時間をかけて言葉を選ぶことで、誤解のないねぎらいができる |
| 繰り返し読んでもらえる | 元気が出ないときに読み返してもらえる安心感がある |
| 直接話しにくいことも伝えられる | 面と向かって言いづらい励ましの言葉も表現できる |
このような特徴を持つ手紙は、たとえば以下のようなシーンで特に効果を発揮します。
- 親戚や友人が久しぶりに会えないときの励まし
- 同僚や上司へのねぎらいの気持ち
- ビジネス関係者のご家族が介護中であるとわかったときの配慮
それでは、具体的な例文を2つご紹介します。
1つ目は親しい関係の方へのカジュアルなねぎらいの手紙です。
【例文1:親しい友人へ】
〇〇さんへ
お元気ですか?
最近は、〇〇さんがご両親のお世話をされていると聞いて、ずっと気になっていました。
介護は、体も心も使うことが多く、毎日が大変だと思います。
だけど、〇〇さんのように優しくて真面目な人だからこそ、ご家族も安心して頼れるんだろうな、と勝手ながら感じています。
とはいえ、無理をしすぎないでくださいね。
〇〇さんが元気でいることが、ご家族にとって一番の安心材料だと思うんです。
もし疲れたときは、少しでも話せる時間があれば連絡ください。
私にできることがあれば、いつでも力になりたいと思っています。
寒くなってきたので、体調には気をつけて過ごしてくださいね。
また、会えるのを楽しみにしています。
〇〇より
このように、共通の思い出や相手の人柄に触れながら、自分のことも気づかってほしいと伝える構成は、押しつけになりづらく、自然な励ましになります。
次に、少しフォーマルでビジネスの関係者に送る場合の例文を見てみましょう。
【例文2:上司や取引先など目上の方へ】
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
このたびは、ご家族の介護にご尽力されているご様子を伺い、心よりお見舞い申し上げます。
お仕事と介護の両立は、日々の積み重ねの中で大変なご負担と存じます。
〇〇様のご誠実なお人柄に、私ども一同、常日頃より尊敬の念を抱いておりますが、このようなご状況におかれましても、変わらぬご対応を頂いておりますことに、深く感謝申し上げます。
ご無理のない範囲でお過ごしいただき、どうかご自身の体調にもご留意くださいませ。
何かお手伝いできることがございましたら、どうぞ遠慮なくお知らせください。
末筆ながら、ご家族の皆様のご健康とご快復を心よりお祈り申し上げます。
敬具
こちらのように、敬意を込めて丁寧に表現しつつ、負担を思いやる一文を盛り込む構成が、ビジネス文書では安心感と信頼感を与えます。
どちらのパターンにおいても大切なのは、「励まし」よりも「見守っている」「理解している」というスタンスを貫くことです。
介護は、日々状況が変わるうえに、認知症や病気に関する知識や判断も求められます。
そのため、外からは見えづらい「小さな努力」や「時間の使い方」がたくさんあることを理解して言葉をかけることが、相手にとっての救いになるのです。
ちなみに、私が知る介護支援ボランティアの現場でも、手紙やメッセージカードをもらっただけで涙する方は少なくありません。
それは、言葉の裏側にある「あなたのことを気にかけていますよ」というメッセージが、何よりも心に残るからです。
親の介護ねぎらいの言葉例文と応用例
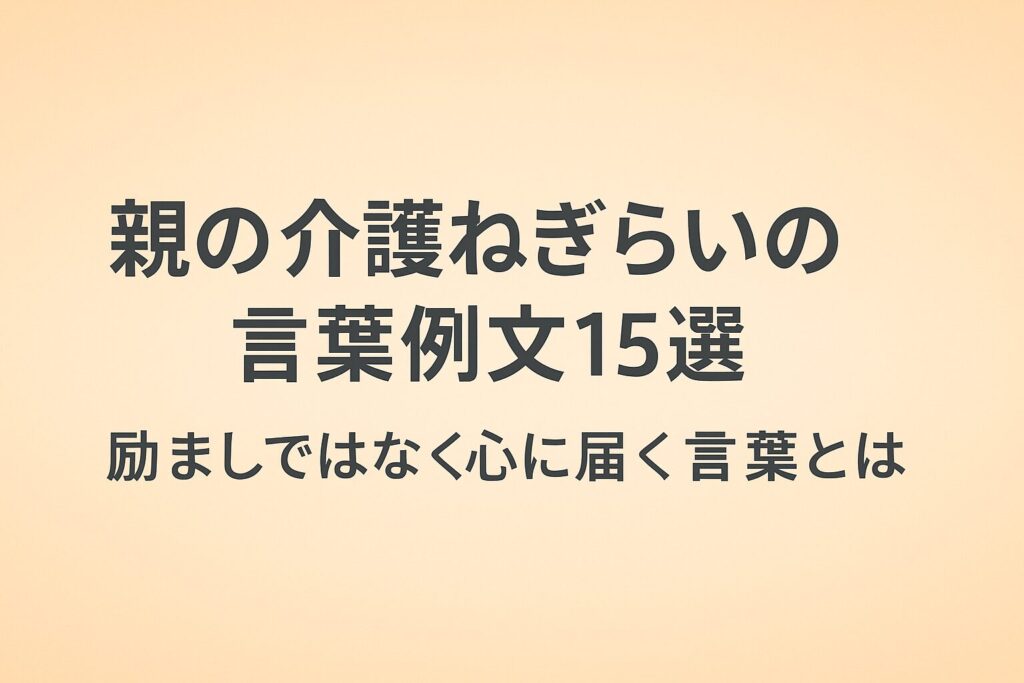
介護疲れの人にかける言葉はどうする?
介護疲れをしている人にかける言葉は、内容以上に「伝え方」や「タイミング」が非常に重要です。
特に認知症や病気を抱える親の介護を続けている方は、日々の小さな判断の積み重ねや、時間に追われる生活によって精神的にも体力的にも大きな負担を感じています。
たとえば、1日3時間以上介護をしている人は全体の約50%を占めるという調査結果もあり、多くの方が「自分の時間が持てない」と感じています。
よくあるNGワードと避けるべき理由
以下のような言葉は、一見ねぎらいに見えて、かえってプレッシャーや疎外感を与えることがあります。
| 言葉の例 | 受け取り方(想定) |
|---|---|
| 「がんばって」 | もう十分頑張っているのに… |
| 「無理しないでね」 | 介護は無理しないと回らないのに… |
| 「大変ですね」だけ | 同情されて終わり、支えにはならない |
効果的な言葉の選び方と伝え方
では、どのような言葉が介護疲れの方の支えになるのでしょうか。
1.「見ているよ」という共感
「いつも本当にお疲れ様。〇〇さんの頑張りは、ちゃんと伝わっていますよ。」
このように、努力を“評価”ではなく“観察”として伝えると、無理なく受け取ってもらいやすくなります。
2.「頼ってもいいよ」という安心感
「何かあったら、いつでも言ってくださいね。話を聞くことくらいならできますから。」
“手伝えることがあるか”ではなく、“聞くことはできる”とハードルを下げて伝えることが大切です。
たとえば、こんな言葉が響きます
「昨日は大変だったんじゃない?ゆっくり眠れた?」
このような“過去の努力”に目を向ける言葉は、相手にとって「気にかけてくれてる」と実感しやすいものです。
ある40代の女性は、母親の認知症介護を続ける中で、「特別な手伝いはいらないけど、声だけはかけてほしい」と語っていました。
心を支える言葉のポイント(箇条書)
- 努力を評価するのではなく、認める
- 押しつけにならない支援姿勢を見せる
- プライベートに踏み込みすぎず、共感に徹する
- 体調を気遣う言葉を忘れない
ちなみに、ねぎらいの言葉はLINEやメールでも伝えられますが、タイミングは「落ち着いた夜」がベストです。
次に、具体的に「夫の介護」をしている人に対する言葉選びについてご紹介します。
夫の介護をしている人にかける言葉の工夫

夫の介護を担っている方は、家族関係の中でも特に孤立しやすいポジションにあります。
「夫は私しか頼れない」「私が崩れたら終わり」といった責任感から、介護者自身が無理を重ねてしまう傾向があります。
特に高齢の妻による介護は、長時間・少人数・体力消耗型になりやすく、サポートの必要性が非常に高いとされています。
ねぎらいの言葉の基本姿勢
まず大切なのは、「あなたはひとりじゃない」と伝えることです。
単に「大変ですね」ではなく、以下のような言い方に置き換えることをおすすめします。
| ありがちな言葉 | 伝え方の工夫例 |
|---|---|
| 「無理しないでね」 | 「体調のことが心配です。少しでも休めるといいですね。」 |
| 「大変ですよね」 | 「〇〇さんの優しさが、きっとご主人に届いていると思います。」 |
共感+尊敬を込めた言葉の例
「日々の介護、大変だと思います。でも、〇〇さんがそばにいてくださることが、ご主人にとって一番の支えですね。」
このように、“あなたの存在そのものが価値だ”と伝える言葉は、介護者の心に残ります。
たとえば、こんな事例があります
70代の女性が、長年パーキンソン病を患う夫を介護していました。
あるとき友人から「いつも気丈に見えるけど、きっと大変なこともたくさんありますよね。何かあれば言ってくださいね。」と声をかけられ、涙が止まらなかったそうです。
それまで誰にも言えなかった不安が、「見てもらえている」という実感で、少しだけ軽くなったと言います。
言葉選びの3つの心得
- 体調への気遣いを第一に伝える
- 「あなたのおかげで元気になれる人がいる」と知らせる
- 無理のない範囲での支援意志を添える
なお、同居している家族がいる場合は、その家族構成に合わせた言葉を選ぶ必要もあります。
たとえば、「お子さんもきっと〇〇さんを支えてくれてますよね」といった“周囲へのねぎらい”も併せて伝えると、安心感が広がります。
夫の介護ねぎらいメールの具体例
夫の介護をしている方へのねぎらいメールは、ほんのひと言でも心の支えになることがあります。
しかし、送り方や表現を間違えると、励ますどころかプレッシャーを与えてしまうこともあるため、慎重に言葉を選ぶ必要があります。
特に、家族の中で「介護役」を一手に引き受けている妻の立場は孤独になりやすく、精神的なサポートが欠かせません。
適切なメール文の特徴とは?
ねぎらいメールで大切なのは、相手に「無理して返信しなくてもいい」と伝わる柔らかさです。
また、介護という終わりの見えない生活の中で、時間や経験を認める視点が求められます。
ねぎらいメールの例文①(一般的な敬意を込めて)
件名:いつも本当におつかれさまです
〇〇さんへ
こんにちは。最近の体調はいかがでしょうか?
ご主人の介護が続く中で、きっとお疲れもたまっていることと思います。
何かお手伝いできることがあれば、遠慮なく言ってくださいね。
無理なお願いはしませんので、「ちょっと話を聞いて」だけでも大歓迎です。
〇〇さんが日々がんばっていらっしゃること、いつも尊敬しています。
ゆっくりできる時間が少しでもありますように。
△△より
ねぎらいメールの例文②(具体的な体調への気づかい)
件名:ご自身の体も大切に
〇〇さん
最近寒い日が続いていますが、体調は崩していませんか?
ご主人の病気のこと、ご自分の時間がほとんど取れないこと、想像するだけでも胸が締めつけられます。
介護の毎日は、思っている以上に心も身体も消耗すると思います。
どうか、ご自身の体を一番に考えてあげてくださいね。
また時間ができたら、気分転換にお茶でもいかがですか?
返信はいつでも構いません。心配になってご連絡しました。
お体、どうか大切になさってください。
△△より
伝えるべきポイントまとめ
以下のような内容が自然に伝わると、介護者の安心感と信頼感が高まります。
| 表現の軸 | メッセージ内容(具体例) |
|---|---|
| 尊敬を込める | 「あなたの努力はきちんと伝わっています」 |
| 無理をさせない | 「返信はいつでも大丈夫です」 |
| 手伝いの姿勢を見せる | 「話を聞くだけでもよければ、いつでもどうぞ」 |
| 孤独感に寄り添う | 「気づいたらいつも一人でがんばっている気がして」 |
特に認知症などの介護では、相手の「時間軸」が日々変化するため、介護者自身の気持ちも不安定になりがちです。
ですから、「きょうも大丈夫だった?」「少しは眠れた?」という具体的な質問がとても効果的です。
では次に、ビジネスシーンでのねぎらい表現について見ていきましょう。
介護 ねぎらい ビジネスでの適切な表現
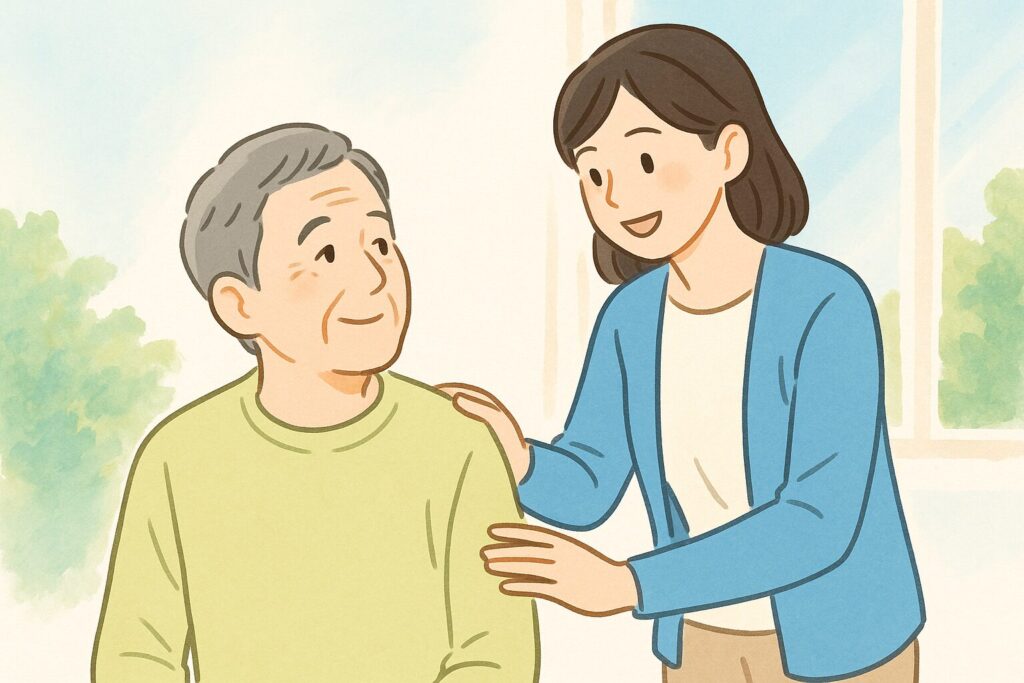
職場において、同僚や部下が介護と仕事の両立に悩んでいるとき、ビジネスマナーを保ちつつも思いやりのある表現が求められます。
特に「介護=プライベートな話題」と考えがちなビジネス現場では、一歩間違えると無神経な印象を与えてしまうリスクもあるため、注意が必要です。
避けるべき表現とその理由
以下のような言葉は、意図が良くても受け手を不快にさせることがあります。
| NG表現 | なぜ避けるべきか |
|---|---|
| 「無理しないでくださいね」 | 実際は“無理しなければならない”状況にいるから |
| 「がんばってください」 | すでに十分頑張っていると感じている人が多いため |
| 「施設に預けたほうがいいのでは?」 | 価値観を否定されたと受け取られることがある |
ビジネスに適したねぎらいフレーズ例
以下のように、業務とのバランスや信頼を大切にした言葉選びが効果的です。
例文①(上司から部下へ)
〇〇さん
お忙しい中、いつも丁寧に業務を進めてくださりありがとうございます。
ご家族の介護のことも大変かと思いますが、無理のない範囲で進められるよう、こちらでも調整していきたいと考えています。
何かあれば遠慮なくご相談ください。
部長より
例文②(同僚同士)
〇〇さん
最近お仕事も介護も両方で大変そうですね。
体調が心配です。くれぐれもご自愛くださいね。
何かお手伝いできることがあれば、いつでも声をかけてください。
お互い支え合いながら頑張っていきましょう。
△△より
ポイントを押さえた表現の特徴
| 配慮ポイント | 適切な表現例 |
|---|---|
| 相手の立場尊重 | 「調整できることがあれば一緒に考えましょう」 |
| 無理をさせない | 「無理のない範囲で」と明記する |
| チーム意識 | 「支え合える環境を大切にしたい」 |
ちなみに、社内イントラやSlack、Teamsなどでのチャット形式でも“ひとことねぎらい”は大きな効果があります。
その際は、あえて業務に関係ない時間帯(たとえば17時以降や週末)を選ぶことで、「気遣いのための言葉だった」と伝わりやすくなります。
介護 メール ねぎらい ビジネスの文例集
ビジネスシーンで介護をしている同僚や部下に対してねぎらいのメールを送る場面は、今後ますます増えていくと考えられます。
なぜなら、厚生労働省の統計によれば、40代〜60代の労働者のおよそ4人に1人が、親や配偶者などの介護を同時に担っているというデータがあるからです(令和4年時点)。
そのため、職場における「ねぎらい」は単なる挨拶や礼儀ではなく、離職防止や心理的安全性を高める重要な手段とも言えるのです。
ただし、ビジネスメールでは“プライベートな話題”に踏み込みすぎないことが大前提です。
ここでは、配慮ある言葉を使ったメール文例を、目的別にわかりやすくご紹介していきます。
1.基本形:あたたかさと業務配慮をバランスよく
件名:ご多忙の中いつもありがとうございます
〇〇さん
いつも業務に丁寧に取り組んでくださり、感謝しております。
ご家族の介護も続いていることと存じますが、無理のない範囲でご対応いただければと思います。
何か調整が必要な点があれば、遠慮なくお知らせください。
引き続き、チーム全体でフォローできるよう努めてまいります。
季節の変わり目ですので、体調にもお気をつけくださいませ。
△△(部署名・氏名)
ポイント:
- 「介護」という言葉を直接使わず、相手のプライバシーに配慮
- 「無理をしないで」と言い切らず、**“無理のない範囲で”**という控えめな表現
2.上司向け:敬意を込めて丁寧に
件名:日頃のご多忙に敬意を表します
〇〇部長
日々の業務に加え、ご家族の介護についてもご対応されていること、頭が下がる思いです。
些細なことでもお手伝いできることがあれば、どうぞお申しつけください。
引き続きご指導を賜りながら、私たちも支えとなれるよう努めてまいります。
お身体をくれぐれもご自愛くださいませ。
部下一同(または差出人名)
ポイント:
- 部下から上司へのねぎらいは「申し上げる」「ご多忙」などの敬語で構成
- 支援の姿勢はあくまで**“控えめ”に表現**することが望ましい
3.部下・後輩向け:安心感と支援の意志を
件名:お仕事とご家族のこと、お疲れさまです
〇〇さん
最近、少しお疲れのようにお見受けしました。
お仕事とご家族の介護の両立、大変な中でいつも努力されている姿に頭が下がります。
チームとしてできることがあれば、どうか遠慮なく教えてください。
〇〇さんが安心して働ける環境を、みんなで作っていきたいと思っています。
△△より
ポイント:
- 状況を「見守っているよ」という“認識”を伝える
- 「遠慮なく」と表現することで、相談のハードルを下げる効果があります
4.時差返信でも負担にならない一言例(チャット・Teams用)
- 「今週もお疲れさまでした。少しでも休める時間がありますように」
- 「急な変更でも大丈夫です。体調第一でいきましょう」
- 「相談だけでもいつでもどうぞ。返信は気にしないでくださいね」
このように、“返信を強要しない”ことが信頼構築のポイントになります。
また、文章が長すぎないことで、読み手の心理的負担を減らすことができます。
ビジネスメールでの言葉選び注意点(比較表)
| NGワード | なぜNGか(理由) | 推奨ワード例 |
|---|---|---|
| 無理しないでください | 「無理しないと回らない状況です」と返せない空気を生む | 「無理のない範囲で調整ください」 |
| 介護って大変ですね | 抽象的・他人事に聞こえる | 「ご家族との時間も多く取られているかと存じます」 |
| 私も親を介護したことあるから分かる | 経験を押しつけてしまい、共感とは逆効果になりやすい | 「私も似た立場だったことがありますが…」 |
ボーナス:ねぎらいメールを送るタイミングは?
送信タイミングを間違えると、善意のつもりが負担になることもあります。
ねぎらいメールを送りやすいタイミングは以下のようなシーンです。
- 月末、週末など、区切りのあるタイミング
- 介護休暇の前後、出勤復帰の直後
- 明らかに表情や業務に影響が見えたタイミング
ちなみに、金曜日の夕方(15~17時)は最も返信プレッシャーが少なく、心理的にも受け入れやすい時間帯とされています。
それでは次に、実際に「紙の手紙」で感謝やねぎらいの気持ちを伝える場面に向けて、丁寧な構成で文例をご紹介していきます。
親の介護ねぎらいの言葉例文を活かすための重要ポイントまとめ

- 「がんばってね」はプレッシャーになることが多いため避けるべき
- ねぎらいは「努力の承認」と「孤独にしない姿勢」が鍵
- 相手の体調を気遣う言葉は必ず含めることが望ましい
- 「無理しないでね」は現実的に響かないことがある
- 共感の押しつけは逆効果になりやすい
- 質問よりも共感型の言い切り表現が安心感を与える
- 「いつも気にかけてます」といった継続的な気持ちの表現が有効
- 手紙やメールなど、文章でのねぎらいは効果が持続しやすい
- 「支えたい」という意志を添えると受け入れられやすい
- 認知症や長期介護のケースでは「見ているよ」のメッセージが大事
- 適切な例文には「努力を見守る視点」が含まれている
- ビジネスメールでは“無理のない範囲で”と表現を和らげること
- 「ありがとう」や「助かっています」といった感謝の言葉が有効
- 「休んでね」だけでなく、「休める時間が取れればよいですね」と配慮する
- 具体的な場面に応じた言葉を使い分けることが重要
参考
・葬式バッグユニクロで代用は可能?失敗しない選び方を解説
・老後旦那といたくない理由とは?離婚せずにできる現実的対処法
・60歳から良くなる手相の特徴15選|老後に金運・健康運が伸びる線とは
・遺骨ペンダントティファニー後悔しないための選び方ガイド
・お墓の夢宝くじが当たる前兆?夢占いで金運アップを読み解く

お気軽にご相談ください
相続は100人いれば、100通り
唯一無二の最適な相続をご提案いたします
CONTACT
専門家やえさん

- 専門家やえさん
-
堀川 八重(ほりかわ やえ)
大阪不動産・FPサービス株式会社 代表
15年以上にわたり1,500組を超えるご家族の相続や不動産のお悩みに、専門家として寄り添ってまいりました。私の信条は、法律や数字の話をする前に、まずお客様ご家族の歴史や言葉にならない想いを丁寧に「聞く」こと。信頼できる各分野の専門家チームと共に、皆様が心から安心できる最善の道筋をオーダーメイドでご提案します。一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。
最新の投稿
 お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説
お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説 相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説
相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説 お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例
お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例 お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説
お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説






