「うちの親も認知症かも…もし行方不明になったらどうしよう」と不安に感じていませんか。ニュースで高齢者の方が行方不明で見つからないと聞くたびに、他人事とは思えないお気持ち、本当によく分かります。認知症の行方不明者が見つかる確率は?と心配になりますよね。
結論から言うと、行方不明者の多くは早期に発見されていますが、時間が経過するほど生存率が下がり、最悪の場合、死亡に至るケースも少なくないのが現実です。ただし、認知症の方がなぜ見つからないのか、その理由や本人の心理状態を知ることで、有効な対策を立てることが可能です。
認知症の行方不明者が見つからない場合はどうしたらいいですか?という切実な問いや、認知症で行方不明になったらどうなるのか、その探し方、考えられる死因、そして認知症の行方不明者はいったいどこにいるのか。知恵袋などでも多くの心配の声が見られます。この記事では、こうした疑問に答えながら、大切なご家族を守るための具体的な認知症の行方不明対策まで、分かりやすく解説していきますね。
この記事のポイント
- 認知症の行方不明者がなぜ見つからないかの理由がわかる
- 行方不明になった際の具体的な探し方と初期対応がわかる
- 事前に家族ができる有効な対策と準備がわかる
- 万が一の事態を避けるための地域との連携の重要性がわかる

こんにちは、終活・相続の専門家やえです!
「うちの家族は大丈夫」と思っていても、ある日突然…というケースは本当に多いんです。でも、正しい知識を持って事前に備えておけば、防げる悲劇はたくさんあります。大切なのは、一人で抱え込まず、周りを頼ること。
この記事が、あなたの不安を安心に変えるきっかけになれば嬉しいです!
目次
認知症行方不明なぜ見つからない?その深刻な現状と背景
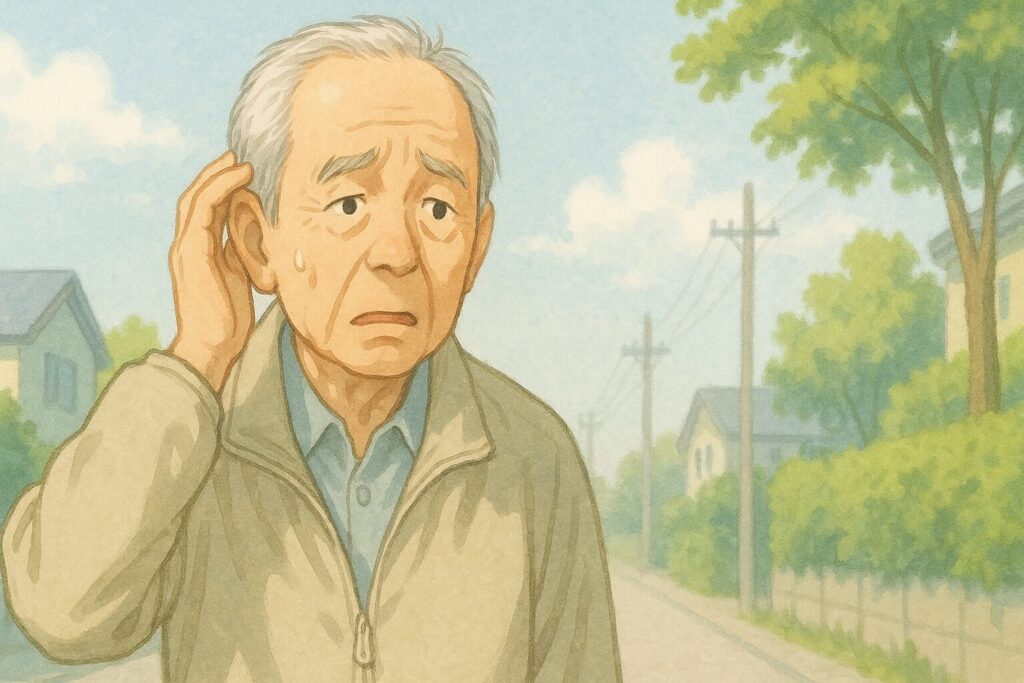
認知症の行方不明者が見つかる確率は?
大切なご家族が認知症と診断され、もし行方不明になったら…と考えると、夜も眠れないほど心配になりますよね。ですが、まず知っておいていただきたいのは、決して希望を捨てる必要はないということです。警察庁が毎年発表している統計によると、届け出があった認知症の行方不明者は、驚くことに99%以上が1週間以内に無事発見されています。
この非常に高い発見率の背景には、ご家族からの迅速な行方不明届の提出をきっかけに、全国の警察官が情報を共有し、パトロールや職務質問を通じて発見に繋げてくれるおかげです。
それに加えて、近年では各自治体が整備を進めている「SOSネットワーク」のように、地域の消防団や協力企業、そして一般の住民の方々による捜索体制が大きな力となっています。
特に、日頃から地域での見守り活動が活発なエリアでは、行方不明になってから数時間のうちに「〇〇さんなら、さっきあそこで見かけたよ」といった有力な情報が寄せられ、早期保護に結びつくケースが本当に多いんですよ。
発見率の高さは「早期対応」が前提
この99%という数字は、あくまで「行方不明になった」と認知され、捜索活動が開始されたケースの全体像です。この数字に安堵して「きっと大丈夫だろう」と対応が遅れることが、最も避けなければならない事態なのです。
発見率の高さは、迅速な通報と捜索活動があってこそ、ということを心に留めておく必要があります。
言ってしまえば、この数字は私たちに希望を与えてくれると同時に、いなくなったと気づいた瞬間の初動がいかに重要であるかを教えてくれているわけですね。
厳しい現実、認知症行方不明の生存率

前述の通り、発見率そのものは非常に高いのですが、その一方で、私たちは「時間との戦い」という、もう一つの厳しい現実から目をそらすことはできません。発見されるまでの時間が長引けば長引くほど、ご本人の心身の状態は悪化し、生存率が著しく低下してしまうのです。
ある調査では、行方不明になってから発見までに3日以上経過した場合、残念ながら死亡して発見される割合が急激に高まるという報告もあります。
これは、認知症の症状がある高齢者の方が、判断力の低下から食事や水分補給を適切に行うことができず、急速に体力を消耗してしまうためです。特に、夏場であれば脱水症状や熱中症、冬場であれば低体温症といった、命に直結する危険な状態に陥りやすいのです。
「様子を見る」という選択が最も危険
「いつもの散歩が少し長引いているだけだろう」「そのうち疲れて帰ってくるはず」といったご家族の判断が、取り返しのつかない事態を招くことがあります。
行方不明は時間経過とともにリスクが指数関数的に増大する「命に関わる緊急事態」であると認識し、いなくなったと気づいた時点ですぐに行動を起こすことが何よりも大切です。
このように、発見までの時間は、ご本人が無事な姿で家族の元へ帰れるかどうかを左右する、極めて重要な要素となります。この時間の重要性を理解することが、すべての対策の出発点になると言っても過言ではありません。
高齢者が行方不明で見つからない理由
では、一体なぜ認知症の症状がある高齢者の方は、一度外に出てしまうと見つかりにくくなってしまうのでしょうか。その背景には、ご本人も好きで迷っているわけではない、認知症特有の複雑な要因が絡み合っています。
記憶障害と見当識障害
認知症、特にアルツハイマー型認知症の中核的な症状として、脳の記憶を司る「海馬」という部分の機能低下が挙げられます。これにより、まず新しい出来事を記憶することが困難になります。さらに症状が進行すると、自分が今どこにいるのか、今はいつなのか、周りにいる人が誰なのかを正しく認識する「見当識(けんとうしき)」が障害されます。
この見当識障害が起こると、毎日通っているスーパーへの道や、自宅のすぐ近所の路地ですら、まるで初めて来た場所のように感じられてしまいます。「家を出て散歩に行った」という目的自体を忘れてしまい、気づいた時には全く知らない場所に一人でいる、という不安な状況に陥ってしまうのです。こうなると、自力で家に帰ることは極めて困難になります。
本人の心理状態と「目的のある」行動
ご家族から見ると目的もなく歩き回っているように見えるため、「徘徊」という言葉が使われることが多いですが、脳科学者の研究などでは、ご本人にとっては何かしらの目的や理由があって行動しているケースがほとんどだと指摘されています。
ご本人なりの「目的」の例
- 役割の遂行:「会社に出勤しなくては」「夕飯の買い物に行かなくては」など、過去に深く根付いた習慣や役割を果たそうとする。
- 安心の探求:現在の状況への不安感から、最も安心できた場所である「実家」や「昔住んでいた家」に帰ろうとする。
- 不快からの回避:自宅での居心地の悪さや、家族との関係で感じたストレスなど、不快な状況から逃れようとする。
しかし、前述の記憶障害や見当識障害があるため、その目的を達成するための正しい道筋をたどることができません。結果として、不安と焦燥感に駆られながら、誰かに助けを求めることもできずに、ただひたすら歩き続けてしまうのです。
このように、認知症の症状とご本人の切実な心理状態が複雑に絡み合い、発見を一層困難にさせているのが実情と言えます。
認知症で行方不明、なぜ見つからない?知恵袋の声
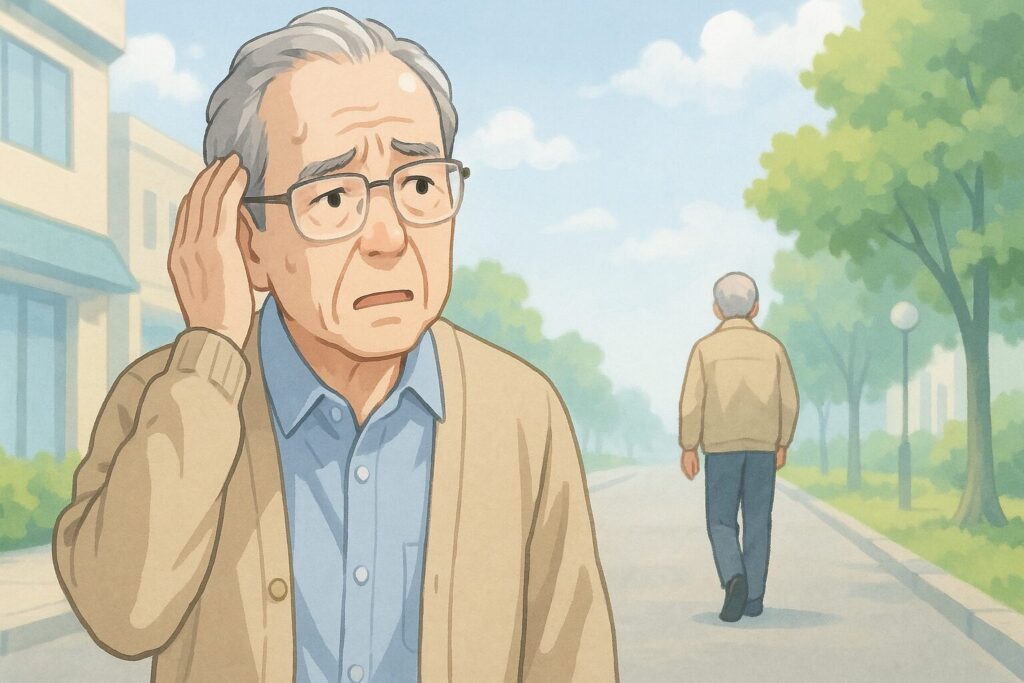
「Yahoo!知恵袋」のようなインターネット上のQ&Aサイトには、認知症の家族が行方不明になった方々の、胸が締め付けられるような投稿が数多く見られます。そこには、専門書には書かれていない、当事者だからこそのリアルな後悔や、やり場のない思いが綴られています。
これらの声に共通して見られるのは、「まさか、うちの家族が」という思いです。例えば、「足腰が弱っていたので、せいぜい数百メートルしか歩けないと思っていたら、数キロ先の隣町で発見された」「いつも穏やかだったのに、あんな行動をするなんて信じられなかった」といった内容です。
ご家族が陥りがちな「思い込み」の罠
- 能力の過小評価:「体力がないから遠くへは行けないはず」という思い込みが、捜索範囲を狭めてしまう。
- 症状の軽視:「まだ初期だから大丈夫」「時々物忘れがあるだけ」と症状を軽く考え、事前の対策を怠ってしまう。
- 世間体への配慮:「近所に知られるのが恥ずかしい」「警察沙汰にしたくない」という気持ちが、初動の遅れに繋がる。
これらの声は、決して他人事ではありません。ご家族の「これくらい大丈夫だろう」という希望的観測や思い込みが、結果的に発見を遅らせる最も大きな要因になり得るという、重要な教訓を私たちに示してくれています。行方不明になったご家族を責めるのではなく、こうしたリアルな声から学び、いざという時に冷静な判断ができるよう備えておくことが、何よりも大切なのです。
認知症の行方不明者はどこにいるのか
ご家族が行方不明になった時、やみくもに探し回るのではなく、どこにいる可能性が高いのか、その傾向を知っておくことが極めて重要です。もちろん、全てのケースに当てはまるわけではありませんが、過去の統計や事例から、いくつかの特徴的なパターンが見えてきます。
まず、警察庁の統計では、亡くなった状態で見つかった方の約8割が、行方不明になった場所から5キロ圏内で発見されているというデータがあります。これは非常に重要なポイントで、多くの場合、驚くほど遠方へ行っているわけではなく、比較的近場で、ただし「発見されにくい場所」にいる可能性が高いことを示唆しています。
| 発見されやすい場所の傾向 | 具体的な場所の例 |
|---|---|
| ① 過去の記憶に繋がる場所 | 昔住んでいた家、以前の職場、子どもの頃の通学路、故郷、よく利用した駅・バス停、思い出の公園など |
| ② 人目につきにくい場所 | 山林、畑、田んぼのあぜ道、河川敷、用水路、神社の境内、空き家、工事現場、公園の茂みなど |
| ③ 特定の習性による場所 | 下り坂を好む傾向、線路や川沿いなど目印に沿って歩き続ける傾向、休憩できそうなベンチやバス停など |
特に、ご本人の人生史(ライフヒストリー)を丁寧に振り返ることは、非常に有力な手がかりとなります。「あの人は昔、鉄道員だったから線路沿いを歩いているかもしれない」「若い頃、〇〇公園でよくデートしたと話していた」といった情報が、捜索範囲を絞り込む上で決定的な役割を果たすことがあるのです。普段からのご家族との会話が、いざという時に命を救う情報になるかもしれませんね。
認知症で行方不明になるとどうなるのか
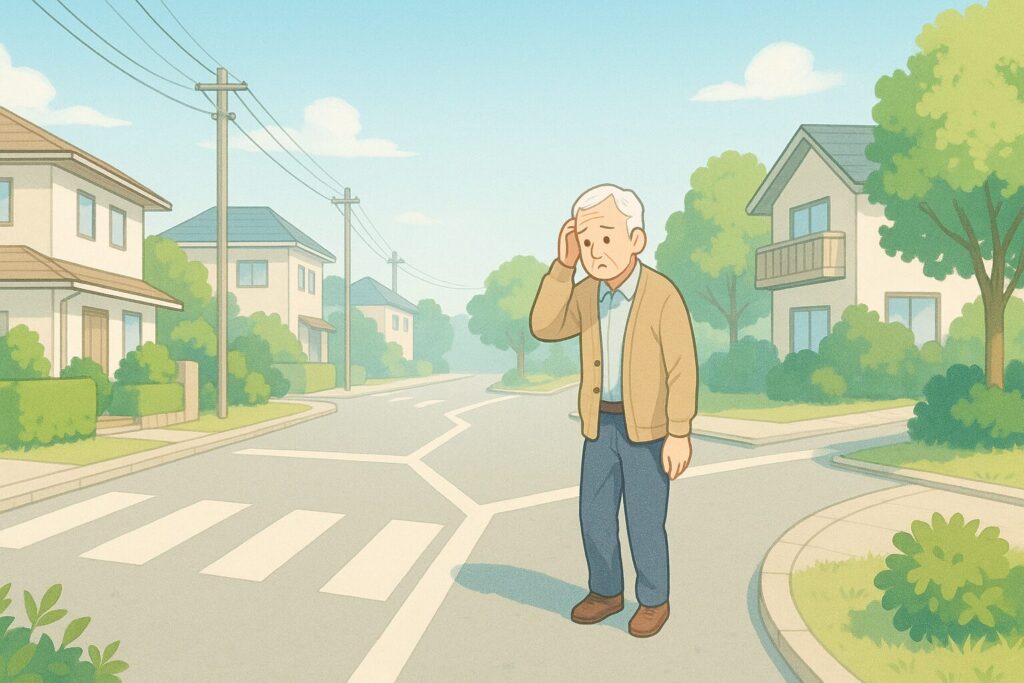
認知症の方が何の備えもなく一人で外に出てしまうと、時間の経過とともに、ご本人は深刻な危険に晒されることになります。行方不明になったご本人がどのような状況に陥るのかを具体的に理解しておくことは、早期発見の重要性を再認識するために不可欠です。
まず、精神的な側面として、自分がどこにいるのか分からなくなる見当識障害から、極度の不安と混乱、そして恐怖に襲われます。家に帰りたい一心で、ひたすら歩き続けることが多く、これにより体力を著しく消耗してしまいます。
時間経過とともに増大する身体的リスク
- 脱水症状・栄養失調:適切な水分や食事を摂ることができず、特に夏場は短時間で命に関わる状態になり得ます。
- 低体温症:冬場や夜間、雨天時などは、体温が奪われて体力を消耗し、命の危険に直結します。
- 二次的な事故:判断力が低下しているため、信号を無視して道路に飛び出したり、足元がおぼつかずに転倒・骨折したり、用水路や崖から転落したりするリスクが非常に高まります。
- 持病の悪化:常用している薬が飲めなくなることで、糖尿病や高血圧などの持病が急激に悪化する危険もあります。
このように、行方不明の状態が続くことは、単に「道に迷っている」というレベルではなく、ご本人の生命そのものが危機的な状況に置かれているということを、ご家族は強く認識する必要があります。だからこそ、一刻も早い発見と保護が求められるのです。
認知症で行方不明、死亡に至るケース
これは考えたくないことかもしれませんが、最悪の事態を避けるためには、なぜ死亡に至ってしまうのか、その背景を直視することも大切です。行方不明になった認知症の方が亡くなった状態で見つかる悲劇は、残念ながら毎年発生しています。
その背景には、いくつかの共通した要因が見られます。一つは、発見の遅れです。特に、一人暮らしの高齢者や、日中独居(家族が仕事などで家を空けている)の世帯では、行方不明になったこと自体に気づくのが遅れがちです。気づいた時にはすでに数時間が経過しており、捜索が後手に回ってしまうのです。
もう一つ、繰り返しになりますが、ご家族による通報の遅れも大きな要因として挙げられます。
なぜ家族は通報をためらうのか?
「大事にしたくない」「ご近所に知られたら恥ずかしい」「警察に迷惑をかけてしまうのでは」…こうしたお気持ちは、私も多くのご家族からお聞きしてきました。しかし、行方不明は個人の問題ではなく、社会全体で対応すべき問題です。
ためらいが、ご家族にとって生涯の後悔に繋がる可能性もあります。行方不明届を出すことは、決して恥ずかしいことでも、迷惑なことでもありません。それは、家族としてできる最も重要で責任ある行動なのです。
これらの要因が重なった時、悲しい結末を迎えるリスクが高まります。大切なのは、個々の家族の問題として抱え込むのではなく、早期に公的な支援や地域の力を借りるという意識を持つことです。
認知症で行方不明になった方の死因とは
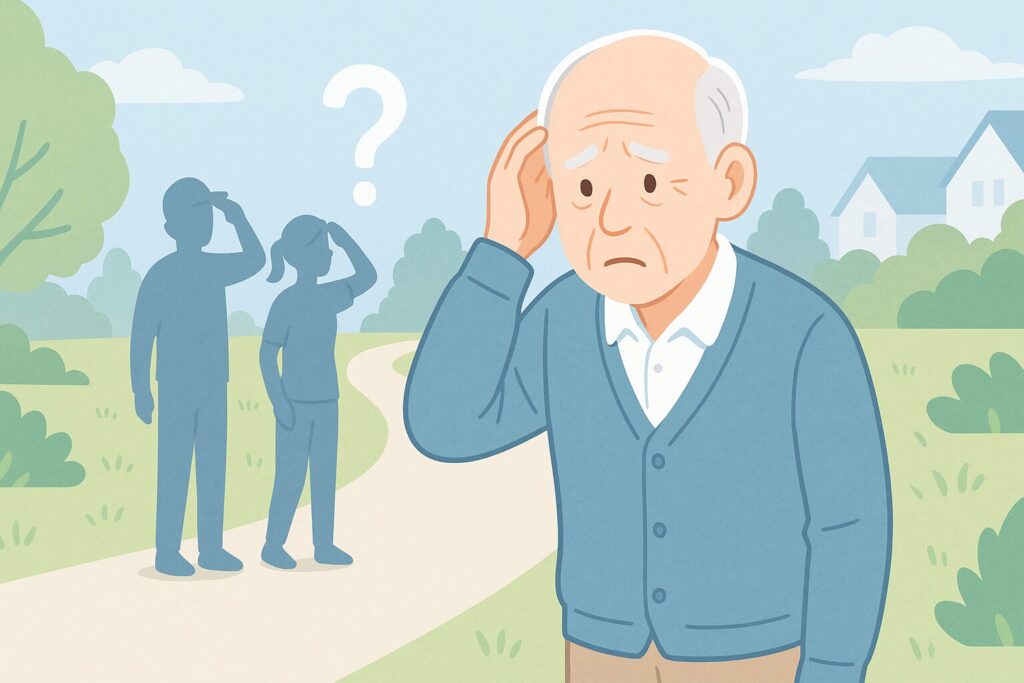
行方不明になった方が亡くなってしまう原因は、どのようなものが多いのでしょうか。警察庁の調査結果は、私たちが捜索する際に特に注意すべき場所を示唆してくれています。
最も多い発見場所は、河川や用水路、側溝といった水辺です。これは、脱水症状により本能的に水を求めて水辺に向かい、そこで力尽きたり、暗闇や足元の不安定さから誤って転落し、溺れてしまうケースが多いと考えられています。
特に、田園地帯に多いコンクリート三面張りの用水路は、一度落ちると自力で這い上がることが非常に困難なため、危険性が高い場所です。
| 発見場所 | 考えられる主な死因 | 捜索時の注意点 |
|---|---|---|
| 河川・用水路・側溝 | 溺死(転落) | 橋の下や草木の陰など、見えにくい場所も入念に確認する。 |
| 山林 | 滑落による外傷、低体温症 | 遊歩道から少し外れた斜面や窪地などを重点的に探す。 |
| 畑・田んぼ | 脱水症状、低体温症、転倒 | あぜ道や休耕田など、人の出入りが少ない場所を確認する。 |
また、山林では道に迷い、斜面を滑落して動けなくなったり、夜間の冷え込みで低体温症に陥ったりするケースが見られます。これらのデータは、捜索を行う際に、ただ闇雲に歩き回るのではなく、「水辺」と「高低差のある場所」、「普段人が入らない場所」を重点的に確認することの重要性を示しています。(出典:警察庁生活安全局人身安全・少年課「令和5年における行方不明者の状況」)

数字だけ見ると、少し怖くなってしまいますよね。でも、なぜ見つかりにくいのか、どこで見つかることが多いのか、その理由が分かれば、次にお話しする「じゃあ、どうすればいいの?」という対策が、より具体的に考えられるようになります。もう少しだけ、お付き合いくださいね!
認知症行方不明なぜ見つからないを防ぐための具体的な対策

すぐにできる認知症の行方不明の探し方
万が一、ご家族の姿が見えないことに気づいた時、多くの人はパニックに陥ってしまいます。しかし、そんな時こそ深呼吸をして、落ち着いて行動することが何よりも大切です。初期対応の速さと的確さが、その後の結果を大きく左右すると言っても過言ではありません。
ステップ1:まずは警察へ速やかに連絡
私がこれまでご相談を受けた中で、ご家族が最も後悔されるのが「警察への連絡の遅れ」です。「もう少し待てば帰ってくるかも」「大袈裟にしたくない」という気持ちは絶対に禁物です。いなくなったことに気づいたら、1秒でも早く、ためらわずに110番通報、もしくは最寄りの警察署・交番に連絡してください。
行方不明届を提出することで、ご家族からの情報が即座に全国の警察システムに登録されます。これにより、パトロール中の警察官が本人の特徴と照合したり、職務質問で保護したりと、組織的な捜索活動が開始されます。これが早期発見への最も確実な道筋です。
警察に正確に伝えるべき重要情報
- 本人の情報:氏名、年齢、性別、身長、体型、髪型、身体的な特徴(ほくろ、あざ、歩き方など)
- 服装・持ち物:いなくなった時に着ていた服(上下)、靴、帽子の色や特徴。カバンや杖の有無。
- 写真:できるだけ最近撮影した、顔や全身がはっきりとわかる写真。スマホの画像でも大丈夫です。
- 健康状態:認知症の進行度、持病、かかりつけ医、服用している薬の情報。
- 考えられる行き先:本人の過去の記憶(故郷、元職場など)から推測される場所や、最近の言動など。
これらの情報を事前にメモなどにまとめておくと、いざという時に慌てず、正確に伝えることができますよ。
ステップ2:地域包括支援センターやケアマネジャーにも連絡
警察への連絡と並行して、日頃から介護でお世話になっている専門家にも必ず連絡を入れましょう。市区町村が設置する地域包括支援センターや、担当のケアマネジャーは、地域における高齢者支援のプロフェッショナルです。
彼らは地域の「見守りネットワーク(SOSネットワーク)」を熟知しており、連絡を受けると、地域の協力機関(バス・タクシー会社、郵便局、金融機関、コンビニ、スーパーなど)に一斉に情報網を発動してくれます。これにより、警察の捜索網とは別に、地域住民や事業者の「日常の目」が加わり、捜索の範囲と精度が格段に向上します。まさに、地域全体で捜索する体制を築くための司令塔のような存在なのです。
今日から始める認知症の行方不明対策

行方不明は、起こってしまってから対応するのでは、ご家族の心労も計り知れません。最も重要なのは、「いつか起こるかもしれない」という前提に立ち、日頃から備えておくことです。今日からでも始められる対策はたくさんあります。
テクノロジーを活用した見守り
現代では、便利な機器を活用することで、ご家族の安心感を大きく高めることができます。
- GPS端末:今は本当に小型で高性能なものがたくさんあります。本人が気づかないうちに靴に内蔵できるタイプや、カバンにつけられるキーホルダー型、お守り袋に入れておけるタイプなど、本人の性格や生活スタイルに合わせて選びましょう。スマートフォンでいつでも居場所が確認できる安心感は、何物にも代えがたいものです。
- ドアセンサー・離床センサー:玄関のドアや寝室のベッドにセンサーを設置し、本人が一人で外に出ようとしたり、夜中に起き出したりした際に、家族のスマートフォンに通知が届く仕組みです。特に夜間の無断外出を防ぐのに非常に効果的です。
アナログながら効果的な対策
ハイテク機器だけでなく、昔ながらの方法も依然として非常に有効です。
| 対策の種類 | 具体的な方法とポイント |
|---|---|
| 衣類・持ち物への情報記入 | 本人がよく着る上着やズボンのタグ、帽子、カバン、杖などに、油性ペンで名前と連絡先を書いた布を縫い付けておきます。保護された際に、すぐに身元が判明する最も確実な方法の一つです。 |
| 見守りシール・QRコード | お住まいの市区町村によっては、アイロンで衣類に貼り付けられる「見守りシール」や、読み取ると登録情報が表示されるQRコード付きのシールを無料で配布しています。地域包括支援センターなどで相談してみましょう。 |
| ご近所との関係づくり | 日頃から「いつもお世話になっています」と挨拶を交わし、「実はうちの母、少し物忘れがあって…」とオープンに話しておくことが、何よりの防犯網になります。「徘徊」は決して恥ずかしいことではありません。 |
厚生労働省も、こうした認知症施策の中で、地域全体での見守り体制の構築を推進しています。ご家族だけで抱え込まず、社会のリソースを積極的に活用する視点が大切です。
認知症の行方不明者についてよくあるご質問FAQ
-
Q1. 認知症の行方不明捜索に費用はかかりますか?
-
A1. 警察や消防団による公的な捜索活動に費用はかかりません。ただし、ご家族の判断で民間の捜索サービスなどを利用した場合は、もちろん費用が発生します。
-
Q2. 徘徊が始まったら、もう外出させない方が安全ですか?
-
A2. 外出を完全に制限すると、本人の心身機能の低下やストレス増加に繋がります。GPSを持たせる、家族が付き添うなどの対策を取りながら、安全な形での散歩や外出は続ける方が良いとされています。
-
Q3. SOSネットワークに登録するにはどうすればいいですか?
-
A3. お住まいの市区町村の高齢福祉課や、地域包括支援センターで登録手続きができます。事前に登録しておくことで、万が一の際に迅速な情報共有が可能になりますので、ぜひ相談してみてください。
認知症で行方不明、見つからない時の行動

警察や地域に連絡した後、家族としてできることは何でしょうか。やみくもに探すのではなく、ポイントを絞って行動することが大切です。前述の通り、ご本人の思い出の場所や過去の生活圏を重点的に探してみましょう。
通勤で使っていた駅、よく通ったお店、昔住んでいた家の周辺など、具体的な場所をリストアップして、手分けして確認に向かうのが効果的です。
また、捜索中は、ご本人が好きだった歌を歌ったり、名前を呼びかけたりすることも有効と言われています。遠くまで声は届かなくても、近くに潜んでいる場合に本人の注意を引くきっかけになるかもしれません。
何よりも、捜索するご家族自身が体力を消耗しすぎないよう、交代で休憩を取り、一人で抱え込まないことが重要です。
行方不明者が見つからない場合はどうしたらいいですか?
捜索が長期化し、数週間、数ヶ月と経過しても見つからない場合、ご家族の心労は計り知れません。このような状況になった場合、法的な手続きも視野に入れる必要が出てきます。
具体的には、家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てる制度があります。これは、生死が7年間明らかでない場合に、法律上死亡したものとみなす「普通失踪」と、戦争や災害などで1年間生死不明の場合の「危難失踪」があります。行方不明の場合は、前者に該当する可能性があります。
失踪宣告が認められると、相続の開始や生命保険金の受け取りなどが可能になります。しかし、これはあくまで法的な区切りであり、ご家族の心情的な整理とは別の問題です。このような段階になった場合は、弁護士などの専門家に相談しながら、慎重に手続きを進めることをお勧めします。(参考:裁判所「失踪宣告」)

たくさんの対策をお話ししてきましたが、一番大切なのは、ご家族だけで問題を抱え込まないことです。今は便利なツールも、地域や行政のサポート体制も整っています。
使えるものは何でも使って、家族みんなで大切な人を見守っていく。そんな気持ちが、きっと一番の対策になりますよ。
まとめ:認知症行方不明なぜ見つからないかを知り備える

- 認知症の行方不明者は99%以上が1週間以内に発見される
- しかし時間が経つと生存率は著しく低下し3日目が一つの目安
- 見つからない主な理由は記憶障害や見当識障害、本人の心理状態
- 家族の「うちの親は大丈夫」という思い込みが対応を遅らせる危険がある
- 発見場所は5キロ圏内の山林や水路など人目につきにくい場所が多い
- 本人の過去の記憶(元自宅や職場)に関連する場所に向かう傾向もある
- 行方不明になると脱水症状や低体温症、二次的な事故のリスクが高まる
- 死因は溺死や滑落、低体温症などが報告されている
- 行方不明に気づいたら「様子見」せずすぐに警察へ通報することが最重要
- ケアマネジャーや地域包括支援センターにも連絡しSOSネットワークを活用する
- 事前の対策としてGPS端末の活用や衣類への連絡先記入が有効
- 日頃から近所付き合いを大切にし地域に見守りの協力を頼む姿勢が大事
- 公的な捜索に費用はかからないが民間サービスは有料
- 捜索が長期化した場合は失踪宣告という法的手続きも視野に入る
- 最も重要なのは家族だけで抱え込まず社会のサポートを積極的に利用すること
▼あわせて読みたい関連記事▼

お気軽にご相談ください
相続は100人いれば、100通り
唯一無二の最適な相続をご提案いたします
CONTACT
専門家やえさん

- 専門家やえさん
-
堀川 八重(ほりかわ やえ)
大阪不動産・FPサービス株式会社 代表
15年以上にわたり1,500組を超えるご家族の相続や不動産のお悩みに、専門家として寄り添ってまいりました。私の信条は、法律や数字の話をする前に、まずお客様ご家族の歴史や言葉にならない想いを丁寧に「聞く」こと。信頼できる各分野の専門家チームと共に、皆様が心から安心できる最善の道筋をオーダーメイドでご提案します。一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。
最新の投稿
 お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説
お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説 相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説
相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説 お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例
お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例 お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説
お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説






