「お墓参りに行くんだけど、お供え物って何を持っていけばいいんだっけ?」「お菓子の置き方とか、飲み物の作法とか、実はあまり自信がないのよね…」なんて、ふと思うこと、ありませんか?こんにちは!終活やご供養のアドバイザー、やえです。
お墓参りって、故人を思う大切な時間ですけど、意外と細かいルールが多くて戸惑いますよね。特にお供え物に関しては、食べ物やお酒、ペットボトルのお供え、さらには半紙は必要なのか、法事の時はどうするのか、など疑問は尽きません。
そして、お供えした後にその場で食べるのはアリなのか、持ち帰るべきなのか、その後の処分はどうすればいいのか…考え出すとキリがないかもしれません。でも、ご安心ください!この記事を読めば、お墓へのお供え物に関するアレコレが、スッキリ解決しますよ。
この記事のポイント
- お供え物の基本的な種類と選び方
- 食べ物や飲み物をお供えする際の具体的な作法
- お供えをした後の正しい後始末とマナー
- 法事など特別な日のお供えに関する注意点

ご先祖様や故人を思うお気持ちが何よりも大切。これは大前提です。でも、そこに正しいマナーや知識が加わると、もっと清々しい気持ちでお参りができると思いませんか?基本的な作法から、意外と知られていない注意点まで、分かりやすくお伝えしていきますね。ご自身の心遣いが、きっと故人にも、そして周りの方にも届きますよ。一緒に確認していきましょう!
目次
お墓お供え物置き方基本をおさえる
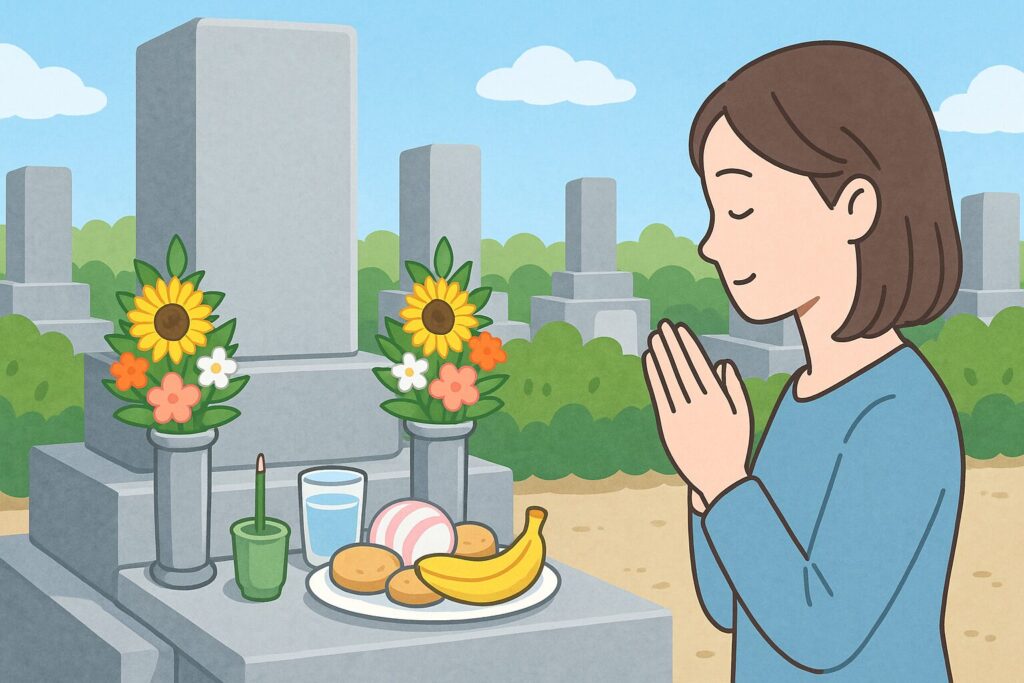
お墓へのお供え物には何がありますか?
お墓参りのお供え物、いざ準備するとなると「何がいいんだっけ?」と迷ってしまうこと、ありますよね。基本として覚えておきたいのが、仏教における「五供(ごくう)」という考え方です。これは、お供え物の基本となる5つの要素を指していて、故人への感謝や供養の気持ちを表すためにとても大切なものなんですよ。
具体的には、「香」「花」「灯燭(とうしょく)」「浄水(じょうすい)」「飲食(おんじき)」の5つです。
| 種類 | 内容 | 意味・役割 |
|---|---|---|
| 香 | お線香 | 香りで心身を清め、故人に食事を楽しんでもらう(食香)という意味があります。 |
| 花 | 生花(仏花) | ご先祖様への感謝の気持ちを表し、心を穏やかにしてくれます。 |
| 灯燭 | ろうそく | 闇を照らす仏様の知恵を象徴し、煩悩を消し去るとされています。 |
| 浄水 | きれいな水 | 心を洗い清めるという意味があります。 |
| 飲食 | 食べ物や飲み物 | 故人が生前好きだったものをお供えし、偲ぶ気持ちを表します。 |
このように、普段私たちが何気なくお供えしているものには、一つひとつに深い意味が込められているんですね。もちろん、最も大切なのは故人やご先祖様を思う気持ちですから、厳格にすべてを揃える必要はありません。ただ、この基本を知っておくと、より心のこもったお墓参りができるのではないでしょうか。
食べ物やお菓子をお供えする際の注意点

「飲食」としてお供えする食べ物やお菓子は、故人を偲ぶ上でとても身近な供え物ですよね。「おじいちゃん、このお饅頭が好きだったなあ」なんて思い出しながら選ぶ時間は、とても尊いものです。基本的には、故人が生前好きだったものをお供えするのが一番の供養になります。
ただ、いくつか知っておきたい注意点もあるんです。
お供えする食べ物で避けたいもの
- 肉や魚などの生もの:仏教では殺生を禁じているため、殺生を連想させるものは避けるのが一般的です。
- 香りの強いもの:ニンニクやニラなど、香りが強すぎる食べ物は、他の参拝者の迷惑になる可能性があるため控えるのがマナーです。
- 日持ちしないもの:特に夏場は、生クリームを使ったケーキなど、傷みやすいものは避けた方が安心です。
お菓子であれば、分けやすいように個包装になっているものや、季節を感じさせる果物などがおすすめです。お供えする際は、包装紙から出して、中身が見えるようにお供えすると、故人が召し上がりやすいと言われていますよ。
飲み物やペットボトルをお供えする作法
食べ物とセットでお供えすることが多い飲み物。これも故人が好きだったジュースやお茶、コーヒーなどを用意するのが良いでしょう。ここでもちょっとした作法があるんです。
一番のポイントは、缶やペットボトルの蓋を開けてお供えすること。これは、故人がすぐに飲めるように、という心遣いの表れなんです。また、より丁寧にするなら、湯呑みやコップを持参して、そこに移し替えてからお供えすると、さらに気持ちが伝わります。
飲み物をお供えする際のポイント
- 故人が好きだった飲み物を選ぶ。
- 缶やペットボトルの場合は、必ず蓋を開ける。
- 可能であれば、湯呑みやコップに移し替える。
- お酒の場合は墓石にかけない(後述します)。
ただし、注意点として、糖分を含むジュースやコーヒー、お茶などを墓石にこぼしてしまうと、シミや変色の原因になったり、虫が集まってきたりすることがあります。お供えする際には、こぼさないように十分気を付けてくださいね。
お供え物の下に半紙を敷く意味とは
お供え物を置くときに、半紙や懐紙(かいし)を下に敷いているのを見かけたことはありませんか?「あれって、何のためにやっているんだろう?」と疑問に思った方もいらっしゃるかもしれませんね。
これには、ちゃんとした意味があるんです。主な理由としては、以下の2つが挙げられます。
理由1:敬意を表すため
お供え物を墓石に直接置くのは、少し失礼にあたるという考え方があります。半紙を一枚敷くことで、「お皿」の代わりとなり、故人やご先祖様への敬意を示すことができるのです。
理由2:墓石を汚さないため
前述の通り、果物の汁や食べ物の油分が墓石に付着すると、シミや変色の原因になります。半紙を敷くことで、大切なお墓をきれいに保つという実用的な意味合いもあるんですよ。
半紙は100円ショップなどでも手軽に購入できますので、お墓参りの持ち物に加えてみてはいかがでしょうか。必須ではありませんが、こうした小さな心遣いが、より丁寧なご供養につながります。
法事におけるお墓へのお供え物の選び方
四十九日や一周忌といった法事の際にお墓参りをすることもありますよね。普段のお墓参りと、法事の時とで、お供え物は変えた方が良いのでしょうか?
結論から言うと、基本的な考え方は同じで、必ずこうしなければならないという厳格な決まりはありません。ただ、法事は親族などが集まる大切な節目ですので、普段より少しだけ格式を意識すると良いかもしれませんね。
例えば、以下のようなものがよく選ばれています。
- 分けやすい個包装のお菓子:参列者で分け合う(お下がりをいただく)ことを想定して、持ち帰りやすいものが喜ばれます。
- 少し高級な果物の盛り合わせ:見た目も華やかになり、特別な日のお供え物としてふさわしいです。
- 故人にゆかりのある品:普段のお参り以上に、故人の思い出を語り合うきっかけになるような品を選ぶのも素敵です。
また、お供え物には「のし(熨斗)」をかけるのが一般的です。表書きは「御供」とし、水引は黒白か双銀の結び切りを選びましょう。地域や宗派によって習慣が異なる場合もあるので、心配な場合は年長の親族やお寺さんに相談してみるのが一番確実ですよ。

お供え物で意外とトラブルになりやすいのが、実は「後始末」なんです。特にカラスや猫などの動物に荒らされてしまうと、自分のお墓だけでなく、霊園全体が汚れてしまい、他の方にまでご迷惑をかけてしまうケースがあります。故人を思う気持ちと同じくらい、「周りへの配慮」を大切にすることが、気持ちの良いお墓参りの秘訣ですよ。
間違いやすいお墓お供え物置き方と後始末

お墓へのお供え物でお酒は避けるべきか
「お酒好きだった父のために、ビールをお供えしたいんだけど…」というお話、よく耳にします。故人がお酒好きだった場合、ぜひお供えしてあげたいですよね。もちろん、お酒をお供えすること自体は、全く問題ありません。
ただし、一つだけ絶対にやってはいけないことがあります。それは、墓石にお酒をかけることです。
これをやってしまうと、お酒に含まれる糖分や酸が墓石を傷め、シミや変色、カビの原因になってしまいます。一度ついたシミは、専門の業者に頼まないと落とせないことも多く、修復に高額な費用がかかる場合も。感謝の気持ちが、逆にお墓を傷つけてしまうなんて、悲しいですよね。
お酒をお供えする際の注意点
お酒は、缶や瓶の蓋を開けて、コップなどに注いでお供えしましょう。そして、お参りが終わったら、必ず持ち帰るようにしてください。故人を思う気持ちは、かけがえのないもの。大切なお墓を守るためにも、このルールはぜひ覚えておいてくださいね。
ちなみに、宗派によっては飲酒を良しとしない場合もありますので、気になる方は事前にお寺さんへ確認しておくとより安心です。
お供え物をその場で食べるのは良いのか
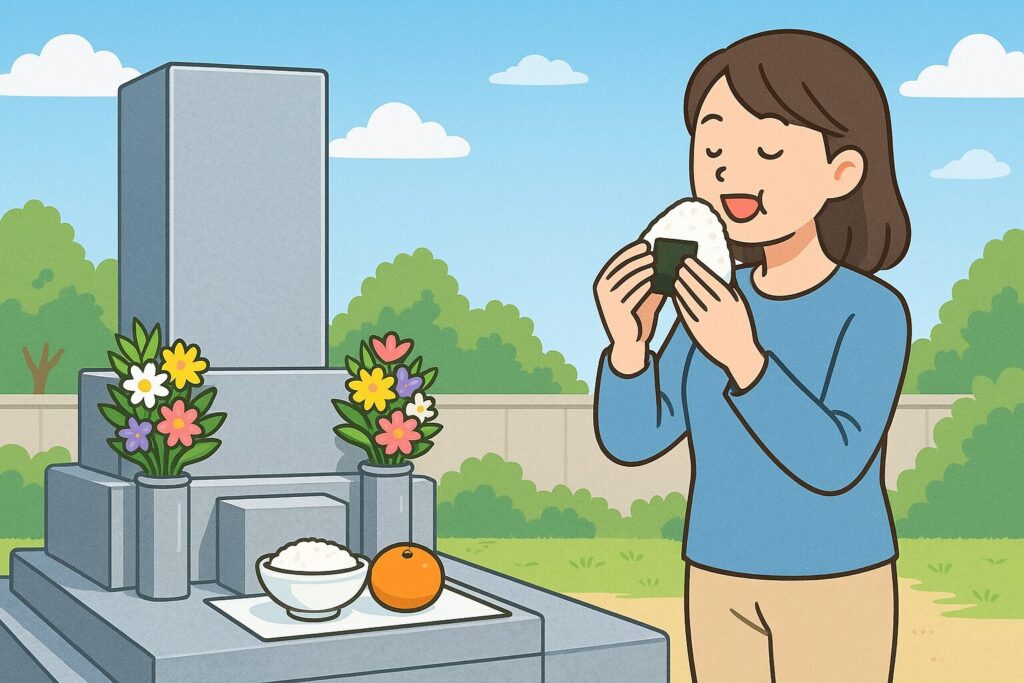
お供えしたお下がりをその場でいただくこと。これって、マナー違反なんでしょうか?実は、これは「ご先祖様と食事を共にする」という意味合いがあり、とても良いことだとされています。仏様やご先祖様へのお供え物を、後から私たちがいただくことを「お下がり」と呼び、これを食べることで、そのご利益を分けてもらえると考えられているんですよ。
ただし、これも時と場合によります。お墓はあくまで故人を偲ぶ神聖な場所です。大声で騒いだり、宴会のように長時間居座ったりするのは、もちろんNG。他にお参りに来ている方もいらっしゃいますから、周りの方々への配慮を忘れないことが大前提です。
お供えしたお菓子を一口いただく、といった程度であれば、故人もきっと喜んでくれるはず。節度ある行動を心がけたいですね。
お墓参りのお供えは持ち帰るのがマナー
さて、ここが一番大切なポイントかもしれません。お参りが終わった後、お供えした食べ物や飲み物は、どうすれば良いのでしょうか?答えは、「必ず持ち帰る」が正解です。
「え、置いて帰っちゃダメなの?」と思われるかもしれませんが、これにはちゃんとした理由があります。
お供え物を持ち帰るべき理由
- 動物に荒らされるのを防ぐため:カラスや猫、その他の動物が食べ物を漁り、お墓の周りを汚してしまう原因になります。
- 墓石をきれいに保つため:食べ物が腐敗したり、飲み物がこぼれたりすると、墓石のシミや劣化につながります。
- 衛生上の問題を防ぐため:腐った食べ物は悪臭や害虫の発生源となり、霊園全体の環境を悪化させてしまいます。
- 他の参拝者への配慮:散らかったお墓は、見ていて気持ちの良いものではありませんよね。
多くの霊園や墓地では、管理規約で「お供え物は持ち帰ること」と定められています。詳しくは、都立霊園の公式サイトなど、各霊園のルールを確認してみてください。みんなが気持ちよくお参りできるよう、このマナーは必ず守るようにしましょう。
お供え物をした後の処理と処分方法
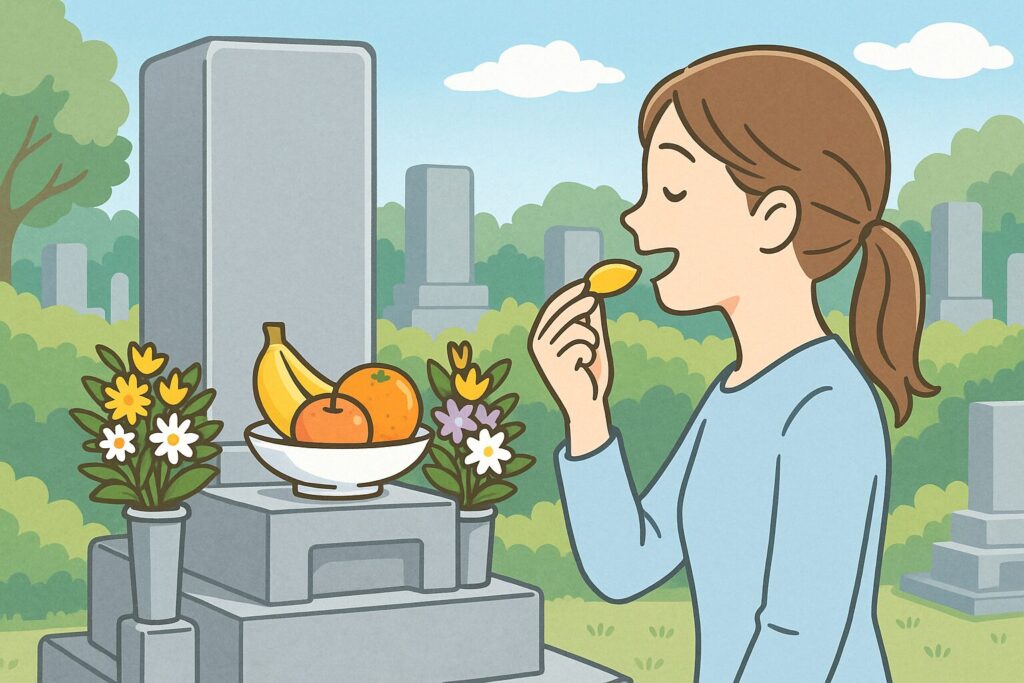
「持ち帰ったはいいけど、このお供え物、どうしよう?」と悩む方もいらっしゃいますよね。持ち帰った供え物は、先ほどお話しした「お下がり」です。ご先祖様からのお福分けと考えて、ご家族でいただくのが一番良い供養になります。
「故人を偲びながら、みんなで美味しくいただく」。これが理想的な形です。
とはいえ、量が多くて食べきれなかったり、傷んでしまったりすることもありますよね。その場合は、食べ物に感謝の気持ちを伝え、白い紙(半紙が望ましい)に包んで塩で清めてから、生ゴミとして処分するのが丁寧な方法です。可燃ゴミとして処分することに、何ら問題はありませんのでご安心ください。大切なのは、最後まで感謝の気持ちを忘れないことです。
お墓参りについてよくあるご質問FAQ
-
お供え物はいつまで置いておいていいですか?
-
お参りをしている間だけお供えし、帰る際には必ず持ち帰るのがマナーです。長時間放置すると、動物に荒らされたり、腐敗したりする原因となります。お参りが終わったら、すぐに片付けるようにしましょう。
-
お供えしたお花の処分はどうすればいいですか?
-
枯れた花は、お墓参りの際に新しい花と交換し、持ち帰って処分するのが基本です。多くの霊園では、古い花を捨てるためのゴミ箱が設置されている場合もありますので、その場合は霊園のルールに従ってください。そのまま放置すると、見た目も悪く、衛生的にも良くありません。
-
偽物のお花(造花)をお供えしてもいいですか?
-
頻繁にお墓参りに行けない場合など、お墓が寂しくならないようにと造花をお供えする方も増えています。生花が基本とされていますが、造花をお供えすること自体は問題ありません。ただし、長期間放置すると色褪せたり、汚れたりしてかえってみすぼらしくなってしまうことも。定期的にお手入れや交換ができると良いですね。霊園によっては禁止されている場合もあるので、事前に確認が必要です。
正しいお墓お供え物置き方を理解しよう

この記事では、お墓へのお供え物の置き方に関する基本的なマナーから、後始末の方法まで詳しく解説してきました。最後に、大切なポイントをまとめておきましょう。
- お供え物の基本は「五供」という考え方
- 食べ物は故人が好きだったものを選ぶのが一番
- 肉や魚、香りの強いものは避けるのが一般的
- お菓子は個包装のもの、果物などがおすすめ
- 飲み物は蓋を開け、できればコップに移す
- お供え物の下には半紙を敷くとより丁寧
- 墓石を汚さない、傷めない配慮が大切
- 法事の際は少し格式を意識し、のしをかける
- お酒を墓石にかけるのは絶対にNG
- お下がりをその場でいただくのは良いこと
- ただし周りの迷惑にならない範囲で
- お参りが終わったらお供え物は必ず持ち帰る
- 動物による被害や墓石の劣化を防ぐため
- 持ち帰ったお供え物は家族でいただくのが一番の供養
- 食べきれない場合は感謝して処分する

▼あわせて読みたい関連記事▼
お墓の花は一対でないとダメ?現代マナーと失礼にならない供え方
終活とは?意味と始め方をわかりやすく解説|初心者が損しない準備法

お気軽にご相談ください
相続は100人いれば、100通り
唯一無二の最適な相続をご提案いたします
CONTACT
専門家やえさん

- 専門家やえさん
-
堀川 八重(ほりかわ やえ)
大阪不動産・FPサービス株式会社 代表
15年以上にわたり1,500組を超えるご家族の相続や不動産のお悩みに、専門家として寄り添ってまいりました。私の信条は、法律や数字の話をする前に、まずお客様ご家族の歴史や言葉にならない想いを丁寧に「聞く」こと。信頼できる各分野の専門家チームと共に、皆様が心から安心できる最善の道筋をオーダーメイドでご提案します。一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。
最新の投稿
 お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説
お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説 相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説
相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説 お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例
お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例 お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説
お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説






