お世話になった友人やパートナーを助けたい、そんな優しい気持ちで「友達にお金をあげると税金はかかりますか?」と調べていませんか?結論から言うと、贈与税いくらから他人への贈与で発生するかは、年間110万円を超えるかどうかで決まります。
つまり、他人から100万円をもらったら贈与税はかかりません。ただし、贈与税が複数人からであっても、受け取った側の合計金額で判断される点には注意が必要です。
例えば、他人への仕送りという名目でも、扶養義務がないため原則として贈与税の対象となります。
この記事では、贈与税が他人からの贈与でかからない方法の基本から、贈与税の計算シュミレーション、例えば贈与税が200万円や500万円、1000万円、そして贈与税が3000万円でいくらになるのかまで、贈与税の他人に関する計算を具体例で分かりやすく解説しますね。
この記事のポイント
- 他人への贈与で贈与税がいくらから発生するかの基本
- 贈与税がかからない方法と、他人には適用されない非課税ルール
- 200万円から3000万円まで、金額別の贈与税計算シミュレーション
- 贈与税の申告で失敗しないための注意点とよくある質問

こんにちは、専門家のやえです。
大切な人への「ありがとう」や「頑張って」の気持ちが、思わぬ税金問題に繋がったら悲しいですよね。他人への贈与は、親子間とは少しルールが違います。でも、基本さえ押さえれば大丈夫。
この記事で、あなたの優しい気持ちを安心して届けられるよう、しっかりお手伝いしますね。
贈与税いくらから他人にかかる?基本ルール

友達にお金をあげると税金はかかりますか?
はい、ご友人や恋人、お世話になった方など、法律上の扶養義務がない「他人」にお金を渡した場合、原則として贈与税の課税対象になります。これは、贈与税が親子や夫婦といった親族間に限定されず、個人から個人へ財産が無償で渡されたすべてのケースを対象としているためです。
「感謝の気持ちで少し渡しただけなのに…」と驚かれるかもしれませんが、法律上の考え方では、金額の大小にかかわらず財産を無償で渡す行為そのものが「贈与」と定義されています。ただ、もちろんご安心ください。
実際には、すべての贈与に対して税金がかかるわけではありません。贈与税には「基礎控除」という非課税の枠がきちんと設けられています。
この基礎控除の仕組みを正しく理解することが、他人への善意のプレゼントで税金の心配をしないための最も重要な第一歩となります。この後の項目で、その金額やルールについて詳しく見ていきましょう。
他人から100万円もらう贈与税はいくら?

結論から申し上げますと、他人から1年間(その年の1月1日から12月31日まで)に受け取った金額の合計が100万円だった場合、贈与税は0円で、税務署への申告も不要です。
その理由は、贈与税には年間110万円の基礎控除額が法律で定められているからです。この制度は「暦年課税制度」と呼ばれ、財産をもらった人(受贈者)一人につき、1年間の贈与合計額が110万円以下であれば、贈与税は一切かからないという仕組みになっています。
基礎控除の最重要ポイント
「もらった人」を基準に「1年間で合計110万円まで」という点が非常に重要です。この110万円という金額は、贈与税を考える上での絶対的な基準となります。他人からの贈与だけでなく、親や兄弟などからの贈与も含めて、すべての贈与を合計した金額がこの範囲内に収まっていれば、税金の心配をする必要はありません。
したがって、ご質問のケースである100万円という金額は、110万円の非課税枠の中に完全に収まるため、贈与税は発生しない、という明確な答えになります。
贈与税は複数人からでも合計額で計算
ここで、多くの方が勘違いしやすい非常に重要な注意点についてお話しします。年間110万円の基礎控除は、「お金をあげる側(贈与者)」一人ひとりに対してではなく、「お金をもらう側(受贈者)」がその年にもらった合計金額で判断されるということです。
つまり、複数の友人からお祝いなどでお金をもらった場合、それぞれの方からの金額が110万円以下であっても、1年間にあなたが受け取った合計金額が110万円を超えてしまうと、その超えた部分が贈与税の課税対象となってしまいます。
知らないと損する!よくある勘違いの例
例えば、あなたが同じ年に、友人Aさんから起業のお祝いで80万円、お世話になったBさんから50万円をもらったとします。
- Aさんから:80万円(110万円以下だから大丈夫!)
- Bさんから:50万円(これも110万円以下だからセーフ!)
…とはなりません!
この場合、税務署はあなたが受け取った年間の合計金額、つまり130万円(80万円+50万円)に注目します。この合計額から基礎控除110万円を差し引いた20万円に対して、贈与税が課税されることになります。
このルールを知らずに申告漏れとなり、後から税務署の指摘を受けるケースは本当に多いので、しっかりと覚えておきましょう。
贈与税が他人からの贈与でもかからない方法

前述の通り、他人への贈与で贈与税がかからないようにする最も基本的で確実な方法は、年間に渡す(受け取る)財産の合計額を110万円以下にしっかりと管理することです。これが暦年課税の基礎控除を最大限に活用する、最もシンプルな贈与税対策となります。
もし、110万円を超える金額、例えば300万円を支援したいと考えている場合は、複数年に分けて贈与するという方法が有効です。具体的には、3年間に分けて毎年100万円ずつ贈与すれば、各年の贈与額は基礎控除の110万円の範囲内に収まるため、結果として贈与税はかからずに済みます。
ただし、この分割贈与には一つ注意点があります。毎年同じ時期に同じ金額を贈与し続けると、税務署から「あらかじめ300万円を贈与する約束があり、それを分割で支払っているだけ」と見なされる「定期贈与」と判断されるリスクがあります。
そうなると、合計額である300万円に対して一括で課税される可能性も出てきます。このリスクを避けるためにも、贈与の都度、日付や金額を明記した「贈与契約書」を作成しておくことが、後々のトラブルを防ぐ上で非常に有効な手段となります。
他人への仕送りは贈与税の対象になる?
「親子間での生活費の仕送りは非課税って聞いたことがあるけど、これが友人やパートナーでも同じように扱われるの?」というご質問は、私のところにも非常によく寄せられます。
これに対する答えは、残念ながら「原則として贈与税の対象になります」となります。なぜなら、国税庁の指針によると、生活費や教育費が非課税となるのは、法律で定められた「扶養義務者」(夫婦、親子、兄弟姉妹など、互いに生活を支え合う義務がある関係)の間柄に限定されているからです。友人や恋人、事実婚・内縁関係のパートナーなどは、この扶養義務者に含まれません。
したがって、たとえ生活に困っている友人を助けるための仕送りであっても、税法上は純粋な「贈与」として扱われるのが原則です。この場合も、年間の合計額が110万円を超えれば贈与税の申告と納税が必要になりますので、注意しましょう。

基本ルール、ご理解いただけましたか?他人への贈与は「もらった人が年間合計で110万円まで」というのが鉄則です。
ここからは、いよいよ具体的な税額計算に入っていきましょう。「もし110万円を超えたら、一体いくら払うの?」という疑問に、速算表を使いながら分かりやすくお答えします。
シミュレーションで、安心を手に入れましょう!
贈与税いくらから他人への贈与で発生?計算例

贈与税の計算シュミレーション(他人向け)
年間の贈与額が110万円を超えた場合、贈与税は以下の計算式で具体的に算出します。他人への贈与の場合は、親から成人した子への贈与(特例税率)よりも税率が高くなる「一般税率」という区分が適用されますので、注意が必要です。
(1年間にもらった財産の合計額 - 基礎控除110万円) × 税率 - 控除額 = 贈与税額
この計算式で使う「税率」と「控除額」は、基礎控除を引いた後の金額(課税価格)によって段階的に変わります。下の速算表を使って、ご自身のケースを当てはめながら見ていきましょう。
【一般贈与財産用】贈与税の速算表
この表は、兄弟間、夫婦間、他人への贈与、または親から未成年の子への贈与の場合に適用されます。
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | - |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
(出典:国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税))
他人への贈与税200万円はいくら?

では、最初のシミュレーションです。もし他人から年間で合計200万円の財産をもらった場合、贈与税はいくらになるのでしょうか。一緒に計算してみましょう。
【計算例】200万円の贈与を受けた場合
- 基礎控除後の課税価格を計算します:
200万円 - 110万円(基礎控除) = 90万円 - 速算表を適用します:
課税価格90万円は、上の表の「200万円以下」の区分に該当します。そのため、税率は10%、控除額は0円です。 - 贈与税額を計算します:
90万円 × 10% - 0円 = 9万円
このケースでは、納めるべき贈与税額は9万円となります。
他人への贈与税500万円の計算方法
次に、もう少し金額が大きくなり、年間で合計500万円の贈与を受けたケースを見ていきましょう。金額が上がると税率の区分も変わってきます。
【計算例】500万円の贈与を受けた場合
- 基礎控除後の課税価格を計算します:
500万円 - 110万円(基礎控除) = 390万円 - 速算表を適用します:
課税価格390万円は「400万円以下」の区分に該当するため、税率は20%、控除額は25万円です。 - 贈与税額を計算します:
(390万円 × 20%) - 25万円 = 78万円 - 25万円 = 53万円
この場合の贈与税額は53万円です。もらった金額の約1割が税金として必要になる計算ですね。
他人への1000万円の贈与税を計算

さらに金額が上がり、年間で1,000万円というまとまった金額の贈与を他人から受けた場合の税額を計算してみましょう。
【計算例】1,000万円の贈与を受けた場合
- 基礎控除後の課税価格を計算します:
1,000万円 - 110万円(基礎控除) = 890万円 - 速算表を適用します:
課税価格890万円は「1,000万円以下」の区分に該当します。税率は40%、控除額は125万円となります。 - 贈与税額を計算します:
(890万円 × 40%) - 125万円 = 356万円 - 125万円 = 231万円
贈与税額は231万円となり、かなり大きな金額の納税が必要になることがお分かりいただけると思います。
贈与税3000万円はいくらになる?
最後に、かなり高額なケースとして、年間で3,000万円の贈与を受けた場合をシミュレーションしてみましょう。税率もかなり高くなります。
【計算例】3,000万円の贈与を受けた場合
- 基礎控除後の課税価格を計算します:
3,000万円 - 110万円(基礎控除) = 2,890万円 - 速算表を適用します:
課税価格2,890万円は「3,000万円以下」の区分ですので、税率は50%、控除額は250万円です。 - 贈与税額を計算します:
(2,890万円 × 50%) - 250万円 = 1,445万円 - 250万円 = 1,195万円
贈与税額は1,195万円にも達します。このように、何の対策もせずに高額な財産を一度に贈与すると、その約3分の1以上が税金として徴収される可能性があるため、計画的な贈与がいかに重要かご理解いただけたかと思います。
贈与税いくらから他人についてよくあるご質問FAQ
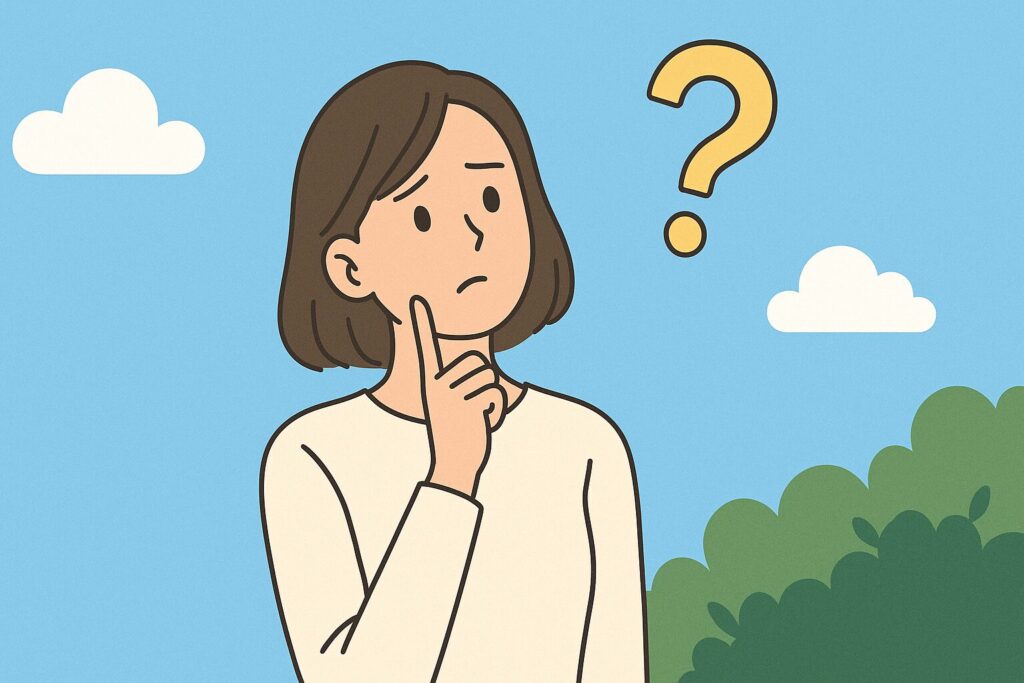
-
贈与税の申告はいつまでに、どこでするのですか?
-
贈与税の申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日までの期間内に行います。申告書を提出する場所は、財産をもらった人(受贈者)の住所地を管轄する税務署です。
-
手渡しでお金をもらった場合、税務署にばれないのではないでしょうか?
-
手渡しでも税務署に発覚する可能性は高いと言えます。例えば、もらったお金で不動産や車を購入したり、多額の現金を銀行に預金したりすると、その資金の出所について税務署から「お尋ね」が来ることがあります。
-
他人から不動産をもらった場合の金額はどう計算しますか?
-
不動産の贈与税を計算する際の評価額は、実際の売買価格ではなく相続税評価額を使います。土地であれば路線価、建物であれば固定資産税評価額を基に計算するため、時価よりも低くなることが多いです。
-
贈与税を払わなかった場合のペナルティはありますか?
-
期限内に正しい申告と納税をしなかった場合、重いペナルティが課されます。本来納めるべき税金に加えて、無申告加算税や、納付が遅れた日数に応じた延滞税を追加で支払うことになります。

最後までお読みいただき、本当にありがとうございます!
他人への贈与は、金額が大きくなると税金の負担も大きくなることがお分かりいただけたかと思います。一番大切なのは、贈与する側とされる側、双方がルールを理解しておくこと。
この記事が、あなたの大切な想いをスムーズに届けるための一助となれば、これほど嬉しいことはありません。
まとめ:贈与税いくらから他人に発生か再確認
他人への贈与は、善意から始まるものですが、税金のルールを知らないと思わぬ負担が発生することがあります。最後に、この記事で解説した重要なポイントをまとめました。
- 他人への贈与は年間110万円を超えると贈与税の対象になる
- 110万円の基礎控除はもらう側一人あたりの年間の合計額で計算する
- 複数人から贈与を受けても合計が110万円を超えれば課税対象
- 他人への生活費や教育費の援助は原則として非課税にならない
- 贈与税がかからない方法は年間の贈与額を110万円以下に抑えること
- 他人への贈与には親子間の特例税率より高い一般税率が適用される
- 200万円の贈与で税額は9万円
- 500万円の贈与で税額は53万円
- 1000万円の贈与では税額が231万円になるケースがある
- 3000万円の贈与では税額が1195万円と高額になる
- 贈与税の申告と納税は贈与を受けた翌年の3月15日までに行う
- 手渡しや現金での贈与でも税務署に発覚する可能性は高い
- 無申告は加算税や延滞税などの重いペナルティが課される
- 高額な贈与を検討する場合は計画的に行うか専門家への相談が安心
▼あわせて読みたい関連記事▼
- 贈与生活費いくらで課税?非課税の境界線を専門家が解説
- paypay贈与税は現金と同じ扱い|申告漏れで後悔しないための完全ガイド
- 生前贈与お礼状例文とマナー|失礼なく感謝を伝える書き方
- 結婚資金贈与バレる確率は高い?安心できないリスクを徹底解説
- 相続税はいつまでに払う?期限や手続きを徹底解説

お気軽にご相談ください
相続は100人いれば、100通り
唯一無二の最適な相続をご提案いたします
CONTACT
専門家やえさん

- 専門家やえさん
-
堀川 八重(ほりかわ やえ)
大阪不動産・FPサービス株式会社 代表
15年以上にわたり1,500組を超えるご家族の相続や不動産のお悩みに、専門家として寄り添ってまいりました。私の信条は、法律や数字の話をする前に、まずお客様ご家族の歴史や言葉にならない想いを丁寧に「聞く」こと。信頼できる各分野の専門家チームと共に、皆様が心から安心できる最善の道筋をオーダーメイドでご提案します。一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。
最新の投稿
 お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説
お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説 相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説
相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説 お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例
お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例 お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説
お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説






