「うちの相続、誰が相続人になるんだろう?」「相続権ってどこまで関係あるの?」なんて、いざという時に漠然とした不安を感じていませんか。相続の話って、なんだか複雑で難しそうに感じますよね。
法定相続人と相続人の違いも曖昧だったり、法定相続人とはどこまでなのか、その順位や割合、兄弟の相続はどこまで関係するのか、なんて考え始めると、もう頭がパンクしそう!なんてことも。
もし相続放棄したらどうなるの?相続義務の範囲は?相続権に時効はあるの?と、疑問は尽きないものです。わかります、私もこの仕事に就く前は同じ気持ちでしたから(笑)。でも、ご安心ください。
相続できる人の範囲は、法定相続人の範囲を図や図解で確認すれば、意外とスッキリ理解できるものなんですよ。この記事で、あなたの相続に関するモヤモヤを解消し、スッキリした気持ちで未来への一歩を踏み出すお手伝いができれば嬉しいです。
この記事のポイント
- 法定相続人の範囲と優先順位が明確になる
- 自分の家族構成における相続割合の目安がわかる
- 相続放棄や相続義務に関する重要な注意点がわかる
- 兄弟姉妹が相続人になる具体的なケースが理解できる

相続は「誰にでも起こる」のに、学ぶ機会が少ないのが現状です。だからこそ、多くの方が漠然とした不安を抱えています。この記事では、まず「誰が相続人になるのか」という基本中の基本をしっかり押さえることを目指します。ここが分かると、次のステップである遺産分割や相続税の話もスムーズに理解できるようになりますよ。リラックスして読み進めてくださいね。
目次
相続権どこまで?法定相続人の範囲を徹底解説
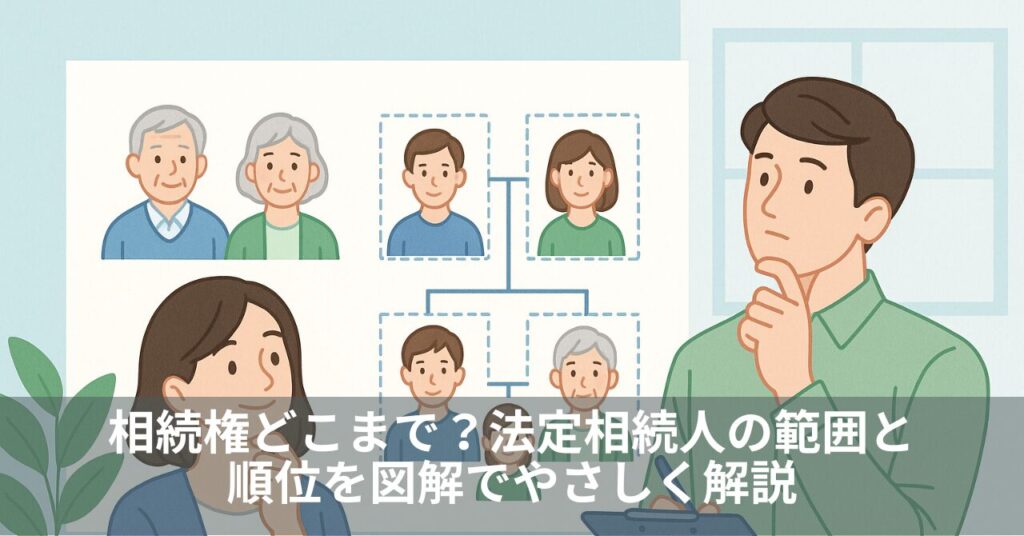
法定相続人と相続人の違いとは?
こんにちは!終活・相続・不動産コンサルタントのやえです。さて、相続の話で最初につまずきがちなのが、この「法定相続人」と「相続人」という言葉の違いなんですよね。似ているようで、実はちょっと意味合いが違うんです。
結論から言ってしまうと、一番大きな違いは「遺言書の有無によって呼び方が変わることがある」という点です。
「法定相続人」というのは、民法という法律で「遺産を相続する権利がありますよ」と定められた人のことを指します。亡くなった方(被相続人といいます)の配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などがこれにあたります。遺言書がない場合は、基本的にこの法定相続人たちが遺産を分け合うことになります。
一方、「相続人」は、実際に遺産を相続する人のことです。遺言書がなければ「法定相続人=相続人」となることが多いですね。しかし、もし遺言書に「全財産を長年お世話になった友人のAさんに遺贈する」と書かれていた場合、実際に財産を受け取るのはAさんです。この場合、Aさんが「受遺者」となり、法定相続人であるご家族は(遺留分という最低限の取り分を除いて)相続人になれない、というケースも出てくるのです。

以前ご相談いただいたお客様で、長年連れ添った内縁のパートナーがいらっしゃる方がいました。「事実婚だから、自分が亡くなったら財産は彼女に行くだろう」と安心されていたのですが、法律上、内縁のパートナーは法定相続人にはなれません。この事実をお伝えした時の衝撃は、今でも忘れられません。慌てて遺言書の作成をお手伝いし、無事にパートナーへ財産を遺す準備ができました。遺言書一枚で、大切な人の未来が大きく変わることを実感した出来事です。
▼あわせて読みたい
» 遺言書書き方法務局で正確に遺言を残す方法|失敗しない書き方と注意点
法定相続人とはどこまでか、図解で解説

では、具体的に「法定相続人」とはどこまでの範囲の人を指すのでしょうか。これを理解するのが相続の第一歩です。言葉だけだと少しややこしいので、簡単な図をイメージしながら見ていきましょう!
法定相続人は、大きく分けて2つのグループに分けられます。
法定相続人の2大グループ
- 配偶者相続人:亡くなった方の夫または妻。法律上の婚姻関係にあることが条件です。配偶者は、他の相続人が誰であっても、常に相続人となります。
- 血族相続人:亡くなった方と血のつながりのある親族。こちらは相続人になる順番(順位)が決まっています。
そして、重要なのが血族相続人の「順位」です。上位の順位の人が一人でもいる場合、下位の順位の人は相続人にはなれません。
血族相続人の順位
- 第1順位:子(子が亡くなっている場合は孫などの直系卑属)
- 第2順位:親(親が亡くなっている場合は祖父母などの直系尊属)
- 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪)
例えば、亡くなった方に配偶者と子どもがいる場合、相続人は「配偶者」と「子ども(第1順位)」になります。このとき、第2順位の親や第3順位の兄弟姉妹は法定相続人にはなれません。もし子どもがいなければ、相続人は「配偶者」と「親(第2順位)」となるわけです。この順番がとても大切なので、ぜひ覚えておいてくださいね。
相続できる人の範囲は法律で定められている
前述の通り、相続できる人の範囲は民法で厳格に定められています。なぜなら、「誰が相続するのか」を法律で決めておかないと、親族間での激しい争いに発展しかねないからです。「私が一番お世話をしたから」「家業を継いでいるから」といった個別の事情を言い出すと、収拾がつかなくなってしまいますよね。
そのため、法律は被相続人との関係性の近さ(配偶者、子、親、兄弟姉妹という順番)を基準に、相続人の範囲を明確にしているのです。
相続人になれない人の具体例
どんなに仲が良く、被相続人のために尽くしたとしても、以下の立場の方は原則として法定相続人にはなれません。
- 内縁の配偶者:法律上の婚姻届を出していないパートナー
- 離婚した元配偶者:離婚が成立した時点で相続権はなくなります
- 配偶者の連れ子:養子縁組をしていない場合、血縁関係がないため相続権はありません
- 長男の嫁など、子の配偶者:いわゆる「姻族」には相続権がありません
- いとこ、おじ、おば:第3順位の兄弟姉妹までが範囲です

「お義父さんの介護を10年間、私一人でやってきたのに、遺産は1円ももらえないなんて…」。そう涙ながらに話されたのは、あるお客様(長男のお嫁さん)でした。法律上、子の配偶者に相続権はありません。しかし、2019年の民法改正で「特別寄与料」という制度ができました。これは、相続人ではない親族でも、被相続人の療養看護などに貢献した場合、相続人に対して金銭を請求できるというものです。このお客様も、最終的にはこの制度を利用して、ご自身の貢献分をきちんと受け取ることができました。法律を知っているかどうかで、結果が大きく変わる一例ですね。
参考情報サイト: e-Gov法令検索「民法」
URL: https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
法定相続人の順位と優先される人

相続人の順位については先ほど触れましたが、ここでもう少し詳しく見ていきましょう。特に「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」という仕組みは、少しややこしいですが非常に重要です。
代襲相続とは、本来相続人になるはずだった子や兄弟姉妹が、相続が開始される前にすでに亡くなっていた場合に、その人の子ども(被相続人から見ると孫や甥・姪)が代わりに相続するという制度です。
代襲相続の具体例
例えば、Aさんが亡くなり、相続人が長男と次男だったとします。しかし、長男はAさんより先に亡くなっており、長男には子ども(Aさんの孫)が2人いました。この場合、
- 次男はそのまま相続人になります。
- 亡くなった長男の代わりに、その子ども2人(Aさんの孫)が相続人になります。
これが代襲相続です。もし孫も亡くなっていたら、ひ孫、やしゃご…と下の世代に権利が移っていきます(これを再代襲といいます)。
代襲相続の注意点
- 第2順位(親・祖父母)には代襲相続はありません。親が亡くなっていれば、自動的に祖父母が相続人になるだけです。
- 第3順位(兄弟姉妹)の代襲相続は、その子(甥・姪)の一代限りです。甥や姪が亡くなっていても、その子どもが相続することはありません。

ご兄弟のいない一人っ子の方の相続をお手伝いした時の話です。その方には配偶者も子もおらず、ご両親もすでに他界されていました。法定相続人は第3順位の兄弟姉妹ですが、その方も一人っ子。
となると、相続人が誰もいない…?と思いきや、戸籍をたどると、なんと先に亡くなっていたお父様に10人の兄弟姉妹がいたことが判明!そのうち何人かは亡くなっており、代襲相続で甥・姪が相続人になりました。最終的な相続人の数は20人を超え、全国に散らばる相続人を探し出すだけで半年以上かかった、大変な案件でした。
法定相続人の割合はケースによって異なる
「誰が相続人になるか」がわかったら、次に気になるのは「どれくらいの割合をもらえるのか」ですよね。この法律で定められた取り分の割合を「法定相続分」といいます。
この割合は、誰と誰が相続人になるのか、その組み合わせによって変わってきます。一番わかりやすいように、表にまとめてみました!
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | 子(第1順位) | 親(第2順位) | 兄弟姉妹(第3順位) |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者と子 | 1/2 | 1/2 (※) | - | - |
| 配偶者と親 | 2/3 | - | 1/3 (※) | - |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | - | - | 1/4 (※) |
| 配偶者のみ | すべて | - | - | - |
| 子のみ | - | すべて (※) | - | - |
※子どもや親、兄弟姉妹が複数人いる場合は、その人数で均等に分けます。例えば、相続人が「配偶者」と「子2人」の場合、子の取り分である1/2を2人で分けるので、子ども一人当たりの相続分は1/4ずつとなります。
【カズのリアル体験談】
あるお客様が「うちは子どもがいないから、俺の財産は全部、妻のものになるんだよな?」とおっしゃっていました。よくある勘違いなのですが、お子さんがいない場合、相続権は第2順位のご両親に移ります。
そのお客様のご両親はご健在でしたので、法定相続分は「妻が2/3、両親が1/3」となります。もし、全財産を奥様に遺したいのであれば、その旨を記した遺言書が必要になるのです。「知らなかった…!遺言書、絶対に書くよ!」と、その場でご決心されていました。この法定相続分のルールを知っておくことは、円満な相続の第一歩ですね。
▼あわせて読みたい

ここまで、法定相続人の範囲と順位、そして割合について解説してきました。基本は「配偶者は常に相続人」「血族は順位が上の人から」という2点です。自分の家族に当てはめてみて、誰が相続人になるか一度シミュレーションしてみると、理解が深まりますよ。後半では、兄弟姉見や相続放棄といった、より具体的なケースについて見ていきましょう。
相続権どこまで?注意すべきケースと特殊な相続ケース

法定相続人である兄弟の相続はどこまで?
さて、ここからはもう少し具体的なケースを見ていきましょう。ご相談の中でも質問が多いのが、「兄弟姉妹の相続」についてです。
前述の通り、兄弟姉妹の相続順位は第3順位。つまり、亡くなった方(被相続人)に子や孫(第1順位)がおらず、かつ親や祖父母(第2順位)もすでに亡くなっている場合に、初めて相続人となります。
割合については、配偶者の有無で変わります。
- 配偶者がいる場合:配偶者が3/4、兄弟姉妹全員で1/4を分け合います。
- 配偶者がいない場合:兄弟姉妹全員で、遺産のすべてを分け合います。
ちょっと待って!異母・異父兄弟は?
お父さんだけが同じ(異母)、またはお母さんだけが同じ(異父)兄弟姉妹も、相続権を持っています。ただし、その法定相続分は、両親ともに同じ兄弟姉妹の半分となります。少し複雑な計算になるので、該当する場合は専門家への相談をおすすめします。

生涯独身を貫いた女性の相続をお手伝いした時のことです。ご両親はすでに他界。法定相続人はご兄弟でしたが、長年疎遠だったため、遺産分割の話し合いはなかなか進みませんでした。
「姉さんには世話になった覚えはない」と主張する弟さんと、「姉の晩年は私が支えた」と主張する妹さん。法定相続分は均等ですが、感情的なしこりが邪魔をしてしまうのです。兄弟姉妹が相続人になるケースは、関係性が希薄になっていることも多く、遺産分割が「争続」になりやすい典型的なパターンの一つだと感じています。
また、兄弟姉妹の相続で忘れてはならないのが、代襲相続は甥・姪までの一代限りという点です。ここも重要なポイントですよ。
法定相続人が相続を放棄した場合の注意点

「うちは財産より借金のほうが多いから、相続なんてしたくない…」そんな時に検討するのが「相続放棄」です。これは、家庭裁判所に申し出ることで、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない、と意思表示する手続きです。
ここで非常に重要な注意点があります。それは、誰かが相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったことになり、相続権が次の順位の人に移ってしまうということです。
相続放棄で起こりがちなトラブル
よくあるのが、第1順位の子どもたち全員が相続放棄をしたケースです。子どもたちは「これで借金から解放された」と安心しますが、相続権は自動的に第2順位である亡くなった方の親(子どもたちから見れば祖父母)に移ります。そして、祖父母に突然、債権者から督促状が届いて大パニックに…ということが実際に起こるのです。
相続放棄の鉄則
- 相続放棄は、自分が相続人であることを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
- 相続放棄をする場合は、次の順位の相続人になる人に必ず連絡を入れ、事情を説明するのがマナーであり、トラブルを防ぐための鉄則です。
相続放棄は代襲相続の原因にはなりません。例えば、子が相続放棄をしても、孫が代わって相続人になることはありませんので、混同しないように注意しましょう。
▼あわせて読みたい
» 相続放棄遺品整理バレる?失敗例と絶対NG行動を完全ガイド
借金が多いけれど、自宅だけは手放したくない…といった場合には、家族信託などの生前対策が有効なこともあります。早めの準備が大切ですね。
相続義務の範囲はどこまでですか?
「相続」というと、預貯金や不動産といったプラスの財産に目が行きがちですが、忘れてはならないのが「相続義務」、つまり借金や未払金、損害賠償義務といったマイナスの財産です。
相続は、これらプラスの財産とマイナスの財産をすべてセットで引き継ぐのが原則です。相続する範囲は、法定相続分に応じて決まります。例えば、2,000万円の預金と1,000万円の借金があり、子ども2人で相続する場合、一人あたり1,000万円の預金と500万円の借金を相続することになります。
マイナスの財産が多そうな時は「限定承認」
借金がどれくらいあるか不明な場合や、プラスの財産の範囲内であれば返済してもよい、と考える場合に使えるのが「限定承認」という手続きです。これは、「相続したプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産も引き継ぎますよ」という条件付きの相続方法です。ただし、手続きが非常に複雑で、相続人全員で申し立てる必要があるため、利用されるケースは少ないのが現状です。
よくあるご質問(FAQ)
-
亡くなった父の葬儀費用は、相続財産から支払っても良いですか?
-
はい、社会通念上相当と認められる範囲の葬儀費用であれば、相続財産から支払うことが一般的です。ただし、あまりに高額な墓石の購入費用などは、遺産分割の対象となる可能性があるので注意が必要です。
-
亡くなった人が賃貸アパートに住んでいた場合、家賃の支払い義務も相続しますか?
-
はい、未払いの家賃があれば、それもマイナスの財産として相続人が支払い義務を負います。また、部屋の片付け(原状回復)義務も相続することになります。
相続権に時効はあるのか解説

「相続権に時効ってあるんですか?」というご質問もよく受けます。なんだか権利が消えてしまいそうで、不安になりますよね。
結論から言うと、「相続権」そのものには時効はありません。あなたが相続人であるという地位は、時間が経ったからといって消えることはないのです。
ただし、注意が必要なのは、相続に関連するいくつかの「請求権」には時効があるということです。代表的なものをいくつかご紹介します。
- 遺留分侵害額請求権:遺言などで自分の最低限の取り分(遺留分)が侵害された場合に、多くもらった人に対して金銭を請求する権利です。この権利は、相続の開始と遺留分侵害を知った時から1年、知らなくても相続開始から10年で時効になります。
- 相続回復請求権:相続人ではない人が、あたかも相続人であるかのように財産を管理している場合に、本当の相続人が「その財産を返しなさい」と請求する権利です。これは、侵害を知った時から5年、知らなくても相続開始から20年で時効となります。
「『相続権』そのものには時効はないけど、お金を請求するような『権利』には期限があるんだな」とイメージしておくと、分かりやすいかもしれませんね!特に遺留分の時効は1年と短いので、「遺言書の内容に納得がいかない…」という場合は、早めに専門家に相談することが重要です。
相続人の範囲を図で確認しよう
ここまで解説してきた内容を、少し複雑な家族構成の図を見ながらおさらいしてみましょう。相続人の範囲を確認する上で最も確実な方法は、亡くなった方(被相続人)の「生まれてから亡くなるまで」の連続した戸籍謄本をすべて取得することです。
なぜなら、自分たちが知らない相続人が存在する可能性があるからです。
戸籍を見てビックリ!こんなケースも
- 前妻(夫)との間に子どもがいた:離婚して何十年も会っていなくても、その子どもは第1順位の法定相続人です。
- 養子縁組をしていた:養子も実子と全く同じ権利を持つ法定相続人です。
- 認知している子どもがいた:婚姻関係にない女性との間に生まれた子でも、認知していれば法定相続人となります。
これらの「隠れた相続人」がいると、その人を除いて行った遺産分割協議は無効になってしまいます。相続手続きの第一歩は、手間がかかっても、必ず戸籍で相続人の範囲を確定させることなのです。

穏やかなご家庭の相続手続きをお手伝いしていた時のことです。念のため戸籍をすべて取り寄せたところ、ご主人には前妻との間に一人のお子さんがいることが判明。現在の奥様もお子さんたちも全く知らなかった事実でした。幸い、そのお子さんとは連絡が取れ、円満に話し合いが進みましたが、もし戸籍を確認せず手続きを進めていたら…と考えると、ヒヤッとします。特に不動産相続では、相続人全員の合意がないと売却もできませんからね。
▼あわせて読みたい
» 相続した実家、売却か賃貸か?判断ミスで損しないための全知識
まとめ:相続権どこまでか悩んだら専門家へ

- 法定相続人は法律で定められた遺産を相続する権利を持つ人
- 相続人は遺言も含め、実際に財産を相続する人
- 配偶者は常に相続人になる
- 血族相続人には順位があり、第1順位は子、第2は親、第3は兄弟姉妹
- 上位の順位の相続人がいる場合、下位の人は相続人になれない
- 子が先に亡くなっている場合、孫が代わりに相続する「代襲相続」がある
- 兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪の一代限り
- 法定相続分は誰が相続人になるかの組み合わせで変わる
- 子どもがいない場合、親や兄弟姉妹が相続人になる可能性がある
- 兄弟姉妹が相続人になるのは、子も親もいない場合のみ
- 相続放棄をすると相続権は次の順位の人に移る
- 相続放棄は自分が相続人だと知ってから3ヶ月以内に行う
- 相続はプラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も引き継ぐ
- 相続権自体に時効はないが、遺留分請求など関連する権利には時効がある
- 正確な相続人の範囲の確認には、戸籍謄本の収集が不可欠

ここまでお疲れ様でした!相続権の範囲、少しはクリアになりましたでしょうか?相続は、一つひとつのルールは複雑でも、全体像を掴めば決して怖いものではありません。大切なのは、正しい知識を持って、早めに準備を始めることです。もし「うちの場合はどうなるの?」と少しでも不安に感じたら、一人で抱え込まず、私たちのような専門家に気軽に声をかけてくださいね。あなたの家族が笑顔で未来を迎えられるよう、全力でサポートします!
▼あわせて読みたい関連記事▼
遺言書書き方法務局で正確に遺言を残す方法|失敗しない書き方と注意点

お気軽にご相談ください
相続は100人いれば、100通り
唯一無二の最適な相続をご提案いたします
CONTACT
専門家やえさん

- 専門家やえさん
-
堀川 八重(ほりかわ やえ)
大阪不動産・FPサービス株式会社 代表
15年以上にわたり1,500組を超えるご家族の相続や不動産のお悩みに、専門家として寄り添ってまいりました。私の信条は、法律や数字の話をする前に、まずお客様ご家族の歴史や言葉にならない想いを丁寧に「聞く」こと。信頼できる各分野の専門家チームと共に、皆様が心から安心できる最善の道筋をオーダーメイドでご提案します。一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。
最新の投稿
 お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説
お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説 相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説
相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説 お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例
お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例 お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説
お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説






