「65歳が近づくと『介護保険料は給料から天引きされなくなりますか?』って気になりますよね。給与天引きはいつまで?誕生月の扱いは?給与所得者の支払い方法や会社負担、年金天引きとの二重払いの心配も。
協会けんぽの健康保険料など、65歳以上の給料から引かれるものは何か、もし給料から天引きされていない場合はどうする?など疑問だらけ!この記事で、65歳以上の介護保険料の計算シュミレーションの前に、モヤモヤをスッキリ解決します!
この記事のポイント
- 65歳を境にした介護保険料の変更点
- 給与天引きから年金天引きへの移行プロセス
- 保険料の計算方法と会社負担の有無
- 保険料を滞納してしまった場合のリスク
介護保険料65歳以上給与天引きの仕組み

65歳で給料から天引きされなくなる?
はい、その通りです!会社員の方の場合、65歳になると介護保険料が給与から天引きされなくなります。これは、介護保険制度における立場が変わるためなんですよ。
ご存じの方も多いと思いますが、日本の公的介護保険は40歳になると加入が義務付けられています。そして、64歳までを「第2号被保険者」、65歳以上を「第1号被保険者」と呼び、保険料の徴収方法がガラッと変わるんです。
第2号被保険者の間は、加入している健康保険(協会けんぽや組合健保など)の保険料と一緒に、介護保険料が給与から天引きされます。これが、65歳になると切り替わり、原則として年金からの天引きになる、というわけですね。
私も初めて知ったときは「え、お給料から引かれなくなるの!?ラッキー!」なんて思っちゃったんですけど、もちろん支払いが無くなるわけじゃないんですよね(笑)。むしろ、払い方が変わることで注意すべき点も出てくるので、一緒に確認していきましょう!
給与天引きはいつまで?誕生月の扱い

「じゃあ、給与からの天引きは一体いつの給与までなの?」という疑問、とってもよく分かります。特に誕生月が絡むとややこしく感じますよね。
結論から言うと、介護保険料の天引きがなくなるのは「65歳に到達した月」の分からです。
ここで面白いのが、「年齢計算に関する法律」という法律の存在です。この法律によると、人は「誕生日の前日」に年齢を1つ重ねるとされているんです。
誕生月による切り替えタイミングの例
- 8月15日が誕生日の方:誕生日の前日は「8月14日」。この日が65歳の到達日なので、「8月分」の介護保険料から第1号被保険者としての納付が始まります。つまり、会社からの給与天引きは「7月分」までとなります。
- 8月1日が誕生日の方:誕生日の前日は「7月31日」。この日が65歳の到達日なので、「7月分」の介護保険料から第1号被保険者としての納付が始まります。この場合、給与天引きは「6月分」まででストップします。
先日、担当させていただいたお客様で、まさにこの「1日生まれ」のパターンの方がいらっしゃいました。「8月が誕生日なのに、思ったより早く納付書が届いてビックリしたよ!」とおっしゃっていましたが、この仕組みをご説明したら「なるほど、法律が関係してるのか~!」とスッキリされていました。自分の誕生日でどちらのパターンになるか、一度確認しておくと安心ですね。
介護保険料65歳以上給与所得者の変更点
65歳以上で会社に勤め続ける、いわゆる「給与所得者」の方にとっては、変更点がいくつかあります。一番大きな変化は、保険料の算出方法と納付方法が完全に切り替わることです。
前述の通り、64歳までは健康保険料と一緒に介護保険料が給与から引かれていました。しかし、65歳になると、たとえ会社で働き続けていても、この扱いは変わります。
健康保険料は引き続き給与から天引きされますが、介護保険料は分離され、お住まいの市区町村へ直接(または年金天引きで)納付する形に変わります。つまり、給与明細を見ると、介護保険料の項目が消える代わりに、市区町村から納付書が届いたり、年金から引かれたりするようになる、という流れです。
二重納付になってない?という勘違い
「65歳になったのに、まだ給与から介護保険料が引かれてる!二重払いでは?」というご相談をいただくことがあります。しかし、これは多くの場合、タイミングの問題です。例えば、7月分の保険料を8月の給与で徴収する会社の場合、8月1日が誕生日(=7月31日に65歳到達)の方だと、8月支給の給与からも天引きが発生します。これはあくまで64歳最後の月である「7月分」の保険料なので、二重納付にはあたりません。ご心配な場合は、会社の経理担当の方に確認してみるのが一番確実ですよ。
介護保険料65歳以上での会社負担はどうなる?

これは、金銭的にかなり大きなポイントです!64歳までの第2号被保険者の期間は、介護保険料を会社と自分で半分ずつ負担(労使折半)しています。
例えば、介護保険料が1万円だったとしたら、給与から引かれるのは5千円で、残りの5千円は会社が負担してくれていたわけです。とてもありがたい制度ですよね。
ところが、65歳になって第1号被保険者になると、この会社負担がなくなります。つまり、保険料の全額を自分で負担しなければならなくなるのです。
このため、お住まいの自治体や所得によっては、今まで給与から引かれていた金額よりも、自分で納める保険料のほうが高くなるケースも珍しくありません。私の友人も「天引き額が減ると思ったら、納付書を見てビックリ!むしろ増えてるじゃない!」と驚いていました。これは、算出方法の変更に加えて、会社負担がなくなる影響が大きいんですね。
豆知識:第1号被保険者の保険料は、市区町村ごとに異なります。その地域に住む高齢者の人数や、必要とされる介護サービスの量などから算出されるため、自治体によって基準額に差が出るんです。一般的に、高齢者が多い都市部ほど保険料が高くなる傾向があります。
65歳以上の給料から引かれるものは何?
65歳を過ぎて働き続ける場合、「介護保険料は引かれなくなるとして、他に給料から引かれるものは何があるの?」と気になりますよね。
基本的には、65歳になる前と大きくは変わりませんが、整理しておきましょう。
| 項目 | 天引きの有無 | 備考 |
|---|---|---|
| 健康保険料 | あり | 75歳になるまで、または後期高齢者医療制度に加入するまで継続して徴収されます。 |
| 厚生年金保険料 | あり | 70歳になるまで継続して徴収されます。70歳以降は厚生年金への加入資格を喪失します。 |
| 雇用保険料 | あり | 週の所定労働時間が20時間以上など、加入条件を満たしていれば年齢に関わらず徴収されます。 |
| 所得税 | あり | 給与所得に応じて課税されます。 |
| 住民税 | あり | 前年の所得に応じて課税され、給与から特別徴収されます。 |
| 介護保険料 | なし | 原則として給与からの天引きはなくなります。(年金天引き or 普通徴収へ移行) |
このように、介護保険料以外の社会保険料や税金は、基本的には働き続ける限り天引きが続きます。給与明細を確認する際は、介護保険料の欄がどうなっているか、チェックしてみてくださいね。
介護保険料65歳以上給与天引き後の手続き

65歳以上の介護保険料の支払い方法
65歳からの介護保険料、つまり第1号被保険者としての保険料は、どうやって払うのでしょうか?支払い方法は、主に2種類あり、自分で選ぶことはできません。年金の受給額によって自動的に決まります。
① 特別徴収(年金からの天引き)
こちらが最も一般的な支払い方法です。老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金のいずれかを年間18万円以上受給している方が対象となります。
年金の支給月である偶数月(2月、4月、6月…)に、2ヶ月分の介護保険料が自動的に年金から天引きされて納付されます。手続きは不要で、納付忘れの心配がないのがメリットですね。
特別徴収が始まるまでにはタイムラグがある!
65歳になってすぐに年金からの天引きが始まるわけではありません。日本年金機構と市区町村との情報連携などに時間がかかるため、特別徴収が開始されるまでには半年~1年ほどかかるのが一般的です。その期間は、次に説明する「普通徴収」で納めることになりますので、いきなり納付書が届いても慌てないでくださいね!
② 普通徴収(納付書や口座振替での納付)
年金の受給額が年間18万円未満の方や、65歳になったばかりで特別徴収の準備が整っていない方などがこちらの方法で納付します。
市区町村から送られてくる納付書を使って、金融機関やコンビニエンスストアなどで支払うか、事前に手続きをして口座振替で納付します。納付書払いの場合は、ついつい納付を忘れがちなので、口座振替の手続きをしておくと安心ですよ。
介護保険料が給料から天引きされていない場合

40歳から64歳の方で、「あれ?私の給料、介護保険料が天引きされていないみたい…」と気づいた場合、いくつかの理由が考えられます。
まず考えられるのは、健康保険の扶養に入っているケースです。例えば、配偶者の扶養に入っている専業主婦(主夫)の方などですね。この場合、扶養している方(被保険者)が支払う保険料の中に、扶養されている方(被扶養者)の分も含まれているため、ご自身の給与から直接天引きされることはありません。
また、40歳未満の方はもちろん徴収対象外です。他にも、生活保護を受給している場合など、特定の条件下では納付義務が生じないこともあります。
ただし、「自分は扶養にも入っていないし、40歳以上なのに引かれていない…」という場合は、何らかの手続き上のミスも考えられます。一度、会社の総務や経理の担当部署に確認してみることをお勧めします。
介護保険料の年金天引きと二重払いを解説
65歳になり、普通徴収(納付書払い)から特別徴収(年金天引き)へ切り替わるタイミングは、「二重払いでは?」と勘違いしやすいNo.1ポイントかもしれません。
よくあるケースが、「市役所から納付書が届いたので銀行で納付したのに、同じ時期に振り込まれた年金からも介護保険料が引かれていた」というものです。
これ、パニックになりますよね!「え、なんで両方から取るの!?」って。でも、安心してください。これは本当の二重払いではなく、ほとんどの場合、市区町村と年金機構の連携のタイムラグによって起こる現象なんです。
市区町村は、あなたが納付書で支払ったという情報を、すぐに年金機構に伝えることができません。そのため、年金機構側では「まだ納付されていない」と判断し、予定通り年金からの天引きを行ってしまうことがあるのです。
もし、このように重複して支払ってしまった場合でも、後日、市区町村から還付(返金)のお知らせが届き、払い過ぎた分はきちんと戻ってきますのでご安心ください。もし、お知らせがなかなか来ないなど不安な場合は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口に問い合わせてみましょう。
65歳以上の健康保険料と協会けんぽの関係

65歳以降も会社で働く場合、多くの方が加入しているのが全国健康保険協会、通称「協会けんぽ」だと思います。
前述の通り、65歳になると介護保険料は給与天引きされなくなりますが、健康保険料の扱いは変わりません。75歳になって後期高齢者医療制度に移行するまでは、引き続き給与から天引きされます。
協会けんぽの保険料率は、都道府県ごとに設定されており、毎年見直しが行われます。この健康保険料率の中に、40~64歳の方は「介護保険料率」が含まれています。65歳以上になると、この介護保険料率分が適用されなくなり、純粋な「健康保険料率」のみが適用されることになります。
例えば、協会けんぽの東京都の保険料率(令和6年度)を見てみると、
- 40歳~64歳の方(介護保険第2号被保険者):11.61%(健康保険料率9.98% + 介護保険料率1.63%)
- 65歳~74歳の方:9.98%(健康保険料率のみ)
となっています。このように、適用される料率自体が変わるんですね。
参考情報サイト:全国健康保険協会「令和6年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」
URL: https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r06/r6ryougakuhyou3gatukara/
介護保険料の計算シュミレーション(65歳以上)
「じゃあ、私の保険料は具体的にいくらになるの?」という点が一番気になるところですよね。65歳以上(第1号被保険者)の方の介護保険料は、以下の要素で決まります。
介護保険料 = ①お住まいの市区町村の基準額 × ②所得などに応じた保険料率
①市区町村の基準額
これは、その市区町村で必要とされる介護サービスの総費用を、65歳以上の方の人数で割って算出される、いわば「一人当たりの基本料金」のようなものです。3年ごとに見直されます。
②所得などに応じた保険料率
世帯全員の住民税の課税状況や、ご本人の前年の合計所得金額などに応じて、何段階かの所得段階に区分されます。そして、その段階ごとに「基準額の0.5倍」や「基準額の1.7倍」といったように、異なる保険料率が設定されているのです。この段階の数は、市区町村によって9段階だったり16段階だったりと様々です。
自分の保険料を知るには?
正確な保険料を知るためには、お住まいの市区町村の公式サイトを確認するのが一番です。「〇〇市 介護保険料」といったキーワードで検索すると、保険料の段階表が見つかるはずです。ご自身の前年の所得状況と照らし合わせることで、年間の保険料額をシミュレーションすることができますよ。
所得が低い方や生活が困難な方向けに、保険料の減免制度を設けている自治体も多いです。支払いが難しいと感じたら、滞納してしまう前に、必ず市区町村の窓口に相談することが大切です。
介護保険料65歳以上給与天引きの総まとめ
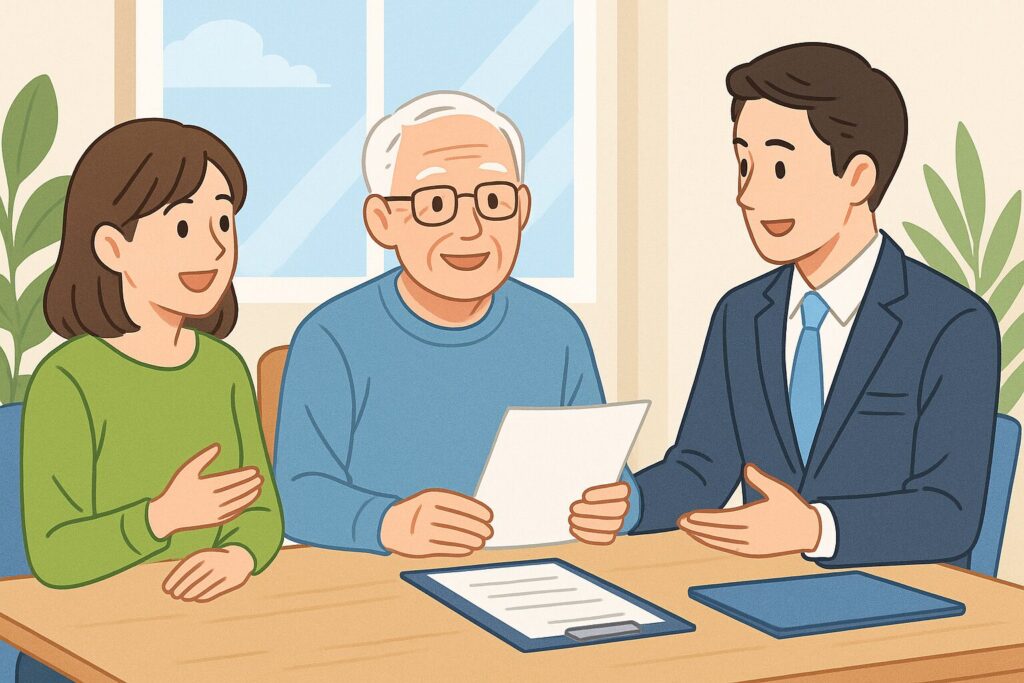
最後に、この記事の重要ポイントをリスト形式で振り返ってみましょう!
- 65歳になると介護保険の「第1号被保険者」になる
- 会社員の場合、介護保険料は給与天引きされなくなる
- 65歳の誕生日の前日が属する月から保険料の扱いが変わる
- 1日生まれの人は切り替えのタイミングが1ヶ月早まる
- 64歳までは保険料を会社と折半で負担していた
- 65歳からは保険料の全額が自己負担になる
- 65歳以降の支払い方法は主に「特別徴収」と「普通徴収」
- 特別徴収は年金受給額が年間18万円以上の方が対象
- 年金から2ヶ月分の保険料が自動で天引きされる
- 普通徴収は納付書か口座振替で自分で納付する
- 65歳になってすぐは普通徴収で納める期間がある
- 支払い方法を自分で選ぶことはできない
- 保険料は市区町村の基準額と所得段階で決まる
- 滞納すると延滞金や給付制限のペナルティがある
- 困ったときは必ず市区町村の窓口へ相談する
参考
・50代シングルマザー老後の不安を減らす住まいとお金の話
・エンディングノート50代おすすめ特集|後悔しない選び方と活用術
・終活やりすぎに注意!家族が後悔しないための断捨離ルール
・エンディングノート40代おすすめ|失敗しない選び方と無料の始め方
・老後一人ぼっち女性の生活費と貯金目安をわかりやすく徹底解説

お気軽にご相談ください
相続は100人いれば、100通り
唯一無二の最適な相続をご提案いたします
CONTACT
専門家やえさん

- 専門家やえさん
-
堀川 八重(ほりかわ やえ)
大阪不動産・FPサービス株式会社 代表
15年以上にわたり1,500組を超えるご家族の相続や不動産のお悩みに、専門家として寄り添ってまいりました。私の信条は、法律や数字の話をする前に、まずお客様ご家族の歴史や言葉にならない想いを丁寧に「聞く」こと。信頼できる各分野の専門家チームと共に、皆様が心から安心できる最善の道筋をオーダーメイドでご提案します。一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。
最新の投稿
 お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説
お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説 相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説
相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説 お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例
お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例 お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説
お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説






