「老後、お金がなかったらどうしよう…」なんて、夜な夜なYahoo!知恵袋を覗いては、ため息をついていませんか?老後貧乏の実態なんて記事を読むと、お金がないと心がすさむという言葉がズシンと響きますよね。
貯金がない人の老後が必ずしも、みすぼらしい老後になるとは限りません。でも、お金がない親の老後を考えて「面倒見たくないな…」なんて罪悪感を抱いたり、最悪の場合、生活保護を考えたり…。老後貧貧乏になる人の特徴という記事に、思わず「これ、私のことかも…」とドキッとしたり。
お金がない老後はどうしたらいいですか?その切実な問い、すごくよく分かります!実は私も昔はそうでした(笑)。この記事では、老後の「お金の残し方」で絶対やってはいけない3つのことから、具体的な対策まで、あなたの不安を「なーんだ、大丈夫じゃん!」に変えるヒントを、これでもかと詰め込みました。一緒に、明るい未来への一歩を踏み出しましょう!
この記事のポイント
- データで分かる老後貧乏のリアルな実態
- あなたが当てはまっていないかチェックできる老後貧乏になる人の特徴
- お金がなくても心豊かに暮らすための具体的なアクションプラン
- 専門家が教える本当に効果的な節約術と資産形成のコツ
目次
【実態】「老後お金がないみじめ」な生活、現実はもっと深刻?

データで見る老後貧乏の実態|夫婦と単身世帯のリアルな生活費
「老後にお金がないとみじめ」と一言で言っても、一体いくらあれば安心できる生活が送れるのでしょうか?まずは敵を知ることから!ということで、リアルなデータを見てみましょう。ここで頼りになるのが、総務省が発表している家計調査報告です。
ちょっと数字が並ぶと眠くなっちゃう…という方も、大丈夫です!ポイントだけ、かみ砕いてお伝えしますね!
総務省統計局の「家計調査年報(家計収支編)2022年(令和4年)」によると、65歳以上の無職世帯の1ヶ月の平均的な支出は以下のようになっています。
| 項目 | 夫婦のみの世帯(円) | 単身世帯(円) |
|---|---|---|
| 食費 | 67,776 | 37,485 |
| 住居 | 15,578 | 12,746 |
| 光熱・水道 | 22,611 | 14,704 |
| 交通・通信 | 28,878 | 14,625 |
| 保健医療 | 15,681 | 8,128 |
| 教養娯楽 | 21,365 | 14,473 |
| その他の消費支出 | 49,433 | 31,872 |
| 消費支出 合計 | 236,696 | 143,139 |
補足情報
上記の「住居」費が低いのは、持ち家率が高いためです。もし賃貸に住む場合は、この金額に家賃がプラスされるので、支出はさらに増えることになります。また、これはあくまで「消費支出」。この他に、税金や社会保険料などの「非消費支出」も必要です。
参考情報サイト: 総務省統計局「家計調査報告」
URL: https://www.stat.go.jp/data/kakei/sokuhou/tsuki/index.html
一方で、年金の平均受給額を見てみましょう。厚生労働省の「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、厚生年金(国民年金含む)の平均受給額は月額約14.4万円です。国民年金(基礎年金)のみの場合は、月額約5.6万円となっています。
もうお分かりですよね?
夫婦二人で厚生年金に加入していたとしても「14.4万円 × 2人 = 28.8万円」なので、なんとか生活はできそうですが、大きな贅沢は難しいかもしれません。
もし夫婦のどちらかが国民年金のみだったり、単身だったりすると、年金だけでは赤字になってしまう可能性が高いのです。この赤字分を、現役時代に貯めた貯蓄で補っていくのが、多くの人の老後のリアルな姿と言えます。だからこそ、早いうちからの資金計画が何よりも大切なんですね。
あなたは大丈夫?老後貧乏になる人の5つの残念な特徴

「私は大丈夫!」と思っていても、意外な落とし穴にはまってしまうのが老後資金の問題です。ここでは、私がこれまで見てきた中で「こういう方はちょっと危ないかも…」と感じた、老後貧乏になる人の特徴を5つ、こっそりお教えします。自分に当てはまっていないか、チェックしてみてくださいね。
特徴1:「なんとかなる」が口癖の楽観主義さん
計画性がなく、将来の不安から目をそむけて「まぁ、なんとかなるでしょ!」と考えるタイプです。退職金や年金をあてにしすぎて、具体的な貯蓄計画を立てていません。私が担当したお客様Bさん(68歳・男性)は、現役時代に年収1,000万円を超えていたそうですが、「退職金が2,000万円も出るんだから安泰だ」と、趣味のゴルフや飲み会にお金を使い、奥様に内緒のローンまで組んでいました。
結果、退職金はローンの返済や生活費であっという間に消え、今は夫婦で切り詰めた年金生活を送っています。「あの時、少しでも貯蓄に回していれば…」と後悔されていました。
特徴2:見栄っ張りで世間体を気にしすぎるさん
「子どもには良い教育を」「ご近所付き合いも派手に」と、収入以上に見栄を張ってしまうタイプです。特に子どもの教育費や住宅ローンで無理をしがち。子どものためを思う気持ちは素晴らしいですが、その結果、自分たちの老後資金が空っぽになっては元も子もありません。子どもの独立後も、孫へのお祝いやプレゼントで出費がかさみ、自分たちの生活を圧迫してしまうケースも少なくないです。
要注意!
見栄のための出費は、満足感が一時的なわりに、家計へのダメージは深刻です。他人と比較するのではなく、自分たち夫婦の安心できる生活水準を見つけることが大切です。
特徴3:行き過ぎた節約で楽しみを忘れたさん
これは意外に思われるかもしれませんが、冒頭の記事にあったAさんのように、「老後のために!」と現役時代に過度な節約をしすぎた結果、いざ老後になってもお金を使う習慣がなく、何を楽しんだらいいか分からなくなってしまうパターンです。お金を使うことに罪悪感を覚えてしまい、せっかく貯めたお金を使えずに、結局みじめな気持ちで過ごしてしまう…。
これでは本末転倒ですよね。節約ももちろん大事ですが、人生を楽しむためのお金は、必要経費と考えるバランス感覚も必要です。
特徴4:健康への関心が薄い不摂生さん
健康こそが最大の資産です。若い頃の不摂生がたたり、老後に医療費や介護費がかさんでしまうケースは本当に多いです。「医療費なんて、高額療養費制度があるから大丈夫」と思うかもしれませんが、差額ベッド代や先進医療費、通院の交通費などは対象外。じわじわと家計を圧迫します。健康寿命を延ばすことが、結果的に最大の節約に繋がるのです。
特徴5:金融知識のアップデートをしないさん
「投資は怖い」「よく分からない」と、せっかくの資産形成のチャンスを逃してしまうタイプです。低金利の時代に、銀行預金だけでお金を増やそうとするのは非常に困難です。
もちろん、ハイリスクな投資に手を出す必要はありませんが、NISAやiDeCoといった国が推奨する非課税制度を活用しないのは、本当にもったいない!正しい知識を身につけ、少しでも資産に働いてもらう意識を持つことが、ゆとりある老後に繋がります。
親の老後も人ごとじゃない!お金がない親の面倒、どうする?
自分の老後も不安なのに、追い打ちをかけるように「お金がない親の老後」という問題がのしかかってくる…。これは本当に深刻ですよね。「面倒見たくない」なんて思ってしまう自分に自己嫌悪を感じる方もいるかもしれません。でも、それは決して薄情なことではないんですよ。
だって、自分の生活で精一杯ですもの!無理して共倒れになってしまったら、それこそ悲劇です。ここでは、冷静に、そして賢くこの問題と向き合うための考え方をお伝えします。
まず大原則として、「親の生活は親の資産と年金でまかなう」ということを忘れないでください。親子とはいえ、家計は別です。あなたにはあなたの生活があり、守るべき未来があります。
その上で、できることとできないことを明確に線引きすることが重要です。感情的に「助けなきゃ!」と考える前に、まずは親の経済状況を正確に把握しましょう。
親の状況を把握する3ステップ
- 収入の確認:年金はいくらもらっているのか?その他の収入はあるか?
- 支出の確認:毎月の生活費はどのくらいか?借金やローンはないか?
- 資産の確認:預貯金はいくらか?生命保険は?不動産などの資産はあるか?
この現実を直視した上で、もし親の資金だけでは生活が困難な場合でも、いきなりあなたが金銭的な援助をする前に、使える公的制度がないかを探すのが先決です。
例えば、お住まいの市区町村にある「地域包括支援センター」は、高齢者の暮らしを総合的にサポートしてくれる心強い味方です。保健師や社会福祉士などの専門家が、介護保険サービスのことだけでなく、生活の困りごと全般について相談に乗ってくれます。あなた一人で抱え込まず、まずは専門機関に相談することが、解決への一番の近道です。
親に「お金の援助はできないけれど、制度を探す手伝いはするよ」と伝えることは、決して冷たいことではありません。むしろ、持続可能で現実的な親孝行の形だと言えるでしょう。
【解決策】老後お金がないみじめな老後を回避!今日から始めるべき8つのアクション

まずは現状把握から!家計の「見える化」で不安を解消
老後資金の不安を解消する第一歩、それは「家計の見える化」です!なぜなら、何にいくら使っているか分からない状態では、節約のしようがないからです。これは、目隠しでマラソンを走るようなもの。ゴール(安心な老後)にたどり着けるはずがありませんよね。
「家計簿なんて面倒…」という声が聞こえてきそうですが、今は便利なアプリがたくさんあります。銀行口座やクレジットカードを連携すれば、自動で支出を記録・分類してくれるので、ズボラさんでも大丈夫!
編集部おすすめ!簡単家計簿アプリ
- マネーフォワード ME:連携できる金融機関が多く、レシート撮影機能も優秀。オールマイティに使えます。
- Zaim:分析機能が充実しており、家計改善のヒントが見つかりやすいのが特徴です。
まずは1ヶ月、記録をつけてみてください。「えっ、私こんなにコンビニでお金使ってたの!?」とか「サブスク、こんなに契約してたっけ…」といった、驚きの発見がきっとあります。この「気づき」こそが、節約成功へのロケットスタートになるんです。
ちなみに、私の失敗談ですが、独身時代に家計簿をつけ始めた時、エンゲル係数ならぬ「カフェラテ係数」が異常に高くて愕然とした経験があります(笑)。毎日何気なく買っていた300円のカフェラテが、月々9,000円、年間10万円以上の出費になっていたんです。それに気づいてからは、マイボトル持参に切り替えました。小さなことですが、こういう「見える化」が大きな効果を生むんですよ。
固定費の見直しが最強の節約!スマホ・保険・住居費を斬る
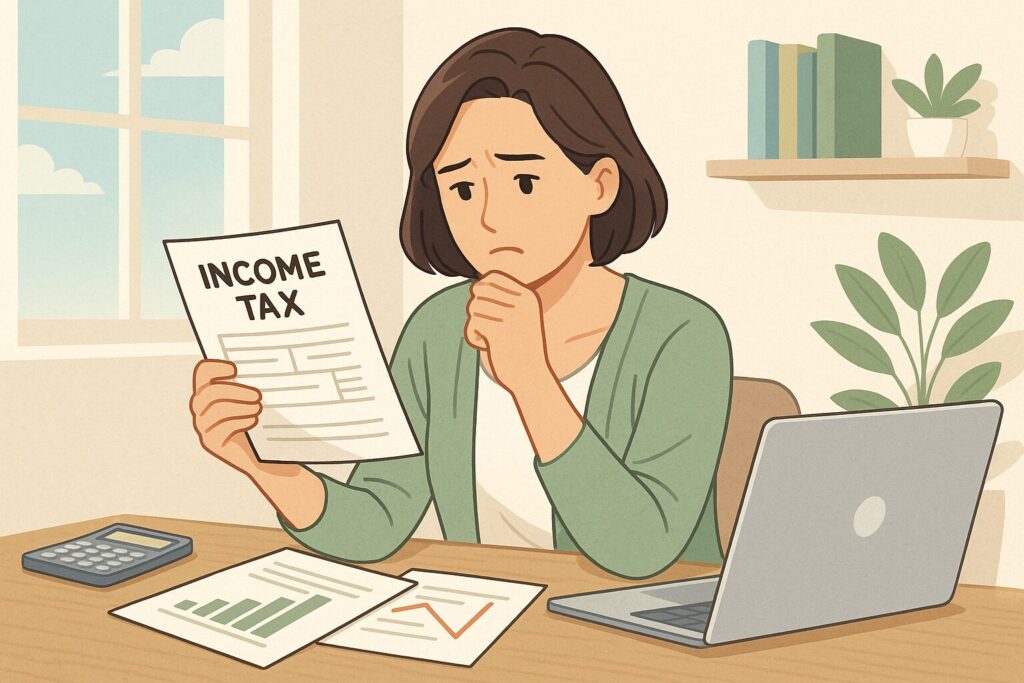
家計の見える化ができたら、次はいよいよメスを入れていきます!効果が絶大で、一度やれば効果がずっと続くのが「固定費の見直し」です。食費や娯楽費のような変動費を切り詰めるのは精神的にも辛いですが、固定費は一度見直せば、我慢することなくお金が貯まっていきます。
スマホ代:大手キャリアから格安SIMへ
まだ大手キャリアで月々8,000円以上払っていませんか?今は格安SIMでも通信品質は十分で、月々の料金を2,000円〜3,000円程度に抑えることが可能です。夫婦二人なら、年間10万円以上の節約になることも!「手続きが面倒…」と思うかもしれませんが、その数時間の手間で、将来の海外旅行に行けると思えば、頑張れる気がしませんか?
保険料:その保険、本当に必要?
「なんとなく不安だから」と、勧められるがままに加入した保険はありませんか?特に、貯蓄性の高い保険は、手数料が高く、今の時代には合っていないケースも。
日本の公的医療保険は非常に優秀なので、民間の医療保険は最低限で良い場合がほとんどです。無料の保険相談窓口などを利用して、今の自分たちに本当に必要な保障だけを残し、スリム化を図りましょう。
保険見直しのポイント
「お守り代わり」で高い保険料を払い続けるのはやめましょう。万が一の時に必要な金額(生活費、子どもの教育費など)を具体的に計算し、不足分だけを保険で賄うのが賢い考え方です。
住居費:人生最大の固定費
住宅ローンが残っている方は、借り換えを検討する価値があります。金利が1%下がるだけでも、総返済額が数百万円単位で変わる可能性があります。また、子どもが独立して夫婦二人になったら、ダウンサイジング(より小さな家への住み替え)も有効な選択肢。家を売却した資金で老後資金を確保し、固定資産税や光熱費の負担も軽くなります。
健康こそ最高の資産!心と体のメンテナンスで医療費を節約する方法
前述の通り、老後の家計を圧迫する大きな要因の一つが「医療費・介護費」です。健康でいること、つまり「健康寿命」を延ばすことが、何よりの節約であり、豊かな老後を送るための鍵となります。
厚生労働省のデータによると、平均寿命と健康寿命の間には、男性で約9年、女性で約12年もの差があります。この期間は、誰かの助けが必要な「不健康な期間」ということ。この期間が長引けば、それだけ医療費や介護費がかさみ、何よりQOL(生活の質)が大きく下がってしまいます。
でも、大丈夫!今日から始められる簡単なことで、未来の医療費は大きく変えられますよ。
特別なジムに通ったり、高級な健康食品を食べたりする必要はありません。まずは、「1日20分の早歩き」から始めてみませんか?ウォーキングは心肺機能を高め、生活習慣病の予防に繋がります。景色を楽しみながら、夫婦でおしゃべりしながら歩けば、ストレス解消にもなって一石二鳥です。
また、食生活も見直しましょう。野菜をたっぷり摂り、塩分を控えるといった基本的なことが大切です。完璧を目指す必要はありません。「週に1日は休肝日にする」「お味噌汁の具を増やす」など、小さな目標からクリアしていくのが長続きのコツです。健康への投資は、絶対に裏切らない、最もリターンの大きい自己投資だと言えます。
年金だけに頼らない!iDeCoやNISAを活用した賢い資産形成術

「年金だけでは心もとない…」と感じているなら、積極的に資産を育てるステップに進みましょう。ここで強い味方になってくれるのが、国が「みんな、これ使って老後資金の準備をしてね!」と用意してくれた、おトクな非課税制度、iDeCo(個人型確定拠出年金)とNISA(少額投資非課税制度)です。
投資の基本
「投資」と聞くと怖いイメージがあるかもしれませんが、iDeCoやNISAで推奨されているのは、長期・積立・分散投資。これは、時間をかけてコツコツと、様々な資産に分けて投資することで、リスクを抑えながら安定的なリターンを目指す方法です。
それぞれの特徴を簡単に説明すると…
- iDeCo:掛金が全額所得控除になるので、節税効果が抜群です。ただし、原則60歳まで引き出せないので、まさに「老後資金専用の貯金箱」というイメージです。
- NISA:iDeCoと違って、いつでも引き出し可能です。運用して得た利益が非課税になるのが最大のメリット。2024年から新NISAが始まり、非課税で投資できる枠が大幅に拡大しました。
「どちらを選べばいいの?」と迷ったら、まずはiDeCoで節税メリットを最大限に受けつつ、余裕があればNISAも活用するのがおすすめです。金融機関によっては、月々1,000円や5,000円といった少額から始められます。「知識がないから…」と尻込みせず、まずは口座を開設して、少額から始めてみることが大切です。お金に働いてもらう感覚を、ぜひ体験してみてください。
参考情報サイト: 金融庁「NISA特設ウェブサイト」
URL: https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/index.html
公的制度を賢く利用!知らないと損する支援制度とは
「もう切り詰める場所がない…」「どうしても生活が苦しい…」そんな時は、一人で抱え込まず、国や自治体の制度を頼りましょう。これらは、国民の権利として用意されているものですから、利用することに何ら恥ずかしさはありません。
困った時に頼れる主な公的制度
- 生活福祉資金貸付制度:低所得者や高齢者世帯に対して、生活費や住宅入居費などを無利子または低金利で貸し付けてくれる制度です。窓口は市区町村の社会福祉協議会になります。
- 生活困窮者自立支援制度:生活保護に至る前の段階で、専門の支援員が一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、自立に向けた手助けをしてくれる制度です。家計相談支援なども行っています。
- 年金の繰上げ受給:本来65歳から受け取る年金を、60歳から前倒しで受け取ることができます。ただし、一度手続きすると取り消せず、受給額が減額される点には注意が必要です。
- 生活保護制度:あらゆる手段を尽くしても生活が困難な場合の、最後のセーフティネットです。資産や能力などすべてを活用してもなお生活に困窮する方が対象となります。
「自分は対象になるのかな?」と迷ったら、まずはお住まいの市区町村役場の相談窓口や、前述の地域包括支援センターに足を運んでみてください。専門家が親身に話を聞き、利用できる制度を一緒に探してくれます。情報は知っているか知らないかで、大きな差が生まれます。困った時のために、こうした選択肢があることを頭の片隅に置いておくだけでも、心の安心に繋がります。
究極の対策!老後の「お金の残し方」で絶対やってはいけない3つのこと
せっかく頑張って貯めてきた大切なお金。最後の最後で使い方を間違えて、みじめな老後を迎えることだけは避けたいですよね。ここでは、冒頭の記事にあったAさんのような後悔をしないために、老後の「お金の残し方=使い方」で絶対やってはいけない3つのことをお伝えします。
1. 「老後のため」と我慢しすぎて、お金を全く使わない
これは本当に皮肉な話ですが、過度な節約生活が染み付いてしまい、いざ自由な時間とお金が手に入っても、何にも使えなくなってしまうケースです。「旅行なんて贅沢」「外食はもったいない」とお金を使うことに恐怖すら覚えてしまうのです。その結果、貯金通帳の数字だけが増えていき、心は満たされないまま…。お金は、使うためにあるという大原則を忘れてはいけません。現役時代から、予算を決めて旅行や趣味を楽しむなど、上手にお金を使う練習をしておくことが大切です。
2. 退職金を「一つのカゴ」に盛る
まとまった退職金が入ると、銀行などから「この投資信託がおすすめです!」といった甘い誘いが来ることがあります。言われるがままに、退職金の大部分を一つの金融商品にドン!とつぎ込んでしまうのは非常に危険です。もし、その商品の価値が暴落したら…?大切な老後資金が一瞬で吹き飛んでしまいます。退職金は、当面の生活費、リフォームなどの使う予定のあるお金、そして長期で運用するお金、と複数のカゴに分けて管理するのが鉄則です。
「卵は一つのカゴに盛るな」という投資の格言は、退職金の管理にもそのまま当てはまるんですよ!
3. 周囲のアドバイスを鵜呑みにする
良かれと思ってアドバイスしてくれる友人や親戚もいるでしょう。しかし、その人の成功体験が、必ずしもあなたに当てはまるとは限りません。家族構成も、資産状況も、リスク許容度も人それぞれです。特に、「絶対儲かる」といった話には要注意。最終的に判断するのは、他の誰でもないあなた自身です。しっかりと自分で調べ、納得した上でお金を動かすようにしましょう。少しでも疑問に思ったら、複数の専門家(ファイナンシャルプランナーなど)に意見を聞いてみるのも一つの手です。
【まとめ】老後お金がないみじめにならない老後の不安を安心に!今日からできることリスト

長い時間お付き合いいただき、ありがとうございました!最後に、この記事の要点をリストにまとめました。明日から、いえ、今日からできることばかりです。一つでもいいので、ぜひ行動に移してみてくださいね。あなたの老後が、みじめどころか、最高にハッピーなものになるよう、心から応援しています!
- 老後の不安はまず「家計の見える化」から解消する
- 年金受給額と平均生活費を比べて現実を知る
- 老後貧乏になる人の特徴は「楽観」「見栄」「過度な節約」「不健康」「無知」
- お金がない親の面倒は一人で抱えず公的機関に相談する
- 最強の節約術はスマホ・保険・住居費などの「固定費削減」
- 毎日20分の早歩きなど簡単な運動を習慣にする
- 銀行預金だけでなくiDeCoやNISAで資産運用を始める
- iDeCoは節税効果、NISAは手軽さが魅力
- 生活に困ったら生活福祉資金貸付制度などの公的支援を頼る
- 権利として使える制度なので利用をためらわない
- お金は「貯める」だけでなく「上手に使う」練習も必要
- 退職金は一つの金融商品に集中させず分散管理する
- 他人の安易なアドバイスを鵜呑みにせず自分で判断する
- 老後の不安は具体的な行動でしか解消できない
参考
・50代シングルマザー老後の不安を減らす住まいとお金の話
・エンディングノート50代おすすめ特集|後悔しない選び方と活用術
・終活やりすぎに注意!家族が後悔しないための断捨離ルール
・エンディングノート40代おすすめ|失敗しない選び方と無料の始め方
・老後一人ぼっち女性の生活費と貯金目安をわかりやすく徹底解説

お気軽にご相談ください
相続は100人いれば、100通り
唯一無二の最適な相続をご提案いたします
CONTACT
専門家やえさん

- 専門家やえさん
-
堀川 八重(ほりかわ やえ)
大阪不動産・FPサービス株式会社 代表
15年以上にわたり1,500組を超えるご家族の相続や不動産のお悩みに、専門家として寄り添ってまいりました。私の信条は、法律や数字の話をする前に、まずお客様ご家族の歴史や言葉にならない想いを丁寧に「聞く」こと。信頼できる各分野の専門家チームと共に、皆様が心から安心できる最善の道筋をオーダーメイドでご提案します。一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。
最新の投稿
 お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説
お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説 相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説
相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説 お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例
お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例 お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説
お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説






