年金の追納、一括と分割どっちが得なんだろう…って、インターネットの情報とにらめっこしていませんか?(笑)実は私も、学生のときに猶予してもらっていた国民年金保険料を追納すべきか、真剣に悩んだ経験があります。
インターネットで検索すると、「国民年金を4年間未納だといくら減りますか?」といった具体的な疑問から、「年金追納はしない方がいい」「いや学生特例は追納しないほうが良い」なんていう気になる噂まで、色々な情報が飛び交っていますよね。
そもそも年金の追納は1ヶ月分毎にできるのか、年金追納のやり方自体がよく分からない!という方もいらっしゃるかもしれません。さらに、年金追納には期限切れや10年過ぎたものはどうなるのかという時効の問題、気になる年金追納の加算額、そして嬉しい年金追納の控除シミュレーションまで、知りたいことが山積みです!
このままだと、せっかくのメリットを逃してしまう可能性も…。この記事を読めば、そんなモヤモヤがスッキリ晴れて、あなたにピッタリの追納方法が見つかります。将来のお金と賢く向き合うための第一歩、一緒に踏み出しましょう!
この記事のポイント
- 一括払いと分割払いのメリット・デメリットがわかる
- あなたに合った追納方法が見つかる
- 追納の具体的な手続きと注意点が理解できる
- 節税効果や加算額の仕組みがわかる
目次
年金追納一括分割どっちが得?基本と損得勘定

| 比較項目 | 一括払い | 分割払い |
|---|---|---|
| 支払総額 | 加算額の増加を抑えやすい | 支払いが長期にわたると加算額が増え、総額が高くなる可能性あり |
| 家計への負担 | 一度に大きな出費が必要 | 月々など、計画的に支払えるため負担を分散できる |
| 節税効果 | 支払った年にまとめて高額の控除を受けられる | 支払った年ごとに、その年の納付額分が控除対象になる |
| 手続きの手間 | 一度で完了 | 納付書が複数回に分けて届き、その都度支払いが必要 |
| 年金額への反映 | 早く満額に近づく | 全額納付が完了してから満額に反映される |
国民年金を4年間未納だといくら減りますか?
結論からお伝えすると、国民年金を4年間(48ヶ月)追納しない場合、将来受け取る年金額は年間で約8万円も減ってしまいます。
これは、老後の生活を考えるとかなり大きな金額の違いになりますよね。もう少し詳しく解説します。
日本の年金制度では、20歳から60歳までの40年間(480ヶ月)すべての国民年金保険料を納付すると、満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。令和7年度の満額の年金額は、年間で約81.6万円と公表されています。(※年金額は毎年改定されます)
もし4年間(48ヶ月)分の保険料が未納(免除や猶予期間を追納しない場合も同様)だと、受け取れる年金額は以下のように計算できます。
年金額の計算式
満額の年金額 × (保険料納付月数 ÷ 480ヶ月) = 将来の年金額
【4年間未納の場合】
約816,000円 × ( (480ヶ月 - 48ヶ月) ÷ 480ヶ月 ) = 約734,400円
つまり、満額の場合と比較して、年間で約81,600円、月額にすると約6,800円も受給額が少なくなってしまう計算です。
月々約7,000円って、結構大きいですよね!おいしいランチが何回も食べられますし、趣味にもお金を使えます。私の担当させていただいたお客様の中にも、「計算してみて思ったより金額が大きくてびっくりした。将来のために追納を決めました」とおっしゃっていた方がいました。一度、ご自身の状況でどれくらい変わるのか考えてみるのはとても必要ですね。
もちろん、これはあくまでシミュレーション上の金額ですが、追納するかしないかで将来の生活に大きな差が生まれることは間違いありません。この金額の差をどう捉えるかが、追納を検討する上での最初のステップになります。
年金追納しない方がいいケースとは
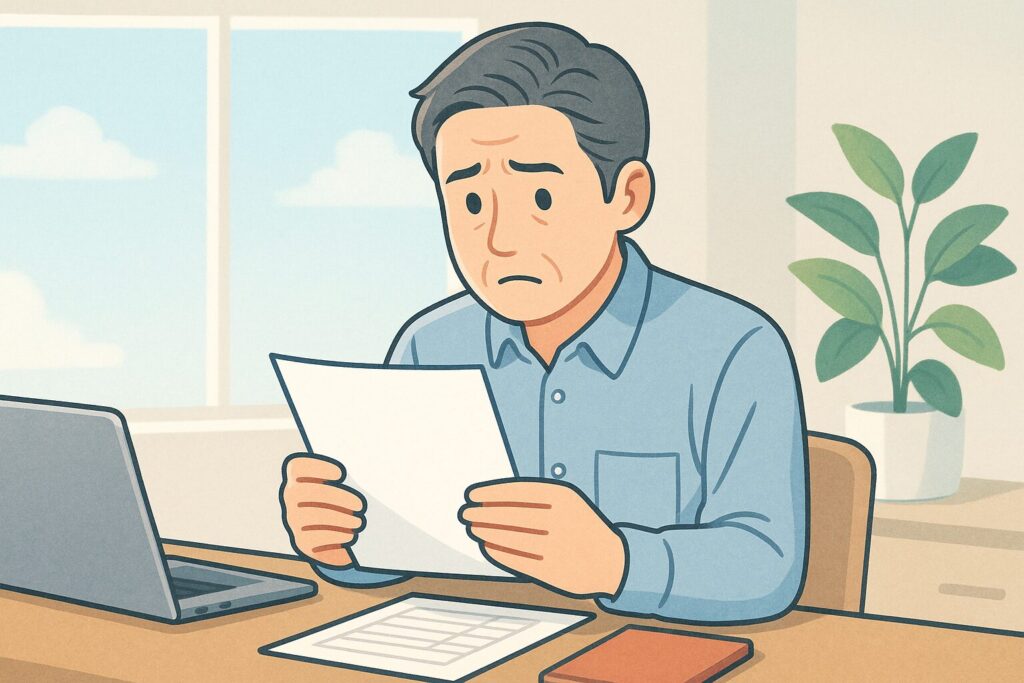
「じゃあ、絶対に追納した方がいいんだ!」と思われるかもしれませんが、実はごく稀に「追納しない方がいい」と言われるケースも存在します。ただ、これはかなり限定的な状況ですので、注意が必要です。
基本的には、将来受け取れる年金額が増え、さらに社会保険料控除による節税メリットもあるため、追納する方が圧倒的にお得です。しかし、以下のような状況にある方は、慎重な判断が必要かもしれません。
手元の資金が極端に少なく、生活が困窮している場合
追納するための保険料を支払うことで、日々の生活が成り立たなくなってしまっては本末転倒です。国民年金保険料の追納には、免除や猶予の承認を受けた期間の翌年度の4月末日から10年以内という期限があります。今は生活を安定させることが最優先、という方は、無理に追納せず、家計に余裕ができてから検討するという選択肢もあります。
以前、脱サラして起業したばかりのお客様が、「今は事業を軌道に乗せるのが最優先。運転資金を確保したいから、追納は数年後に考える」とおっしゃっていました。このように、ライフプランの中で明確な優先順位がある場合は、計画的に追納を後回しにするのも一つの手ですね。ただし、期限切れには要注意です!
投資などで年金以上のリターンを得る絶対的な自信がある場合
追納するはずだった保険料を、ご自身で投資などに回して、将来の年金の増額分以上の利益を生み出す、という考え方です。ただ、これは投資に関する深い知識と経験が必要であり、元本割れのリスクも伴います。
追納しない場合の大きなデメリット
「追納しない」という選択をする前に、デメリットをしっかり理解しておくことが重要です。
- 将来の年金額が減る:前述の通り、老後の生活資金が少なくなります。
- 障害年金や遺族年金が受給できない可能性:障害年金や遺族年金は、受給要件の一つに「保険料の納付状況」が含まれます。未納期間が多いと、万が一の際にこれらの年金が受け取れない可能性があります。
これらの理由から、ほとんどの方にとっては追納するメリットの方が大きいと言えます。ご自身の経済状況やライフプランと照らし合わせ、慎重に判断することが大切です。
年金学生特例は追納すべきか追納しないほうが良いか
学生時代に「学生納付特例制度」を利用していた方は、結論として、追納することを強くおすすめします。
「学生特例を使ったんだから、保険料は払わなくていいんでしょ?」と思われがちですが、これは大きな誤解です。学生納付特例は、保険料の納付が「免除」されるのではなく、社会人になるまで「猶予(ゆうよ)」される制度なのです。
「免除」と「猶予」の決定的な違い
- 免除:所得が低いなどの理由で保険料の納付が免除された期間。保険料を納めていなくても、その期間に応じて一定額が将来の年金額に反映されます。(例:全額免除の場合、保険料を全額納付した場合の2分の1が反映)
- 猶予(学生特例など):保険料の支払いを先延ばしにしている期間。追納しないと、将来の年金額には全く反映されません。
つまり、学生納付特例の期間をそのままにしておくと、その期間は保険料を全く納めていないのと同じ扱いになり、将来もらえる年金額が満額よりも少なくなってしまうのです。
私も学生時代はこの制度にお世話になりました!社会人1年目のときは、お給料もまだ少なくて「うーん、追納は厳しいかな…」なんて思っていましたが、将来の自分への投資だと考えて、少しずつ分割で納付しました。今となっては、あのとき頑張って本当に良かったと思っています(笑)。
「学生特例は追納しないほうが良い」という意見は、おそらく「社会人になったばかりで経済的に大変な時期に、無理して支払う必要はない」という意味合いで語られることが多いのかもしれません。もちろん、前述の通り、生活が苦しい場合に無理は禁物です。しかし、追納できるのは10年以内という期限付き。計画的に追納を進めて、将来もらえる年金額を満額に近づけるのが賢い選択と言えるでしょう。
年金追納の加算額とは何か

年金の追納を考え始めると、「加算額」という言葉を目にすることがあります。これは、簡単に言うと追納するのが遅くなった場合に、本来の保険料に上乗せして支払う必要がある金額のことです。
「え、なんで追加料金がかかるの?」と思いますよね。その理由は、保険料を期限通りに納付してきた方との公平性を保つため、とされています。当時の物価や賃金の変動などを考慮して、現在の価値に換算するための調整金、というイメージです。
この加算額が発生するのは、免除や猶予の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合です。つまり、2年以内に追納すれば、加算額はかからず、当時の保険料だけで済みます。
加算額の具体例を見てみよう!
例えば、平成27年度(2015年度)の保険料(1ヶ月分)を、令和7年度(2025年度)中に追納する場合で見てみましょう。
- 当時の保険料額:15,590円
- 経過期間に応じた加算額:340円
- 追納に必要な金額:15,930円
このように、1ヶ月あたり340円が上乗せされます。1年分(12ヶ月)追納すると、加算額だけで4,080円にもなります。これが「ちりつも」で、追納する期間が長ければ長いほど、結構な負担になってくるのです。
参考情報サイト:日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」
URL: https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html
だからこそ、「いつか追納しよう」と考えているなら、なるべく早めに手続きするのがおすすめです。加算額がかからない2年以内がベストですが、それが難しい場合でも、先延ばしにすればするほど支払う総額が増えてしまう、ということを覚えておきましょう。
年金追納一括分割どっちが得か知恵袋での疑問
「年金追納、一括と分割どっちが得?」という疑問は、多くの方が抱くようで、Yahoo!知恵袋などのQ&Aサイトでも頻繁に質問が寄せられていますね。私もついつい覗いてしまうことがあります(笑)。
知恵袋でよく見かける疑問に、WEBライターの視点からお答えします!
「知恵袋で『一括で払うと割引がある』って見たんですけど、本当ですか?」というご質問、実はよくいただきます!気持ちはすっごく分かりますが、残念ながら…答えはNOなんです。
よくある疑問①:「一括で払うと保険料が割引されるの?」
結論から言うと、追納に関しては一括で支払っても保険料自体の割引はありません。
国民年金保険料には、前もって納付する「前納」という制度があり、こちらは割引が適用されます。この情報と混同されがちなのですが、追納はあくまで過去の分を後から納める制度なので、割引の対象にはならないのです。
よくある疑問②:「分割で払うと損するの?」
これも一概に「損」とは言えません。ただし、注意点はあります。前述の通り、追納するのが3年度目以降になると「加算額」が発生します。分割払いを選ぶことで納付期間が長引き、その間に加算額が増えてしまい、結果的に支払う総額が一括で払うより多くなる可能性はあります。
しかし、「分割払い」は、一度にまとまったお金を用意するのが難しい方にとっては、非常に助かる制度です。家計への負担を抑えながら、計画的に未納期間を解消できる大きなメリットがあります。
知恵袋の情報の歩き方
知恵袋などのサイトは、同じ悩みを持つ方の実体験が読めるので参考になりますが、中には古い情報や誤った情報が紛れていることもあります。特に年金制度は法改正などで内容が変わることも少なくありません。
最終的な判断は、日本年金機構の公式サイトで最新情報を確認したり、年金事務所に相談したりするのが一番確実です。この記事も、そのための第一歩として活用していただけると嬉しいです!
年金追納一括分割どっちが得?手続きと注意点

年金追納のやり方と必要書類
「よし、追納しよう!」と決めたものの、「で、どうすればいいの?」となりますよね。ご安心ください、手続き自体は意外とシンプルで、それほど難しくありません。
ここでは、追納の申し込みから納付までの具体的な流れを解説します。
STEP1:申込書の入手と提出
まずは、「国民年金保険料 追納申込書」という書類を提出する必要があります。
- 入手方法:お近くの年金事務所の窓口、または日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
- 提出先:住民票のある住所地を管轄する年金事務所
- 提出方法:年金事務所の窓口に直接持っていくか、郵送でもOKです。
マイナンバーで申請する場合の注意点
マイナンバー(個人番号)で申請する場合は、本人確認書類が必要です。
- 窓口提出の場合:マイナンバーカードを提示します。持っていない場合は、通知カードやマイナンバーが記載された住民票の写しと、運転免許証やパスポートなどの身元確認書類の2点が必要です。
- 郵送提出の場合:マイナンバーカードの両面のコピー、または上記2点の書類のコピーを申込書に添付します。
STEP2:納付書が届くのを待つ
申込書を提出してから、およそ1ヶ月〜2ヶ月ほどで、日本年金機構から専用の納付書が郵送されてきます。この納付書を使って保険料を支払います。
一括払いを選んだ場合は1枚、分割払いを選んだ場合は複数枚の納付書が届きます。
STEP3:金融機関やコンビニで納付する
届いた納付書を持って、以下の場所で保険料を納付します。
- 金融機関(銀行、信用金庫など)
- 郵便局
- コンビニエンスストア
- 電子納付(Pay-easy ペイジー)
この支払い方法はNG!
追納保険料の支払いは、以下の方法ではできませんのでご注意ください。
- 口座振替
- クレジットカード払い
通常の国民年金保険料はクレジットカード払いも可能ですが、追納は対象外となっています。
「え、クレカでポイント貯めようと思ってたのに!」というお客様、結構いらっしゃいます(笑)。残念ながら追納は現金かペイジーでの納付になるので、お気をつけくださいね。手続きで分からないことがあれば、迷わず年金事務所に電話で問い合わせてみるのが一番早いですよ!
参考情報サイト:日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」
URL: https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html
年金追納は分割で1ヶ月分毎にできますか?

はい、結論から言うと、年金の追納は1ヶ月分毎の分割で納付することが可能です。
「追納したいけど、一度に何十万円も払うのは厳しい…」という方にとって、この分割払いはとても心強い味方になりますよね。追納を申し込む際の「国民年金保険料 追納申込書」に、希望する納付方法を記入する欄があります。
申込書での分割方法の選び方
申込書には「分割区分」という項目があり、以下のような選択肢から希望の納付パターンを選んで申し込むことができます。
- 全部一括:追納可能な全期間分をまとめて支払う
- 1ヶ月毎:1ヶ月分ずつの納付書が送られてくる
- 2ヶ月毎、3ヶ月毎、6ヶ月毎など:希望する月数分をまとめた納付書が送られてくる
私の友人は、社会人になって初めての追納のとき、「毎月お給料が出たら、忘れないように1ヶ月分ずつコンビニで払う」というマイルールを決めて、コツコツ完納していましたよ。自分にとって一番続けやすいペースを選ぶのが、途中で挫折しないコツかもしれませんね。
分割払いを選ぶ際の注意点
手軽さが魅力の分割払いですが、いくつか知っておきたい注意点があります。
分割払いの注意ポイント
- 古い期間から納付するルール:追納は、必ず承認された期間のうち、古い月の分から順番に納めていく必要があります。例えば、平成30年度分と令和元年度分の追納をする場合、令和元年度分を先に支払うことはできず、平成30年度分から納付しなければなりません。
- 加算額の可能性:前述の通り、追納するのが3年度目以降の期間である場合、納付するタイミングに応じて加算額が上乗せされます。分割でゆっくり支払う場合、その間に加算額が増えてしまう可能性があることは覚えておきましょう。
- 納付書の有効期限:送られてくる納付書には有効期限があります。期限を過ぎてしまうと、その納付書では支払えなくなってしまうので注意が必要です。
これらのポイントを理解した上で、ご自身の収入や家計の状況に合わせて最適な分割プランを選ぶことが大切です。無理なく、でも計画的に。賢く分割払いを利用して、将来の年金を育てていきましょう。
年金追納は10年過ぎたら期限切れ?
この質問に対する答えは、残念ながら「はい、その通りです」となります。
国民年金保険料の追納ができるのは、免除・納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間の翌年度の4月末日から起算して10年以内と定められています。この10年という期間を過ぎてしまうと、原則として追納することはできなくなり、その期間は年金額に反映されないまま確定してしまいます。
「10年」のカウント方法に注意!
例えば、平成27年度(2015年4月~2016年3月)分の保険料を追納したい場合。
この期間の追納期限は、10年後の令和8年(2026年)4月末日までとなります。うっかりしていると、あっという間に期限が来てしまう可能性があるので注意が必要です。
「まだ大丈夫だと思ってたのに、気づいたら期限が…!」というお客様の悲しいお声を、これまで何度か耳にしたことがあります。特に複数の年度にわたって猶予期間がある方は、一番古い期間の期限をしっかり把握しておくことが本当に大切です。カレンダーや手帳にメモしておくことをおすすめします!
もし期限切れになってしまったら?
10年の追納期限を過ぎてしまった保険料は、残念ながら後から納める方法はありません。そのため、その期間分の年金額は増やすことができなくなります。
だからこそ、追納を少しでも検討しているなら、ご自身の追納可能な期間と、それぞれの期限を一度確認してみることが重要です。「ねんきんネット」を利用すれば、ご自身の年金記録や追納可能な期間を手軽に確認できますし、お近くの年金事務所に問い合わせれば詳しく教えてもらえます。
「後でやろう」が、将来の後悔につながらないように。大切な年金を守るために、まずはご自身の状況を確認することから始めてみてください。
参考情報サイト:日本年金機構「ねんきんネット」
URL: https://www.nenkin.go.jp/n_net/
年金追納の控除シミュレーション

年金追納の大きなメリットの一つが、支払った保険料が全額「社会保険料控除」の対象となり、所得税や住民税が安くなるという節税効果です。
「でも、実際にどれくらいお得になるの?」というのが一番気になるところですよね。ここで、簡単な控除のシミュレーションをしてみましょう。
所得税の税率は、課税される所得金額(年収から給与所得控除や基礎控除などを引いた金額)によって変わります。住民税の税率は、一般的に約10%です。
| 課税所得金額 | 所得税率 | 節税額の目安(所得税+住民税) |
|---|---|---|
| 約300万円 | 10% | 40万円 × (10% + 10%) = 約80,000円 |
| 約500万円 | 20% | 40万円 × (20% + 10%) = 約120,000円 |
| 約700万円 | 23% | 40万円 × (23% + 10%) = 約132,000円 |
シミュレーションから分かること
この表から分かるように、所得が高い(所得税率が高い)方ほど、追納による節税効果は大きくなります。例えば、課税所得500万円の方が40万円追納すると、約12万円も税金が戻ってくる(安くなる)計算です。これは非常に大きなメリットと言えますね。
節税効果を最大化するタイミングは?
このシミュレーション結果を踏まえると、節税という観点では「収入が多い年にまとめて一括で追納する」のが最も効果的です。例えば、ボーナスがたくさん出た年や、転職して年収が上がった年などが狙い目です。
年末調整の時期になると、「今年は追納した方が得ですか?」というご相談が増えます。お客様の年収や家族構成をお伺いして、「この収入なら、今年中に追納すればこれくらい住民税や所得税がお得になりますよ」とお話しすると、皆さんとても喜んでくださいます。ご自身の状況に合わせて、一番メリットのあるタイミングを見つけるのが賢いやり方ですね。
この控除を受けるためには、会社員の方は年末調整で、自営業やフリーランスの方は確定申告で、追納した保険料の金額を申告する必要があります。支払った際に受け取る領収書や、日本年金機構から送られてくる「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、大切に保管しておきましょう。
年金追納一括分割どっちが得かの最終判断
ここまで様々な角度から年金追納の一括払いと分割払いについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。最後に、あなたがどちらを選ぶべきか、最終判断するためのポイントをまとめます。
- 年金の追納は、将来受け取る年金額を増やせる重要な制度
- 追納した保険料は、全額が社会保険料控除の対象となり、所得税や住民税の節税につながる
- 一括払いでも分割払いでも、月々の保険料自体に割引はない
- 一番の違いは「加算額」と「節税のタイミング」
- 追納が3年度目以降の場合、経過期間に応じた「加算額」が上乗せされる
- 早く支払う(一括に近い形)ほど、加算額の総額は少なく済む
- 節税効果は、所得が高い(所得税率が高い)年に支払うほど大きくなる
- 学生納付特例は「猶予」制度であり、追納しないと年金額に全く反映されないため、追納が強く推奨される
- 追納ができるのは、承認期間の翌年度から10年以内という期限がある
- 10年の期限を過ぎてしまうと、原則として追納はできなくなる
- 追納の申し込みは年金事務所で行い、支払いは金融機関やコンビニなどで行う
- 追納の支払いには、クレジットカードや口座振替は利用できない
- 【一括払いが向いている人】資金に余裕があり、支払総額を抑えたい、またはその年の節税効果を最大化したい人
- 【分割払いが向いている人】一度にまとまった資金を用意するのが難しく、家計への負担を抑えながら計画的に納めたい人
- どちらの選択が自分にとって「得」かは、経済状況やライフプラン、何を重視するかによって異なるため、この記事を参考にじっくり検討することが必要
参考
・50代シングルマザー老後の不安を減らす住まいとお金の話
・エンディングノート50代おすすめ特集|後悔しない選び方と活用術
・終活やりすぎに注意!家族が後悔しないための断捨離ルール
・エンディングノート40代おすすめ|失敗しない選び方と無料の始め方
・老後一人ぼっち女性の生活費と貯金目安をわかりやすく徹底解説

お気軽にご相談ください
相続は100人いれば、100通り
唯一無二の最適な相続をご提案いたします
CONTACT
専門家やえさん

- 専門家やえさん
-
堀川 八重(ほりかわ やえ)
大阪不動産・FPサービス株式会社 代表
15年以上にわたり1,500組を超えるご家族の相続や不動産のお悩みに、専門家として寄り添ってまいりました。私の信条は、法律や数字の話をする前に、まずお客様ご家族の歴史や言葉にならない想いを丁寧に「聞く」こと。信頼できる各分野の専門家チームと共に、皆様が心から安心できる最善の道筋をオーダーメイドでご提案します。一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。
最新の投稿
 お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説
お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説 相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説
相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説 お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例
お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例 お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説
お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説






