こんにちは!突然ですが、「墓じまい知恵袋」というキーワードで検索されたあなたは、もしかして、お墓のことで頭を悩ませていらっしゃるのでしょうか?「墓じまいお金がない」と不安に思ったり、「墓じまい費用」がどれくらいかかるのか気になったり、「墓じまいしないとどうなる」のか心配になったりしていませんか?
中には「墓じまい費用払えない知恵袋」で情報を探している方もいらっしゃるかもしれませんね。もしかしたら、「墓じまい補助金」ってあるのかな?とか、「一人っ子墓じまい」ってどう進めるの?「墓じまい費用誰が払う」のが一般的なの?と、具体的な疑問をお持ちかもしれません。
また、「墓放置無視」は良くないって聞くけど、実際どうなの?「墓じまいしないとどうなる知恵袋」で調べても、情報が多すぎて迷ってしまうこともありますよね。
「墓じまいは呪われたりする」なんて都市伝説のような話を聞いて、ちょっとドキドキしている方もいるかもしれません。そして、一番気になるのは「墓じまいにかかる費用は平均していくらですか」ということや、「墓じまいをしてはいけない時期はいつですか」といった具体的なタイミングのお話ではないでしょうか。
このブログ記事は、そんなあなたの疑問に寄り添い、墓じまいに関する不安を一つずつ解消できるよう、優しく丁寧に解説していきますので、ぜひ最後までお付き合いくださいね。
墓じまい、何から始めればいいかわからない…。
そんな方は、まず専門家に無料で相談してみませんか?
この記事のポイント
- 墓じまいの基本的な流れと必要な費用がわかる
- 費用を抑えるための具体的な方法がわかる
- トラブルを避けてスムーズに進めるためのポイントがわかる
- 墓じまい後の供養方法の選択肢がわかる
目次
墓じまい知恵袋|墓じまいを検討する際の基本

墓じまい費用とその平均はいくら?
墓じまいを検討される際に、まず頭に浮かぶのは「費用」のことではないでしょうか。結論から申し上げますと、墓じまいの費用は、お墓の規模や場所、そして墓じまい後の供養方法によって大きく変動します。一般的に、墓じまいにかかる総費用は、50万円から200万円程度と言われています。
墓じまい費用の内訳
- 墓石の撤去・解体費用
- 閉眼供養(魂抜き)のお布施
- 離檀料(檀家の場合)
- 行政手続き費用
- 新しい供養方法の費用(改葬先への納骨費用など)
例えば、墓石の撤去費用は、墓地の広さや墓石の大きさ、そして重機の搬入が可能かどうかといった立地条件によって変わります。山間部など、重機が入りにくい場所にある墓地では、手作業が増えるため費用が高くなる傾向にあります。
私の知人が経験されたケースでは、かなり古い墓地で道幅が狭く、重機が入れなかったため、手作業での解体となり、当初の見積もりよりも費用がかさんでしまったと嘆いていました。このように、立地条件は費用に大きく影響します。
また、お寺に墓地がある場合、閉眼供養という儀式が必要になります。これは、墓石から故人の魂を抜き、ただの石に戻すという意味合いがあります。この際にお寺へお布施をお渡ししますが、金額はお寺によって様々です。
さらに、檀家をやめる場合には「離檀料」が必要となることもあります。これは、これまでお世話になったお寺への感謝の気持ちとしてお渡しするもので、明確な金額が定められているわけではありませんが、トラブルを避けるためにも事前に相談することが大切です。
そして、最も費用がかかる可能性のあるのが、墓じまい後の新しい供養方法です。永代供養墓や納骨堂、樹木葬、散骨など、様々な選択肢があり、それぞれ費用が異なります。例えば、永代供養墓への納骨費用は、合祀であれば数万円から、個別の区画であれば数十万円かかることもあります。遺骨の数によっても費用が変わる場合がありますので、事前に確認が必要です。
注意点:見積もりは複数社から取りましょう
墓じまいの費用は、石材店や業者によって大きく異なります。そのため、必ず複数の業者から見積もりを取り、サービス内容と費用を比較検討することをおすすめします。安さだけで選ぶのではなく、信頼できる業者を選ぶことが大切です。
参考情報サイト: 一般社団法人全国優良石材店の会「墓じまいにかかる費用」
URL: https://www.zenyuseki.or.jp/
費用や手続きが不安な方へ。
専門家があなたの状況に合わせて丁寧にアドバイスしてくれますよ。
墓じまいをしてはいけない時期はいつですか
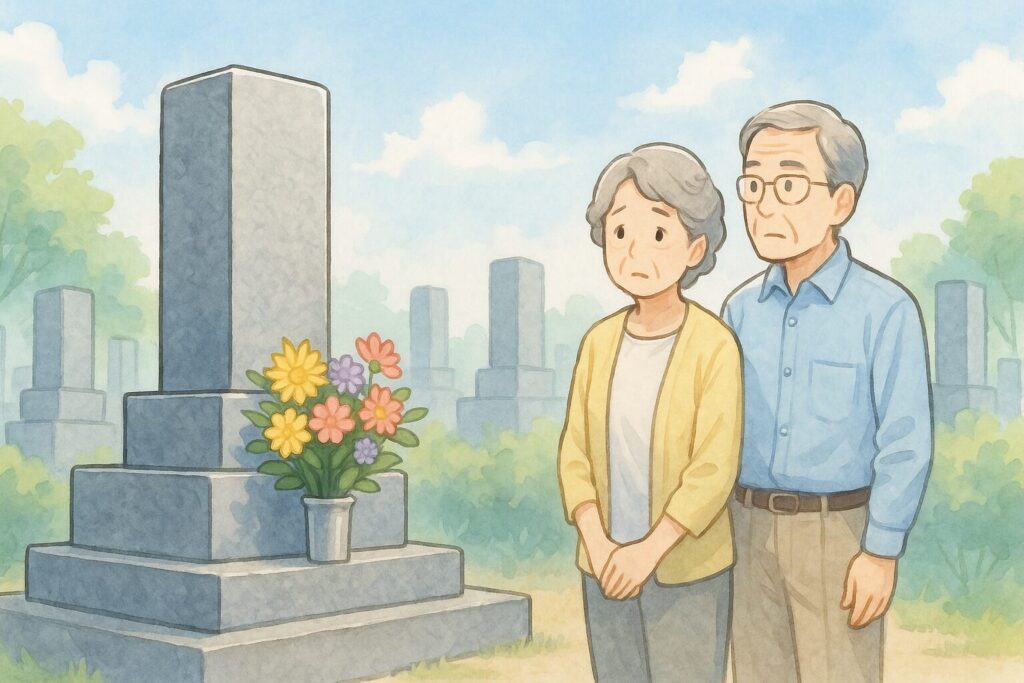
墓じまいには、特に「この時期は絶対に避けるべき」という明確な決まりはありません。しかし、一般的には、お盆やお彼岸などの仏事の時期は避けるのが望ましいとされています。なぜなら、これらの時期はお寺が法要などで忙しく、閉眼供養などの対応が難しい場合があるからです。
私のお客様で、お盆の直前に墓じまいをしようとされた方がいらっしゃいました。しかし、お寺から「この時期は多くの檀家さんの法要で手がいっぱいなので、別の時期にしてほしい」とお願いされてしまい、結局、お盆明けに延期することになったそうです。やはり、お寺やご先祖様への配慮は大切ですね。
また、親族が集まる機会が少ない時期や、悪天候が予想される時期も避けるのが賢明です。墓じまいは、親族の同意が必要な場合が多く、全員が立ち会うことが難しいこともあります。そのため、親族が集まりやすい時期を選んだり、工事がスムーズに進むような気候の良い時期を選ぶと、トラブルなく進められるでしょう。
結論として、墓じまいの時期を決める際は、まずお寺や墓地の管理者に相談し、都合の良い時期を確認することが最も重要です。そして、親族との話し合いの場を設け、皆で納得できるタイミングを選ぶことが大切です。
墓じまいしないとどうなる?知恵袋の疑問
「墓じまいしないとどうなるのか」という質問は、知恵袋でもよく見かける疑問の一つです。墓じまいをせずにお墓を放置してしまうと、様々な問題が発生する可能性があります。
墓じまいをしないことのリスク
- 管理費の滞納と墓地の使用権の剥奪
- 無縁墓となり、行政代執行で撤去される可能性
- 親族間でのトラブル
- 精神的な負担の継続
まず、墓地の管理費を支払い続ける必要があり、これを滞納すると墓地の使用権を失うことがあります。使用権がなくなると、墓石が撤去され、遺骨は合祀墓などに移されることになります。
これは「無縁墓」として扱われる状態です。私のお客様の中には、遠方に住んでいてなかなかお墓参りに行けず、管理も疎かになっていた方がいらっしゃいました。
ある日、墓地管理者から連絡があり、このままでは無縁墓として処理されてしまうと告げられ、慌てて墓じまいを検討されたそうです。このように、放置すると最終的には行政代執行によって強制的に撤去される可能性も出てきます。
また、お墓の管理は、継承者が行うのが一般的ですが、もし継承者がいなくなったり、管理が困難になったりすると、親族間で誰が管理するのか、費用は誰が負担するのかといった質問が持ち上がり、トラブルに発展することもあります。
特に、お墓に入っているご先祖様の遺骨に関わる問題は、感情的になりやすく、知恵袋でも多くの回答が寄せられるデリケートな問題です。
さらに、お墓が遠方にあってなかなかお参りに行けない、管理が大変だという状況が続くと、精神的な負担が大きくなることもあります。墓じまいをすることで、そうした負担から解放され、より自分らしい形で供養を続けることができる場合もあります。
墓放置無視は問題になる?

前述の通り、お墓を放置し、管理を無視することは、様々な問題を引き起こします。最も大きな問題は、墓地の管理費の滞納です。管理費が支払われない状態が続くと、墓地の使用契約が解除され、墓石が撤去されてしまう可能性があります。
私の知人のケースですが、ご両親が亡くなり、長年誰も墓参りに行かなくなったお墓がありました。管理費も滞納していたようで、ある日、墓地から「無縁墓として処理します」という通知が届いたそうです。
慌てて墓じまいをしようとしたものの、手続きが複雑で、さらに追加の費用も発生してしまい、大変な思いをされたと聞きました。このように、放置すると後々大きな手間と費用がかかることになります。
補足:無縁墓とは
無縁墓とは、管理者が不明であったり、管理費が長期間にわたって滞納されていたりするお墓のことです。墓地管理者は、一定の手続きを経て、無縁墓となったお墓を撤去し、遺骨を合祀墓などに移すことができます。
また、お墓が荒れてしまうと、周囲のお墓にも影響を与え、景観を損ねるだけでなく、墓地全体の管理にも支障をきたす可能性があります。このような状況は、故人やご先祖様への供養の気持ちにも影響を与えかねません。
お墓の維持が難しいと感じたら、放置するのではなく、早めに墓じまいを検討することが、結果的に故人にとっても、残された方にとっても良い選択となるでしょう。
墓じまいは呪われたりする?
「墓じまいは呪われたりする?」という、少しドキッとするような質問も、実はよく耳にします。しかし、結論から申し上げますと、墓じまいをしたからといって呪われるということは一切ありません。これは、墓じまいに関する迷信や誤解からくる不安だと言えるでしょう。
以前、お客様から「墓じまいをしたら、何か悪いことが起きるんじゃないかと心配で…」と相談を受けたことがあります。その方は、ご近所の方から「ご先祖様が怒る」と言われたそうで、とても不安そうでした。でも、墓じまいは、ご先祖様を大切に思う気持ちから、より良い供養の形を求めるための現代的な選択肢の一つです。むしろ、管理が行き届かずに荒れてしまうお墓よりも、きちんと供養の形を変えて、これからも大切にしてもらえる方が、ご先祖様も喜んでくださるのではないでしょうか。
大切なのは、墓じまいをきちんと手順を踏んで行うことです。閉眼供養(魂抜き)を行い、ご先祖様の遺骨を丁寧に改葬することで、故人への感謝と供養の気持ちを伝えることができます。
宗教的な儀式を適切に行うことで、心の平穏も保たれるでしょう。もし不安な気持ちが拭えない場合は、信頼できるお寺や専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。
墓じまいは、決してご先祖様を粗末に扱う行為ではありません。むしろ、時代の変化に合わせて、より良い供養の形を模索する、前向きな選択肢なのです。
墓じまい知恵袋|具体的な手続きと費用に関する疑問

墓じまい費用は誰が払う?
墓じまいの費用は、原則としてお墓の祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)が負担することになります。祭祀承継者とは、お墓や仏壇、位牌といった祭祀財産を受け継ぎ、管理する人のことです。多くの場合、故人の配偶者や長男がその役割を担います。
しかし、現代では、祭祀承継者が一人で費用を負担するのが難しいケースも少なくありません。特に、墓じまいにかかる費用は決して安くはないため、親族間で話し合い、分担して支払うこともあります。
私の担当したお客様の中には、兄弟姉妹で費用を出し合って墓じまいをされた方がいらっしゃいました。事前にきちんと話し合い、合意形成ができていたため、スムーズに進めることができたそうです。
費用負担に関するポイント
- 原則は祭祀承継者が負担
- 親族間で話し合い、分担することも可能
- トラブルを避けるため、書面で合意を残すのが理想
重要なのは、費用負担について親族間で質問や疑問が生じる前に、しっかりと話し合いの場を設けることです。誰がいくら負担するのか、いつまでに支払うのかなど、具体的な内容を決めておくことで、後々のトラブルを避けることができます。もし話し合いが難しい場合は、弁護士などの専門家に相談することも検討してください。
墓じまい費用が払えない場合やお金がない時の対処法

「墓じまい費用が払えない」「お金がない」という状況は、決して珍しいことではありません。知恵袋でも、このような質問が多く寄せられています。もし、墓じまいの費用を捻出するのが難しいと感じたら、いくつかの対処法があります。
まず、最も現実的な選択肢として、費用を抑える工夫をすることが挙げられます。例えば、墓じまい後の供養方法を、費用が比較的安価な合祀墓(共同墓地)や散骨にするという方法です。合祀墓であれば、数万円程度で納骨できるケースも多く、個別の墓石を建てるよりも大幅に費用を抑えることができます。
| 供養方法 | 費用目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 永代供養墓(合祀) | 数万円~20万円 | 他の遺骨と一緒に埋葬される。管理費不要。 |
| 永代供養墓(個別) | 20万円~100万円 | 一定期間個別に供養後、合祀される。 |
| 樹木葬 | 10万円~80万円 | 樹木を墓標とする。自然志向の方に人気。 |
| 納骨堂 | 10万円~150万円 | 屋内に遺骨を納める。天候に左右されない。 |
| 散骨 | 5万円~50万円 | 海や山に遺骨を撒く。法的な規制あり。 |
次に、親族に相談し、費用を分担してもらうという方法です。前述の通り、墓じまいは祭祀承継者だけでなく、親族全体に関わることでもあります。正直に経済状況を伝え、協力を仰ぐことで、解決の糸口が見つかるかもしれません。
また、自治体によっては、墓じまいに関する相談窓口を設けている場合もあります。直接的な補助金ではないかもしれませんが、情報提供や、低費用で利用できる公営の合祀墓などを紹介してもらえる可能性があります。諦めずに、まずは情報収集をすることが大切です。
さらに、墓じまいを専門とする業者に相談し、分割払いや費用に関する相談に乗ってもらうことも可能です。業者によっては、様々なプランを用意している場合もありますので、まずは問い合わせてみましょう。
私の知人で、本当に費用に困っていた方がいました。その方は、まずお寺に正直に事情を説明し、閉眼供養のお布施について相談したそうです。お寺も事情を理解してくださり、無理のない範囲で対応してくださったと喜んでいました。やはり、隠さずに相談することが第一歩ですね。
墓じまい補助金は利用できる?
墓じまいに際して「補助金」という言葉を耳にすることがありますが、残念ながら、国や地方自治体から直接的に「墓じまい補助金」として支給される制度は、現在のところほとんどありません。
しかし、全く支援がないわけではありません。一部の自治体では、公営の合祀墓や納骨堂への改葬を促進するため、その費用を比較的安価に設定している場合があります。これは直接的な補助金ではありませんが、結果的に墓じまい後の費用を抑えることにつながります。
例えば、東京都内の一部の区では、区民向けの合祀墓を提供しており、非常に低価格で利用できると聞きます。
補足:自治体の支援例
- 公営合祀墓の低価格提供
- 改葬手続きに関する情報提供
- 終活相談窓口の設置
また、墓じまいとは少し異なりますが、生活困窮者向けの葬儀費用補助など、間接的に関連する制度がある場合もあります。しかし、これらは墓じまいそのものに特化したものではないため、利用できるケースは限られます。
補助金という形で直接的な支援は期待薄ですが、費用を抑えるための選択肢はいくつか存在します。まずは、お住まいの自治体の窓口や、墓じまいを検討している墓地の所在地の自治体に問い合わせてみることをおすすめします。思わぬ回答が得られるかもしれません。
一人っ子墓じまい
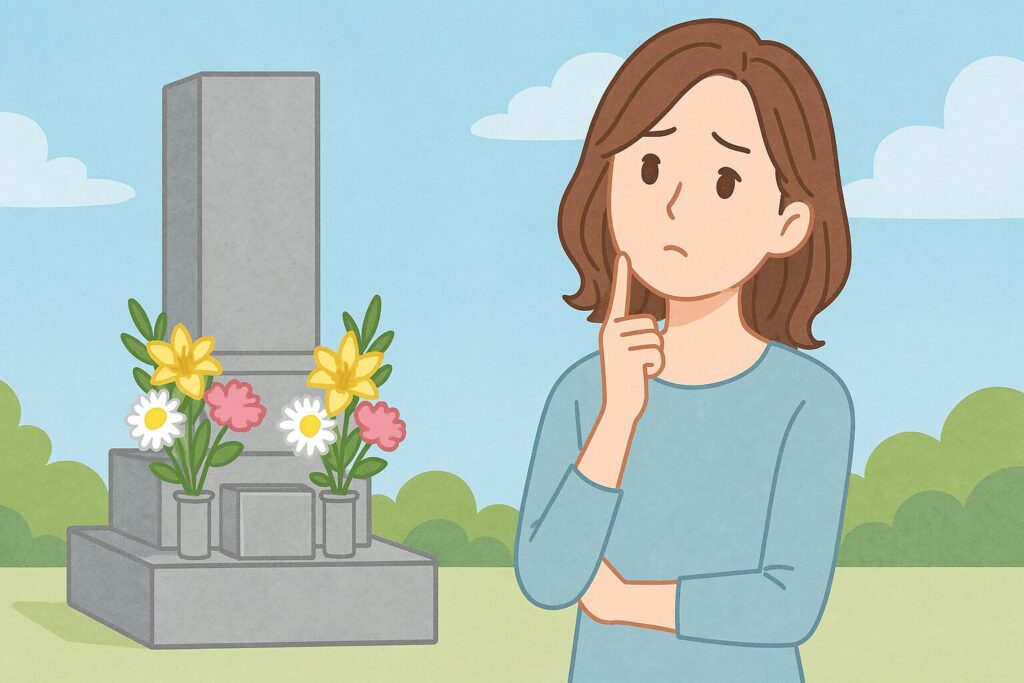
「一人っ子墓じまい」というキーワードで検索される方も多いことでしょう。一人っ子の場合、将来的に実家のお墓を継ぐのは自分一人、そしてその先にはお墓を継ぐ人がいないという状況に直面することがほとんどです。そのため、自分が元気なうちに墓じまいをして、子供や親族に負担をかけたくないという思いから、早めに検討される方が増えています。
一人っ子墓じまいのポイント
- ご両親との生前での話し合いが重要
- 親族への事前説明と理解を得る
- 墓じまい後の供養方法を検討する
私の知人で、まさに一人っ子で墓じまいをされた方がいます。彼女は、ご両親がまだご健在のうちから、将来のお墓のことで話し合いを始めたそうです。最初はご両親も寂しそうにされていたそうですが、彼女が「私が管理できなくなったら、誰もお墓を守ってくれなくなる。
だから、私が元気なうちに、きちんと供養の形を変えたい」と熱意を伝えたところ、最終的には理解を得ることができたそうです。そして、ご両親が亡くなった後、合同墓への改葬を選択し、無事に墓じまいを終えられました。
一人っ子の場合、親族の数が少ないため、話し合いの対象となる人が限られるというメリットもありますが、一方で、全ての手続きや費用の負担が自分一人にかかってくるという側面もあります。そのため、早めに情報収集を開始し、計画的に進めることが必要です。
特に重要なのは、ご両親がご健在であれば、生前にしっかりと話し合い、意向を確認しておくことです。ご両親の気持ちを尊重しつつ、現実的な選択肢を提示することで、納得のいく墓じまいができるでしょう。
また、もしご両親が亡くなっている場合でも、お墓に入っているご先祖様の血縁者(叔父や叔母など)がいる場合は、後々のトラブルを避けるためにも、事前に墓じまいの意向を伝えて理解を得ておくことが大切です。
墓じまい知恵袋で解決!まとめ
このブログ記事では、「墓じまい知恵袋」をテーマに、墓じまいに関する様々な疑問や不安について解説してきました。墓じまいは、ご先祖様への感謝の気持ちを大切にしつつ、現代のライフスタイルに合わせて供養の形を見直す、前向きな選択肢です。最後に、これまでの内容をまとめてみましょう。
- 墓じまいの総費用は50万円から200万円程度が目安
- 費用は墓石撤去、閉眼供養、離檀料、改葬費用などで構成される
- お盆やお彼岸など、お寺が忙しい時期は墓じまいを避けるのが望ましい
- 墓じまいをしないと管理費の滞納や無縁墓化のリスクがある
- お墓を放置することは、後々大きな手間と費用につながる
- 墓じまいをしても呪われることはなく、迷信である
- 墓じまいの費用は祭祀承継者が原則負担する
- 親族間で費用を分担することも可能である
- 費用が払えない場合は、安価な供養方法や親族への相談を検討する
- 国や自治体からの直接的な墓じまい補助金はほとんどない
- 一部自治体では公営合祀墓の低価格提供などがある
- 一人っ子の墓じまいは、生前の両親との話し合いが特に重要
- 親族への事前説明と理解を得ることがトラブル回避につながる
- 墓じまい後の供養方法には永代供養墓、樹木葬、散骨などがある
- 墓じまいは、ご先祖様を大切に思う気持ちから行う現代的な選択肢である
- 不安な点は専門家やお寺に相談し、情報収集をしっかり行うことが大切
墓じまいは、今こそ向き合うタイミング。
放置する前に、あなたにとって最適な選択肢を一緒に探しましょう。
参考
・50代シングルマザー老後の不安を減らす住まいとお金の話
・エンディングノート50代おすすめ特集|後悔しない選び方と活用術
・終活やりすぎに注意!家族が後悔しないための断捨離ルール
・エンディングノート40代おすすめ|失敗しない選び方と無料の始め方
・老後一人ぼっち女性の生活費と貯金目安をわかりやすく徹底解説
専門家やえさん

- 専門家やえさん
-
堀川 八重(ほりかわ やえ)
大阪不動産・FPサービス株式会社 代表
15年以上にわたり1,500組を超えるご家族の相続や不動産のお悩みに、専門家として寄り添ってまいりました。私の信条は、法律や数字の話をする前に、まずお客様ご家族の歴史や言葉にならない想いを丁寧に「聞く」こと。信頼できる各分野の専門家チームと共に、皆様が心から安心できる最善の道筋をオーダーメイドでご提案します。一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。
最新の投稿
 お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説
お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説 相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説
相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説 お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例
お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例 お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説
お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説






