わかります、3階建ての建売住宅って便利そうに見えて、つい「老後もこのままで大丈夫かな…」って不安になりますよね。
私の母も、定年を迎えた60代の頃から「エレベーターなし3階の老後はしんどいかも…」ってこぼすようになったんです。
特に「60歳過ぎたら2階で寝てはいけない」なんて聞くと、いよいよ現実味が増してくるもの。
「階段を登れなくなる年齢って、意外と早いのかも」って考えると、老後に階段が登れない生活をどうするか、真剣に検討したくなりますよね。
「3階建て老後建売って、売却しづらいってホント?」「老後にリフォームすれば解決するの?」なんて疑問も自然と湧いてきます。
この記事では、そんな「3階建て老後建売」にまつわる後悔や、リフォーム・売却・階段昇降機の選択肢などをわかりやすくまとめています。
このまま読み進めていただければ、きっと今の不安が少しずつ軽くなるはずです。
この記事のポイント
- 3階建て住宅が老後に与える生活への影響
- エレベーターなし住宅での階段問題と対策
- 老後に必要なリフォームや間取り変更の選択肢
- 3階建て建売住宅の売却の難しさとその理由
目次
3階建て老後建売で後悔しないために知るべきこと

何歳まで3階建てに住めるのか
「今は元気だけど、何歳まで3階建ての家に住めるのかな…?」
このように考える方は、とても多いと思います。
実は、3階建てに住める年齢の“限界”に明確なラインはありません。
ですが、一般的な目安としては70代前半までが1つの区切りとされています。
これは、体力・筋力・バランス感覚の低下が進む年齢と重なるためです。
年齢と階段の上り下りの負担感については、以下のデータが参考になります。
| 年齢 | 階段の上り下りを「つらい」と感じる人の割合 |
|---|---|
| 60代 | 約25% |
| 70代 | 約45% |
| 80代 | 約70% |
※厚生労働省「高齢期の生活実態調査」などを参考にした推定
こうしてみると、70代に入ると半数近くの人が階段を負担に感じているのがわかります。
特に3階建ての場合、階段が2フロア分あるため、日常の移動が想像以上に大変になる可能性があります。
ある60代の女性の方が、定年退職を機に3階建て住宅のリフォームを検討し始めました。
理由は「以前は当たり前にできていた3階のベランダへの移動が、息が切れるほど苦しくなったから」。
結局、その方は3階を完全に物置として使い、1階と2階だけで生活が完結するように間取りを変更したそうです。
このように、生活の中で階段を負担に感じた時点で、“住める年齢の限界”が来たと考えるのが現実的です。
さらに注意したいのは、突然の体調変化やケガによって一気に移動が難しくなる可能性がある点です。
骨折や膝の手術後に「もう2階以上には上がれない」と感じる方も多いです。
そのため、事前に「もしも」に備えた間取りや生活導線を整えておくことが重要です。
具体的には、次のような備えが有効です。
- 1階に寝室と水回りを集約する
- 2階リビングでもエレベーター設置の余地を確保する
- 階段に手すりを設置し、段差をゆるやかにする
- 将来的にリフォームができる構造の住宅を選ぶ
こうした配慮をしておけば、実年齢にかかわらず「自分にとって無理のない生活」が続けやすくなります。
それでも迷う場合は、体力があるうちに“やめる”か“備える”かを決めておくことが大切です。
次に、そもそも老後に3階建てを選ぶこと自体をやめた方がいいのか、その判断基準についてお話ししていきます。
老後は3階建てをやめた方がいいのか

このテーマは、多くの方が直面する悩みではないでしょうか。
老後に向けて住み替えや建て替えを検討している人にとって、「3階建てってやっぱりやめたほうがいいのかな…?」という不安はよくある声です。
答えを先にお伝えするなら、老後の暮らしやすさを最優先にするのであれば、3階建ては“慎重に検討すべき住宅タイプ”だと言えます。
その理由は大きく分けて3つあります。
- 階段の移動が必須な構造
- 間取りによっては生活がバラバラになりやすい
- 後からのリフォームに高額な費用がかかる
これらの要素が、**老後の「安全性」「快適性」「経済性」を圧迫してしまう可能性があるのです。
以下に3階建てとそれ以外の選択肢の比較を表にまとめました。
| 住宅タイプ | 老後の生活しやすさ | 改修のしやすさ | 移動の負担 | 費用面の柔軟性 |
|---|---|---|---|---|
| 平屋 | 非常に高い | 高い | 少ない | リフォーム費用も抑えやすい |
| 2階建て | 高い | 中程度 | 中程度 | ある程度柔軟 |
| 3階建て | 低め | 低い | 大きい | 改修やエレベーター設置が高額 |
実際、私の知人(70代・男性)は定年後も3階建てに住み続けていましたが、膝の痛みが出てからは「2階リビングに行くのも苦痛」と言い出し、最終的には中古の平屋に住み替える決断をされました。
その際、住宅ローンの残債や引っ越し費用もあり、トータルで約600万円以上の追加費用がかかったそうです。
「最初から平屋を選んでおけば…」と、後悔をにじませていたのが印象的でした。
ただし、必ずしも3階建てが悪いというわけではありません。
以下のような条件が揃っている場合には、老後でも無理なく3階建てに住む可能性はあります。
- ホームエレベーターを設置している
- 1階と2階だけで生活が完結する間取りにしている
- 若い家族と同居し、3階を任せられる
- 老後も体力維持に積極的な生活をしている
つまり、間取りと設備、そして生活スタイル次第で、3階建てを“選んでもいい”老後もあるということです。
ただ、これにはある程度の準備や予算が必要になります。
だからこそ、「やめた方がいいのか?」という問いに対しては、今後のライフプランと身体状況の変化を想定したうえで、“自分の未来に合っているかどうか”を判断することが何よりも大切です。
では次に、その判断のひとつでもある「老後に3階建てをリフォームして住み続ける」ことの可能性について見ていきましょう。
エレベーターなし3階は老後にしんどい
老後の生活において、エレベーターがない3階建て住宅は、想像以上にしんどい場面が増えていきます。
体力があるうちは「階段もいい運動になるし大丈夫」と思っていても、年齢とともに膝や腰への負担が増し、“日常の移動そのものがストレス”に変わってしまう可能性があるんです。
例えば、私の近所に住む70代のご夫婦は、若い頃に3階建て住宅を新築され、当初は「広さがあって快適」と喜んでいました。
でも、70歳を過ぎたあたりからご主人が階段の上り下りを苦にするようになり、「3階には1年以上行っていない」と笑って話されていたんです。
それが冗談では済まなくなったのは、ご主人が心臓の持病で入退院を繰り返すようになってから。
介護ベッドの搬入やトイレ・浴室の動線に問題が生じ、結局1階のリビングを寝室に変える大がかりな間取り変更と簡易トイレの設置を行うことになりました。
このように、エレベーターがない3階建てでは、老後の急な体調変化に対応しにくい構造的な課題がつきまとうのです。
さらに、以下のような問題も見逃せません。
| 問題点 | 具体的な影響例 |
|---|---|
| 食事や洗濯のたびに階段移動が必要 | 食材の買い物後、重たい荷物を3階まで運ぶのが大変 |
| 暑い日・寒い日でも上下階の移動が避けられない | 高齢者にとって温度差は体調悪化のリスク |
| 来客や宅配応対で何度も階段を使う必要がある | 階段移動が面倒になり、家にこもりがちになる可能性も |
特に3階を寝室にしているご家庭では、夜間にトイレに行くたびに階段を下りなければならないという不安定な生活になりがちです。
夜の転倒は骨折や入院につながる重大リスク。
住宅そのものが老後の“安心な暮らし”を妨げてしまう構造になってしまうのは避けたいところですよね。
このような事態を回避するためには、以下のような対策を早めに検討しておくことが重要です。
- ホームエレベーターの設置を見越したスペースを設ける
- 1階に寝室・トイレ・浴室を集約した間取りに変更する
- 将来、介護用設備を導入できるような建物構造を選ぶ
老後の生活を見据えると、「住める」ではなく「安心して住み続けられるかどうか」が重要な視点です。
そしてこの問題は、実際に階段の上り下りが難しくなる「年齢の目安」を知ることで、より具体的に想像しやすくなります。
老後に階段を登れなくなる年齢の目安

階段を登れなくなるタイミングは人によって異なりますが、一般的には70代前半から負担を感じ始める方が増えてきます。
実際、こんな調査結果があります。
| 年齢層 | 「階段の昇降がつらい」と感じている割合(推定) |
|---|---|
| 60代前半 | 約25% |
| 60代後半 | 約38% |
| 70代 | 約50% |
| 80代以上 | 約70% |
この表からもわかるように、70代になると約半数の方が階段の移動に不安を抱えている状況です。
それでも、「自分は元気だし関係ない」と思ってしまうのが人の常ですよね。
でも、実際に私の伯母(68歳)も「まだまだ大丈夫」と言いながら3階建ての家に住み続けていたのですが、ある日、足を踏み外して階段から落ちて骨折。
それをきっかけに「老後の間取りを甘く見ていた」と深く反省し、1階リビングの間仕切りを外して寝室を新設しました。
骨折や脳梗塞などの突然の出来事は、これまで当たり前だった階段の上り下りを不可能にしてしまう可能性があります。
そのため、以下のような事前準備をおすすめします。
- 65歳を過ぎたら、1階だけで生活できる動線にしておく
- 間取り変更やリフォームを視野に入れた建物を検討する
- 階段に滑り止めや手すりを設置する
ちなみに、「階段昇降の安全度」は以下のように変化します。
| 加齢段階 | 階段昇降の安定性 | 転倒リスク | 対策の必要性 |
|---|---|---|---|
| 60歳前後 | 安定している | 低い | 軽い運動・安全対策を意識 |
| 65~74歳 | やや不安定 | 中程度 | 手すり・明るさ確保 |
| 75歳以上 | 不安定になりやすい | 高い | 間取り見直し・介護設備の検討 |
このように見ていくと、階段に不安を覚え始める“予備軍”の段階から備えることがとても大切だとわかります。
まだ元気なうちにこそ、「もしも」のときのことを考えて、住宅や生活スタイルを見直しておくと安心ですね。
次はその「備え方」のひとつとして注目される、階段昇降機について詳しく見ていきましょう。
階段昇降機の導入コストと注意点
老後の3階建て住宅での生活を安全に続けるために、階段昇降機の導入は現実的な選択肢のひとつです。
特に階段の上り下りに不安を感じはじめた段階で検討することで、転倒リスクの回避や生活の質の向上につながります。
ただし、導入にはコストもかかりますし、設置に向かない住宅構造もあるため、事前の確認がとても大切なんです。
私の知人(70代の女性)も、2階建て住宅に昇降機を設置したのですが、設置費用が想定より高くて驚いたそうです。
もともと「20〜30万円くらいでつけられるでしょ?」と思っていたら、実際には工事費込みで約110万円かかったとのこと。
しかも階段幅が狭かったため、既製品では対応できず、カスタム対応で費用が上がってしまったのだとか…。
このように、階段昇降機の導入にはある程度の資金と事前知識が必要になります。
そこでまずは、導入コストの相場を確認しておきましょう。
| 種類 | 特徴 | 費用の目安(設置費込) |
|---|---|---|
| 直線型 | 真っすぐな階段に設置しやすい | 約40〜80万円 |
| 曲線型(L字・U字) | 複雑な間取りや曲がり角のある階段用 | 約100〜200万円以上 |
| 屋外用 | 玄関階段など屋外向け | 約60〜120万円 |
さらに費用を左右するポイントは次のとおりです。
- 階段の形状(曲がり角や踊り場があると高額に)
- 階段の長さや角度(距離が長いと費用アップ)
- 電源の位置(工事の必要がある場合追加費用)
- 建物の構造(設置できない住宅もあり)
導入前には、「設置できるかどうか」も含めて現地調査を依頼するのが鉄則です。
メーカーや販売店の中には、無料で下見と見積もりをしてくれるところもあるので、複数社に相談することをおすすめします。
では、実際に階段昇降機を導入した場合、どのような点に注意が必要なのでしょうか。
階段昇降機の注意点まとめ
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 設置できない場合がある | 階段幅が狭すぎたり、構造上取り付けられないことがある |
| 電源工事が必要なケースがある | コンセントの位置によっては別途工事費が発生 |
| 座席部分が場所を取ることがある | 昇降機のレールや椅子が階段の一部を占有し、家族の生活動線に支障が出る可能性も |
| 故障リスクとメンテナンスの必要性 | 電動機械のため定期点検が必要。保証期間を確認し、メンテナンス費用も考慮しておくべき |
| 介護保険制度の対象外になることもある | 昇降機のタイプや設置条件によっては補助金や介護保険対象外になることがあるので、自治体に事前確認が必要 |
こうして見ると、階段昇降機は非常に便利な設備ではありますが、導入するための“ハードル”も決して低くはありません。
導入を検討しているなら、早い段階から住宅の間取りや建物構造を確認し、必要に応じてリフォームを視野に入れることがポイントです。
また、今後の生活全体の設計として、昇降機の有無だけでなく「3階部分をどう使うか」も含めて見直すタイミングになるかもしれません。
次に、将来的に3階部分をどう活用していくか、また老後に住み替えを選ぶべきケースについても考えてみましょう。
3階建て老後建売を選ぶ前に考えるべき視点

老後に3階建てをリフォームする選択肢
老後も3階建て住宅に住み続けたいと考えるなら、生活スタイルの変化にあわせたリフォームは避けて通れません。
特に「階段がつらくなってきた」「2階以上の部屋が空き部屋になっている」という声は、60代以降の方からよく聞かれます。
私の母もそうだったのですが、70歳を過ぎたころから2階にある寝室まで上がるのが億劫になり、1階にベッドを置くようになりました。
それでも洗濯物を干すためには3階まで上がらなくてはいけない構造だったので、少しずつ生活全体が負担になっていったんですね。
このような現実をふまえ、老後に3階建て住宅をどう活用していくかを真剣に検討することが大切です。
そこで有力な選択肢になるのが、部分的なリフォームです。
以下のような内容が、老後に多くの人が選んでいるリフォームの一例です。
| リフォーム内容 | 目的・効果 | 予算目安(目安) |
|---|---|---|
| 1階への生活空間集約 | 1階に寝室・トイレ・浴室を集約することで階段の昇降を最小限に | 約100〜300万円 |
| 階段の手すりや滑り止め設置 | 転倒予防と安全性アップ | 約10〜20万円 |
| トイレ・洗面のバリアフリー化 | 段差の解消や引き戸化によって身体負担を軽減 | 約30〜100万円 |
| キッチン・浴室の高齢者対応 | 掴みやすい取手や温度制御、転倒防止マットなどの導入 | 約50〜150万円 |
| 空き部屋の賃貸用改修 | 使わなくなった上階を賃貸に回して収入源に(※法的制限あり) | 約100〜500万円 |
たとえば、私の友人のご両親は、3階建ての家に長年住んでいたのですが、70代に入ったタイミングで1階に生活空間を集めるリフォームを実施しました。
元々の間取りは1階が駐車場と玄関ホールだけで、生活スペースは2階が中心だったのですが、
和室をフローリングに改修+シャワートイレの増設+簡易キッチン設置という形で、生活がすべて1階で完結できるようになったそうです。
「これで3階まで上ることが無くなって本当に楽になった」とのこと。
このように、生活の中心を1階に移すリフォームは、身体の衰えを感じ始めた頃にぴったりなんです。
もちろん、建物の構造によっては大規模な工事が必要な場合もあるため、複数のリフォーム業者に見積もりを取って比較検討することが重要です。
さらに、使わない3階をどうするかも含めたプランニングも必要ですね。
ここで気になるのが、次の話題につながる「売却しやすさ」の問題です。
3階建ての家は老後に売却しづらい?
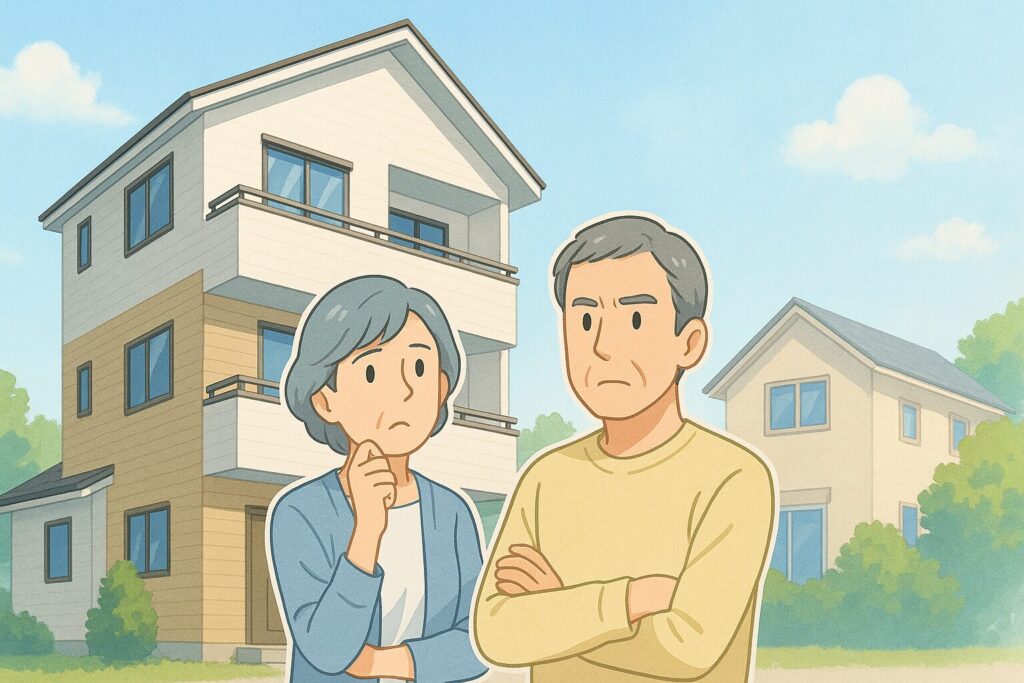
実際のところ、3階建て住宅は老後に売却しようと思っても、なかなか思い通りに売れないケースが多いです。
これは単に建物の築年数や場所の問題だけではなく、3階建てという構造自体が“ネック”になりやすいからです。
とくにエレベーターなしの3階建ての場合、買い手が限られてしまうというのが大きなポイントなんです。
以下は、3階建て住宅の売却における「売りにくさ」の要因を表にまとめたものです。
| 売却しづらい理由 | 内容 |
|---|---|
| 階段の昇降がネック | 高齢者世帯や子育て世帯からは敬遠されがち |
| 間取りが縦長・狭小なケースが多い | ファミリー層が求める広さ・動線と合わないことがある |
| 住宅ローン控除の対象外もある | 建築時の条件によって減税対象から外れることがあり、買主に敬遠される |
| 立地が旗竿地などのケースも多い | 土地形状が特殊だと評価額が下がる |
実際、不動産会社に勤めていた知人は、「3階建ては新築時は需要あるけど、中古になると動きが鈍い」と話していました。
特に築20年以上で階段が急なタイプの物件は、内覧者が来てもほぼ決まらないことも多いそうです。
では、どうすればスムーズな売却につながるのでしょうか?
以下のような対応が、3階建て住宅の売却を現実的に進めるための対策になります。
- 1階に生活スペースを集約しておく(内覧時の印象が良くなる)
- リフォーム済みであれば、広告でアピール
- 空き部屋の活用プラン(賃貸・民泊)を提案できる状態にしておく
- エレベーターの設置が難しい場合は、階段昇降機の導入実績を強みにする
このように、「売れにくい」イメージを持たれがちな3階建て住宅も、工夫次第で売却の可能性を高めることは十分に可能です。
そのためにも、リフォームと売却プランは並行して考えることが、老後の安心につながりますね。
次は、実際に「3階建てを手放すべきタイミング」や「老後の住み替え選択肢」について、詳しく見ていきましょう。
60歳過ぎたら2階で寝てはいけない?
一見すると少し極端に聞こえるかもしれませんが、**「60歳を過ぎたら2階で寝ない方がいい」**という考えには、しっかりとした理由があるんです。
特に3階建て住宅や階段の多い建物で暮らしていると、毎日の上り下りがじわじわと体に負担をかけてしまいます。
これは私の叔母(当時63歳)の話ですが、2階の寝室で暮らしていたある日、夜中にトイレへ行こうとして階段を踏み外し、腰椎を骨折してしまいました。
その後はリハビリ生活になり、「もう2階には戻らない」と言って、リビング横の和室にベッドを設置することになったんです。
こうした話は、年齢とともに筋力やバランス感覚が低下することが大きな要因になっています。
以下のような身体機能の変化が、60代を境に起こりやすいとされています:
| 年齢 | 筋力低下率(目安) | バランス感覚 | 階段事故リスク |
|---|---|---|---|
| 50代 | -10% | まだ安定 | 中 |
| 60代 | -20〜30% | 低下し始める | 高 |
| 70代 | -40%以上 | 明らかに低下 | 非常に高 |
このように、60歳以降は夜間の移動にリスクが増える年代なんですね。
もし3階建ての住宅で、主寝室が2階や3階にある場合は、次のような選択肢を検討してみてもよいと思います:
- 1階にベッドを置けるスペースを確保する
- リフォームで1階に寝室を設置する
- トイレの近くに寝る間取りに変える
どれも生活の質を落とさずに安全な暮らしを維持するために必要な対策です。
このように、老後の安全性を考えると、「もう少し早い段階から寝室の場所を見直す」ことがとても大切になってきます。
この流れで、次に気になるのは「階段そのものの危険性」ですよね。
老後の階段昇降が危険な理由
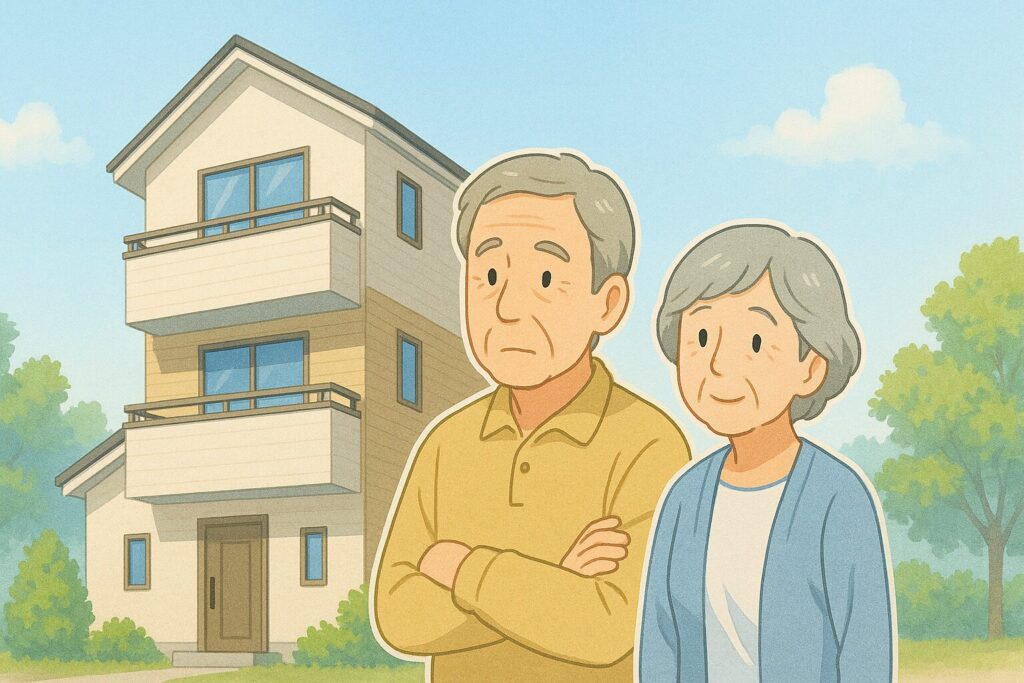
老後における階段の昇り降りが危険になる理由は、単に体力や筋力の問題だけではありません。
実は、脳や神経の反応速度の低下、視力の変化、深夜のトイレ移動など複数の要素が重なることで、事故の可能性が一気に高まるんです。
私の祖父(当時78歳)は、夜に寝ぼけながら階段を降りようとして、最後の1段を踏み外し、手首を骨折してしまいました。
今でも母は「たった1段だったのに…」とよく話しています。
このように、ほんの少しの油断が大きな事故につながるのが、老後の住宅生活なんですね。
以下に、階段昇降時に起きやすい老後の事故リスクを整理しました。
| リスクの原因 | 具体的な影響 | 起きやすい時間帯 |
|---|---|---|
| 視力の低下 | 段差の認識が甘くなる | 夜間・早朝 |
| 筋力の低下 | 足が上がらずつまずく | 階段昇降時 |
| 神経伝達の遅れ | バランスを崩しても反応が遅い | 不意の転倒時 |
| 不十分な手すり設置 | 支えがなく不安定なまま移動してしまう | 階段全般 |
また、3階建て住宅の場合はこのリスクがさらに倍増します。
特に「寝室が2階」「洗濯物干しが3階」「浴室が1階」といった縦動線の多い間取りでは、階段の往復回数も多くなるため、疲れやすくなりますし、日常的な転倒リスクも増えてしまいます。
そのため、階段昇降機の設置や、1階だけで生活が完結するようなリフォームの検討も必要になってきます。
階段を昇ることが日々の運動になるという意見もありますが、その前に「安全であること」が大前提なんです。
そう考えると、3階建て住宅に暮らす場合、どのような間取りが老後に向いているか、しっかり考えておきたいですよね。
このあとご紹介する「老後に安心できる間取りの工夫」では、具体的な住宅設計の工夫についてお話ししていきます。
安心して暮らすための間取りの工夫
老後の生活を見据えたとき、「安心して暮らせる間取りかどうか」はとても大切なポイントになりますよね。
特に3階建ての住宅にお住まいの方や、これから購入やリフォームを検討されている方にとっては、「今は便利だけど、将来もこのままで大丈夫かな?」と不安になることがあると思います。
私の実家も3階建ての建物で、親が70代になった今、階段の昇り降りが負担になってきたとよく話しています。
そこで私たちは間取りの工夫によって、老後の安心を確保することに力を入れました。
具体的にどんな工夫が効果的だったのか、実際の事例とともにご紹介していきますね。
✅ 1階で「生活が完結する」動線を作る
老後の生活で一番のカギになるのは、1階だけで日常が完結できるかどうかです。
以下のような動線が1階にあると、かなり楽になります。
- リビング
- 寝室(または和室をベッドルーム代わりに)
- トイレ
- 洗面所・お風呂
- キッチン
このように必要な設備を1階にまとめることで、階段の昇降を最小限に抑えることができます。
✅ 「将来の変化」に対応できる柔軟な間取りを
今は元気でも、将来、車いすや歩行器が必要になる可能性もゼロではありません。
そのため、ドアの幅を広めにする(80cm以上)、段差をなくすフラット設計にするなど、ちょっとした配慮が将来の快適さを左右します。
また、洋室を和室に変えられるようにしておくなど、可変性のある設計もおすすめです。
✅ 配置にゆとりを持たせた「階段」設計
階段はどうしても必要な構造になりますが、段数が急だったり、手すりがなかったりすると事故のリスクが高くなります。
なので、
- 階段は勾配をゆるやかに(蹴上17cm以下、踏面25cm以上)
- 両側に手すりを設置
- 足元を照らす足元灯やセンサーライトを設ける
などの工夫があると、かなり安心できます。
ちなみに、私の知り合いのご夫婦(60代)はこの工夫をしなかったことで、夜間の転倒がきっかけで骨折という苦い経験をされていました。
✅ よく使う場所を「水平移動」で行けるようにする
年を重ねると、上下移動よりも横の移動(水平移動)のほうが圧倒的に楽になります。
なので、
- キッチン→ダイニング→リビング→トイレが一直線に並んでいる
- 洗面所からお風呂、脱衣所までがワンルーム感覚
こうした水平動線の工夫をすることで、移動のストレスをぐっと減らせます。
✅ 具体例:安心な間取りイメージ(1階完結型)
| 設置設備 | 推奨する場所 | 備考 |
|---|---|---|
| トイレ | リビング近く | 夜間移動が少なくて安心 |
| 寝室 | 和室や洋室 | 将来ベッドが入る広さ必須 |
| お風呂 | キッチン近く | 介助しやすい広さが◎ |
| キッチン | 寝室と同フロア | 夜食や薬準備に便利 |
| リビング | 中央配置 | 家族との交流を保ちやすい |
このような間取りにすると、「老後になっても、家の中が安心・安全な場所」として暮らし続けられます。
3階建て老後建売で後悔しないための重要ポイントまとめ
- 3階建て住宅は老後の体力低下に備えて慎重に選ぶべき
- エレベーターなしの3階は将来的にしんどくなる可能性が高い
- 60歳を過ぎたら2階以上での寝室利用は避けた方が安全
- 階段の上り下りが難しくなる年齢は平均75歳前後
- 階段昇降機の設置費用は高額で構造次第で設置できないこともある
- 老後にリフォームするなら1階で生活が完結する間取りが理想
- 3階建ての売却は高齢者や家族層にとって不人気傾向がある
- バリアフリー設計がされていない3階建ては資産価値が下がりやすい
- 若い頃は便利でも老後の生活動線に課題が残る建物が多い
- 老後の暮らしでは階段の位置や数が負担になることがある
- トイレや浴室は1階に設置するだけで生活負担を軽減できる
- 住宅設備の見直しで快適性を維持できる可能性はある
- 家族構成の変化に対応できる柔軟な間取りであることが望ましい
- 将来的な賃貸や売却を検討するなら立地と設計の汎用性が重要
- 3階建て老後建売は「今の快適さ」だけで判断しないことが大切
参考
・50代シングルマザー老後の不安を減らす住まいとお金の話
・エンディングノート50代おすすめ特集|後悔しない選び方と活用術
・終活やりすぎに注意!家族が後悔しないための断捨離ルール
・エンディングノート40代おすすめ|失敗しない選び方と無料の始め方
・老後一人ぼっち女性の生活費と貯金目安をわかりやすく徹底解説

お気軽にご相談ください
相続は100人いれば、100通り
唯一無二の最適な相続をご提案いたします
CONTACT
専門家やえさん

- 専門家やえさん
-
堀川 八重(ほりかわ やえ)
大阪不動産・FPサービス株式会社 代表
15年以上にわたり1,500組を超えるご家族の相続や不動産のお悩みに、専門家として寄り添ってまいりました。私の信条は、法律や数字の話をする前に、まずお客様ご家族の歴史や言葉にならない想いを丁寧に「聞く」こと。信頼できる各分野の専門家チームと共に、皆様が心から安心できる最善の道筋をオーダーメイドでご提案します。一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。
最新の投稿
 お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説
お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説 相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説
相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説 お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例
お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例 お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説
お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説






