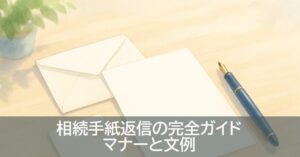「相続放棄手続き自分で知恵袋」で検索して、親の借金があって相続放棄したいけど、自分でやるのは難しいかな?と悩んでいませんか? こんにちは、終活・相続・不動産相続の専門家、やえです。
結論から言うと、相続放棄の手続きは、ポイントさえ押さえればご自分でも十分可能ですよ。ただし、相続放棄の前にやってはいけないことをしてしまうと、相続放棄が認められない事例になることも…。
それに、相続放棄の申立て方法を自分で調べても、相続放棄の戸籍謄本など必要書類集めに戸惑う方も多いんです。
この記事では、「相続放棄とは?」を簡単に説明し、相続放棄の手続きを自分で行うための必要書類、相続放棄申述書の書き方、相続放棄にかかる費用、そして「相続放棄できない?」と知恵袋でよく見る疑問(相続放棄 司法書士 費用や相続放棄 弁護士 相談の目安)まで、まるっと解説しますね。
この記事のポイント
- 自分で相続放棄する具体的な手順
- 相続放棄に必要な書類と費用
- 相続放棄が認められなくなるNG行動
- 専門家に依頼するかの判断基準

相続放棄は「知らなかった」では済まされない、大切な手続きです。
特に期限が厳しいので、この記事を読んだらすぐに「自分はどの状況か」を確認するのが最初のステップですよ。大丈夫、一つずつクリアしていきましょうね!
目次
相続放棄手続き自分で知恵袋で学ぶ基本

相続放棄とは簡単に説明
こんにちは!やえです。まず「相続放棄」について、簡単に説明しますね。
相続が始まると、私たち相続人には基本的に3つの選択肢があります。「①単純承認(すべて相続する)」「②限定承認(プラスの財産の範囲でマイナスを相続する)」「③相続放棄」です。
この中で「相続放棄」とは、亡くなった方(被相続人)のプラスの財産(預貯金や不動産など)も、マイナスの財産(借金や未払金など)も、一切合切受け継ぎません!と法的に宣言することです。「この不動産だけ欲しいけど、借金はいらない」といった、一部だけの相続放棄は認められません。
「どう考えても借金の方がプラスの財産より多い…」「相続トラブルに関わりたくない」という状況で、家庭裁判所に「私は相続人じゃなかったことにしてください」と正式に申し立てる。これが相続放棄の手続きなんです。
この申立てが家庭裁判所に受理されると、その人は「初めから相続人ではなかった」ものとして扱われます。これがとても重要で、借金を返済する法的な義務が一切なくなるということなんですね。その代わり、もし後から高額な財産が見つかっても、もちろん相続することはできません。
ちなみに「限定承認」って?
「限定承認」は、亡くなった方のプラスの財産の範囲内でだけ、借金などのマイナスの財産を引き継ぐ方法です。借金がいくらあるか不明だけど、家など手放したくない財産がある場合に有効ですが、手続きが非常に複雑で、相続人全員で申立てる必要があるため、実際にはあまり利用されていないのが現状です。
相続放棄の申立て件数は増加傾向
裁判所の司法統計によると、相続放棄(「相続の放棄の申述」)が受理された件数は年々増加傾向にあります。2022年(令和4年)には、全国の家庭裁判所で受理された件数は260,497件に上り、過去最多となりました。
これは、社会的な関心の高まりや、管理が難しい空き家問題なども背景にあると考えられています。
親の借金と相続放棄の関係

親御さんが借金を残して亡くなった場合、相続放棄は非常に有効な、そして最もよく検討される手段となります。
なぜなら、前述の通り、相続はプラスの財産だけでなく借金というマイナスの財産も引き継いでしまうからです。この「借金」には、消費者金融からの借り入れや住宅ローンなどはもちろん、「連帯保証人」としての地位(義務)も含まれます。
親御さんが誰かの連帯保証人になっていた場合、その返済義務まで相続してしまう可能性があるんです。
もし相続財産を調査してみて(例えば、信用情報機関へ情報開示請求をしてみたり、自宅に届く郵便物を確認したりして)、明らかに借金が多い、あるいは連帯保証債務があることが判明した状況なら、相続放棄を速やかに検討するのが一般的です。
故人の借金(信用情報)を調べる方法
故人(被相続人)がどこから借金をしていたか分からない場合、相続人は「指定信用情報機関」に情報開示を請求することができます。日本には以下の3つの機関があり、金融機関は必ずいずれか(または複数)に加盟しています。
- CIC(株式会社シー・アイ・シー):主にクレジットカード会社、信販会社系
- JICC(株式会社日本信用情報機構):主に消費者金融会社系
- KSC(全国銀行個人信用情報センター):主に銀行系
相続人であることが証明できる戸籍謄本など所定の書類を揃えて申請することで、故人の借入残高や契約状況などを確認できる場合があります。相続放棄の判断材料として非常に重要です。
ただし、ここで最大の注意点があります。相続放棄には期限があり、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立てをしなければなりません。
この「知った時」とは、多くの場合「故人の死亡を知り、かつ、それによって自分が相続人になったことを知った日」を指します。この3ヶ月という期間は「熟慮期間」と呼ばれますが、葬儀や法要などで慌ただしくしていると、本当にあっという間に過ぎてしまいます。判断はスピーディーに行う必要がありますよ。
相続放棄は自分で難しい?
「相続放棄の手続きって、自分でやるのは難しいですか?」というご質問、本当によくいただきます。
結論としては、ご自身での手続きは可能です。実際に多くの方が、費用を抑えるためにご自身で手続きをされています。ですが、決して「誰でも簡単にできる」とは言えないのが実情ですね。
ご自身でやる場合のメリットは、なんといっても専門家への報酬(数万円)がかからず、実費だけで済むことです。一方、デメリットは「手間」と「期限切れのリスク」です。
難しいと感じるポイントは、主に2つあります。
- 期限が厳しい(原則3ヶ月)
仕事や日々の生活、さらに葬儀後の諸手続き(役所関係、公共料金の名義変更など)に追われながら、期限内に必要書類を完璧に揃えて提出するのは、想像以上に慌ただしいものです。 - 集めるべき戸籍謄本類が複雑
ご自身の戸籍謄本だけでは足りません。亡くなった方の戸籍謄本も必要で、本籍地が遠方の場合は郵送で請求する手間がかかります。昔の戸籍は手書きで読みにくかったり、市町村合併で管轄が変わっていたりすることも。特に相続人が兄弟姉妹(第3順位)の場合などは、亡くなった方の「出生から死亡まで」の全ての戸籍を集める必要があり、これが非常に手間と時間がかかるんです。
この「時間的・手続き的なコスト」と「専門家費用のコスト」を天秤にかけて、ご自身の状況(期限までの残り日数、集める戸籍の複雑さ、ご自身の時間的余裕)で判断するのが良いと思いますよ。
相続放棄ができない?知恵袋の疑問

知恵袋などのQ&Aサイトを見ていると、「相続放棄ができないと聞いた」「相続放棄に失敗した」という書き込みを見かけることがありますね。これは本当に不安になると思います。
相続放棄が認められない(受理されない)のには、いくつかの典型的な原因が考えられます。
一番多いのは、やはりうっかり相続財産に手をつけてしまう「法定単純承認」とみなされる行為をしてしまった場合です。「故人の預金を少し引き出してしまった」などで、放棄が認められなくなるケースですね。(これについては、後の見出しで詳しく解説しますね!)
また、前述の通り、期限の3ヶ月を過ぎてしまった場合も、原則として相続放棄は認められません。家庭裁判所は期限に厳格です。「知らなかった」「忙しかった」という理由だけでは、残念ながら通用しにくいのが現実です。
知恵袋では「一度受理された相続放棄は取り消せますか?」という質問も見かけますが、一度正式に受理された相続放棄は、原則として取り消すことができません。後から「やっぱり財産があったから相続したい」と思ってもダメなんです。だからこそ、最初の3ヶ月での判断がとても重要になります。
「知らなかった」は通用しにくいのが現実です。ただし、故人とは長年疎遠で、死亡の事実や借金があることを3ヶ月経過後に初めて知った(例:債権者からの督促状で知った)など、正当な事情がある場合は、期限後でも認められる可能性があります。諦める前に、すぐに専門家に相談してください。
相続放棄の手続きを自分でする必要書類
ご自身で相続放棄の手続きをする場合、家庭裁判所に提出するメインの必要書類は、大きく分けて2種類です。
- 相続放棄申述書
- 戸籍謄本類
この他に、手続き費用として「収入印紙(800円分)」と「連絡用の郵便切手(数百円分)」も必要になります。
「相続放棄申述書」は、手続きの申請書本体です。これは、裁判所ウェブサイトの「家事審判の申立書」ページから書式(ExcelやPDF)をダウンロードできますし、もちろん裁判所の窓口で直接もらうことも可能です。
問題は、2つ目の「戸籍謄本類」です。これは、申立てをする人(申述人)が、亡くなった方(被相続人)の法的な相続人であることを証明するために必須の書類です。
この戸籍謄本類が、亡くなった方と申立てをするあなたの関係性(あなたが子なのか、親なのか、兄弟姉妹なのか)によって、集めるべき範囲がガラッと変わってきます。これが、ご自身で手続きする際の最初のハードルになることが多いんです。
相続放棄の戸籍謄本など必要書類

では、具体的にどのような戸籍謄本が必要になるのか、相続順位別に見ていきましょう。これは非常に重要なので、しっかり確認してくださいね。
| 申述人(あなた)の立場 | 主な必要書類 |
|---|---|
| 配偶者 | 被相続人(亡くなった方)の死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本 被相続人の住民票除票(または戸籍附票) 申述人(あなた)の現在の戸籍謄本 |
| 子(第1順位) ※子が先に死亡し孫(代襲相続人)が申述する場合も同様 | (配偶者と同じ書類一式) ※孫(代襲相続人)の場合:子の死亡の記載がある戸籍謄本 |
| 親(第2順位) (子や孫が全員死亡または相続放棄した場合) | (配偶者と同じ書類一式) 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 子や孫(被代襲者)の死亡の記載がある戸籍謄本 |
| 兄弟姉妹(第3順位) (第1・第2順位が全員死亡または相続放棄した場合) | (配偶者と同じ書類一式) 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 子や孫(被代襲者)の死亡の記載がある戸籍謄本 被相続人の直系尊属(父母や祖父母)の死亡の記載がある戸籍謄本 |
いかがでしょうか? 配偶者や子(第1順位)の場合は、比較的シンプルです。しかし、相続権が第2順位(親)、第3順位(兄弟姉妹)に移ると、「前の順位の相続人がいない(または全員相続放棄した)こと」を戸籍で証明しなければならないため、集める書類が一気に増えるんです。
特に大変! 兄弟姉妹(第3順位)の場合
上記の表にある「被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本」というのが、一番の難関です。人は婚姻や転籍(本籍地を移すこと)で戸籍が新しく作られます。そのため、亡くなった方の現在の戸籍(除籍謄本)だけでは足りず、その一つ前の戸籍、さらにその前の戸籍…と、出生時の戸籍まで遡って全て取得する必要があるんです。
昔の戸籍は手書きで読みにくかったり、本籍地が全国に点在していたりすると、全ての役所に郵送で請求をかけることになり、全部集めるのに1ヶ月以上かかることも珍しくありません。3ヶ月の期限がある中でこれを行うのは、本当に大変な作業になります。
相続放棄申述書
「相続放棄申述書」は、手続きのキモとなるメインの書類です。これは家庭裁判所に「私は相続放棄します」と正式に申し立てるための用紙ですね。A4サイズで、通常は表裏の2ページ構成になっています。
記入する項目は主に以下の通りです。
- 申立て先の家庭裁判所名
- 申立てをした日付
- 申述人(あなた)の本籍、住所、氏名、生年月日など
- 法定代理人(もし申述人が未成年者などの場合)の情報
- 被相続人(亡くなった方)の本籍、最後の住所、氏名、死亡日など
- 申述の趣旨:「相続を放棄します」という宣言(定型文)
- 相続の開始を知った日:非常に重要! 期限(3ヶ月)の起算日になります。
- 放棄の理由:選択式(生活が困難、債務超過など)
- 相続財産の概要:把握している範囲で記入(不明なら「不明」でも可)
記入自体はそこまで難しいものではなく、多くは戸籍謄本や住民票除票を見ながら書き写す作業になります。「相続の開始を知った日」は、ご自身の記憶に基づき正確に記入してください。
「放棄の理由」の書き方
記入欄は選択式になっていることが多いです(例:「被相続人から生前に贈与を受けている」「生活が困難」「債務超過」「その他」)。ご自身の状況に最も近いものを選べば大丈夫です。「債務超過」が理由ならそれを選び、「その他」の場合は「遺産分割に関わりたくないため」などと簡潔に記載すれば問題ありません。
前述の通り、裁判所のホームページに記入例もありますので、ぜひ参考にしながら作成してくださいね。
もし、申立てをするあなたが未成年者や成年被後見人である場合は、ご本人ではなく法定代理人(親権者や成年後見人)が申立てを行うことになります。その際は、申述書に加えて、法定代理人であることを証明する書類(親権者ならご自身の戸籍謄本、後見人なら登記事項証明書など)が追加で必要になります。
相続放棄の申立て方法(自分で)

さあ、必要書類がすべて揃ったら、いよいよ家庭裁判所への提出(申立て)です。
提出先:
被相続人(亡くなった方)の「最後の住所地」を管轄する家庭裁判所です。これは鉄則です!申述人(あなた)の住所地や本籍地の近くの裁判所ではないので、絶対に間違えないように注意してくださいね!管轄の裁判所がどこかは、裁判所のウェブサイト「裁判所の管轄区域」で調べることができます。
提出方法:
裁判所の窓口に直接持参する方法と、郵送で提出する方法があります。遠方の場合や平日の日中に時間が取れない場合は、郵送が便利です。郵送の場合は、書類が裁判所に届いた日が受付日となります。期限ギリギリの場合は、配達記録が残り、到着日が明確になる「簡易書留」や「レターパックプラス」などで送ることをおすすめします。
申立て後の流れ:
申立てが無事に受け付けられると、通常1〜2週間ほどで、裁判所からご自宅に「相続放棄についての照会書(回答書)」という書類が郵送されてきます。これは、「本当にあなたの意思で放棄するんですね?」「誰かに脅されたりしていませんか?」「故人の財産を使ったり隠したりしていませんね?」といった内容を確認するための、質問状のようなものです。
この回答書に正直に記入(チェック)して、署名・押印して返送します。この回答内容が非常に重要で、ここで「財産を使いました」などと書いてしまうと、申立てが受理されない(却下される)可能性があります。
返送した回答書の内容に問題がなければ、さらに1〜2週間ほどで、今度は「相続放棄申述受理通知書」という書類が届きます。これで家庭裁判所があなたの相続放棄を法的に認めたことになり、手続きは無事完了となります。
「受理通知書」と「受理証明書」は違う?
手続きが完了すると届く「受理通知書」は、基本的に再発行ができません。もし、借金の債権者などから「相続放棄したことを証明する書類」の提出を求められた場合は、この通知書のコピーを提示するのが一般的です。
それでも原本(またはそれに代わるもの)を求められた場合は、家庭裁判所に別途「相続放棄申述受理証明書」の発行を申請(1通150円の収入印紙が必要)することができます。こちらは何通でも発行が可能です。

手続きの流れ、なんとなくイメージできましたか? やはり一番の山場は「戸籍集め」と「期限管理」ですね。
特にご兄弟の相続放棄(第3順位)の場合は、戸籍集めに時間がかかって期限ギリギリになりがちです。大変そう…と感じたら、時間切れになる前に、早めに専門家を頼るのも賢い選択ですよ。
相続放棄手続き自分で知恵袋で見る注意点

相続放棄の前にやってはいけないこと
ここからは、相続放棄を考えている場合に最も注意すべき点をお話しします。これをやってしまうと、もう相続放棄は認められません!というNG行動があるんです。
これを法律用語で「法定単純承認」と呼びます。
「やってはいけないこと」の法的根拠(法定単純承認)
相続財産を使ってしまうと相続放棄ができなくなるのは、民法で「相続を承認した」とみなされる行為(法定単純承認)が定められているためです。
民法 第九百二十一条(法定単純承認)
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。(中略)
三 相続人が、相続の承認又は放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私(ひそ)かにこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。
つまり、故人の預金を使ったり、財産を売却・処分したりする行為は、この「処分したとき」に該当し、自動的に相続を承認したとみなされてしまうのです。
(出典:e-Gov法令検索「民法」)
これは民法(第921条)で定められており、「あなたは(言葉では放棄すると言っていても)その行動は『相続する意思がある』とみなされますよ」ということです。一度こうみなされると、たとえ3ヶ月の期限内に家庭裁判所に申立てをしても、相続放棄は認められなくなってしまいます。
要注意!こんな行動はNGです(法定単純承認)
具体的には、以下のような行動が当てはまります。
- 相続財産(預貯金)を使う・解約する:
故人の預金を引き出して自分の生活費に使ったり、自分の借金の返済に充てたりするのは絶対にいけません。口座を解約する行為もNGです。 - 故人の財産を売却する・処分する:
故人の車や不動産、価値のある遺品(骨董品や貴金属、ブランド品など)を勝手に売ってお金に換える行為。また、価値がないと思っていても、車を廃車にしたり、家を取り壊したりするのも「処分」にあたります。 - 故人の借金を(自分の財産から)返済する:
良かれと思って借金の一部でも返済してしまうと、「自分は相続人として借金を払います」と認めたことになりかねません。債権者から督促が来ても「相続放棄を検討中です」と伝えるに留めましょう。 - 故人のクレジットカードを使う:
死亡後に故人名義のカードで買い物をすることは、故人の債務を増やす行為であり、単純承認とみなされる可能性が非常に高いです。 - 高価な形見分けをする:
写真や手紙、衣類など、財産的価値のない(または極めて低い)ものの形見分けは問題ないとされています。しかし、車や宝石、不動産など、客観的に見て高価なものを「形見だから」と相続人の一人が受け取ると、財産の処分・取得にあたる可能性があります。 - 財産を隠す(隠匿):
借金だけ放棄して、価値のある財産(例えばタンス預金や貴金属など)をこっそり隠し持つ行為。これは論外であり、悪質な行為として放棄が認められません。
相続放棄を検討している熟慮期間中は、故人の相続財産には一切手を付けず、現状のまま保存しておくのが鉄則です!
ただし、社会通念上相当な範囲内での葬儀費用(豪華すぎない一般的な葬儀)を、故人の預金から支払うことについては、例外的に認められる傾向にあります。とはいえ、判断が非常に難しいグレーゾーンであることに変わりはありません。
もし支払う場合でも、必ず領収書や明細書をすべて保管しておき、裁判所から説明を求められた際に提示できるようにしておく必要があります。不安なら、ご自身の財産から一時的に立て替えておき、相続財産には一切手を触れないのが一番安全です。
相続放棄が認められない事例とは

前述の通り、相続放棄が認められない(受理されない)事例として最も多いのは、単純承認とみなされる行為をしてしまったケースです。
家庭裁判所から送られてくる「照会書」には、「相続財産を処分したり、使ったり、隠したりしていませんか?」という質問が必ずあります。
ここで「はい」と答えてしまえば、もちろん受理は難しくなりますし、もし「いいえ」と嘘をついても、後で債権者などからの指摘で発覚すれば、受理が取り消される可能性もあります。「知らなかった」「うっかり預金を使ってしまった」という言い訳は、残念ながら通用しないことが多いのです。
もう一つの典型的な事例は、申立て期限(原則3ヶ月)を過ぎてしまった場合です。
裁判所は期限に厳格なため、正当な理由がなく、単に「忘れていた」「忙しかった」「手続きが面倒だった」という理由だけでは、まず受理されません。
もし期限を過ぎてしまった場合は、「期限内に放棄できなかった正当な理由」を詳細に記した「上申書(事情説明書)」を申述書と一緒に提出する必要があります。この作成は法的な主張が求められるため、ご自身で行うのは非常に難しく、弁護士などの専門家の領域となります。
また、申述書や戸籍謄本などの提出書類に不備があり、裁判所から「この戸籍が足りません」「ここの記入を訂正してください」という補正(修正)指示が出たにもかかわらず、それを無視したり、期限までに対応しなかったりした場合も、申立てが却下(取り下げ)扱いになる可能性があります。裁判所からの連絡(電話や郵便)は、必ず誠実に対応する必要があります。
相続放棄にかかる費用(実費)
ご自身で手続きする場合、専門家への報酬はかかりませんが、裁判所に納める実費や書類の取得費用は必ず必要になります。どれくらいの費用がかかるのか、目安をしっかり把握しておきましょう。
| 項目 | 費用(目安) | 備考 |
|---|---|---|
| 収入印紙 | 申述人1人につき 800円 | 申述書に貼って裁判所に納めます。郵便局やコンビニ(一部)で購入できます。 |
| 連絡用の郵便切手 | 300円~1,000円程度 | 裁判所からの連絡(照会書や受理通知書)に使われます。管轄の家庭裁判所によって総額や「84円切手○枚、10円切手○枚」といった組み合わせが細かく指定されている場合が多いです。必ず事前に裁判所のウェブサイトや電話で確認しましょう。 |
| 戸籍謄本類の取得費用 | 数千円~1万円以上 | 戸籍謄本(1通450円)、除籍・改製原戸籍謄本(1通750円)が基本です。これに住民票除票(1通300円前後、自治体による)などが加わります。 |
ご自身でやれば、相続人が1人(配偶者や子)で戸籍集めも簡単な場合、総額5,000円~1万円程度で収まるケースが多いですね。
ただし、注意が必要なのは戸籍謄本類の取得費用です。兄弟姉妹の相続(第3順位)などで、亡くなった方の出生まで遡る戸籍を集める場合、取得する戸籍が10通以上に及ぶこともあります。
さらに、本籍地が全国各地に点在している場合、それぞれの役所に郵送で請求をかけることになります。郵送請求の際は、手数料分の「定額小為替」を郵便局で購入し、返信用の封筒(切手貼付)を同封する必要があり、手間も時間もかかります。このような複雑なケースでは、実費だけで1万円を優に超えることも珍しくありません。
相続放棄の司法書士費用
「戸籍集めや書類作成がやっぱり面倒…」「本籍地が遠くて自分では集められない」「期限が迫っていて不安…」という場合、専門家に依頼する選択肢があります。まずは、司法書士に依頼するケースです。
司法書士は、登記や裁判所に提出する書類作成のプロフェッショナルです。司法書士に依頼すると、面倒な戸籍謄本類の収集から、相続放棄申述書の作成、裁判所への提出代行(郵送や持参)まで、一連の作業を任せることができます。
相続放棄の司法書士費用は、事務所によって異なりますが、大体3万円~6万円程度(+実費)が相場かな、という印象です。ただし、これは申述人1人あたりの基本料金であることが多く、集める戸籍の通数が多い複雑な案件(例:兄弟姉妹相続)の場合や、相続人調査が必要な場合は、追加費用がかかる事務所もありますので、依頼前に必ず見積もりを確認しましょう。
司法書士に依頼するメリット
- 面倒な戸籍収集や申述書作成をすべて任せられる(時間と手間が大幅に削減できる)
- 専門家が作成するため書類の不備がなくなり、スムーズに手続きが進む
- 弁護士に依頼するより費用が抑えられる傾向にある
ご自身で動く時間はあまりないけれど、手続き自体は標準的(期限内である、財産を使っていないなど、法的な争いがない)という方には、司法書士への依頼が適しています。
ただし、司法書士の業務はあくまで「書類作成代行」です。裁判所からの照会書(質問状)への回答は、最終的にご自身で行う必要がありますし、もし期限を過ぎているなど法的な主張が必要なケースや、債権者との交渉が必要なケースには対応できません。
相続放棄で弁護士に相談する目安

では、弁護士に相談するのはどんな時でしょうか? 司法書士との大きな違いは、弁護士はあなたの「代理人」として、法的な権限を持ってすべての手続きを行える点、そして「交渉」や「法的な判断」が求められる複雑な案件に対応できる点です。
弁護士に依頼すると、書類作成や提出はもちろんのこと、裁判所からの照会書(質問状)への回答も弁護士が代理人として作成・提出してくれます。さらに、もし借金の債権者から督促の電話や手紙が来ている場合、弁護士が窓口となって「相続放棄の手続き中です」と対応してくれるため、精神的な負担が大きく軽減されます。
弁護士への相談がおすすめなケース
- すでに3ヶ月の期限を過ぎてしまっている
(裁判所を納得させる「事情説明書(上申書)」の作成が必要なため) - うっかり財産を使ってしまった(単純承認が疑われる)
(それが単純承認にあたらない、という法的な主張を組み立てるため) - 他の相続人や債権者(借金相手)とトラブルになっている、またはなりそう
(交渉や連絡の窓口になってもらうため) - 借金がいくらあるか不明で、相続財産の調査から丸ごとお任せしたい
- 裁判所からの照会書(質問状)への回答が不安
これらの状況では、単なる書類作成代行では対応が難しいため、弁護士のサポートが望ましいです。費用は司法書士より高くなる傾向があり、事務所によりますが、基本料金として5万円~10万円程度(+実費)が目安になります。期限切れや単純承認疑いなど、案件の難易度が高い場合は、追加費用や成功報酬が発生する場合もありますので、こちらも必ず事前に見積もりを確認してくださいね。
司法書士と弁護士、どっちに頼む?
- 司法書士がおすすめ:
期限内で、財産にも手をつけていない。とにかく面倒な戸籍集めと書類作成を任せたい。 - 弁護士がおすすめ:
期限を過ぎている、財産を使ってしまった、債権者から督促が来ているなど、法的な問題や不安要素がある。
ご自身の状況に合わせて選ぶのが一番ですよ。
相続放棄についてよくあるご質問FAQ
ここでは、相続放棄の手続きでよくいただくご質問にお答えしますね。
-
相続放棄の期限3ヶ月はいつから数えますか?
-
原則として「自分が相続人になったことを知った日」から数え始めます。多くの場合は、亡くなった日(死亡日)を知った日になりますね。
-
借金がいくらあるか調査中に3ヶ月過ぎそうです…
-
家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることができます。これが認められれば、判断するための期間を3ヶ月など延長してもらえますよ。
-
亡くなった父の生命保険金は受け取っても大丈夫ですか?
-
受取人があなた(相続人)個人に指定されている生命保険金は「受取人固有の財産」です。これは相続財産ではないので、受け取っても相続放棄できます。
-
相続人全員が相続放棄したら、借金や空き家はどうなりますか?
-
誰も相続しなくなった財産は、利害関係人(債権者など)の申立てにより「相続財産清算人」が選任され、清算手続きを経て最終的に国のものになります。ただし、空き家などは次の管理者が決まるまで管理義務が残る場合があり注意が必要です。

相続放棄は、一度受理されると取り消しができません。「借金だらけだと思ったら、後から高価な財産が見つかった!」なんてことも…。だからこそ、最初の3ヶ月での財産調査と判断が本当に大切なんです。ご自身の状況をしっかり見極めてくださいね。
相続放棄手続き自分で知恵袋のまとめ
最後に、相続放棄の手続きを自分で行う際のポイントをまとめます。
- 相続放棄はプラスもマイナスも一切相続しない手続き
- 親の借金が多い場合に有効な手段
- 手続きは自分でできるが戸籍収集が大変な場合も
- 相続放棄は原則「知った日から3ヶ月以内」に申立て
- 提出先は故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
- 必要な書類は相続放棄申述書と戸籍謄本類
- 相続順位(子・親・兄弟)で必要な戸籍は異なる
- 申述書は裁判所のサイトでダウンロード可能
- 相続財産を使うと「単純承認」とみなされ放棄できない
- 預金の解約や財産の売却はNG行動
- 期限を過ぎると原則認められない
- 自分でやる実費は1万円程度が目安
- 書類作成代行は司法書士(費用3万~6万目安)
- 期限切れやトラブル時は弁護士に相談(費用5万~10万目安)
- 生命保険金(受取人指定)は受け取っても放棄可能
今日からできるアクションプラン
もし相続放棄を少しでも考えているなら、今日からこの3つを始めてください!
- まずは故人の財産を調べる:
通帳や郵便物(督促状など)を確認し、借金(負債)と預貯金(資産)の概要を把握する。(注意:財産には絶対に手を触れない!) - 自分の相続順位を確認する:
自分と故人の関係(子、親、兄弟など)を明確にする。 - 期限(3ヶ月)の起算日を確認する:
故人の死亡を知ったのはいつか、カレンダーで日付を再確認する。
まずは状況把握からです!期限があるので、悩んでいる時間はありません。今日から一歩踏出してみましょうね!
▼あわせて読みたい関連記事▼
相続印鑑証明なぜ必要?手続きの全知識
空き家の放置がもたらす3つのリスクと損しないための対処法
遺産相続末路スピリチュアルな学び|放棄と独占の明暗とは
相続した実家、売却か賃貸か?判断ミスで損しないための全知識
遺産分割調停中にやってはいけないこと【完全ガイド】

お気軽にご相談ください
相続は100人いれば、100通り
唯一無二の最適な相続をご提案いたします
CONTACT
専門家やえさん

- 専門家やえさん
-
堀川 八重(ほりかわ やえ)
大阪不動産・FPサービス株式会社 代表
15年以上にわたり1,500組を超えるご家族の相続や不動産のお悩みに、専門家として寄り添ってまいりました。私の信条は、法律や数字の話をする前に、まずお客様ご家族の歴史や言葉にならない想いを丁寧に「聞く」こと。信頼できる各分野の専門家チームと共に、皆様が心から安心できる最善の道筋をオーダーメイドでご提案します。一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。
最新の投稿
 お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説
お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説 相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説
相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説 お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例
お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例 お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説
お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説