こんにちは!終活・相続・不動産相続の専門家、やえです。
突然ですが、「だいしゅうそうぞく」って言葉、耳にしたことはありますか?相続の話になったとき、急に出てきて「え、何それ?」って戸惑ってしまう方も少なくないんです。この代襲相続の読み方、最初はちょっと難しい感じがしますよね。
そもそも代襲とは何かというと、本来、相続人になるはずだった方が亡くなっていた場合に、そのお子さんなどが代わりに相続する制度のことなんです。でも、この制度が少し複雑でして…。
例えば、代襲相続はどこまでの範囲の親族に認められるのか、相続の割合はどう計算するのか、気になりませんか?
また、子供がいないケースや残された配偶者の立場、さらには第三順位の兄弟姉妹が関係する場合など、家族の形によって考えるべきことは様々です。加えて、代襲相続の手続きや気になる税金の問題、よく混同されがちな相続放棄との違い、そして避けたいトラブルまで、知っておくべきポイントがたくさんあります。
特に、代襲相続ができない場合という落とし穴もあるので注意が必要なのです。
この記事では、そんなあなたの「?」をスッキリ解決できるよう、代襲相続の基本から具体的なケースまで、会話をするように丁寧にご案内しますね!
この記事のポイント
- 代襲相続の基本的な意味と対象になる人
- 【ケース別】代襲相続できる範囲と相続割合
- 代襲相続ができない場合の注意点や相続トラブルの回避策
- 代襲相続で必要になる手続きや税金の知識

相続って、ただでさえ考えることが多くて大変なのに「代襲相続」なんて言葉が出てくると、もうパニック!ってなりますよね。
でも、ご安心ください。私がこれまでご相談に乗ってきた多くのご家庭でも、最初は皆さん同じでした。
大切なのは、一つひとつのルールを丁寧に理解することです。この記事を道しるべに、一緒に不安を解消していきましょう!
目次
代襲相続とはわかりやすく|基本から解説
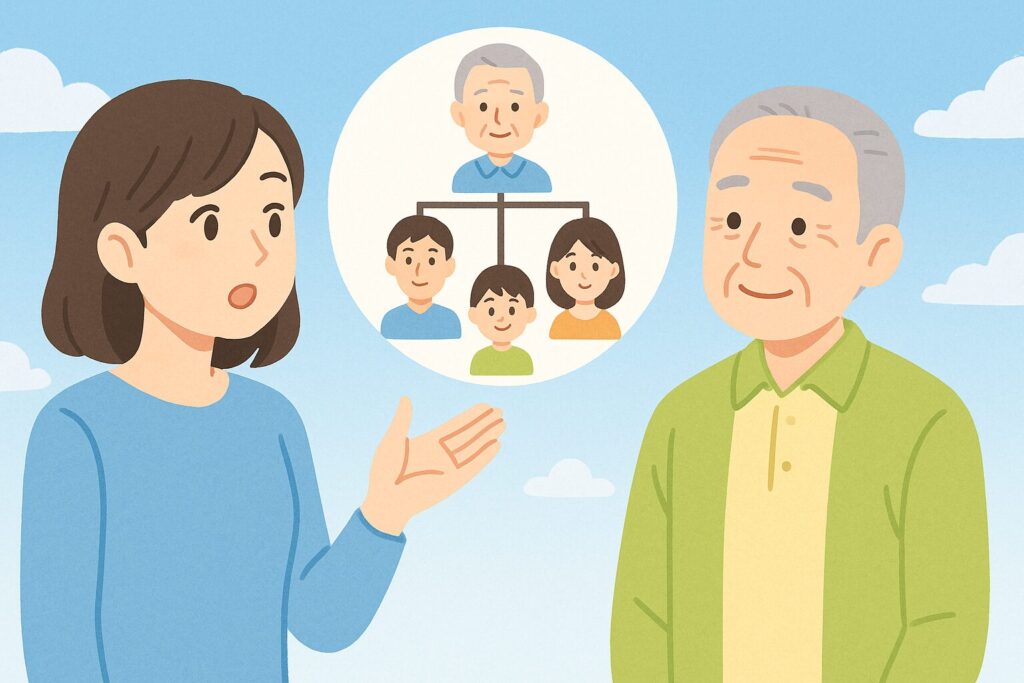
代襲とは?まず読み方から確認
まず、基本中の基本からお話ししますね。「代襲相続」は「だいしゅうそうぞく」と読みます。少し難しい言葉ですが、分解して考えるとイメージしやすくなりますよ。
「代襲」の「代」は「代わりに」、「襲」は「受け継ぐ」という意味を持っています。つまり、「代わりに受け継ぐ相続」ということです。
法律(民法)では、誰が遺産を相続する権利を持つか(これを相続人といいます)が順位とともに定められています。しかし、亡くなった方(被相続人)より先に、相続人となるはずだった子どもや兄弟姉妹が亡くなっているケースも少なくありません。このような場合に、その亡くなった相続人に代わって、その方の子ども(被相続人から見れば孫や甥・姪)が相続権を引き継ぐ制度、それが代襲相続です。
この制度があるおかげで、世代を超えて財産を受け継ぐ機会の公平性が保たれている、と考えると少しわかりやすいかもしれませんね。
代襲相続の割合はどう決まるか

「じゃあ、代わりに相続することになった場合、どれくらいの割合をもらえるの?」という疑問が湧いてきますよね。
結論から言うと、代襲相続人が受け継ぐ相続分は、亡くなった本来の相続人が受け取るはずだった割合と全く同じです。そして、代襲相続人が複数いる場合は、その割合を均等に分け合うことになります。
少し具体例で見てみましょう。
具体例:夫が亡くなり、妻と子ども2人が相続人の場合
このケースでは、法定相続分は妻が2分の1、子どもたちがそれぞれ4分の1ずつです。しかし、もし長男がすでに亡くなっていて、長男に子どもが2人(被相続人から見て孫)いたとします。
この場合、長男が受け取るはずだった「4分の1」の相続権を、孫2人が代襲相続します。孫は2人いるので、この4分の1を2人で均等に分け合うわけです。つまり、孫1人あたりの相続分は「4分の1 ÷ 2人 = 8分の1」となります。
| 相続人 | 本来の相続割合 | 代襲相続後の割合 |
|---|---|---|
| 配偶者(妻) | 1/2 | 1/2 |
| 長女 | 1/4 | 1/4 |
| 長男(故人) | 1/4 | - |
| 孫(長男の子)① | - | 1/8 |
| 孫(長男の子)② | - | 1/8 |
このように、代襲相続が発生しても、他の相続人(この例では妻と長女)の相続割合には影響がない、という点がポイントです。
代襲相続はどこまで認められる?
「孫が相続できるのはわかったけど、ひ孫は?甥や姪の子は?」と、どこまでの範囲で認められるのか気になりますよね。実はこれ、誰の代襲相続かによって範囲が変わるので、注意が必要です。
亡くなった相続人が「被相続人の子」の場合
被相続人の子どもが亡くなっている場合は、その子どもである孫が代襲相続します。さらに、その孫も亡くなっている場合は、ひ孫が代襲相続できます。このように、下の世代に続く限り、代襲相続は何代でも繰り返されます。これを「再代襲(さいだいしゅう)」といいます。
亡くなった相続人が「被相続人の兄弟姉妹」の場合
被相続人の兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子どもである甥・姪までしか代襲相続は認められません。甥や姪も亡くなっている場合でも、その子どもがさらに代襲相続することはないのです。こちらは再代襲が認められていないので、しっかり覚えておきましょう。
なぜこのような違いがあるかというと、あまりにも遠い親戚まで相続関係が広がると、遺産分割が非常に複雑になってしまうのを防ぐため、とされています。
代襲相続ができない場合の条件

「代わりに相続できる」と聞くと便利な制度に思えますが、実は代襲相続が発生しないケースもあります。それは、本来の相続人が「相続放棄」をした場合です。
相続放棄とは、家庭裁判所に申し出ることで、プラスの財産もマイナスの財産(借金など)も一切受け継がないとすることです。相続放棄をした人は、「初めから相続人ではなかった」とみなされます。
相続権そのものが無くなるわけですから、その人の子どもが代わりに権利を引き継ぐ(代襲する)ということも起こり得ないのです。
【豆知識】相続欠格や廃除の場合は?
ちなみに、相続人が重大な不正行為(被相続人を殺害しようとしたなど)をした場合の「相続欠格」や、被相続人の意思で相続権を奪う「相続廃除」によって相続権を失った場合は、代襲相続が発生します。これは、その人個人の問題であり、そのお子さんには責任がない、という考え方に基づいています。
代襲相続と相続放棄の違いとは
前の見出しでお話しした通り、「相続放棄」をすると代襲相続は発生しません。この2つは相続において重要なポイントなので、違いをしっかり整理しておきましょう。
一番の違いは、「次の世代に相続権が引き継がれるかどうか」です。
親が亡くなっている場合は、その相続権が子ども(孫)に引き継がれます(=代襲相続)。
一方、親が相続放棄をした場合は、その相続権は消滅し、子ども(孫)には引き継がれません。
| 代襲相続(相続人が死亡など) | 相続人が相続放棄 | |
|---|---|---|
| 相続権の行方 | 子や孫に引き継がれる | 引き継がれない(消滅する) |
| 相続人になる人 | 孫や甥・姪など | 次の順位の相続人(例:祖父母や兄弟姉妹) |
もしご自身の親が相続放棄を検討している場合は、「自分には関係ない」と思わずに、相続権がどう動くのかをしっかり確認することが大切です。
代襲相続の基本についてよくあるご質問FAQ

ここでは、代襲相続の基本的な事柄について、よくいただくご質問にお答えしますね。
-
養子の子どもは代襲相続できますか?
-
はい、できます。ただし、そのお子さんが養子縁組をした後に生まれた子である必要があります。養子縁組より前に生まれていたお子さんには、残念ながら代襲相続権は認められていません。
-
被相続人と同時に亡くなった場合も代襲相続は発生しますか?
-
はい、発生します。例えば、事故などで親子が同時に死亡したと法的に扱われる場合でも、子どもが先に亡くなったものとみなされ、孫がいれば代襲相続が起こります。
-
お腹の中にいる赤ちゃん(胎児)も代襲相続できますか?
-
はい、できます。法律上、相続においては胎児は「既に生まれたもの」として扱われるため、無事に生まれれば代襲相続人になることができます。
ケース別・代襲相続とはわかりやすく注意点を解説


ここまで基本を学んで、少し頭がスッキリしてきた頃でしょうか?ここからは、より具体的なケースを見ていきます。
「うちの場合はどうなんだろう?」という視点で読んでいただくと、さらに理解が深まりますよ。特にご親族の関係が複雑な場合は、思いがけない方が相続人になることもありますので、しっかり確認していきましょうね。
代襲相続で子供がいないケース
亡くなった方(被相続人)に子どもがいない、または子どもが全員すでに亡くなっている場合、相続権は次の順位に移ります。
- 第1順位:子どもや孫(直系卑属)
- 第2順位:親や祖父母(直系尊属)
- 第3順位:兄弟姉妹
子どもがいない場合、まず第2順位の親が相続人になります。しかし、親もすでに亡くなっている場合は、第3順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。ここで、もし兄弟姉妹の中に亡くなっている方がいれば、その方の子ども、つまり甥や姪が代襲相続することになるのです。
被相続人に子どもがいない場合は、ご自身の兄弟姉妹やお元気な甥姪がいらっしゃるか、事前に確認しておくと、いざという時にスムーズかもしれませんね。
代襲相続における配偶者の立場

「代襲相続で甥や姪が登場したら、自分の取り分が減るのでは?」と心配される配偶者の方もいらっしゃるかもしれません。
でも、ご安心ください。亡くなった方の配偶者は常に相続人であり、その法定相続分は代襲相続が発生しても変わりません。
例えば、被相続人に子どもがおらず、相続人が配偶者と兄弟姉妹だった場合、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。この兄弟姉妹が亡くなっていて甥や姪が代襲相続したとしても、この「4分の1」を甥や姪で分け合うだけで、配偶者の「4分の3」という割合は守られます。
ただし、遺産分割を行う際には、これまであまり付き合いのなかった甥や姪と話し合い(遺産分割協議)をしなければならない、という点は心に留めておく必要があります。
代襲相続と第三順位の関係性
前の見出しでも少し触れましたが、代襲相続は相続の第三順位である兄弟姉妹が関係するときに、よく登場します。
相続は、第一順位(子・孫)、第二順位(親・祖父母)の相続人が誰もいない場合に、初めて第三順位の兄弟姉妹に権利が回ってきます。ご高齢の方が亡くなった場合、ご兄弟もすでに亡くなっているケースは非常に多く、その結果、甥や姪が代襲相続人として登場することが頻繁にあるのです。
この場合、甥や姪は「被相続人の兄弟姉妹の子」という立場であり、相続権としては一代限りで、再代襲しないというルールを再度思い出してくださいね。
代襲相続の手続きと税金について
代襲相続が発生した場合、通常の手続きや税金の計算でいくつか注意点があります。
手続きで必要な追加書類
遺産分割協議や不動産の名義変更(相続登記)などの手続きでは、誰が相続人であるかを証明するために戸籍謄本を集める必要があります。代襲相続がある場合は、通常の書類に加えて、亡くなった本来の相続人(被代襲者)の「出生から死亡まで」の連続した戸籍謄本も必要になります。これが意外と集めるのに時間がかかることがあるので、早めに準備を始めると安心です。
相続税の計算でのポイント
相続税には、財産額から差し引ける「基礎控除」という非課税枠があります。この金額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算されます。
メリット:相続人が増えれば基礎控除額も増える
代襲相続によって相続人の数が1人から2人(例:亡くなった兄の代わりに甥と姪)に増えれば、その分、基礎控除額が600万円増えることになり、節税につながる可能性があります。
デメリット:甥・姪は相続税が2割増しに
一方で注意したいのが、甥・姪が遺産を相続する場合、相続税額が2割加算されるというルールです。これは、被相続人の配偶者と一親等の血族(子や親)以外が相続する場合に適用されます。孫が代襲相続する場合は、一親等の血族とみなされるため2割加算の対象にはなりません。
この相続税のルールについて、詳しくは国税庁のウェブサイトも参考にしてください。
(参照:国税庁 No.4157 相続税額の2割加算)
代襲相続で起こりうるトラブル

代襲相続は、時として予期せぬトラブルの原因になることもあります。特に多いのが、相続人同士の関係性が遠いことから生じる問題です。
- 面識のない相続人が現れた
長年付き合いのなかった甥や姪が、突然相続人として遺産分割協議に参加することになり、話し合いがスムーズに進まないケース。 - 相続人の連絡先が分からない
戸籍をたどって甥や姪の存在は分かったものの、どこに住んでいるか分からず、連絡が取れないまま手続きが停滞してしまうケース。 - 感情的な対立
「生前お世話になったのだから、配偶者が多くもらうべきだ」「法律通りの権利を主張したい」など、お互いの立場や感情がぶつかり、協議がまとまらないケース。
このようなトラブルを避けるためには、被相続人が元気なうちに遺言書を作成しておくことが非常に有効です。誰にどの財産を遺したいかを明確にしておくことで、相続人同士の無用な争いを防ぐことにつながります。
遺言書の作成方法などについては、法務省のウェブサイトも参考になります。
(参照:法務省「自筆証書遺言書保管制度」)

最後までお読みいただき、ありがとうございます!代襲相続は、法律用語が多くて難しく感じたかもしれませんね。でも、これはご家族の歴史が関わる大切な制度なんです。
もし手続きで迷ったり、親族間の話し合いが不安になったりしたら、決して一人で抱え込まないでください。私たちのような専門家を気軽に頼っていただけると嬉しいです。
悩む前に|代襲相続とはわかりやすく専門家へ
この記事では、代襲相続の基本から注意点までを解説しました。最後に、重要なポイントをリストで振り返ってみましょう。
- 代襲相続(だいしゅうそうぞく)は本来の相続人に代わって子が相続する制度
- 相続割合は本来の相続人の分を代襲相続人の人数で分ける
- 他の相続人の相続割合は変わらない
- 被相続人の子の代襲は何代でも続く(再代襲)
- 兄弟姉妹の代襲は甥・姪までで再代襲はない
- 相続放棄をした人の子は代襲相続できない
- 被相続人に子や親がいない場合、兄弟姉妹の子(甥・姪)が代襲相続することがある
- 配偶者の相続分は代襲相続があっても影響を受けない
- 手続きには亡くなった相続人の出生から死亡までの戸籍も必要
- 代襲相続で相続人が増えると相続税の基礎控除額が増えるメリットがある
- 甥・姪が相続する場合は相続税が2割加算されるので注意が必要
- 面識のない親族が相続人になるなどトラブルに発展しやすい
- トラブル防止には生前の遺言書作成が有効
- 養子の子が代襲相続するには養子縁組後に生まれた子である必要がある
- 複雑で分からない場合は一人で悩まず専門家への相談を検討する
▼あわせて読みたい関連記事▼
【相続税いくらから親子でかかる?】専門家が相続税の早見表や基礎控除・計算方法をわかりやすく解説
遺言書書き方法務局で正確に遺言を残す方法|失敗しない書き方と注意点
初めてでも安心!不動産名義変更の流れをわかりやすく解説する決定版ガイド

お気軽にご相談ください
相続は100人いれば、100通り
唯一無二の最適な相続をご提案いたします
CONTACT
専門家やえさん

- 専門家やえさん
-
堀川 八重(ほりかわ やえ)
大阪不動産・FPサービス株式会社 代表
15年以上にわたり1,500組を超えるご家族の相続や不動産のお悩みに、専門家として寄り添ってまいりました。私の信条は、法律や数字の話をする前に、まずお客様ご家族の歴史や言葉にならない想いを丁寧に「聞く」こと。信頼できる各分野の専門家チームと共に、皆様が心から安心できる最善の道筋をオーダーメイドでご提案します。一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。
最新の投稿
 お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説
お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説 相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説
相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説 お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例
お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例 お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説
お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説






