「年金の納付猶予って、結局払わなくていいの?」「年金納付猶予払わない知恵袋の投稿を見てると、情報が違いすぎてワケがわからない…!」なんて、頭を抱えていませんか?
国民年金払えない知恵袋をのぞけば、「納付猶予払わなくていい」という声もあれば、「将来困るよ!」という声もあって、ますます混乱しちゃいますよね。国民年金の猶予のデメリットって具体的に何なのか、年金免除猶予どっちがいいのか、年金納付猶予いつまで知恵袋で聞いても答えはバラバラ…。
しまいには、国民年金の催告状が払えません、どうしたらいいですか?なんて切実な悩みも。でも、ご安心ください!この記事では、そんなあなたのモヤモヤを吹き飛ばします。
納付猶予とはわかりやすく、そして年金納付猶予払わないとどうなるのか、正しい申請手続きから国民年金払えない相談先、お得な追納制度まで、まるっと解説しちゃいますね!
この記事のポイント
- 納付猶予と免除の明確な違い
- 保険料を払わない場合の具体的なデメリット
- 払えない時の正しい申請手続きと相談先
- 将来の年金額を減らさないための追納制度
年金納付猶予払わない?知恵袋の疑問を解決

納付猶予とはわかりやすく制度を解説
「そもそも国民年金の納付猶予ってなんなの?」というところから、まずはお話しさせてくださいね。
日本の公的年金制度は、現役世代が納めた保険料で高齢者の方々の生活を支える「世代と世代の支え合い」という考え方で成り立っています。この制度があるからこそ、私たちは老後はもちろん、病気やケガで障害が残ってしまった時や、一家の働き手が亡くなった時にも、年金という形で経済的なサポートを受けられるわけです。
ただ、人生いろいろありますよね。学生さんだったり、一時的に収入が減ってしまったりして、毎月の保険料を納めるのが難しい時だってあります。そんな時のために用意されているセーフティネットの一つが「納付猶予制度」なんです。
補足:未納とは全く違う!
一番やってはいけないのが、払えないからといって手続きをせずに放置してしまう「未納」の状態です。未納のままだと、将来年金がもらえないだけでなく、万が一の時の障害年金や遺族年金も受け取れない可能性がありますし、最悪の場合は財産を差し押さえられることも…。
猶予制度は、そうした最悪の事態を避けるための、国が認めた正式な手続きなんですよ。
この制度を利用すると、承認された期間の国民年金保険料の納付を、文字通り「猶予(待ってもらう)」してもらえます。対象となるのは、50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合です。学生さんには「学生納付特例制度」という、同じく納付猶予の仕組みがあります。
手続きをして承認されれば、その期間は年金の受給資格期間(年金をもらうために最低限必要な加入期間)にはカウントされます。これによって、とりあえず「年金が全くもらえなくなる」というリスクは回避できるんです。ありがたい制度ですよね。
納付猶予払わなくていいという噂は本当?

さて、ここが一番気になるところだと思います。「納付猶予は払わなくていい」という噂、これは半分ホントで、半分は注意が必要、というのが正直なところです。
「ホント」の部分は、納付猶予が承認されれば、その期間の保険料を支払う法的な義務はなくなるという点です。日本年金機構から「払ってください!」と督促状が届くことはありませんし、財産を差し押さえられる心配もありません。この点だけを見れば、「払わなくていい」と言えるかもしれません。
しかし、話はこれで終わりじゃないんです。ここからがとっても大事なポイントになってきます。
私の友人A子さんも、フリーター時代に「猶予は払わなくていいらしいよ」と聞いて、ずっと放置していたんです。でも数年後、自分の年金記録を見て「え、この期間、年金額に全く反映されてない!」って真っ青になっていました。義務がないことと、将来もらえる額は別問題なんですよね。
そう、納付猶予された保険料を払わないままでいると、将来受け取る自分の年金額に大きな影響が出てしまうんです。次の項目で、そのデメリットについて詳しく見ていきましょう。
国民年金の猶予のデメリットは?
国民年金の納付猶予制度を利用する際の、最大のデメリット。それは、ズバリ「追納(後払い)しない限り、将来の老齢基礎年金の額に全く反映されない」ことです。
【要注意】猶予期間は「カラ期間」として扱われます
老齢基礎年金は、20歳から60歳までの40年間(480か月)、保険料をすべて納めて初めて満額を受け取れます。納付猶予が承認された期間は、年金を受け取るための「受給資格期間」には含まれますが、年金額を計算する上では「保険料を納めていない期間(カラ期間)」として扱われてしまうのです。
これはどういうことかと言うと、例えば2年間(24か月)納付猶予を受けたままにすると、将来もらえる年金額の計算式における「納付済月数」が24か月分まるまる減ってしまう、ということです。
もう一つの隠れたデメリットとして、障害年金や遺族年金を受け取るための「納付要件」を満たせなくなる可能性もゼロではない、という点が挙げられます。
これらの年金は、病気やケガをした日(初診日)の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上が保険料納付済期間(または免除期間)であることなどが要件となります。猶予期間が長くなると、この「3分の2」の条件をクリアできなくなるリスクが出てくるため、注意が必要です。
年金納付猶予払わないとどうなるか解説

では、実際に納付猶予された保険料を払わないと、将来の年金額はどれくらい減ってしまうのでしょうか。具体的な数字で見てみると、その影響の大きさがよくわかりますよ。
老齢基礎年金の満額は、令和6年度で年額816,000円です。これを基準に計算してみましょう。
(計算式:816,000円 × 納付済月数 ÷ 480か月)
【ケース1】学生時代に2年間(24か月)の学生納付特例を受け、追納しなかった場合
本来480か月納めるはずが、24か月分が「カラ期間」になるので、納付済月数は456か月(480 - 24)となります。
これを計算式にあてはめると…
816,000円 × 456か月 ÷ 480か月 = 775,200円
満額との差は、なんと年間で40,800円にもなります。10年で約40万円、20年で約80万円…と考えると、かなり大きな差ですよね。
「月々で見れば数千円の違いでも、一生続くとなると、海外旅行1回分くらい軽く変わってきちゃいますよね…!私も若い頃にこの計算を知っていたら、もっと真剣に追納を考えたのになぁと、今になって思います(笑)」
このように、納付猶予は一時的に家計を助けてくれるありがたい制度ですが、その後のフォローをしないと、将来の自分への仕送りが減ってしまう、ということを覚えておいてくださいね。
年金免除猶予どっちがいい知恵袋での結論
「免除」と「猶予」、どちらも保険料の支払いが難しい時のための制度ですが、この二つには決定的な違いがあります。知恵袋でも「どっちがいいの?」という質問をよく見かけますが、結論から言うと、もし選べる状況なら「免除」の方が有利なケースが多いです。
その理由は、免除期間は、追納しなくても一部が年金額に反映されるからです。
なぜなら、免除期間中は、保険料の半分が税金(国庫)から負担されているためです。一方、猶予期間にはこの国庫負担がありません。この違いが、将来の年金額に差を生むのです。
二つの制度の違いを、表で分かりやすく比較してみましょう。
| 項目 | 納付猶予 | 全額免除 |
|---|---|---|
| 将来の年金額への反映 (追納しない場合) | 全く反映されない(0円) | 一部反映される(1/2) |
| 対象者(所得要件など) | 50歳未満で本人・配偶者の所得が一定以下の方、学生 | 本人・配偶者・世帯主の所得が一定以下の方 |
| メリット | 世帯主の所得は審査対象外 | 追納なしでも年金額に一部反映される |
| デメリット | 追納しないと年金額に全く反映されない | 世帯主の所得も審査されるため、承認のハードルがやや高い |
このように、免除は審査の対象に「世帯主」が含まれるため、ご両親などと同居している場合は承認されにくいこともあります。しかし、もし一人暮らしなどで所得要件を満たすのであれば、猶予よりも免除を申請する方が、将来のためにはベターな選択と言えますね。
年金納付猶予払わない知恵袋|対処法まとめ

国民年金の催告状が払えません。どうしたらいいですか?
ポストに「国民年金保険料」に関する封筒、特に「特別催告状」などが入っていると、心臓がドキッとしちゃいますよね。「払えないのにどうしたら…」とパニックになるお気持ち、すごくよく分かります。
【最重要】絶対に無視しないでください!
催告状が届いた時に一番やってはいけないのは、見なかったことにして放置することです。放置を続けると、最終的には延滞金が加算されたり、財産(預貯金、給与、不動産など)の差し押さえに至る可能性があります。これは脅しではなく、法律で定められた手続きなんです。
でも、大丈夫。催告状は「早く差し押さえますよ!」という最後通告ではなく、「このままだと大変なことになりますよ。連絡をくださいね」というメッセージなんです。
ですから、まずは深呼吸をして、封筒に書かれている年金事務所に電話をしてください。「催告状を受け取ったのですが、経済的に支払いが困難で…」と正直に状況を話せば、担当の方が必ず相談に乗ってくれます。
以前、お客様で真っ青な顔をして催告状を持ってきた方がいました。一緒に年金事務所に電話したところ、担当の方がとても丁寧に対応してくれて、その場で免除申請の方法や分割納付の相談に乗ってくれました。電話一本で、差し押さえの不安から解放されて、心からホッとしていましたよ。
支払う意思があること、そして現在の状況を伝えることが何よりも大切です。勇気を出して、まずは一本、電話をかけてみましょう。
国民年金払えない相談は年金事務所へ

国民年金の保険料が払えない時、一人で悩まずに相談できる場所があります。主な相談先は以下の2つです。
- お住まいの市区町村の役所(年金担当窓口)
- お近くの年金事務所
役所の窓口は、住民票の手続きなどのついでに気軽に立ち寄れるのがメリットですね。基本的な手続きの案内や申請書の受け取りができます。
一方、より専門的で具体的な相談をしたい場合は、年金事務所がおすすめです。特に、前述の催告状が届いた場合や、複雑な事情がある場合は、直接年金事務所に相談するのが一番スムーズです。
相談に行く際には、以下のものを持っていくと話が早く進みます。
- 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、ねんきん定期便など)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 所得の状況がわかるもの(源泉徴収票、確定申告書の控えなど)※免除・猶予申請の場合
- 離職したことがわかる書類(雇用保険受給資格者証、離職票など)※失業による特例免除を申請する場合
「年金の相談って、なんだか怒られそう…」なんてイメージがあるかもしれませんが、そんなことは全くありません。担当の方は、私たちが制度を正しく利用して、将来困らないようにサポートするのがお仕事です。安心して相談してみてくださいね。
参考情報サイト: 日本年金機構「全国の相談・手続き窓口」
URL: https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
年金納付猶予申請の方法と必要なもの
それでは、実際に納付猶予を申請する手続きについて見ていきましょう。手続き自体は、そんなに難しくありませんよ。
STEP1:申請書の入手
「国民年金保険料 免除・納付猶予申請書」を入手します。申請書は、以下の場所で手に入ります。
- 市区町村の役所の年金担当窓口
- 年金事務所
- 日本年金機構のホームページからダウンロード
学生の方は、「国民年金保険料 学生納付特例申請書」という専用の様式になります。
STEP2:申請書の記入
申請書に必要事項を記入します。主に、基礎年金番号、氏名、住所、そして所得状況などを記入する欄があります。書き方で分からないことがあれば、窓口で質問すれば丁寧に教えてもらえます。
STEP3:申請書の提出
記入した申請書を、お住まいの市区町村の役所か、年金事務所に提出します。郵送での提出も可能です。マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから電子申請もできて、とっても便利ですよ。
添付書類が必要な場合も
基本的には申請書のみでOKですが、失業などを理由に「特例免除」を申請する場合は、その事実を証明する公的な書類(雇用保険受給資格者証のコピーなど)の添付が必要です。
申請後、日本年金機構で審査が行われ、結果が郵送で通知されます。審査には2~3か月ほど時間がかかることもあります。結果が届くまでは、手元にある納付書は支払わずに保管しておきましょう。
参考情報サイト: 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
URL: https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
年金納付猶予いつまで申請できる?
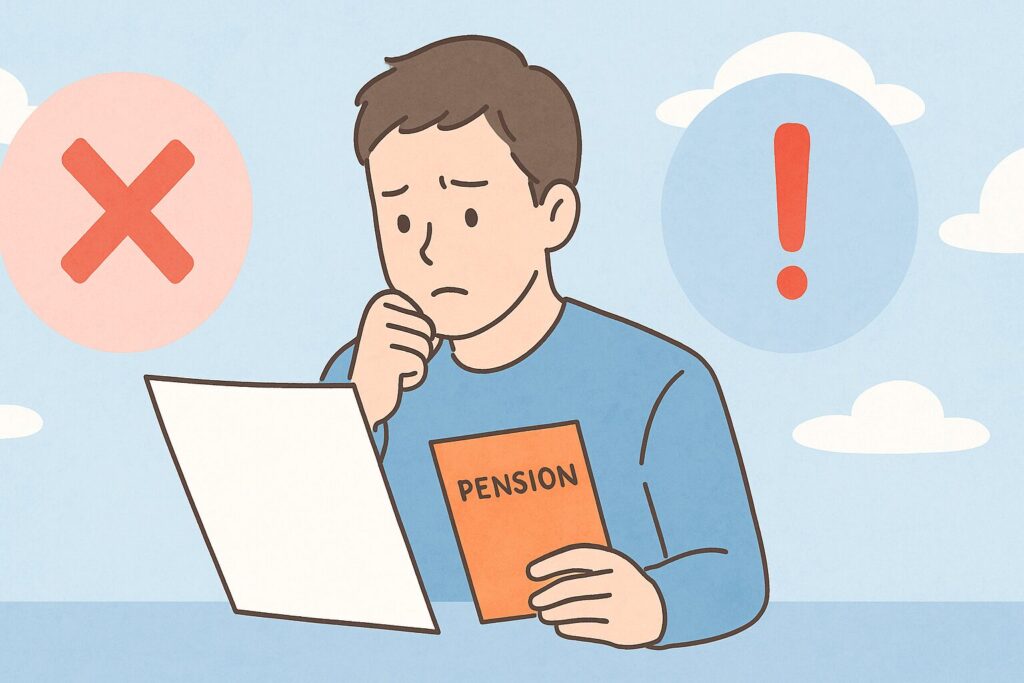
「しまった!去年の分、払えなかったけど申請し忘れてた…」なんて方もいらっしゃるかもしれませんね。でも、諦めるのはまだ早いです!
国民年金の免除・納付猶予の申請は、過去の期間にさかのぼって申請することが可能です。
具体的には、申請時点から2年1か月前までの期間について申請ができます。
例えば、もし今日が2025年7月26日だとすると、2023年6月分までの保険料について、さかのぼって免除や猶予の申請ができる、ということになります。
これは、国民年金保険料の納付期限が「納付対象月の翌月末日」であり、そこから2年を過ぎると時効で納付できなくなるため、それに合わせた仕組みになっているんですね。
申請は年度ごと(7月~翌年6月)
申請は、毎年7月から翌年6月までを1つの期間として行います。例えば、令和5年度(令和5年7月~令和6年6月)と令和6年度(令和6年7月~令和7年6月)の両方の期間で申請が必要な場合は、それぞれの年度の申請書が必要になるので注意してくださいね。
もし申請し忘れている期間があることに気づいたら、すぐに役所や年金事務所に相談してみましょう。未納のまま放置しておくよりも、さかのぼってでも猶予や免除の承認を受けておく方が、将来のために断然有利ですよ。
年金納付猶予追納で将来の年金を増やす
さて、ここまで納付猶予のデメリットについてお話ししてきましたが、そのデメリットを解消できるパワフルな制度が「追納(ついのう)」です。
追納とは、免除や納付猶予の承認を受けた期間の保険料を、後からさかのぼって納めることができる制度のこと。これを活用すれば、猶予していた期間を「保険料をきちんと納めた期間」として復活させ、将来受け取る年金額を満額に近づけることができるんです!
まさに「過去は変えられる!」って感じの制度ですよね(笑)。私も社会人になって少し余裕ができた時に、学生時代の猶予分を追納しました。当時はちょっと痛い出費でしたけど、将来の自分への投資だと思えば、やっておいて本当に良かったなと思います。
追納のメリット
- 老齢基礎年金の年金額が増える(これが最大のメリット!)
- 納めた保険料は「社会保険料控除」の対象になるため、年末調整や確定申告で所得税・住民税が安くなる
ただし、追納する際には一つだけ注意点があります。それは、保険料の免除・猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納すると、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされるということです。
つまり、追納するなら早ければ早いほど、お財布に優しいというわけですね。
追納を希望する場合は、年金事務所に申し込むと、専用の納付書が送られてきます。一括で納めるのが難しければ、月ごとに分けて納めることもできますので、ご自身のペースで計画的に利用するのがおすすめです。
年金納付猶予いつまで知恵袋での回答

「追納がお得なのは分かったけど、一体いつまでできるの?」という疑問も、知恵袋でよく見かけますね。この期限はとても重要なので、しっかり覚えておきましょう。
納付猶予や免除、学生納付特例の承認を受けた保険料を追納できる期間は、
追納が承認された月の前10年以内の期間
と定められています。
つまり、10年を過ぎてしまうと、もう二度とその期間の保険料を納めることはできなくなり、減額された年金額が確定してしまうということです。
10年という期間を意識しよう!
例えば、2015年度に猶予を受けた分は、2025年度中までが追納のチャンス、ということになります。「まだ時間はあるや」と思っていると、あっという間に10年は過ぎてしまいます。日本年金機構から定期的に「追納のご案内」が届くので、それを一つのきっかけとして、ご自身のライフプランと照らし合わせながら追納の計画を立てていくのが良いでしょう。
もし、どの期間が追納できて、保険料がいくらになるのか詳しく知りたい場合は、「ねんきんネット」で確認するか、お近くの年金事務所に問い合わせてみてくださいね。
参考情報サイト: 日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」
URL:https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html
年金納付猶予払わない知恵袋の結論まとめ
最後に、この記事の要点をリストでまとめておきますね。これであなたも「年金納付猶予払わない知恵袋」の疑問から卒業です!
- 納付猶予は保険料の支払いを待ってもらう制度
- 承認されれば支払う法的な義務はなくなる
- しかし追納しないと将来の老齢年金が減額される
- 年金額は猶予1年につき約2万円減るのが目安
- 猶予より免除の方が年金額の面では有利
- 免除は追納なしでも年金額に半分反映されるから
- 払えない時は無視せず役所や年金事務所に相談する
- 催告状が届いたらすぐに電話で連絡することが重要
- 申請は過去2年1か月前までさかのぼって可能
- 申請を忘れていた期間があれば今からでも手続きを
- 減った年金は追納制度で復活させることができる
- 追納できるのは過去10年以内の期間のみ
- 追納は早ければ早いほど加算金がなくお得
- 追納した保険料は社会保険料控除の対象になる
- 困った時は一人で悩まず専門家に相談するのが一番
参考

お気軽にご相談ください
相続は100人いれば、100通り
唯一無二の最適な相続をご提案いたします
CONTACT
専門家やえさん

- 専門家やえさん
-
堀川 八重(ほりかわ やえ)
大阪不動産・FPサービス株式会社 代表
15年以上にわたり1,500組を超えるご家族の相続や不動産のお悩みに、専門家として寄り添ってまいりました。私の信条は、法律や数字の話をする前に、まずお客様ご家族の歴史や言葉にならない想いを丁寧に「聞く」こと。信頼できる各分野の専門家チームと共に、皆様が心から安心できる最善の道筋をオーダーメイドでご提案します。一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。
最新の投稿
 お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説
お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説 相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説
相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説 お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例
お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例 お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説
お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説






