身近な人の介護や相続に直面して、「終活って何から始めればいいの?」と戸惑った経験はありませんか。
実は「終活とは?意味と始め方をわかりやすく解説」と検索される背景には、漠然とした不安と、「今さら聞けない」思いが隠れています。
放っておくと、葬儀や財産整理のトラブル、家族の後悔につながることも珍しくありません。
私も以前、親の介護で右も左もわからず困り果てました。
そこから「終活とは?意味と始め方をわかりやすく解説」という視点で学び直し、「終活の目的」や「エンディングノートの大切さ」に気づいたんです。
この記事では、「終活は何歳から始めるべき?」「終活 50代からの始め方」「終活 20代に必要な備え」など、世代別の準備も具体的にご紹介します。
「終活 100のリスト」や「終活 別の言い方」といった柔らかい切り口にも触れながら、「終活で大切な10ことは何ですか?」にもしっかり答えます。
今、必要なのは大きな一歩ではなく、小さな準備の積み重ねです。
あなたにとって自然な形で、終活を始めるきっかけを見つけてみませんか。
この記事のポイント
- 終活の本来の意味と「なんの略」かがわかる
- 終活を始める適切な年齢や世代別の準備内容がわかる
- エンディングノートや遺言書などの使い分けが理解できる
- 終活をしない場合に起こるリスクや家族の負担が想像できる
終活とは?意味と始め方をわかりやすく解説
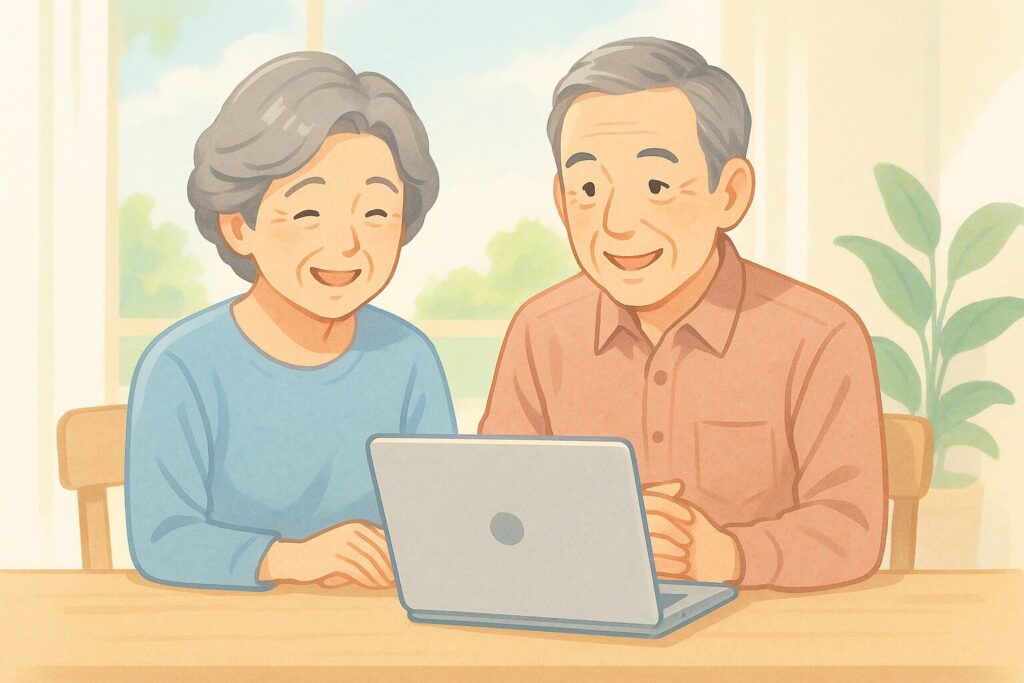
終活の目的は何ですか?家族の負担を減らす意味
終活の最大の目的は、残された家族の精神的・経済的負担を減らすことにあります。
人生の終盤を見据えたこの活動は、自分自身の「死後」に起こる問題を事前に整理・準備しておくことで、周囲の混乱を最小限に抑える工夫とも言えます。
たとえば、突然の訃報を受けて遺族が行うべき手続きは数多く存在します。
中でも負担が大きいとされるのが、葬儀の準備、遺品整理、相続手続きなどです。
このような手続きを行う遺族の様子は、まるで突然降ってわいた試験に答えを求められる受験生のようだと言ってもよいでしょう。
事前に終活がされていれば、その「答え」が書かれたカンニングペーパーのように活用できるわけです。
では実際に、終活を行うことでどれだけ家族の負担が軽減できるのか、項目ごとに確認してみましょう。
| 項目 | 終活がない場合の負担 | 終活がある場合の影響 |
|---|---|---|
| 葬儀の準備 | 遺族が形式・予算を判断 | 希望が明記されていれば即決可能 |
| 遺品整理 | 保管や処分に時間と手間がかかる | 生前整理により不要物は処分済み |
| 財産の把握 | 通帳や証券の所在が不明 | リストがあるため、すぐに確認できる |
| 相続トラブル | 争いに発展する可能性 | 遺言書があることで争いの回避につながる |
| 介護・医療方針 | 遺族が判断に苦しむ | 本人の意思表示により安心して対応できる |
この表からもわかる通り、終活を行っていない状態では家族が「何も知らない状態」で様々な選択を強いられます。
これは心理的にも大きなストレスや不安、時にはトラブルを生む要因となります。
また、例え話としてひとつ紹介します。
ある60代の男性が、自分の死後に子どもたちが迷わないようにと、遺言書を作成し、エンディングノートに葬儀の形式や保有財産の一覧までまとめました。
その方が亡くなった後、家族は悲しみに包まれながらも、落ち着いて対応を進めることができ、「父がすべて考えてくれていたんだね」と、感謝の言葉が自然と出てきたといいます。
終活は、単なる事務的な整理ではなく、家族への最後の思いやりの形でもあるのです。
ちなみに、家族の中に高齢の親がいる場合、本人が終活に踏み切れないケースもあります。
その際は、エンディングノートなどのツールを一緒に使いながら話題にしてみるとスムーズに進めやすくなります。
そしてもう一つは、介護方針の共有です。
自分の希望を明記しておけば、たとえ認知症などで意思が伝えられなくなっても、家族が迷わず判断できる環境が整います。
終活を始めることで見えてくる安心感は、実際にその時を迎えた家族にとって何よりの支えとなるでしょう。
このように、終活は「死に備える準備」ではありますが、その本質は家族の未来を守るための思いやりの行動です。
それでは次に、終活という言葉の語源と背景を見ていきましょう。
終活なんの略?本当の意味と背景
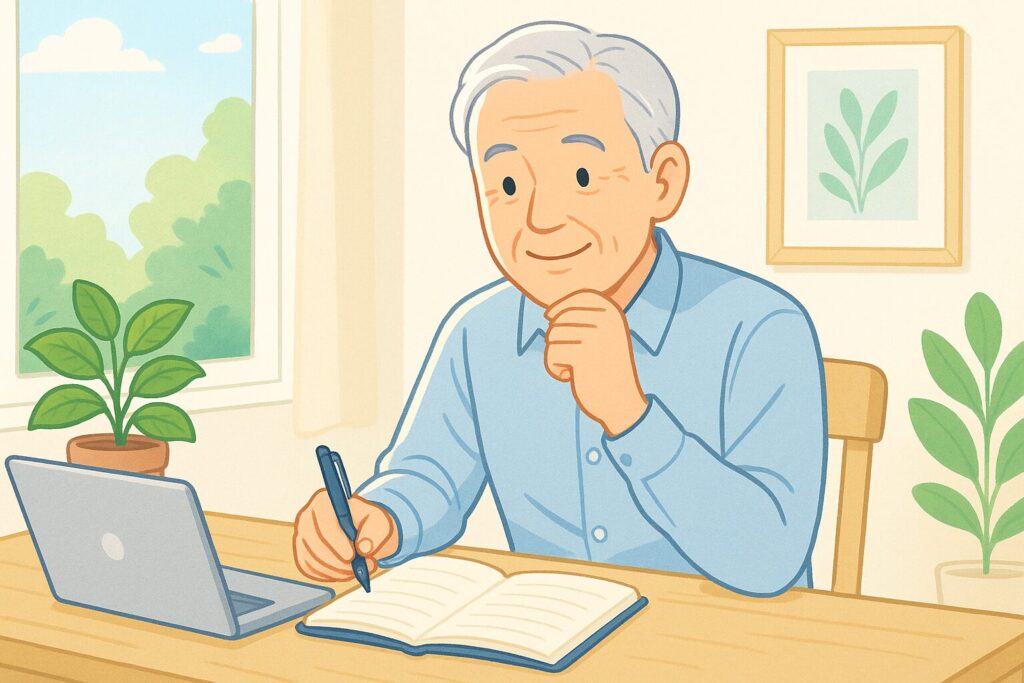
「終活(しゅうかつ)」という言葉は、“人生の終わり”に向けた活動=終末活動を略したものです。
この言葉が広まったきっかけは、2009年に週刊朝日が「終活特集」を組んだことが大きいとされています。
それまで、人生の終末期の準備については「遺言」や「生前整理」という言葉で語られることが多かったのですが、「終活」はそれらを包括し、よりライフスタイルに近い感覚で捉えられる表現として浸透していきました。
ここで一度、終活という言葉が含む要素を整理しておきましょう。
| 表現 | 内容 |
|---|---|
| 終活 | 人生の終わりに向けての準備全般(法的整理・心の整理) |
| 生前整理 | 財産・物品の整理。身辺の物理的な整理 |
| エンディングノート | 医療・介護・葬儀・メッセージなどの本人の意向をまとめた記録 |
| 遺言書 | 法的効力を持つ、財産分与に関する最終意思表示 |
このように、終活は単なる片付けや契約書類の整備にとどまらず、精神的・社会的な面までを含む幅広い準備であることがわかります。
たとえば、就職活動を「就活」と呼ぶようになったことで、「人生の節目をどうデザインするか」という発想が一般化しました。
その流れをくむように、自分らしい最期を迎えるための準備=終活という発想が受け入れられたのです。
就活が人生のスタートをデザインするものであれば、終活は人生の終わりを自分の価値観で彩る行為ともいえます。
言ってしまえば、終活とは「人生を締めくくるセルフプロデュース」です。
誰にどう見送られたいか、残された人たちに何を伝えたいか。
それを形にする手段が終活なのです。
私の場合、「終活なんてまだ早い」と思っていた祖父が、新聞の特集記事を読んで意識を変え、数年かけて整理を始めました。
そのおかげで、葬儀の準備から遺品整理まで、本当に驚くほどスムーズに進み、親族一同がその判断力と準備に感謝したのを今でも覚えています。
このように、終活という言葉は決して堅苦しいものではなく、自分と向き合うきっかけになる言葉として、多くの人の心に浸透しています。
そして終活の出発点として多くの人が疑問に思うのが、「何から始めるべきか」という点です。
終活をやらないとどうなる?リスクと困ること
終活を後回しにすると、遺された家族に大きな負担やトラブルを残す可能性があります。
それはちょうど、長年住んでいた家を片付けないまま引っ越し日を迎えてしまうようなものです。
本人は気づいていなくても、整理されていない財産や意志が、あとで家族を悩ませることにつながります。
終活をやらなかった場合に起こりやすい「困ること」は、大きく分けて以下のように整理できます。
| 困ること | 内容 |
|---|---|
| 遺産相続トラブル | 遺言書がなく、相続人間で意見が食い違い争いになる可能性が高まる |
| 医療や介護の方針が不明 | 延命治療や施設の選択など、本人の意志が不明なまま家族が苦渋の選択を迫られる |
| 葬儀方法や費用で混乱 | 希望が伝わっていないため、準備が遅れ費用も膨らみがち |
| 財産の把握が難しい | 通帳や不動産、証券の所在がわからず、名義変更などに時間がかかる |
| 遺品整理が大変 | 本人しかわからないモノが大量に残り、心理的にも時間的にも負担が重くのしかかる |
例えば、実際に終活をしていなかった70代男性が亡くなったケースでは、相続人である2人の子どもが、父親の預金口座の存在を知らず、通帳を探すのに3か月以上かかったことがあります。
また、父親がどの保険に加入していたか不明だったため、保険金の請求ができず失効してしまった例も報告されています。
これらはほんの一部に過ぎず、終活を行わないことで、家族が一から調べ、判断し、処理する負担が大きくなってしまうのです。
さらに、相続トラブルについては次のような統計もあります。
| 相続トラブル発生の有無 | 割合(全国相続実態調査より) |
|---|---|
| トラブルがあった | 約32% |
| トラブルはなかった | 約68% |
およそ3人に1人が相続に関するトラブルを経験しているという事実からも、終活の準備の有無が将来的な安心に直結することがわかります。
ちなみに、終活は「高齢者だけのもの」ではありません。
若い世代でも、介護や医療の希望、もしもの時の対応について考えることは、現代社会における備えのひとつといえます。
むしろ、余裕のある時期だからこそ冷静に判断でき、必要な準備がスムーズに進められるのです。
では次に、そんな終活はいつ始めるのが適切かについて見ていきましょう。
終活は何歳から始めるべき?適齢期の目安とは

終活に「絶対この年齢から」という明確な決まりはありませんが、多くの専門家は60代前後を目安として推奨しています。
ただし、それはあくまで一般的な傾向であり、実際にはもっと早く始めても問題はありません。
終活の開始年齢に関する目安を、年代別に整理すると次のようになります。
| 年代 | 終活の始めどきの目安 | 主な目的や行動内容 |
|---|---|---|
| 20〜30代 | 興味や関心があるときが始めどき | エンディングノートの作成、医療・介護の希望のメモなど |
| 40〜50代 | 親の介護が始まる、または自分の健康が気になる頃 | 財産の棚卸し、保険や資産運用の見直し、家族との話し合い |
| 60〜70代 | 退職後の時間を使って進めやすい時期 | 遺言書の作成、葬儀の希望、財産分与の整理、身の回りの物の処分 |
| 80代〜 | 判断力のあるうちに済ませることが大切 | 残された部分の見直しや修正、家族への引き継ぎ |
たとえば、50代で終活を始めた方のケースでは、親の介護を経験したことで、自分の将来に備える重要性を痛感し、介護保険の見直しやエンディングノートの作成を進めていきました。
この方は「親の準備不足で自分が大変だった分、自分の子どもには苦労をかけたくない」と語っています。
こうした実体験に基づく判断こそが、終活を早く始めるメリットをよく表しているのではないでしょうか。
さらに、終活を始めるタイミングには、気持ちのゆとりや家族との関係性も影響します。
前述の通り、終活は本人のためだけではなく、家族のための準備でもあります。
焦って進めるよりも、計画的に、できることから少しずつ始めるのが理想です。
終活 20代でもやる意味はある?若いうちの備え方
「終活」と聞くと、どうしても高齢者のための活動というイメージが強いかもしれません。
ですが、20代の若い世代にも、終活には十分な意味があります。
むしろ、若いうちだからこそ気づけること、考えられることがあるのです。
終活の基本的な目的は、「自分の死後に家族が困らないようにするための準備」と「自分らしい人生を振り返り、これからを充実させていくための活動」です。
20代のうちは、介護や葬儀、相続といった現実的な課題を感じにくいかもしれません。
ですが、若いうちに終活的な考え方を取り入れておくことは、将来の選択を自分でコントロールする力にもつながります。
例えば、終活の一部に「エンディングノートの作成」がありますが、これを20代で書く場合、こんな内容が考えられます。
| 若い世代のエンディングノートの項目 | 書いておく内容例 |
|---|---|
| 緊急連絡先 | 家族や信頼できる友人の電話番号、LINE IDなど |
| 医療・介護の希望 | 万一の事故や重病時に希望する医療(延命措置の有無など) |
| 所有するサービスアカウント | SNSやサブスク、スマホアプリのID・パスワード |
| ペットや植物のこと | 万が一の際の引き取り先や世話の方法 |
| 自分の価値観・将来の夢 | これまでの人生で大切にしてきたこと、今後挑戦したいことなど |
ある20代女性は、大学卒業と同時に一人暮らしを始めたタイミングで、エンディングノートを作成しました。
きっかけは、知人の突然死で「自分が急にいなくなったら、誰に連絡が行くのか不安になったから」だそうです。
彼女は緊急連絡先や、スマホに残している写真データの保管先、葬儀では流してほしい音楽まで書き残していました。
結果として、日々の生活を**「自分らしく、誰かのためにも」意識するようになった**と語っています。
もう少し視点を広げてみると、20代からの終活的思考は「人生設計そのもの」に役立つとも言えます。
たとえば、
- 老後の生活費をどう貯めるか
- 結婚するか、しないか
- 子どもを持つか持たないか
- 親の介護が必要になったらどうするか
こうした「まだ先の話」と思えることに対して、少しでも準備のイメージを持てること自体がリスク回避につながるのです。
さらに、終活は単に「死に備えること」だけではありません。
**「モノを持ちすぎない」「人間関係を整える」「生き方を定期的に見直す」**など、自分の価値観を明確にしていく活動でもあります。
いわば、自分の人生の“設計図”を整理する作業です。
ちなみに、若いうちに身軽にしておくことで、突然の引っ越しや転職、介護のサポートなどにも対応しやすくなります。
物も情報も整理されていれば、必要な時にすぐに行動できるのは、大きな安心につながるはずです。
こうした「いつかやる」を「今やる」力こそ、若いうちの終活の意味といえるでしょう。
終活とは?意味と始め方をわかりやすく解説

終活 何から始める?初心者がすべき準備
初めて終活を考えるとき、何から手をつければ良いのか戸惑う方は少なくありません。
ですが、一歩ずつ整理していけば、決して難しいことではありません。
まず大切なのは、自分の人生を振り返るところから始めることです。
そのうえで「どんな準備が必要か」を整理していくと、自然とやるべきことが見えてきます。
たとえば、「終活=遺言書を書くこと」と思っている方も多いですが、それだけではありません。
むしろ、生活の土台や人間関係を整えることも大事な終活の一部です。
ここでは初心者の方でも無理なく進められるよう、終活の準備ステップを具体的に整理しました。
| ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 自分の現状を整理 | 所有資産、契約中の保険、加入しているサービスをリスト化 |
| 2 | 家族への希望を考える | 葬儀の形、介護の希望、緊急連絡先をまとめておく |
| 3 | エンディングノートを作成 | 遺言書より自由度が高く、自分の思いを記録しやすい |
| 4 | 不用品や書類を整理 | モノの整理を通じて気持ちもスッキリ。遺品整理の負担も減らせる |
| 5 | プロに相談(FP・弁護士) | 相続や保険については専門家に一度確認しておくと安心 |
例えば、「保険の見直し」を始めた方が、そこから「葬儀の費用」や「相続税対策」にも目が向くようになったという話があります。
このように、一つ行動を起こすことで次のステップが自然とつながっていくのが終活の良さです。
私が以前担当したお客様では、60代前半の男性が「まずエンディングノートだけでも」と始めたことがきっかけでした。
そこから家の整理を始め、結果的に遺言書も作成され、最終的には介護のことまで考えるようになったのです。
特に印象的だったのは、「家族の中で終活を最初に始めたことで、親子の会話が増えた」とおっしゃっていた点です。
家族の未来を守るための準備が、今の生活の充実にもつながるということを実感しました。
ちなみに、最初の一歩として「エンディングノートだけ書いてみる」というのはとても良い方法です。
紙で用意するのも良いですし、最近ではスマホやパソコンで作成できるフォーマットも充実しています。
こうして基本を押さえておくことで、次のステップにもスムーズに進めることができます。
続いては、終活において大切にすべき基本項目を詳しく見ていきましょう。
終活で大切な10ことは何ですか?基本をチェック

終活にはさまざまな要素がありますが、まずは基本の10項目を押さえておくことが大切です。
これらは、自分のためだけでなく、家族のためにもなる準備です。
下記に、初心者の方が意識すべき終活の基本項目を整理しました。
| 項目 | 内容とポイント |
|---|---|
| 1. 自分の資産を把握する | 預貯金、不動産、有価証券などを一覧に。デジタル資産(仮想通貨、サブスク)も要確認 |
| 2. 医療・介護の希望をまとめる | 延命治療の意向、認知症への備えなど。事前指示書や尊厳死宣言書の活用も |
| 3. 葬儀のスタイルを決める | 一般葬、家族葬、直葬など。費用の目安や希望も伝えておくと家族の負担を軽減 |
| 4. 遺言書の作成 | 法的効力を持たせるなら公正証書がおすすめ。資産分配の意向は明文化する |
| 5. エンディングノートの記入 | 自由形式で自分の想いを記す。家族に読んでほしい手紙も含められる |
| 6. パスワードや契約情報の整理 | SNSやスマホ、ネット銀行のアカウント管理が重要に。ログイン情報は信頼できる形で保管 |
| 7. 持ち物の整理・片付け | 生前整理をすることで遺品整理の負担を軽減。片付けが心の整理にもつながる |
| 8. 家族への感謝を形にする | 手紙や音声、動画メッセージなども有効。感情の伝達は文字以上に大切 |
| 9. 保険の見直し | 保障内容が今の生活に合っているか確認。相続税の非課税枠にも活用可能 |
| 10. 法律・税務の知識を確認 | 相続税、贈与税、成年後見制度など。制度理解がトラブル防止に役立つ |
例えば、「持ち物の整理」がうまく進まなかった方が、「1日1アイテムだけ捨てる」というルールにしたことで続けられた、という事例があります。
完璧を目指すより、できる範囲で習慣化することが成功のコツだと実感されていました。
また、40代の女性が実母の終活を手伝ったことで「自分もそろそろ始めようかな」と思うようになったという声もあります。
家族との会話の中で自然と終活のテーマが出てくると、お互いの考えを知る機会にもなります。
ちなみに、保険の見直しについては、「終身保険」や「医療保険」が相続や介護の備えとして注目されています。
中には、相続税の非課税枠を活用する目的で保険に加入するケースも少なくありません。
これらの項目を無理なく少しずつ取り入れていくことが、終活を続ける大きな力になります。
終活 エンディングノートの活用法と記入のコツ
エンディングノートは、終活の中でも多くの方にとって手軽に始められる第一歩です。
形式にとらわれず、自分の気持ちや希望を書き残せる点が大きな特徴です。
ですが、「何を書いたらいいのかわからない」「書き方が不安」という声も少なくありません。
ここでは、エンディングノートの具体的な活用方法と、記入のコツを整理してご紹介します。
まず、エンディングノートと遺言書の違いを理解することが大切です。
エンディングノートには法的効力がありませんが、その分自由度が高く、気持ちや価値観を表現しやすくなっています。
| 項目 | エンディングノート | 遺言書 |
|---|---|---|
| 法的効力 | なし | あり |
| 書き方 | 自由形式 | 法律で定められた形式が必要 |
| 主な目的 | 気持ちや希望の共有 | 財産の分配や法的手続きの指示 |
| 修正のしやすさ | 何度でも自由に修正可能 | 公正証書の場合は手続きが必要 |
書く内容は人それぞれですが、以下のような項目を押さえておくと、家族にとっても実用的な手がかりになります。
- 緊急連絡先
- 医療・介護の希望(延命治療の有無、入院時の希望など)
- 葬儀のスタイルや連絡してほしい人
- 財産・保険の情報
- デジタル遺産(パスワード、SNSアカウントなど)
- メッセージや感謝の言葉
たとえば、ある70代の女性は、エンディングノートに「私が好きだった歌」「旅の思い出」「孫に伝えたい言葉」を記しました。
これが家族にとっては、葬儀のときの音楽選びや、遺品整理の際の判断材料になったそうです。
本人の「人生の軌跡」を知るきっかけにもなり、親族の会話が深まったと聞いています。
書くときのコツとしては、「一気に仕上げようとしないこと」が重要です。
ページごとにテーマが分かれているものを選び、1日1ページだけ書くようにすると、負担が軽減されます。
また、ペンで書くだけでなく、音声メモや動画で残しておくのも最近のトレンドです。
ちなみに、エンディングノートは100円ショップや書店で販売されているほか、無料のテンプレートをダウンロードできるサイトも増えています。
ご自身のライフスタイルに合った形で進めてみてください。
こうして自分の思いを言葉にする作業は、同時にこれからの人生を整理し、より充実させるための機会にもなります。
次は、より視野を広げて理想の老後を描くために役立つ「終活100のリスト」についてご紹介します。
終活 100のリストで理想の老後を描こう
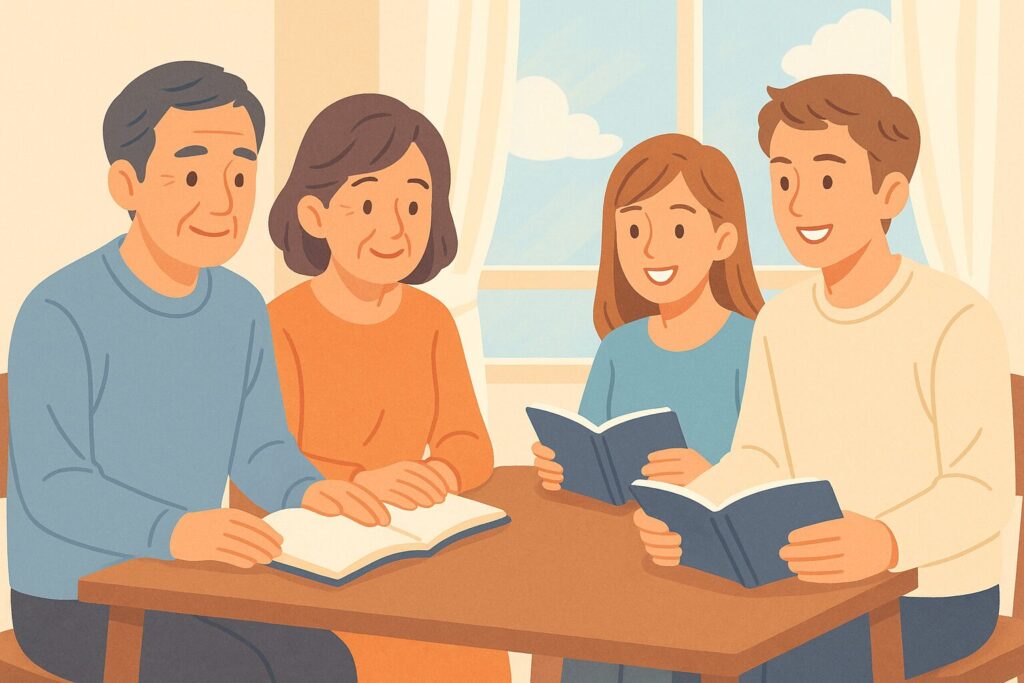
「終活100のリスト」とは、老後や人生の終盤に向けてやっておきたいことを100個書き出すリストのことです。
バケットリストや夢リストとも呼ばれ、自分らしい人生を送るための道しるべになります。
このリストの良いところは、ただの願望だけでなく、終活に関する具体的な準備も一緒に書き出せる点です。
以下のように、生活・感情・準備の3ジャンルに分けてリストを作るとバランスが取れやすくなります。
| ジャンル | 内容の例 |
|---|---|
| 人生を楽しむ | ・夫婦で温泉旅行へ行く ・思い出の地を訪れる |
| 感謝を伝える | ・両親に手紙を書く ・孫にアルバムを作る |
| 準備を整える | ・遺言書を作成する ・介護施設の見学に行く |
例えば、60代の男性が「100のリスト」を作成したところ、**10個目で「自宅の整理をする」**という項目にたどり着きました。
それをきっかけに断捨離を始めたところ、押し入れの奥から亡き奥様の手紙が出てきたそうです。
手紙には「私がいなくなっても、あなたが楽しく暮らせますように」と書かれていたとのこと。
これが、彼の終活を加速させる原動力になったというエピソードがあります。
このように、リストに書き出すことで気持ちの整理が進み、漠然とした不安が行動に変わっていくのが特徴です。
「書いてみたけれど、思いつかないことが多い」と感じたら、以下のようなキーワードを参考にしてください。
- 行きたい場所
- 話しておきたい人
- 伝えたい想い
- 見直したい契約(保険、スマホ、銀行)
- 片づけたい部屋
- 見ておきたい映画や舞台
- 調べておきたい介護施設やサービス
ちなみに、完成を目指すことが目的ではありません。
途中でリストの内容が変わっても、書き換えても構わないのです。
人生の方向性を明るく描くツールとして、思いつくたびに追記していくスタイルで十分です。
こうしてリスト化することで、日常にワクワク感が生まれ、結果的に今の生活も充実していきます。
終活 50代から始めるならこれがポイント
50代は、終活を始めるのにもっとも適したタイミングだとよく言われます。
それは体力も気力もまだ十分にあり、仕事や家庭の節目に差し掛かる年代だからです。
また、親の介護が現実になってくる時期でもあり、「自分の老後」について考える機会も自然と増えてきます。
ここでは、50代からの終活をスムーズに進めるためのポイントをわかりやすくまとめました。
まず確認したいのは、50代の終活が他の世代とどう違うのかという点です。以下に特徴を整理しました。
| 世代 | 特徴 | 主な終活の内容 |
|---|---|---|
| 20〜30代 | 経験や知識が浅く、将来像が曖昧 | 保険・貯蓄の見直し、エンディングノートの導入など |
| 40代 | 家庭・仕事の両立期、親の介護問題が始まる | 財産把握、家族への意志表示など |
| 50代 | 人生の折り返し地点、子育てや住宅ローンも落ち着く | 介護・葬儀の希望明記、遺言書の準備、住まいの整理 |
| 60代以降 | 健康に不安が出てくる、退職期を迎える | 相続計画、葬儀・墓の選定、身辺整理など |
このように、50代は前向きに準備できるラストチャンスのような世代ともいえるのです。
とくに以下の3つのポイントを押さえておくと、後の手続きが格段に楽になります。
- 住まいの整理と資産の把握
持ち家やローン、保有している不動産がある方は、この時期に一度見直しましょう。
「使っていない部屋がある」「子どもが巣立った後の生活を考えたい」という方は、
老後のライフスタイルに合った住み替えやリフォームを検討するのもおすすめです。 - 保険や年金の確認
医療・介護・死亡保障といった保険が、自分の現状に合っているかを再確認します。
特に、介護保険の保障内容をしっかり把握しておくことが大切です。
加入状況と年金見込み額を一度まとめておくと、後のプランニングがしやすくなります。 - 家族への意志表示
介護や葬儀に対する考えを、口頭だけでなくエンディングノートなどに記録しておきましょう。
これは将来的なトラブルを防ぐと同時に、家族の精神的な負担も大きく減らします。
たとえば、ある50代の男性は、50歳の誕生日を機にエンディングノートを書き始めました。
最初は抵抗があったそうですが、両親の介護を経験していたことから、
「自分が動けなくなったとき、子どもに迷惑をかけたくない」という気持ちが原動力になったと話しています。
実際に書いてみると、「老後の住まいはどうしたいのか」「もし認知症になったらどうしたいのか」など、
自分でも気づかなかった不安が整理されていき、気持ちが軽くなったと感じたそうです。
このように、50代からの終活は「不安の整理」と「人生の棚卸し」の両方に効果があります。
次に、終活という言葉にこだわらず、別の表現をどう使い分けるかについても見ていきましょう。
終活 別の言い方も紹介!使い分けのヒント

「終活」という言葉に、少し重さを感じる方も多いかもしれません。
実際、終活という響きに対して「死の準備みたいで気が滅入る」といった声もよく耳にします。
ですが、呼び方を変えるだけで、心のハードルがぐっと下がることもあるのです。
ここでは、終活の“別の言い方”とその使い方のヒントをご紹介します。
以下の表は、終活を表す際によく使われる表現と、それぞれのニュアンスの違いをまとめたものです。
| 表現 | 意味・使い方 |
|---|---|
| ライフプラン整理 | 経済面や生活設計の見直しを強調したいときに使える |
| 人生の棚卸し | 自分の経験や価値観を振り返る意味合いが強い |
| 第二の人生の準備 | リタイア後の生活を前向きにとらえる表現 |
| エンディングプランニング | 葬儀・お墓・相続など、死後の準備に焦点を当てた表現 |
| セカンドライフ設計 | 趣味や生きがいに重点を置きたい場合に適している |
たとえば、60代の女性が「終活って言葉はちょっと嫌だから、私は“セカンドライフ設計”って言ってるの」と話してくれました。
その言葉に変えるだけで、準備する行為が前向きなものに思えてくると感じたそうです。
このように、終活の本質は変わらなくても、表現次第で周囲や本人の捉え方はガラリと変わります。
特に家族と話すときには、「終活しよう」ではなく、「これからの暮らしを一緒に考えたい」という柔らかい言い方の方が、
受け入れやすいことも多いです。
ちなみに、金融機関や保険会社では「エンディングサポート」や「ライフエンディング設計」といった言葉を使うケースが増えています。
これは終活をサポートサービスとして提供する際、顧客の不安を和らげるために意識的に穏やかな表現を使っているからです。
このように、言葉選び一つで、終活に対する抵抗感が減り、家族とのコミュニケーションも円滑に進みやすくなります。
終活を始める年齢は?世代別おすすめの準備内容
終活を始める年齢に明確な決まりはありませんが、それぞれのライフステージによって適した準備内容が変わってきます。
つまり、どの年齢であっても、無理なくできる範囲から進めることが大切です。
ここでは、世代別に終活で意識しておきたいポイントをわかりやすくご紹介します。
まずは、以下のように世代ごとの準備内容を整理してみました。
| 年代 | 特徴 | おすすめの終活内容 |
|---|---|---|
| 20代 | 経済的・精神的に余裕が少ない | ライフプランの可視化、将来の医療や介護への関心を持つこと |
| 30代 | 家族を持ち始める、住宅購入など大きな選択期 | 保険の見直し、資産の整理、簡単なエンディングノート作成など |
| 40代 | 親の介護が現実に、教育費・住宅ローンが重なる | 親の終活支援、自身の保険や資産の見直し、家族への意志伝達 |
| 50代 | 子育て終了、定年までの見通しが立つ | 遺言書・介護方針の準備、葬儀や墓の選定、身の回りの整理 |
| 60代 | 退職、持病など健康への不安が増す | 財産管理、後見制度の検討、信託や相続手続きの下準備 |
| 70代以降 | 身体的負担が大きくなる | 実際の手続き実行(遺言執行者の選定など)、介護施設の検討など |
たとえば、ある60代のご夫婦は「まだ元気だから」と思いながらも、親の葬儀と相続を経験したことがきっかけで、
早めに自分たちのエンディングノートを用意しました。
実際に記入してみると「自分たちの望む葬儀はどんな形か」や「子どもに伝えておきたいこと」が明確になり、
家族との対話のきっかけにもなったと話しています。
このように、年齢に合わせた準備をしていくことで、終活は重く考えすぎずに自然と日常に取り入れられるものになります。
ちなみに、早すぎる準備には「忘れてしまう」「制度が変わって使えない」といった注意点もありますが、
内容を定期的に見直す習慣さえ持てれば問題ありません。
このように、年齢に応じて少しずつ段階的に進めるのが理想ですが、次に紹介する支援サービスや制度をうまく活用することで、
より効率的に終活を進めることができます。
終活に使える便利なサービス・支援制度

終活を進めるうえで、「何から始めればいいのかわからない」「手続きが複雑で一人では難しい」といった不安を抱える方は少なくありません。
そんなときに役立つのが、各種の支援制度や民間サービスです。
ここでは、初心者でも安心して利用できる終活関連のサービスをいくつかご紹介します。
以下に、よく使われている終活支援サービスとその内容を整理しました。
| サービス名・制度 | 内容 | 主な対象者・メリット |
|---|---|---|
| 市区町村の終活講座 | 終活ノートの書き方や介護制度の基本を学べる公的講座 | 初心者、費用が安く地域に密着 |
| 法テラスの無料相談 | 相続・遺言・成年後見制度など法律的な支援を受けられる | 法的な不安がある人、無料で専門家の意見が聞ける |
| 成年後見制度 | 判断能力が低下した場合に備えて財産・身上を守る制度 | 認知症や高齢者の支援に必要 |
| エンディングノート作成支援 | 民間業者や保険会社によるノート配布や書き方サポート | 書き方がわからない人、テンプレートが便利 |
| 遺品整理・生前整理サービス | プロの業者が不用品の整理・処分をサポート | 一人暮らし、遠方に家族がいる方など |
| デジタル遺品整理サービス | スマホやSNSのアカウント整理、クラウドデータ削除など | デジタル世代に特化、家族が知らない情報の対策に有効 |
たとえば、ある70代の男性は、地域の社会福祉協議会が主催する「終活セミナー」に参加したことで、
「遺言書をきちんと残すことで、家族が相続で揉めなくなる」と気づき、
実際に行政書士に相談して公正証書遺言を作成したそうです。
このようなサービスを利用することで、専門知識がなくても安心して準備を進められるのは大きなメリットです。
また、費用や手間の面でも比較的ハードルが低いものが多いため、まずは身近な行政サービスから利用してみるのもおすすめです。
終活とは?意味と始め方をわかりやすく解説する総まとめ
- 終活とは人生の最期に備えて身の回りや想いを整理する活動
- 最大の目的は家族の精神的・経済的な負担を減らすこと
- 葬儀や遺品整理、相続など死後のトラブルを事前に回避できる
- エンディングノートで医療や介護の希望を明確にできる
- 遺言書の作成で相続トラブルの発生リスクを下げられる
- 財産や契約の情報をリスト化することで手続きがスムーズになる
- 生前整理によって不要なモノを処分し遺品整理が楽になる
- デジタル遺産の管理も終活で重要なポイントとなっている
- 自分らしい最期を迎えるための「人生のセルフプロデュース」とも言える
- 家族との対話を促すきっかけとしても有効に機能する
- 始める年齢に決まりはなく、20代からでも意味がある
- 「何から始めるか」は現状の棚卸しから始めると進めやすい
- 100のリストでやりたいことを見える化し老後の充実に役立てられる
- 表現を変えることで終活に対する心理的抵抗をやわらげられる
- 公的支援や専門家サービスを活用すれば手軽に始められる

お気軽にご相談ください
相続は100人いれば、100通り
唯一無二の最適な相続をご提案いたします
CONTACT
専門家やえさん

- 専門家やえさん
-
堀川 八重(ほりかわ やえ)
大阪不動産・FPサービス株式会社 代表
15年以上にわたり1,500組を超えるご家族の相続や不動産のお悩みに、専門家として寄り添ってまいりました。私の信条は、法律や数字の話をする前に、まずお客様ご家族の歴史や言葉にならない想いを丁寧に「聞く」こと。信頼できる各分野の専門家チームと共に、皆様が心から安心できる最善の道筋をオーダーメイドでご提案します。一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。
最新の投稿
 お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説
お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説 相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説
相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説 お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例
お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例 お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説
お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説






