「え、この道も相続財産なの!?」なんて、ある日突然、私道共有持分名義変更という難問に直面していませんか?親が亡くなって、家の相続手続きはなんとなくわかるけど、私道が共同所有の場合、相続はどうなるの?共有名義の相続で名義変更は必要?
持分2分の1だけ相続したけど、相続登記って持分のみでもできるの?など、疑問が次から次へと湧いてきますよね。共有私道でよく起こるトラブルの話を聞くと、不安で夜も眠れないかもしれません。
さらに、共有持分の相続では遺産分割協議書や登記申請書の書き方も特別で、私道の名義変更にかかる費用や、共有名義から単独名義に変更する費用も気になるところ。
この複雑な手続き、放置すると大変なことになるかも…!この記事で、そんなあなたの悩みをスッキリ解決します!
この記事のポイント
- 私道共有持分の相続で何が問題になるかわかる
- 名義変更の具体的な手続きと流れを理解できる
- 必要な書類の書き方と注意点がわかる
- 名義変更にかかる費用や税金の目安がわかる
目次
私道共有持分名義変更の前に知るべきこと

私道が共同所有の場合、相続はどうなりますか?
「実家の前の道、実は私道でしかもお隣さんと共有だった!」なんてこと、結構あるんですよね。こんにちは!これまで数々の不動産案件に携わってきたWEBライターの私です。今日は、分かりにくい私道の相続について、一緒に見ていきましょう!
まず結論から言うと、私道が共同所有の場合でも、その持分は土地や建物と同じように立派な相続財産になります。つまり、亡くなった方(被相続人)が持っていた私道の権利(持分)は、相続人が引き継ぐことになるんですね。
「え、道も財産なの?」と驚かれるかもしれませんが、私道は国や市町村が管理する「公道」と違って、個人や複数の人たちが所有している「個人の土地」なんです。だから、その土地の所有権の一部である「共有持分」も、当然ながら相続の対象となります。
私が以前担当したお客様も、お父様が亡くなった後の相続手続きで、初めてご実家の前の道路が近隣5軒での共有名義になっていることを知って、すごく驚かれていました。「固定資産税の納税通知書」に、家の土地とは別に小さな土地(公衆用道路)が記載されていて、そこで発覚したんです。非課税の「公衆用道路」だと通知書に載ってこないこともあるので、さらに気づきにくいんですよ。
この私道の持分を相続した場合は、家や他の土地と同じように、相続人全員で「この私道の持分は誰が相続する?」という話し合い(遺産分割協議)をして、決まった人の名義に変更する「相続登記」という手続きが必要になります。
もしこの手続きを忘れてしまうと、後々「家を売りたいのに売れない!」「建て替えができない!」なんていう、とんでもない事態に発展することもあるので、注意が必要なんです。次の項目では、その恐ろしいトラブルについて詳しく見ていきましょう。
共有私道でよく起こるトラブルは?
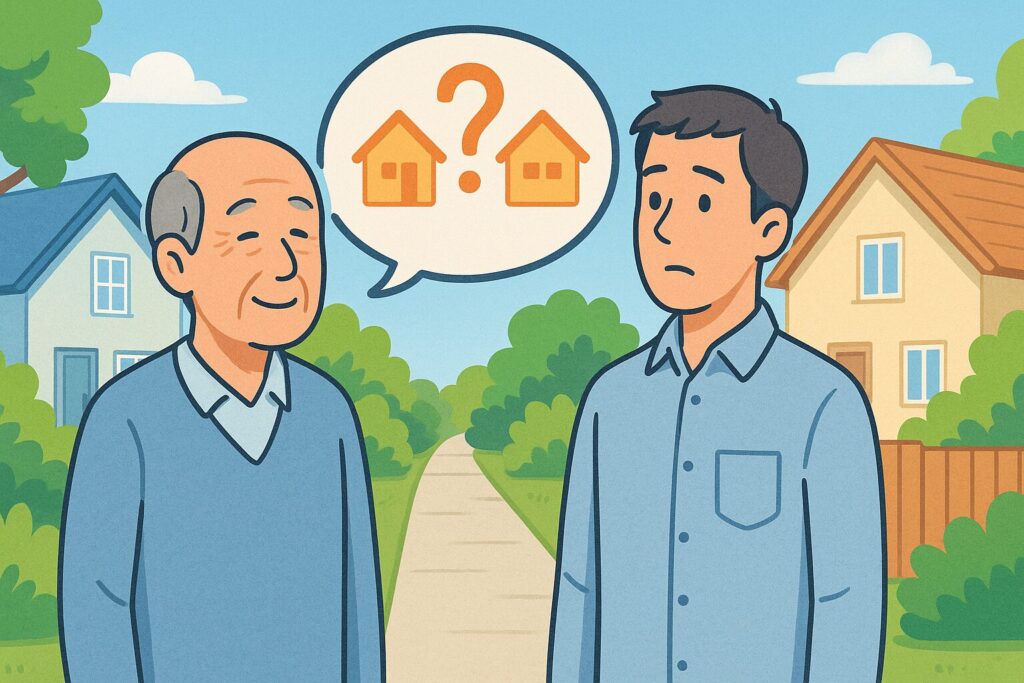
「共有」って聞くと、なんだかみんなで協力し合う良いイメージがありますけど、不動産の世界、特に共有私道では、残念ながらトラブルの火種になることが多いんです…。ここでは、実際に起こりがちなトラブルをいくつかご紹介しますね。
① 通行や掘削に関するトラブル
共有私道は、共有者全員のものです。そのため、何か大きな変更を加えようとすると、共有者全員の同意が必要になるのが原則です。
例えば、こんなケースがありました。
【失敗談】建て替えたいのに…水道管工事に反対された!
Aさんは、相続した実家を二世帯住宅に建て替えることにしました。しかし、建て替えには水道管やガス管を新しいものに引き直す必要があり、共有私道を掘削しなければなりません。
Aさんは他の共有者に工事の同意を求めましたが、共有者の一人であるBさんから「道路を掘り返すなんてとんでもない!絶対に許可しない!」と、猛反対されてしまったのです。結局、Bさんの同意が得られず、建て替え計画は頓挫してしまいました…。
このように、自分の家の建て替えやリフォームであっても、私道を掘削する必要がある場合、他の共有者の同意がなければ進められません。他にも、車の通行を巡って「駐車の仕方が気に入らない!」といった些細なことから、ご近所トラブルに発展するケースも少なくないんですよ。
② 売却や担保設定に関するトラブル
私道に面した土地や建物を売却する場合、通常は私道の共有持分もセットで買主に移転させます。なぜなら、私道の持分がなければ、買主は家の前の道を使えないという、とんでもない事態になってしまうからです。
しかし、相続登記を忘れていて、亡くなったお父さんの名義のままだった…なんてことになると、売却手続きはストップしてしまいます。買主が見つかってから慌てて相続登記をしようとしても、他の相続人が協力してくれなかったり、連絡がつかなかったりすると、売買契約そのものが白紙になってしまう可能性もあるのです。
また、不動産を担保にお金を借りる(抵当権設定)場合も、共有者全員の同意が必要です。一人でも反対すれば、ローンを組むことはできません。
共有私道トラブルのポイント
- 道路の掘削や工事には共有者全員の同意が必要
- 売却時は私道持分もセットでないと買い手がつかない
- 相続登記を忘れていると売却できない
- 担保設定(ローン)にも共有者全員の同意が必要
これらのトラブルを避けるためにも、相続が発生したら、速やかに自分の名義に変更しておくことが、とっても重要になるわけですね。
共有名義の相続と名義変更の基本
さて、共有私道の重要性とトラブルがわかったところで、次は「じゃあ、具体的にどうやって名義変更するの?」というお話に進みましょう。共有名義の不動産を相続したときの名義変更(相続登記)は、基本的な流れは単独名義の不動産とほとんど同じです。
大まかな流れは、以下のようになります。
- 相続人を確定させる(戸籍集め)
- 遺産分割協議を行う
- 必要書類を揃えて登記申請する
一つずつ見ていきましょう!
1. 相続人を確定させる
まず、誰が相続人になるのかを法的に確定させる必要があります。そのために、亡くなった方(被相続人)の「生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)」を集めます。これで、配偶者や子供、親、兄弟姉妹など、法律上の相続人が誰なのかが全て判明するんです。
これが意外と大変な作業で…。本籍地が何度も変わっている方だと、全国の役所に請求をかける必要があって、全部集めるのに1~2ヶ月かかることも珍しくありません。司法書士に依頼すれば、この戸籍集めから代行してもらえるので、時間がない方や手続きが苦手な方にはおすすめです。
2. 遺産分割協議を行う
相続人が全員確定したら、その全員で遺産の分け方を話し合います。これを「遺産分割協議」といいます。この協議で、「実家の土地と建物、そして共有私道の持分は、長男の〇〇が相続する」といったように、誰がどの財産を取得するかを決めます。
話し合いがまとまったら、その内容を証明するために「遺産分割協議書」という書類を作成し、相続人全員が署名し、実印を押します。この書類が、後の登記手続きで非常に重要な役割を果たすんですよ。
3. 必要書類を揃えて登記申請する
遺産分割協議書ができたら、いよいよ法務局へ名義変更の申請(相続登記)をします。申請には、遺産分割協議書のほか、集めた戸籍謄本一式、相続人全員の印鑑証明書、新しい名義人になる人の住民票、固定資産評価証明書など、たくさんの書類が必要です。
これらの書類を揃えて「登記申請書」を作成し、不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。申請に不備がなければ、1~2週間ほどで登記が完了し、晴れてあなたの名義に変更される、という流れになります。
これが、共有名義不動産における相続と名義変更の基本的な方法です。次の項目では、もう少し具体的なケースを見ていきましょう。
持分2分の1を相続するケース

「共有持分」と一言で言っても、その割合は様々ですが、実務で非常によく見かけるのが「持分2分の1」というケースです。特に、ご夫婦でマイホームを購入された場合に多いんですよ。
例えば、家を買うときに、ご主人と奥様がそれぞれお金を出し合ったり、ペアローンを組んだりすると、その出資割合に応じて不動産の名義を「夫 持分2分の1、妻 持分2分の1」のように共有名義で登記します。これが、持分2分の1が生まれる典型的なパターンですね。
私の友人夫婦も、共働きで一緒に住宅ローンを組んで、この「持分2分の1」パターンでマイホームを購入しました。お互いが所有者であるという意識が持てて良い、なんて話していましたね。
さて、この状態で、もしご主人が亡くなられたとします。この場合、相続の対象となるのは、ご主人が所有していた「持分2分の1」の部分だけです。奥様がもともと持っている持分2分の1は、当然ながら奥様自身の財産なので、相続財産には含まれません。
そして、亡くなったご主人の持分2分の1を、相続人である奥様やお子様が相続することになります。遺産分割協議で、「夫の持分2分の1は、妻が相続する」と決まれば、奥様は自分の持分2分の1と合わせて、不動産全体の所有者(単独名義)になることができます。
もちろん、「夫の持分2分の1は、長男が相続する」と決めることも可能です。その場合、不動産の名義は「母 持分2分の1、長男 持分2分の1」という新しい共有関係になります。
持分2分の1相続のポイント
- 夫婦で家を購入したケースで多い。
- 亡くなった方の持分だけが相続の対象になる。
- 遺産分割協議で、誰がその持分を取得するかを決める。
- 相続の結果、単独名義になることも、新たな共有名義になることもある。
このように、相続するのは不動産全体ではなく、亡くなった方の「持分」だけだという点をしっかり理解しておくことが大切です。そして、その持分を相続した際には、必ず名義変更の手続きが必要になる、ということですね。
相続登記は持分のみでも申請できるか
「不動産全体じゃなくて、共有持分だけを相続したんだけど、そんな中途半端な権利でも名義変更ってできるの?」というご質問をよくいただきます。
ご安心ください!結論から言うと、共有持分のみの相続登記は、まったく問題なく申請できます。
法律上、共有持分というのも、一つの独立した財産権(所有権)として扱われます。ですから、不動産全体を相続した場合と同じように、持分だけを特定の人に名義変更する手続きがちゃんと用意されているんです。
例えば、お父さんが「A土地の持分3分の1」だけを持っていて亡くなったとします。この場合、相続人はお父さんが持っていた「A土地の持分3分の1」についてのみ、相続登記の申請をすることになります。不動産の一部分の権利だけを移転させる、というイメージですね。
この「持分のみ」の相続登記は、特に私道の場合でよく発生します。前述の通り、家の土地と建物は亡くなったお父さんの単独名義だったけれど、家の前の私道だけは近所の人たちとの共有名義(例えば持分5分の1)だった、というケースです。
この場合、家の土地・建物については「所有権移転」の登記を、私道については「〇〇(お父さんの名前)持分全部移転」という登記を、それぞれ申請する必要があります。一つの相続で、複数の登記申請が必要になることもあるんですね。
【失敗談】私道の登記を忘れて大慌て!
以前、ご自身で相続登記をされたというお客様からのご相談でした。家の土地と建物の名義変更は無事に済んだものの、数年後に家を売却しようとした際に、私道の持分がお亡くなりになったお父さんの名義のままだったことが発覚!売買契約は目前なのに、そこから慌てて私道持分の相続登記をすることになりました。他の相続人の方に再度連絡を取って、実印をもらって…と、大変な手間と時間がかかってしまったそうです。
このように、建物や主要な土地の登記に気を取られて、共有私道のような細かい財産の登記を漏らしてしまうのは、本当によくある失敗例です。持分のみの財産であっても、れっきとした不動産の権利。忘れずに、きちんと名義変更の手続きを行いましょう。専門家である司法書士に依頼すれば、こうした登記漏れも防ぐことができますよ。
私道共有持分名義変更の具体的な手続き

共有持分相続の遺産分割協議書
さあ、ここからは、いよいよ具体的な手続きの話に入っていきますよ!まずは、相続手続きの心臓部とも言える「遺産分割協議書」についてです。特に共有持分を相続する際には、この書類の書き方にちょっとしたコツがあるんです。
遺産分割協議書とは、相続人全員が「このように遺産を分けます」と合意したことを証明する契約書のようなものです。この書類がないと、原則として不動産の名義変更はできません。
共有持分を記載する際の最大のポイントは、「どの不動産の、どれくらいの持分なのか」を誰が読んでもわかるように、正確に記載することです。
不動産の情報を特定するために使うのが「登記事項証明書(登記簿謄本)」です。これを見ながら、一字一句間違えないように書き写すのが基本となります。
遺産分割協議書への不動産の書き方(記載例)
【土地の場合】
所在:〇〇市〇〇町一丁目
地番:〇〇番〇
地目:宅地
地積:〇〇.〇〇平方メートル
【共有私道の場合】
所在:〇〇市〇〇町一丁目
地番:〇〇番〇
地目:公衆用道路
地積:〇〇.〇〇平方メートル
被相続人〇〇の有する持分全部
そして、誰が相続するかを明確にするために、以下のような一文を加えます。
「上記の不動産(共有持分)は、相続人〇〇が取得する。」
特に私道の場合、地目が「宅地」ではなく「公衆用道路」になっていることが多いので、登記事項証明書の記載をよく確認してくださいね。また、「持分〇分の〇」と書いても良いですが、「被相続人〇〇の有する持分全部」と書くのが一番間違いがなくて確実です。
【失敗談】記載が曖昧で法務局からダメ出し!
「父の持っていた私道を相続する」と、簡単な記載しかしていなかった遺産分割協議書。法務局に提出したところ、「どの私道のことか特定できません」と、補正(修正)の指示が来てしまいました。結局、もう一度相続人全員から実印をもらい直すという、大変な二度手間に…。財産の表示は、面倒でも正確に書くことが本当に大切だと痛感した出来事でした。
遺産分割協議書は、相続人全員の財産に関する重要な合意文書です。後々のトラブルを防ぐためにも、作成は慎重に行いましょう。不安な方は、司法書士などの専門家に作成を依頼することをおすすめします。
共有持分相続の登記申請書の準備

遺産分割協議書という最強の武器を手に入れたら、次はいよいよラスボス(法務局)に挑むための準備、「登記申請書」の作成と必要書類の収集です!ここを乗り切れば、ゴールはもうすぐですよ。
登記申請書そのものは、管轄の法務局のウェブサイトから雛形(テンプレート)をダウンロードできます。Word形式なので、パソコンで入力して作成するのが一般的です。
参考情報サイト: 法務局「不動産登記の申請書様式について」
URL: https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html
そして、この申請書と一緒に提出する添付書類が、まさに山のようにあります。一般的な相続登記で必要になる主な書類は以下の通りです。
| 書類の種類 | 取得場所 | ワンポイントアドバイス |
|---|---|---|
| 登記申請書 | 法務局サイト等で作成 | 次の項目で書き方を詳しく解説します! |
| 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等 | 本籍地の市区町村役場 | これが一番集めるのが大変な書類です。 |
| 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票) | 最後の住所地の市区町村役場 | 登記簿上の住所と死亡時の住所を繋げる証明になります。 |
| 相続人全員の現在の戸籍謄本 | 各相続人の本籍地の市区町村役場 | 相続人が生存していることの証明です。 |
| 財産を取得する相続人の住民票 | その相続人の住所地の市区町村役場 | 新しい名義人として登記される方のものです。 |
| 遺産分割協議書 | 相続人全員で作成 | 相続人全員の実印と印鑑証明書が必要です。 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 各相続人の住所地の市区町村役場 | 遺産分割協議書に押した印鑑が本物である証明です。 |
| 固定資産評価証明書 | 不動産所在地の市区町村役場(都税事務所) | 登録免許税という税金を計算するために必要です。 |
どうでしょう?このリストを見ただけで、ちょっとめまいがしませんか?(笑)私も初めて自分でやろうとした時は、書類の多さに心が折れかけました…。
特に戸籍集めは、古いものだと手書きで読みにくかったりして、解読するのに一苦労なんてことも。これらの書類を一つでも欠かすと、法務局は申請を受け付けてくれません。
これらの書類を不備なく集め、正しく登記申請書を作成するのは、慣れていない方にとっては非常にハードルが高い作業です。時間と労力を節約したい、確実に手続きを終わらせたい、という方は、やはり司法書士に手続きを依頼するのが賢明な選択と言えるでしょう。専門家は、これらの書類収集から申請書の作成、法務局への提出まで、全てを代行してくれますよ。
登記申請書の私道や持分の書き方
さあ、いよいよ登記申請書の書き方です!ここが一番専門的な部分かもしれませんが、ポイントさえ押さえれば大丈夫。特に「登記の目的」と「不動産の表示」の書き方が、共有持分ならではの特殊な部分になります。
通常の土地や建物を丸ごと相続する場合は、登記の目的は「所有権移転」となります。しかし、亡くなった方が共有持分だけを持っていた場合は、書き方が変わるんです。
登記の目的の書き方
登記の目的:被相続人〇〇 持分全部移転
このように、「誰の」「持分を」移転させるのかを明確に記載します。「所有権」ではなく「持分」という言葉を使うのがポイントですね。ちなみに、亡くなった方の氏名の前には「被相続人」と書き加えるのが正式なルールです。
次に、申請書の「不動産の表示」の欄です。ここには、遺産分割協議書と同じように、登記事項証明書に書かれている情報をそのまま正確に書き写します。
不動産の表示の書き方(共有私道の例)
不動産の表示
所在:〇〇市〇〇町一丁目
地番:〇〇番〇
地目:公衆用道路
地積:〇〇.〇〇㎡
持分 〇分の〇
そして、一番下に、今回相続する持分の割合を記載します。登記事項証明書を見れば、亡くなった方がどれくらいの持分を持っていたかが記載されているので、その通りに書きましょう。
申請書の他の部分、「登記原因」は「相続」、「権利者」は財産を取得する相続人の住所・氏名、「義務者」は亡くなった方の氏名(被相続人〇〇)を記載します。
この申請書の書き方を一つでも間違えると、法務局から電話がかかってきて、補正(修正)のために平日に法務局まで出向かなければならなくなります。私も駆け出しの頃、不動産の表示の地積の小数点を間違えて、冷や汗をかきながら法務局に走った苦い経験があります…。細かい部分ですが、細心の注意を払って作成してくださいね。
もし自分で作成するのが不安な場合は、法務局の登記相談を利用するのも一つの手です。無料で相談に乗ってくれますが、予約が必要な場合が多いので、事前に管轄の法務局に確認してみてください。
私道の名義変更や単独名義への費用

手続きの話が続いたので、ここらで一番気になる「お金」の話をしましょう!私道の名義変更には、一体どれくらいの費用がかかるのでしょうか。大きく分けて、「登録免許税」という税金と、専門家に依頼した場合の「司法書士報酬」の2つが必要になります。
① 登録免許税
これは、登記を申請する際に国に納める税金です。避けては通れない費用ですね。税額の計算方法は、法律で決まっています。
計算式:不動産の固定資産税評価額 × 税率(0.4%)
「固定資産税評価額」は、毎年春に送られてくる固定資産税の納税通知書に記載されていますし、市区町村役場で「固定資産評価証明書」を取得すれば確認できます。
ここでポイントなのが、共有持分の場合は、不動産全体の評価額に、相続する持分の割合を掛けてから税率を計算する、という点です。
【計算例】
私道全体の固定資産税評価額が500万円で、持分5分の1を相続する場合
1.まず、相続する持分の評価額を計算します。
500万円 × 1/5 = 100万円
2.次に、登録免許税を計算します。
100万円 × 0.4% = 4,000円
ちなみに、私道が「公衆用道路」として評価されていて、固定資産税評価額がゼロ円(非課税)の場合、登録免許税もかからないことがあります。これは嬉しいポイントですね!
② 司法書士報酬
手続きを司法書士に依頼した場合に発生する費用です。報酬額は事務所によって異なりますが、一般的な相続登記の相場としては、5万円~15万円程度を見ておくと良いでしょう。
不動産の数や評価額、相続人の数、戸籍集めの難易度などによって報酬は変動します。複数の不動産をまとめて依頼したり、共有名義から単独名義への変更など、手続きが複雑になると高くなる傾向があります。
「え、そんなにかかるの!?」と思われるかもしれませんが、あの膨大な書類の収集や作成、法務局とのやり取りを全て任せられることを考えると、決して高くはないと私は思います。時間と安心を買う、というイメージですね。複数の事務所から見積もりを取って比較検討するのも良い方法ですよ。
その他、戸籍謄本や住民票などを取得するための実費が数千円程度かかります。これらの費用を合計したものが、名義変更にかかる総額となります。
墓じまいなどお金がない時の注意点
相続って、不動産の名義変更だけでなく、色々なところでお金がかかりますよね。例えば、最近よく聞く「墓じまい」。お墓を管理する人がいなくなって、お墓を撤去して更地に戻すのにも、数十万円から百万円以上かかることもあるそうです。
そんな風に、相続にまつわる出費が重なって、「私道の名義変更まで手が回らない…お金がない…」と悩んでしまう方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、費用がないからといって、私道の共有持分の名義変更を放置しておくのは非常に危険です。これまでお話ししてきたように、様々なリスクが待ち構えています。
名義変更を放置するリスク(おさらい)
- いざという時に土地や建物を売却できない。
- 家の建て替えやリフォームができない可能性がある。
- 時間が経つほど、相続関係が複雑になり、手続きが困難になる。
- (令和6年4月1日から)相続登記が義務化され、放置すると過料(罰金のようなもの)が科される可能性がある。
参考情報サイト: 法務省「相続登記の申請義務化について」
URL: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html
では、どうしても費用が捻出できない場合はどうすれば良いのでしょうか。
私がお客様にご提案することがあるのは、「相続不動産を売却して、その売却代金から費用を支払う」という方法です。もちろん、他の相続人の方の同意が必要ですが、誰もその不動産を使う予定がないのであれば、現金化して費用を清算し、残りをみんなで分けるというのは、とても合理的な解決策の一つです。
また、すぐに売却する予定がなくても、まずは司法書士などの専門家に相談してみることを強くお勧めします。事務所によっては、費用の分割払いに応じてくれる場合もありますし、何か良い解決策を一緒に考えてくれるはずです。
目先の費用を惜しんで大きな問題を抱え込むよりも、まずは専門家の知恵を借りて、問題を整理することが大切です。一人で抱え込まず、ぜひ相談してみてくださいね。
確実な私道共有持分名義変更の要点
ここまで、私道共有持分名義変更の様々な側面についてお話ししてきました。最後に、この記事の要点をまとめておさらいしましょう!これさえ押さえておけば、あなたも「私道相続マスター」に一歩近づけるはずです!
- 私道の共有持分も土地や建物と同じく相続財産になる
- 相続したら必ず名義変更(相続登記)の手続きが必要
- 名義変更をしないと売却や建て替えができない等のトラブルに繋がる
- 共有私道では通行や掘削工事で他の共有者との同意が必要になることがある
- 相続登記は令和6年4月1日から義務化され放置すると過料の対象になる可能性がある
- 名義変更はまず相続人を確定させるための戸籍集めからスタートする
- 相続人全員で遺産の分け方を話し合う遺産分割協議が必須
- 協議内容は遺産分割協議書にまとめ相続人全員が実印を押す
- 不動産の表示は登記事項証明書通りに正確に記載することが重要
- 共有持分のみの相続登記も可能で手続きの基本は同じ
- 登記申請書では登記の目的を「持分全部移転」と記載する
- 費用は登録免許税と司法書士報酬が主で事前に確認する
- 費用がなくても放置はせず専門家に相談し解決策を探すことが賢明
- 手続きが複雑で不安な場合は無理せず司法書士に依頼するのが確実な方法
参考
・50代シングルマザー老後の不安を減らす住まいとお金の話
・エンディングノート50代おすすめ特集|後悔しない選び方と活用術
・終活やりすぎに注意!家族が後悔しないための断捨離ルール
・エンディングノート40代おすすめ|失敗しない選び方と無料の始め方
・老後一人ぼっち女性の生活費と貯金目安をわかりやすく徹底解説

お気軽にご相談ください
相続は100人いれば、100通り
唯一無二の最適な相続をご提案いたします
CONTACT
専門家やえさん

- 専門家やえさん
-
堀川 八重(ほりかわ やえ)
大阪不動産・FPサービス株式会社 代表
15年以上にわたり1,500組を超えるご家族の相続や不動産のお悩みに、専門家として寄り添ってまいりました。私の信条は、法律や数字の話をする前に、まずお客様ご家族の歴史や言葉にならない想いを丁寧に「聞く」こと。信頼できる各分野の専門家チームと共に、皆様が心から安心できる最善の道筋をオーダーメイドでご提案します。一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。
最新の投稿
 お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説
お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説 相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説
相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説 お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例
お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例 お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説
お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説






