「独身で持ち家だけど、老後の生活費って年金だけで足りるのかな…?」そんな風に、将来のお金のことで漠然とした不安を感じていませんか。老後資金は独身なら5000万円必要、なんて話も聞くと、余計に心配になりますよね。
結論からお伝えすると、老後資金独身持ち家の場合は、毎月の家賃負担がない分、賃貸暮らしより有利なのは間違いありません。
ただし、持ち家があれば老後はいくら必要かという問いに対しては、平均的な生活費だけを見て安心してしまうのは少し早いかもしれません。
例えば、老後一人暮らしの生活費の内訳には家の修繕費や固定資産税は十分に含まれていなかったり、ゆとりのある老後生活費を一人暮らしで送るには追加の資金が必要になったりします。
この記事では、老後一人暮らしの生活費シミュレーションを通じて、持ち家なしで独身の場合の老後資金や、老後資金が持ち家ありの夫婦世帯とどう違うのかも比較します。
さらに、女性一人暮らしの老後資金シミュレーションも行い、「一生独身で老後を生きていくにはいくら貯金が必要ですか?」という切実な疑問に、専門家の視点から具体的にお答えしていきますね。
この記事のポイント
- 独身で持ち家がある場合の老後資金の目安がわかる
- 老後の一人暮らしで毎月かかる生活費の内訳を把握できる
- 男女別の具体的な老後資金シミュレーションができる
- 持ち家を活かした資金準備の方法を知ることができる

こんにちは!終活・相続の専門家、やえです。
老後のお金の話って、ついつい後回しにしがちですよね。でも、数字だけ見て「大変!」と焦る必要はありませんよ。特に「持ち家」という大きな資産をお持ちのあなたは、すでに大きなアドバンテージがあります。
この記事では、その強みを最大限に活かしながら、あなただけの安心な老後プランを一緒に見つけていくお手伝いをします。少し先の未来を、楽しく計画していきましょう!
目次
老後資金独身持ち家のリアルな必要額

老後一人暮らし生活費の平均
まず、老後の生活に一体いくらかかるのか、信頼できる平均的なデータから見ていきましょう。総務省統計局が公表している「家計調査報告」によると、65歳以上の単身無職世帯、つまり一人暮らしで年金などを主な収入源としている方の平均的な消費支出(毎月の生活費)は、149,286円です。
一方、収入の平均は社会保障給付(年金など)が12万円前後で、合計の実収入は約134,116円。これらを差し引くと、毎月およそ15,000円から28,000円ほどの赤字が出ているのが現状です。
「え、年金だけじゃ足りないの?」と不安に思われたかもしれませんね。この数字はあくまで平均値であり、持ち家がある方と賃貸住宅にお住まいの方の両方を含んだ平均値です。ですから、持ち家にお住まいで家賃の支払いがないあなたは、この赤字額がもっと少なくなる、あるいは黒字になる可能性も十分にあります。
しかし、近年の物価上昇などを考えると、支出は今後さらに増える可能性もあります。この公式データは、私たちがお金の計画を立てる上での、揺るぎない「出発点」として捉えることが大切です。
【公的データ】65歳以上・単身無職世帯の平均的な家計収支
- 実収入(年金など):134,116円
- 消費支出(生活費):149,286円
- 可処分所得(手取り):121,469円
- 収支の不足分:-27,817円(可処分所得-消費支出)
このデータを基準に、ご自身の現在の生活費と比較してみましょう。
老後一人暮らし生活費の内訳

次に、先ほどの平均生活費約14万9,000円の内訳を、より詳しく見ていきましょう。何にどれくらいお金がかかっているのかを知ることで、ご自身の生活スタイルと照らし合わせ、より現実的な資金計画を立てる手助けになります。
| 費目 | 平均金額(月額) | 内容とワンポイントアドバイス |
|---|---|---|
| 食料 | 約42,000円 | 最も大きな割合を占める支出です。一人暮らしは食材が割高になりがちですが、健康維持の要。まとめ買いや作り置きなどで工夫したいですね。 |
| 住居 | 約12,000円 | 持ち家の方の修繕費や税金、賃貸の方の家賃が含まれた平均値。持ち家の方はこの項目が低く抑えられますが、ゼロではありません。 |
| 水道・光熱 | 約14,000円 | 電気・ガス・水道代。近年のエネルギー価格高騰の影響を受けやすい費目です。季節によっても大きく変動します。 |
| 交通・通信 | 約15,000円 | 車の維持費や公共交通機関の利用料、そして現代の生活に不可欠なスマートフォンやインターネットの通信費です。格安SIMへの乗り換えも検討の価値ありです。 |
| 保健医療 | 約8,600円 | 病院の診察代や薬代、サプリメント代など。年齢を重ねるにつれて増加する可能性が高い費用なので、少し多めに見積もっておくと安心です。 |
| 教養娯楽 | 約15,000円 | 趣味や習い事、旅行、友人との交流など、心豊かな生活を送るために不可欠な費用。人生を楽しむための大切な予算ですね。 |
| その他の消費支出 | 約31,000円 | 交際費や理美容費、冠婚葬祭費、雑費などが含まれます。予期せぬ出費もこの項目で吸収することが多いです。 |
この内訳を見ると、日々の生活に必要なお金がいかに多岐にわたるかがわかります。特に、食費、交通・通信費、教養娯楽費、その他の消費支出が大きな割合を占めています。ご自身の現在の家計簿と見比べて、「老後はこの部分を少し抑えられそう」「ここはもう少しお金をかけたいな」と、未来の生活を具体的にイメージしてみることが大切です。
老後一人暮らし生活費 持ち家の場合
さて、ここからが本題です。持ち家がある場合の老後一人暮らしの生活費について、さらに深掘りしていきましょう。最大の強みは、なんといっても毎月の家賃負担がないことです。これは精神的にも経済的にも、計り知れないほどの安心感につながります。
しかし、「家賃がないから安泰」と考えるのは少し早いかもしれません。持ち家には、賃貸住宅にはない、特有の維持費用が必ず必要になります。これを忘れていると、将来思わぬ出費に慌てることになりかねません。
【重要】持ち家だからこそ必要な三大費用
- ①固定資産税・都市計画税:土地と建物を所有している限り、毎年必ず納税義務が発生します。金額は自治体や物件の評価額によって異なりますが、年間数万円~十数万円が一般的です。
- ②修繕費:建物は時間と共に劣化します。外壁の塗り替え(10~15年周期で約100万円~)、給湯器の交換(10年前後で約20万円~)、水回りのリフォームなど、計画的な積立てが不可欠です。
- ③火災保険料・地震保険料:自然災害はいつ起こるかわかりません。大切な資産を守るための保険料も、数年ごとにまとまった支払いが必要です。
特に見落としがちなのが、この修繕費です。マンションにお住まいの場合でも、管理費や修繕積立金が毎月かかります。これらの費用は、決して小さな金額ではありません。
老後の生活費を計算する際には、これらの維持費をあらかじめ月割りで計算し、生活費の一部として組み込んでおくことを強くお勧めします。例えば、15年で150万円の修繕費がかかると見込むなら、年間10万円、月々約8,300円を積み立てていくイメージですね。
持ち家なし老後資金独身との比較
持ち家があることの有利さをより客観的に理解するために、もし持ち家がなかったら…つまり、賃貸で暮らし続けた場合の独身の老後資金と比較してみましょう。その差は歴然としています。
最大の相違点は、もちろん生涯にわたって「家賃」を払い続ける必要があるという点です。仮に、月6万円の賃貸住宅に65歳から90歳までの25年間住み続けると仮定して、単純計算してみましょう。
6万円(月家賃) × 12ヶ月 × 25年 = 1,800万円
これだけで、なんと1,800万円もの大金が家賃として消えていく計算です。実際には、これに加えて2年ごとの契約更新料や、引越し費用なども発生する可能性があります。持ち家の場合、この1,800万円が基本的に不要になるわけですから、老後資金計画における難易度が大きく変わることがお分かりいただけるでしょう。
| 持ち家あり | 持ち家なし(賃貸) | |
|---|---|---|
| メリット | ・家賃の支払いがない ・資産になる ・リフォーム等が自由 | ・固定資産税がない ・修繕費の負担がない ・住み替えが容易 |
| デメリット | ・固定資産税がかかる ・修繕費がかかる ・流動性が低い | ・生涯家賃がかかる ・高齢になると借りにくい ・資産にならない |
補足:高齢者の賃貸契約という現実
もう一つ、賃貸暮らしで考えておきたいのが、高齢になると新たな賃貸契約が難しくなるケースがあるという現実です。収入が年金のみになることや、孤独死のリスクなどから、入居審査が厳しくなる傾向があります。その点、持ち家は「終の棲家」としての絶対的な安心感を与えてくれます。
もちろん、持ち家には固定資産税や修繕費がかかりますが、長期的な視点で見れば、賃貸の家賃総額よりも安く収まる可能性が高いと言えるでしょう。
ゆとりのある老後生活費一人暮らし
これまでは、あくまで平均データに基づいた「最低限の文化的な生活」を送るための費用を見てきました。しかし、せっかくのセカンドライフ、たまには旅行に行ったり、趣味に没頭したり、美味しいものを食べたりと、少しは生活に彩りを加えたいですよね。「ゆとりのある老後」を送るためには、一体いくらくらいの生活費が必要なのでしょうか。
この点について参考になるのが、生命保険文化センターの調査です。この調査によると、「ゆとりある老後生活を送るための費用」として、最低日常生活費に上乗せしたい金額の平均は月額14.8万円とされています。つまり、先ほどの平均的な生活費にこの「ゆとり分」をプラスすると…
約14.9万円(平均生活費) + 約14.8万円(ゆとり分) = 約29.7万円
毎月約30万円ほどの生活費があれば、多くの方が「ゆとりのある生活」を送れると感じているようです。もちろん、これはあくまで平均的な価値観です。「あなたにとってのゆとり」が何なのかを考えることが何より大切になります。
「ゆとり」の使い道の例
- 旅行やレジャー:温泉旅行や海外旅行、観劇など
- 趣味や教養:習い事やサークル活動、書籍の購入など
- 身の回り品や家具の購入:少し質の良いものに買い替える
- 子どもや孫との付き合い:プレゼントやお祝い、一緒に食事をする費用
ご自身の理想の老後生活をより具体的に描くことで、必要な資金もより明確になります。エンディングノートなどに書き出してみるのも良い方法ですよ。
老後資金持ち家あり夫婦との差

独身の方の老後資金を考える上で、もう一つ比較対象として「夫婦世帯」のデータも見ておくと、ご自身の状況を客観的に捉えるのに役立ちます。老後資金が持ち家ありの夫婦の場合、生活費は単純に一人暮らしの2倍になるわけではない、という点がポイントです。
総務省の同じ家計調査によると、65歳以上の夫婦のみの無職世帯の消費支出は月額約25万5,000円です。一人暮らしの平均が約14万9,000円でしたから、一人当たりの生活費に換算して比べてみると、その違いがよくわかります。
【比較】一人当たりの生活費
- 単身世帯:約149,000円
- 夫婦世帯:約127,500円(255,000円 ÷ 2人)
このように、夫婦世帯の方が一人当たりの生活費は2万円以上も安くなっています。これは、住居費や水道光熱費といった、生活の基盤となる固定費を二人で分担できるためです。経済学ではこれを「スケールメリット(規模の経済)」と言ったりしますね。
独身の場合は、このスケールメリットが効かないため、生活費がどうしても割高になりがち、という側面も知っておくと良いでしょう。ただし、もちろん収入も一人分ですから、夫婦世帯よりも一人ひとりがより計画的に資金を準備する必要がある、とも言えますね。

平均額や比較データを見て、少しリアルに感じてきましたか?数字と向き合うのは少し勇気がいるかもしれませんが、現状を把握することが計画の第一歩です。
ここからは、さらに具体的に、あなた自身のケースをシミュレーションしていきます。漠然とした不安を「今日からできること」に変えていきましょう!専門家として、しっかりナビゲートしますからね。
老後資金独身持ち家シミュレーション

老後一人暮らし生活費シミュレーション
それでは、ここまでのデータを基に、より具体的な老後資金のシミュレーションをしてみましょう。ここでは、65歳から平均寿命に近い90歳までの25年間、一人暮らしで生活すると仮定します。
まず、平均的な生活を送る場合です。毎月の赤字額が約28,000円(可処分所得ベース)でしたので、年金収入以外に必要となる生活費の補填総額は以下のようになります。
28,000円 × 12ヶ月 × 25年 = 840万円
この840万円が、年金だけでは足りない生活費の合計額です。しかし、本当に必要なのはこれだけではありません。忘れてはならないのが、これまでもお話ししてきた「特別な支出」です。これらを考慮しないと、計画が大きく狂ってしまう可能性があります。
【重要】生活費以外に必ず考慮すべき大きな支出
- 住宅の修繕・リフォーム費用:20~30年で少なくとも200万円~500万円は見込んでおきたい費用です。
- 医療・介護費用:生命保険文化センターの調査では、介護にかかる一時的な費用の平均が約74万円、月々の費用が約8.3万円となっています。これが平均約5年続くと仮定すると、総額で約500万円以上になります。
- 葬儀関連費用:ご自身の葬儀やお墓の準備に、150万円~200万円程度は見ておくと安心です。
これらの「特別な支出」を合計すると、少なく見積もっても約870万円~1,270万円は別途必要になります。つまり、生活費の不足分840万円と合わせると、合計で約1,710万円~2,110万円。これが、持ち家ありの独身の方が、平均的な老後を送るための一つの目安となる資金額です。
女性一人暮らし老後資金シミュレーション
特に女性の場合は、一般的に男性よりも平均寿命が長いため、より多くの老後資金が必要になる可能性が高いと言えます。厚生労働省の「令和5年簡易生命表」によると、日本の女性の平均寿命は87.14歳。男性の81.09歳と比較して約6年も長くなっています。
この「長生きリスク」に備えるため、女性一人暮らしの老後資金シミュレーションでは、老後の期間を少し長めに、例えば95歳までの30年間で設定して考えることが重要です。
毎月の赤字28,000円 × 12ヶ月 × 30年 = 1,008万円
生活費の不足分だけでも1,000万円を超えてきます。これに、先ほどの「特別な支出」(約870万円~1,270万円)を加えると、合計で約1,878万円~2,278万円が必要という計算になります。2,000万円~2,500万円ほどの資金があると、より安心して豊かな老後生活を送れると言えるでしょう。
また、一般的に女性は非正規雇用の経験がある方も多く、男性に比べて厚生年金の加入期間が短く、結果として受け取れる年金額が少なくなる傾向があります。ご自身の正確な年金見込額を「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で必ず確認し、よりパーソナルなシミュレーションを行うことが、安心への第一歩です。
老後資金独身なら5000万円必要か
数年前に「老後2000万円問題」が大きな話題になりましたが、メディアや雑誌などでは「独身でも5000万円は必要」といったさらに大きな金額を目にすることもあり、不安に感じている方もいらっしゃるかもしれません。ここで専門家としてハッキリお伝えしますと、老後資金として独身で5000万円が、全ての人に絶対必要というわけではありません。
この「5000万円」という金額は、かなり裕福で「ゆとりのある老後」を想定した場合の、一つのモデルケースです。例えば、現役時代と変わらないかそれ以上の生活水準を維持し、毎年海外旅行に行ったり、高価な趣味やお稽古事にお金を存分に使ったり、都心の一等地の高級な有料老人ホームへの入居を希望したり、といったケースが考えられます。実際に老後資金1億円を持つ方の生活レベルは、かなり余裕があるようです。
「5000万円」が必要になる可能性のあるライフスタイル
- 毎月30万円以上のゆとりある生活費で暮らすことを希望する
- 高級な有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅への入居を考えている
- 現役時代からの趣味や交際費を一切減らさずに生活したい
- 子どもや孫へ、まとまった額の資金援助をしたい
これまでシミュレーションしてきたように、持ち家がある独身の方であれば、1,500万円~2,500万円が現実的な一つの目安となります。もちろん、資金は多く準備するに越したことはありませんが、いたずらに不安を煽る情報に惑わされる必要はありません。ご自身の価値観や理想のライフプランに合った、現実的な目標金額を設定することが何よりも大切なのです。
持ち家があれば老後はいくら必要か

ここまで様々な角度からデータやシミュレーションを見てきましたが、「結局のところ、私の場合、持ち家があれば老後はいくら必要なの?」という疑問に、改めてお答えします。その答えは、突き詰めると「あなたがどのような老後生活を送りたいか」によって大きく変わります。
そこで、ご自身のケースに当てはめて考えられる、簡単な計算方法をご紹介します。ぜひ、電卓片手に試してみてください。
【実践編】3ステップで計算!あなただけの必要老後資金額
- 【STEP1】老後の「総支出」を見積もる
まず、老後の1ヶ月の生活費を予測します。(現在の生活費 - 老後不要になる支出 + 老後に増える支出)で計算。これに12ヶ月と老後の年数(例:25年)を掛け合わせます。
例:(15万円 - 2万円 + 1万円)× 12ヶ月 × 25年 = 4,200万円 - 【STEP2】老後の「総収入」を把握する
次に、年金収入と退職金などを合計します。「ねんきんネット」で年金見込額を確認し、それに12ヶ月と老後の年数を掛け合わせ、退職金を足します。
例:12万円 × 12ヶ月 × 25年 + 500万円 = 4,100万円 - 【STEP3】「不足額」を計算する
【STEP1】の総支出から【STEP2】の総収入を引きます。これが生活費の不足額です。最後に、これに「特別な支出(予備費)」を加えます。
例:(4,200万円 - 4,100万円) + 1,000万円 = 1,100万円
この計算に、先ほど解説した平均データなどを参考にしながら、ご自身のリアルな数字を当てはめてみてください。「特別な支出(予備費)」としては、やはり1,000万円~1,500万円ほど見ておくと、いざという時に安心感が高まります。
この計算を一度行ってみることで、漠然としていた不安が具体的な目標金額に変わり、今から何をすべきか、その道筋がはっきりと見えてくるはずですよ。
一生独身で老後の貯金はいくら必要?
「一生独身で老後を生きていくにはいくら貯金が必要ですか?」というご質問は、私がお客様から最も多くいただく、非常に切実な質問の一つです。頼れるパートナーや子どもがいない分、お金の不安はより一層重くのしかかりますよね。
前述のシミュレーションの通り、持ち家があるという大きなアドバンテージがあったとしても、残念ながら年金収入だけで生活していくのは厳しい可能性が高いため、ある程度の貯蓄は必要不可欠です。
具体的な金額は、あなたの価値観やライフスタイルによりますが、公的データを基にした一つの目安としては、やはり1,500万円~2,500万円が現実的な目標ラインとなります。
もし、現時点で「そんな貯蓄はない…」と肩を落としてしまったとしても、決して悲観する必要はありません。今からでも、できることはたくさんあります。
家計の見直しによる支出の削減、iDeCo(個人型確定拠出年金)や新NISA(少額投資非課税制度)といった税制優遇制度を最大限に活用した資産形成など、今日からでも始められる対策は豊富に存在します。
そして何より、あなたには「持ち家」という大きな資産があります。これを将来どのように活用していくか、という視点を持つことが、安心な老後への鍵となります。お一人様の老後に備える終活の始め方について知っておくことも、不安の解消につながります。
老後資金独身持ち家についてよくあるご質問FAQ
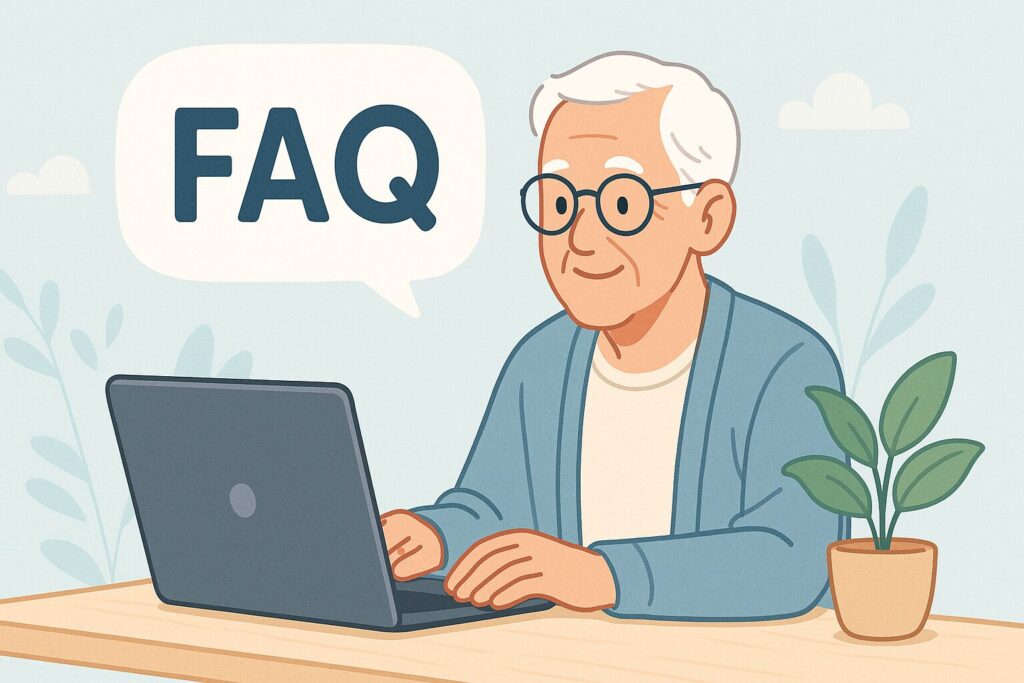
ここでは、独身で持ち家がある方の老後資金について、よく寄せられる質問にお答えします。
-
持ち家があれば年金だけでも生活できますか?
-
年金額によりますが、家の修繕費や固定資産税、介護費用などを考えると年金だけでは厳しい場合が多いです。計画的な貯蓄や資産の活用を検討することが大切です。
-
老後資金はいつから準備すればいいですか?
-
準備を始めるのは早ければ早いほど良いです。特にiDeCoやNISAなどの税制優遇制度は、長期間運用することで複利の効果が大きくなるため、早期に始めることをお勧めします。
-
持ち家を売却するのも選択肢になりますか?
-
はい、持ち家を売却してサービス付き高齢者向け住宅などの入居資金に充てるのは有力な選択肢です。ただし、売却後の住まいの費用や税金も考慮して慎重に計画しましょう。
-
リバースモーゲージとは何ですか?
-
自宅を担保にお金を借り、ご自身が亡くなった時に自宅を売却して返済する仕組みです。住み慣れた家に住み続けながら、老後資金を確保できる方法の一つになります。
老後資金独身持ち家で安心を手に入れるまとめ
独身で持ち家がある方の老後資金について、様々な角度から解説してきましたが、最後に重要なポイントを整理してみましょう。
- 独身持ち家の老後は家賃負担がなく賃貸より有利
- ただし家の修繕費や固定資産税は継続的に必要
- 65歳以上一人暮らしの平均生活費は約14万9000円
- 平均的な収支では毎月約1万5000円の赤字となる
- 生活費の内訳で最も大きいのは食費
- 夫婦世帯より一人暮らしは生活費が割高になる傾向
- 生活費の不足分に加え介護や医療の予備費も準備する
- 予備費を含めると1500万円から2000万円が一つの目安
- 女性は平均寿命が長いため男性より多くの資金が必要
- 老後資金5000万円は全ての人に必須ではない
- ゆとりのある生活には月30万円程度が必要というデータもある
- 持ち家なしの場合は家賃分として1500万円以上の上乗せが必要
- ご自身の年金受給額の確認が計画の第一歩
- iDeCoやNISAの活用も有効な資金準備の方法
- 持ち家を売却したりリバースモーゲージを活用する方法もある

ここまでお疲れ様でした!具体的な数字を見て、少し気が引き締まったかもしれませんね。でも、老後資金の準備は、決して暗い話ばかりではありません。
むしろ、これからの人生を自分らしく、豊かに生きるための「未来への投資」です。あなたには「持ち家」という大きな追い風が吹いています。
今日からできる小さな一歩を大切に、あなたの素敵なセカンドライフを心から応援しています!
▼あわせて読みたい関連記事▼
女性一人暮らし老後資金シュミレーションでわかる必要額と貯蓄戦略
終活とは?意味と始め方をわかりやすく解説|初心者が損しない準備法

お気軽にご相談ください
相続は100人いれば、100通り
唯一無二の最適な相続をご提案いたします
CONTACT
専門家やえさん

- 専門家やえさん
-
堀川 八重(ほりかわ やえ)
大阪不動産・FPサービス株式会社 代表
15年以上にわたり1,500組を超えるご家族の相続や不動産のお悩みに、専門家として寄り添ってまいりました。私の信条は、法律や数字の話をする前に、まずお客様ご家族の歴史や言葉にならない想いを丁寧に「聞く」こと。信頼できる各分野の専門家チームと共に、皆様が心から安心できる最善の道筋をオーダーメイドでご提案します。一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。
最新の投稿
 お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説
お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説 相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説
相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説 お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例
お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例 お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説
お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説






