大切な人へ、あなたの想いをきちんと残したい。そう思っても「遺言書書き方法務局で正確に遺言を残す方法」がわからず、不安になっていませんか?
私も最初、「遺言書 書き方 例文」を検索してもピンとこなくて…結局、放置してしまった時期がありました。
でも「遺言書作成 自分で 法務局」へ行けば、自筆証書遺言を安全に保管できるって知ってから、心が軽くなったんです。
この記事では、「遺言書書き方法務局で正確に遺言を残す方法」を中心に、遺言書 書き方 自筆のポイントや、遺言書 用紙 ダウンロード・無料テンプレート活用法まで、ひとつずつ丁寧に解説しています。
法務省 遺言 サンプルも交えながら、簡単な遺言書の書き方、誤字の訂正方法や注意点、自筆証書遺言 法務局 デメリットまで、知っておいて損のない情報ばかりです。
初めてでも、安心して一歩踏み出せる内容になっていますので、ぜひ読み進めてみてくださいね。
この記事のポイント
- 法務局で遺言書を正しく保管する具体的な手順がわかる
- 自筆証書遺言を書く際のルールと注意点が理解できる
- 遺言書テンプレートやひな形の活用方法がわかる
- 遺言の効力を失わないためのチェックポイントが学べる
遺言書書き方法務局で正確に残す方法の基本

遺言書 書き方 例文でイメージを掴む
「遺言書って難しそう…何を書けばいいの?」って思っている方、実はとても多いです。
わたしの叔母も、「ちゃんと子どもたちに残したいとは思ってるの。でも書き方がわからないのよ」と不安げに話していたことがありました。
でも実は、自筆証書遺言は形式を守っていれば、わりとシンプルに書けるんです。
難しく考えるよりも、まずは「どんなふうに書けばいいかイメージすること」が大事です。
🔸自筆証書遺言の基本構成
自分で書くタイプの遺言書「自筆証書遺言」には、決まった書き方があります。
下記のように5つの要素を含めれば、形式的にはOKです。
| 要素 | 説明内容 |
|---|---|
| ①日付 | 作成した日を明記(例:令和7年7月8日) |
| ②署名 | 遺言者のフルネームを手書きで記入 |
| ③捺印 | 実印または認印を押す(印影のあるもの) |
| ④遺言内容 | 誰に、どの財産を、どう相続させるかを明記 |
| ⑤目録(任意) | 不動産や預貯金など詳細は別紙の財産目録として添付してもOK |
遺言書
私は、以下のとおり遺言します。
1.東京都杉並区〇丁目〇番地の不動産を、長女 佐藤美咲(昭和55年1月1日生)に相続させます。
2.三井住友銀行〇〇支店の普通預金口座(口座番号:1234567)にある預金全額を、長男 佐藤大輔(昭和52年5月5日生)に相続させます。
令和7年7月8日
佐藤一郎(自筆)
印
このように、財産の種類ごとに相続人を明確にしておくのがポイントです。
🔸失敗談:「曖昧な書き方」で遺言が無効に
あるご家庭では、「長男に財産をすべて相続させる」とだけ書かれた遺言書が見つかりました。
でも…実はこの「財産」の中には亡くなったご主人名義の不動産が含まれていたんですが、具体的な住所や登記情報が書かれておらず、どれを指すのか不明確だったため、相続手続きで大きなトラブルになってしまったんです。
結局、家庭裁判所で調停になり、半年以上も手続きがストップしたそうです。
なので、遺言書には財産の特定情報をしっかり書くことが重要なんですね。
🔸例文②:財産目録を添付するパターン
コピーする編集する遺言書
私は、以下の財産を長男 山田健太(昭和50年4月4日生)に相続させます。
【別紙 財産目録 参照】
令和7年7月8日
山田太郎(自筆)
印
※別紙の財産目録には、以下のように記載します(こちらは手書きでなくてもOKです)
| 種別 | 内容 |
|---|---|
| 不動産 | 大阪市北区〇丁目〇番地 建物付き土地 |
| 預金 | ゆうちょ銀行 普通預金(記号番号12345) |
このように「本文と財産目録を分ける書き方」は、財産が多い人や整理しやすくしたい人におすすめです。
では、この遺言書を書いたあと、どうやって法務局に申請すればいいのか?というところを見ていきましょうね。
遺言書作成 自分で 法務局へ申請する流れ

「遺言書を書いたあと、どこにしまえばいいんだろう?」と悩む方、多いと思います。
わたしの知人(60代女性)も、しっかり書いたつもりの自筆証書遺言を、仏壇の引き出しに入れていたそうなんですが…
亡くなった後に誰も気づかず、そのまま処分されてしまったという悲しい出来事がありました。
今はそんなリスクを防ぐために、法務局が自筆証書遺言を保管してくれる制度があります。
2020年にスタートしたこの制度、正式には「自筆証書遺言書保管制度」といって、法務省が設けた公式サービスなんですよ。
参考公的機関: 法務省「自筆証書遺言書保管制度について」
URL: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
🔸法務局に遺言書を提出するステップ
自分で作った遺言書を、法務局にきちんと保管してもらうまでの流れはこちらです。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ①準備 | 自筆証書遺言を作成(形式をしっかり守って) |
| ②予約 | 近くの遺言書保管対応の法務局に、事前予約を取る |
| ③持参 | 本人確認書類(運転免許証など)と一緒に遺言書を持参 |
| ④申請 | 窓口で「保管申請書」を記入し、提出。印鑑も必要です |
| ⑤受理 | 問題なければ、その場で保管証を交付してもらえます |
🔸成功談:法務局保管で相続手続きがスムーズに
80代の男性がこの制度を使って遺言書を保管したところ、亡くなったあとに相続人である娘さんが「法務局に遺言書がある」ことを知り、すぐに請求して手続きに移れたそうです。
しかもこの制度を利用していると、家庭裁判所での「検認手続き」が不要になるんです。
だから、財産の相続にかかる期間が大幅に短縮されるというメリットもあるんですよ。
🔸法務局での保管制度|メリットとデメリット
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| メリット① | 紛失・改ざん・焼失の心配がない |
| メリット② | 相続人がスムーズに遺言書を取得できる(検認が不要) |
| メリット③ | 相続トラブルを防げる。法務局から相続人へ通知もある(※死亡時) |
| デメリット① | 平日に法務局まで行く必要がある(※一部地域で混雑) |
| デメリット② | 提出時に形式ミスがあると「保管不可」となることも |
こうして見てみると、「難しそう」と思っていた遺言書の手続きも、法務局を活用することで一気に安心感が増すのが分かりますよね。
次は、自筆証書遺言を書くうえで避けてほしい注意点やトラブル例をご紹介していきますね。
遺言書 書き方 自筆で無効を防ぐコツ
自分の手で遺言書を書く「自筆証書遺言」は、費用もかからず気軽に始められる反面、ちょっとしたミスで無効になるリスクがあるんです。
実際に、わたしの父の知人で「自分で書いたから大丈夫」と思っていた方がいたのですが…
亡くなったあとに確認すると、日付が抜けていたせいで効力が認められなかったんです。
その結果、相続人たちは家庭裁判所で調停を行うことになり、相続手続きが数ヶ月も延びてしまったそうです。
そんな事態を防ぐために、無効になりやすいポイントとその対策をまとめてみました。
参考公的機関: 法務省「遺言制度の利用をお考えの皆さまへ」
URL: https://houmukyoku.moj.go.jp/nagano/content/001363172.pdf
🔸無効になりやすいポイント一覧
| ミスの内容 | 無効になる可能性 | 回避のコツ |
|---|---|---|
| 日付の記載がない | 高い | 「令和〇年〇月〇日」と必ず記入 |
| ワープロやPCで作成 | 高い | 全文を手書きにすること |
| 署名がない | 高い | 必ずフルネームを自筆で記入 |
| 押印がない | やや高い | 認印でもよいので必ず捺印 |
| 相続人や財産が不明確 | 中〜高 | 名前や財産の情報を具体的に記載 |
🔸失敗談:誤字を二重線で訂正して無効に
ある方が遺言書の中で「長男に不動産を相続させる」と書いたあと、漢字を間違えたことに気づき、二重線で消して書き直したそうなんです。
でもその時、訂正印も署名も日付も記入していなかったため、家庭裁判所で無効と判断されてしまいました。
自筆証書遺言では、訂正の仕方まで法律で細かく決まっているんです。
🔸訂正の正しい手順(自筆証書遺言の場合)
- 誤字に二重線を引く
- 余白に「○字削除、○字追加」と記載
- その横に署名と日付、印鑑を押す
たとえば、「山田健太」を「山田賢太」に直したい場合…
「"健"の字を削除し、"賢"を追加」と書いたうえで、署名と印を忘れずに添えないと効力が認められません。
🔸効力を保つためのポイント5つ
- 全文手書きで記入すること(財産目録だけはパソコンOK)
- 日付・署名・押印を必ず書くこと
- 財産はできる限り不動産や口座番号まで特定すること
- 訂正には厳格なルールがあることを知っておくこと
- 不安なときは、法務局の遺言書保管制度も検討すること
これらを守るだけでも、自筆証書遺言の信頼性と効力がぐっと高まるんですよ。
では次に、実際に自分で書く場合に便利な「用紙のダウンロード方法」について見ていきましょう。
遺言書 用紙 ダウンロード方法と注意点

「遺言書って、どこかでテンプレートをダウンロードできたら助かるな」って思ったこと、ありませんか?
わたしの母もそうだったんですが、「白紙に書くのが不安」「どう書き始めていいかわからない」と言って、ネットで遺言書のひな形を探していました。
最近では、法務省や自治体・公証役場の公式サイトなどでもテンプレートや記入例を公開しているので、まずは信頼できるところからダウンロードするのが安心です。
🔸主なダウンロード先
| サイト名 | 特徴と内容 |
|---|---|
| 法務省公式サイト | 自筆証書遺言のひな形(記入例つき)あり/PDFでDL可 |
| 行政書士会のサイト | 相続や財産目録つきテンプレート/記入見本あり |
| 自治体の終活ガイド | 地方自治体で作成したやさしい解説つきテンプレートも増えてきてます |
🔸注意点①:テンプレートをそのまま印刷→手書きすること
テンプレートが便利なのは確かですが、印刷後にパソコンで打ち込んでしまうと無効になります。
たとえば「遺言内容をPC入力、署名だけ手書き」では、自筆証書遺言としての効力が認められないんです。
あくまで、「ダウンロード=記入の下書きの参考」として使ってくださいね。
🔸注意点②:罫線や余白に注意して記入
実は、罫線(けいせん)の位置に署名がかかってしまっただけで無効になったケースもあるんです。
署名欄にはしっかりスペースを取り、日付・署名・捺印が1枚の紙に収まるように気をつけましょう。
また、**財産目録を別紙にする場合も、必ず「遺言書と紐づける文言」**を記入しておくと安心です。
🔸おすすめの活用法
- テンプレートで構成を確認し、自分の言葉で手書きする
- 財産ごとに箇条書きにすると見やすくトラブル防止にも
- 不安なときは、行政書士や法務局の無料相談を活用する
テンプレートを「正しく使いこなす」ことで、自筆の遺言書もぐっと書きやすくなりますよ。
次は「法務局保管制度」の注意点やデメリットについて、さらに深掘りしていきましょう。
遺言書 テンプレート 無料で使える素材集
「遺言書を自分で書こうと思っても、何から始めたらいいのかまったく分からない…」という方、多いですよね。
実は、わたしの叔母もそうだったんですが、「遺言」と聞いただけで難しそうだし、字を間違えたらどうしようと不安になって放置してしまっていたんです。
でもある日、無料で使えるテンプレートを見つけて「これなら書けそう!」とやっと一歩踏み出すことができたそうです。
今は信頼できる無料テンプレートがたくさん公開されているので、うまく活用すれば、初めてでも失敗しにくい自筆証書遺言が書けるようになりますよ。
🔸無料テンプレートがダウンロードできる主な場所
| 提供元 | 主な内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| 法務省公式サイト | 自筆証書遺言のひな形と記入例付きPDF | 法的に安心できる内容 |
| 全国の行政書士会 | 財産目録付きのフォーマット | 相続財産を整理しやすい |
| 地方自治体の終活ガイド | 高齢者にもわかりやすいフォーマット&図解あり | やさしい言葉で説明されてる |
| 成年後見センターなど | 相続人や分割割合の書き方も例示 | 相続トラブルを防ぐ設計 |
🔸成功談:テンプレートで一気に書けた母のケース
わたしの母は、ある自治体の終活講座で紹介されたテンプレートを使って、1日で完成させたんです。
それまで「財産目録って何?」「誰にどれだけ書けばいいの?」と悩んでいたのですが、テンプレートに沿って記入するだけで、スムーズに内容が整理できて、相続人ごとにきちんと分けられたそうです。
何より、「これで残された子どもたちが困らずに済む」と安心していたのが印象的でした。
🔸テンプレートを選ぶときの注意点
- 出どころが公的機関や法律家団体のものかどうか
- 自筆証書遺言に対応した形式か(手書き前提かどうか)
- 財産目録ページがついているか
- 署名・押印欄が明確か
中には、署名欄や日付欄が見当たらないテンプレートもあるので要注意です。
署名・日付・押印は、自筆証書遺言の「効力を持たせるために絶対に必要」な3点セットですから、これが抜けるテンプレートは避けてくださいね。
🔸テンプレート活用のコツ
- まずは下書きとして使い、清書は必ず全文手書き
- 財産は箇条書きにして誰に何を渡すか具体的に
- 相続人以外に財産を残す場合も、その理由を一言添えておくと親切
テンプレートを使えば「一から考える」プレッシャーが減って、気持ちの整理にもつながる遺言書が作れますよ。
では次に、その自筆証書遺言を法務局に保管してもらう際の準備ポイントを詳しくご紹介します。
遺言書 法務局での提出に必要な準備

「せっかく書いた遺言書、なくしたり改ざんされたらどうしよう…」
そんな不安を抱えている方には、法務局での遺言書保管制度がとてもおすすめです。
この制度では、自筆証書遺言を法務局が安全に保管してくれるので、相続のときに「本物かどうか」の確認もスムーズになります。
でも、提出には事前の準備がけっこう大事なんです。
参考公的機関: 法務省「遺言書保管所における遺言書の保管申請手続について」
URL:https://www.moj.go.jp/MINJI/02.html
🔸提出前に準備しておくもの
| 準備項目 | 詳細とポイント |
|---|---|
| 自筆証書遺言 | 本人が全文手書き。財産目録はPC印刷でも可 |
| 本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカードなど写真付き |
| 保管申請書 | 法務局のサイトか窓口で取得/事前に記入が必要 |
| 手数料 | 1通につき3,900円(現金納付) |
| 印鑑(任意) | 提出時には印鑑不要/ただし訂正の際は必要なことも |
🔸失敗談:記入ミスで出直しに…
あるシニアの男性が、法務局に行った日に「署名と日付が抜けていた」ことが分かり、その場で申請できずに出直すことに。
さらに「財産目録をパソコンで作成したけど、それが本文と別紙という形で明確にされていなかった」ため、訂正にも時間がかかったそうです。
🔸提出手続きの流れ
- 法務局の予約を取る(多くは事前予約制)
- 必要書類をすべて持参し、窓口で申請
- 職員による形式チェック(内容までは見ません)
- 問題がなければその場で保管番号が発行される
- 保管後、家族に「保管してあるよ」と伝えておく
ちなみに、保管された遺言書は全国どの法務局でも確認できるようになっているので、相続人が遠方にいても安心です。
🔸法務局での保管が安心できる理由
- 遺言書が「改ざんされない」仕組み
- 相続発生時、法務局から相続人に通知される(希望者のみ)
- 家庭裁判所での「検認」が不要に
- 本人がいつでも閲覧・撤回が可能
遺言の効力を正しく保つためにも、法務局での保管はとても心強い選択肢です。
このように、準備をしっかり整えておくことで、大切な人への想いがきちんと届く形になりますよ。
次は、実際にこの制度を使う上で気をつけたい「デメリット」や誤解されがちな点について深掘りしていきましょう。
遺言書書き方法務局で正確に残す方法の注意点

法務省 遺言 サンプルの正しい使い方
「遺言書ってどう書けばいいの?」「法律に合ってるか不安…」
そんなふうに感じている方にぜひ知ってほしいのが、法務省が公開している「遺言サンプル」です。
このサンプルは、自筆証書遺言の基本構成や書き方のルールを正しく理解するためのガイドとしてとっても頼れる存在なんです。
でも、使い方を間違えると、逆に「無効な遺言書」になってしまう危険性もあるので、注意が必要なんですよ。
参考公的機関: 法務省「自筆証書遺言に関するQ&A」
URL: https://houmukyoku.moj.go.jp/gifu/content/001321181.pdf
🔸法務省のサンプルってどこで見られるの?
法務省の公式サイトには、自筆証書遺言の記載例(サンプル)と説明がセットになった資料が無料公開されています。
【掲載内容の一例】
- 遺言のタイトル(例:遺言書)
- 相続人ごとの財産配分
- 日付と署名の記入例
- 財産目録の構成例
- 保管制度との連動方法
こうした項目がA4用紙2〜3枚ほどにまとめられていて、初めての方でも視覚的に理解しやすいレイアウトになっているんです。
🔸注意すべき!サンプルの“まま”使うのはNG
「この通りに書いたら大丈夫なんでしょ?」と思ってしまいがちなんですが、法務省のサンプルはあくまで「例」です。
実際にあった失敗談として、ある70代の男性が自分の名前を「相続人:長男」と記載していたのですが、これは完全に逆。
「誰が」「誰に」どの財産を渡すのかをはっきり書かないと、相続時に効力が発揮されない可能性があるんです。
🔸正しい使い方のポイント
| 正しい使い方 | 誤解されがちな使い方 |
|---|---|
| サンプルを見ながら、自分の財産や家族構成に合わせて内容を変える | サンプルの文章をそのまま丸写しする |
| 財産目録は、自分の所有財産を具体的に書き出す | 「不動産など一式」とまとめてしまう |
| 署名と日付を手書きで忘れずに書く | 日付が抜けていた/署名が印刷だった |
| 書いたあと、保管制度を利用して保存する | 家の引き出しにしまいこみ忘れてしまう |
🔸自分仕様にアレンジして活用するのが正解!
法務省のサンプルは、遺言書作成の「お手本」ではなく「ガイドライン」として使うのが正解です。
「わたしには借金があるけど、それって書くべき?」「ペットの世話については書けるの?」など、一人ひとり異なる事情に合わせて柔軟に内容を考えましょう。
ちなみに、相続財産だけでなく「相続人に対する感謝の言葉」や「家族へのメッセージ」を添えるのも、サンプルにはない心のこもった遺言書になりますよ。
では次に、この遺言書を法務局に預けるときに気になる、「法務局保管制度のデメリット」について見ていきましょう。
自筆証書遺言 法務局 デメリットの理解
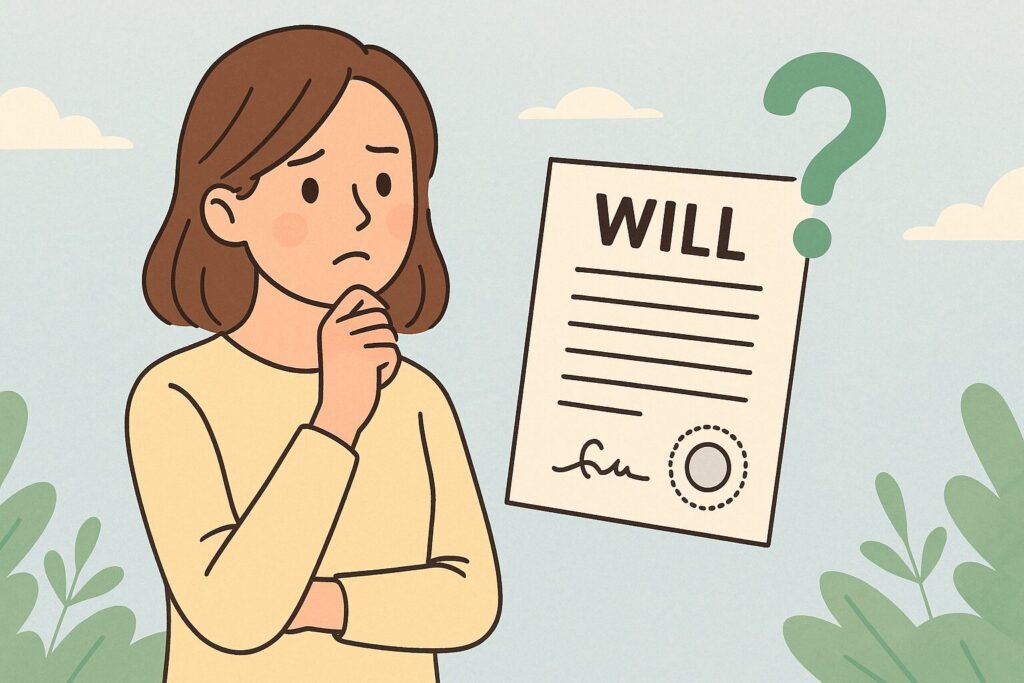
自筆証書遺言を法務局に預ける制度(遺言書保管制度)は、とても便利で安全な仕組みですが、「すべての人にとって完璧」な方法ではないんです。
利用前にデメリットをしっかり理解しておくことで、「こんなはずじゃなかった…」という後悔を防ぐことができますよ。
🔸法務局保管制度の概要(ざっくりおさらい)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象遺言書 | 自筆証書遺言のみ |
| 保管場所 | 本人の住所地・本籍地などを管轄する法務局 |
| 検認(家庭裁判所手続) | 不要 |
| 手数料 | 1通あたり3,900円(現金) |
| 保管期間 | 本人の死亡後、法務局が通知を受けた時点 |
これだけ見ると「便利そう!」と思いますが、実は見落としがちなポイントがいくつかあるんです。
🔸デメリット① 書き方の「内容チェック」はされない
法務局では、「形式が正しいか」は確認してくれますが、遺言内容の法的妥当性まではチェックされません。
たとえば、「遺産を全部A子にあげる」と書いたとしても、それが法定相続人の遺留分を侵害している場合、後で相続人間のトラブルになる可能性があります。
また、ある高齢女性のケースでは、「財産目録を記入したけれど、実際にはその不動産が亡き夫名義のままだった」ため、効力がなかったことも。
🔸デメリット② 申請できるのは本人だけ
本人が法務局に出向く必要があるので、病気や高齢、遠方に住んでいると難しいことも。
わたしの義父も、足腰が不自由で外出が大変だったため、「出張してくれないの?」と期待していたのですが…残念ながら対応していません。
そういった方には、公正証書遺言(公証人が作成)のほうが安心かもしれません。
🔸デメリット③ 他の遺言との「競合」に注意
実は、自筆証書遺言を保管していても、後から別の遺言書(たとえば公正証書遺言)が出てくると、そちらが有効になるケースもあります。
遺言書には作成日が最も新しいものが優先されるという原則があるので、「保管されてるから安心」と油断してはいけません。
🔸法務局保管制度が合わない可能性のある人
- 法的なアドバイスを受けずに遺言を書くのが不安な方
- 体調や事情で自力で法務局に行けない方
- 他の書類(遺贈契約書など)と一緒にまとめたい方
こうした方には、司法書士や弁護士に相談して「より自分に合った方法」を選ぶのがベストかもしれませんね。
以上のように、法務局の保管制度にも弱点があることを知っておけば、自筆証書遺言の選び方・書き方においてより確実で安心な判断ができるようになります。
次は、そのデメリットをカバーする「ひな形」や実例について、法務局が提供するフォーマットの使い方を詳しく見ていきましょう。
自筆証書遺言 ひな形 法務局が示す形式
「自分で遺言書を書くのって、どんな形式が正しいの?」と迷ってしまう方、多いのではないでしょうか。
特に自筆証書遺言の場合、法律で定められた形式を守らないと無効になってしまうことがあるので、本当に気をつけてほしいポイントです。
そこで役に立つのが、法務局が公開している「ひな形」や「記載例」です。
これは法務省の公式サイトなどで公開されていて、正しい形式で遺言書を書くためのガイドとして使えるんです。
たとえば、こんな形式が推奨されています。
| 項目 | 内容の書き方例 |
|---|---|
| 日付 | 「令和7年7月8日」と、西暦または和暦で年月日を明記 |
| 遺言内容 | 「長男○○に自宅(東京都○○町○丁目)を相続させる」など具体的な財産と相続人の記載 |
| 財産の特定 | 不動産なら登記簿通りに、預金なら銀行名・支店・口座番号も明記 |
| 署名・押印 | 自筆で氏名を書いて押印(認印も可能ですが実印推奨) |
このように、すべての内容を自分で手書きすることが必要です。
途中でPCで入力したり、誰かに代筆してもらったりすると、その遺言は無効になります。
実際にあったケースとして、70代の女性が息子に「ちゃんと残してね」と頼んで、息子が代筆した遺言を母の署名だけで完成させたものの、後に裁判で無効と判断されたことがありました。
「せっかく家族のためを思って書いたのに、これじゃ意味がない」と泣かれてしまったそうです。
そうならないためにも、法務局が示す正式なひな形を参考にして、自筆ですべて書き切ることがとても大切です。
このひな形は、法務局の「自筆証書遺言保管制度」の案内ページにも載っているので、そこからチェックするのが安心ですよ。
また、財産が多岐にわたる方は、財産目録を別紙でつけることもできます。
ただし、目録はワープロ作成でもOKですが、その際も1枚ごとに署名・押印が必要ですので、お忘れなく。
このように、形式通りに書いても内容に抜けがあれば効力が失われてしまうことがあるので、次にチェックしておきたいのが「書き方の簡単な落とし穴」です。
簡単な遺言書の書き方と落とし穴
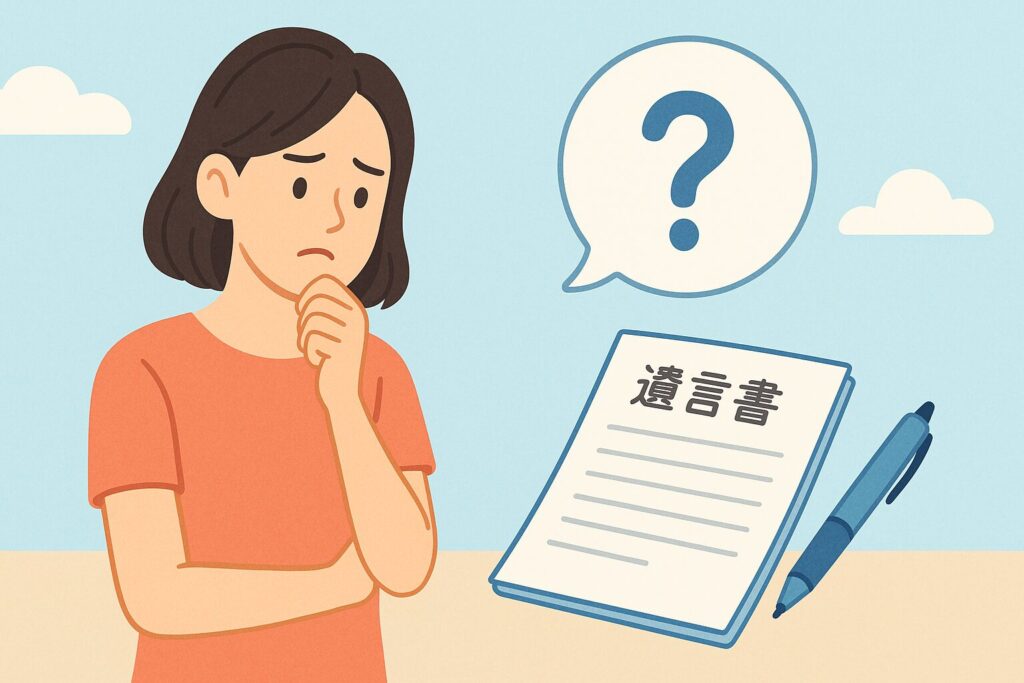
「できるだけシンプルに」「とりあえず書いておけばいいよね」と思って書いた簡単すぎる遺言書が、残された相続人にとってトラブルのもとになるケースって、実はとっても多いんです。
たとえば…
例:よくある簡略な遺言内容
「私の財産はすべて妻に相続させます。」
一見、明確に見えますよね?
でも実際は、この文面だけでは何の財産があるのか?どこに保管されているのか?相続人は他に誰がいるのか?が分かりません。
結果的に、相続の手続きに手間も時間もかかってしまうんです。
特に問題になるのが、「相続財産が不明確な場合」。
銀行口座や不動産が複数あると、それぞれに対して証明資料を出さなければならず、手続きが進まなくなることがあります。
うちの母も実は、自筆で簡単に書いた遺言書を残してくれていたのですが、「○○銀行の口座を長男に」と書いてあったものの、支店名や口座番号が不明で、銀行に問い合わせても情報が出せず…結局、遺言の効力が及ばない部分が出てしまったということがありました。
そのとき、感じたことは…
雑に書いた遺言は、かえって家族を困らせる
だからこそ、簡単に見える内容こそ、正確に・具体的に書く必要があるんです。
簡単に遺言書を書く際でも、次のようなポイントは最低限押さえておきましょう。
| 注意点 | 説明 |
|---|---|
| 財産の種類・場所を書く | 「三井住友銀行 ○○支店 普通預金 ○○番」など明確に記載 |
| 相続人をフルネームで記載 | 「妻 ○○ ○○に相続させる」と記名 |
| 署名と日付の記載必須 | 自筆で署名し、日付も忘れず明記 |
| 保管場所を家族に伝える | どこにあるか分からなければ見つからない可能性も |
このように、いくら「簡単に書ける」とはいっても、最低限のルールを守らないと効力が弱まるんです。
次にチェックしておきたいのは、無料で使えるテンプレートや例文をどう活用するか、という点になります。
自筆証書遺言の誤字の訂正方法は?
「遺言書を書いたあとに誤字を見つけちゃった…」そんなとき、どうしたらいいのか焦ってしまいますよね。
実は、自筆証書遺言はとっても繊細で、訂正のルールを間違えるとその部分の効力がなくなってしまうことがあるんです。
たとえば、こんなケースがありました。
70代の男性が「長女に300万円を贈与する」と書いたつもりが、うっかり「3000万円」と書いてしまったそうなんです。
すぐに「ゼロ1個多かった」と気づいて、横線で消して「300万円」に直したのですが、訂正の手順を踏んでいなかったために、結果的にその記載が無効となってしまいました。
そのせいで、相続人の間で「これ、本当に本人の意志なの?」とトラブルに…。
じゃあ、どうやって正しく訂正すればいいの?と不安になる方もいらっしゃると思うので、ここで正式な訂正方法をわかりやすくまとめておきますね。
参考公的機関: 法務省「遺言書の訂正・加除方法」
URL: https://www.moj.go.jp/MINJI/03.html
自筆証書遺言の訂正方法(正式な手順)
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| ① 該当部分に二重線を引く | 消したい文字に二重線を引く(定規を使うと◎) |
| ② 上や余白に訂正内容を書く | 「〇字削除、〇字加除」など正確に補足する |
| ③ その近くに署名・押印する | 署名と印鑑を忘れずに(訂正専用) |
たとえば、「長男太郎」を「長女花子」に直す場合は、
- 「長男太郎」に二重線を引く
- 近くに「長男太郎 3字削除、長女花子 3字加除」と書く
- その訂正文のそばに署名と印鑑を押す
この3ステップが必要になります。
ちょっと面倒そうに見えますが、きちんと訂正しないと、遺言の効力が失われるおそれがあるのでとっても大事なんです。
ちなみに、もし訂正が多くなってしまった場合は、新しく書き直した方が安全なこともあります。
私の叔父は、最初の遺言書を3回も訂正していて、そのたびに署名や印を忘れていた箇所があって、保管の際に法務局で「このままではお預かりできません」と言われて書き直すはめに…。
結局、最初から丁寧に書いたほうが早かった、というお話でした。
では、訂正を避けるためにも、最初に書くときに気をつけるべき注意点についても確認しておきましょう。
遺言を書くときの注意点は?
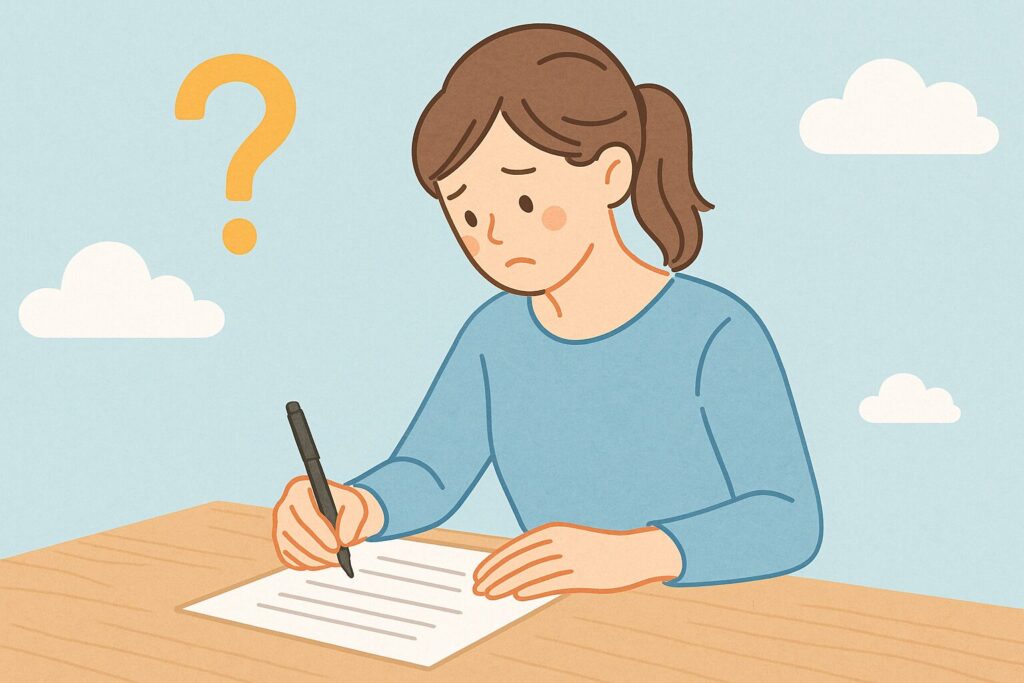
遺言書を書くときのちょっとしたミスや勘違いが、あとあと大きなトラブルを引き起こすことがあるんです。
ここでは、特に多い失敗例や注意点をわかりやすくお伝えしますね。
まず押さえておきたいのは、自筆証書遺言は全部手書きであること。
日付も名前も内容も、すべて自分で書く必要があります。
さらに、財産の内容があいまいだったり、相続人が特定できなかったりすると、その部分が無効になることもあるんです。
よくある注意点と失敗例
| 注意点 | 具体的な失敗例 |
|---|---|
| 財産の特定が不十分 | 「銀行の預金」とだけ書いて、どの銀行か不明で相続手続きがストップ |
| 相続人の名前が不完全 | 「長男に渡す」とだけ書いて、長男が2人いたケースでトラブルに |
| 日付があいまい | 「令和〇年〇月」までしか書かれておらず、複数の遺言があったときに判断不能に |
| 署名・押印忘れ | 自分の名前を書き忘れたために無効となった例も |
私の知り合いで、「とにかく早く書かなきゃ!」と焦って1日で遺言書を書いた方がいたんですが…。
後から見返したら、相続する財産に「土地」としか書いておらず、場所も番地もなくて、どの土地なのか分からずに相続人が困ってしまったそうなんです。
「せっかくお父さんが残してくれたのに…」って、ご家族が涙していました。
そこで、遺言を書くときのチェックリストを簡単にまとめておきますね。
遺言書作成時のチェックリスト
- □ 日付は「〇年〇月〇日」まで明記
- □ 相続人はフルネームで記載
- □ 財産の種類・場所・金額などをできる限り具体的に
- □ 署名と押印を忘れずに(印鑑もなるべく実印が安心)
- □ 財産が多い場合は目録を別紙で添付
- □ 保管場所は家族にこっそり伝える or 法務局で保管
こうしたポイントをしっかり押さえておけば、遺言の効力がきちんと発揮されて、相続人がスムーズに手続きできるはずです。
さて、ここまでで「遺言書を正確に書く」大切さをお伝えしてきましたが、次に気になるのが「保管方法と法務局の活用法」ではないでしょうか。
遺言書書き方法務局で正確に遺言を残す方法を理解するための総まとめ
- 自筆証書遺言はすべて手書きで作成する必要がある
- 日付は「○年○月○日」まで正確に記載する
- 署名は必ず自筆でフルネームを記載する
- 押印は実印が望ましいが認印でも有効
- 財産の記載は具体的に、口座番号や地番まで明記する
- 相続人の氏名や続柄をはっきり記載することが重要
- 財産目録を別紙にする場合も自筆で署名押印が必要
- 誤字訂正は二重線と訂正文、署名押印をセットで行う
- 訂正が多い場合は一から書き直した方が安全
- 法務局の保管制度を活用すると紛失・改ざんリスクを減らせる
- 無料テンプレートを活用すると初心者でも書きやすい
- 法務省のサンプルは構成の参考になるが丸写しは避ける
- 提出前に「必要書類」を法務局に確認しておくと安心
- 自筆証書遺言は検認が必要だが法務局保管で不要になる
- 書いたあとも内容の見直しと定期的な更新が大切
参考

お気軽にご相談ください
相続は100人いれば、100通り
唯一無二の最適な相続をご提案いたします
CONTACT
専門家やえさん

- 専門家やえさん
-
堀川 八重(ほりかわ やえ)
大阪不動産・FPサービス株式会社 代表
15年以上にわたり1,500組を超えるご家族の相続や不動産のお悩みに、専門家として寄り添ってまいりました。私の信条は、法律や数字の話をする前に、まずお客様ご家族の歴史や言葉にならない想いを丁寧に「聞く」こと。信頼できる各分野の専門家チームと共に、皆様が心から安心できる最善の道筋をオーダーメイドでご提案します。一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。
最新の投稿
 お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説
お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説 相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説
相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説 お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例
お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例 お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説
お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説






