「生活保護生命保険親が払うと違反になるの?」と不安に感じていませんか?
親が生活保護を受けている中で、子どもが死亡保険の保険料を支払っていると、「援助」とみなされる可能性があります。
生活保護で生命保険に加入していてもばれる?そんな疑問を持つ方も多いですが、調査は意外と厳しく、ばれないつもりでも発覚するケースが少なくありません。
私も最初は「生活保護者に生命保険をかけるのは当然」と思っていました。ですが、実はそれが制度上とても繊細な問題だったんです。
この記事では、「生活保護生命保険親が払う」がどこまで問題視されるのか、実際に生活保護 生命保険 調査はどう行われるのかをやさしく解説します。
あなたやご家族が損をしないために、知っておきたい制度のホンネを、生活保護 生命保険 知恵袋的にしっかりお伝えしますね。
この記事のポイント
- 親が生活保護を受けている場合に生命保険料を子どもが支払うことのリスク
- 生活保護受給中でも生命保険への加入や継続が可能な条件
- 保険契約や保険金が生活保護制度にどう影響するかの判断基準
- 調査や申告義務に違反した場合の不正受給リスクと対応方法
親が生命保険料を払うと生活保護にどう影響する?
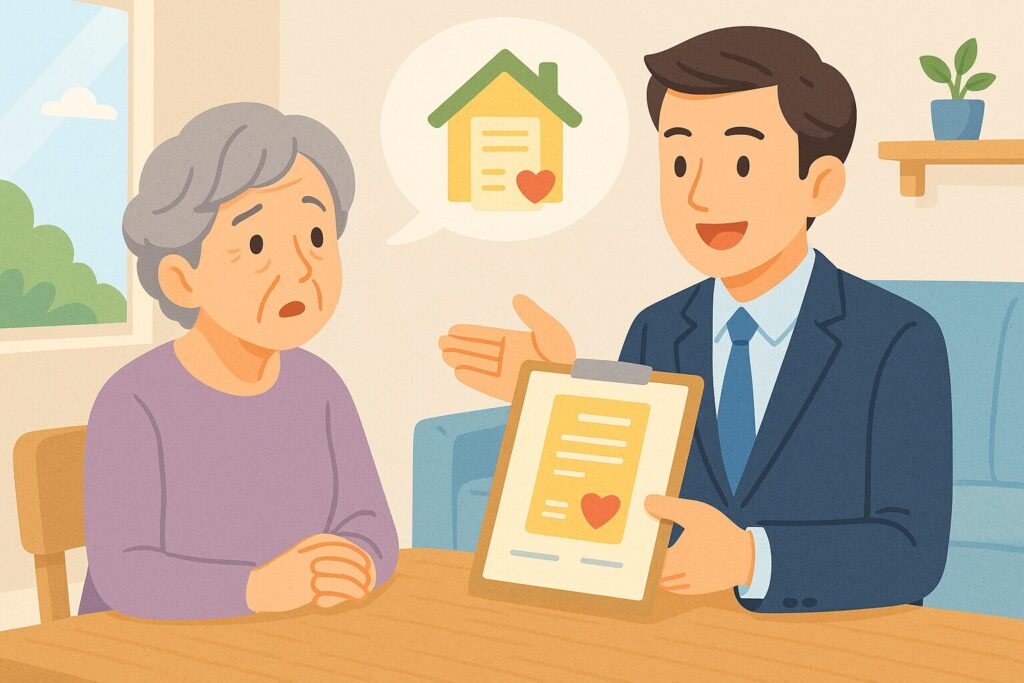
親が生活保護 生命保険の支払いは援助と見なされる?
生活保護を受けている親のために、子どもが生命保険の保険料を支払っていると聞くと、「親の代わりに払っているだけなら問題ないのでは?」と思ってしまう方もいらっしゃるかもしれません。
ただ、生活保護制度の考え方では、この行為が『親族からの援助』と見なされることがあります。
これはつまり、保険料を肩代わりすること自体が“援助能力あり”と判断される可能性があるということです。
ここで少し、制度の根本的な考え方を整理してみましょう。
| 用語 | 解説 |
|---|---|
| 生活保護 | 自分の力や資産、家族の援助では生活できないときに支給される制度 |
| 援助能力 | 親族が金銭的に支援できるかどうかの基準 |
| 保険料の支払い | 支援とみなされる可能性あり |
このように、**「保険料を親が払っていない=生活の一部を子どもが担っている」**と解釈される場合、生活保護の見直し対象になることがあるのです。
私の知り合いに、お母様が生活保護を受けている方がいました。
その方は「せめてもの親孝行に」と、月額3,000円の死亡保険の保険料を自分で支払っていたんです。
でも、保護課にそれがバレたときに言われたのは、
「保険料を出せる余裕があるなら、そもそもあなたが生活費を直接援助すべきではないですか?」
という指摘でした。
つまり、保険を継続すること以上に、“援助できる人がいる”という事実が問題視されたのです。
もちろんすべてのケースが同じとは限りません。
生活保護の運用は自治体ごとの判断にゆだねられている部分も多く、契約者が別世帯であること、返戻金が少ないこと、保険料が生活費に大きな影響を与えないことなど、条件によっては認められることもあります。
ですが、「ばれなければ大丈夫」と考えるのはとてもリスクが高いです。
黙って続けていると、最悪の場合、不正受給と判断されてしまう可能性もあるため注意が必要です。
こうしてみると、親が生活保護を受けている間に生命保険料を肩代わりするのは、善意であっても制度上は複雑な問題をはらんでいるといえるでしょう。
この問題をもう少し深掘りするために、次は「実際にばれるのかどうか」について考えてみましょう。
生活保護で生命保険に加入していてもばれる?

多くの人が気にされるのが、「生活保護を受けている間に生命保険に入っていたら、それってばれるの?」という点かと思います。
それでは、この疑問について詳しく見ていきましょう。
まず押さえておきたいのは、生活保護の審査や継続には“資産調査”があるということです。
この調査では、銀行口座の残高だけでなく、保険契約の有無や保険金の受け取り履歴まで調査の対象になるんです。
例えば、保護の申請時に記入する書類には、「保険の契約状況を正確に記載する」ことが求められます。
また、保護開始後も定期的に福祉事務所から情報提供の確認が入ることがあります。
以下に、ばれるケースとばれないと思っていても実際に発覚する事例をまとめてみました。
| ケース | 発覚する可能性 |
|---|---|
| 正直に申告した | 問題なし(条件により認可される可能性も) |
| 黙って継続していた | 保険会社からの情報照会で発覚する可能性大 |
| 死亡保険金を受け取った | 収入申告漏れにより不正受給扱いされることも |
特に注意が必要なのは、「保険金の受け取り」です。
死亡保険や解約返戻金を受け取った際に、それを申告しないままでいると、それだけで不正受給と判断される可能性があります。
一例をあげると、あるご家庭では父親の死亡により300万円の保険金を受け取ったそうです。
生活保護の受給者だった母親は申告を忘れてしまい、数ヶ月後に福祉事務所から指摘を受け、その期間中の生活保護費を全額返還するよう求められました。
たとえ意図的でなくても、こうした事態になってしまうことがあるんです。
ちなみに、保険料の支払いが毎月1,000円以下、かつ解約返戻金が30万円未満のような掛け捨て型の生命保険であれば、ケースワーカーの判断で加入が認められることもあります。
このように、すべてが「絶対にだめ」というわけではありませんが、黙っていれば通るだろうという考えは非常に危険です。
次に、そうしたケースをどう判断されるのか、どこまで調べられるのかについて触れていきたいと思います。
生活保護者に生命保険をかけることはできるのか?
「生活保護を受けている人に生命保険って、そもそもかけられるの?」という疑問を持たれる方は多いと思います。
特に親が高齢だったり、体調が不安定な場合、「もしものときのために保険をかけておきたい」と感じるのは当然の気持ちです。
ただ、生活保護の制度上は、その判断がとても慎重に行われるんです。
というのも、生命保険には「資産性」があると見なされる可能性があるからなんです。
たとえば、こんなふうに思っていたとします。
「親は生活保護を受けているけれど、私(子ども)が保険料を出しているから問題ないはず」と。
ところが、保護の考え方から見ると、その保険料の支払い自体が“援助行為”とされることもあるのです。
実際、こんな事例があります。
70代のお母様が生活保護を受けていて、娘さんが月3,000円の死亡保険をかけていました。
「自分が払っているし、資産にはならない掛け捨てタイプだし大丈夫」と思っていたそうです。
けれど、ケースワーカーさんに報告したところ、「継続するなら契約名義を変更して、受取人も見直すように」と伝えられました。
つまり、生活保護を受けている人に対して生命保険をかけることは、条件次第で認められることもあるけれど、基本的には“例外的な対応”なんです。
以下のような条件を満たしていれば、比較的認められる可能性があると言われています。
| 判断の目安 | 内容 |
|---|---|
| 保険の種類 | 掛け捨て型で返戻金が発生しないもの |
| 保険料 | 最低生活費の10~15%以下(例:生活費8万円→保険料8,000円以内) |
| 契約者 | 同居でない親族(祖父母や兄弟など)などに限定される場合あり |
| 名義 | 被保険者=生活保護受給者/契約者=他人、という形式が基本 |
ここで大切なのは、必ずケースワーカーに事前相談することです。
制度の解釈は自治体によっても違いますし、加入の意図や契約内容によって対応が分かれることもあります。
ちなみに、私の場合は母が身体を悪くして生活保護を受けることになったとき、「保険はどうすべきか」でずいぶん悩みました。
結果的には、すでに保険に入っていたものの返戻金が5万円程度だったので、「資産として見なされない」と判断され、そのまま継続できたんです。
このように考えると、「生命保険をかけたい気持ち」と「制度の制約」とのバランスを取ることがとても大切なんですね。
この話を踏まえて、次は「そもそも生活保護を受けている人自身が生命保険に入れるのか?」という疑問に進んでみましょう。
生活保護者は生命保険に入れないのか?

生活保護を受けていると、いろいろと制限があるのはなんとなくイメージできますよね。
では、「新しく生命保険に加入すること」はどうなのでしょうか。
この点、よくある誤解は「生活保護を受けたら絶対に保険に入れない」というものです。
実は、必ずしも全面的に禁止されているわけではなく、一定の条件を満たせば加入が認められることもあります。
ここで押さえておきたいのが、「補足性の原則」という生活保護制度の大前提です。
簡単にいうと、「他の手段で生活できるなら、まずそちらを優先してね」という考え方です。
そのため、資産とみなされるような保険、たとえば終身保険や返戻金付きの医療保険などは、基本的にNGとされる傾向があります。
以下に、生活保護受給者が新たに生命保険に入る際に、考慮される判断基準をまとめました。
| 比較項目 | 認められにくい保険 | 認められる可能性がある保険 |
|---|---|---|
| 保険の種類 | 終身保険、養老保険など | 掛け捨て型、低額な定期保険など |
| 資産性 | 高い(返戻金が発生) | 低い(返戻金なし) |
| 月額保険料 | 高額 | 最低生活費の10〜15%以内 |
ちなみに、ある40代男性が過去に医療保険に加入していた状態で生活保護の申請をしたところ、解約返戻金が25万円だったため「資産にあたらない」と判断されて継続が認められたそうです。
一方で、別のケースでは返戻金が50万円超だったため解約を求められ、申請自体もいったん却下されたという話もあります。
このように、具体的な金額や内容によって対応が大きく分かれるのが現実なんですね。
そしてもうひとつ重要なのが、「保険に加入していることを黙っていた場合」のリスクです。
ばれなければいい、と思っていても、資産調査で発覚することがほとんどです。
そのときに無申告だったと分かると、最悪の場合は不正受給として過去の生活保護費を返還しなければならないこともあるんです。
このような背景があるので、生命保険の加入を考えている方は、まずケースワーカーに正直に相談することが何よりも大切です。
この話題をさらに深めるには、「保険金を受け取った場合どうなるのか」という点も確認しておくと安心かもしれません。
生活保護 生命保険 調査はどこまでされる?
「生活保護を受けたら、保険会社に入っていることまで本当に調べられるの?」という声をよく耳にします。
正直なところ、私も最初にこの制度について調べていたとき、「そんな細かいところまで見られるの?」と驚いたことを覚えています。
でも、今ではわかります。
生活保護という制度は、税金で支えられている大切な社会保障なので、不正を防ぐためにも調査はとても丁寧に行われているんです。
まずは、調査の範囲について全体像をつかんでいただくために、以下の表にまとめました。
| 調査項目 | 内容 | チェックされる目的 |
|---|---|---|
| 銀行口座 | 残高・入出金履歴 | 収入や貯金の有無を確認 |
| 生命保険 | 契約の有無・返戻金 | 資産性があるか判断するため |
| 不動産 | 土地・建物の所有 | 生活に必要ない資産の売却確認 |
| 車両 | 所有の有無 | 不要な資産とみなされることがある |
| 収入 | 給与・年金・副業など | 毎月の生活費に影響するから |
ここで注目したいのが「生命保険」の調査です。
実は、生活保護の申請時に、「資産調査への同意書」にサインを求められることが多いんですね。
この書類にサインをすると、福祉事務所は本人の同意のもとで、保険会社や銀行に対して情報開示を求める権限を持つようになります。
そのため、申請者が「保険に入っていない」と自己申告していても、本当に未加入なのかは裏取りがされることが多いのです。
実際、ある主婦の方が生活保護を申請したとき、10年前に加入したまま忘れていた掛け捨ての保険が調査で見つかり、「その内容次第で保護の継続可否を判断する」と言われたそうです。
このように、保険が「資産」になるかどうかが判断の分かれ目なんです。
例えば、
- 返戻金がある終身保険や養老保険 → 資産とみなされるため原則解約
- 返戻金がない掛け捨て型の死亡保険 → 条件付きで継続可能
という違いがあります。
また、もし保険金を将来的に受け取る予定がある場合、それが**「死亡後の収入」として取り扱われる可能性がある**ので、事前にきちんとケースワーカーに相談するのが安心です。
ここでちょっとした例え話を挟ませてくださいね。
保険の調査って、たとえるなら「小学生の持ち物検査」に少し似ているかもしれません。
鉛筆や消しゴムはOKだけど、ゲーム機を持っていたら「これは遊ぶためのものだよね?学校に必要ないよね」と取り上げられますよね。
同じように、生活保護では「これは最低限の生活に必要なものか?」という視点で、持ち物(=資産や契約内容)を見ていくんです。
このように考えると、保険の加入そのものが悪いわけではなく、資産性があるかどうかが問題とされるのが、制度のポイントなんだとわかりますよね。
ちなみに、私の場合も、母の生活保護申請をお手伝いしたとき、わずかに残っていた小さな保険が調査で見つかりました。
返戻金は3万円ほどだったので「この程度なら大丈夫」と言われたのですが、申告せずに黙っていたら問題になっていたと思います。
こうした事例からもわかるように、保険に関する調査は想像以上にしっかり行われるということを心にとめておくとよいでしょう。
では次に、「生活保護を受けている親の保険料を子どもが払っている場合、それはどう判断されるのか?」という点について見ていきましょう。
生活保護生命保険親が払う場合のリスクと例外

生活保護 死亡保険 子供が払うと認められる?
生活保護を受けている方が死亡保険に入っている場合、もし保険料を子どもが代わりに払っているとしたら、それは認められるのでしょうか?
この点はとても繊細な話で、福祉の現場でも判断が分かれるところなんです。
まずお伝えしておきたいのは、生活保護制度は「本人や世帯が生活できる力をすべて使ったうえで、それでも足りないときに支援する制度」という点です。
ですので、親のために子どもが死亡保険の保険料を支払っているとなると、「それって実質的な援助では?」とみなされる可能性が出てきます。
たとえば、こんなケースを想像してみてください。
母親(生活保護受給者)が、もしものときに備えて死亡保険に加入していたとします。
でも、生活保護を受け始めたあとも、娘さんがその保険料を負担し続けていました。
この状況を福祉事務所が知った場合、「それだけ支援できる家族がいるなら、生活保護の対象ではないのでは?」と判断されるリスクがあります。
ここで大事になってくるのが、「保険の契約形態」と「保険料の流れ」です。
以下の表にまとめてみました。
| 契約者 | 被保険者 | 保険料支払者 | 判断されやすい内容 |
|---|---|---|---|
| 子ども | 親 | 子ども | 親族援助とみなされる可能性高 |
| 親 | 親 | 子ども | 援助とみなされることが多い |
| 子ども | 子ども | 子ども | 問題なし(親は関係なし) |
このように、子どもが契約者・支払者で、親が被保険者になっている場合は、特に注意が必要なんです。
とはいえ、例外的に認められるケースもあるとされています。
たとえば、
- 生活保護の受給が一時的なものである
- 保険の内容がごくわずか(保険料が低額、解約返戻金がほとんどない)
- 将来の就労や収入回復の見通しが立っている
こういった条件がそろえば、「今だけ子どもが支払っていても、保護を打ち切る理由にはならない」と判断される場合もあるんですね。
これって、たとえるなら「親が働けない間だけ、息子さんが実家の新聞代を払ってあげている」ようなものです。
その後、親が元の生活に戻れるなら、それは一時的な助けと考えることもできるというわけです。
ただ、これもあくまでケースワーカーの判断次第になります。
同じ状況でも、地域によっては「完全にアウト」と判断されることもあれば、「今回は特別に認める」となることもあるのが現状です。
ちなみに、私の場合も、義母が生活保護を受けることになったとき、主人が「保険料くらい自分が払うよ」と言い出しました。
でも、ケースワーカーさんから「それを続けるなら、生活保護の対象ではなくなるかもしれません」と、はっきり言われました。
そこで、義母が保険を一度解約し、今は元気になってから再度入り直すことにしたんです。
こうした事情からも、死亡保険を子どもが払っている場合は、援助と見なされる可能性が非常に高いという点は、知っておいていただきたいです。
では、次に「生活保護で生命保険を親が払っている場合」について詳しく見ていきましょう。
生活保護で生命保険を親が払っている場合どうなるのか?

「親が生活保護を受けているけど、生命保険の保険料は親自身がなんとか支払っているんです…これって大丈夫ですか?」
実際、こうした相談は意外と多いです。
まず押さえておきたいのは、生活保護を受けている人が生命保険に加入し続けることは、原則として難しいという制度の背景です。
これは、生命保険が資産として扱われる可能性があるからです。
ですが、保険にはさまざまなタイプがありますよね。
以下のように整理すると、イメージがつかみやすいかもしれません。
| 保険の種類 | 保険料(月額) | 解約返戻金 | 継続可能性 |
|---|---|---|---|
| 終身保険(貯蓄型) | 5,000円以上が多い | 数十万円~ | 原則不可(資産) |
| 掛け捨て型保険 | 数百円~3,000円程度 | なしまたは少額 | 条件付きで可能 |
| 医療保険 | 2,000円~6,000円 | なしまたは少額 | 条件次第で可 |
このように、「掛け捨て型」で返戻金がないタイプの保険であれば、親が自分で保険料を支払っていたとしても、状況によっては認められることもあります。
たとえば、生活扶助の中から保険料を支払っていて、月額が収入の10%以内(約8,000円未満)だったり、保険金が最低限の額であったりする場合には、「それなら保険を継続しても生活に大きな支障はないですね」となることもあるんです。
でも、ここで注意が必要なのが「支払えている=余裕がある」とみなされてしまう可能性です。
たとえば、毎月5,000円の保険料を支払っているとすると、「それだけのお金があるなら、生活保護の受給額を減らしても良いのでは?」という判断がされることも。
たとえるなら、毎月ギリギリの生活をしているのに、映画館のサブスク(月3,000円)に入っているようなものです。
それが本当に生活に必要なのか?と問われることになるんですね。
また、保険料を生活扶助から出していたとしても、その使用内訳を説明できるようにしておくことが大切です。
ケースワーカーから「この支出は本当に必要ですか?」と聞かれたときに、何にいくら使っているかを答えられないと、「これは支援の使い方としてふさわしくない」と判断される場合もあります。
ちなみに、私の友人の母親も、以前から入っていた掛け捨て型の保険を生活保護受給中に継続していました。
そのときも、保険料は1,500円程度で、担当のケースワーカーに相談した結果、「この程度なら認めます」と言っていただけたそうです。
このように、親が保険料を支払っている場合でも、内容や金額次第で判断は変わるんです。
次のセクションでは、こうしたケースで「保険金を実際に受け取ったとき」にどうなるのか、詳しく見ていきましょう。
生活保護 保険金 ばれないと思っていても危険
「生活保護を受けているけれど、実はこっそり保険金を受け取ったことがある」「小さな額だから、ばれないと思っている」……そんなふうに思っていらっしゃる方も、もしかしたらいらっしゃるかもしれません。
ですが、生活保護の制度において「保険金の未申告」は、想像以上に重い問題として扱われます。
まず前提として、生活保護受給者は、すべての収入を福祉事務所へ報告する義務があります。
たとえ一時的なものであっても、保険金のように現金で受け取れるものは「収入」としてカウントされるんですね。
たとえば、死亡保険金を100万円受け取った場合。
一見すると、「これは遺族として当然の補償」だと感じるかもしれません。
でも生活保護の制度上は、この100万円は資産とみなされ、「まずこれで生活してからにしてくださいね」という扱いになります。
実際のところ、ケースワーカーには調査権限があり、以下のような調査が行われています。
| 調査項目 | 内容 |
|---|---|
| 金融機関の照会 | 銀行・ゆうちょ・ネット銀行の入出金履歴確認 |
| 保険会社への確認 | 解約返戻金・死亡保険金の受取履歴 |
| 世帯収入の聞き取り | 年金やパート収入、援助などもチェック対象 |
こうして見ると、「ばれないだろう」と思っていても、実際には高確率で把握されていることがわかります。
私の知人の話ですが、お母様が亡くなられて、50万円の死亡保険金を受け取ったことがありました。
その方は「少額だし言わなくていいかも」と思っていたそうなのですが、後日、福祉事務所から「この保険金の使途について説明してください」という連絡が入り、とても驚いたとお話されていました。
結果として、その方は保護費の一部を返還することになりました。
金額によっては、それに加えて「過去にさかのぼっての保護費返還命令」が出されることもあり、さらに悪質と判断されれば、不正受給として刑事告発される場合もあるんです。
これを例えるなら、「食費をもらっていたのに、実は隠し弁当を持ち込んでいた」ようなものです。
正直に伝えていれば、「今日の分は不要ですね」と済んだ話が、隠していたという事実だけで信頼を失ってしまうんですね。
ちなみに、私の場合、義父の死亡保険金を受け取った際には、すぐに担当のケースワーカーさんへ報告しました。
正直に申告したことで「それでは、当面はその金額で生活いただき、保護は一時停止しましょう」とスムーズに話が進み、大ごとにならずに済んだのです。
このように、「保険金は申告しなくても大丈夫」という考え方は非常に危険であり、必ず報告するという姿勢がご自身と家族を守ることにもつながります。
では、そのようにして受け取った保険金――とくに死亡保険金――が、生活保護制度の中でどのように扱われるのかを次で見ていきましょう。
生活保護 生命保険 死亡保険金の扱いは?

「もし親が亡くなって、死亡保険金を受け取ったら、生活保護はどうなるのか気になる…」という方、実はとても多いんです。
死亡保険金というのは、人の死に関わる大切なお金ですし、突然の出来事で生活に混乱が生じることもありますよね。
では、この死亡保険金、生活保護を受けている方やその家族が受け取った場合、どう扱われるのでしょうか。
ポイントは、「誰が受け取るか」「いくら受け取るか」「いつ申告するか」です。
まず、死亡保険金は原則として「収入」として扱われます。
それは一時的なものであっても、生活費にあてられるだけの金額であれば、生活保護を一時的に停止されたり、受給額を減額される原因になるんですね。
以下の表に、よくあるケースをまとめてみました。
| 保険金の受取人 | 状況 | 生活保護への影響 |
|---|---|---|
| 本人(受給者) | 保険契約者・被保険者ともに本人 | 原則、保険解約 → 保護停止または減額 |
| 家族(同一世帯) | 子や配偶者が受取人 | 世帯収入として計算 → 減額対象 |
| 別世帯の親族 | 例えば子どもが独立していて別居 | 場合によって影響なし。ただし申告要 |
ここでよくある誤解が、「自分じゃなくて、子どもが受け取ったから大丈夫」というものです。
ですが、同じ住所に住んでいる世帯員であれば、受け取った保険金も「世帯の収入」として扱われます。
このあたりは、たとえば「夫が働いているけど、私名義で生活保護を受けている」ようなケースに似ていて、家計が一つであれば、収入も合算して判断されるというイメージです。
また、受け取った金額が一定の基準を超えると、「しばらくはその保険金で生活してください」と保護が打ち切られることもあります。
一般的に、その基準は生活扶助の3ヶ月分程度(約30~50万円)とされています。
ちなみに、私の友人のケースでは、亡くなった親の保険金80万円を受け取った後、2ヶ月間は生活保護が停止されました。
保険金が生活を支えるのに十分だと判断されたからです。
ただ、その後も失業中で収入がなかったため、あらためて生活保護の申請を行い、無事に再開されたそうです。
こうした経験からもわかるように、死亡保険金の扱いはケースバイケースですが、基本的には「生活費として使えるお金=収入」とみなされることが多いんです。
そして、なによりも大切なのは、保険金を受け取ったらすぐに申告すること。
「言わなければバレないかも」と思ってしまう気持ちもわかるのですが、それが大きなトラブルにつながってしまうこともあります。
このように、死亡保険金がどう扱われるのかを知っておくことで、生活保護との両立においても安心感を持てるようになります。
では次に、こうしたケースで受け取る「保険金」が、どこまで調査されるのかを一緒に確認していきましょう。
生活保護 死亡保険 受け取り時の注意点
死亡保険金を受け取るとき、「生活保護を受けていても保険金は受け取っていいのか」という悩みをお持ちの方はとても多いです。
私もはじめてこの話を聞いたとき、「保険ってそもそも家族のためのお金なのに、なんで問題になるの?」と正直、疑問に思いました。
でも実際は、生活保護制度のなかでは、死亡保険金も“収入や資産の一部”と見なされることがあるんです。
たとえば、ある日突然親族が亡くなり、保険金として100万円が振り込まれたとします。
受け取った人が生活保護を受けている場合、その100万円が“自力で生活できるお金”と判断される可能性があるのです。
ここで知っておきたいのが、死亡保険金の金額に応じて生活保護の支給に変化が出ることがあるという点です。
| 保険金の金額 | 生活保護への影響 |
|---|---|
| 30万円未満 | 一般的には収入と見なされず、そのまま保護継続可 |
| 30万〜50万円 | 一時的な停止や減額の可能性あり |
| 50万円以上 | 保護の打ち切り、または再申請が必要になるケースも |
たとえ一時的な金額であっても、申告せずに保険金を受け取ってしまうと、“不正受給”として扱われることがあるんですね。
これはたとえるなら、給食費を免除されている子どもが、お小遣いで毎日ランチを買っているのを見つけられてしまったようなもの。
「それならもう免除は必要ないですよね?」という判断になってしまうのです。
また、死亡保険金が「葬儀費用」として使われることがはっきりしている場合は、ある程度柔軟な判断がされることもあります。
その際は、領収書や費用の内訳など、きちんとした使途証明が必要になります。
ちなみに私の場合、祖母の死亡時に保険金が入りましたが、そのお金で葬儀社や火葬場の費用などをすべて支払ったうえで、担当ケースワーカーさんに明細を提示しました。
そのおかげで特に問題なく、保護は継続されました。
こうした一連の流れを見ていると、死亡保険金は受け取っても良いが、必ず「使い道」と「申告」が重要な判断ポイントになるとわかります。
では次に、生活保護を受けている親がまだ生きている場合に、保険契約がどうなるのか、という少し踏み込んだ内容を見ていきましょう。
生活保護を受けている親が生きていたらどうなる?

「生活保護を受けている親が生きている間、保険ってどう扱われるの?」というご相談もよくあります。
このケースでは、親が生命保険に加入しているかどうか、そして誰が契約者なのかが重要なポイントになります。
たとえば、親自身が契約者・被保険者で、保険料も自分で支払っていた場合、生活保護申請の際にはその保険の内容を必ず報告する必要があります。
なぜなら、保険に解約返戻金がある場合、それが“資産”と判断されてしまうからです。
ここでは、よくあるパターンを表で整理してみました。
| 親の立場 | 保険の契約内容 | 保護制度の対応 |
|---|---|---|
| 加入者・保険料支払い者 | 解約返戻金あり | 解約を求められる可能性大 |
| 加入者・保険料は子供が支払い | 掛け捨て型 | 継続の判断はケースワーカーによる |
| 名義は親族(子ども)・親が被保険者 | 掛け捨て型または死亡保障型 | 状況により継続可能なことも |
つまり、「親がまだ生きている=影響はない」というわけではないのです。
たとえば、実家の母が掛け捨ての医療保険に入っていたんですが、保険料が月に7,000円もして、生活保護費の1割以上を占めていたんですね。
そのため、ケースワーカーさんから「この保険料は生活費に充ててください」と指導され、泣く泣く解約したという話を聞いたことがあります。
このように、生活保護を受けている間は「保険に入っていること=問題」ではなく、「保険料をどう払っているか」と「保険の内容」が焦点になります。
また、親が死亡した際に受け取る可能性のある死亡保険金も、生活保護との兼ね合いでしっかり確認されます。
とくに「親が生活保護を受けている間に子どもが保険料を払っていた場合」は、「援助とみなされる」可能性があるため注意が必要です。
生活保護生命保険親が払う場合の制度的リスクと判断ポイント
- 生命保険料を親の代わりに子が払うと援助とみなされる可能性が高い
- 親が生活保護を受けている場合、子の保険料負担は支援能力の証拠と見なされやすい
- ケースワーカーは契約者・支払者・被保険者の関係を詳細にチェックする
- 保険の種類や返戻金の有無が継続可否の判断材料になる
- 掛け捨て型の保険であっても、無申告で続けると不正受給とされることがある
- 生活保護制度では「保険=資産」と判断されることが多い
- 自治体によって運用判断が異なるため事前相談が重要となる
- 保険金を受け取った場合は「収入」として申告義務がある
- 少額の保険料でも生活費に影響すると判断されることがある
- 死亡保険金の申告漏れは返還請求や支給停止の対象になる
- 調査対象には銀行口座・保険契約・保険金受領履歴などが含まれる
- 同一世帯の家族が保険金を受け取ると生活保護に影響することがある
- 契約名義の変更や内容の見直しで継続可能になるケースもある
- 保険料が生活扶助の10~15%以内なら認められる可能性がある
- 保険に関する対応は「ばれなければ大丈夫」ではなく慎重な判断が必要
参考
・お墓除草剤スピリチュアル|金運・健康運を守る正しい使い方
・老後旦那といたくない理由とは?離婚せずにできる現実的対処法
・親の介護ねぎらいの言葉例文15選|励ましではなく心に届く言葉とは
・遺骨ペンダントティファニー後悔しないための選び方ガイド
・お墓の夢宝くじが当たる前兆?夢占いで金運アップを読み解く

お気軽にご相談ください
相続は100人いれば、100通り
唯一無二の最適な相続をご提案いたします
CONTACT
専門家やえさん

- 専門家やえさん
-
堀川 八重(ほりかわ やえ)
大阪不動産・FPサービス株式会社 代表
15年以上にわたり1,500組を超えるご家族の相続や不動産のお悩みに、専門家として寄り添ってまいりました。私の信条は、法律や数字の話をする前に、まずお客様ご家族の歴史や言葉にならない想いを丁寧に「聞く」こと。信頼できる各分野の専門家チームと共に、皆様が心から安心できる最善の道筋をオーダーメイドでご提案します。一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。
最新の投稿
 お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説
お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説 相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説
相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説 お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例
お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例 お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説
お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説






