「私の介護保険料っていくらなんだろう…?」なんて、給与明細や年金の通知を見て、頭にハテナが浮かんだ経験はありませんか?(私はあります!笑)40歳になった途端に始まる介護保険料の計算。
かと思えば、65歳以上になるとまた計算方法が変わるなんて、ちょっと複雑すぎますよね!介護保険料は年収で決まるって聞くけど、具体的な計算方法や、計算に使う合計所得金額とは何なのか、よくわからない…という方も多いのではないでしょうか。
この記事では、そんなあなたのモヤモヤを吹き飛ばします!介護保険料一覧表や介護保険料計算表を使いこなし、40歳、65歳以上、そして75歳以上といった年齢別の保険料や、国民健康保険料の計算シミュレーション、後期高齢者保険料の計算シミュレーションとの違いまで、まるっと解説。
介護保険料の自動計算の仕組みや月額の目安も、どこよりも分かりやすくお伝えしますので、ぜひ最後までついてきてくださいね!
この記事のポイント
- 介護保険料の基本的な計算の仕組みがわかる
- 年齢や所得による保険料の違いを具体的に理解できる
- ご自身の介護保険料のおおよその金額を把握できる
- 計算で使われる専門用語の意味がスッキリわかる
目次
介護保険料計算シミュレーションの基礎知識
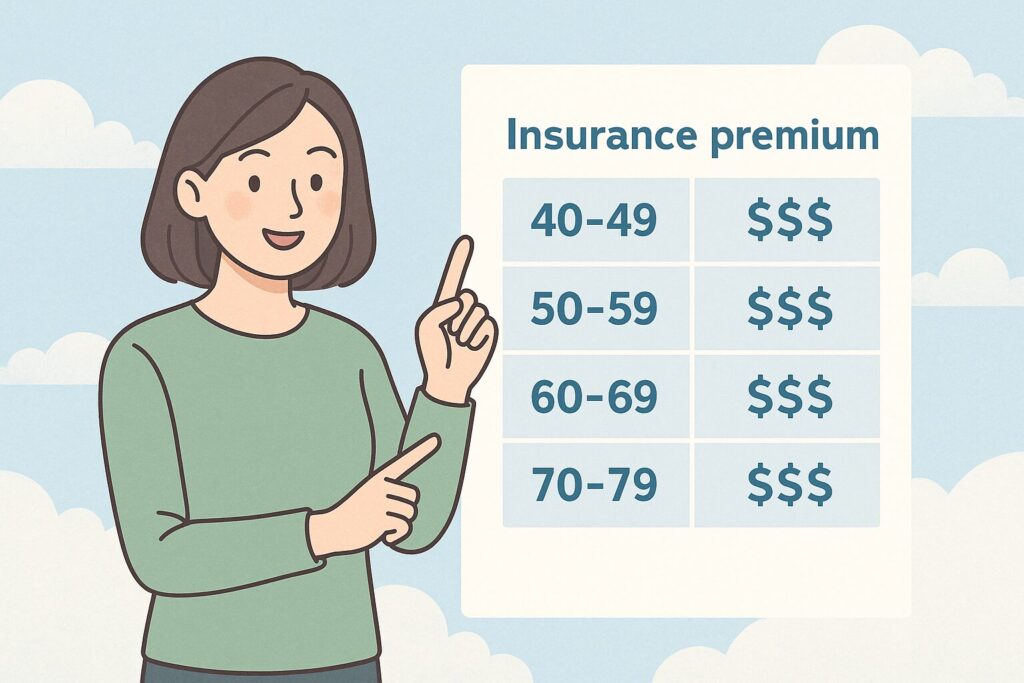
基本的な介護保険料の計算方法
こんにちは!あなたの「お金のギモン」をスッキリさせる案内人のアヤです!さて、さっそくですが、私たちの生活に深く関わる「介護保険料」。一体どうやって計算されているのか、気になりますよね。実は、介護保険料の計算方法は、年齢によって大きく2つのグループに分かれているんです。
それが、「第1号被保険者」と「第2号被保険者」です。なんだか難しそうに聞こえますが、大丈夫!一つずつ見ていきましょう。
介護保険の2つのグループ
- 第1号被保険者:65歳以上の方
- 第2号被保険者:40歳から64歳までの医療保険加入者
まず、40歳から64歳までの現役世代である「第2号被保険者」の場合、計算方法はご自身が加入している健康保険の種類によって異なります。会社員の方なら健康保険組合や協会けんぽ、自営業の方なら国民健康保険といった具合です。基本的には、お給料や所得に応じて保険料が決まり、健康保険料と一緒に徴収される仕組みになっています。
一方、65歳以上になる「第1号被保険者」の計算方法は、お住まいの市区町村が主役になります。各自治体が「うちの市(区、町、村)で必要な介護サービスの総費用はこれくらいだから、一人あたりの基準額は〇〇円ね!」という感じで、「基準額」を決めます。そして、その基準額に、前年の所得に応じた段階別の「保険料率」を掛けて、一人ひとりの年間の介護保険料が決定されるのです。
つまり、第1号被保険者の介護保険料 = 自治体の基準額 × 所得段階ごとの保険料率 という式で成り立っているんですね。この「所得段階」が、次のテーマである「年収」に大きく関わってきます。
ちなみに、この保険料を財源にして、介護が必要になったときに1割~3割の自己負担でサービスを受けられるのが「介護保険制度」です。みんなで支え合う、大切な仕組みなんですよ。
介護保険料は年収で決まるのか解説

「結局のところ、介護保険料って年収で決まるの?」という疑問、とってもよく分かります!結論から言ってしまうと、YES!介護保険料はあなたの年収(正しくは所得)に大きく左右されます。
特に65歳以上の第1号被保険者の場合、この仕組みがとても分かりやすく反映されています。前述の通り、お住まいの市区町村が定めた「基準額」に、所得に応じた「保険料率」を掛けて計算されるとお伝えしましたよね。この「保険料率」が、まさに所得段階によって細かく分けられているんです。
多くの自治体では、所得の低い方には負担が軽くなるように低い料率を、所得の高い方には応分の負担をお願いするために高い料率を設定しています。標準的には13段階程度に分かれていることが多いですが、自治体によってはさらに細かく設定しているところもあります。
所得段階のイメージ
例えば、住民税が非課税の世帯の方や生活保護を受けている方は最も低い第1段階、逆に所得が非常に高い方は最も高い第13段階(あるいはそれ以上)といったイメージです。真ん中の第5段階あたりが「標準」で、保険料率は1.0倍(つまり基準額そのもの)に設定されていることが多いですね。
私の友人で、親の介護を機に実家に戻った子がいたんですが、そのお父様が退職されて年金暮らしになったんですね。現役時代と比べて所得がガクッと下がったので、翌年度の介護保険料の通知が来たときに「え、こんなに安くなるの!?」と驚いていました。これはまさに、所得に応じて保険料が変動する良い例だと思います。
一方、40歳から64歳までの第2号被保険者も、会社員であればお給料(標準報酬月額)に保険料率を掛けて計算されるので、やはり収入が多いほど保険料も高くなります。どの年代であっても、介護保険は「負担できる人が、その能力に応じて負担する」という考え方が基本になっている、と理解しておくとスッキリしますね。
介護保険料はいくら?年収別に紹介
「じゃあ具体的に、私の年収だと介護保険料はいくらくらいになるの?」と思いますよね。ここでは、65歳以上の方をモデルに、年収(年金収入)別の保険料の目安を見ていきましょう。
ただし、これはあくまで一例です!前述の通り、実際の保険料はお住まいの市区町村の「基準額」や「所得段階の分け方」によって大きく異なります。正確な金額は、必ずお住まいの自治体のホームページなどで確認してくださいね。
ここでは、全国の標準的なモデルとして、基準月額が6,500円のA市を例に考えてみましょう。
| 本人の年金収入(年間) | 世帯の状況 | 該当する所得段階(例) | 保険料(月額)の目安 |
|---|---|---|---|
| 80万円以下 | 世帯全員が住民税非課税 | 第1段階(料率0.3倍など) | 約1,950円 |
| 150万円 | 本人のみ住民税非課税 | 第4段階(料率0.9倍など) | 約5,850円 |
| 200万円 | 本人のみ住民税課税 | 第6段階(料率1.2倍など) | 約7,800円 |
| 300万円 | 本人のみ住民税課税 | 第7段階(料率1.3倍など) | 約8,450円 |
| 500万円 | 本人のみ住民税課税 | 第10段階(料率1.9倍など) | 約12,350円 |
いかがでしょうか?年金収入が上がるにつれて、月々の保険料も段階的に上がっていくのが分かりますね。特に注意したいのが、「世帯の状況」です。ご自身が住民税非課税でも、同居している家族に課税者がいると、保険料の段階が変わることがあります。
世帯分離の影響
お客様から「親の介護保険料を安くするために世帯分離をした方がいい?」と聞かれることがあります。確かに、世帯分離をして親が単身の非課税世帯になれば、保険料が下がるケースはあります。ただ、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料など、他の部分で負担が増える可能性も…。メリット・デメリットを総合的に判断する必要があるので、安易な世帯分離は禁物ですよ。
まずはご自身の昨年の年収(公的年金等の源泉徴収票を確認!)と、お住まいの自治体の介護保険料の段階表を見比べて、ご自身の保険料をチェックしてみてくださいね。
参考情報サイト: 厚生労働省「第9期計画期間における介護保険の第1号保険料について」
URL:https://www.mhlw.go.jp/content/12303500/001253798.pdf
計算に使う合計所得金額とは?

さて、保険料の計算の話で必ず出てくるキーワード、「合計所得金額」。なんだか税金の専門用語みたいで、ちょっと身構えちゃいますよね(笑)。でも、大丈夫!仕組みは意外とシンプルです。
一言でいうと、「合計所得金額」とは、あなたの1年間の「儲け」の合計のことです。会社員の方のお給料や、自営業の方の事業の儲け、そして年金などもこれに含まれます。
ここでポイントなのが、「収入」と「所得」は違う、ということです。
収入と所得の違い
- 収入:会社から支払われる給与の総額や、年金の額面金額そのもの。
- 所得:収入から、必要経費にあたる「控除額」を差し引いた後の金額。
例えば、お給料をもらっている方なら、年収(給与収入)から「給与所得控除」という、いわば「サラリーマンの必要経費」を引いたものが「給与所得」になります。同じように、年金をもらっている方も、年金収入から「公的年金等控除」を引いて「雑所得」を計算します。
これらの計算された所得(給与所得、事業所得、雑所得など)をぜーんぶ合計したものが、「合計所得金額」となるわけです。
え?控除額はどうやって計算するのかって?それは国税庁のホームページに速算表があるんですよ。でも、自分で計算するのはちょっと大変ですよね。なので、まずは「収入と所得は違うんだな」「保険料計算で見るのは、経費を引いた後の『所得』の方なんだな」と覚えておけばOKです!
遺族年金・障害年金は非課税
ここで一つ、とても重要な注意点があります。遺族年金や障害年金は、税法上「非課税所得」とされています。そのため、これらは介護保険料を計算する際の合計所得金額には含まれません。老齢年金と遺族年金を両方もらっている方などは、計算の基になるのが老齢年金の部分だけになるので、覚えておいてくださいね。
参考情報サイト: 国税庁「No.1410 給与所得控除」
URL: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
便利な介護保険料計算表の活用法
「所得の計算とか、やっぱり自分でやるのは難しそう…」と感じたあなたに朗報です!今や、多くの市区町村のホームページで、オンラインの「介護保険料計算表(シミュレーター)」が用意されているんです。これは使わない手はありません!
これらのシミュレーターは、多くの場合、こんな情報を入力するだけで、あなたの年間の介護保険料をパパっと自動で計算してくれます。
- 昨年の公的年金収入
- 昨年の給与収入
- その他の所得
- 年齢
- 世帯の状況(課税者がいるか、など)
先日、お客様にこの話をしたところ、「え、そんな便利なものがあるの!?」と早速スマホで試していました。その方は年金とパート収入があったのですが、源泉徴収票と給与明細を見ながらポチポチ入力するだけで、年間の保険料の目安がすぐに表示されて、「これでやっとスッキリしたわ~!」と、とても喜んでいらっしゃいました。
計算表を使うメリット
最大のメリットは、面倒な所得計算や、ご自身の所得段階を探す手間が省けることです。特に、複数の収入源がある方や、ご自身の所得段階がどの区分になるか分かりにくい方にとっては、力強い味方になります。
ただし、いくつか注意点もあります。これらのシミュレーターで算出されるのは、あくまで「概算額」です。実際の保険料は、賦課期日(通常は4月1日)時点での世帯の状況などで最終決定されるため、多少の誤差が出ることがあります。
また、シミュレーターによっては対応していない所得の種類があったりもします。それでも、大まかな金額を把握して、年間の家計の計画を立てる上では非常に役立ちます。ぜひ一度、「〇〇市 介護保険料 シミュレーション」といったキーワードで検索してみてくださいね!
自治体ごとの介護保険料一覧表

「お隣の市に住んでる友達と、年収は同じくらいなのに介護保険料が違う…」なんて話、聞いたことありませんか?そうなんです、介護保険料は、お住まいの市区町村によって金額が変わります。全国一律ではないんですね。
なぜかというと、65歳以上の方の介護保険料は、その自治体で「どれくらいの介護サービスが必要と見込まれるか」を基に算出されるからです。
なぜ自治体によって保険料が違うの?
高齢者の人口が多い自治体や、介護施設の整備に力を入れている自治体では、それだけ介護サービスにかかる費用も多くなります。そのため、保険料の基準額が高くなる傾向があるのです。逆に、高齢者人口が比較的少なく、健全な財政運営をしている自治体では、基準額が低めに設定されることもあります。
例えば、厚生労働省の発表によると、令和6年度~8年度の介護保険料の基準額が全国で最も高いのは大阪府大阪市で月額9,249円。一方、最も低いのは東京都小笠原村で月額3,374円と、その差は歴然です。(参照:厚生労働省「第9期計画期間における介護保険の第1号保険料について」)
ですから、ご自身の保険料を知るためには、必ずお住まいの市区町村が公表している「介護保険料一覧表」を確認することが大切です。この一覧表には、所得段階ごとの保険料率や、年間の保険料額が詳しく記載されています。
「〇〇市 介護保険料」で検索すれば、だいたいPDFファイルで見つかりますよ。自分の前年の所得と照らし合わせれば、「私は第〇段階だから、年間の保険料は△△円ね」と、一目瞭然です。ぜひ、ご自身の「保険料の通知書」が届いたら、この一覧表と見比べてみてください。計算の根拠がわかると、納得感も違いますよ!
介護保険料計算シミュレーション年齢別

介護保険料の計算は40歳からスタート
「え、もう介護保険料を払う年齢!?」…そう、40歳の誕生日を迎えると、私たちは皆、介護保険の第2号被保険者となり、保険料の支払いがスタートします。まさに、人生の新たなステージの幕開けですね(笑)。
40歳から64歳までの方の保険料は、ご自身が加入している公的医療保険(健康保険)の保険料と一緒に徴収されます。これがポイントです。
会社員・公務員の方(協会けんぽ・健康保険組合など)
会社員の方の場合、介護保険料は毎月のお給料から天引きされます。給与明細をよーく見てみてください。「健康保険料」の近くに「介護保険料」という項目があるはずです。
計算式は、標準報酬月額 × 介護保険料率 となります。この「介護保険料率」は、加入している健康保険組合によって少しずつ異なります。例えば、協会けんぽ(東京都)の令和6年度の料率は1.60%です。算出された保険料は、会社と自分で半分ずつ負担(労使折半)します。給与明細に記載されているのは、ご自身が負担する半額分なんですね。
例えば、標準報酬月額が30万円の方なら…
30万円 × 1.60% = 4,800円(月額保険料)
このうち自己負担分は、半分の2,400円となります。
自営業・フリーランスの方(国民健康保険)
国民健康保険に加入している方は、医療保険料と介護保険料が合算された形で「国民健康保険税(料)」として請求されます。計算方法は自治体によって異なり、所得に応じて計算する「所得割」や、加入者数に応じてかかる「均等割」などを組み合わせて算出されます。詳しくは、お住まいの市区町村の窓口で確認するのが一番確実です。
扶養されている配偶者は?
会社員の夫(または妻)に扶養されている40歳~64歳の配偶者(専業主婦など)は、ご自身で個別に介護保険料を支払う必要はありません。これは、被保険者(夫または妻)が加入している健康保険制度全体で、被扶養者の分も負担しているためです。ご安心くださいね。
便利な介護保険料の自動計算(65歳以上)

65歳になり、介護保険の「第1号被保険者」になると、保険料の納め方が変わります。多くの方は、年金からの天引き(これを「特別徴収」と言います)によって、自動的に保険料を納めることになるんです。まさに「自動計算」ならぬ「自動徴収」ですね!
これは、年金を支給している日本年金機構などが、あらかじめ市区町村から通知された保険料額を年金から差し引いて、本人に代わって市区町村に納めてくれる、という非常に便利な仕組みです。
ただし、誰もがこの特別徴収の対象になるわけではありません。対象となるのは、以下の条件を満たす方です。
特別徴収(年金天引き)の対象者
年間の年金受給額が18万円以上の方
年金の受給額が年間18万円未満の方や、年度の途中で65歳になった方、他の市区町村から転入してきたばかりの方などは、特別徴収の対象外となります。その場合はどうなるかというと、「普通徴収」という方法で自分で納めることになります。
| 徴収方法 | 対象者 | 納付の仕方 |
|---|---|---|
| 特別徴収 | 年金受給額が年額18万円以上の方 | 年金の支給月(偶数月)に、2ヶ月分の保険料が自動的に天引きされる。 |
| 普通徴収 | 年金受給額が年額18万円未満の方など | 市区町村から送られてくる納付書を使って、金融機関やコンビニなどで自分で支払う。口座振替も可能。 |
私の担当したお客様で、65歳になって最初の数か月は納付書で払っていたのに、途中から年金天引きに切り替わって「二重払いしてる!?」と慌てて相談に来られた方がいました。これは年度の途中で対象条件を満たしたため、徴収方法が切り替わっただけなんです。自治体からの通知をよく確認してくださいね、とお伝えして安心されていました。よくあるケースなので、覚えておくと安心です!
介護保険料の月額の目安(65歳以上)
ご自身の介護保険料が高いのか安いのか、気になりますよね。そんな時、一つの判断材料になるのが「全国平均」です。
厚生労働省の発表によると、令和6年度から令和8年度までの3年間(これを第9期事業計画期間といいます)における、65歳以上の第1号被保険者の介護保険料は、全国平均で月額6,225円となる見込みです。
介護保険料は上昇傾向…
ちなみに、この平均額は制度が始まった2000年度(月額2,911円)から、見直しのたびに上昇を続けています。これは、高齢化の進展によって介護サービスを利用する人が増え、必要な費用も増大しているためです。今後もこの傾向は続くと考えられています。
参考情報サイト: 厚生労働省「介護保険制度をめぐる最近の動向について」
URL:https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000917423.pdf
この「月額6,225円」という数字を一つのベンチマークとして、ご自身の保険料と比べてみてください。
- 平均より安い場合:お住まいの自治体の基準額が比較的低いか、ご自身の所得が平均よりも低い段階にあると考えられます。
- 平均より高い場合:お住まいの自治体の基準額が高いか、ご自身の所得が平均よりも高い段階にあると考えられます。
先日、ある相談会で「うちは夫婦2人で月2万円も介護保険料を払っていて、高すぎる!」とおっしゃる方がいました。詳しくお話を聞くと、旦那様の現役時代の所得が高く、現在も多くの年金を受給されているため、所得段階がかなり高い区分になっていたんです。
全国平均や、お住まいの自治体の所得段階ごとの保険料一覧表をお見せして、「ご主人の所得ですと、この段階になるので、この金額になるんですよ」とご説明したところ、「なるほど、そういう仕組みだったのか」と納得されていました。
ただ金額だけを見て高い・安いと判断するのではなく、その背景にある「所得に応じた負担」という原則を理解することが、保険料と上手に付き合っていくコツかもしれませんね。
介護保険料の計算方法(75歳以上)

75歳になると、多くの方がそれまで加入していた国民健康保険や会社の健康保険から、「後期高齢者医療制度」という新しい医療保険制度に移行します。人生の大きな節目の一つですね。
ここでよくある勘違いが、「後期高齢者になったら、介護保険料の計算も変わるの?」というものです。
結論から言うと、NO!75歳以上になっても、介護保険料の計算の仕組み自体は65歳から74歳までの方と全く同じです。
つまり、引き続き「第1号被保険者」として、お住まいの市区町村が定めた基準額と、前年の所得に応じた保険料率によって保険料が計算されます。納付方法も、年金が年額18万円以上の方は原則として年金からの天引き(特別徴収)が続きます。
注意!負担する保険料は「2種類」に!
75歳以上の方が注意すべきなのは、支払う社会保険料が1種類ではなくなる点です。以下の2つの保険料をそれぞれ納めることになります。
- 介護保険料(介護サービスのための保険料)
- 後期高齢者医療保険料(医療サービスのための保険料)
この2つは全く別の制度の保険料なので、混同しないようにしましょう。年金天引きの場合、年金から「介護保険料」と「後期高齢者医療保険料」がそれぞれ差し引かれることになります。
私の祖母も75歳になったとき、「なんだか保険料の通知がたくさん来て、よくわからない!」と混乱していました。「おばあちゃん、こっちは介護の分、こっちは病院にかかるときの分。2つに分かれただけだから大丈夫だよ」と説明したら、やっと安心していました。同じように、ご両親が75歳を迎える方は、ぜひこの点を優しく教えてあげてくださいね。
国民健康保険料の計算シミュレーション
自営業の方やフリーランスの方、退職して会社の健康保険を任意継続しなかった方などが加入する「国民健康保険(国保)」。40歳から64歳までの国保加入者の方は、介護保険料がどのように計算されるのか、気になりますよね。
国保の場合、「医療分保険料」と「介護分保険料(これが介護保険料のことです)」を合算したものが、「国民健康保険料」として請求されます。請求書が一本化されているので、内訳を意識していない方も多いかもしれません。
「介護分保険料」の計算方法は、お住まいの市区町村によって異なりますが、主に以下の要素を組み合わせて算出されます。
国保の介護分保険料の計算要素
- 所得割:前年の所得に応じて計算される部分。
- 均等割:世帯の被保険者数に応じて一人ひとりにかかる部分。
- 平等割(採用していない自治体もあり):一世帯あたりにかかる部分。
例えば、埼玉県さいたま市(令和6年度)の場合、介護分の計算は所得割と均等割の2方式です。前年の所得から基礎控除を引いた額に「介護分所得割率」を掛け、それに「介護分均等割額」を加算して世帯の保険料を計算します。
うーん、やっぱり言葉で聞くと複雑ですよね(汗)。そこでおすすめなのが、やはり自治体のホームページにある「国民健康保険料計算シミュレーション」です!
これを使えば、ご自身の世帯の収入や年齢、加入人数などを入力するだけで、年間の国保料の総額と、そのうちの「医療分」と「介護分」の内訳まで詳しく表示してくれます。フリーランスの友人が確定申告後に毎年このシミュレーションを使って、「よし、今年の国保料はこれくらいか。事業計画に盛り込んでおこう」と、資金繰りの参考にしていると話していました。
国民健康保険に加入している40歳以上の方は、ぜひ一度、このシミュレーションを試してみてください。ご自身の保険料の内訳が分かると、家計管理もしやすくなりますよ!
参考情報サイト: さいたま市「国民健康保険税の計算」
URL: https://www.city.saitama.lg.jp/001/153/002/004/p010020.html
総括:正しい介護保険料計算シミュレーションを

ここまで、介護保険料の計算について、様々な角度から見てきました。最後に、この記事の要点をまとめておさらいしましょう!
- 介護保険の被保険者は65歳以上の第1号と40~64歳の第2号に分かれる
- 第1号の保険料は自治体の基準額と所得段階で決まる
- 第2号の保険料は加入している医療保険の種類によって計算方法が異なる
- 会社員の場合、介護保険料は給与から天引きされ会社と折半する
- 保険料の計算の基礎となるのは収入ではなく所得(儲け)である
- 合計所得金額とは各種所得を合計したもので遺族年金などは含まない
- 40歳になると介護保険料の支払いがスタートする
- 65歳以上で年金が年18万円以上だと原則として年金から天引きされる
- 令和6年度からの全国の介護保険料の平均月額は約6,225円である
- 保険料の基準額は自治体によって差があるため一覧表での確認が重要
- 75歳以上になっても介護保険料の計算方法は変わらない
- ただし75歳からは後期高齢者医療保険料も別途納付が必要になる
- 国保加入者は医療分と介護分を合算して国民健康保険料として納める
- 正確な保険料を知るには自治体のシミュレーターや計算表が最も便利
- ご自身の保険料の計算根拠を理解することが納得への第一歩
参考

お気軽にご相談ください
相続は100人いれば、100通り
唯一無二の最適な相続をご提案いたします
CONTACT
専門家やえさん

- 専門家やえさん
-
堀川 八重(ほりかわ やえ)
大阪不動産・FPサービス株式会社 代表
15年以上にわたり1,500組を超えるご家族の相続や不動産のお悩みに、専門家として寄り添ってまいりました。私の信条は、法律や数字の話をする前に、まずお客様ご家族の歴史や言葉にならない想いを丁寧に「聞く」こと。信頼できる各分野の専門家チームと共に、皆様が心から安心できる最善の道筋をオーダーメイドでご提案します。一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。
最新の投稿
 お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説
お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説 相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説
相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説 お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例
お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例 お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説
お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説






