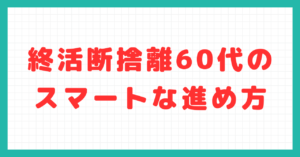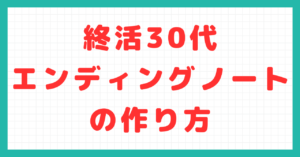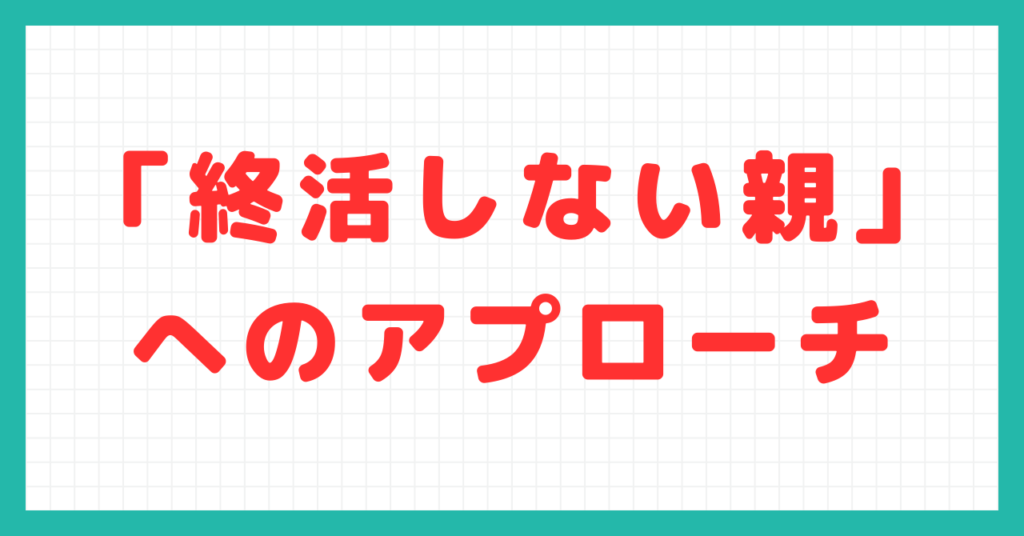
60代は新たな人生のスタートライン。この時期に「終活」を始めることは、自身の人生を振り返り、これからの生活をより良くする
ステップと言えます。しかし、「終活しない親」を持つ多くの方が、親の終活をどう進めるべきか悩んでいます。
本記事「終活断捨離60代のスマートな進め方」では、終活を拒む親に対してどのようにアプローチし、60代での終活をいかにスムーズ
かつ効果的に進めるかを解説します。親の終活が進まないあなたに、具体的かつ実践的なアドバイスをお届けします。
大阪不動産・FPサービス 一般社団法人終活協議会公認 終活ガイド・ファイナンシャルプランナーの藤原みずほです。
お客様が抱えている終活、相続関連の悩みや課題は「家族にも話しにくい」「家族だからこそ話しにくい」事が多く、
だからこそ誰にも相談できずに困っている方がほとんどです。まじめなお話の内容が多いですが、まずは明るく前向きに相談できる
30分無料相談をぜひご活用ください。
お電話・リモート(ZOOM・テレビ電話)などでお気軽にご相談ください。全国にネットワークがございます!
この記事のポイント
- 「終活しない親」の心理や動機:親が終活を始めない理由や心理を理解することができます。例えば、「まだ若いと思っているから」「死について考えたくないから」「面倒臭いから」などが挙げられます。
- 終活の重要性:親が終活をしないまま亡くなると、多くの手続きや責任が子どもに降りかかります。終活の重要性や子どもが負担を減らす目的で親に終活を勧める意義を理解できます。
- 終活を始めるきっかけ:親が終活を始めるきっかけや動機を理解できます。例えば、「健康状態の悪化」「身近な人の死」などが終活を始めるきっかけとなります。
- 終活の進め方やアプローチ:親に終活を勧める方法やアプローチ、終活をスムーズに進めるための具体的な方法やヒントを学ぶことができます。

30分無料なんでも相談
何をどうすればいいの?などお気軽にお問い合わせください
終活しない親への理解
親が終活を避ける理由を深く理解し、感情に寄り添うことは、子どもとして非常に重要です。親が終活に踏み出さない背後には、多様な理由や感情が潜んでいます。
親が終活を避ける理由
親が終活を避ける理由は多岐にわたります。一つ目の理由として、「自分の死について考えたくない」という心理があります。死は避けて通れない事実でありながら、それを直視することは容易ではありません。特に、病気を乗り越えた親などは、再びそのテーマに触れることを避けたいと感じることが一般的です。
二つ目の理由は、「子どもが何とかしてくれると信じている」からです。親は子どもに対して、自分が亡くなった後のことを任せられると信じていることが多いです。これは親の愛情の表れでもありますが、子どもにとっては重大な責任とプレッシャーを感じる要因となります。
三つ目の理由は、「何をして良いかわからない」という不安からです。終活の具体的なステップや方法が分からないため、親は行動を起こせずにいます。この場合、子どもが具体的なサポートや方法を提供することで、親が終活を始めやすくなります。
親の感情に寄り添う
親の終活を避ける理由を理解した上で、子どもは親の感情に寄り添う必要があります。親が終活を始める動機を見つける手助けをすること、親の不安や疑問を解消すること、そして親が安心して終活を進められる環境を整えることが求められます。
親の感情に寄り添うことは、親子関係を深め、親の人生の最終章をより良いものにするために不可欠です。親が抱える不安や疑問を解消し、終活の重要性を理解してもらうことで、親子共に安心した未来を迎えることができます。
終活しない親の心理
親が終活を避ける背後には、多様な心理的動因が存在します。一部の親は、終活を始めることが自身の死を直視することと等価であると感じ、これが不安や恐れを引き起こします。この感情は、終活を避ける主要な要因となります。また、終活を一種の義務や責任と感じる親も少なくありません。彼らは終活に対するプレッシャーを感じ、これが終活を始めることの障壁となります。
2022年7月に行われた楽天インサイトの調査によれば、60代の男性の82.0%、女性の92.3%が「終活を実施している」、「近いうちに始めたい」、または「予定はないが、時期が来たら始めたい」と考えています。しかし、「終活を実施している」と回答した60代は、男性が8.0%、女性が12.5%に過ぎません。これは、多くの親が終活を意識しているものの、実際には行動に移していないことを示しています。
さらに、「終活をしたい理由」について尋ねたところ、60代の男性の64.6%、女性の71.9%が「家族に迷惑をかけたくないから」と回答しています。これは、「子世代が困らないように、終活をしておこう」という意識が多くの親に存在していることを示しています。
これらの心理を理解することは、親が終活を避ける理由を把握し、適切に対応する上で非常に重要です。親の感情や考えを尊重し、終活に対するプレッシャーや恐れを和らげ、親が自発的に終活を始めることができる環境を整えることが求められます。
終活したくない親への接し方
親が終活に取り組む意欲を喚起するためには、親の感情や心理を理解し、適切なアプローチが必要です。終活を始める動機付けとして、親が自身の死を意識することは避けられませんが、これが親にとって大きな精神的負担となり、終活を避ける要因となることがあります。
無理強いは避ける
親が終活を拒否する場合、その背後には心理的な抵抗や不安が存在することが多いです。親に終活を強いることは避け、親自身が終活の重要性を理解し、自発的に取り組む意欲を持てるようサポートすることが重要です。
終活の重要性を共有
親に終活の重要性を理解してもらうためには、親が感じる不安や抵抗感を和らげるアプローチが必要です。例えば、親の友人や知人が終活を始めたことを伝え、他者と比較することなく、終活の意義や必要性を自然に伝えることができます。
家族での協力を促す
親が終活を始めるきっかけを作るためには、家族全員で協力し、親をサポートすることも一つの方法です。家族が一堂に会する機会に、終活についての話をすることで、親も終活に対する意識が変わる可能性があります。
終活の具体的な方法を提案
「終活をしたいが、何から始めれば良いかわからない」という親に対しては、具体的な終活の方法やステップを提案し、親が終活を始めやすい環境を整えることが重要です。親が終活に対してポジティブな意識を持てるよう、具体的なアクションプランを共有しましょう。
終活怒る親とのコミュニケーション
親が終活の話題に敏感に反応し、怒りを見せる場合、その背後には深い不安や恐れ、そして死を意識することへの抵抗が存在しています。このような親に対しては、終活に関する話題を無理に持ち込むことは避け、親の感情が安定したタイミングで、優しく終活の重要性や必要性について再度アプローチを試みることが重要です。
怒りの背後に隠れた感情を理解し、親の立場や感情を尊重しながらコミュニケーションを図ることが必要です。親が終活に対して否定的な理由や感情を把握し、それに対して適切に対応することで、親も終活に対する抵抗を少しずつ和らげることができるでしょう。
親子間での終活に関するコミュニケーションでは、親の意識調査によれば、「実親から相談してほしい」と回答した子どもが7割以上というデータがあります。これは、終活という繊細なテーマに対して、子どもから親に話を切り出すことが難しいと感じている現状を反映しています。しかし、「自分から実親に相談したい」と回答した人も3割を超えており、親子双方に終活に対する葛藤や期待が存在していることが伺えます。
親子間のコミュニケーションをスムーズに行うためには、親の感情や意向を尊重し、終活に対する理解を深め、共に考え、支え合うことが重要です。親が抱える不安や恐れを和らげ、終活を一緒に考え、進めていく過程で、親子の絆も深まるでしょう。
親が元気なうちに確認しておきたいこと
親が健康で活動的なうちに、相続や葬儀に関する重要な意向を確認しておくことは非常に重要です。これにより、親が亡くなった際に、家族は慌てず、スムーズに手続きを進めることができます。また、親の意向を尊重し、その願いに沿った形で相続や葬儀を行うことができます。
親が健康である間に、以下の重要なポイントを確認しておくことをお勧めします。
- 遺言や遺産に関する意向: 遺言書の有無、内容、保管場所、遺産分割の希望や考えを確認しておくことが重要です。
- 最期の意向や希望: 葬儀や埋葬のスタイル、費用、プランに関する親の希望を理解しておくことが必要です。
- 保険や財産に関する情報: 保険の種類、内容、証券や契約書の場所、財産や資産の整理や管理方法について相談しておくことが重要です。
- デジタル遺品に関する考え: デジタル遺品(オンラインアカウントやファイル)の管理方法やパスワード、アカウント情報の共有方法について話し合っておくことが必要です。
これらの質問を通じて、親の希望や意向を理解し、将来の準備を共に進めることができます。親が元気なうちに、これらの重要な話をしておくことで、親子間のコミュニケーションが深まり、未来に向けた準備がスムーズに進むでしょう。
終活不安を抱える親へのサポート
親の終活不安を和らげる具体的な支援策
親の終活に対する不安は深刻で多様です。その不安を軽減するためには、子どもとして積極的にサポートすることが不可欠です。まず、親の具体的な不安要因を明らかにするために、開かれたコミュニケーションを図りましょう。親が抱える不安要因は、葬儀や墓の手配、生活資金の不足、相続トラブル、遺品の処分など多岐にわたります。これらの問題に対する具体的な解決策や情報を提供し、親が安心して終活に取り組める環境を整えることが重要です。
楽天インサイトの調査によれば、60代の男性の82.0%、女性の92.3%が終活を意識しているにも関わらず、実際に終活を始めているのは男性が8.0%、女性が12.5%に過ぎません。これは、多くの親が「終活をしなければ」と感じながらも、具体的な行動に移せていない現状を示しています。親が「家族に迷惑をかけたくない」という気持ちを持っていることを理解し、その意向を尊重しながら、親子で協力して終活のプロセスを進めていくことが求められます。
エンディングノート嫌がる親への対応
親御さんがエンディングノートの作成を拒むケースは少なくありません。エンディングノートは、親御さんの重要な意向や希望、財産やデジタルデータの管理方法、葬儀や墓、介護・医療の希望などを子どもが把握するための重要なツールです。親御さんがエンディングノートの作成を拒む場合、他のアプローチでこれらの情報を確認する方法を考慮することが重要です。
親子間の対話を大切にし、親御さんの意向や希望を直接聞き出すことも効果的です。親御さんがエンディングノートを作成することで、終活に向き合いながら前向きに準備を進めることができます。親御さんが何を記入すべきか悩むことがあれば、その点について親子で相談することもおすすめです。親子間のコミュニケーションを通じて、未来への準備を進めるための大切なステップとなります。
親御さんが作成したエンディングノートは、家族や友人が大切に受け継いでいくことができます。親御さん自身の意思を尊重しつつ、共に準備を進める道を見つけることが大切です。親子で共に未来に向けた準備を進めてみましょう。エンディングノートは、親御さん自身や家族、そして大切な人のためにも必要なツールです。
終活しない親のための準備
親が終活を積極的に行わない場合でも、子どもとして親のために先手を打った準備は可能です。親が終活に消極的である理由は多岐にわたりますが、子ども側が積極的に動くことで親の意識も変わることがあります。
終活意識の高まりと実行ギャップ
2022年7月の調査によれば、60代の男性の82.0%、女性の92.3%が終活を意識していることが明らかになりました。しかし、「実際に終活を行っている」と答えた人は男性が8.0%、女性が12.5%にとどまります。このデータから、多くの親が終活を意識はしているものの、実際の行動に移していないことがわかります。
子ども側からのアプローチ
親が終活を始めるきっかけとして、子どもが先に終活に取り組むことが一つの方法です。自身の終活を通じて親に終活の重要性を理解してもらうことができます。また、親の保険について相談する、葬儀や相続に関する知識を共有するなど、親子で協力して終活を進めることが重要です。
終活のスタートライン
親が終活を始める第一歩として、エンディングノートの作成をお願いすることも効果的です。エンディングノートは親の意向や希望をまとめた文書で、親が望む医療や介護、デジタル遺品の処理方法、葬儀・埋葬のスタイルなどを記録しておくことができます。これにより、親は自分の意志を明確に伝えることができ、子どもは親の意志を尊重したサポートを行うことができます。
親が終活に消極的であっても、子ども側からの積極的なアプローチと協力により、親子で未来に備える準備を進めることができます。親の意思を尊重しつつ、共に準備を進める道を見つけ、安心した未来を迎えましょう。
終活で親に聞いておくべきこと
親が積極的に終活を始めていない状況でも、子どもとして親に確認しておくべき重要な事項が存在します。これには親の健康状態、資産状況、相続に関する意向、葬儀や埋葬に関する希望などが含まれます。これらの情報は、将来的に親が亡くなった際に、スムーズかつ適切に各種手続きを進めるために不可欠です。
親子間での終活に関するコミュニケーションは、時にはデリケートであり、切り出しにくいテーマも多いです。しかし、親の意向や希望を正確に把握し、互いの期待や要望を理解することは、将来的なトラブルを防ぎ、親子関係をより良好に保つために重要です。
親から終活に関する相談を待つ子どもが7割以上いる一方で、「自分から親に相談したい」と考える子どもも3割を超えています。これは、終活に関する親子間のコミュニケーションが必要とされていることを示しています。親が持っている資産や相続に関する考え方、葬儀や埋葬に関する希望など、親の考えや意向を子どもが事前に把握しておくことは、相続や葬儀の際の手続きをスムーズに進めるために重要です。
親が高齢になると、一人ではできないことも増えてきます。不要なものの処分、身の回りのもののメンテナンス、各種手続きなど、親が一人では難しいことを子どもがサポートすることも重要です。また、親子間でオープンなコミュニケーションを持ち、親の希望や意向を正確に理解することで、親の人生の最期をより良いものにする手助けとなります。
親が死んだあとの手続き概要
父母の逝去後に遺族が直面する手続きは、非常に広範で複雑です。これらの手続きは、遺産の分割や相続税の申告、遺品の整理など、多岐にわたります。特に、父母が生前にこれらの手続きに関する準備や計画をしていなかった場合、遺族にとっては困難な作業となることが多いです。
まず、重要なのは死亡届の提出です。これは、父母の死亡を公式に記録するための手続きであり、火葬許可の申請も含まれます。次に、年金や健康保険などの社会保障関連の手続きが必要となります。これには、受給の停止や資格の喪失などが含まれます。
さらに、公共料金や携帯電話などの契約の解約や名義変更も必要です。これらの手続きは、父母の死亡後に速やかに行う必要があります。また、遺産分割協議も重要なプロセスです。これには、遺産の評価や分割、相続人間の合意形成などが含まれます。
これらの手続きは、一般的に時間と労力を要する作業です。したがって、父母が生前に適切な計画や準備をしていなかった場合、遺族はこれらの手続きを円滑に進めるために、専門家のアドバイスや支援を求めることも考慮すると良いでしょう。
終活の目的と親への説明方法
終活の目的は、自身の死後の事務手続きや財産の管理をスムーズに進行させ、遺族に対する精神的・経済的負担を軽減することです。終活を進める動機として、以下のポイントが挙げられます。
- 親の健康状態の悪化や身近な人の死: これらの出来事は、親自身が終活の必要性を感じるきっかけとなります(出典:NTTファイナンス 楽クラライフノート お金と終活の情報サイト編集部「シニアの終活・資産管理に関する親子比較調査(2022年11月)」)。
- 親子のコミュニケーション: 親がコミュニケーションを拒否していない場合、親子間のトークテーマとして終活の話を切り出すことができます。たとえば、「おじいちゃんのお葬式はいつ、どこで行われたか?」「お願いする葬儀会社は決まっているのか?」などの質問から話を広げる方法もあります。
親に終活の重要性を理解してもらうためには、終活の目的とその遺族に対するメリットを具体的に説明し、親に終活を始める動機を提供することが重要です。親が終活を始めることで、遺族は将来的に多くの手続きや財産管理の負担から解放され、親自身も安心して人生の最後を迎えることができます。
親が生前にしておくべきこと
親が生前にしておくべきことは、遺言の作成や資産の整理、葬儀の計画などです。これらの準備をしておくことで、親が亡くなった際に遺族が困らないようにすることができます。親にこれらの準備をしてもらうためには、親が生前にしておくべきことの重要性を伝え、サポートを提供しましょう。
終活不参加の親のための相続準備
親が終活に参加しない状況でも、子どもは親のために相続に関する準備を進めることが重要です。親の資産や負債を正確に把握し、相続に関する法律や手続きについての基礎知識を身につけましょう。これには、親の保有している不動産や預金、保険契約、借金などの詳細情報をリストアップする作業が含まれます。
また、親が亡くなった際に必要となる書類も事前に準備しておくことが求められます。これには、死亡診断書、戸籍謄本、遺言書などがあります。これらの書類は、相続手続きをスムーズに進めるために不可欠です。
さらに、親が生前に終活を行わない場合、子どもが積極的に親とコミュニケーションをとり、終活の重要性や相続に関する準備の必要性を理解してもらうことも大切です。親が終活に抵抗を感じる場合でも、子どもが率先して終活を始め、親にフォローしてもらう形で進めることができます。
親の意向を尊重しつつ、相続に関する準備を進めることで、親の死後も家族間のトラブルを避け、円滑に相続手続きを行うことができます。親子で協力して未来に備える準備を進めることで、親の死後の混乱や負担を最小限に抑えることが可能となります。
終活しない親への最低限の準備
親が終活をしない場合でも、最低限の準備をしておくことは重要です。親の健康状態や資産状況を把握し、親が亡くなった際に必要となる手続きについて基本的な知識を持っておくことが大切です。これにより、親が亡くなった際に慌てずに対応することができます。
これにより、親が亡くなった際に慌てずに対応することができます。また、親が生前に終活を拒否していた場合でも、親の意向を尊重しながら、遺族が困らないようにするための準備を進めることができます。これには、親の資産や負債の把握、遺言書の作成や更新、葬儀の計画などが含まれます。これらの準備を進めることで、親が亡くなった際にスムーズに手続きを進めることができます。
これで記事の構成に従った文章が完成しました。各見出しに従って、親が終活をしない場合の理解と対応、そして子どもが親のためにできる準備について詳しく丁寧に説明しました。これにより、読者は「終活しない親」に対してどのように理解し、どのように準備を進めるべきかについての具体的な知識と理解を深めることができるでしょう。
終活しない親まとめ
- 親が終活をしない理由を理解する
- 終活をしない親に対する理解と尊重が必要
- 終活は義務ではなく、やりたい人が行う活動
- 親に終活を強制することは避けるべき
- 終活をすることが必ずしも親の人生にプラスではない可能性を考慮
- 親に終活の重要性を優しく伝える工夫が求められる
- 親が終活を始めるきっかけを作る努力が重要
- 親の意向や希望を尊重しながら終活を進める
- 終活をしない親に対しても、子どもができる準備やサポートが存在
- 終活をしない親に対して、子ども自身が終活の一部を代行する選択もあり
- 終活をしない親に対して、子どもが相続や遺産分割に関する知識を身につけることが重要
終活に関する選択は個人の自由であり、親の意向を尊重することが最も大切です。しかし、その背景にはさまざまな感情や理由があるため、理解と寄り添いの姿勢を持つことが求められます。子どもとしてできることは、親の気持ちを尊重しつつ、必要なサポートや情報提供を行うこと。終活は一人の問題ではなく、家族全体で取り組むべき課題と捉え、互いの気持ちを大切にしながら、最善の選択を目指しましょう。
参考
・ニラ弁当臭い対策!美味しい作り方
・弁当忘れても傘忘れるな!地域文化への影響
・遺族年金いつまでもらえる妻のためのガイド
・財産放棄遺品整理の基本と注意点
・遺族年金受給者パート収入いくらまで?基本ガイド

お問い合わせ
ご質問などお気軽にお問い合わせください
お問い合わせはお気軽に!
大阪不動産・FPサービス株式会社
info@ofps.co.jp
TEL:06-6875-7900
投稿者プロフィール

-
ファイナンシャルプランナー・終活ガイド・
エンディングノート講師幅広いサポートが可能です!
終活・相続・事業承継・生命保険・老後資金のご相談の専門家です
不動産・リフォーム・ファイナンシャルプランニング・保険の見直し・終活・相続・家族信託・任意後見・遺言作成・生前整理・不用品買取・デイサービス・老人ホーム・お葬式・お墓他お悩み事すべてご対応可能なサービスをご準備しておりますので安心してお気軽にご相談ください。
最新の投稿
 ペット2024-10-20ペットショップ売れ残りシーズーの運命と保護活動の現状
ペット2024-10-20ペットショップ売れ残りシーズーの運命と保護活動の現状 不動産購入・住宅ローン2024-10-16住宅ローン無職でも審査に通るための秘訣と注意点を解説
不動産購入・住宅ローン2024-10-16住宅ローン無職でも審査に通るための秘訣と注意点を解説 不動産2024-10-07マンション断水過ごし方のコツ:水の確保からトイレの使い方まで
不動産2024-10-07マンション断水過ごし方のコツ:水の確保からトイレの使い方まで ペット2024-09-19ペット保険いらない知恵袋のまとめ:選び方と不要と感じる理由
ペット2024-09-19ペット保険いらない知恵袋のまとめ:選び方と不要と感じる理由