相続の“モメない”進め方とは?専門家が円満解決をお手伝い
相続は、家族の大切な財産を未来へつなぐ、大事な節目――
でも実際には、「誰に何をどれだけ渡すか」が原因で、
ご家族の関係にヒビが入ってしまうことも珍しくありません。
「うちはそんなに財産がないから大丈夫」
「兄弟仲はいいから、揉めるはずがない」
そう思っていた方ほど、いざ相続が始まったときに
「こんなことになるなんて…」と戸惑うケースが多く見られます。
相続手続きには、法律・税金・人間関係など、
専門知識が求められる場面がたくさんあります。
そして、多くの方が「もっと早く相談しておけばよかった」と振り返ります。
OFPSでは、相続の流れや必要な手続きをわかりやすく整理し、
ご家族が“もめない”ためのサポートを丁寧に行っています。
相続は、亡くなった方の想いをつなぐだけでなく、
残された家族がこれからも支え合っていくための、大切な機会です。
少しでも不安がある方は、まずはお気軽にご相談ください。
「相続、何から始めればいいの?」という一言からでも大丈夫です。
こんな相続の悩み、ありませんか?
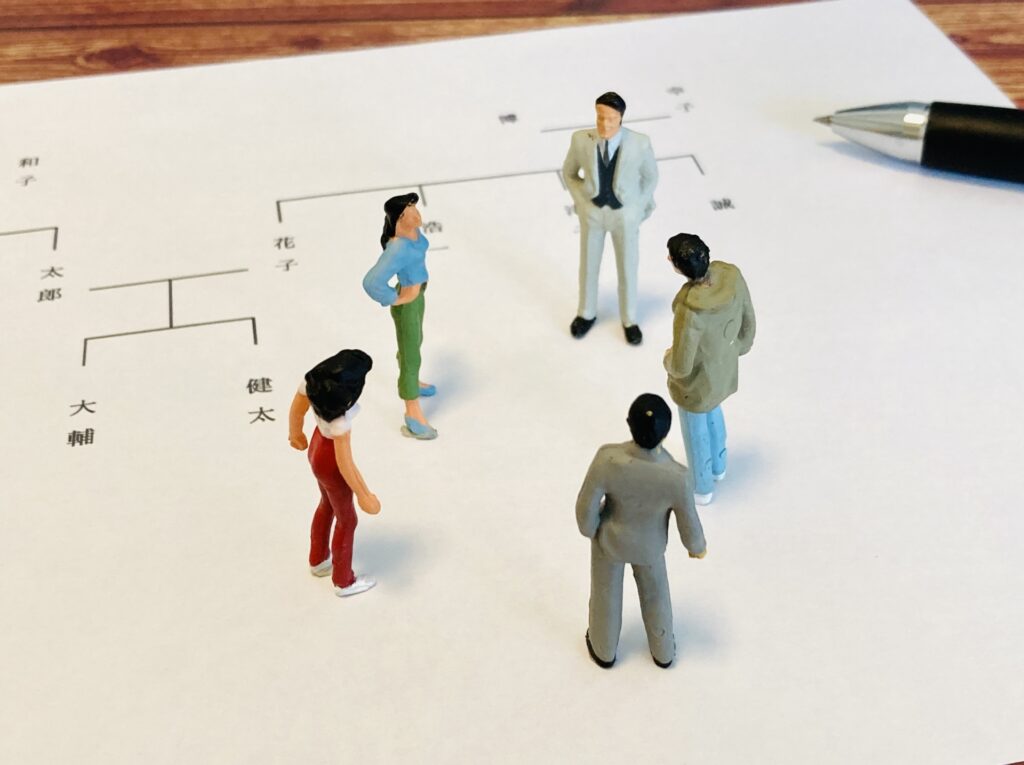
✅ 親が遺言を残していなかった
「きっと大丈夫だと思ってた」…そのひと言が、話し合いを難しくしてしまうことも。相続は事前準備がカギです。
✅ 兄弟で意見が分かれて話がまとまらない
仲が悪いわけじゃない。でも、お金や不動産が絡むと、遠慮が本音に変わることも。中立なサポートが円満の近道です。
✅ 名義変更や相続登記、何をすればいいの?
必要な書類や手順が複雑で、「時間がない」と先延ばしにされがち。専門家に任せるとスムーズです。
✅ 相続税がかかるか不安。でも誰に聞けば?
税金のことはネットで調べるにも限界があります。申告が必要かどうか、プロの目でチェックできます。
✅ 預金口座が凍結されてしまって困っている
葬儀費用の支払いに使えない、相続人全員の署名が必要など、思ったより大変。早めの対応が必要です。
✅ 実家の土地や家をどうするか決まらない
「売る?貸す?住む?」家族で答えが出ないときは、第三者の視点がヒントになります。
📌 ひとつでも「これ、うちもかも…」と感じた方へ
相続は、一見“家の問題”のようでいて、実は“人の想い”が深く関わるもの。
だからこそ、感情と手続きの両方に寄り添える専門家が必要です。
OFPSでは、相続の進め方や不安を、ひとつひとつ丁寧に整理するサポートを行っています。
✅ 相続のこと、まずは話してみませんか?
相続手続きの流れ|まず何から始めればいい?
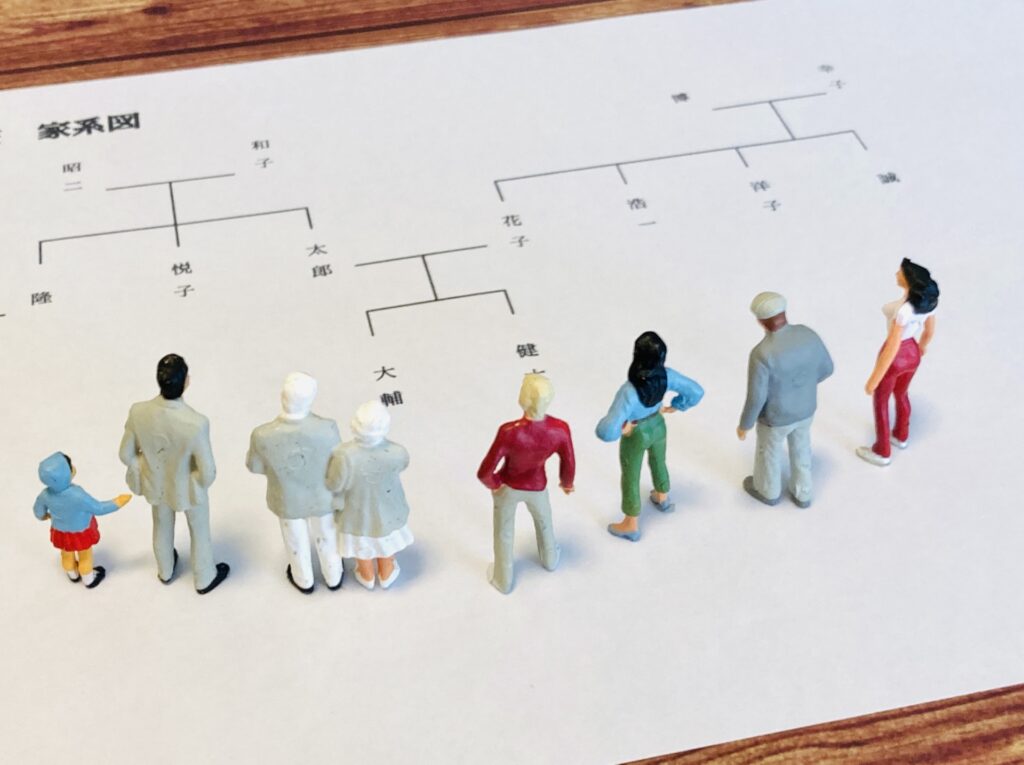
相続手続きは「亡くなったあとすぐに始まる」一方で、「何から着手すべきか分からない」と感じる方が非常に多い分野です。法律、税金、書類、不動産…たくさんの情報に触れれば触れるほど、不安になってしまうもの。
ここでは、一般的な相続の進め方を「5つのステップ」に分けて、初心者の方にも分かりやすくご紹介します。全体の流れを把握することで、落ち着いてひとつずつ進めることができます。
🔷 相続手続きの全体像(イメージ図解)
🕊 相続開始(被相続人の死亡)
↓ ① 相続人の確定(誰が相続するのか)
↓ ② 財産の調査(何を相続するのか)
↓ ③ 遺産分割協議(どう分けるのか)
↓ ④ 名義変更・登記手続き(不動産や預金の変更)
↓ ⑤ 相続税の申告・納税(必要な人のみ)
🗂 各ステップの詳細と注意点
| ステップ | やること | 注意点・必要書類 |
|---|---|---|
| ① 相続人の確定 | 戸籍を取得し、法定相続人を全員確認する | 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍・住民票など。隠れた相続人がいないか注意が必要。 |
| ② 財産の調査 | 預金、不動産、保険、有価証券、借金などの洗い出し | プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も対象。通帳、不動産登記簿、証券残高証明などを収集。 |
| ③ 遺産分割協議 | 相続人全員で分け方を話し合い、協議書を作成 | 1人でも欠けると無効に。協議書には全員の署名・実印+印鑑証明が必要。揉めそうな場合は専門家の同席をおすすめ。 |
| ④ 名義変更・登記 | 預金や不動産、車などの名義変更・相続登記を行う | 放置すると後々面倒に。不動産は登記しないと相続登記義務違反(罰則あり)。金融機関や法務局の提出書類は多め。 |
| ⑤ 相続税の申告・納税 | 財産の総額が基礎控除を超える場合に必要 | 相続開始から10ヶ月以内に申告と納税が必要。税額や控除の判断には専門家の試算が安心。 |
💡 相続手続きをスムーズに進めるためのポイント
- 相続人が1人でも抜けていると、手続きがすべてやり直しになります。
- 財産の中に、遠方の不動産や名義不明の土地、思いがけない借金が含まれていることもあります。
- 遺産分割協議がまとまらないと、銀行口座は凍結されたままで葬儀費用が出せない…ということも。
実際、「知らなかった」「後回しにしていた」ことが原因で、手続きが大幅に遅れたり、ご家族の関係にひびが入ってしまうケースも少なくありません。
相続は、金額の大小にかかわらず、“心の整理”でもあります。 だからこそ、早めの準備と正しい情報が、とても大切なのです。
✅ 専門家に相談すると、ここが安心
相続には、法律・税務・登記などの知識が必要となる場面が多くあります。時間も手間もかかるうえ、ひとつのミスが手続きのやり直しやトラブルの原因になることも。
OFPSのプライベートコンサルタントでは、司法書士・行政書士・税理士など、分野ごとの専門家と連携しながら、相続の全体設計から実行までを一括サポートしています。単なる士業紹介ではなく、お客様のご事情をお伺いして"家族の一員の目線"で寄り添い最適な解決方法を考え最適な士業を選択するコンシェルジュです。
初めての方でも安心して相談できるよう、無料相談、チェックリストなどもご用意しています。
「何から始めていいかわからない」 「もめずに進めたい」 「家族に負担をかけたくない」
そんな気持ちを、まずはお聞かせください。
\ あなたの状況に合わせた、最適な進め方をご提案します /
小さな不安のうちに、一歩踏み出すことが、あなたとご家族の未来を守る大きな安心につながります。
相続トラブル事例と解決方法

相続の場面では、「まさかうちがトラブルになるなんて…」という声を本当によく耳にします。
兄弟仲が良かったはずなのに話がまとまらない。親の希望を大切にしたいのに意見がぶつかる。手続きを進めようとしたら、思わぬ障害に直面してしまった…。
それは、決して特別なケースではありません。相続には“感情”と“お金”が交差するからこそ、少しのすれ違いが、大きな争いに発展することもあるのです。
ここでは、実際にあった相続トラブルの事例をご紹介します。「我が家もこうなるかもしれない」そんな視点で読んでみてください。
Case 1|兄弟の仲が悪くなってしまった
「実家の相続、どうする?」
父が亡くなった後、兄と私(妹)は二人きりの相続人でした。 子どもの頃から仲は良く、遺産をめぐって揉めるなんて思ってもいませんでした。
でも、話が進むうちに雲行きが怪しくなりました。
兄:「介護をしてきたのは俺だ。多めにもらって当然だろう」 私:「私は遠方に住んでたけど、それなりに支援はしてたし、そんな言い方…」
だんだんと言葉がキツくなり、連絡もぎこちなく。
結果、分割協議が止まり、何カ月も手続きが進まなくなってしまいました。
📌 解決のヒント:
兄妹だけで話すと感情がぶつかってしまう。そんなときこそ、第三者の存在が有効です。 中立的な専門家が間に入ることで、冷静に「事実」と「気持ち」のバランスをとることができ、スムーズな話し合いに戻すことができました。
Case 2|親から相続した実家が“共有名義地獄”に
「名義はとりあえず兄妹3人で分けよう」
父が亡くなったとき、3人兄妹で話し合い、実家の土地と建物を“共有名義”にしました。
そのときは、「あとで考えればいいか」と安易な判断。
けれど10年後、誰も住まない実家は荒れ放題。管理する人もいない。固定資産税は毎年届くけれど、「誰が払う?」でもめ始め、結局私だけが支払い続けることに…。
売ろうにも、共有者全員の同意が必要。ひとりは海外在住、ひとりは連絡がとれない。
📌 解決のヒント:
“とりあえず共有”は、実は将来のトラブルの温床です。
不動産の名義整理(共有持分の売却・贈与・持ち分調整)や活用の選択肢(売却・賃貸・管理代行)を提案することで、相続人全員が納得できる着地点を見つけられました。
Case 3|遺留分をめぐる争い。家族に気まずさが残った
父の遺言には「すべての財産を長男に相続させる」とだけ書かれていました。 私は次男。少しはもらえると思っていたのに…
家族から「父の意思を尊重しよう」と言われても、納得できませんでした。 私は父の看病もしてきたし、家のリフォーム代も出したのに。
怒りというより、悲しみと寂しさが大きかったです。
📌 解決のヒント:
遺留分は、法律で保障された“最低限の取り分”。
遺言でゼロと書かれていても、遺留分侵害額請求を行えば、相続財産の一部を請求する権利があります。
専門家を通じて穏やかに請求を進めることで、法的にも気持ち的にも納得できる形で決着を迎えられました。
トラブルを防ぐために、今できること
相続トラブルの多くは、知識がないまま進めてしまったことが原因です。
- 遺言がなかった
- 共有名義でとりあえず分けた
- 感情的な話し合いをしてしまった
- 調べすぎて、かえって動けなくなった
でも、逆に言えば、トラブルは“防げる”ということ。
だからこそ、相続を円満に進めたいなら、まずは話せる相手=専門家をもつことが大切です。
✅ OFPSではこんなサポートを行っています:
- 遺産分割協議の進め方アドバイス
- 相続人間の意見調整・中立的立場でのヒアリング
- 不動産共有名義の整理・活用提案
- 遺留分侵害請求の書面作成・提案サポート
ご家族同士では難しいことも、第三者の手を借りるだけで、うまく進むことがあります。
▶ いまの状況を少し話してみませんか?
▶ 相続トラブルのチェックリストを使って自己診断も可能です
遺言書の作成サポート|「まだ早い」と思っていませんか?

「遺言書って、自分にはまだ早い気がする…」 「仲のいい家族だから、わざわざ書かなくても大丈夫でしょ」
そんなふうに思って、遺言書の準備を先延ばしにしてしまう方はとても多いです。
ですが実際には、遺言がなかったばかりに、兄弟での争いや不動産の処分でもめてしまったり、遺されたご家族が「お父さん、どうして何も書いておいてくれなかったの…」と嘆くようなケースが数多くあります。
遺言書は、“財産を誰に渡すか” を決めるための書類であると同時に、 “あなたの人生の意思”をカタチにして家族に伝える、大切な手紙でもあるのです。
公正証書遺言と自筆証書遺言、どう違うの?
遺言には、大きく分けて2つの作成方法があります。
✅ 公正証書遺言(おすすめ)
- 公証役場で作成(公証人が関与)
- 法律の専門家が内容をチェックするため、無効になるリスクがほとんどない
- 原本が公証役場に保管されるので、紛失や改ざんの心配も不要
- 手間や費用(1~3万円程度+財産の額による手数料)はかかるが、信頼性が高い
✅ 自筆証書遺言(ご自身で作成可能)
- 全文を自分の手で書く形式。費用はかからない
- ただし、書き方にルールがあり(全文自筆・日付・署名・押印など)、ミスをすると“無効”になるリスクも
- 2020年からは法務局での「遺言書保管制度」が始まり、保管の安心感が増した
よくある“失敗例”とその後…
📝 相続財産の記載が曖昧で「どの土地か分からない」とトラブルに
📝 遺言書が自宅から発見されたのが葬儀の数日後。生前に内容を共有できていれば…と後悔
📝 財産を特定の子だけに渡す内容だったため、他の兄弟が遺留分侵害を主張して争いに
これらのケースは、ほんの少しの準備や配慮があれば防げることがほとんどです。
「いま書いておいてよかった」と思える理由
- 万が一、突然倒れたときも安心できる
- 夫婦どちらかに先立たれたあとも、配偶者や子どもが揉めずに手続きできる
- 子どもがいない・再婚・相続人が複数いる場合など、自分の意思を明確に伝えられる
- お世話になった人へ“感謝の気持ち”として財産を遺せる
一見難しそうな遺言書も、「何を伝えたいか」から考えれば、意外とスムーズに進みます。
✅ OFPSの遺言書作成サポートでできること
- ご家庭の状況を丁寧にヒアリングし、あなたに合った遺言の形をご提案
- 「書きたいこと」を一緒に整理し、文章化をサポート
- 自筆証書遺言のチェック・誤りの指摘・補正アドバイス
- 公証人との面談予約・手続き代行(公正証書遺言)
- ご家族にも伝わる「想いのこもった遺言」の作り方をサポート
▶ 想いをカタチにする“第一歩”は、情報収集から。
▶ 「何を書けばいいの?」という方にこそ、わかりやすくサポートします。
家族を守るための準備、いまからはじめてみませんか?
相続税対策・生前贈与のご提案|“将来の安心”は今の準備から
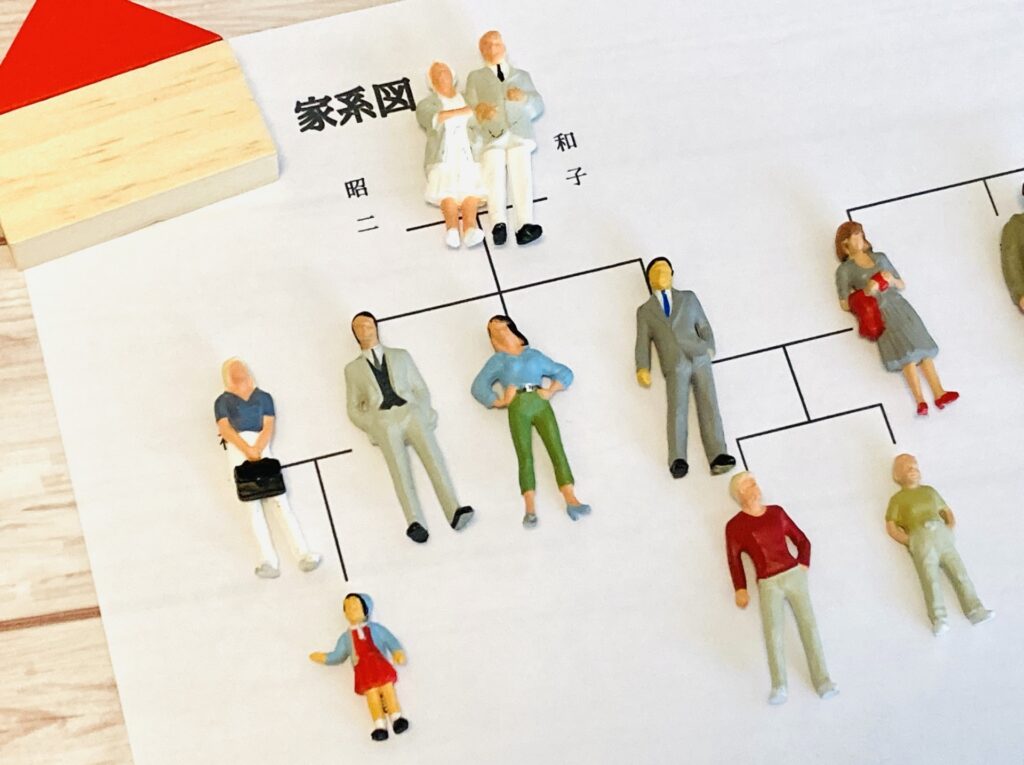
「うちはそんなに財産があるわけじゃないし、相続税は関係ないよね」
そんなふうに思っていた方が、いざ相続が発生してから、 「えっ、こんなに税金がかかるの…?」と驚き、 慌てて対応を始めるケースは少なくありません。
相続税は、一部の資産家だけの問題ではありません。
今や「持ち家+預金+土地」だけで、相続税の対象となる方は増えています。 とくに都市部や地価の高い地域に不動産を所有している方は、 思っていた以上に評価額が高くなり、基礎控除を超えてしまうことも。
もしも、ご家族が相続税の申告・納税に直面したとき、 「払うお金が足りない」「納税のために実家を手放さないといけない」 そんな状況になってしまったら…
だからこそ、“相続税対策”は「まだ先の話」ではなく、 “いま”からできる家族への備えなのです。
相続税の基本|まずは基礎控除を知っておく
📌 相続税の基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の人数
例)相続人が3人の場合 → 3,000万円 + 600万円×3=4,800万円
この金額を超えると、相続税の申告が必要になります。
実際に「土地は古いから安いと思ってた」という方が、 評価額では数千万円と判定され、相続税対象になるケースも。
よくある“うっかり課税”の例
- 不動産が郊外に複数あり、合算すると5,000万円を超えていた
- 預金+保険+株式などの金融資産で基礎控除を上回っていた
- 生前贈与とみなされる取引をしていて、課税対象になった
思いがけず「申告対象」になってしまうことは、誰にでも起こりえます。
今からできる!相続税対策の具体例
🔸 年間110万円まで非課税の「生前贈与」をコツコツ活用
🔸 教育資金や住宅資金の一括贈与(特例)を使って実質節税
🔸 小規模宅地等の特例で不動産の評価額を大幅に下げる
🔸 生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人)を活用 🔸 不動産の共有・法人化で納税負担を抑える
🔸 認知症対策として「家族信託」を活用し、資産凍結を防ぐ
「節税テクニック」というより、「家族を守る仕組み作り」として、 いまできることを一緒に考えていくことが大切です。
相続税の対策=“争族”の予防にも
相続税対策は、単なる税金の節約にとどまりません。
遺産の分け方、納税資金の確保、財産の整理や想いの伝え方など── これらを準備しておくことは、「家族のこれから」を守る手段でもあります。
「財産を“残す”」だけでなく、 「“負担を残さない”こと」も大切な相続準備なのです。
✅ OFPSの相続税・贈与サポートでできること
- ご家族構成・財産状況に合わせた節税設計
- 不動産の評価額診断と小規模宅地特例の活用アドバイス
- 贈与のタイミング・金額・手続きに関するアドバイス
- 家族信託や法人化など“生前”にできる仕組み作りの提案
- 税理士・司法書士と連携した一括支援
「いつかじゃなくて、いま」始めることで、 節税はもちろん、ご家族の不安や混乱も防ぐことができます。
▶ 相続税、かかるかどうかを知るだけでも、安心につながります。
▶ まずは、いまの状況を整理するところから始めてみませんか?
よくある質問(FAQ)|「これ、実はずっと気になっていました」

相続のことって、身近すぎて聞きづらい。ネットで調べてもケースによって答えが違ったり、難しい専門用語ばかりで「よく分からないまま不安だけが残る」…そんな方も多いのではないでしょうか?
ここでは、実際のご相談の中でも特に多い“リアルなお悩み”をQ&A形式でご紹介します。 「私もこれ気になってた!」という項目があれば、ぜひお気軽にご相談くださいね。
Q1. 相続放棄って本当にできる?費用は?手続きは面倒?
A. はい、できます。ただし“3か月以内”に家庭裁判所へ申し出る必要があります。
相続放棄は、亡くなった方の財産を一切受け取らない代わりに、借金などのマイナス財産も負わなくてよくなる制度です。
「親が借金を残していた」「財産の全容が分からず怖い」「兄弟にすべて譲りたい」などの理由で選ばれることが多く、実際に利用される方も年々増えています。
ただし、以下のような注意点があります:
- 一部だけ放棄はできない(全部かゼロか)
- 不動産や通帳を勝手に触ってしまうと“相続を認めた”とみなされる可能性あり
- 手続きは家庭裁判所への書類提出が必要。費用は印紙・郵送代含めて1万円前後+書類作成のサポート料
📌 迷ったらまず「放棄すべきかどうか」を整理するヒアリングをおすすめしています。
Q2. 相続税はいつ払うの?現金が足りないときはどうするの?
A. 相続開始(亡くなった日)から“10か月以内”が申告・納税期限です。
遅れると延滞税・無申告加算税などが発生し、余計に負担が増える恐れがあります。
また、相続税は「現金」で納める必要がありますが、実際には「不動産はあるけど現金が足りない」というご家庭も少なくありません。
そんな場合に備え、以下の方法で事前に対策することが可能です:
- 生前から納税資金を確保する(生命保険・預金の整理など)
- 納税猶予制度・延納制度・物納の活用(条件あり)
- 不動産の一部売却や賃貸化による資金確保
📌 OFPSでは「相続税がかかるかどうか」のシミュレーションも無料で実
施しています。
Q3. 遺言書があったら、それに従わないとダメですか?
A. 基本的には従う必要がありますが、相続人全員の合意があれば別の分け方も可能です。
たとえば、「長男にすべてを相続させる」と書いてあっても、他の兄弟が納得せず、「遺留分侵害額請求」という法的措置を取ることがあります。
また、遺言書が古かったり、家族の関係が変化していた場合、「こんな分け方で本当にいいのか」と迷うことも。
遺言は“法的効力”がある一方で、“家族の気持ち”とズレてしまうこともあるのです。
📌 専門家が遺言書の内容確認・再整理をお手伝いします。家族に納得してもらえる分け方を一緒に考えましょう。
Q4. 実家の名義がそのままです。何か問題ありますか?
A. 大きな問題があります。2024年4月から、相続登記が“義務化”されました。
つまり、相続が発生したのに不動産の名義変更をせずに放置していると、法律違反として“10万円以下の過料”が科される可能性があります。
また、名義が故人のままだと:
- 売却も活用もできない
- 相続人が増え、手続きがさらに複雑化
- 固定資産税だけがかかり続ける
📌 相続登記は「早め」が肝心です。司法書士連携でワンストップ対応が可能です。
Q5. 誰に相談すればいいのか分からなくて…
A. その気持ち、とてもよく分かります。
相続には「弁護士」「税理士」「司法書士」など様々な専門家が関わります。 でも、どこに相談すればいいのか、どの段階で誰に頼めばいいのか、初めてだととても分かりづらいですよね。
OFPSでは、あなたの状況を丁寧にヒアリングし、必要に応じて最適な専門家と連携。
“まずはどこに聞けばいいか分からない”という方こそ、ぜひ最初の窓口としてご相談ください。
▶ 疑問や不安がある方は、今すぐ無料でご相談ください。
▶ 相続は“知らなかった”だけで損することも。まずは一歩、踏み出してみませんか?
まずはご相談ください|ひとりで悩まず、ゆっくり話してみませんか?
終活や相続、不動産のこと。
「そろそろ考えなきゃ…」と思っても、
何から始めればいいのか分からないまま、つい時間だけが過ぎてしまうこともありますよね。
でも、大丈夫です。
「まだ早いかも…」「相談するほどでもないかも…」という方こそ、私たちは丁寧にお話をお聞きします。
あなたの状況、ご家族の想い、これからの暮らし。
どんな小さなことでもかまいません。
私たちが、安心して未来へ進むお手伝いをいたします。
✅ 初回相談・ヒアリングは【完全無料】です
✅ 「いま相談するべきか分からない」方も歓迎
✅ ご希望があれば、匿名での相談も可能です
「相談してよかった」
「もっと早く聞けばよかった」
そんなお声を、たくさんいただいています。
▶ ご不安なこと、まずはお話ししませんか?
▶ 押し売りのない、やさしい終活・相続サポートをお約束します。
