「もし親や兄弟の老人ホームの保証人を頼まれたら…正直、なりたくないな」なんて、一人でモヤモヤしていませんか?いや~、その気持ち、めちゃくちゃ分かります!
老人ホームの保証人には、予期せぬリスクやトラブルがつきものですし、勝手に話を進められたらどうしよう…なんて不安にもなりますよね。特に、親の保証人になりたくない、兄弟の保証人になりたくないと感じている方は少なくありません。
子供としての責任や、無職でも条件を満たせるのか、連帯保証人の極度額はいくらなの?など、疑問は尽きないはずです。
でも、ご安心ください!この記事では、身元保証人になりたくないあなたの悩みを解決するため、老人ホームの保証人を上手に断るにはどうすればいいか、具体的な方法を分かりやすく解説していきます。介護施設の保証人に関する不安を解消し、あなたとご家族にとって最善の道を見つけるお手伝いをさせてくださいね!
この記事のポイント
- 保証人になるリスクと具体的なトラブル事例がわかる
- 保証人に求められる条件や法的な義務の範囲がわかる
- 保証人を引き受けたくない場合の断り方と交渉術がわかる
- 保証人を立てずに済む具体的な代替案が見つかる
目次
老人ホーム保証人になりたくない人が知るべきこと
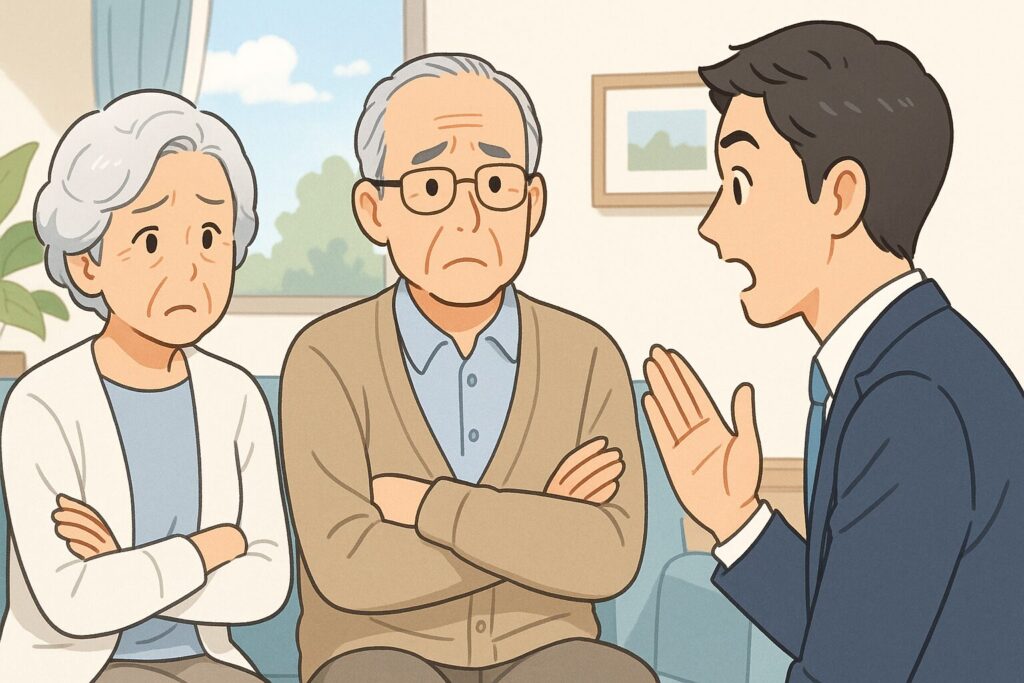
老人ホームの保証人になるリスクとは
老人ホームの保証人、と聞くと「名前を貸すだけでしょ?」なんて軽く考えてしまうかもしれませんが、実はそこには見えないリスクが潜んでいるんです。安易に引き受けてしまうと、後で「こんなはずじゃなかった…」と頭を抱えることになりかねません。
主に考えられるリスクは、「金銭的リスク」「精神的リスク」「時間的リスク」の3つです。
金銭的リスク
これが一番イメージしやすいリスクかもしれませんね。具体的には、以下のようなケースが考えられます。
- 利用料の滞納:入居者本人の年金や貯蓄が底をつき、月々の利用料が支払えなくなった場合、連帯保証人であるあなたに支払いの義務が生じます。
- 損害賠償:入居者が他の入居者にケガをさせたり、施設の備品を壊してしまったりした場合の損害賠償を請求される可能性があります。
- 原状回復費用:退去時に、部屋の修繕費用やクリーニング代などを請求されることがあります。
私の知人Aさんは、お父様の保証人になったのですが、お父様の年金だけでは費用が足りなくなり、毎月3万円ほど補填しているそうです。「自分の老後資金も貯めたいのに…」と嘆いていました。他人事ではないですよね。
精神的・時間的リスク
お金も大変ですが、精神的・時間的な負担もかなり大きいものがあります。
- 緊急時の対応:入居者の体調が急変した場合、深夜でも病院への駆けつけを求められることがあります。仕事や家庭との両立が難しくなるケースも少なくありません。
- 重要な意思決定:入居者の判断能力が低下した場合、治療方針や介護計画など、命に関わる重要な決断を迫られることがあります。このプレッシャーは想像以上に重いものです。
- 各種手続きの代行:入退院の手続きや行政手続きなど、様々な手続きを本人に代わって行う必要があります。平日に時間を取られることも多く、これも大きな負担となります。
リスクを軽視しないこと
「家族だから当たり前」と思っていても、これらのリスクが積み重なると、ご自身の生活が破綻してしまう可能性もゼロではありません。保証人になるということは、入居者の方の生活と人生の一部を背負う覚悟が必要だということを、しっかり理解しておくことが大切です。安易な気持ちで引き受けず、慎重に判断しましょう。
老人ホームの保証人でよくあるトラブル

「うちは家族仲が良いから大丈夫!」と思っていても、保証人をめぐるトラブルは意外なところに潜んでいます。ここでは、私がこれまで見聞きしてきた「あるある」なトラブル事例をいくつかご紹介しますね。
ケース1:支払い能力をめぐる兄弟間の押し付け合い
これは本当に多いケースです…。長男だから、近くに住んでいるから、といった理由でなし崩し的に保証人を引き受けたものの、いざ親の貯金が尽きて支払いが始まると、「なんで私だけが…」と不満が爆発。他の兄弟に協力を求めても、「保証人になったんだから責任持ってよ」と突き放され、骨肉の争いに発展してしまうのです。
以前ご相談を受けたお客様は、お兄様が保証人だったそうですが、お兄様の会社の経営が傾き支払いが困難に。「お前が代わりに払え」と言われ、大喧嘩になったと涙ながらに話していました。お金の問題は、本当に根が深いですよね。
ケース2:「聞いてないよ!」入居者本人との認識のズレ
入居者ご本人が「迷惑はかけないから」と言っていたのに、実際には頻繁に呼び出されたり、想定外の支払いを求められたりするケースです。悪気はないのでしょうが、入居者ご本人は施設のサービス内容や契約の詳細を完全には理解していないことも多いのです。
その結果、「話が違うじゃないか!」と保証人が不満を抱え、入居者本人との関係までギクシャクしてしまうこともあります。
ケース3:施設側とのコミュニケーション不足
「何かあったら連絡します」と言われていたのに、実際には事後報告ばかりで、気づいた時には大きなトラブルになっていた…というケースもあります。例えば、他の入居者との小さな揉め事が、いつの間にか大きな問題に発展し、高額な損害賠償を請求される、といった具合です。
保証人としては、施設の対応に不信感を抱きますし、「もっと早く教えてくれれば…」と悔やんでも悔やみきれません。
トラブルを避けるための心得
これらのトラブルを避けるためには、保証人を引き受ける前に、家族間で役割分担や費用負担についてしっかり話し合い、書面に残しておくことが非常に重要です。また、契約時には施設側にも疑問点を全て確認し、納得できるまで説明を求める姿勢が大切になります。面倒くさがらず、最初の一歩を丁寧に進めましょう!
老人ホームの連帯保証人と極度額
「連帯保証人」と聞くと、なんだかすごく重い責任を負わされるイメージがありますよね。そのイメージ、残念ながら正解です(笑)。そして、その責任の重さに関わる重要なキーワードが「極度額」です。
2020年の民法改正で何が変わった?
実は、2020年4月1日に民法が改正され、老人ホームなどの個人向け保証契約では、保証人が負う可能性のある最大の負担額、つまり「極度額」を契約書に明記することが義務付けられました。
それ以前は、「発生した損害の一切を保証する」といった青天井の契約がまかり通っていましたが、これでは保証人の負担が無限に膨らむ可能性があり、あまりにも酷ですよね。そこで、保証人を保護するために、このルールが導入されたのです。
極度額が設定されていない契約は無効!
もし、2020年4月1日以降に結んだ契約書に極度額の記載がなければ、その保証契約は無効になります。契約書にサインする前には、必ず極度額の欄を確認するようにしてくださいね。
参考情報サイト:法務省「保証に関する民法のルールが大きく変わりました」
URL: https://www.moj.go.jp/content/001399956.pdf
極度額の相場は?
では、気になる極度額の相場ですが、これは施設の月額利用料によって大きく変わってきます。
| 月額利用料の目安 | 極度額の相場 |
|---|---|
| 15万円 | 200万円~500万円程度 |
| 25万円 | 400万円~800万円程度 |
| 35万円以上 | 600万円~1,000万円以上 |
一般的には、月額利用料の24ヶ月分(2年分)から60ヶ月分(5年分)程度に設定されることが多いようです。ただ、これはあくまで目安。高級な老人ホームであれば、極度額が1,000万円を超えるケースも珍しくありません。
契約書を見て「極度額500万円」なんて書いてあったら、思わず「ご、ごひゃくまんえん!?」って声が出ちゃいますよね(笑)。でも、これはあくまで「最大でこの金額まで責任を負う可能性がある」という上限額です。実際にこの金額を全額請求されるケースは稀ですが、そのリスクを背負う覚悟があるかを自分に問いかける良い機会になります。
契約時には、極度額が妥当な金額かどうか、なぜその金額に設定されているのかを施設側にしっかりと確認することが大切です。納得できない場合は、安易にサインしないようにしましょう。
老人ホームの保証人に求められる条件

「保証人になりたい(なりたくないはさておき)けど、私でもなれるの?」という疑問も湧いてきますよね。実は、誰でも保証人になれるわけではなく、多くの施設ではいくつかの条件を設けています。
法的に定められたルールはありませんが、一般的に施設側が求める主な条件は以下の通りです。
① 安定した収入があること
これは最も重要な条件の一つです。万が一、入居者の利用料が支払えなくなった場合に、代わりに支払う能力があるかどうかが問われます。そのため、現役で働いていて、定期的な収入があることが求められるのが一般的です。契約時に、源泉徴収票や課税証明書などの提出を求められることもあります。
② 年齢が高すぎないこと
保証人は、入居者よりも長生きして、最後まで責任を果たすことが期待されます。そのため、入居者本人と同年代や、それ以上にご高齢の方は保証人として認められないケースがほとんどです。一般的には、65歳未満や75歳未満といった年齢制限を設けている施設が多いようです。
以前、80歳のお父様の保証人として、78歳のお母様を立てようとした方がいらっしゃいましたが、施設側から「申し訳ありませんが…」と断られていました。気持ちは分かりますが、現実的には難しいんですよね。
③ 原則として親族であること
多くの施設では、保証人は子供や兄弟などの親族に限定しています。友人や知人では、いざという時に責任を果たしてもらえないリスクが高いと判断されるためです。ただし、身寄りのない方のために、後述する保証会社などの利用を認めている施設も増えてきています。
④ 国内に居住していること
緊急時にすぐに駆けつけられるよう、国内、できれば施設の近くに住んでいることが望ましいとされます。海外に住んでいる場合は、保証人として認められないことがほとんどです。
条件は施設によって様々
これらの条件は、あくまで一般的なものです。施設の方針によって条件は大きく異なるため、必ず入居を検討している施設に直接確認するようにしましょう。「自分は条件に合わないかも…」と思っても、他の親族と共同で保証人になるなど、柔軟に対応してくれる場合もあります。まずは相談してみることが大切ですよ。
子供は老人ホームの保証人になる義務があるか
「親の面倒を見るのは子供の義務。だから保証人になるのも当たり前」…本当にそうでしょうか?この問題、法律と感情が複雑に絡み合っていて、悩んでいる方も非常に多いんです。
結論から言ってしまうと、子供が親の老人ホームの保証人になる法的な義務は一切ありません。
「扶養義務」と「保証契約」は別モノ!
よく混同されがちなのですが、「親を扶養する義務」と「保証人になる契約」は全くの別問題です。
民法では、直系血族(親子など)は互いに扶養する義務があると定められています。しかし、この扶養義務とは、「自分の生活を犠牲にしない範囲で、経済的に困窮している親族を助ける」という程度のものです。これを「生活扶助義務」と言います。
一方、老人ホームの保証人契約は、施設の利用料の支払いを保証したり、何かあった時の責任を負ったりする、全く別の契約です。扶養義務があるからといって、自動的に保証人になる義務が発生するわけではないのです。
介護は「努力義務」
親の介護や支援は、あくまで「努力義務」とされています。つまり、「自分の生活や人生が大きく狂わない範囲で、できる限りの努力をすれば良い」ということです。自分の家庭や子供の生活を守ることの方が優先されるべき、と法律でも考えられています。ですから、「保証人にならない=親不孝」と自分を責める必要は全くないんですよ。
義務はないけど…断りづらいのが現実
とはいえ、理屈では分かっていても、親から「お前しか頼れる人がいないんだ」と言われたり、施設側から「お子様がなるのが一般的ですよ」と説明されたりすると、断りづらいのが人情ですよね。
私が担当したお客様の中にも、「断ったら親との縁が切れてしまうかもしれない」と涙ぐむ方がたくさんいらっしゃいました。でも、無理して保証人になって、ご自身の家庭が壊れてしまっては元も子もありません。大切なのは、義務感や罪悪感だけで判断しないこと。冷静に、ご自身の状況と将来を見つめ直すことが重要です。
もし断る決心がつかない場合は、一人で抱え込まず、ケアマネジャーや後述する専門機関に相談してみてください。きっと、あなたに合った解決策が見つかるはずです。
老人ホームの保証人に勝手にされる危険性

「まさかとは思うけど、知らないうちに保証人にされていた…なんてこと、あるの?」と不安に思う方もいるかもしれません。特に、親や兄弟との関係が少し複雑な場合、心配になりますよね。
結論から言うと、あなたが知らない間に勝手に保証人にされて、法的な責任を負わされることは、基本的にはありません。
保証契約には本人の意思確認が必須!
保証契約は、保証人になる本人が「保証します」という意思を明確に示し、契約書に自ら署名・捺印して初めて成立します。誰かがあなたの名前を勝手に書いても、その契約は無効です。
特に、連帯保証人になる場合は、実印と印鑑登録証明書の提出を求められることがほとんどです。あなたが知らない間に誰かがあなたの実印を持ち出し、印鑑登録証明書を取得するのは、極めて困難ですよね。
「身元引受人」や「緊急連絡先」には注意!
ただし、注意が必要なのは、「連帯保証人」ではなく「身元引受人」や「緊急連絡先」の欄に、相談なく名前を書かれてしまうケースです。これらは金銭的な責任は発生しないことが多いですが、緊急時の対応や退去時の身柄・遺品の引き取りなどを求められる可能性があります。「聞いてないよ!」という事態を避けるためにも、注意が必要です。
勝手に名前を使われた場合の対処法
万が一、施設からあなた宛に請求書が届くなどして、勝手に保証人にされていたことが発覚した場合は、慌てずに以下のように対応しましょう。
- 契約書を確認する:まずは施設側に連絡し、保証契約書を見せてもらいましょう。筆跡が明らかに違うなど、自分が署名したものでないことを確認します。
- 契約の無効を主張する:自分が署名したものではないことを明確に伝え、「この契約は無効です」と主張します。内容証明郵便で通知を送ると、より確実な証拠となります。
- 専門家に相談する:施設側が応じないなど、話がこじれそうな場合は、すぐに弁護士などの専門家に相談しましょう。
勝手に名前を使われるなんて、ドラマの中だけの話だと思いたいですよね。でも、実際にそういったトラブルに巻き込まれてしまう可能性はゼロではありません。一番の予防策は、やはり家族間のコミュニケーションです。
「保証人は誰がやるのか」という大切な話を、きちんとオープンに話し合える関係を築いておくことが、何よりの防御策になりますよ。
老人ホーム保証人になりたくない場合の対処法

親や兄弟の保証人になりたくない時は?
さて、ここからが本題です。「保証人になりたくない!」という気持ちが固まった時、どう行動すれば良いのでしょうか。親や兄弟という近しい関係だからこそ、伝え方には細心の注意が必要です。角を立てずに、自分の意思を伝えるためのステップをご紹介します。
ステップ1:まずは自分の気持ちと状況を整理する
感情的に「無理!」と突っぱねる前に、なぜ保証人になりたくないのか、その理由を自分の中で明確にしましょう。
- 金銭的な余裕がない(子供の教育費、住宅ローンなど)
- 仕事が忙しく、緊急時の対応が難しい
- 持病があり、精神的な負担に耐えられない
- 他の兄弟との間で、不公平感がある
このように具体的に書き出してみることで、冷静に話し合うための土台ができます。
ステップ2:正直に、かつ丁寧に断る
準備ができたら、親や兄弟に直接会って話す機会を設けましょう。電話やメールで済ませるのはNGです。大切なのは、「あなたのことは大切に思っているけれど、保証人になることはできない」というスタンスを明確に伝えることです。
「お父さんのことは心配だし、できる限りの協力はしたいと思ってる。でも、正直に言うと、うちも子供の学費でいっぱいいっぱいで、金銭的な保証をすることは難しいんだ。
それに、仕事柄、急に呼び出されても駆けつけられないことが多くて、責任を果たせないと思う。だから、保証人だけは本当にごめんなさい」
こんな風に、「I(アイ)メッセージ(私はこう思う)」で伝えると、相手を責めるニュアンスがなくなり、気持ちが伝わりやすくなりますよ。
ステップ3:代替案を一緒に探す姿勢を見せる
ただ断るだけでなく、「じゃあどうすればいいの?」という次のステップを一緒に考える姿勢を見せることが、関係をこじらせないための最大のポイントです。
「保証人は難しいけど、他の方法を探すのは手伝うよ」と伝え、後述する成年後見制度や身元保証会社といった選択肢を提示してみましょう。問題を丸投げするのではなく、一緒に解決しようとする協力的な態度が、相手の理解を得る鍵となります。
話し合いは根気強く
一度で理解してもらえるとは限りません。「冷たい」「親不孝だ」などと感情的な言葉をぶつけられることもあるでしょう。しかし、そこで諦めずに、根気強く対話を続けることが大切です。あなたの誠実な態度は、きっといつか相手に伝わるはずです。一人で抱え込まず、配偶者や信頼できる人に同席してもらうのも良い方法ですよ。
無職でも介護施設の保証人になれるのか

「今は専業主婦(主夫)だけど、親の保証人になれる?」「定年退職して無職だけど、大丈夫かな?」といったご相談もよく受けます。結論から言うと、無職だからといって、絶対に保証人になれないわけではありませんが、ハードルはかなり高くなるのが現実です。
施設側が重視するのは「支払い能力」
前述の通り、施設側が保証人に求める最も重要な条件は、「万が一の時に利用料を支払えるか」という点です。そのため、定期的な収入がない「無職」の場合は、支払い能力がないと判断され、保証人として認められないケースが多くなります。
ただし、以下のような場合は、無職でも保証人になれる可能性があります。
- 十分な預貯金や資産がある:定期収入がなくても、支払いを肩代わりできるだけの十分な預貯金や不動産などの資産がある場合。この場合、預金通帳のコピーや資産証明書の提出を求められることがあります。
- 安定した年金収入がある:年金収入が施設の利用料を十分にカバーできる金額であれば、認められる可能性があります。
収入のある親族との「共同保証」という選択肢
もし、ご自身の資産だけでは不安な場合、収入が安定している他の親族(兄弟や自分の子供など)と一緒に「共同保証人」になるという方法もあります。
例えば、専業主婦のあなたが身元引受人としての役割を担い、会社員の兄弟が連帯保証人として金銭的な責任を負う、といった形です。二人で責任を分担することで、施設側も安心してくれやすくなります。
「私、無職だから…」と最初から諦めるのではなく、まずは施設側に相談してみることが大切です。「妻は専業主婦ですが、私の収入と合わせれば問題ありません」と夫婦で説明したり、「兄と私で協力して保証人になります」と兄弟で申し出たりすることで、道が開けることもありますよ。
無理は禁物!
無職の状態で保証人になるということは、ご自身の資産や将来の生活費を切り崩すリスクを伴います。もし少しでも不安があるなら、無理して引き受けるべきではありません。後述する保証会社などの利用も視野に入れ、ご自身の生活を守ることを最優先に考えてくださいね。
老人ホームの保証人を断るにはどうする?
「保証人にはなれない」という意思は固い。でも、どうやって切り出せばいいか分からない…。そんな時は、一人で悩まずに第三者の力を借りるのが得策です。感情的なしがらみがない専門家に入ってもらうことで、話がスムーズに進むことがよくあります。
相談先1:ケアマネジャー
まず最初に相談すべきは、担当のケアマネジャーさんです。ケアマネジャーは介護のプロであると同時に、様々な家族のケースを見てきている、いわば「家族問題の専門家」でもあります。
「経済的な理由で保証人になるのが難しい」「精神的に負担が大きい」といったあなたの状況を正直に伝えれば、きっと親身に相談に乗ってくれるはずです。ケアマネジャーから親や施設側に、あなたの状況を客観的に説明してもらったり、保証人がいなくても入れる施設や、保証会社の利用といった代替案を提案してもらったりすることもできます。
「私から言うと角が立つので、ケアマネさんから父にうまく伝えてもらえませんか?」とお願いするのも一つの手です。第三者から冷静に説明されると、親御さんも意外とすんなり受け入れてくれることがありますよ。
相談先2:地域包括支援センター
地域包括支援センターは、高齢者の暮らしを様々な面からサポートする公的な相談窓口です。介護、福祉、医療など、各分野の専門家が在籍しており、無料で相談に乗ってくれます。
保証人の問題だけでなく、今後の介護生活全般に関する不安や悩みを相談できます。成年後見制度の利用について詳しく教えてもらったり、お住まいの地域で利用できるサービスを紹介してもらったりと、心強い味方になってくれます。
参考情報サイト:厚生労働省「地域包括支援センター」
URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/
相談先3:弁護士などの法律の専門家
もし、家族間の話し合いがこじれてしまい、トラブルに発展しそうな場合は、弁護士に相談することも検討しましょう。法律の専門家から、あなたの権利や義務について正確なアドバイスをもらうことで、自信を持って交渉に臨むことができます。
弁護士に代理人として交渉してもらうことで、感情的な対立を避け、冷静に話を進めることも可能です。相談料はかかりますが、将来の大きなトラブルを避けるための必要経費と考えることもできます。
一人で抱え込まないで!
保証人を断ることは、決して悪いことではありません。大切なのは、あなた自身の生活と未来を守ることです。一人で抱え込んで精神的に追い詰められる前に、勇気を出して専門家のドアを叩いてみてください。きっと、解決の糸口が見つかるはずです。
身元保証人になりたくない場合の代替案

「保証人を断りたいけど、親を見捨てるわけにはいかない…」。そんなジレンマを解決してくれる、心強い選択肢があります。それが、「成年後見制度」と「身元保証会社」の利用です。
代替案1:成年後見制度
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分になった方に代わって、家庭裁判所が選んだ「後見人」が財産管理や契約手続きなどを行う制度です。
成年後見人ができること
- 預貯金の管理や不動産の処分といった財産管理
- 老人ホームの入居契約や介護サービスの利用契約といった身上監護
後見人がいれば、本人に代わって施設の利用料を支払ったり、契約手続きを行ったりできるため、施設側も安心して受け入れてくれやすくなります。
成年後見制度の注意点
ただし、注意点が一つ。成年後見人は、あくまで本人の代理人であり、「身元保証」や「連帯保証」は行えません。そのため、施設によっては、後見人を立てた上で、さらに身元引受人や連帯保証人を求められる場合があります。また、後見人には弁護士や司法書士などの専門家が選ばれることが多く、その場合は月々数万円の報酬が必要になります。
参考情報サイト:法務省「成年後見制度・成年後見登記制度」
URL: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html
代替案2:身元保証会社(身元保証サービス)
近年、利用者が増えているのが、NPO法人や一般企業が提供する身元保証サービスです。家族に代わって、身元保証や身元引受の役割を総合的に担ってくれます。
| 成年後見制度 | 身元保証会社 | |
|---|---|---|
| 主な役割 | 財産管理、契約手続き | 身元保証、連帯保証、緊急時対応、死後事務など |
| メリット | 法的な権限が強く、財産をしっかり守れる | 保証から死後事務まで幅広く対応。家族の負担が軽い |
| デメリット | 保証はできない。専門家への報酬が必要 | まとまった費用が必要。業者選びが重要 |
| 費用目安 | 月額2~6万円(専門家後見人の場合) | 契約時50~150万円程度(プランによる) |
身元保証会社の最大のメリットは、金銭的な連帯保証から、緊急時の駆けつけ、入院手続き、亡くなった後の葬儀や遺品整理まで、家族が担うべき役割を丸ごと引き受けてくれる点です。これにより、子供や親族は精神的・金銭的な負担から解放されます。
費用は決して安くはありませんが、「これで安心して親を任せられる」「自分の生活を守れる」と考えれば、価値のある投資だと言えるかもしれません。トラブルを避けるためにも、複数の会社から資料を取り寄せ、サービス内容や実績をしっかり比較検討することが大切ですよ。
老人ホーム保証人になりたくない悩みの解決策
ここまで、老人ホームの保証人に関する様々な情報をお伝えしてきましたが、いかがでしたでしょうか。最後に、あなたの「なりたくない」という悩みを解決するための要点をまとめます。
- 老人ホームの保証人になることには金銭的・精神的・時間的なリスクが伴う
- 保証人をめぐるトラブルは親族間でも起こり得るため事前の話し合いが不可欠
- 2020年の民法改正で連帯保証人には極度額の設定が義務付けられた
- 保証人には安定収入や年齢などの条件があり誰でもなれるわけではない
- 子供が親の保証人になる法的な義務は一切ない
- 自分の生活を守ることを優先して考えて良い
- 知らないうちに勝手に保証人にされることは基本的にない
- 保証人になりたくない時は正直に、かつ丁寧に断ることが大切
- ただ断るだけでなく代替案を一緒に探す姿勢が関係を良好に保つコツ
- 無職でも資産があれば保証人になれる可能性はあるが無理は禁物
- 断りづらい時はケアマネジャーや地域包括支援センターに相談する
- 話がこじれそうな場合は弁護士などの専門家の力を借りる
- 代替案として成年後見制度や身元保証会社の利用を検討する
- 身元保証会社は費用がかかるが家族の負担を大幅に軽減できる
- 一人で抱え込まずに周りに相談することが解決への第一歩
保証人の問題は、あなた一人の問題ではありません。家族や専門家と協力しながら、あなたとご家族全員が納得できる、最善の道を見つけてくださいね。応援しています!
参考

お気軽にご相談ください
相続は100人いれば、100通り
唯一無二の最適な相続をご提案いたします
CONTACT
専門家やえさん

- 専門家やえさん
-
堀川 八重(ほりかわ やえ)
大阪不動産・FPサービス株式会社 代表
15年以上にわたり1,500組を超えるご家族の相続や不動産のお悩みに、専門家として寄り添ってまいりました。私の信条は、法律や数字の話をする前に、まずお客様ご家族の歴史や言葉にならない想いを丁寧に「聞く」こと。信頼できる各分野の専門家チームと共に、皆様が心から安心できる最善の道筋をオーダーメイドでご提案します。一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。
最新の投稿
 お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説
お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説 相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説
相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説 お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例
お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例 お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説
お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説






