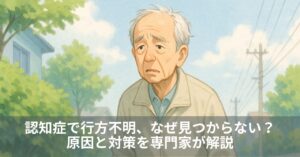「配偶者居住権って、もしかして相続財産の評価から外れるの?」なんて、ちょっと期待しちゃいますよね。残された家族の住まいを守るための優しい制度ですし、できれば税金もお安くなると嬉しいな…なんて思うお気持ち、とってもよく分かります。
結論から申し上げますと、配偶者居住権相続財産評価対象外というのは残念ながら誤解でして、しっかり相続税の課税対象になるんです。ただ、配偶者居住権の評価方法には独特のルールがあって、便利な計算シートもありますし、小規模宅地の特例が使えるかどうかも気になるところです。
それに、配偶者居住権のデメリットや、譲渡できない性質、登記の必要性、配偶者死亡後の権利の行方、そして二次相続への影響など、知っておかないと後で困るポイントもたくさんあるんですよ。
この記事では、「居住権は相続の対象ですか?」や「配偶者居住権は相続税の課税対象ですか?」といった基本的な疑問から、具体的な相続税申告の方法まで、ややこしい部分をスッキリ解説していきますね!
この記事のポイント
- 配偶者居住権が相続税の評価対象となる理由
- 具体的な相続税評価額の計算方法と便利なツール
- 配偶者居住権を設定する際のメリットと知るべき注意点
- 二次相続や登記など実務上で押さえておくべきポイント

こんにちは、終活・相続の専門家やえです。
配偶者居住権は、残された配偶者の方の生活を守る、とても心強い制度です。でも、税金のことが絡むと一気に複雑に見えてしまいますよね。
大切なのは、メリットとデメリットを両方しっかり理解して、ご自身の家族にとって本当に最適な選択なのかを見極めることです。一緒に一つずつ確認していきましょう!
配偶者居住権相続財産評価対象外という誤解と基本知識

配偶者居住権は相続税の課税対象ですか?
はい、配偶者居住権は相続税の課税対象となります。「配偶者の居住を守るための権利なのに、なぜ税金が?」と疑問に思うお気持ちは、ごもっともです。
この法的な根拠は、相続税法にあります。法律では、亡くなった方から「相続または遺贈によって取得した一切の財産」が課税対象と定められています。ここで言う「財産」とは、現金や預貯金、不動産といった目に見えるものだけではありません。経済的な価値があると評価できる「権利」も、立派な財産として扱われるのです。
配偶者居住権は、建物の所有権がなくても、終身または一定期間、無償でその家に住み続けられるという、非常に大きな経済的利益をもたらす権利です。
もし同じ条件で家を借りれば、本来は高額な家賃が発生するはずですよね。その家賃負担がなくなるわけですから、その分の価値が財産として評価され、課税対象となるのは自然なことなのです。
そのため、遺産分割協議や遺言によってこの権利を取得した場合、その権利の価値を評価して他の相続財産と合算し、相続税の計算を行う必要があります。「評価対象外」という認識は誤りであることを、最初の重要なポイントとして確実に押さえておきましょう。
そもそも居住権は相続の対象ですか?

こちらも結論から申し上げますと、配偶者居住権は遺産分割の対象となる、立派な相続財産です。
この権利は、以下の3つのいずれかの方法によって設定されます。
配偶者居住権の設定方法
- ① 遺産分割協議:相続人全員の話し合いによって、配偶者が取得することを決める。
- ② 遺贈:被相続人が生前に作成した遺言書によって、配偶者に権利を遺すことを指定する。
- ③ 家庭裁判所の審判:相続人間の話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所に申し立てて決めてもらう。
このように、配偶者居住権は相続財産の一つとして、相続手続きの中で正式に取得するものです。亡くなった時点で自動的に発生する権利ではない、という点も知っておくと良いでしょう。
注意点:一代限りの権利で、再相続はできません
配偶者居住権を理解する上で非常に重要なのが、この権利が「一身専属権(いっしんせんぞくけん)」であるという性質です。これは、「その権利者個人のためだけに認められた、一代限りの権利」という意味です。
そのため、配偶者居住権を取得した配偶者が亡くなった際に、その権利を子どもなどがさらに相続することはできません。配偶者の死亡と同時に、権利はきれいに消滅します。この性質が、後の二次相続にも大きく関わってきます。
相続税に関わる配偶者居住権の評価方法
では、相続税の計算の基礎となる配偶者居住権の評価額は、具体的にどうやって算出するのでしょうか。計算方法は一見すると複雑ですが、パーツごとに分解して見ていけば、その仕組みを理解することができます。
評価額の基本的な考え方は、「建物全体の価値から、“居住権がない”状態の所有権の価値を差し引く」というものです。つまり、建物という一つの財産を「住む権利(配偶者居住権)」と「それ以外の権利(所有権)」の二つに分け、それぞれの価値を算出するイメージです。
国税庁が示す具体的な計算式は以下の通りです。
配偶者居住権の価額 = 居住建物の時価 - 居住建物の時価 × (残存耐用年数-存続年数)/残存耐用年数 × 存続年数に応じた複利現価率
式に出てくる各項目を詳しく見ていきましょう。
1. 居住建物の時価
これは、相続税を計算する際の建物の評価額を指します。一般的には、毎年市区町村から送られてくる固定資産税納税通知書に記載されている「不動産の評価額」をそのまま使用します。
2. 残存耐用年数
建物があと何年くらい使用できるかを示す年数です。税法で定められた建物の構造ごとの法定耐用年数を1.5倍し、そこから建物の築年数(経過年数)を差し引いて算出します。例えば、一般的な木造住宅の法定耐用年数は22年なので、その1.5倍の33年が計算の基礎となります。
3. 存続年数
配偶者居住権が何年間続くか、という期間です。遺言などで期間が定められていればその年数を使いますが、多くの場合は「終身」と設定されます。その場合は、厚生労働省が公表している「簡易生命表」に基づき、配偶者の年齢に応じた「平均余命」を存続年数として用います。例えば、令和4年の簡易生命表によると、80歳の女性の平均余命は11.93年となります。
4. 複利現価率
これは少し難しい概念ですが、「将来のお金の価値を、現在の価値に換算するための係数」です。例えば、金利が年3%なら、今の100万円は1年後には103万円になりますよね。その逆で、「将来の価値を今受け取るとしたら、いくらになるか」を計算するための数値で、存続年数に応じて国税庁が公表している表から該当する係数を使います。
これらの情報を組み合わせて計算することで、相続税申告に使用する正確な評価額が明らかになります。
より詳しい計算ルールや耐用年数については、国税庁のタックスアンサー「No.4666 配偶者居住権等の評価」で詳細に解説されています。
便利な配偶者居住権の計算シートとは

「計算の仕組みは分かったけれど、自分で全部計算するのはやっぱりハードルが高い…」と感じるのが正直なところですよね。特に、耐用年数や複利現価率の表を探して当てはめる作業は、慣れていないと間違う可能性もあります。
でも、ご安心ください。国税庁は、この複雑な評価額計算を誰でも正確に行えるように、非常に便利な公式ツールを提供しています。
それが、「配偶者居住権等の評価明細書」という書類です。これは本来、相続税の申告書に添付して提出するためのものですが、その様式が実質的な「計算シート」として完璧に機能するように作られているのです。
評価明細書でできること
この明細書には、建物の固定資産税評価額、建築年月日、建物の構造、配偶者の生年月日といった必要な情報を書き込む欄が順番に用意されています。これらの情報を一つずつ埋めていくだけで、複雑な計算式を意識することなく、最終的な配偶者居住権と敷地利用権の評価額が算出できるようになっています。
税理士などの専門家も、この公式の明細書を使用して評価額を計算するのが一般的です。様式は国税庁のウェブサイトからいつでもダウンロードできますので、まずは概算額を知るために、ご自身で一度試算してみることをお勧めします。具体的な数字が見えることで、遺産分割の話し合いも進めやすくなるかもしれません。
権利を守るための配偶者居住権の登記
遺産分割協議がまとまり、配偶者居住権の取得が決まったら、それで終わりではありません。その権利を法的に確定させ、第三者から守るために絶対に欠かせない手続きが「登記」です。
登記とは、不動産の権利関係を法務局の公的な帳簿(登記簿)に記録し、社会に公示する制度です。これを「第三者対抗要件」と呼びます。簡単に言えば、「この家の居住権は法的に私のものです!」と、誰に対しても正々堂々と主張できる状態にする手続きのことです。
もしこの登記を怠ると、非常に大きなリスクを背負うことになります。例えば、建物の所有権を相続した子どもが、お金に困ってその建物を第三者に売却してしまったとします。
この場合、配偶者居住権の登記がなければ、新しい所有者から「私が新しいオーナーです。家から出ていってください」と退去を求められた場合、法的に「私には住み続ける権利があります」と主張することができなくなってしまうのです。これでは、何のために権利を設定したのか分かりませんよね。
そうした悲劇を避けるためにも、配偶者居住権が設定されたら、速やかに法務局で所有権移転登記ならぬ「配偶者居住権設定登記」を行うことが極めて重要です。この手続きは専門的な知識が必要なため、通常は不動産名義変更と同様に司法書士に依頼して行います。登録免許税などの費用はかかりますが、安心して暮らし続けるための保険だと考えて、必ず手続きを行いましょう。
配偶者居住権は譲渡できないという注意点

配偶者居住権の基本的な性質として、もう一つ絶対に知っておかなければならない重要な注意点があります。それは、この権利は他人に譲渡したり、売却したり、担保に入れたりすることが一切できない、という点です。
この理由は、配偶者居住権が「その配偶者個人の生活の安定」だけを目的として作られた、特別な権利(一身専属権)だからです。もしこの権利を自由に売買できてしまうと、目先のお金のために住む家を失ってしまう人が出てくるかもしれません。法律は、そうした事態を防ぐために、権利の譲渡を固く禁じているのです。
したがって、以下のような行為は認められていません。
- 権利を不動産業者に売却して現金化する。
- 子どもや友人に権利を無償で譲る。
- 権利を担保にお金を借りる。
賃貸は可能?
建物の所有者の承諾を得れば、家の一部または全部を第三者に賃貸することは可能です。ただし、これは権利自体の譲渡ではなく、あくまで建物利用の一環として認められるものです。この場合も、所有者との密な連携が不可欠となります。
この「資産価値がない(換金性がない)」という性質は、将来のライフプランを考える上で非常に重要です。例えば、将来的に介護施設へ入居するためまとまった資金が必要になった際に、配偶者居住権を売却して充当する、といったことはできないのです。この点は、デメリットとしても捉えられるため、権利を設定する前に十分な検討が必要です。

どうでしょう、少しずつ配偶者居住権のキャラクターが見えてきましたか?「評価対象外じゃないんだ!」「登記が必要なんだ!」といった発見があったかもしれませんね。
税金や手続きの話は少し頭が痛くなるかもしれませんが、ご家族の大切な暮らしを守るための知識です。後半では、さらに踏み込んで税金や具体的な手続きについて見ていきましょう。
配偶者居住権相続財産評価対象外ではない?税金と手続き

配偶者居住権と相続税の具体的な関係
前述の通り、配偶者居住権は相続税の課税対象です。これが実際の遺産分割と相続税にどう影響するのか、具体的な例で見ていきましょう。
【設例】
- 相続財産:自宅不動産(評価額5,000万円)、預貯金(4,000万円)
- 相続人:配偶者と子1人
- 法定相続分:それぞれ2分の1(合計9,000万円 ÷ 2 = 4,500万円ずつ)
ケース1:配偶者が自宅の「所有権」を相続した場合
配偶者が住み続けるために自宅の所有権(5,000万円)を相続すると、法定相続分の4,500万円を超えてしまいます。このままでは子どもの遺留分を侵害する可能性もあり、超過した500万円分を自己資金から子へ支払う(代償分割)必要が出てくるかもしれません。
結果、配偶者の手元に残る預貯金が減り、その後の生活に不安が残る可能性があります。
ケース2:配偶者が「配偶者居住権」を相続した場合
同じ自宅でも、配偶者が取得するのが配偶者居住権(仮に評価額が2,000万円とします)と敷地利用権だったとします。すると、配偶者はまず2,000万円分の財産を取得したことになります。
法定相続分の残り(4,500万円 - 2,000万円 = 2,500万円)を預貯金から相続できます。そして、建物の所有権(5,000万円 - 2,000万円 = 3,000万円相当)は子が相続します。
この結果、配偶者は住み慣れた家に暮らし続けながら、生活資金として2,500万円もの預貯金を確保できるのです。
このように、配偶者居住権は、不動産を「居住権」と「所有権」に分けることで、遺産分割の選択肢を増やし、配偶者の生活資金確保に大きく貢献する制度なのです。
配偶者居住権の相続税申告は必要か

相続税の申告義務は、遺産の総額が「基礎控除額」を超えるかどうかで判断されます。配偶者居住権を取得したこと自体が、申告義務に直結するわけではありません。
相続税の基礎控除額の計算式
3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
例えば、相続人が配偶者と子2人(計3人)の場合、基礎控除額は 3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円となります。
配偶者居住権の評価額を含めた、すべての相続財産の合計額がこの基礎控除額以下であれば、相続税の申告も納税も一切不要です。しかし、合計額が基礎控除額を1円でも超える場合は、申告が必要になります。
ここで非常に重要なのが、「配偶者の税額軽減(通称:配偶者控除)」という特例です。これは、配偶者が相続した財産のうち、「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額までは、相続税がかからないという強力な制度です。
しかし、この特例の適用を受けるためには、納税額がゼロになる場合であっても、必ず相続税の申告書を税務署に提出しなければなりません。申告を忘れると、この特例は適用されず、多額の税金が発生する恐れがあるため、くれぐれもご注意ください。
配偶者居住権と小規模宅地の特例活用
相続税対策の王様とも言われる制度に、「小規模宅地等の特例」があります。これは、亡くなった方が住んでいた自宅の敷地などについて、一定の要件を満たす相続人が取得した場合に、その土地の評価額を最大で80%も減額できる、極めて効果の大きい特例です。
そして、この強力な特例は、配偶者が取得した「敷地利用権(配偶者居住権の対象となっている建物の敷地)」についても適用することが可能です。これは税務上の大きなメリットと言えます。
特例適用の主な要件(配偶者の場合)
- 亡くなった方の居住用だった宅地であること。
- 配偶者がその宅地等に係る敷地利用権を取得すること。
- 相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月後)まで、その権利を有し、かつその建物に住み続けていること。
配偶者がこれらの要件を満たせば、敷地利用権の評価額が大幅に圧縮され、相続税の負担を大きく軽減することができます。
例えば、評価額3,000万円の敷地利用権であれば、80%減額で600万円として計算できるのです。配偶者居住権の活用を検討する際には、この小規模宅地等の特例とセットで考えることが非常に重要になります。
知っておくべき配偶者居住権のデメリット

ここまで主にメリットの側面から解説してきましたが、物事には必ず裏表があります。配偶者居住権は万能の制度ではなく、安易に設定すると「こんなはずではなかった」と後悔に繋がりかねないデメリットも存在します。設定を検討する際は、以下の点を必ずご家族全員で共有し、慎重に判断してください。
配偶者居住権の主なデメリットと対策
| デメリットの内容 | 具体的な説明とリスク | 考えられる対策 |
|---|---|---|
| ① 資産価値・換金性がない | 権利の売却や譲渡、担保設定ができないため、将来まとまったお金が必要(例:介護施設への入居)になった際、自宅を売却して資金に充てることができません。 | 権利設定時に、将来のライフプランを見据え、十分な金融資産を配偶者が相続できるよう遺産分割を調整する。 |
| ② 利用の制約が多い | 大規模なリフォームや増改築、建物の用途変更などを行うには、所有権を持つ人(子など)の承諾が必須です。所有者との関係性次第では、希望通りに住環境を改善できない可能性があります。 | 遺言書や遺産分割協議書に、修繕や改築に関する取り決めを可能な範囲で明記しておく。 |
| ③ 費用負担が曖昧になりやすい | 建物の固定資産税の納税義務者は所有者ですが、民法上、居住権者は通常の必要費(小規模な修繕費など)を負担する義務があります。この分担が曖昧だとトラブルの原因になります。 | 遺産分割協議書などで、固定資産税や将来発生しうる修繕費の負担割合を明確に定めておく。 |
| ④ 所有者との関係悪化リスク | 設定当初は良好な親子関係でも、子の結婚や転勤など、将来の環境変化で関係が悪化しないとは限りません。関係が悪化すると、前述の利用の制約や費用負担の問題が深刻化する恐れがあります。 | 権利のメリット・デメリットを家族全員で深く理解し、将来にわたって協力体制を築けるか、冷静に話し合う。 |
これらのデメリットを理解した上で、それでもなおメリットが大きいと判断できる場合にのみ、設定を検討することが、円満な相続への道筋と言えるでしょう。
配偶者居住権は配偶者死亡により消滅
これは制度の根幹をなす非常に重要なルールですので、改めて強調します。配偶者が亡くなった時点で、その方が有していた配偶者居住権は、特別な手続きなく自動的に消滅します。
権利が消滅すると、どうなるのでしょうか。それは、これまで配偶者居住権という形で制限されていた建物の所有権が、完全な形で所有者のもとに戻ることを意味します。あたかも、建物を覆っていたヴェールが取り払われるようなイメージです。
これにより、建物の所有権を相続していた人(例えば子)は、その時点から建物を100%自由に扱うことができるようになります。具体的には、
- 自分でその家に住む
- 第三者に売却する
- 賃貸に出す
- 取り壊して更地にする
といった選択が、誰の制約も受けずに行えるようになるのです。この際、権利の消滅にあたって、所有者から元々の配偶者の相続人(子など)に対して、何らかの金銭の支払いや法的な手続きが発生することは一切ありません。
「配偶者の死亡」という事実をもって、自動的に権利が消え、所有権が本来の姿に戻る、とシンプルに理解してください。この点が、次の二次相続対策にも繋がります。
配偶者居住権が二次相続に与える影響

配偶者居住権は、残された配偶者の生活を守るだけでなく、長期的な視点で見ると「二次相続」対策としても非常に有効な選択肢となり得ます。
「二次相続」とは、ご夫婦のうち、先に亡くなった方の相続(一次相続)の後、残された配偶者が亡くなった際に発生する相続のことです。一般的に、一次相続では「配偶者の税額軽減」という強力な特例が使えるため、相続税の負担は比較的軽いことが多いです。
しかし、二次相続ではその特例が使えず、また財産が配偶者に集中しているため、一次相続よりもはるかに高額な相続税が発生しやすいという特徴があります。
ここで配偶者居住権が効果を発揮します。一次相続の際に、配偶者が取得する財産を「自宅の所有権」ではなく「配偶者居住権」にしておくことで、二次相続の課税対象となる財産そのものを減らすことができるのです。
二次相続対策としての仕組み
- 一次相続:配偶者は「配偶者居住権」(評価額は所有権より低い)を取得。子は「負担付の所有権」を取得。
- 配偶者の死亡:配偶者居住権は消滅し、相続財産にはなりません。
- 二次相続:配偶者が所有していた預貯金などだけが課税対象となる。子は負担の取れた完全な所有権を(相続税負担なく)手に入れる。
例えば、評価額5,000万円の自宅所有権を配偶者が相続すれば、二次相続ではその5,000万円が丸々課税対象になります。一方、評価額2,000万円の配偶者居住権を相続した場合、二次相続の際にはこの2,000万円は課税対象から消えてなくなります。
この差額3,000万円分だけ、二次相続の課税財産を圧縮できる可能性があるのです。このように、配偶者居住権は、ご家族全体の相続税負担を長期的に見て最適化するための、戦略的な一手となり得るのです。
配偶者居住権についてよくあるご質問FAQ
-
配偶者居住権と使用貸借はどう違うのですか?
-
配偶者居住権は法律で保護された強力な権利ですが、使用貸借は当事者間の契約に過ぎず、法的な保護が弱いという違いがあります。登記もできる配偶者居住権の方が、居住の安定性は格段に高いと言えます。
-
配偶者居住権を設定した場合、固定資産税は誰が払うのですか?
-
納税義務者は建物の所有者です。ただし、居住権者も通常の必要費を負担する義務があるため、当事者間で負担割合を話し合って決めておくことがトラブル回避のために重要です。
-
配偶者居住権を途中でやめることはできますか?
-
居住権者からの申し出や、所有者との合意によって権利を消滅させることは可能です。ただし、一度権利を放棄すると元に戻すことはできないため、慎重な判断が求められます。
-
内縁の妻でも配偶者居住権は取得できますか?
-
残念ながら、配偶者居住権は法律上の婚姻関係にある配偶者が対象です。そのため、事実婚や内縁関係の場合は取得することができません。事前の遺言などで対策を講じる必要があります。

お疲れ様でした!配偶者居住権が、ただ「住める」だけの単純な権利ではないことがお分かりいただけたかと思います。税金の話や二次相続のことまで考えると、ご家族の将来設計に大きく関わってくる重要な選択肢です。
最後に、この記事のポイントをしっかりおさらいして、知識を定着させましょう。
まとめ:配偶者居住権相続財産評価対象外ではないと理解しよう
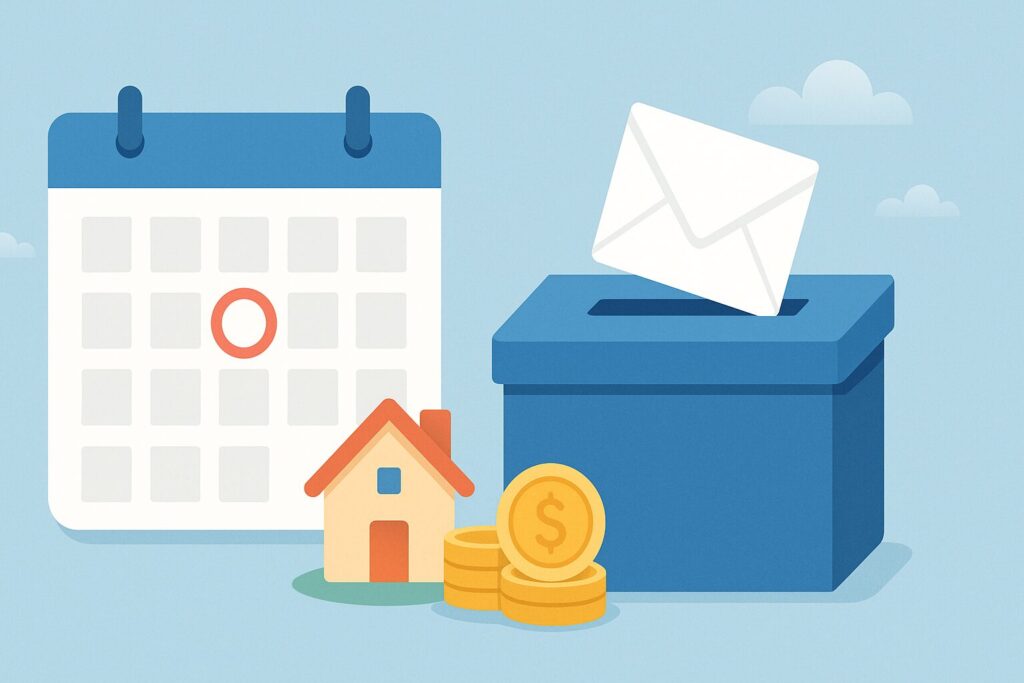
- 配偶者居住権相続財産評価対象外という考えは誤解
- 配偶者居住権は相続税の課税対象となる財産権である
- 遺産分割協議や遺言によって取得する相続財産の一つ
- 権利の価値は国税庁の定める計算式で評価する
- 国税庁の「評価明細書」が計算シートとして利用できる
- 第三者に対抗するためには配偶者居住権の登記が不可欠
- 配偶者居住権は一身専属権であり譲渡や売却はできない
- 自宅所有権より評価額を抑えられ預貯金を多く相続できる可能性がある
- 遺産総額が基礎控除を超えれば相続税申告が必要
- 敷地利用権には小規模宅地等の特例を適用できる場合がある
- 資産価値がなく自由にリフォームできないなどのデメリットもある
- 固定資産税などの費用負担は所有者と協議が必要
- 配偶者の死亡によって権利は自動的に消滅する
- 消滅した権利は二次相続の課税対象にならない
- 二次相続の節税対策として有効なケースがある
▼あわせて読みたい関連記事▼
【相続税いくらから親子でかかる?】専門家が相続税の早見表や基礎控除・計算方法をわかりやすく解説
遺言書書き方法務局で正確に遺言を残す方法|失敗しない書き方と注意点
不動産の評価額はどう決まる?相続や売買で損しないための全知識

お気軽にご相談ください
相続は100人いれば、100通り
唯一無二の最適な相続をご提案いたします
CONTACT
専門家やえさん

- 専門家やえさん
-
堀川 八重(ほりかわ やえ)
大阪不動産・FPサービス株式会社 代表
15年以上にわたり1,500組を超えるご家族の相続や不動産のお悩みに、専門家として寄り添ってまいりました。私の信条は、法律や数字の話をする前に、まずお客様ご家族の歴史や言葉にならない想いを丁寧に「聞く」こと。信頼できる各分野の専門家チームと共に、皆様が心から安心できる最善の道筋をオーダーメイドでご提案します。一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。
最新の投稿
 お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説
お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説 相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説
相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説 お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例
お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例 お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説
お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説