「相続」と聞くと、何から手をつけていいか分からなくなってしまいますよね。特にたくさんの書類を集めて手続きするのは、本当に大変です。私も最初は「不動産相続って何だか難しそう…」と思っていました。
例えば、父が死亡して土地の名義変更をするには何が必要ですか?といった疑問や、そもそも遺産相続の名義変更に必要な書類は?という基本的なことから、法務局で名義変更をするにはどんな書類が必要ですか?と具体的な手続きまで、気になることはたくさんあるかと思います。
不動産相続の名義変更を自分で行う場合、まずは相続登記の必要書類を法務局へ提出しますが、その必要書類を一覧表で確認しながら自分で集めるのは一苦労です。
法務局の相続登記申請書をダウンロードして、ひな形を参考に作成するのも骨が折れますし、「結局、相続手続きは司法書士と税理士どちらが頼んだほうがいいですか?」と専門家選びで迷うことも。
この記事で、そんなお悩みをスッキリ解決していきましょう!
この記事のポイント
- 不動産相続の名義変更に必要な書類が一覧でわかる
- 自分で相続登記を行う際の具体的な手順を理解できる
- 法務局の申請書ダウンロード先や書き方のポイントがわかる
- 専門家に依頼する場合の判断基準が明確になる

こんにちは!終活・相続・不動産相続の専門家、やえです。
相続手続きは、人生で何度も経験することではないので、戸惑うのは当然ですよ。特に不動産の名義変更は、専門用語も多くて大変に感じるかもしれません。
でも、一つ一つの手順をしっかり理解すれば、ご自身で進めることも可能です。この記事で、あなたの不安を安心に変えるお手伝いをさせてくださいね。
目次
不動産相続名義変更、法務局の必要書類

遺産相続の名義変更に必要な書類は?
遺産相続で不動産の名義変更、いわゆる「相続登記」を行うには、いくつかの公的な書類を集める必要があります。誰が相続するかによって必要書類は少し変わってきますが、基本となるのは「誰が亡くなって、誰が法律上の相続人なのか」を証明する一連の書類です。
具体的には、亡くなった方(被相続人)の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本や、相続人全員の現在の戸籍謄本などが必要になります。
これらを揃えることで、法務局は「この不動産は、間違いなくこの相続人に名義変更して良いのだな」と確認できるわけですね。最初は大変に感じるかもしれませんが、一つずつ着実に集めていきましょう。
父が死亡、土地名義変更に何が必要?
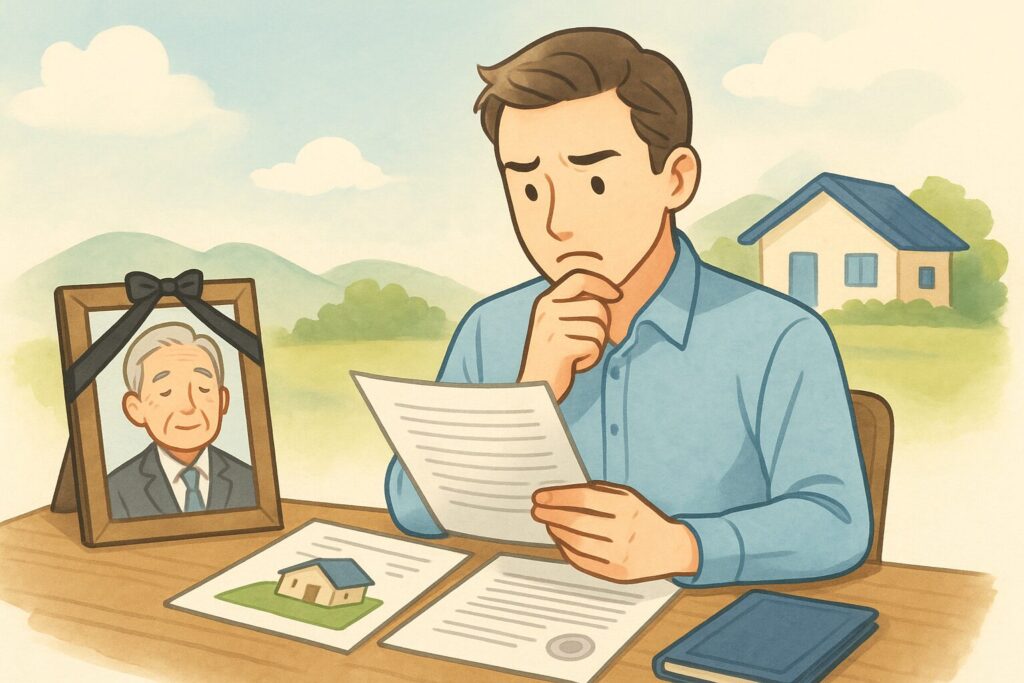
例えば「父が亡くなって、実家の土地の名義を自分に変更したい」という、具体的なケースで考えてみましょう。この場合、まずはお父様(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本一式が必要です。これでお父様に他の相続人(例えば、前妻の子など)がいないかを確認します。
次に、あなた(相続人)を含む、相続人全員の現在の戸籍謄本と印鑑証明書、そして住民票(新しく名義人になる方のみ)を用意します。さらに、相続人全員で「この土地は、長男のあなたが相続します」と合意したことを証明する「遺産分割協議書」を作成するのが一般的です。これらの書類を揃えて、法務局へ登記申請を行う流れとなります。
【ポイント】遺産分割協議書とは?
相続人が複数いる場合に、「誰が」「どの財産を」「どれくらいの割合で」相続するのかを話し合って決めた内容をまとめた書類です。相続人全員が署名し、実印を押す必要があります。この書類があることで、法定相続分とは異なる割合での相続登記が可能になります。
不動産相続の名義変更を自分で行う
「費用を抑えたいから、不動産相続の名義変更を自分でやってみたい」と考える方も多いでしょう。結論から言うと、ご自身で手続きすることは可能です。ただし、それなりの時間と手間がかかることは覚悟しておく必要があります。
主な流れは、①必要書類の収集 → ②遺産分割協議書の作成 → ③登記申請書の作成 → ④法務局への申請、となります。
特に①の戸籍謄本集めは、本籍地が遠方にある場合など、郵送での取り寄せに時間がかかることも。
また、書類に不備があると法務局から修正の連絡(補正といいます)があり、何度も足を運ぶことになる可能性もあります。それでも、一つ一つクリアしていく達成感は大きいかもしれませんね。
相続登記を自分で進める際の必要書類

相続登記を自分で進める場合、先ほども触れましたが、特に重要なのが戸籍謄本一式です。亡くなった方の「出生から死亡まで」の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本をすべて集める必要があります。これは、他に相続人がいないことを証明するために不可欠です。
その他、相続人全員の現在の戸籍謄本や、不動産の名義人になる方の住民票、そして登記申請の際に税金(登録免許税)を計算するために必要な「固定資産評価証明書」も市区町村役場で取得します。
これらの書類は、相続の状況(遺言の有無、相続人の数など)によって少しずつ変わるため、事前に法務局の相談窓口で確認しておくと安心です。
注意点:相続登記の義務化
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。過去の相続でまだ登記が済んでいない不動産も対象となるため、注意が必要です。(参照:法務省「相続登記の申請義務化について」)
相続登記の必要書類は一覧表で確認
相続登記の必要書類は多岐にわたるため、一覧表でチェックしながら進めるのがおすすめです。ここでは、最も一般的な「遺産分割協議」によって相続する場合の必要書類をまとめてみましょう。
| 書類の種類 | 取得する場所 | 簡単な説明 |
|---|---|---|
| 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本等 | 本籍地の市区町村役場 | 他に相続人がいないかを確認するために全て必要です。 |
| 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票) | 最後の住所地の市区町村役場 | 登記簿上の住所と亡くなった方の繋がりを証明します。 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 各相続人の本籍地の市区町村役場 | 相続人が現在も生存していることを証明します。 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 各相続人の住所地の市区町村役場 | 遺産分割協議書に押した印鑑が本人のものだと証明します。 |
| 不動産を相続する方の住民票 | その方の住所地の市区町村役場 | 新しい名義人として登記簿に住所を記載するために必要です。 |
| 固定資産評価証明書 | 不動産所在地の市区町村役場(東京23区は都税事務所) | 登録免許税という税金を計算するために使います。 |
| 遺産分割協議書 | 自分で作成 | 相続人全員が署名し、実印を押印します。 |
| 登記申請書 | 自分で作成 | 法務局のウェブサイトからひな形をダウンロードできます。 |
これはあくまで一例です。事案によっては他の書類が必要になることもあります。

戸籍集めは相続手続きの第一関門です。特に、亡くなった方が転籍を繰り返していると、あちこちの役所に請求が必要になり時間がかかります。
郵送での請求も可能ですが、定額小為替の準備など少し手間がかかることも。時間に余裕をもって、計画的に進めるのが成功の秘訣ですよ。
焦らず、一つずつクリアしていきましょう。
法務局での不動産相続名義変更と必要書類
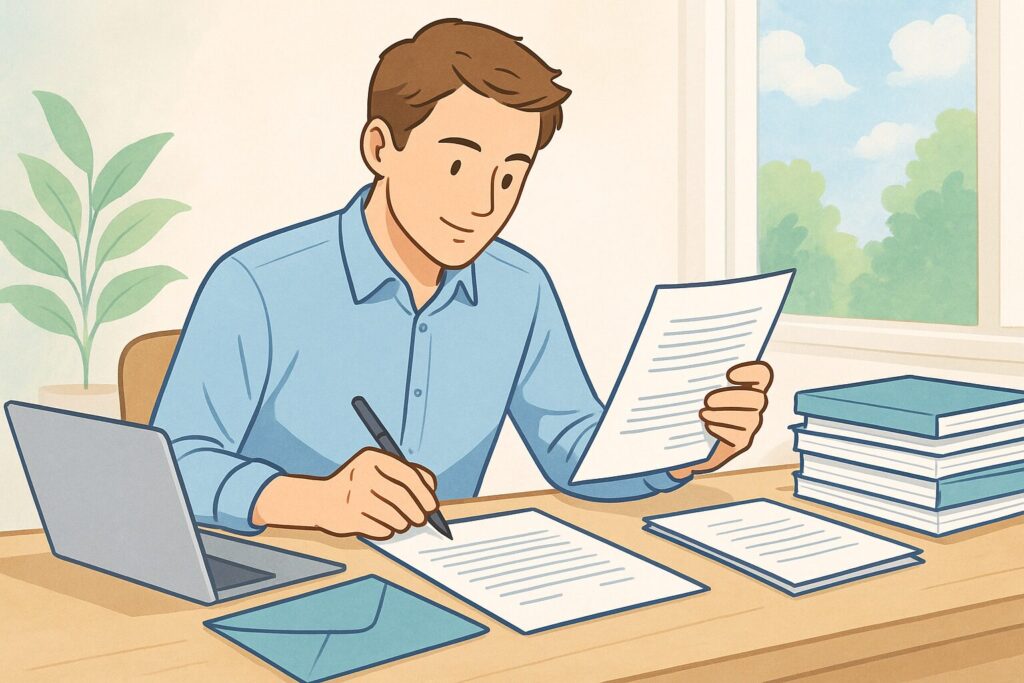
法務局で名義変更、どんな書類が必要?
前述の通り、法務局へ不動産の名義変更(相続登記)を申請する際には、戸籍謄本一式や遺産分割協議書、固定資産評価証明書などを揃えて提出する必要があります。
法務局の担当官は、これらの提出された書類だけを元に、登記の審査を行います。つまり、書類が全て、と言っても過言ではありません。
法務局で名義変更をするにはどんな書類が必要ですか?と窓口で質問する前に、まずはご自身のケース(法定相続か、遺産分割か、遺言か)を整理し、それに合った書類を事前に調べておくと、相談もスムーズに進みますよ。
法務局で名義変更を自分で行う流れ

法務局で名義変更を自分で行う場合、大まかな流れは以下のようになります。
- 事前準備:登記簿謄本を取得し、不動産の正確な情報を確認します。
- 書類収集:市区町村役場などで、戸籍謄本や住民票などを集めます。
- 書類作成:遺産分割協議書や登記申請書を作成します。
- 申請:管轄の法務局へ、集めた書類と作成した申請書を提出します。郵送でも申請可能です。
- 補正対応:書類に不備があれば、法務局から連絡があるので指示に従い修正します。
- 完了:申請から1~2週間ほどで手続きが完了し、登記識別情報通知書(権利証)が発行されます。
最近では、法務局も予約制の相談窓口を設けていることが多いです。いきなり訪問するのではなく、事前に電話などで予約をしてから相談に行くことをお勧めします。
法務局の相続登記申請書ダウンロード
登記申請書は、法務局のウェブサイトから書式をダウンロードして作成するのが便利です。手書きでも問題ありませんが、パソコンで作成した方が修正も簡単ですし、見た目もきれいに仕上がります。
法務局のサイトには、様々なケースに応じた申請書の様式(テンプレート)と記載例が用意されています。ご自身の状況に最も近いものを選んで、参考にしながら作成しましょう。
▼法務局の公式サイトはこちら
申請書の様式や記載例が豊富に掲載されています。まずは一度、目を通してみることをお勧めします。
→ 法務局:不動産登記の申請書様式について
法務局の相続登記、必要書類のひな形
申請書だけでなく、遺産分割協議書や相続関係説明図など、自分で作成する必要がある書類についても、インターネットで検索するとたくさんのひな形(テンプレート)が見つかります。法務局のサイトにも、相続関係説明図の様式が用意されています。
ただし、インターネット上のひな形は、あくまで一般的なケースを想定したものです。ご自身の家族構成や財産の状況によっては、内容を修正したり、条項を追加したりする必要があります。
ひな形をそのまま使うのではなく、ご自身の状況に合わせて適切にカスタマイズすることが大切です。不安な場合は、専門家に相談するのが確実です。
相続は司法書士と税理士どちらに頼む?
相続手続きを進める中で、「専門家に依頼したいけれど、司法書士と税理士、どちらに頼めばいいの?」という疑問を持つ方もいらっしゃいます。これはそれぞれの専門分野の違いを理解するとスッキリします。
| 専門家 | 主な業務内容 | どんな時に依頼する? |
|---|---|---|
| 司法書士 | 不動産の名義変更(相続登記)、遺産分割協議書の作成、裁判所への提出書類作成など | 不動産の名義変更手続きを丸ごとお願いしたい時。 |
| 税理士 | 相続税の計算と申告、生前の相続税対策(節税)など | 相続財産が多く、相続税の申告が必要な時。 |
つまり、不動産の名義変更(相続登記)の専門家は司法書士、相続税の専門家は税理士、と覚えておくと分かりやすいです。相続税の申告が必要かどうか分からない、という段階であれば、まずは税理士に相談してみるのが良いかもしれませんね。
不動産相続名義変更についてよくあるご質問FAQ

ここでは、不動産の名義変更に関してよくいただく質問にお答えします。
-
登記に必要な戸籍謄本などの書類に有効期限はありますか?
-
相続登記の申請で法務局に提出する戸籍謄本や住民票、印鑑証明書には、有効期限はありません。発行から3ヶ月以上経過していても使用できます。
ただし、金融機関での手続きなど、提出先によっては3ヶ月や6ヶ月以内のものを求められることがあるので注意が必要です。
-
提出した戸籍謄本などの原本は返してもらえますか?
-
はい、返してもらえます。申請時に「原本還付」の手続きを行えば、登記完了後に原本を返却してもらえます。手続きは、提出したい書類のコピーを取り、そのコピーに「原本に相違ありません」と記入して署名・押印するだけです。
戸籍一式については、「相続関係説明図」を提出すれば、コピーなしで原本を返却してもらえます。
-
登録免許税はいくらかかりますか?
-
相続登記にかかる登録免許税は、不動産の固定資産税評価額の0.4%です。例えば、評価額が2,000万円の不動産であれば、8万円となります。この税額分の収入印紙を購入し、申請書に貼り付けて納付します。

相続登記は義務化されましたが、手続きが複雑でご自身で進めるのが難しいと感じたら、無理せず専門家を頼るのも賢い選択です。
特に相続人が多かったり、遺産分割で揉めていたりするケースでは、専門家の介入でスムーズに解決することも。
費用はかかりますが、時間と精神的な負担を大きく減らせるメリットがありますよ。
不動産相続名義変更、法務局の必要書類まとめ
最後に、この記事の要点をリストで確認しましょう。
- 不動産相続時の名義変更を「相続登記」という
- 2024年4月1日から相続登記は義務化された
- 期限は相続を知った日から3年以内で怠ると過料の可能性も
- 自分で手続きは可能だが時間と手間がかかる
- 基本となる必要書類は戸籍謄本一式
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要
- 遺産分割協議を行う場合は遺産分割協議書と印鑑証明書も用意
- 書類は市区町村役場や法務局で取得または自分で作成する
- 法務局のサイトで書式をダウンロードできる
- 書類に不備があると法務局から補正の指示がある
- 登記申請は管轄の法務局の窓口か郵送、オンラインで行う
- 登記の専門家は司法書士、税金の専門家は税理士
- 提出する証明書に有効期限はない
- 原本還付の手続きをすれば書類は返却される
- 登録免許税は固定資産税評価額の0.4%
▼あわせて読みたい関連記事▼
- 相続権どこまで?法定相続人の範囲と順位を図解でやさしく解説
- 不動産の評価額はどう決まる?相続や売買で損しないための全知識
- 相続税はいつまでに払う?期限や手続きを徹底解説
- 相続した実家、売却か賃貸か?判断ミスで損しないための全知識
- 終活とは?意味と始め方をわかりやすく解説|初心者が損しない準備法

お気軽にご相談ください
相続は100人いれば、100通り
唯一無二の最適な相続をご提案いたします
CONTACT
専門家やえさん

- 専門家やえさん
-
堀川 八重(ほりかわ やえ)
大阪不動産・FPサービス株式会社 代表
15年以上にわたり1,500組を超えるご家族の相続や不動産のお悩みに、専門家として寄り添ってまいりました。私の信条は、法律や数字の話をする前に、まずお客様ご家族の歴史や言葉にならない想いを丁寧に「聞く」こと。信頼できる各分野の専門家チームと共に、皆様が心から安心できる最善の道筋をオーダーメイドでご提案します。一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。
最新の投稿
 お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説
お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説 相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説
相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説 お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例
お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例 お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説
お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説






