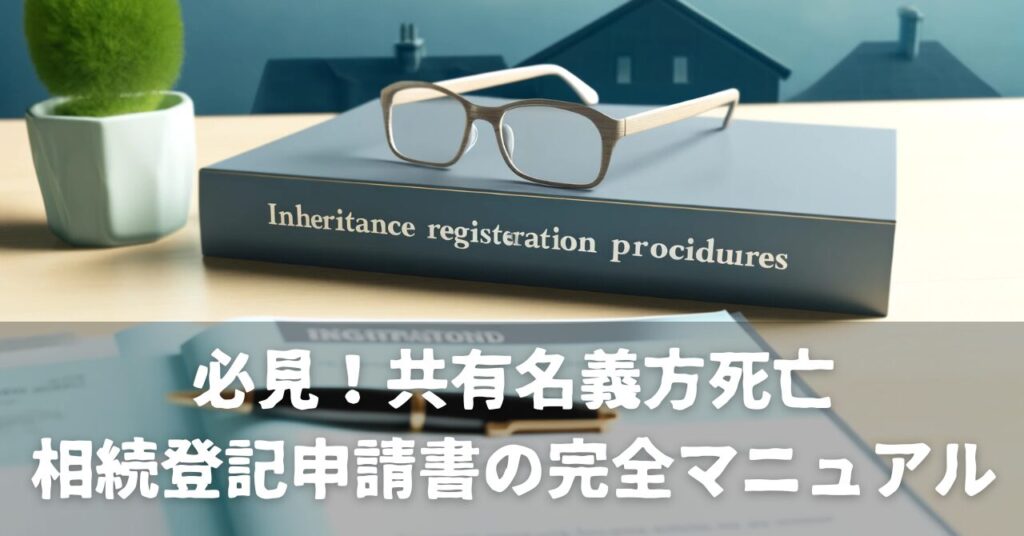
相続が発生した際、共有名義の不動産について適切な登記を行うことは重要です。本記事では、「共有名義方死亡相続登記申請書書き方」をはじめ、さまざまなシナリオにおける登記申請書の書き方を詳しく解説します。
登記申請書共有名義の書き方から、登記申請書の持分書き方、さらには登記申請書を手書きで記入する方法、複数の不動産に対する登記の申請方法に至るまで、必要なステップを一つずつ丁寧に説明します。
また、相続登記申請書のダウンロード方法や、申請書の綴じ方、相続人が一人の場合の特別な考慮点も解説します。これにより、相続登記の手続きが初めての方でも迷うことなく進められるようになります。さぁ、正確で効率的な登記申請を目指しましょう。
この記事のポイント
- 共有名義の不動産の相続登記申請書の基本的な書き方
- 各共有者の持分とその記載方法
- 必要な添付書類とその準備方法
- 手書きとタイプ入力による申請書の記入指南
一般社団法人終活協議会認定資格 終活ガイド・心託コンシェルジュのお役立ちブログです。終活についてのご相談やサポートサービスをご提供しています。生涯笑顔で過ごせる環境づくりをお手伝いさせていただいております。
・生活のサポートを含むサービス
『入院、介護施設入居に伴う身元保証(身元引受け)連帯保証』のご相談
・おひとりさまや、もしもの時に家族に負担をかけたくないあなたに
『葬儀、連絡、お墓、手続き、遺品整理、遺言、相談、公正証書の作成』のご相談
・今は元気だが歳を重ねても不安にならないために
老後資金や年金、貯金の不安のご相談、万一認知症やお体や生活環境に不自由が発生し、デイサービスや老人施設が必要となった際の選び方や準備金、入所の問題
上記のように簡単に気になる事を並べただけでもたくさんあり、終活は多岐にわたりますのでその方のご事情によって様々です。
私たちは、医療、介護、法律、金融をはじめお客様の様々なご事情に対応できる専門家チームが一丸となりお客様に寄り添いながら様々なご事情に合わせた適正なサービスをご提供し、生涯笑顔で過ごせる環境づくりをお手伝いをしています。お気軽にご相談ください。
終活・相続 お悩みご相談事例
- 相続人に長い間連絡が取れない人がいる
- 相続人の仲が悪い
- 今依頼している弁護士・税理士等が親身に対応してくれない
- 財産が何があるのかよくわからない
- 再婚している
- 誰も使っていない不動産がある
- 子供がいない
- 相続する人に『障害』『未成年』『認知』等の人がいる
- 誰にも相談せずに作った遺言がある
- 相続税がかかるのか全く分からない
他にもたくさんお気軽に相談いただいて解決しております。
『もっと早く相談すればよかった』とのありがたいお声をたくさんいただいております。

終活・相続
お気軽にご相談ください
- 何をしたら良いのかわからない
- エンディングノート・終活
- 老後資金・自宅売却の時期
- 資産活用対策・医療・介護
- 施設選び・生命保険・相続対策
- 遺言・葬儀・お墓・相続登記
- 相続発生後の対応や処理方法
- 信用できる士業への安全な橋渡し
その他なんでもお気軽にご相談ください!
営業時間 10:00-18:00(日・祝日除く)
共有名義方死亡相続登記申請書書き方の基本
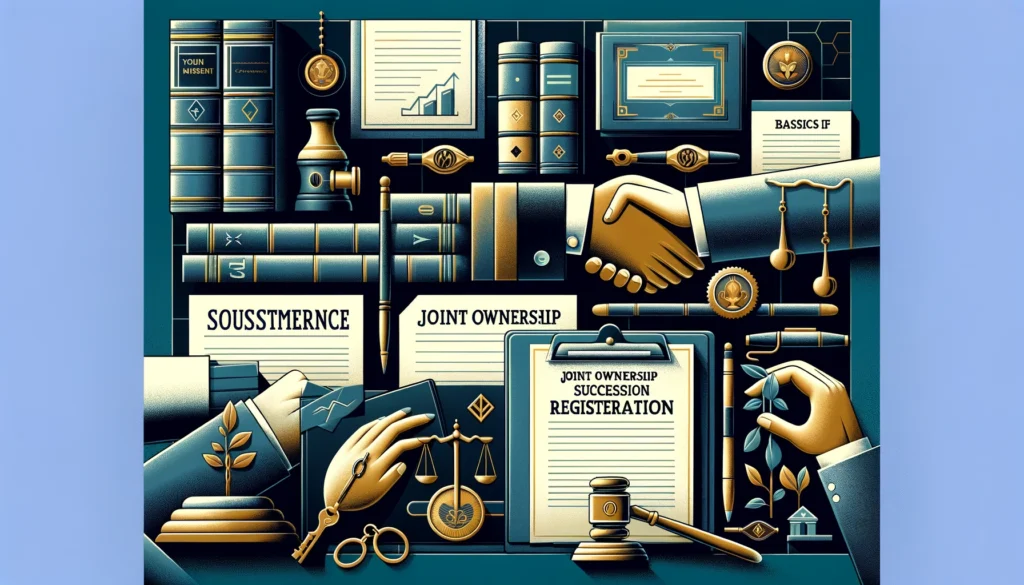
登記申請書 共有名義 書き方
共有名義の不動産における登記申請書の書き方について解説します。共有名義の不動産登記は、複数の所有者が関与しているため、一般的な単独所有の登記よりも注意が必要です。ここでは、共有名義の登記申請書の書き方をわかりやすく説明します。
まず、登記申請書には、全共有者の情報を正確に記載する必要があります。それには、各共有者の氏名、住所、持分比率を明記することが不可欠です。たとえば、不動産を二人で所有している場合、一人が持分の2/3、もう一人が1/3を持っているとします。この持分比率は登記申請書に「持分2/3、持分1/3」として記入します。
次に、遺産分割協議書や死亡証明書など、申請に必要な添付書類も準備することが必要です。これらの書類は、登記の根拠となる重要なものですから、確実に準備しましょう。
さらに、登記申請書は手書きでもタイプ入力でも可能ですが、読みやすさを考慮してクリアに記載することが大切です。もし手書きで申請する場合は、誤字脱字のないように慎重に記入してください。
最後に、登記申請を行う際は、登記所によって細かな書式や要求される書類が異なることがありますので、事前に最寄りの登記所に確認することをお勧めします。これにより、申請時の手間や時間のロスを防ぐことができます。
共有名義の登記は複雑に思えるかもしれませんが、正しい手順と正確な書類でスムーズに進めることが可能です。不明点があれば専門家に相談するのも良いでしょう。
登記申請書 書き方 手書き

手書きで登記申請書を作成する際には、読みやすさと正確さが非常に重要です。手書きであっても、フォーマットを正確に守り、すべての情報を明確に記入する必要があります。ここでは、初めて登記申請書を手書きする方に向けて、基本的な書き方を説明します。
まず、必要な項目をすべて記載することが基本です。具体的には、申請者の氏名、住所、登記する不動産の所在地及び地番などを正確に記入します。また、申請する登記の種類(例えば、所有権移転や抵当権設定など)もはっきりと書かれていなければなりません。
手書きの場合、筆跡がはっきりしていることが求められます。ぼやけたり、かすれたりすると、情報が正確に伝わらない可能性があるため、ブラックインクのボールペンを使用して、はっきりとした文字で記入しましょう。書き間違えた場合は、修正液や修正テープできれいに修正してください。訂正部分には、その横に訂正印を押し、改ざん防止のための措置を施します。
さらに、全ページにページ数を記載し(例:「1/3ページ」)、各ページに署名または印鑑を押すことを忘れないでください。これは文書の一貫性と真正性を保証するために重要です。
最後に、登記申請書には添付する書類の一覧も記載する必要があります。これにより、申請書と一緒に提出する書類が一目でわかるようになり、手続きの進行がスムーズになります。
これらのポイントを押さえて、丁寧に手書きで申請書を作成することで、ミスを減らし、手続きの遅延を防ぐことができます。手書きでの記入は時間がかかる場合がありますが、その分、内容を確認しながら進めることができるので、正確な申請が可能です。
登記申請書 持分 書き方

登記申請書における持分の書き方は、不動産の共有者がいる場合に特に重要です。正確に持分を記入することで、各共有者の権利が明確にされ、将来のトラブルを避けることができます。ここでは、初めて登記申請書を記入する方にも理解しやすいように、持分の記載方法を具体的に説明します。
まず、登記申請書の「権利部分」または「持分欄」に、持分の割合を正確に記入する必要があります。たとえば、不動産を二人で共有しており、一方が3分の2、もう一方が3分の1の持分を有する場合、「持分3分の2」と「持分3分の1」と記述します。
この書き方のポイントは、持分が分数で表現されることが一般的であるという点です。たとえば、「50%」ではなく、「2分の1」と書くことが推奨されます。この分数表記は、不動産の共有割合を明確に示す上で法的な効力を持つため重要です。
持分を記入する際には、各共有者の名前とともに、それぞれの持分を隣接させて記入します。例えば、「田中太郎 持分3分の2、山田花子 持分3分の1」といった形です。これにより、誰がどのような割合で不動産を所有しているのかが一目で明確になります。
また、持分の記載に際しては、登記する不動産の所在地や地番も併記し、その不動産に対する正確な持分関係が文書上で認識できるようにすることが大切です。これは、登記内容の確認を行う登記官や将来的にこの情報を必要とする人々にとって、必要不可欠な情報となります。
登記申請書の持分の書き方を正確に行うことで、不動産の所有権関係が法的に保護され、すべての関係者にとってクリアな状態が保たれます。明瞭な持分記載は、共有不動産における権利関係を透明にし、将来の紛争を防ぐためにも重要です。
登記申請書 書き方 見本

登記申請書の書き方を理解するためには、具体的な見本が非常に役立ちます。ここでは、初めて登記申請書を書く方にも分かりやすく、基本的なフォーマットと共にポイントを説明します。
まず、登記申請書は主に所在地、登記の目的、申請人(相続人)の情報、添付書類などを記載する必要があります。これらの項目を明確に記入することで、登記申請の意図がはっきりと伝わります。
例えば、一般的な登記申請書の見本は以下のようになります:
- 所在地:
- 住所:東京都渋谷区恵比寿1-1-1
- 地番:渋谷区恵比寿町100番地
- 登記の目的:
- 所有権移転
- 申請人情報:
- 名前:山田太郎
- 住所:東京都渋谷区恵比寿2-2-2
- 関係:被相続人の長男
- 添付書類:
- 遺産分割協議書
- 被相続人の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
この見本に基づいて、申請書を作成する際には、各項目を具体的に、かつ正確に記入する必要があります。登記の目的を書く際には、具体的な登記の種類を明記し、「所有権移転」や「抵当権設定」などと書きます。また、申請人情報では、申請人が相続人である場合、「相続人」という言葉を入れ、その関係を示すとより明確になります。
添付書類の部分では、どの文書を添付するのかを具体的に列挙し、それらが申請内容を証明するためにどのように役立つのかを理解しておくことが重要です。これにより、申請の過程での疑問や不明点を事前に解消でき、スムーズな登記手続きが期待できます。
この見本を参考にしながら、自身の登記申請に必要な情報を適切に整理し、正確に記入することが成功への鍵です。
相続登記申請書 ダウンロードの手順
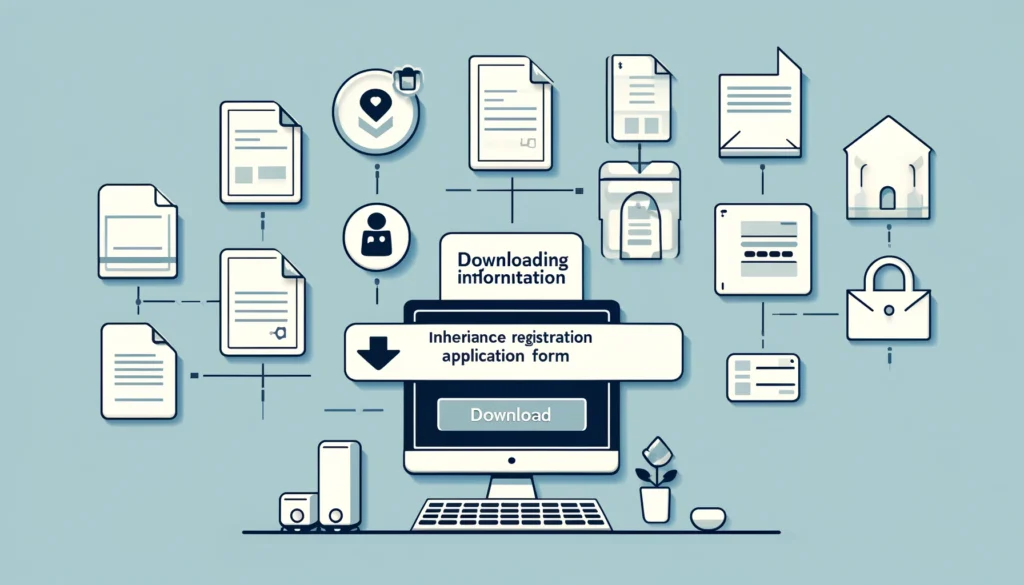
相続登記申請書のダウンロードは、インターネットを活用することで簡単に行えます。ここでは、具体的な手順を説明し、初めての方でも迷わずに進められるようにします。
まず、必要な申請書をダウンロードするためには、法務局の公式ウェブサイトまたは地元の市役所、区役所のウェブサイトを訪れることがスタートラインです。次に、サイト内の「登記・供託」セクションを探し、「相続登記関連フォーム」またはそれに類似するリンクをクリックします。
このリンクから、さまざまな登記申請書がリストアップされていますが、その中から「相続登記申請書」を選んでください。大多数のウェブサイトでは、申請書はPDF形式で提供されており、Adobe Readerやその他のPDFビューアがあれば、直接ダウンロードして開くことができます。
ダウンロード後は、ファイルを開いて内容を確認し、必要な情報を手書きまたはタイプ入力して記入します。記入例も同様にサイト上で提供されていることが多く、これを参考にしながら正確に情報を入力していくことが大切です。
最後に、申請書に必要な書類一覧を確認し、添付書類をそろえた後、所定の場所に提出します。提出先は通常、財産がある場所の管轄内の法務局または地方法務局になります。
この手順に沿って行えば、相続登記申請書のダウンロードから提出までスムーズに進めることができます。プロセスを始める前に、現在の登記情報を確認するために必要な書類も忘れずに準備してください。
登記申請書 複数の不動産 書き方

複数の不動産に対して一度に登記申請を行う場合、申請書の書き方には特に注意が必要です。ここでは、複数の不動産を対象とした登記申請書の記入方法について、わかりやすく解説します。
まず、登記申請書には、それぞれの不動産の登記情報が正確に記載されている必要があります。これには、不動産の所在地、地番、建物の有無などの基本情報が含まれます。また、各不動産ごとに登記の目的を明確にすることが重要です。例えば、一つの申請書に所有権移転と抵当権設定を記載する場合、どの不動産にどの権利が適用されるのかを明記する必要があります。
次に、申請書には各不動産の所有者の情報も正確に記入します。所有者が異なる場合、それぞれの所有者の住所と氏名を個別に記載し、どの不動産が誰の所有かをはっきりさせることが重要です。この部分に誤りがあると、登記が拒否される可能性があります。
各不動産に関する登記申請理由も個別に記入する必要があります。たとえば、相続による所有権移転の場合、相続人と被相続人の関係、死亡日、遺産分割の協議結果などが具体的に記載されるべきです。こうした詳細を各不動産ごとに記載することで、申請の目的と背景が明確になり、手続きがスムーズに進みます。
申請書には、必要に応じて添付書類の一覧も記載し、それぞれの不動産に関連する書類を綴じる順番を明記しておくことが助けになります。このように整理しておくことで、法務局の審査が迅速かつ正確に行われるため、登記の遅延やミスを避けることができます。
以上のように、複数の不動産に対する登記申請書の作成では、各不動産の情報を明確にし、それぞれの登記の理由と必要書類を正確に記載することが求められます。こうすることで、複雑な登記申請も一度に効率的に進めることが可能となります。
登記申請書 相続人 一人の場合

相続人が一人だけの場合、登記申請書の記入方法は他のケースと異なるポイントがいくつかあります。このシンプルな状況は、申請プロセスを大幅に簡略化することができ、特に初めてこの手続きを行う方にとっては、より理解しやすくなります。
まず、登記申請書に記載する相続人の情報は、被相続人の全財産について唯一の相続人としての名前、住所、生年月日を明記します。相続人が一人の場合、遺産分割協議書は必要ありませんが、代わりに単独相続を証明する書類を添付する必要があります。
次に、不動産の所在地、地番、権利内容などの詳細情報を正確に記入します。不動産が複数ある場合でも、全ての不動産を一人で相続することが確定しているため、各不動産項目を個別に記載することが重要です。
登記の目的を「相続による所有権移転」と明確にし、登記の原因となる被相続人の死亡日とその死亡による相続発生を記入します。この部分では、法定相続情報の正確な提供が求められるため、死亡証明書や除籍謄本などの公的書類のコピーを添付する必要があります。
最後に、すべての情報が記入された後、申請書に相続人本人の署名と印鑑を押し、必要に応じて印鑑証明書を添付します。この印鑑証明書は、登記を行う地域の公証役場で発行されたものを使用することが一般的です。
こうした手順に従って、登記申請書を法務局に提出することにより、相続登記の手続きを完了させることができます。相続人が一人の場合は、手続きの複雑さが減少するため、スムーズかつ迅速に登記を進めることが可能です。
共有名義方死亡後の相続登記申請の詳細
相続登記申請書 綴じ方と提出ガイド

相続登記申請書の綴じ方と提出に関するガイドは、手続きを円滑に進めるために非常に重要です。綴じ方が適切でない場合、法務局での受理が遅れることがあります。ここでは、相続登記申請書の正しい綴じ方と提出手順をわかりやすく解説します。
まず、相続登記申請書とその添付書類は、クリアファイルやファイルフォルダーに整理して提出します。法務局では通常、A4サイズの書類が基準ですので、すべての書類をこのサイズに合わせることが重要です。書類は左側を綴じる形式で提出するのが一般的で、右側が開くようにしてください。
相続登記申請書のページ数が多い場合、または添付書類が多数ある場合は、目次を作成して書類の先頭に置くと良いでしょう。これにより、法務局の担当者が必要な書類を迅速に見つけることができ、手続きがスムーズに進みます。
書類を綴じる際は、プラスチック製のバインダークリップやファスナーを使用することをおすすめします。金属製のステープラーは使用しないでください。金属製のステープラーを使用すると、書類が痛む原因になり、また取り外しが困難になることがあります。
書類提出の際には、受付番号が記載された受付証を受け取ることを忘れないでください。この受付証は、申請の進行状況を確認する際や、何らかの問題が発生したときに重要な役割を果たします。
以上のように、相続登記申請書の綴じ方と提出方法に注意を払うことで、手続きの遅延を避け、より迅速に登記を完了させることが可能です。いずれにしても、書類の取り扱いには慎重を期し、事前に法務局の指示や規定を確認することが望ましいです。
不動産の持分に関する相続手続き

不動産の持分相続は、特に共有名義の場合、複雑な手続きが伴うことが多いです。ここでは、不動産の持分に関する相続手続きの基本的な流れと注意点を簡潔に解説します。
まず、不動産の持分相続においては、故人が持っていた持分が正確に何分の何であるかを確認することが最初のステップです。たとえば、故人が不動産を他の共有者と共に所有していた場合、その持分が2分の1や3分の1などであるかを把握する必要があります。
次に、遺産分割協議を行います。これは相続人全員が集まり、どの相続人がどのように持分を引き継ぐかを決める大切なプロセスです。この協議を通じて、持分の引き継ぎがスムーズに進むよう、具体的な分配比率を合意し、遺産分割協議書に記載します。
持分の相続が決定した後は、相続登記を行う必要があります。これには、遺産分割協議書を基にして、法務局に登記の申請を行います。登記申請には、故人の戸籍謄本や死亡証明書、相続人全員の印鑑証明書が必要です。持分の相続には特に注意が必要で、誤って全体の所有権移転を申請してしまわないよう、登記申請書の記載には細心の注意を払いましょう。
不動産の持分相続手続きにおいては、様々な法的な複雑性が伴いますので、不明点がある場合は専門家に相談することが推奨されます。特に、持分の取り扱いに誤りがあると、後日大きなトラブルの原因となることもありますので、登記手続きの完了をもって、手続きがすべて終了したと安心するのではなく、定期的な確認が必要です。
以上のステップを踏むことで、不動産の持分に関する相続手続きをより安全かつ効率的に進めることが可能です。相続は感情的な問題も絡むため、相続人間のコミュニケーションを保ちながら進めることが、争いを避ける鍵となります。
共有名義の不動産相続時の注意点
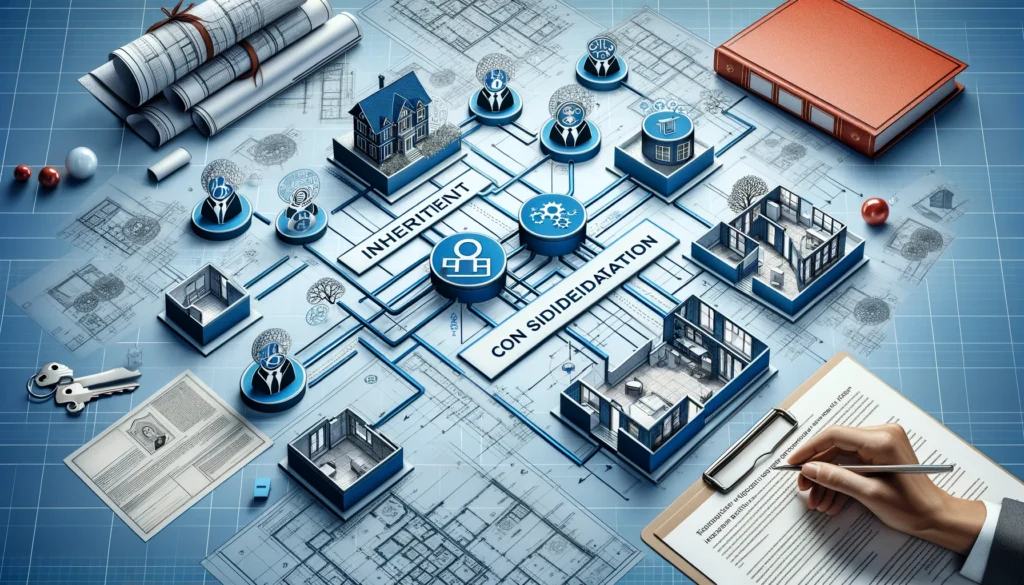
共有名義の不動産相続は、他の相続と比較して特に注意が必要です。この場合、故人が持っていた不動産の持分が正確にどのように相続されるかが問題となります。以下に、共有名義の不動産を相続する際の主要な注意点を挙げます。
まず、相続人間の合意形成が必要です。共有名義の不動産では、他の共有者が存在するため、相続人が不動産をどのように扱うかについて全員の合意が得られる必要があります。合意がなければ、不動産の売却や改修が困難になることがあります。特に、共有者の中で意見の不一致がある場合、法的な介入が必要になることもあります。
次に、遺産分割協議書の重要性が増します。共有名義の不動産相続では、協議書によって具体的な持分の分配が明確に記されている必要があります。この文書は後々の紛争を防ぐためにも、詳細かつ明確に作成する必要があります。
また、税務上の処理にも注意が必要です。不動産の持分に応じて、相続税の計算が行われるため、正確な評価が求められます。これには専門家のアドバイスが有効です。
さらに、共有名義の不動産相続では、登記の更新が重要な手続きです。相続によって不動産の持分が変動するため、法務局への適切な登記手続きを行わなければ、不動産の正式な所有権に影響が出ることがあります。登記は相続人全員の協力が必要となるため、このプロセスをスムーズに進めるためには、相続人間の良好なコミュニケーションが不可欠です。
最後に、共有名義の不動産の相続では、未来のリスク管理も視野に入れる必要があります。相続後に新たな共有者との間でトラブルが生じないよう、相続時にすべての可能性を考慮した対策を立てることが大切です。
これらの注意点を踏まえ、共有名義の不動産相続には計画的かつ慎重なアプローチが求められます。不明瞭な点があれば、法律専門家に相談し、確実な手続きを心掛けることが賢明です。
遺産分割協議の進め方

遺産分割協議を進める際は、争いを避けるためにも、明確かつ計画的なアプローチが求められます。ここでは、初めて遺産分割協議に臨む方にもわかりやすい進め方をご説明します。
まず、遺産分割協議は、故人の財産を相続人がどのように分けるかを決める重要なプロセスです。相続人全員の合意が必要なため、協議を始める前に全員が参加できる日時を設定することが大切です。
次に、故人の財産一覧を明確にしましょう。銀行口座、不動産、価値ある個人所有物まで、すべての資産と負債をリストアップします。これには財産評価も含まれ、不動産などの場合は市場価値を把握するために専門家の評価を受けることが望ましいです。
協議では、まず遺言書の有無を確認します。遺言書がある場合、その内容に従うことが法律的に義務付けられています。遺言書がない場合、相続人全員で公平な分割方法について話し合います。このとき、感情的になりがちなので、冷静かつ公平な立場で進めることが重要です。
遺産分割協議が成立した後は、合意内容を遺産分割協議書に記載し、相続人全員の署名と押印を得ます。この文書は法的な効力を持ち、後の紛争を防ぐための重要な証拠となります。
最後に、協議書に基づき法務局での登記変更など、必要な法的手続きを完了させます。これには相続人それぞれの身分証明書や印鑑証明書が必要となることもあります。
このプロセスを通じて、遺産分割協議は全相続人が納得する形で平和的に解決されるべきです。適切な準備と、必要に応じて専門家の助言を求めることが、スムーズな遺産分割には不可欠です。
相続手続きにおける登記費用と報酬

相続手続きにおいては、登記費用と司法書士の報酬が重要な費用項目です。これらの費用は相続のプロセスを法的に確実に進めるために必要なものであり、事前に把握しておくことで、予期せぬ出費を避けることができます。
まず、登記費用は、不動産の相続登記を行う際に必要となる国に支払う費用です。具体的には、登録免許税がこれに該当し、この税額は不動産の評価額に基づいて計算されます。たとえば、不動産の固定資産税評価額が1,000万円の場合、登録免許税はその1000分の4である2万5000円が目安となります。
次に、司法書士の報酬ですが、これは相続登記を代行してくれる司法書士に支払う費用です。司法書士の報酬は事務所や地域によって異なりますが、一般的には不動産一件あたり5万円から10万円程度が相場です。また、相続人の数が多かったり、遺産の内容が複雑だったりする場合は、これよりも高額になることがあります。
さらに、遺産が複数の不動産を含む場合や、登記手続きが複雑な場合は、それに比例して追加費用が発生することもあります。例えば、相続人全員の同意が得られない場合には、調停や訴訟といった法的手続きが必要になることがあり、これにはさらなるコストがかかります。
このように、相続手続きにおける費用は多岐にわたりますが、事前にしっかりとした見積もりを取ることで、スムーズかつ経済的に手続きを進めることができます。また、費用の内訳を明確にして、必要な手続きのみを選択することがコスト削減の鍵となります。重要なのは、透明性を持って費用を把握し、計画的に行動することです。
相続登記の流れと必要書類の整理

相続登記は遺産の法的な移転を確実にする重要な手続きです。このプロセスをスムーズに進めるためには、必要書類の整理が非常に重要です。具体的な手続きの流れと、それに必要な主要な書類をここで明確にします。
まず、相続登記の流れは以下のステップに分けられます:
- 遺産分割協議の実施
- 必要書類の収集
- 登記申請の準備と提出
- 登記完了
遺産分割協議は、相続人全員で不動産の分配方法を決定するためのものです。この協議により、どの相続人がどの不動産を引き継ぐかが決定されます。協議が円滑に進むよう、事前に全相続人との意見調整が必要です。
次に、必要書類を収集します。このステップでは、以下の書類が必要となります:
- 戸籍謄本・除籍謄本:相続人と被相続人の関係を証明します。
- 遺産分割協議書:相続人全員の同意が記載された公正証書または自筆の協議書。
- 不動産登記簿謄本:現在の登記状況を確認します。
- 固定資産税評価証明書:不動産の価値を確認します。
これらの書類は、遺産分割協議後に地方法務局へ提出する登記申請のために使用されます。登記申請は、通常、司法書士を通じて行うことが多いです。司法書士はこれらの書類を基に申請書を作成し、法務局に提出します。
最後に、登記が完了すると、新しい所有者名で登記簿が更新され、法的な所有権の移転が完了します。この登記完了証を受け取ることで、全プロセスが終了します。
この流れに従い、事前に必要な書類を整理しておくことで、相続登記を迅速かつ正確に行うことができます。相続は感情的な問題も多いため、書類の準備を含めた手続きを事前にしっかりと計画することが、トラブルを避けるためにも重要です。
共有名義方死亡相続登記申請書書き方のまとめ
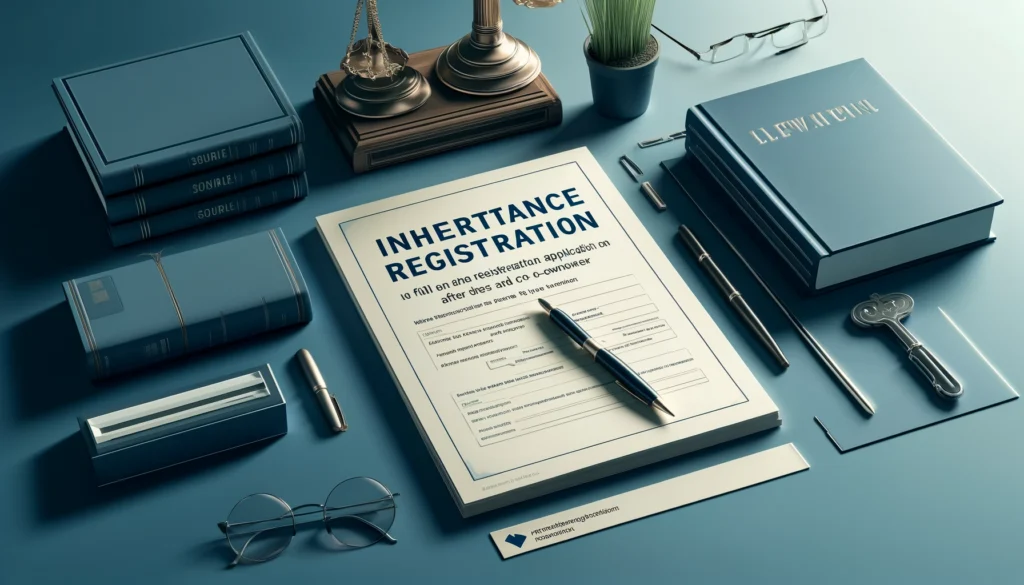
- 共有名義の不動産における登記申請書の書き方を解説
- 共有名義の不動産登記は複数所有者の関与があるため注意が必要
- 登記申請書には全共有者の氏名、住所、持分比率を正確に記載する
- 持分比率例:一人が持分の2/3、もう一人が1/3
- 遺産分割協議書や死亡証明書などの添付書類も準備が必要
- 登記申請書は手書きでもタイプ入力でも可能
- 登記申請時は、最寄りの登記所に書式や要求される書類を事前確認を推奨
- 手書きで登記申請書を作成する際は読みやすさと正確さが重要
- 手書きの場合、フォーマットを正確に守り、情報を明確に記入
- 誤字脱字のないように慎重に記入し、修正液や修正テープで修正可能
- 全ページにページ数を記載し、各ページに署名または印鑑を押す
- 登記申請書の持分の書き方では、持分が分数で表現されることが一般的
- 持分の記載には、各共有者の名前とともに、それぞれの持分を隣接させて記入
- 登記申請書の見本を提供し、申請書作成の具体的なフォーマットとポイントを説明
- 相続登記申請書のダウンロード手順を提供し、法務局の公式ウェブサイトや地元の市役所、区役所のウェブサイト利用を推奨
- 複数の不動産に対して一度に登記申請を行う際の注意点と方法を解説
- 相続人が一人の場合の登記申請書の記入方法とその簡略化可能性を説明
参考
・相続争い末路:家族を守るための遺産分けのコツ
・不動産相続名義変更必要書類法務局の完全ガイド
・相続認知症バレるとどうなる?対策方法を解説
・初心者向け相続年金確定申告入力のガイド
・相続手続き期限過ぎたらどうなる?解決策を紹介
・相続登記義務化未登記建物の罰則と正しい手続き
・遺骨ペンダント完全ガイド:選び方から意味まで
・遺骨ペンダント小さめで感じる故人との絆の大切さ
・遺骨ペンダントどこに売ってる?選び方とポイント
・家族信託手続きで知るべき3つのポイント
・家族信託後見人違い解説:4大メリットを知る
・家族信託費用自分で節約、5つの効果的方法
・家族信託手数料の相場を知る7つのコツ
・30代から始める終活エンディングノートのススメ
・エンディングノート何歳から書くべき?3つのポイント
・家族信託委託者死亡時の全手続きガイド5選
・家族信託後見人違い解説:4大メリットを知る
・家族信託認知症発症後の管理を効率化する4ステップ

お問い合わせ・60分無料相談
何をどうすればいいの?など初歩的な事でもまずはお話を聞かせてください。
エンディングノート・終活・老後資金・医療・介護・保険・相続・葬儀・お墓・その他
相談することによりお気持ちの整理が可能になります!お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはお気軽に!
大阪不動産・FPサービス株式会社
info@ofps.co.jp
TEL:050-3576-2951
投稿者プロフィール

-
ファイナンシャルプランナー・終活ガイド・
エンディングノート講師幅広いサポートが可能です!
終活・相続・事業承継・生命保険・老後資金のご相談の専門家です
不動産・リフォーム・ファイナンシャルプランニング・保険の見直し・終活・相続・家族信託・任意後見・遺言作成・生前整理・不用品買取・デイサービス・老人ホーム・お葬式・お墓他お悩み事すべてご対応可能なサービスをご準備しておりますので安心してお気軽にご相談ください。
最新の投稿
 ペット2024-10-20ペットショップ売れ残りシーズーの運命と保護活動の現状
ペット2024-10-20ペットショップ売れ残りシーズーの運命と保護活動の現状 不動産購入・住宅ローン2024-10-16住宅ローン無職でも審査に通るための秘訣と注意点を解説
不動産購入・住宅ローン2024-10-16住宅ローン無職でも審査に通るための秘訣と注意点を解説 不動産2024-10-07マンション断水過ごし方のコツ:水の確保からトイレの使い方まで
不動産2024-10-07マンション断水過ごし方のコツ:水の確保からトイレの使い方まで ペット2024-09-19ペット保険いらない知恵袋のまとめ:選び方と不要と感じる理由
ペット2024-09-19ペット保険いらない知恵袋のまとめ:選び方と不要と感じる理由






