
相続が発生した際に、古い建物や未だ登記されていない不動産を相続することは珍しくありません。
特に、相続登記義務化の法改正により、未登記の建物を相続した場合の取り扱いについて、正確な情報を知っておくことがこれまで以上に重要になりました。本記事では、相続登記義務化が未登記建物に及ぼす影響、自分で行う相続登記の手続き、さらには未登記建物の名義変更や固定資産税に関わる対処法まで、幅広い情報を網羅しています。
未登記の建物を相続したらどうなるのか、また未登記家屋に対する登記義務や解体に至るプロセスについても触れています。登記しなくてもよい建物があるのか、そして相続未登記に伴う罰則やこれらの問題をどう自分で解決していくのかについても、具体的に解説します。この記事を通じて、相続登記義務化未登記建物に関する疑問を解消し、スムーズな相続手続きへと導きます。
一般社団法人終活協議会認定資格 終活ガイド・心託コンシェルジュのお役立ちブログです。終活についてのご相談やサポートサービスをご提供しています。生涯笑顔で過ごせる環境づくりをお手伝いさせていただいております。
・生活のサポートを含むサービス
『入院、介護施設入居に伴う身元保証(身元引受け)連帯保証』のご相談
・おひとりさまや、もしもの時に家族に負担をかけたくないあなたに
『葬儀、連絡、お墓、手続き、遺品整理、遺言、相談、公正証書の作成』のご相談
・今は元気だが歳を重ねても不安にならないために
老後資金や年金、貯金の不安のご相談、万一認知症やお体や生活環境に不自由が発生し、デイサービスや老人施設が必要となった際の選び方や準備金、入所の問題
上記のように簡単に気になる事を並べただけでもたくさんあり、終活は多岐にわたりますのでその方のご事情によって様々です。
私たちは、医療、介護、法律、金融をはじめお客様の様々なご事情に対応できる専門家チームが一丸となりお客様に寄り添いながら様々なご事情に合わせた適正なサービスをご提供し、生涯笑顔で過ごせる環境づくりをお手伝いをしています。お気軽にご相談ください。
この記事のポイント
- 相続登記義務化が未登記建物にどのような影響を与えるか
- 未登記建物の相続に必要な手続きと自分で行える部分
- 未登記建物を相続した場合の名義変更方法と固定資産税の対応
- 相続における未登記建物の罰則とその回避策

終活・相続
お気軽にご相談ください
- 何をしたら良いのかわからない
- エンディングノート・終活
- 老後資金・自宅売却の時期
- 資産活用対策・医療・介護
- 施設選び・生命保険・相続対策
- 遺言・葬儀・お墓・相続登記
- 相続発生後の対応や処理方法
- 信用できる士業への安全な橋渡し
その他なんでもお気軽にご相談ください!
営業時間 10:00-18:00(日・祝日除く)
相続登記義務化と未登記建物の現状

未登記建物の相続登記手続きの概要
相続が発生した際に、未登記の建物があるケースは少なくありません。こうした建物の正式な手続きを行うことで、法的に認められた所有者になることができます。未登記建物の相続登記手続きは、初めての方にも分かりやすく解説します。
まず、必要な書類を集めることから始めます。これには、亡くなった人の死亡証明書、相続人全員の同意書、そして建物があることを証明する資料が含まれます。特に、建物の詳細を示す資料は、固定資産税の納税証明や、建物の写真、もしくは建設当時の契約書などが有効です。
次に、法務局への申請に進みます。ここで、未登記建物を登記するための「表題登記」と、亡くなった人から相続人への所有権移転を示す「所有権移転登記」の2つの手続きを行います。表題登記には、建物の所在地や構造などの詳細情報が求められるため、事前に情報を整理しておくことが重要です。
重要なのは、この手続きを通じて、法的に保護された所有権を得ることです。手続きを完了することで、相続人は建物を売却したり、改修したりする権利を得ることができるようになります。さらに、未登記のままでは固定資産税の納税者名が変更されないため、手続き後は税務上の正式な所有者として認識されます。
このプロセスは、専門家のサポートを受けながら進めるとスムーズです。土地家屋調査士や司法書士に相談することで、書類の準備から申請までの手続きを効率的に進めることができます。もちろん、費用はかかりますが、複雑な手続きを正確に、迅速に行うためには、専門家の力を借りることが最適な解決策と言えるでしょう。
最後に、手続きの期間ですが、書類が揃っていれば、数ヶ月程度で完了するケースが多いです。ただし、資料が不足している場合や、申請が集中する時期には、もう少し時間がかかることもあります。事前に準備をしっかりと行い、余裕をもって申請に臨むことが大切です。
相続登記義務化における建物の扱い

相続登記義務化は、土地だけでなく建物にも影響を及ぼします。相続が発生した場合、不動産全体に対して名義変更の手続きを行う必要があるため、建物の扱いが重要なポイントになります。ここでは、相続登記義務化のもとでの建物の扱いについて、簡単に解説します。
まず基本として、建物が未登記の場合でも登記が必要になります。これは、相続登記の義務化が目指す、所有権の明確化と土地の有効活用を促進するためです。具体的には、相続人は亡くなった人から建物を相続した際、未登記の建物についても表題登記を含めた相続登記を行う義務があります。
未登記建物の登記手続きには、建物の位置や構造などの具体的な情報の提供が必要です。しかし、古い建物であるほど、その情報が不足しているケースも少なくありません。そのため、相続登記義務化の下では、これらの情報を補うために、固定資産税の納税通知書や過去の契約書類などが重要な役割を果たします。
相続登記を怠った場合の罰則もあります。仮に相続後3年以内に必要な登記手続きを行わなければ、10万円以下の過料が科される可能性があるため、注意が必要です。これは、所有者不明の不動産を減少させ、不動産取引の安全性を高めるための措置です。
このように、相続登記義務化は建物の所有権に関する透明性を高めることを目的としています。相続人は、適切な時期に専門家に相談することで、スムーズな手続きを進めることができます。建物の正式な登記を完了させることで、相続人は不動産を法的に保護された資産として管理することが可能になり、将来の売却や利用計画においても大きなメリットが期待できます。
古い建物の未登記状態とその対処法

古い建物が未登記のまま残っている状況は、相続登記義務化の中で特に注意が必要です。多くの場合、古い建物は過去に適切な登記手続きが行われず、現代に至るまでその状態が続いている可能性があります。これは、建築当時の文書が失われたり、登記の必要性に対する認識が不足していたために起こり得ます。
古い建物の未登記状態に直面した場合、まず行うべきことは、専門家への相談です。土地家屋調査士や司法書士など、不動産登記に関する専門知識を持つ専門家は、このような状況に対処するための最適なアドバイスを提供できます。特に、建物の図面や当時の契約書など、登記を進める上で必要な情報を集めるサポートが期待できます。
対処法としては、以下のステップが考えられます:
- 過去の書類の収集:固定資産税の納税証明や建築当時の契約書類など、建物の存在を証明できる資料を集めます。
- 表題登記の申請:収集した資料をもとに、未登記の建物に対する表題登記を申請します。これには、建物の所在地、構造、用途などの詳細情報が必要になります。
- 相続登記の完了:表題登記が済んだ後、相続による名義変更を含む相続登記を行います。これにより、建物は正式に相続人の名義となり、法的な保護を受けることが可能になります。
重要なのは、未登記の建物を放置するリスクです。未登記状態が続くと、将来の売却や改築、さらには相続時に大きな問題を引き起こす可能性があります。また、相続登記を怠ると罰則が適用される場合もあるため、適切な時期に手続きを進めることが重要です。
総じて、古い建物の未登記状態は、潜在的なリスクをはらんでいます。しかし、適切な対処法を講じることで、これらのリスクを回避し、建物を安心して次世代に引き継ぐことが可能です。専門家と協力して、一歩ずつ前進しましょう。
相続による未登記建物の罰則と対策

相続が発生した際、未登記の建物があると、単に手続きが煩雑になるだけではなく、法的な罰則に直面する可能性もあります。相続登記義務化の下、所有権の変更を正式に登記しないと、10万円以下の過料が科されることがあるのです。この罰則は、正当な理由なく登記を怠った場合に適用されますが、未登記の建物に対しても同様の対応が求められるケースがあります。
しかし、心配する必要はありません。適切な対策を講じることで、これらの罰則を回避し、スムーズに相続手続きを進めることが可能です。対策として最も重要なのは、専門家への相談です。土地家屋調査士や司法書士に相談することで、未登記建物の現状を正確に把握し、適切な登記手続きを進めることができます。
対策のステップは大きく分けて以下の通りです:
- 資料の収集:建物が建てられた当時の契約書や固定資産税の納税証明書など、建物の存在を証明できる資料を集めます。
- 登記の申請:集めた資料を基に、まず未登記建物の表題登記を申請します。その後、相続による所有権変更の登記を行います。
- 罰則の回避:正式な登記手続きを行うことで、未登記の状態による罰則を回避できます。
重要なのは、相続が発生したらできるだけ早く行動に移すことです。相続登記の期限は、相続が開始されたことを知った日から3年以内とされています。この期間内に手続きを完了させることで、罰則を回過するだけでなく、将来のトラブルを避けることができます。
未登記建物の相続は複雑に感じるかもしれませんが、計画的に対策を講じれば確実に進めることができます。最も大切なのは、一人で悩まずに専門家に相談する勇気を持つこと。これにより、相続のプロセスをスムーズに、そして法的な安全を確保しながら進めることができるでしょう。
名義変更を伴う未登記建物の相続プロセス

未登記建物の相続は、名義変更のプロセスを伴いますが、この手続きは一見複雑に見えるかもしれません。しかし、ステップバイステップに進めれば、必ず乗り越えられます。ここでは、名義変更をスムーズに行うための基本的なプロセスを紹介します。
まず、未登記建物の相続プロセスは相続人の特定から始まります。相続人全員の同意が必要なので、この段階で誰が相続人であるかを明確にしましょう。次に、遺産分割協議を行い、誰がその建物を相続するかを決定します。ここで作成される遺産分割協議書は、後の手続きで非常に重要になります。
その後、未登記建物の表題登記を申請する必要があります。これは、建物が法的に存在することを証明する手続きです。表題登記がなされた後に、初めて名義変更の申請(相続登記)を行うことができます。この申請には、遺産分割協議書や相続人の戸籍謄本などが必要になります。
特に注意すべき点は、このプロセスには時間と費用がかかることです。具体的な費用は、登記を行う土地家屋調査士や司法書士によって異なりますが、数万円から数十万円の範囲が一般的です。また、全ての手続きを完了するまでには数ヶ月を要することも珍しくありません。
このプロセスを通じて最も重要なのは、専門家との連携です。土地家屋調査士や司法書士などの専門家は、このような状況に慣れており、適切なアドバイスを提供できます。彼らのサポートを得ることで、プロセスが大きくスムーズに進むでしょう。
未登記建物の相続と名義変更は、一歩一歩丁寧に進めれば、確実に進展します。焦らず、一つずつ確実に手続きを進めることが成功への鍵です。
固定資産税と未登記建物の相続

相続が発生した際、多くの人が忘れがちなのが、固定資産税に関する問題です。特に、未登記建物を相続するケースでは、注意が必要です。未登記建物であっても、固定資産税の課税対象になることが一般的です。これは、建物が法的に登記されているかどうかとは無関係に、その存在が市町村に認識されている限り、税金が課せられるためです。
未登記建物を相続した場合、まず行うべきことは、亡くなった人の名前で来ている固定資産税の通知書を確認することです。その後、相続人が市町村役場へ相続の事実を伝え、税の納税義務者を変更する手続きを行う必要があります。このプロセスを通じて、建物が相続人の名義に変更されますが、これにより法的な登記がされたわけではない点に注意が必要です。
具体的な手続きには、相続人の戸籍謄本や遺産分割協議書などが必要になる場合が多く、数千円の手数料がかかることがあります。また、固定資産税は年に一度、通常は4月に通知されるため、その時期を逃さないようにすることが重要です。
未登記建物の相続においては、固定資産税の納税義務者の変更は一時的な対応に過ぎません。長期的には、建物の正式な登記を行うことが推奨されます。登記を行うことで、将来的な不動産の取引や相続が発生した際に、手続きがスムーズになり、権利関係が明確になります。
固定資産税と未登記建物の相続は、早期の対応が重要です。亡くなった人の財産としての建物がある場合、可能な限り早く市町村役場に相談し、適切な手続きを行うことが、後のトラブルを避けるための鍵となります。専門家のアドバイスを求めながら、丁寧に対処を進めましょう。
未登記建物の相続に関するQ&A
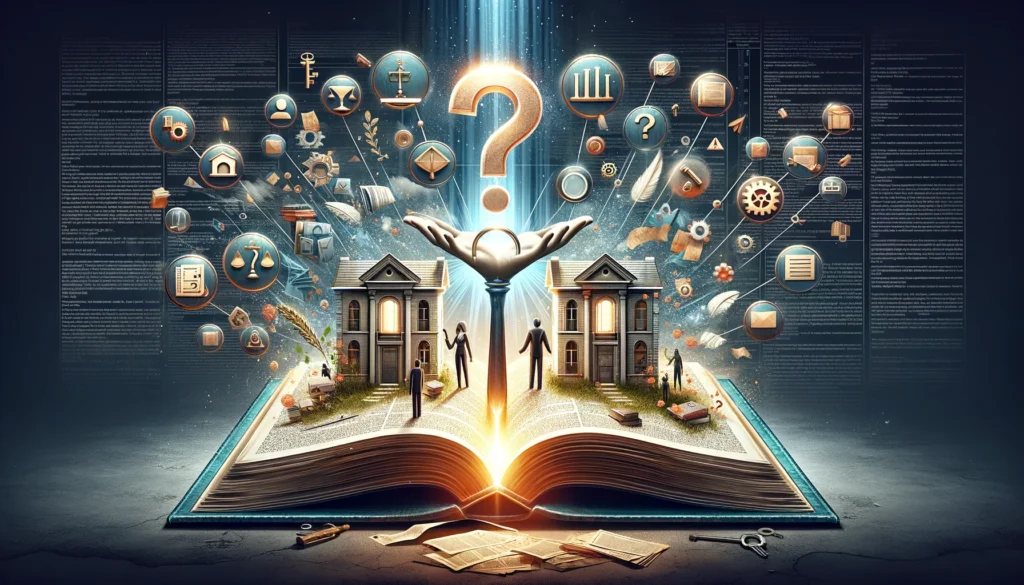
未登記の建物を相続した場合の手続きと注意点
未登記の建物を相続することは、意外と一般的な状況です。しかし、このプロセスにはいくつかの重要なステップと注意点があります。まず最初に理解するべきは、未登記の建物が法的に正式な所有物として認められるためには、建物の登記が必要であるということです。この手続きを怠ると、将来的に建物を売却したり、改築する際に問題が生じる可能性があります。
手続きの第一歩として、相続が発生したことを地元の役場や法務局に通知することが必要です。これにより、固定資産税の納税者名を変更することができます。しかし、これだけでは不十分であり、法務局での正式な建物の登記が必要になります。未登記建物の登記には、土地家屋調査士による測量や建築図面の作成が求められることが一般的です。この過程で発生する費用は数万円から数十万円に上ることがあり、費用と時間がかかるプロセスであることを覚悟する必要があります。
注意点として、未登記建物を相続する際には、遺産分割協議書が重要な役割を果たします。相続人全員の合意形成が必要であり、この協議書に基づいて法務局での手続きが進められます。また、未登記建物が長年放置されている場合、その構造や安全性に問題がある可能性があるため、専門家による建物の点検や評価も検討する必要があります。
さらに、未登記の建物を相続することによって発生する固定資産税の問題にも注意が必要です。相続後も建物が未登記の状態であれば、相続人が固定資産税の納税義務者となりますが、この税金の計算基準や金額に変更がある可能性があるため、地方自治体に相談し、正確な情報を得ることが大切です。
未登記の建物を相続した場合、手続きを迅速に行い、必要な場合は専門家の助言を求めることで、将来のトラブルを避けることができます。このプロセスを通じて、財産としての価値を守り、相続人の権利を確立することが重要です。
未登記家屋の登記義務について

未登記家屋を所有している場合、その登記は法的に義務付けられています。この義務の根拠は、不動産登記法にあり、新しく建物を建築した者、あるいは既に存在する未登記建物の所有権を取得した者は、所有権の取得から1ヶ月以内に表題登記を申請しなければなりません。違反した場合、最大10万円の過料が科される可能性があります。
未登記家屋の登記を行うには、まず建物の所在地や構造などの詳細情報を収集し、土地家屋調査士による測量や図面作成が必要となることが一般的です。このプロセスは、専門的な知識を要し、数万円から数十万円の費用がかかることがあります。しかし、この手続きを行うことで、建物の法的な保護を受けることができ、将来的に売却や贈与、相続などの際にもスムーズに手続きを進めることが可能になります。
また、未登記家屋の登記義務は、所有者が明確になり、固定資産税の適正な評価にも繋がります。未登記の状態では、固定資産税の納税者が不明瞭となり、自治体による適切な税金の徴収が難しくなるため、登記を通じて税務上の問題も解決することができます。
登記が未了の家屋を所有している場合は、速やかに法務局への登記申請を検討し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが賢明です。これにより、不動産としての家屋の価値を保護し、将来にわたって様々なリスクから身を守ることができます。
登記不要とされる建物の特例

通常、建物を新築した際には所有権の登記が必要ですが、全ての建物がこの規則に該当するわけではありません。特定の条件を満たす建物には、登記が不要とされる特例があります。これらの例外には、一時的な用途で建てられた建物や、非常に小規模な構造物などが含まれます。例えば、農作業用の小さな倉庫や、期間限定のイベント用テントなどが該当することがあります。
このような建物は、その用途や機能によって、本来の建物登記の要件から外れると判断されるため、法的手続きを簡略化できる利点があります。しかし、これらの建物でも、使用目的が変わる、あるいは恒久的な構造物へと発展する可能性がある場合は、登記の必要性が生じることもあります。
重要なのは、登記不要とされる建物であっても、地域の条例や建築基準法に違反しないよう注意深く計画し、必要に応じて自治体や専門家へ相談することです。また、固定資産税の評価にも影響を及ぼす可能性があるため、事前に詳細を確認し、適切な対応を取ることが求められます。
登記不要とされる建物に関する特例は、その便利さと共に注意が必要なポイントも伴います。建設を計画する際は、その建物が特例に該当するかどうかを慎重に判断し、将来的に発生するかもしれない法的義務や税金の問題に備えることが重要です。
未登記建物の解体計画とその影響

未登記建物の解体計画を立てる際、いくつかの重要な考慮事項があります。まず、解体にかかるコストはプロジェクトの規模や立地によって大きく異なります。都市部では解体作業が複雑になることが多く、コストも上昇傾向にあります。一方、地方では作業がシンプルに進むことが多いですが、廃材の処理に関する規制が厳しいため、それに伴う費用がかかります。
未登記の状態であることが解体計画に及ぼす影響も見逃せません。所有権の明確化がなされていない建物は、解体許可の申請が困難になる可能性があります。このため、解体に先立ち、適切な手続きを踏んで所有権を確定する必要があります。
また、解体後の土地利用計画も重要です。未登記建物があった土地は、解体後に新たな建築計画や売却のための準備が必要になることがあります。この時、土地の価値を最大化するための計画が求められます。解体工事の実施は、地域の景観や環境にもポジティブな影響を与えることがありますが、一方で近隣住民とのコミュニケーションが必要な場合もあります。
解体計画は、法的規制や環境保護基準にも留意する必要があります。特にアスベストなどの有害物質の処理には細心の注意が必要です。適切な手続きを行うことで、法的なリスクを避け、スムーズな解体が実現します。
未登記建物の解体計画は、単に古い建物を取り除く作業ではなく、法的、社会的、経済的要因を考慮した複雑なプロジェクトです。計画段階で専門家のアドバイスを求めることが、解体作業を成功に導く鍵となります。
自分で行える未登記建物の相続登記手続き

未登記建物の相続登記は、専門的な知識がなくても一定の手順を踏めば自分で行うことが可能です。まず、相続が発生したら、遺産分割協議書を作成し、全相続人の同意を得る必要があります。この協議書は、相続登記を申請する際の根拠となります。
次に、相続人全員の戸籍謄本や被相続人の死亡証明書など、必要な書類を集めます。これらの書類は、法務局での相続登記申請時に必要となり、戸籍謄本は被相続人の出生から死亡までの全てが必要です。
未登記建物の相続登記には、通常、土地家屋調査士の協力が必要となります。建物の正確な測量と図面の作成が求められるため、これらのプロセスは自分で行うことが難しいです。しかし、図面が既に存在する場合や、簡易的な建物であれば、自分で測量して図面を作成することも可能ですが、専門家に相談することをお勧めします。
書類が揃ったら、法務局にて相続登記の申請を行います。申請書類には、遺産分割協議書、戸籍謄本、死亡証明書、図面などが含まれます。手続きの詳細や必要書類は、事前に最寄りの法務局に確認すると良いでしょう。
登記費用は、申請する不動産の種類や価値によって異なりますが、相続登記の場合は登録免許税が減税されることが多いので、その点も事前に確認しておきましょう。
最後に、登記手続きが完了すると、法務局から登記済証が発行されます。これで、未登記建物の相続登記が完了し、法的に認められた所有者となります。
自分で行える未登記建物の相続登記手続きは、一見複雑に思えますが、事前に必要情報を収集し、計画的に進めることでスムーズに完了することができます。しかし、途中で不明な点があれば、専門家に相談することが最善の策です。
未登記建物相続時の名義変更と固定資産税調整方法
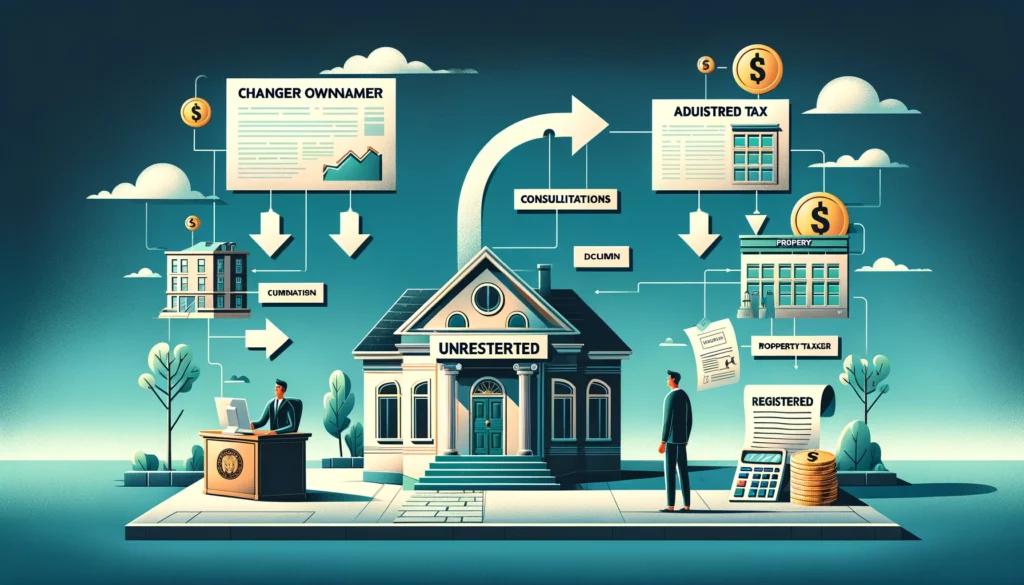
未登記建物を相続した場合、名義変更と固定資産税の調整は重要なステップです。未登記であるため、通常の不動産のように登記簿に基づいて手続きを行うことはできません。ここでは、シンプルで理解しやすい方法を解説します。
まず、名義変更についてですが、これは法務局で行う登記手続きに代わり、土地家屋調査士に依頼して表題登記を行うことがスタートラインとなります。表題登記が完了した後に、相続登記を進めることができます。相続登記には、遺産分割協議書や相続人の戸籍謄本などの書類が必要となり、このプロセスを通じて正式に名義変更が行われます。
次に、固定資産税の調整方法です。未登記建物であっても、固定資産税は課税されているため、相続後は税務上の所有者情報を更新する必要があります。これは、地方自治体の税務課に対して固定資産税の納税者変更届を提出することで行います。提出にあたっては、遺産分割協議書のコピーと新しい所有者の身分証明書が必要になることが多いです。
具体的には、以下のステップで進めましょう:
- 土地家屋調査士に依頼して未登記建物の表題登記を行う。
- 法務局で相続登記を申請し、名義変更を完了させる。
- 地方自治体に対して、固定資産税の納税者変更届を提出し、税務上の所有者情報を更新する。
このプロセスを経ることで、未登記建物の相続時の名義変更と固定資産税の調整が正しく行われます。専門家に相談しながら進めることをお勧めします。手続きにはそれぞれ数週間から数ヶ月かかることがあるため、早めの行動が重要です。
相続登記義務化未登記建物のまとめ
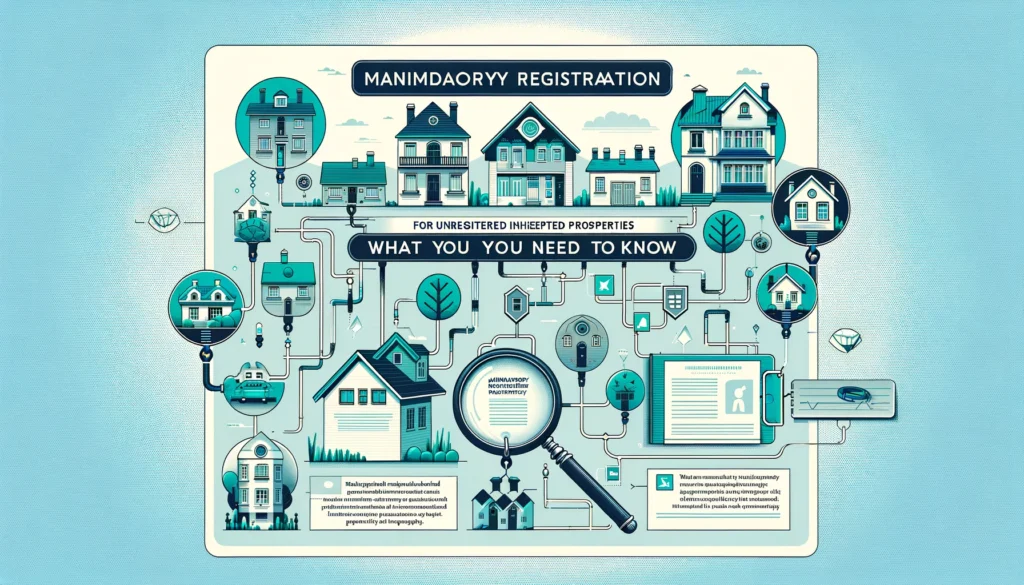
- 相続登記義務化は、所有者の明確化と不動産取引の安全性向上を目的としている
- 2024年4月1日から相続登記が義務化され、正当な理由なく申請を怠った場合は罰則が適用される
- 未登記建物も相続対象に含まれ、相続発生後3年以内に登記申請が必要
- 罰則として、違反した場合には10万円以下の過料が科せられる可能性がある
- 未登記建物の相続登記を自分で行うには、土地家屋調査士や司法書士への相談が推奨される
- 古い建物や昔の建築物も登記義務の対象となり、所有権の証明が必要
- 固定資産税の納税義務者を変更することで、未登記建物の名義変更が部分的に反映される
- 未登記建物の解体を計画する場合も、事前の登記が求められることがある
- 登記不要とされる建物の特例は極めて限定的で、ほとんどの建物が登記対象
- 未登記建物の相続における名義変更は、適切な手続きを経て法的な保護を受けることができる
- 建物の新築や改築時に未登記となったケースでは、表題部登記から始める必要がある
- 相続登記を行うことで不動産の正確な価値評価が可能になり、将来の売却や活用に影響する
- 未登記建物の存在は相続税評価額の算定においても考慮されるべき事項
- 相続登記義務化は国土の適正な利用と所有者不明土地の問題解決に貢献する
- 相続人全員の合意が必要となる遺産分割協議では、未登記建物についても正確な記載と手続きが求められる
参考
・遺骨ペンダント完全ガイド:選び方から意味まで
・遺骨ペンダント小さめで感じる故人との絆の大切さ
・遺骨ペンダントどこに売ってる?選び方とポイント
・家族信託手続きで知るべき3つのポイント
・家族信託後見人違い解説:4大メリットを知る
・家族信託費用自分で節約、5つの効果的方法
・家族信託手数料の相場を知る7つのコツ
・30代から始める終活エンディングノートのススメ
・エンディングノート何歳から書くべき?3つのポイント
・家族信託委託者死亡時の全手続きガイド5選
・家族信託後見人違い解説:4大メリットを知る
・家族信託認知症発症後の管理を効率化する4ステップ
・老後一人ぼっち女性のための10の生活計画
・老後資金1億円の生活レベルを実現する5つの秘訣

お問い合わせ・60分無料相談
何をどうすればいいの?など初歩的な事でもまずはお話を聞かせてください。
エンディングノート・終活・老後資金・医療・介護・保険・相続・葬儀・お墓・その他
相談することによりお気持ちの整理が可能になります!お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはお気軽に!
大阪不動産・FPサービス株式会社
info@ofps.co.jp
TEL:050-3576-2951
投稿者プロフィール

-
ファイナンシャルプランナー・終活ガイド・
エンディングノート講師幅広いサポートが可能です!
終活・相続・事業承継・生命保険・老後資金のご相談の専門家です
不動産・リフォーム・ファイナンシャルプランニング・保険の見直し・終活・相続・家族信託・任意後見・遺言作成・生前整理・不用品買取・デイサービス・老人ホーム・お葬式・お墓他お悩み事すべてご対応可能なサービスをご準備しておりますので安心してお気軽にご相談ください。
最新の投稿
 ペット2024-10-20ペットショップ売れ残りシーズーの運命と保護活動の現状
ペット2024-10-20ペットショップ売れ残りシーズーの運命と保護活動の現状 不動産購入・住宅ローン2024-10-16住宅ローン無職でも審査に通るための秘訣と注意点を解説
不動産購入・住宅ローン2024-10-16住宅ローン無職でも審査に通るための秘訣と注意点を解説 不動産2024-10-07マンション断水過ごし方のコツ:水の確保からトイレの使い方まで
不動産2024-10-07マンション断水過ごし方のコツ:水の確保からトイレの使い方まで ペット2024-09-19ペット保険いらない知恵袋のまとめ:選び方と不要と感じる理由
ペット2024-09-19ペット保険いらない知恵袋のまとめ:選び方と不要と感じる理由






