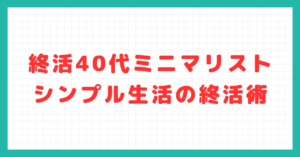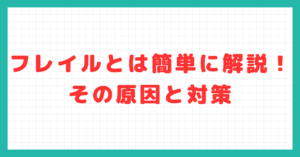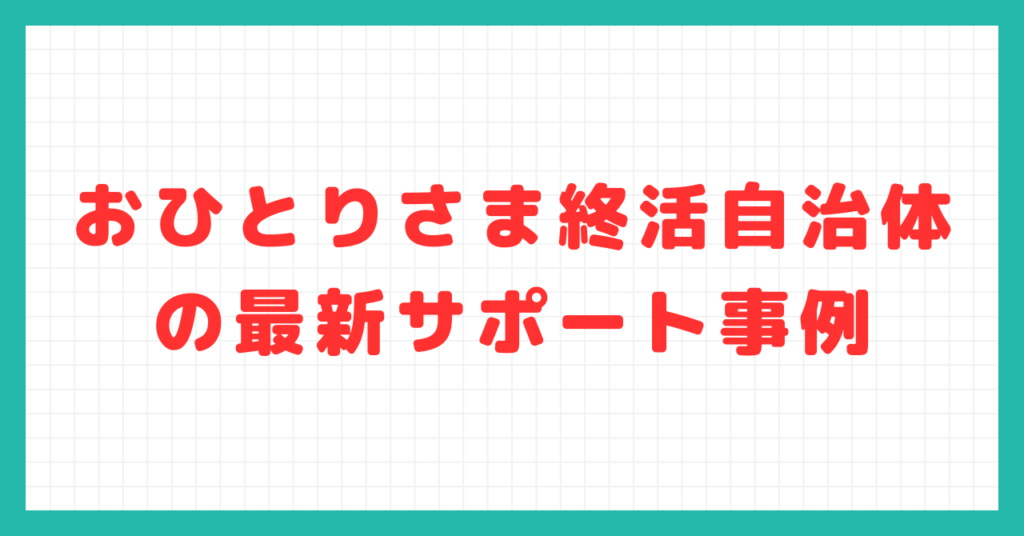
近年、高齢化社会が進む中で「おひとりさま終活」という言葉が注目されています。高齢で家族や親族がいない、または別居している方々が、自らの老後や死後のことを考え、準備を始める動きが増えてきました。
この動きに対応し、多くの自治体が独自のサポートを展開しています。本記事では、各自治体がどのようなサポートを提供しているのか、その最新事例を中心に紹介します。おひとりさまの方だけでなく、将来的におひとりさまになる可能性を考えるすべての方に、役立つ情報をお届けします。
大阪不動産・FPサービス 一般社団法人終活協議会公認 終活ガイド・ファイナンシャルプランナーの藤原みずほです。
お客様が抱えている終活、相続関連の悩みや課題は「家族にも話しにくい」「家族だからこそ話しにくい」事が多く、
だからこそ誰にも相談できずに困っている方がほとんどです。まじめなお話の内容が多いですが、まずは明るく前向きに相談できる30分無料相談をぜひご活用ください。
お電話・リモート(ZOOM・テレビ電話)などでお気軽にご相談ください。全国にネットワークがございます!
この記事のポイント
- おひとりさま終活の重要性とその背景
- 各自治体が提供している終活サポートの具体例
- おひとりさまの老後と死後のリスクとその対策
- 終活サポートの積極的な活用方法とそのメリット

30分無料なんでも相談
何をどうすればいいの?などお気軽にお問い合わせください
おひとりさま終活自治体の取り組みとサービス
現在の私は、多くの自治体が「おひとりさま終活」に注目していることを知っています。なぜなら、高齢化社会が進む中で、一人暮らしの高齢者や身寄りのない方々の終活のサポートが必要とされているからです。
おひとりさまの終活支援事業の深化
日本の高齢化が進む中、特に「おひとりさま」の高齢者が増加しています。この背景から、終活支援事業の需要が高まっており、多くの企業や団体がサービスを提供しています。具体的には、遺言書の作成支援や葬儀の事前準備、遺品整理などのサービスが増えています。
近年のデータによると、終活支援事業の市場規模は年々拡大しており、2022年には約500億円に達すると予測されています。この市場の拡大は、おひとりさまの高齢者が終活に関するサポートを求める声が高まっていることが一因と考えられます。
また、終活支援事業の中でも、デジタル技術を活用したサービスが注目されています。例えば、オンラインでの遺言書作成ツールや、VR技術を使った葬儀のシミュレーションなど、新しい取り組みが増えています。
しかし、終活支援事業にはまだ課題も多く、サービスの質や情報の正確性など、利用者の信頼を得るための取り組みが求められています。
身寄りなし 終活の重要性
身寄りがいない方々の終活は、特に重要です。なぜならば、死後の手続きや遺産の分配など、多くの問題が生じる可能性があるからです。このような状況を避けるためにも、早めの終活が必要とされています。
高齢者 終活支援の必要性
身寄りがいない状況下での終活:なぜそれが極めて重要なのか
終活は、人生の最後の段階を迎える際の準備として認識されています。特に、身寄りがいない人々にとっては、自身の意志や希望を明確にし、それを実現するための手続きや計画を進めることが非常に重要です。このような状況下では、遺産の分配や葬儀の手配、
そして将来の医療や介護に関する意向など、多くの点での事前の計画が求められます。身寄りがいない場合、これらの事項をどのように取り決め、実行するのかがキーとなります。そのため、終活の取り組みは、自分の人生をより良く終えるための大切なステップとして位置づけられています。
おひとりさま 終活 サービスの特徴
おひとりさま向け終活サービスの独自性
近年、日本の高齢化社会において「おひとりさま」としての生活を選択する人々が増加しています。この背景を受けて、終活サービスも多様化してきました。特に「おひとりさま」向けのサービスは、以下のような特徴を持っています。
- パーソナライズされたサポート:お一人ひとりのライフスタイルや希望に合わせたカスタマイズが可能です。例えば、ペットとの同居や趣味の継続など、個人のライフスタイルを尊重したプランニングが行われます。
- 専門的なカウンセリング:終活に関する専門的な知識を持ったカウンセラーが、遺言書の作成や資産の整理など、具体的なアドバイスを提供します。
- 安心のサポート体制:24時間365日のサポートがあり、突発的な事態や緊急時にも迅速に対応します。特に、おひとりさまの場合、突然の健康トラブルなどが心配されるため、このような体制が整っていることは大きな安心材料となります。
- 情報提供と啓発活動:終活に関する最新の情報やトレンドを提供するセミナーやワークショップが定期的に開催され、参加者同士の交流の場も設けられています。
これらの特徴を踏まえて、おひとりさまの方々が安心して終活を進められるようなサービスが提供されています。
終活支援サービスの種類と選び方
終活支援サービスの多様性とその特徴 終活支援サービスは近年、多様化しています。これらのサービスは、個人のニーズや状況に合わせて選択することが重要です。以下は、主な終活支援サービスの種類とその特徴を示すものです。
- 遺言書作成サポート:
- このサービスは、遺言書の作成を専門家と共に行うものです。専門家のアドバイスを受けながら、適切な内容の遺言書を作成することができます。
- 葬儀プランニング:
- 葬儀のプランニングサービスでは、事前に葬儀の内容や費用を計画することができます。これにより、家族や親しい人々の負担を軽減することが期待されます。
- 生前整理のアドバイス:
- 生前整理のアドバイスサービスは、不要な物を整理し、遺品として残す物を選ぶ際のサポートを提供します。
終活支援サービスの選び方のポイント 終活支援サービスを選ぶ際のポイントとして、以下の要素を考慮することが推奨されます。
- サービスの評判や口コミをチェックする。
- 費用やサービス内容を明確にする。
- 自身のニーズや状況に合ったサービスを選択する。
終活 補助金の活用方法
終活補助金の多面的な活用
終活は、自分の死について考えることから始まり、その過程でさまざまなサポートが必要となります。自治体はこの終活をサポートするための補助金を提供しており、それを活用することで、より質の高い終活を進めることができます。
- 補助金の種類と活用方法
- 各自治体では様々な補助金が設けられています。例えば、九州のある田舎都市では、「健康づくりのためのはり、灸利用の費用を1回500円、月4回まで支給」という補助金が存在します。このような補助金を知ることで、終活の中での健康維持に役立てることができます。
- 補助金の適用条件
- 補助金を受け取るための条件は自治体によって異なりますが、一般的には「高額の財産を有していない人」「身寄りがない人」「一人暮らしの人」など、困っている方が優先的にサポートされることが多いです。
- 補助金の申請方法
- 補助金を利用するためには、自治体の指定する申請書を提出する必要があります。申請書は市役所や町役場などの窓口で入手できることが多いです。また、自治体の公式ホームページでダウンロードできる場合もあります。
- 補助金の有効活用
- 補助金を受け取った後は、その金額を最も効果的に活用する方法を考えることが重要です。例えば、エンディングノートの作成や葬儀の準備、遺言書の作成など、終活に関連するさまざまなサービスや商品の購入に利用することが考えられます。
終活補助金は、終活を進める上での大きなサポートとなります。自治体が提供するこの補助金を上手く活用し、自分らしい終活を進めていきましょう。
死後事務委任契約 自治体の役割
死後事務委任契約と自治体の積極的な取り組み
死後事務委任契約は、自身の死後に発生するさまざまな手続きや業務を、信頼する第三者に委任する契約です。この契約は、身寄りが少ない「おひとりさま」や、家族に負担をかけたくないと考える人々にとって、非常に重要なものとなっています。
- 自治体の役割とは
- 自治体は、死後事務委任契約の普及と正しい理解を促進するための啓発活動を行っています。具体的には、セミナーやワークショップの開催、パンフレットやガイドブックの配布などを通じて、市民に正確な情報を提供しています。
- 契約のメリットと自治体のサポート
- 死後事務委任契約の最大のメリットは、自身の意思がしっかりと反映されることです。自治体は、この契約をスムーズに進めるためのサポートを行っており、専門家との相談会や契約書のサンプル提供など、多岐にわたる支援を実施しています。
- 自治体の取り組みの実例
- 例えば、東京都内のある市では、死後事務委任契約に関する無料の相談窓口を設置しており、月に平均50件以上の相談が寄せられています。また、契約に関するセミナーも定期的に開催され、多くの市民が参加しています。
死後事務委任契約は、自身の意思をしっかりと後世に伝えるための重要な手段です。自治体の積極的な取り組みにより、この契約の重要性がより多くの人々に知られるようになってきました。
おひとりさま終活自治体での終活のステップ
おひとりさま終活の現状と重要性
「終活」とは、人生の最期に向けての準備を指します。近年、65歳以上で1人暮らしをしている方が増加しており、この背景から「おひとりさま終活」という言葉が生まれました。特に、高齢で家族や親族がいない、または別居している方々の終活は、社会的な課題として注目されています。
- 65歳以上の1人暮らしの現状: 内閣府「令和5年版高齢社会白書」によれば、65歳以上で1人暮らしをしている方の割合は、令和2年度で男性15.0%、女性22.1%となっています。この数字は今後も増加が予想されており、令和7年度には男性16.8%、女性23.2%となる見込みです。
自治体による終活サポート
多くの自治体が「おひとりさま終活」をサポートする取り組みを行っています。以下は、自治体が提供する主な終活サポートの一部です。
- 安否確認: 1人暮らしの高齢者向けに、定期的な安否確認を行うサービス。特に「配食サービス」では、食事の配達を通じて高齢者の健康状態を確認し、孤独死を防ぐ取り組みが行われています。
- 終活相談窓口: 終活に関する悩みや、相続税などの専門的な問題について無料で相談できる窓口。ただし、常設している自治体は少ないため、利用を検討する際は自治体の情報を確認することが重要です。
この情報を元に、終活を検討している方や、終活の方法について詳しく知りたい方は、自身の住む自治体の提供するサポートやサービスを積極的に活用することをおすすめします。
終活は何から始める?の答え
終活、つまり「終の活動」とは、人生の終わりに向けての準備や計画を意味します。多くの人が「終活」という言葉を耳にするものの、具体的に何をすればよいのか、どこから手をつければ良いのか迷ってしまうことも少なくありません。
- 荷物の整理:生前に不要な物を整理し、後の手間を減らすことが推奨されます。これには、不要な衣類や家具、書類の整理が含まれます。
- 財産の整理:遺産相続に関する問題を未然に防ぐため、財産の状況を把握し、遺言書の作成を検討することが大切です。
- 交友関係の整理:葬儀や法事に呼びたい人のリストを作成することで、家族や親族への負担を軽減できます。
- 医療や介護の意思表示:将来の医療や介護に関する意向を明確にし、リビングウィルやDNR(心肺蘇生を希望しない意思表示)などの文書を用意することも考慮されます。
- 葬式の希望:自分の希望する葬儀の形式や内容、場所などを家族や親族に伝えておくことで、後の混乱を避けることができます。
- 老後の生活設計:残りの人生をどのように過ごすか、その計画を立てることも終活の一部です。これには、趣味や旅行、ボランティア活動など、自分の希望する生活スタイルを考えることが含まれます。
最後に、これらの意思や希望をまとめた「エンディングノート」を作成し、大切な人に伝えておくことが推奨されます。終活はネガティブなイメージを持たれがちですが、実際には自分の人生をより良く、そして家族や親族に迷惑をかけないための前向きな活動と言えるでしょう。
終活の問題点とその対処法
終活、つまり「終の活動」は、近年多くの人々が取り組むようになった活動です。しかし、終活を進める中で様々な問題点が浮き彫りになってきました。以下に、主な問題点とその対処法をまとめてみました。
- 情報過多:終活に関する情報は多岐にわたり、何から手をつければ良いのか迷ってしまうことが多いです。
- 対処法:終活の専門家やカウンセラーに相談することで、自分に合った終活の進め方を知ることができます。
- 遺産相続のトラブル:遺産の分け方や遺言の有無など、相続に関する問題が発生することがあります。
- 対処法:遺言書を作成し、公正証書遺言として残すことで、後のトラブルを防ぐことができます。
- 終活のコスト:葬儀や墓地の費用、遺言書の作成費用など、終活には様々なコストがかかります。
- 対処法:事前に必要な費用をリサーチし、終活の予算を計画的に立てることが大切です。
- 感情のもつれ:終活を進める中で、家族間での意見の不一致や感情のもつれが生じることがあります。
- 対処法:家族全員でのミーティングを定期的に開き、意見や希望を共有することで、感情のもつれを防ぐことができます。
- 終活のタイミング:いつから終活を始めるべきか、そのタイミングが難しいと感じる人もいます。
- 対処法:終活は早めに始めることが推奨されます。特に60代に入ったら、少しずつ終活の準備を始めると良いでしょう。
終活は、自分の人生の終わりをより良く迎えるための大切な活動です。上記の問題点や対処法を参考に、スムーズに終活を進めることができることを願っています。
終活 何をすればいい?の具体的なアクション
終活、つまり「終の活動」は、人生の終わりに向けての準備や計画を意味します。しかし、具体的に何をすれば良いのか、多くの人が迷ってしまいます。以下に、終活で取り組むべき具体的なアクションをまとめてみました。
- 遺言書の作成:自分の財産の分け方や、後の世話を任せる人を明確にするために、遺言書を作成します。公正証書遺言が最も確実な方法とされています。
- エンディングノートの記入:自分の死後の希望や、葬儀の方法、遺品の扱い方などを詳細に記入します。これにより、家族や親族の負担を軽減することができます。
- 葬儀の事前準備:希望する葬儀の形式や内容、場所などを決め、葬儀社との打ち合わせを行います。また、葬儀の費用も事前に確認しておくと良いでしょう。
- 墓地の選定:自分の墓をどこに建てるか、または火葬後の遺骨の扱いを決めます。都市部では納骨堂を利用する人も増えています。
- 生前整理:不要な物や書類を整理し、後の手間を減らすことが推奨されます。特に、大切な書類や遺品は分かりやすい場所に保管しておくと良いでしょう。
- 医療や介護の意思表示:将来の医療や介護に関する意向を明確にし、リビングウィルやDNR(心肺蘇生を希望しない意思表示)などの文書を用意することも考慮されます。
- 金融資産の整理:銀行口座や証券、保険などの金融資産を整理し、家族に伝えておくことで、後の手続きをスムーズに進めることができます。
終活は、自分の意志をしっかりと伝え、後の手間やトラブルを防ぐための大切な活動です。上記のアクションを参考に、自分に合った終活の進め方を見つけてみてください。
終活の目的とその達成方法
終活、つまり「終の活動」は、近年多くの人々が取り組むようになった新しいライフスタイルの一部として注目されています。では、終活の主な目的とは何でしょうか。そして、その目的を達成するための方法はどのようなものがあるのでしょうか。
1. 終活の主な目的
- 自分の意志の確立:自分の死後の希望や遺産の分配、葬儀の方法など、自分の意志をしっかりと確立することが終活の最も基本的な目的です。
- 家族や親族の負担軽減:自分が亡くなった後の手続きや葬儀の準備など、家族や親族の負担を軽減することも大きな目的となります。
- 後悔のない人生の終わり:自分の人生を振り返り、後悔のないように準備をすることも終活の目的の一つです。
2. 目的の達成方法
- 遺言書の作成:自分の意志を明確に伝えるための最も確実な方法。公正証書遺言や自筆証書遺言など、適切な方法を選びましょう。
- エンディングノートの活用:自分の希望や考えを詳細に記入することで、家族や親族の負担を軽減することができます。
- 生前整理の実施:不要な物や書類を整理し、自分の人生を振り返る良い機会ともなります。
- 専門家の相談:弁護士や税理士、終活コンサルタントなどの専門家に相談することで、より具体的なアドバイスを受けることができます。
終活は、自分の人生の終わりをより良いものにするための大切な活動です。上記の方法を参考に、自分に合った終活の進め方を見つけてみてください。
終活サポート 大阪市の取り組み
大阪市は、高齢者の増加や核家族化の進行を背景に、市民の終活をサポートするためのさまざまな取り組みを進めています。終活とは、人生の最後を迎えるための準備活動のことを指し、その内容は多岐にわたります。
1. 終活セミナーの開催
大阪市では、市民が終活に関する正確な知識を得るためのセミナーを定期的に開催しています。これにより、遺言書の作成方法や生前整理のポイント、葬儀の進め方など、終活に関する基本的な情報を学ぶことができます。
2. 終活相談窓口の設置
市内各地に終活相談窓口を設置し、市民が気軽に終活に関する相談をすることができるようにしています。専門家が常駐しており、個別の悩みや疑問に対して的確なアドバイスを提供しています。
3. 終活支援団体との連携
大阪市は、終活をサポートするNPOやボランティア団体と連携し、市民に対するサポートを強化しています。これにより、より専門的なサポートや、個別のニーズに応じたサービスを受けることができます。
4. 終活情報の提供
大阪市の公式ウェブサイトやパンフレットを通じて、終活に関する最新情報や市の取り組みを定期的に発信しています。市民が終活に関する情報を手軽に入手できるように努めています。
終活は、自分の意志をしっかりと伝え、家族や親族の負担を軽減するための大切な活動です。大阪市は、市民が安心して終活を進めることができるよう、さまざまなサポートを提供しています。
終活は何から始める?の答え
終活、つまり終末期の活動は、人生の最後を迎える前に行うさまざまな準備活動を指します。しかし、多くの人が「終活を始めたいけれど、何から手をつければいいのかわからない」と感じることでしょう。以下は、終活を始める際のステップとそのポイントを具体的に解説します。
1. 自分の意志を明確にする
まずは、自分の死後の希望や意志を明確にすることが大切です。例えば、葬儀の形式や場所、遺体の取り扱いなど、具体的な希望をリストアップしましょう。
2. 資産の整理
次に、自分の持っている資産や負債を整理します。銀行口座や不動産、保険などの情報を一覧にして、遺族が迷わないようにしておくことが重要です。
3. 遺言書の作成
遺言書を作成することで、自分の意志を法的に守ることができます。専門家と相談しながら、正確な遺言書を作成しましょう。
4. 生前整理
不要な物を処分し、大切な物や思い出の品を整理することで、遺族の負担を軽減することができます。また、自分自身の心の整理にも繋がります。
5. 終活の情報収集
終活に関するセミナーや講座に参加することで、最新の情報や知識を得ることができます。また、終活の専門家や相談窓口を利用することもおすすめです。
終活は、自分の意志をしっかりと伝え、遺族の負担を軽減するための大切な活動です。上記のステップを参考に、自分に合った終活の方法を見つけて進めていきましょう。
終活の問題点とその対処法
終活、つまり終末期の活動を進める中で、多くの人が直面する問題点と、それらの問題を解決するための対処法を詳しく解説します。
1. 問題点:情報過多
現代はインターネットや書籍など、終活に関する情報が溢れています。そのため、何から手をつければ良いのか迷ってしまうことが多いです。
対処法: 専門家や終活セミナーを活用し、自分に合った情報を絞り込むことが大切です。また、終活の目的を明確にすることで、必要な情報だけを効率的に収集することができます。
2. 問題点:資産の整理の難しさ
遺産分割や財産の管理など、資産の整理は複雑で時間がかかる作業です。
対処法: 専門家との相談や、遺産整理の手引き書を参考にしながら、計画的に進めることが重要です。また、家族や関係者とのコミュニケーションを密に取ることで、スムーズに進めることができます。
3. 問題点:遺言書の作成のハードル
遺言書を作成することは、自分の死を直視することとなり、心理的なハードルが高いと感じる人が多いです。
対処法: 遺言書作成の専門家や弁護士と相談することで、適切な形式や内容を知ることができます。また、遺言書は生前の意思を明確に伝えるための大切なツールであると捉え、前向きに取り組むことが大切です。
終活は、自分の意志をしっかりと伝え、遺族の負担を軽減するための大切な活動です。上記の問題点と対処法を参考に、自分に合った終活の方法を見つけて進めていきましょう。
終活 何をすればいい?の具体的なアクション
「終活」は、近年多くのメディアで取り上げられるようになり、多くの人々がその重要性を認識しています。しかし、具体的に何をすればよいのか、どのようなアクションを取るべきなのかを知らない方も少なくありません。
終活の主要な目的は、人生の最終段階において、どのように生きたいか、そしてそのための事前準備を行うことです。終活には「これを絶対にしなければならない」という固定のルールは存在しませんが、以下のアクションポイントを参考にすることで、終活の方向性を見つける手助けとなるでしょう。
- 荷物の整理:不要な物を処分し、大切な物を整理することで、後の手間を減らすことができます。
- 財産の整理:財産の現状を把握し、遺言書の作成や相続の準備を行います。
- 交友関係の整理:大切な人々との関係を再評価し、最後の時を迎える際のサポート体制を構築します。
- 医療や介護の意思表示:将来の医療や介護に関する意向を明確にし、それを家族や関係者に伝えることが重要です。
- 葬式の希望:自分の葬式に関する希望や要望を明確にし、それを家族や関係者に伝えることで、後の混乱を避けることができます。
- 老後の夢や希望のリストアップ:残りの人生でやりたいことや達成したい目標をリストアップし、それを実現するための計画を立てます。
また、終活の一環として「エンディングノート」の作成も推奨されています。エンディングノートには、自分の意思や希望、大切な思い出などを記録し、家族や友人に伝えることができます。終活はネガティブなイメージを持たれがちですが、ポジティブな計画を立て、残りの人生を充実させるための大切なステップと捉えることができます。
終活の真の目的: 人生の最終章をどう締めくくるか
終活、または「終の活動」は、近年注目を集めるようになった概念ですが、その真の目的は何でしょうか。終活は、単に死後の手続きや葬儀の準備だけではありません。それは、自分の残りの人生をどのように過ごし、どのようにその人生を締めくくるかを考え、計画する活動です。
主な目的:
- 自分の人生を充実させる: 終活を通じて、自分の残りの人生をどのように過ごすか、どのような遺産を残すかを考えることで、人生の質を向上させることができます。
- 家族や親族の負担を軽減する: 死後の手続きや葬儀の準備を事前に行うことで、家族や親族の精神的、経済的な負担を軽減することができます。
達成方法:
- 生前整理: 不要な物を処分し、大切な物や思い出の品を整理することで、後の手続きをスムーズに進めることができます。
- 遺言書の作成: 財産の分配や、自分の死後の希望を明確に記載することで、家族間のトラブルを防ぐことができます。
- 葬儀の計画: 自分の希望する葬儀の形式や、埋葬方法を事前に決めておくことで、家族の負担を軽減することができます。
- エンディングノートの作成: 自分の死後の希望や、家族へのメッセージを記載することで、家族に自分の意志を伝えることができます。
終活は、自分の人生を振り返り、どのようにその人生を締めくくるかを考える大切な活動です。適切な計画と準備を行うことで、自分自身の人生をより良くし、家族や親族の負担を軽減することができます。
終活サポート 大阪市の取り組み
大阪市は、市民の終活をサポートするための多岐にわたる取り組みを展開しています。これには、終活セミナーやワークショップの開催、終活に関する情報提供、専門家との相談会などが含まれます。特に、終活に関する意識や知識を高めるための啓発活動に力を入れており、多くの市民がこれらのサービスを利用しています。
また、大阪市は終活の重要性を認識し、市民一人ひとりが安心して終活を進められるような環境を整えることを目指しています。そのため、終活に関する専門家や団体と連携し、質の高いサポートを提供しています。
さらに、終活に関する情報やサービスを一元的に提供するポータルサイトの構築も進めており、市民が必要な情報を簡単に手に入れられるよう努力しています。このような取り組みを通じて、大阪市は市民の終活を全面的にサポートしているのです。
おひとりさま終活自治体総括
- 「おひとりさま」の定義は一緒に暮らす配偶者やパートナー、子どもなどがいない人を指す
- おひとりさまの老後のリスクとして、病気やケガ、入院や手術時の身元保証人の問題が挙げられる
- おひとりさまの死後のリスクとして、死亡届や社会保険関係の手続きが必要
- 単身高齢者のための「終活支援」に取り組む地方自治体が増加
- 終活支援の一例として、エンディングノートの無料配布や葬儀支援などがある
- 神奈川県横須賀市は死後の手続きを支援する取り組みを実施
- おひとりさまのリスクを考慮し、自治体による終活支援が広がっている
- 65歳以上の1人暮らしの方が増加しており、終活サポートのニーズが高まっている
- 終活相談窓口は、終活全般に関する悩みや相続税などの専門的な悩みを相談できる
- おひとりさま終活のサポート内容は自治体ごとに異なるため、住まいの自治体の情報を確認することが重要
「おひとりさま終活」は、今後の高齢化社会においてますます重要なテーマとなるでしょう。自治体のサポートや各種サービスを上手く活用しながら、自分らしい終活を計画し、安心して未来を迎えるための一歩を踏み出しましょう。皆様の終活がより充実したものとなることを心より願っています。
参考
・「相続登記義務化簡素化」の全てを解説!
・不動産売却税金3000万円控除税金節約術
・不動産売却の手数料を抑えるコツ
・葬儀のマナー: 基本から応用まで
・遺族年金事実婚バレる!知っておくべきポイント

お問い合わせ
ご質問などお気軽にお問い合わせください
お問い合わせはお気軽に!
大阪不動産・FPサービス株式会社
info@ofps.co.jp
TEL:06-6875-7900
投稿者プロフィール

-
ファイナンシャルプランナー・終活ガイド・
エンディングノート講師幅広いサポートが可能です!
終活・相続・事業承継・生命保険・老後資金のご相談の専門家です
不動産・リフォーム・ファイナンシャルプランニング・保険の見直し・終活・相続・家族信託・任意後見・遺言作成・生前整理・不用品買取・デイサービス・老人ホーム・お葬式・お墓他お悩み事すべてご対応可能なサービスをご準備しておりますので安心してお気軽にご相談ください。
最新の投稿
 ペット2024-10-20ペットショップ売れ残りシーズーの運命と保護活動の現状
ペット2024-10-20ペットショップ売れ残りシーズーの運命と保護活動の現状 不動産購入・住宅ローン2024-10-16住宅ローン無職でも審査に通るための秘訣と注意点を解説
不動産購入・住宅ローン2024-10-16住宅ローン無職でも審査に通るための秘訣と注意点を解説 不動産2024-10-07マンション断水過ごし方のコツ:水の確保からトイレの使い方まで
不動産2024-10-07マンション断水過ごし方のコツ:水の確保からトイレの使い方まで ペット2024-09-19ペット保険いらない知恵袋のまとめ:選び方と不要と感じる理由
ペット2024-09-19ペット保険いらない知恵袋のまとめ:選び方と不要と感じる理由